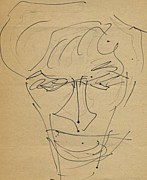この作品を讀む時に、この音樂を聞きながら鑑賞して下さい。
これは自作(オリジナル)の
『Motion1(JAZZ風に) 曲 高秋 美樹彦』
といふ曲で、YAMAHAの「QY100」で作りました。
映像は和歌山懸にある、
『熊野』
へ出かけた時のものです。
雰圍氣を味はつて戴ければ幸ひですが、ない方が良いといふ讀者は聞かなくても構ひませんので、ご自由にどうぞ。
一寸アイヌに就いて調べた事
マイミクさんの日記を見てゐたら、『フェイスブックからの情報メモ』として、
「◯苫編(とまみ)湿地帯の意味(北海道にもリゾート地でトマムがあります)。
◯面白山(おもしろやま) アイヌ語のオモシリオナイが変化したもので、その意味は(川尻に島がある川の意味)。
◯歌野(うたの) アイヌ語オタ(砂浜)で砂地帯の意味。」
といふ記事があり、それに答へてミク友の記事があつたので、許可は得てゐないがそれを掲載すれば、
「アイヌと言うよりは、古い日本語の地名で、それを一番よく保存しているのがアイヌなのでしょう。
必ずしも姫路にアイヌがいたということにはならないです。
というかアイヌという文化は中世になってからできた物で、千年以上前にはアイヌはいませんでし」
といふ文章で、それに對して、
「アイヌ文化といふのはさうかも知れませんが、彌生時代以前の縄文人といふ説から見るとどうなのでせうか。アイヌと蝦夷とが同一であつたかどうかいろんな説があるやうですが、先住民であるインデアンはアメリカ大陸が發見されてからのものでそれ以前にはゐなかつたといふのに似てゐるやうな氣がするのですが。ご教授願ひます」
と應じたのだが、それにも囘答があつたけれども、一寸調べて見る氣になつたのでここに述べてみる。
大伴弟麻呂の副使(副将軍)だつた坂上田村麻呂は、延暦十五年(796)鎭守將軍に任命され戰爭を指揮し、翌年に『征夷大將軍』に昇格した。
『征夷大將軍』の「征夷」とは東夷を征討するといふ意味で、「夷」征討に際し任命された將軍(大將軍)の一つであり、太平洋側から進む軍を率ゐ、日本海側を進む軍を率ゐる將軍は『征狄將軍(鎮狄将軍)』、九州へ向かふ軍隊を率いる將軍は『征西將軍(鎭西將軍)』といふが、中華思想では春秋戦国時代以後になつて天子を頂點とする國家體勢を最上とし、
『東夷(とうい)・西戎(せいじゆう)・南蠻(なんばん)・北狄(ほくてき)』
などと呼んだ「四夷」に由來し、西歐人を南蠻と呼んだのは遙か喜望峰から印度洋を越えて南からやつて來たからである。
「東夷」に對する將軍としては、和銅二年(709)に陸奥鎭東將軍に任じられた巨勢麻呂が最初で、『征夷將軍』の初見は養老四年(720)に任命された多治比縣守であり、『征東將軍」の初見は延暦三年(784)に鎭守將軍から昇格した大伴家持で、『征東將軍』の初見は延暦七年(788)に辭見した紀古佐美であつた。
延暦十年(790)に大伴弟麻呂が征東大使に任命され、延暦十二年(792)に征東使を征夷使と改め、「大使」はまた「將軍」とも呼ばれるやうになつた。
『日本紀略』には延暦十三年(794)に『征夷大將軍』の大伴弟麻呂に節刀を賜ふとあるのが初見とされ、由来としては天皇に任命される軍事指揮官である。
また『征夷大將軍』は「征夷」に関する現地の軍の最高司令官であり、天皇の代理人といふ權能を有してゐた事から、武人の最高司令官としての力が備はつて、鎌倉中期から明治維新まで、武家の棟梁として事実上の日本の最高権力者となつた。また、天皇によつて任命される事から、天皇には世俗的な実力はなくとも權威は維持する事となつた。
その二代目の『征夷大將軍』である坂上田村麻呂は、それまで頑強に戰つてきた蝦夷の阿弖流爲(アテルイ)を京へ連れ歸つて東北地方全土を平定したとあるが、蝦夷(えみし)は古くは『愛瀰詩(神武東征記)』と書き、次に『毛人』と表されて共に「えみし」と讀み、後に「えびす」とも呼ばれたが「えみし」からの轉訛と言はれてゐて、「えぞ」が使はれ始めたのは十一世紀か十二世紀であると言はれてゐる。
文獻的に最古の例は『毛人』で、五世紀の倭王武の上表文に、
「東に毛人を征する事五十五國。西に衆夷を服せしむ事六十六國」
とある。
蝦夷の字をあてたのは、齊明天皇五年(659)の遣唐使派遣の頃ではないかと言はれ、蝦夷と呼ばれた集團の一部は中世の蝦夷(えぞ)則ちアイヌにつながり、一部は和人につながつたと考へられ、 蝦夷と蝦夷(えみし)とは聯續(れんぞく)性を有すると考へられてゐたが、昭和に入つて東北地方に彌生時代の稻作遺蹟が發見された事から、蝦夷と蝦夷を人種的には兎も角、民族的には區別する説が有力となつたとある。
『えみし・毛人・蝦夷』の語源については樣々な説が唱へられてゐるが、いづれも確たる證據はなく、『愛瀰詩』の初見は神武東征記であり、神武天皇によつて滅ぼされた畿内の先住勢力とされてゐて、「蝦夷」の表記の初出は、日本書紀の景行天皇条で、そこでは武内宿禰が北陸及び東方諸国を視察して、
「東の夷の中に、日高見國有り。その國の人、男女竝に椎結け身を文けて、人となり勇みこはし。是をすべて蝦夷といふ。また土地沃壌えて廣し、撃ちて取りつべし」
と述べ、五世紀頃とされる景行期には、蝦夷が現在の東北地方だけではなく廣く東方にゐた事と、「身を文けて」つまり、邪馬臺國の人々と同じく入墨(文身)をしてゐたと記してゐる。
蘇我蝦夷のように古代の日本人の名に使はれた事から、「えみし」には強くて勇敢といふ語感があつたと思はれる。
尤も、蘇我毛人を蘇我蝦夷としたのも『日本書紀』編者が彼を卑しめたものとする説もあるが、佐伯今毛人の例を引いて反對する意見もある。
用字については、『日本書紀』では蝦夷の夷の字に虫偏をつけた箇所も散見され、『蝦夷』の字の使用とほぼ同じ頃から、北の異民族を現す『狄』の字も使はれ、『蝦狄』と書いて「えみし」と讀んだらしい。
また、毛人と結合して「毛狄」と書かれた例もあり、一字で「夷」と「狄」を使い分ける事もあつた。
これは管轄する國(令制國)による區分で、越後國(後に出羽國)所轄の日本海側と北海道の「えみし」を『蝦狄・狄』、陸奥国所轄の太平洋側の「えみし」を『蝦夷・夷』としたのであらう。
蝦夷の生活を同時代人が正面から語つた説明としては、齊明天皇五年(659)の遣唐使と唐の高宗の問答が日本書紀にあつて、それによれば大和朝廷に毎年入朝して來る熟蝦夷(にきえみし・おとなしい蝦夷)が最も近く、麁蝦夷(あらえみし・荒々しい蝦夷)がそれより遠く、最遠方に都加留(つがる)があったといふ。
この使者の説明では、蝦夷は穀物を食べず、家を建てず、樹の下に住んでゐたとあるが、しかしこのような生活は史料にみえる他の記述とも現在の考古學的知見とも矛盾してゐて、これは蝦夷を野蛮人と誇張するための創作ではないかと思はれるやうになり、ただ解るのは、都加留(津軽)が固有名を擧げられる程の有力集團として存在したのであらうといふ事である。
更に、古代の蝦夷(えみし)は本州東部とそれ以北に居住し、政治的・文化的に、大和朝廷やその支配下に入った地域への帰属や同化を拒否してゐた集團を指し、統一した政治勢力をなさず、積極的に朝廷に接近する集團もあれば、敵對した集團もあつたと考えられてゐる。
しかし、次第に影響力を増大させていく大和朝廷により、征服から吸収されて行き、蝦夷と呼ばれた集團の一部は中世の蝦夷則ち『アイヌ』につながり、一部は和人につながつたと考えられてゐるやうだ。
二〇一三年五月二十六日 午後四時四十分店にて
関連記事
私説『九州で分斷された服(まつろ)はぬ民』
http://
これは自作(オリジナル)の
『Motion1(JAZZ風に) 曲 高秋 美樹彦』
といふ曲で、YAMAHAの「QY100」で作りました。
映像は和歌山懸にある、
『熊野』
へ出かけた時のものです。
雰圍氣を味はつて戴ければ幸ひですが、ない方が良いといふ讀者は聞かなくても構ひませんので、ご自由にどうぞ。
一寸アイヌに就いて調べた事
マイミクさんの日記を見てゐたら、『フェイスブックからの情報メモ』として、
「◯苫編(とまみ)湿地帯の意味(北海道にもリゾート地でトマムがあります)。
◯面白山(おもしろやま) アイヌ語のオモシリオナイが変化したもので、その意味は(川尻に島がある川の意味)。
◯歌野(うたの) アイヌ語オタ(砂浜)で砂地帯の意味。」
といふ記事があり、それに答へてミク友の記事があつたので、許可は得てゐないがそれを掲載すれば、
「アイヌと言うよりは、古い日本語の地名で、それを一番よく保存しているのがアイヌなのでしょう。
必ずしも姫路にアイヌがいたということにはならないです。
というかアイヌという文化は中世になってからできた物で、千年以上前にはアイヌはいませんでし」
といふ文章で、それに對して、
「アイヌ文化といふのはさうかも知れませんが、彌生時代以前の縄文人といふ説から見るとどうなのでせうか。アイヌと蝦夷とが同一であつたかどうかいろんな説があるやうですが、先住民であるインデアンはアメリカ大陸が發見されてからのものでそれ以前にはゐなかつたといふのに似てゐるやうな氣がするのですが。ご教授願ひます」
と應じたのだが、それにも囘答があつたけれども、一寸調べて見る氣になつたのでここに述べてみる。
大伴弟麻呂の副使(副将軍)だつた坂上田村麻呂は、延暦十五年(796)鎭守將軍に任命され戰爭を指揮し、翌年に『征夷大將軍』に昇格した。
『征夷大將軍』の「征夷」とは東夷を征討するといふ意味で、「夷」征討に際し任命された將軍(大將軍)の一つであり、太平洋側から進む軍を率ゐ、日本海側を進む軍を率ゐる將軍は『征狄將軍(鎮狄将軍)』、九州へ向かふ軍隊を率いる將軍は『征西將軍(鎭西將軍)』といふが、中華思想では春秋戦国時代以後になつて天子を頂點とする國家體勢を最上とし、
『東夷(とうい)・西戎(せいじゆう)・南蠻(なんばん)・北狄(ほくてき)』
などと呼んだ「四夷」に由來し、西歐人を南蠻と呼んだのは遙か喜望峰から印度洋を越えて南からやつて來たからである。
「東夷」に對する將軍としては、和銅二年(709)に陸奥鎭東將軍に任じられた巨勢麻呂が最初で、『征夷將軍』の初見は養老四年(720)に任命された多治比縣守であり、『征東將軍」の初見は延暦三年(784)に鎭守將軍から昇格した大伴家持で、『征東將軍』の初見は延暦七年(788)に辭見した紀古佐美であつた。
延暦十年(790)に大伴弟麻呂が征東大使に任命され、延暦十二年(792)に征東使を征夷使と改め、「大使」はまた「將軍」とも呼ばれるやうになつた。
『日本紀略』には延暦十三年(794)に『征夷大將軍』の大伴弟麻呂に節刀を賜ふとあるのが初見とされ、由来としては天皇に任命される軍事指揮官である。
また『征夷大將軍』は「征夷」に関する現地の軍の最高司令官であり、天皇の代理人といふ權能を有してゐた事から、武人の最高司令官としての力が備はつて、鎌倉中期から明治維新まで、武家の棟梁として事実上の日本の最高権力者となつた。また、天皇によつて任命される事から、天皇には世俗的な実力はなくとも權威は維持する事となつた。
その二代目の『征夷大將軍』である坂上田村麻呂は、それまで頑強に戰つてきた蝦夷の阿弖流爲(アテルイ)を京へ連れ歸つて東北地方全土を平定したとあるが、蝦夷(えみし)は古くは『愛瀰詩(神武東征記)』と書き、次に『毛人』と表されて共に「えみし」と讀み、後に「えびす」とも呼ばれたが「えみし」からの轉訛と言はれてゐて、「えぞ」が使はれ始めたのは十一世紀か十二世紀であると言はれてゐる。
文獻的に最古の例は『毛人』で、五世紀の倭王武の上表文に、
「東に毛人を征する事五十五國。西に衆夷を服せしむ事六十六國」
とある。
蝦夷の字をあてたのは、齊明天皇五年(659)の遣唐使派遣の頃ではないかと言はれ、蝦夷と呼ばれた集團の一部は中世の蝦夷(えぞ)則ちアイヌにつながり、一部は和人につながつたと考へられ、 蝦夷と蝦夷(えみし)とは聯續(れんぞく)性を有すると考へられてゐたが、昭和に入つて東北地方に彌生時代の稻作遺蹟が發見された事から、蝦夷と蝦夷を人種的には兎も角、民族的には區別する説が有力となつたとある。
『えみし・毛人・蝦夷』の語源については樣々な説が唱へられてゐるが、いづれも確たる證據はなく、『愛瀰詩』の初見は神武東征記であり、神武天皇によつて滅ぼされた畿内の先住勢力とされてゐて、「蝦夷」の表記の初出は、日本書紀の景行天皇条で、そこでは武内宿禰が北陸及び東方諸国を視察して、
「東の夷の中に、日高見國有り。その國の人、男女竝に椎結け身を文けて、人となり勇みこはし。是をすべて蝦夷といふ。また土地沃壌えて廣し、撃ちて取りつべし」
と述べ、五世紀頃とされる景行期には、蝦夷が現在の東北地方だけではなく廣く東方にゐた事と、「身を文けて」つまり、邪馬臺國の人々と同じく入墨(文身)をしてゐたと記してゐる。
蘇我蝦夷のように古代の日本人の名に使はれた事から、「えみし」には強くて勇敢といふ語感があつたと思はれる。
尤も、蘇我毛人を蘇我蝦夷としたのも『日本書紀』編者が彼を卑しめたものとする説もあるが、佐伯今毛人の例を引いて反對する意見もある。
用字については、『日本書紀』では蝦夷の夷の字に虫偏をつけた箇所も散見され、『蝦夷』の字の使用とほぼ同じ頃から、北の異民族を現す『狄』の字も使はれ、『蝦狄』と書いて「えみし」と讀んだらしい。
また、毛人と結合して「毛狄」と書かれた例もあり、一字で「夷」と「狄」を使い分ける事もあつた。
これは管轄する國(令制國)による區分で、越後國(後に出羽國)所轄の日本海側と北海道の「えみし」を『蝦狄・狄』、陸奥国所轄の太平洋側の「えみし」を『蝦夷・夷』としたのであらう。
蝦夷の生活を同時代人が正面から語つた説明としては、齊明天皇五年(659)の遣唐使と唐の高宗の問答が日本書紀にあつて、それによれば大和朝廷に毎年入朝して來る熟蝦夷(にきえみし・おとなしい蝦夷)が最も近く、麁蝦夷(あらえみし・荒々しい蝦夷)がそれより遠く、最遠方に都加留(つがる)があったといふ。
この使者の説明では、蝦夷は穀物を食べず、家を建てず、樹の下に住んでゐたとあるが、しかしこのような生活は史料にみえる他の記述とも現在の考古學的知見とも矛盾してゐて、これは蝦夷を野蛮人と誇張するための創作ではないかと思はれるやうになり、ただ解るのは、都加留(津軽)が固有名を擧げられる程の有力集團として存在したのであらうといふ事である。
更に、古代の蝦夷(えみし)は本州東部とそれ以北に居住し、政治的・文化的に、大和朝廷やその支配下に入った地域への帰属や同化を拒否してゐた集團を指し、統一した政治勢力をなさず、積極的に朝廷に接近する集團もあれば、敵對した集團もあつたと考えられてゐる。
しかし、次第に影響力を増大させていく大和朝廷により、征服から吸収されて行き、蝦夷と呼ばれた集團の一部は中世の蝦夷則ち『アイヌ』につながり、一部は和人につながつたと考えられてゐるやうだ。
二〇一三年五月二十六日 午後四時四十分店にて
関連記事
私説『九州で分斷された服(まつろ)はぬ民』
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
小説・評論:孤城忍太郎の世界 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
小説・評論:孤城忍太郎の世界のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82541人
- 2位
- 酒好き
- 170694人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人