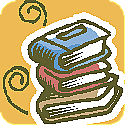日本の児童書・その3の書き込みが増え、見やすいように<その4>を作りました。引き続きよろしくお願いします。
その1〜その3も、トピックをクリックすれば検索することが出来ます。
子どもの時に出会った本が、深くその後の人生に影響を及ぼし、一生の支えになることもあるのです。これからも、一冊一冊を大切に紹介していけたらと思っています。
元気な本棚のメンバーの方なら誰でも、コメントを書きこむことが出来ます。いい本がれば是非紹介してください。
{目次}
1 鈴の音童話シリーズ(銀の鈴社)より
『ナマハゲのくる村』 はさべえみこ・作 横松桃子・絵
『まぶしい涙』 ぶな葉一・作
永元正夫・表紙絵 秋山よしのり・挿し絵
2 『くつが鳴る』 手嶋洋美・作 あべ まれこ・絵 BL出版
3 〜ニッサン童話と絵本のグランプリ・大賞受賞作から 〜
『春のかんむり』 門林真由美・作 岡本万里子・絵 BL出版
『ポレポレ』 西村まり子・作 はやし まり・絵 BL出版
4 『さわってごらん、ぼくの顔』 藤井輝明・著 汐文社
5 椋鳩十の離島物語 1〜4巻
(1)『黄金の島』 (2)『海上アルプス』
(3)『ふしぎな石と魚の島』 (4)『ヤマネコと水牛の島』
6 『車いすからこんにちは』 嶋田泰子・著 風川恭子・絵 あかね書房
8 『さよならの日のねずみ花火』 今関信子・作 おぼ まこと・絵 国土社
9 『ふるさとは無人島』― 八丈小島ものがたり
高橋文子・文 山中桃子・絵 銀の鈴社
10 『きいちゃん』 山元加津子・著 多田 順・絵 アリス館
11 『天と地の方程式』 (全3巻)より 1・2巻
富安陽子・作 五十嵐大介・画 講談社
12 『ぼくのおじいちゃん、ぼくの沖縄』
上條さなえ・作 岡本 順・絵 汐文社
13 『天と地の方程式』 3巻 富安陽子・作 五十嵐大介・画 講談社
14 『だれもが知ってる小さな国』 有川 浩・作 村上 勉・絵 講談社
15 『コロッボクル絵物語』 有川浩・作 村上勉・絵 講談社
16 『おおきな きが ほしい』 さとうさとる・ぶん むらかみつとむ・え 偕成社
|
|
|
|
コメント(20)
『ナマハゲのくる村』 はさべえみこ・作
横松桃子・絵(2000年)1200円
『まぶしい涙』 ぶな葉一・作
永元正夫・表紙絵 秋山よしのり・挿し絵(2004年)1200円
『ナマハゲのくる村』を読み、この本が<鈴の音童話>という、銀の鈴社から出ているシリーズの中の一冊であることを知りました。良かったので、他にも同シリーズの本を図書館で借り、少しづつ楽しみに読んでいます。地味だけれどもキラッと光る作品が収められていて、ページの間から澄んだ鈴の音が聞こえてくるような、清々しい気持ちにさせられるのです。
銀の鈴社という出版社の名前は、図書館の児童書のコーナーに並んでいる<ジュニアポエム・シリーズ>で知っていましたが、童話でもこんなシリーズがあることを、遅まきながら初めて知りました。ジュニアポエム・シリーズの中の作品は、教科書でも取り上げられているということですが、「詩」という分野は小説などに比べると地味で、商業的にもよく売れる分野ではないといいます。このような本を出版されている鈴の音出版についても知りたくなり調べてみて、柴崎俊子さんという方を知りました。(後日ご紹介できたらと思っています)
ナマハゲは秋田県男鹿市の伝統行事です。
明人は、手におえないガキ大将ですが、毎年小正月に家々をたずねて来るナマハゲが恐ろしくてたまりません。いつもナマハゲからかばってくれるじんちゃ(おじいさん)もなくなってしまい・・・・
明人は祖父の命をとおして真の強さを知り、困難に向かっていきます。
小学4年になる隆一。新しいクラスで隣の席に座ったのは、障害を持った輝という少年でした。
≪障害を持つ子どもの登場する児童文学作品は、日本でも外国でも、これまでたくさん書かれてきました。しかし、みんなで障害児を励ましたり助けたりして、めでたしめでたしで終わる物語が大半を占めています。
障害者と共に生きるということは、決して生やさしいものではありません。障害を持つ者と持たない者が、ホンネをぶつけあい、葛藤をくり返してはじめて、おたがいを理解し、共生の世界をつくりだすことができるのです。そのことをきちんと描いた作品は数えるほどしかありませんが、『まぶしい涙』は、それらにじゅうぶん匹敵する物語といっていいと思います。(中略) 教育の主人公は子どもであるということがみごとに描かれていることに、心を打たれました。≫
児童書を読み、子どもの目線に立つことで、さまざまな気づきがもらえるように思います。子ども受難の時代に、子どもの心に寄り添い、成長を支え見守っていく大人たちが、どうか一人でも多くありますようにと切に願っています。
BL出版(2000年)1300円
陽子のはいているくつは、特別なくつで、はきやすいようにマジックテープがついていて、くつとひざのベルトは、二本の金棒でつながっています。転んでもねんざしないように、足をささえているのです。片足だけで一キロ近くあるこのくつの重さで、ふらつく陽子もどうにか立っていられるのです。
桜の下でお母さんが手をふっています。公園で遊んでいたおさななじみの啓太もこっちを見ています。途中であきらめようかと思った陽子は、一才くらいの男の子が転んでも泣かないで一人で起き上がるのをみました。陽子はまた歩きだします。お母さんの待つ桜の木まで一直線。
主人公の少女の明るさ、希望を忘れない心に、生きる力をもらえる気がしました。あべ まれこさんの、明るくあたたかい色合いの絵もぴったりで、とても素敵な絵本でした。
写真左は、梅花高校で講演をされる手嶋洋美さん。
『春のかんむり』 門林真由美・作 岡本万里子・絵
第9回童話大賞受賞 BL出版(1993年)
『ポレポレ』 西村まり子・作 はやし まり・絵
第14回童話大賞受賞 BL出版(1998年)
『くつが鳴る』(前回紹介)がとても素晴らしかったので、<ニッサン童話と絵本のグランプリ>について詳しいことを知りたくて調べてみました。
毎年全国から約3,000編の作品が寄せられます。日産は童話部門と絵本部門でそれぞれ大賞に選ばれた作品を出版し、全国の図書館(約3,400館)に寄贈しているほか、全国の事業所から、近隣の幼稚園や保育園(約700園)にも寄贈しています。入賞作品のレベルの高さには定評があり、現在では、新人作家の登竜門と称されています。
過去の童話・絵本部門受賞作品からまず10冊ほど、図書館で借りて読みました。
童話部門の作品は、字数はさほど多くなく、文字の多い絵本といった感じでした。それぞれ素敵な作品ばかりで、10冊も読んだら楽しかったこと!
今日はその中から2冊をご紹介してみます。
美容院を開いている山田さんのところに、キツネの青年が相談にやってきました。
「どんなものにも負けない、すばらしいかんむりの作り方をおしえてください」
キツネには結婚を約束した恋人があるのですが、キツネたちが結婚するためには、かんむりをおくらなければならないのです。だれよりも見事で、素晴らしいかんむりをプレゼントした若者が、その娘をおよめさんにすることができるのでした。
仕事も手に着かないほど考えつづけた山田さんが、思いついたかんむりとは・・・・・
小学校4年生の友樹のクラスに、ケニアからピーターという少年がやってきました。
明るいピーターのおかげで、クラスのみんなはスワヒリ語を覚えます。
「ジャンボ!」は「こんにちは」、「ポレポレ」は「ゆっくり」とか「のんびり」という意味です。みんなは「ポレポレ」ということばが気に入って、クラス中ではやり出し、学校中でだれもが口にするようになります。
まわりの世界を明るくしていくピーターという少年はすてき!
『さわってごらん、ぼくの顔』 藤井輝明・著
汐文社(2004年)1300円
 さまざまな障がいをかかえた方がいます。この本の著者・藤井さんは、顔に障がいのある方です。
さまざまな障がいをかかえた方がいます。この本の著者・藤井さんは、顔に障がいのある方です。
以前は、こういったテーマの本を読むのは重く感じる時もあり、すっと手に取れる時ばかりではありませんでしたが、最近は全然大丈夫なのです。むしろそんな本にこそはげまされ、生きるエネルギーをいただける気がして、この頃ではためらわずに手に取るようになりました。 障がいをもった方は、困難なことへの挑戦を自らの課題としてこの世に生れて来た、人生のチャレンジャー。私たちを元気づけ、困難に立ち向かう勇気を与えてくれる人生の教師だと思うのです。
 この本の著者・藤井さんの顔には、大きなふくらんだアザがあります。はじめて右ほほに変化が現れたのは2歳のころ。色がピンク色になり、少しづつ腫れがひろがってきました。いろいろな病院をまわりましたが、診断はまちまちでした。
この本の著者・藤井さんの顔には、大きなふくらんだアザがあります。はじめて右ほほに変化が現れたのは2歳のころ。色がピンク色になり、少しづつ腫れがひろがってきました。いろいろな病院をまわりましたが、診断はまちまちでした。
顔のアザは、「海綿状血管腫」とよばれるもので、皮膚の下の脂肪や筋肉に血管が異常に増え、それが広がっていくことで、コブができるのです。
将来、必ずいい治療法が開発されるはず。それまで手術は見合わせようということになりました。
藤井さんは、顔のことでいじめられ、つばを吐きかけられたこともありましたが、習い事や部活にはげみました。中学生になると、英語はクラスで一目おかれるようになり、2年生のときはクラス委員長になりました。ところがその年の夏、「海綿状血管腫」が突然大きくなり・・・・・。
大学生になり、周りの差別と偏見に落ち込んでいた時、経済学部の金田昌司教授に声をかけられ、ゼミにさそわれました。教授は左手に障がいがある方でした。ゼミでは先輩たちにあたたかくむかえられました。
就職活動ではことごとく不合格でした。「キミのようなバケモノはやとえないよ」などと。
その後、医学についての講演会で出会った形成外科医の専門医・河野先生にすすめられ、手術を受けます。そして先生は「うちの病院に就職することを考えてくれないか。これからの医療や福祉には、キミのような人材が必要だ」と言ってくれたのです。
手術では目のまわりの血管腫は取り切れなかったけれども、顔のアザや腫れはずいぶん小さくなりました。
 藤井さんは病院で医療事務の仕事をすることになりました。そして、のちに医療系大学にはいり、看護を学び、筑波大学の大学院、名古屋大学の大学院で学びます。
藤井さんは病院で医療事務の仕事をすることになりました。そして、のちに医療系大学にはいり、看護を学び、筑波大学の大学院、名古屋大学の大学院で学びます。
熊本大学の教授などを経て、現在は鳥取大学大学院教授。顔に病気や障がいを抱える人たちに対する差別・偏見をなくすために、小・中・高校などでの講演・交流活動をはじめ、さまざまな幅広い社会活動を行っておられます。
 写真右は、『笑う顔には福来る』(NHK出版)。 他に絵本『てるちゃんのかお』(金の星社) など、著書も多数あります。
写真右は、『笑う顔には福来る』(NHK出版)。 他に絵本『てるちゃんのかお』(金の星社) など、著書も多数あります。
汐文社(2004年)1300円
以前は、こういったテーマの本を読むのは重く感じる時もあり、すっと手に取れる時ばかりではありませんでしたが、最近は全然大丈夫なのです。むしろそんな本にこそはげまされ、生きるエネルギーをいただける気がして、この頃ではためらわずに手に取るようになりました。 障がいをもった方は、困難なことへの挑戦を自らの課題としてこの世に生れて来た、人生のチャレンジャー。私たちを元気づけ、困難に立ち向かう勇気を与えてくれる人生の教師だと思うのです。
顔のアザは、「海綿状血管腫」とよばれるもので、皮膚の下の脂肪や筋肉に血管が異常に増え、それが広がっていくことで、コブができるのです。
将来、必ずいい治療法が開発されるはず。それまで手術は見合わせようということになりました。
藤井さんは、顔のことでいじめられ、つばを吐きかけられたこともありましたが、習い事や部活にはげみました。中学生になると、英語はクラスで一目おかれるようになり、2年生のときはクラス委員長になりました。ところがその年の夏、「海綿状血管腫」が突然大きくなり・・・・・。
大学生になり、周りの差別と偏見に落ち込んでいた時、経済学部の金田昌司教授に声をかけられ、ゼミにさそわれました。教授は左手に障がいがある方でした。ゼミでは先輩たちにあたたかくむかえられました。
就職活動ではことごとく不合格でした。「キミのようなバケモノはやとえないよ」などと。
その後、医学についての講演会で出会った形成外科医の専門医・河野先生にすすめられ、手術を受けます。そして先生は「うちの病院に就職することを考えてくれないか。これからの医療や福祉には、キミのような人材が必要だ」と言ってくれたのです。
手術では目のまわりの血管腫は取り切れなかったけれども、顔のアザや腫れはずいぶん小さくなりました。
熊本大学の教授などを経て、現在は鳥取大学大学院教授。顔に病気や障がいを抱える人たちに対する差別・偏見をなくすために、小・中・高校などでの講演・交流活動をはじめ、さまざまな幅広い社会活動を行っておられます。
(1)『黄金の島』 (2)『海上アルプス』
(3)『ふしぎな石と魚の島』 (4)『ヤマネコと水牛の島』
椋鳩十さんの著作にはじめて出会ったのは、小学校の教科書に載っていた『ツキノワグマ』でした。京都府の北部(丹波)の市街地に育った私は、実物のクマを見たこともなく、首のところの毛が白い三日月のようになっているクマがいることを、このお話で初めて知ったのと、堂々として威厳を感じさせるクマの存在が迫力をもってせまってきて、たいへん印象に残ったお話しでした。
著者の旅の体験や、地元の人たちに教えてもらった島の歴史などが、素朴でおおらかに語られ、当時の島が置かれた状況や島の人々の暮らしの一端を知ることができます。(3)だけは、夏休みに姫島の親戚を訪ねる少年と、島で暮らす少年のいとこの二人を中心に置いてお話が進んでいきます。一流の作家の文章に触れ、味わって、上質の心の栄養がゆっくりとおだやかに染みわたっていく心地がしました。
(1)『黄金の島』
瀬戸内海の大崎下島は、徳川期には港町として、瀬戸内海の島々のうちでは一番といわれた町でした。またのちの広島みかん発祥の地で、日本で一番最初にミカンのカンヅメのできた島でもあります。
古い時代から島の人々は、封建時代の政治と、時代の波に翻弄されつづけました。著者は、この激しい興亡のあとをたどって、原因をさぐってみようと思ったのでした。
(2)『海上アルプス』
南の海上に浮かぶ屋久島には、千メートル以上の山が30以上もそびえ立っていて、その中には鹿児島県で一番高い山もあり、縄文時代からの杉、野生のサルやシカなどが生息しています。著者は、30回以上もこの島に訪ねていき、たくさんの友人ができたということです。
(3)『ふしぎな石と魚の島』
舞台は、大分県姫島。中学にはいった夏休みにここで暮らす親戚を訪れた少年が、いろいろな人に島の歴史を聞いたり、さまざまな体験をします。いとこの少年といっしょに探した、海底で生まれた美しい石とは?
(4)『ヤマネコと水牛の島』
沖縄県でもいちばん南のはずれ、八重山群島の中の西表島には、太古そのままの原始林が残り、今世紀最大の発見といわれるイリオモテヤマネコが住んでいます。著者は、この島でさまざまなことに出会います。
図書館の本がとても古くて、ネットからきれいな表紙の写真を拝借しようと思って調べましたが、写真は掲載されていませんでした。さすが椋鳩十さんで、本を読まれた感想のほうは、たくさん寄せられていたのですが・・・。
挿し絵は各巻それぞれ別の方が描かれれていますが、どれも素晴らしくて、まだ見ぬ離島へのイメージをふくらませてくれました。
あかね書房(1997年初版)1300円
内海さんは、1956年、8ヶ月の早産で片手にのる大きさで横浜で生まれ、脳性麻痺という障害と共生になります。
小学校は、「車いすに乗っているから」という理由でことわられ、両親が必死でさがし、やっと見つかった「ゆうかり園」に入学できたのは、二年後でした。内海さんはここで親と離れてくらさなければなりませんでした。
さまざまな困難を乗り越えながら、内海さんは成長していきます。1976年には、全日本高等学校弁論大会で2位入賞。
法政大学に入学後、電動車いすに乗り始め、積極的に活動範囲を広げていきます。
ですが、当時は障がい者の就職口はありませんでした。
「日米自立生活セミナー」に参加したことをきっかけに、一人暮らしに挑戦。そのころ「生理学セミナー」で、人間の体の仕組みと、さまざまな障がいについて学んだことが、やがて、内海さんに大きなチャンスをもたらします。障がいのある人たちの治療にも積極的にとりくむ「厚誠会歯科」から、「うちの歯科で働きませんか」というさそいがあります。患者と医師の両方から信頼されるような、障がいへの深い知識があり、よい相談相手になれるような人をさがしていたのです。
就職し、結婚することができ、子どもにも恵まれまれた内海さんですが、心に引っかかっていることがありました。何かし残したことがあるのではないか・・・。
ホームレス襲撃事件や学校でのいじめに心をいためていた内海さんは、小学校での福祉講演会の講師の依頼があった時、まさにやり残していたことはこれだと気づきます。
本書は、<第44回青少年読書感想文全国コンクール課題図書>に選ばれています。
国土社(1995年)
今関信子さんは、1942年生まれ。滋賀県守山市在住の児童文学作家です。《元気な本棚》で紹介するのは、『地雷の村で「寺子屋」づくり』(
ある日、おじいちゃんが脳梗塞で倒れ、その時骨折までして、寝たきりになってしまいました。それを支える家族と親戚の奮闘の日々が続きます。
ある日、おばあちゃんが腰痛を起こして、お母さんが病院に連れて行くことに。留守をたのまれた麻衣子と健太郎は、夕食のカレーライスの支度をしますが、おじいちゃんが便意をもよおし・・・。二人はビニール手袋をはめて、おじいちゃんのお尻の穴に指を入れ、固くてなかなか出てこないウンコを出そうと奮闘します。健太郎がお腹をさすり、麻衣子が出口ごとしぼり、入り口をめくりあげ、おじいちゃんががんばります。そしてついに・・・。
ユーモアを混ぜながら展開していくストーリーに、思わずぷっと吹き出してしまったり、ズッコケたり、ジーンと来たりしながら、いろんなことを考えさせられてしまいます。
おぼまことさんの挿し絵も、とてもよかった。おぼさんの作品では、以前『ひでちゃんとよばないで』を紹介したことがありますが、今関信子さんとのコンビでも何冊か描かれています。
『ふるさとは無人島』― 八丈小島ものがたり
高橋文子・文 山中桃子・絵
銀の鈴社(2013年)1200円
 八丈小島は、八丈島から西にわずか4キロのところにあります。黒潮の激流にはばまれ、断崖絶壁にかこまれていて、簡単には往来できず、港も整備されていません。医療施設も、商店、電気、水道、ガスもない不便な生活の中、島民たちは一生懸命に助け合いながら暮らしていました。しかし、過疎化の流れは止まらず、ついに昭和44年1月から6月にかけて、91人全員が島をあとにしたのでした。
八丈小島は、八丈島から西にわずか4キロのところにあります。黒潮の激流にはばまれ、断崖絶壁にかこまれていて、簡単には往来できず、港も整備されていません。医療施設も、商店、電気、水道、ガスもない不便な生活の中、島民たちは一生懸命に助け合いながら暮らしていました。しかし、過疎化の流れは止まらず、ついに昭和44年1月から6月にかけて、91人全員が島をあとにしたのでした。
 著者の高橋文子さんは中学2年生までこの島で過ごし、高校進学のため、単身昭和35年に八丈島へと旅立ちました。
著者の高橋文子さんは中学2年生までこの島で過ごし、高校進学のため、単身昭和35年に八丈島へと旅立ちました。
本書は、親兄弟の絆、村人同士の助け合いの精神、青い透き通った海、緑の野山、満点の星空などのすばらしい自然など、著者の故郷の思い出を掘り起し、物語として書き溜められたものです。
鳥打小学校が閉校を迎えようとする日、お父さんは学校へ行き、一年間胸の中で温めていた詩を校舎の壁に書き残していこうと、こみあげてくる熱い思いを胸に、一気に書いていきました。
今、小島を去らんわが想い
五十世に暮らしつづけたわが故郷よ
今日を限りの故郷よ
かいなき我は捨て去れど
次の世代に咲かして花を・・・・・
このとき壁に書かれた詩の写真が、「山と渓谷」の昭和58年6月に掲載され、その写真を本書でも見ることが出来ます。
 物語を読むと、生きた人間が立ち上がってきます。お話の中に入って登場人物と喜怒哀楽をともにすることで、どこかまだ人ごとのようであった出来事が、自分に置きかえて想像でき、想いを共有することができるのです。
物語を読むと、生きた人間が立ち上がってきます。お話の中に入って登場人物と喜怒哀楽をともにすることで、どこかまだ人ごとのようであった出来事が、自分に置きかえて想像でき、想いを共有することができるのです。
つい最近、火山の噴火により、永久的ではないにせよ、離島を余儀なくされる事態が起こった口永良部島の人たちのことを思いました。一日も早く故郷の島に帰れる日が来ることを祈ります。
 また、ミクシーのメンバーの方から、炬口(たけのくち)勝広さんという、八丈小島に関する5000枚もの写真を撮られた写真家がいらっしゃることを教えていただき、そこからまた、いろいろな発見があり、本をとおしてぐんぐん世界がひろがっていく感覚をまさに実感することができたことは、大きな喜びでした。
また、ミクシーのメンバーの方から、炬口(たけのくち)勝広さんという、八丈小島に関する5000枚もの写真を撮られた写真家がいらっしゃることを教えていただき、そこからまた、いろいろな発見があり、本をとおしてぐんぐん世界がひろがっていく感覚をまさに実感することができたことは、大きな喜びでした。
(炬口勝広さんは、フリーカメラマンで将棋写真家。八丈小島の離島前後の写真を精力的に撮影。残念ながら2015年5月10日に故人となられました)
高橋文子・文 山中桃子・絵
銀の鈴社(2013年)1200円
本書は、親兄弟の絆、村人同士の助け合いの精神、青い透き通った海、緑の野山、満点の星空などのすばらしい自然など、著者の故郷の思い出を掘り起し、物語として書き溜められたものです。
鳥打小学校が閉校を迎えようとする日、お父さんは学校へ行き、一年間胸の中で温めていた詩を校舎の壁に書き残していこうと、こみあげてくる熱い思いを胸に、一気に書いていきました。
今、小島を去らんわが想い
五十世に暮らしつづけたわが故郷よ
今日を限りの故郷よ
かいなき我は捨て去れど
次の世代に咲かして花を・・・・・
このとき壁に書かれた詩の写真が、「山と渓谷」の昭和58年6月に掲載され、その写真を本書でも見ることが出来ます。
つい最近、火山の噴火により、永久的ではないにせよ、離島を余儀なくされる事態が起こった口永良部島の人たちのことを思いました。一日も早く故郷の島に帰れる日が来ることを祈ります。
(炬口勝広さんは、フリーカメラマンで将棋写真家。八丈小島の離島前後の写真を精力的に撮影。残念ながら2015年5月10日に故人となられました)
アリス館(1999年 初版・2000年 第9刷)1000円
この間図書館に行った時、『きいちゃん』を書架でみつけました。確か以前に新聞で紹介されていて印象に残っていた本でした。著者の山元加津子さんは金沢市生まれ。石川県で養護学校教諭をされていて、他にも何冊も本を出版されているようです。
そして、まっ白な布を買ってきて、きいちゃんといっしょに夕日の色に染め、その布でゆかたをぬってプレゼントすることにしたのです。
きいちゃんはひとりでがんばってゆかたをぬい、おねえさんのところに送りました。
二日ほどたったころ、おねえさんから電話がありました。きいちゃんだけでなく、先生にも結婚式に出てほしいというのです。
お色直しのときに、おねえさんはきいちゃんがぬったゆかたをきて出てきました・・・。
たくさんの著書があり、障がいをもつ子どもさんとの共著も。あちこちで講演活動をされたり、ドキュメンタリー映画にも出演されています。
知ることは世界が広がる喜びですね。だからこれからも、今の自分に出来ることとして、本を読むことは続けていこうと、あらためて思いました。
『天と地の方程式』 (全3巻)より 1・2巻
富安陽子・作 五十嵐大介・画
講談社(1巻−2015年8月 2巻−9月)1400円
富安陽子さんは、日本の古くからのお話をモチーフにして、数々のすぐれた児童書を世に生み出されています。個人的には、現在の児童書作家で最も期待している方で、待望の新刊が出たので、さっそく読んでみました。
黄泉ツ神と戦うカンナギは、猿を入れて全部で7人だといいます。残りの4人とは・・・。
とにかく面白くて、次は何が起こるのかと、先へと進んでいくうちに、一気に(家事の合間に読むので一日では読めなかったが、気持ちの上では一気に)読めてしまいました。
外国の文化を取り入れるのもいいですが、限りなく遠心的に拡がっていくばかりのような昨今の日本人に、危機感を覚えます。古代から今に、とぎれずに続いて来たものの上に今の自分たちがある。私たちは皆、数えきれない数のご先祖様達の遺伝子で出来ている身体を持っているのです。それは何より心強いことだし、すごいことなのだと思います。内なるものに目を向け、深く入っていくことで、かけがえのない大切なことに気づくことが出来るのではないでしょうか。
『ぼくのおじいちゃん、ぼくの沖縄』
上條さなえ・作 岡本 順・絵
汐文社(2015年8月)1400円
 小学6年生の光は不登校になっている。お母さんは、「このまま休んでいるとあんた一生、小学生のままだよ」という。「一生小学生のまま」はさすがにこわい。
小学6年生の光は不登校になっている。お母さんは、「このまま休んでいるとあんた一生、小学生のままだよ」という。「一生小学生のまま」はさすがにこわい。
でも、同級生の上野昇太の顔が頭の中に浮かぶだけで、「やっぱり、いいや」と思ってしまうのだ。
光はお母さんとおばあちゃんの3人暮らし。ある日、おばあちゃんが倒れて、おじいちゃんがどうしているか知りたいと言う。 ぼくにおじいちゃんがいたのか!
おじいちゃんは光が2歳の時、突然家を出て行き、9年前に来たハガキには沖縄の住所が書いてあった。
お母さんは、光に沖縄に行って、おじいちゃんに会って、今どうしているかおしえてほしい、という。
おじいちゃんは、沖縄民謡歌手のひろ子さんと暮らし、辺野古で、「新基地はいらない」と座り込みを続けていた・・・・・。
 まさに「今の時代」を生きる等身大の男の子と、その成長が、明るくさわやかに描かれています。 人間味あふれるひろ子さんとのふれあいにも、心あたたまり、ほろっとさせられます。
まさに「今の時代」を生きる等身大の男の子と、その成長が、明るくさわやかに描かれています。 人間味あふれるひろ子さんとのふれあいにも、心あたたまり、ほろっとさせられます。
岡本順さんの絵が好きで、そのこともあって手に取った本です。岡本さんの絵は、ピリピリした緊張感を感じさせず、人物の表情もリラックスしていて、どこかユーモラスでほっとします。
 本書は、8月15日の沖縄タイムスで紹介されたということです。
本書は、8月15日の沖縄タイムスで紹介されたということです。
作者の上條さんのコメントも掲載。
「子どもの目を通して、今沖縄が抱える理不尽さを伝えたい」
「県外の子どもたちの多くが沖縄を知らない。この本をきっかけに、沖縄の本当の歴史や状況を伝えたい」
上條さなえ・作 岡本 順・絵
汐文社(2015年8月)1400円
でも、同級生の上野昇太の顔が頭の中に浮かぶだけで、「やっぱり、いいや」と思ってしまうのだ。
光はお母さんとおばあちゃんの3人暮らし。ある日、おばあちゃんが倒れて、おじいちゃんがどうしているか知りたいと言う。 ぼくにおじいちゃんがいたのか!
おじいちゃんは光が2歳の時、突然家を出て行き、9年前に来たハガキには沖縄の住所が書いてあった。
お母さんは、光に沖縄に行って、おじいちゃんに会って、今どうしているかおしえてほしい、という。
おじいちゃんは、沖縄民謡歌手のひろ子さんと暮らし、辺野古で、「新基地はいらない」と座り込みを続けていた・・・・・。
岡本順さんの絵が好きで、そのこともあって手に取った本です。岡本さんの絵は、ピリピリした緊張感を感じさせず、人物の表情もリラックスしていて、どこかユーモラスでほっとします。
作者の上條さんのコメントも掲載。
「子どもの目を通して、今沖縄が抱える理不尽さを伝えたい」
「県外の子どもたちの多くが沖縄を知らない。この本をきっかけに、沖縄の本当の歴史や状況を伝えたい」
講談社(2016年3月22日)1400円
待ちに待った『天と地の方程式』の最終巻、ようやく読めました。(1,2巻は<元気な本棚−日本の児童書・その4>に紹介)
地の底に通じる天つ扉を開け、黄泉ツ神を封じ、この地を未曽有の災いから救うことができるのか。
黄泉ツ神の予兆、天ツ神の先触れ。
物語は大団円へと向かいます。
スタジオジプリかどこかが、アニメ映画化してくれないかなあ。
『だれもが知ってる小さな国』 有川 浩・作 村上 勉・絵
講談社(2015年10月)1400円
佐藤さとるさんが生み出した『だれも知らない小さな国』をはじめとする、日本初のファンタジー≪コロボックル物語≫シリーズは、300万人に愛されてきました。
新聞で、その佐藤さとるさんからバトンを受け継ぎ、有川浩さんが書かれた≪コロボックル物語≫が出版されたことを知り、さっそく読んでみました。
新聞にも本のあとがきにも、≪コロボックル物語≫を受け継がれた経緯について詳しくは書かれていなかったので、インターネットで調べ、有川浩さんによるコメント等が見つかりました。
 「コロボックルを、時の流れの中に置き去りにしてはならない。平成の子供たちにも平成のコロボックルに会ってほしい」
「コロボックルを、時の流れの中に置き去りにしてはならない。平成の子供たちにも平成のコロボックルに会ってほしい」
自身も幼い頃からコロボックルに夢中だった。「コロボックルが来てくれるかも、と枕元にミルクを置いて寝ていたぐらい」。自身も愛し、時代を超えて愛されてきた物語を引き継ぐというプレッシャーについては、「物語って、自分が書いていても、自分のものではないんです。物語が欲するところに進むだけ。作者ができるのは、その声に耳を傾け、物語に尽くすことです。佐藤さんも物語に尽くされる方だと思うし、もし私が受け継ぐ素質があるとしたら、そういう部分なのかなと思います」。
 「ヒコ」は、みつ蜂を養ってはちみつを採る「蜂屋」の子供で、父母とみつ蜂たちと一緒に全国を転々とする小学生です。北海道での夏、「ヒコ」はコロボックルの「ハリー」や、同じ「蜂屋」の子供「ヒメ」と出会い ます。
「ヒコ」は、みつ蜂を養ってはちみつを採る「蜂屋」の子供で、父母とみつ蜂たちと一緒に全国を転々とする小学生です。北海道での夏、「ヒコ」はコロボックルの「ハリー」や、同じ「蜂屋」の子供「ヒメ」と出会い ます。
ある日、コロボックルたちの国を脅かす危機が訪れます。養蜂家の子供であるヒコとヒメは、コロボックルを守るために…。
 佐藤さとるさんの思いと、それを引き継がれた有川浩さん。こんなことが出来るのですね。素晴らしいことです。児童書の果たす役目、可能性の大きさに改めて思いを馳せました。
佐藤さとるさんの思いと、それを引き継がれた有川浩さん。こんなことが出来るのですね。素晴らしいことです。児童書の果たす役目、可能性の大きさに改めて思いを馳せました。
現代は、子供受難の時代だとつくづく感じます。本書の読後の心洗われる清々しさとともに、救われたような気持ちになりました。
コロボックルを愛する子供たちと、今もコロボックルの存在を信じる大人にも、是非お薦めしたい本です。
講談社(2015年10月)1400円
佐藤さとるさんが生み出した『だれも知らない小さな国』をはじめとする、日本初のファンタジー≪コロボックル物語≫シリーズは、300万人に愛されてきました。
新聞で、その佐藤さとるさんからバトンを受け継ぎ、有川浩さんが書かれた≪コロボックル物語≫が出版されたことを知り、さっそく読んでみました。
新聞にも本のあとがきにも、≪コロボックル物語≫を受け継がれた経緯について詳しくは書かれていなかったので、インターネットで調べ、有川浩さんによるコメント等が見つかりました。
自身も幼い頃からコロボックルに夢中だった。「コロボックルが来てくれるかも、と枕元にミルクを置いて寝ていたぐらい」。自身も愛し、時代を超えて愛されてきた物語を引き継ぐというプレッシャーについては、「物語って、自分が書いていても、自分のものではないんです。物語が欲するところに進むだけ。作者ができるのは、その声に耳を傾け、物語に尽くすことです。佐藤さんも物語に尽くされる方だと思うし、もし私が受け継ぐ素質があるとしたら、そういう部分なのかなと思います」。
ある日、コロボックルたちの国を脅かす危機が訪れます。養蜂家の子供であるヒコとヒメは、コロボックルを守るために…。
現代は、子供受難の時代だとつくづく感じます。本書の読後の心洗われる清々しさとともに、救われたような気持ちになりました。
コロボックルを愛する子供たちと、今もコロボックルの存在を信じる大人にも、是非お薦めしたい本です。
『コロッボクル絵物語』 有川浩・作 村上勉・絵
講談社(2014年4月)1200円
佐藤さとる版コロボックルから有川浩版コロボックルへの橋渡しの役目をしているのが、本書です。『だれもが知ってる小さな国』に出会ってから、本書が先に出版されていることを知りました。
有川浩さんによる物語に、佐藤版コロボックル物語の挿し絵を描いて来られた村上勉さんによる、豊富な全点描き下ろしの絵が、コロボックルの世界に誘ってくれます。ファンにとって、素敵な贈り物となる一冊ではないでしょうか。
 物語の主人公ノリコは、コロボックルとトモダチになりたいと願い、根気強く毎日手紙を書きます。そのうちノリコは、コロボックルのために毎日牛乳も取りかえるようになりますが、何日か家を留守にすることになります。ノリコが帰ってきたとき、コップの牛乳がつるんと白くかたまってしまっていて、ほんのりすっぱいにおいがしました。「くさっちゃったから捨てなさい」といわれて、牛乳は捨てられましたが、もしかしたら、牛乳はヨーグルトに変わっていたのでは?などと想像がふくらみ、 印象に残る場面でした。
物語の主人公ノリコは、コロボックルとトモダチになりたいと願い、根気強く毎日手紙を書きます。そのうちノリコは、コロボックルのために毎日牛乳も取りかえるようになりますが、何日か家を留守にすることになります。ノリコが帰ってきたとき、コップの牛乳がつるんと白くかたまってしまっていて、ほんのりすっぱいにおいがしました。「くさっちゃったから捨てなさい」といわれて、牛乳は捨てられましたが、もしかしたら、牛乳はヨーグルトに変わっていたのでは?などと想像がふくらみ、 印象に残る場面でした。
講談社(2014年4月)1200円
佐藤さとる版コロボックルから有川浩版コロボックルへの橋渡しの役目をしているのが、本書です。『だれもが知ってる小さな国』に出会ってから、本書が先に出版されていることを知りました。
有川浩さんによる物語に、佐藤版コロボックル物語の挿し絵を描いて来られた村上勉さんによる、豊富な全点描き下ろしの絵が、コロボックルの世界に誘ってくれます。ファンにとって、素敵な贈り物となる一冊ではないでしょうか。
『おおきな きが ほしい』 さとうさとる・ぶん むらかみつとむ・え
偕成社(1971年 ・1刷/2000年・118刷)1000円
 夏休みの間に、子どもたち向けの楽しい本を少しでも紹介出来たら、と思っていたのですが、時間に追われてなかなか果たせませんでした。夏休みももうあとわずかになり、これからは読書の秋ですね。一冊の楽しい絵本に出会いましたので、是非ご紹介したいと思います。
夏休みの間に、子どもたち向けの楽しい本を少しでも紹介出来たら、と思っていたのですが、時間に追われてなかなか果たせませんでした。夏休みももうあとわずかになり、これからは読書の秋ですね。一冊の楽しい絵本に出会いましたので、是非ご紹介したいと思います。
 この絵本は、「おおきな木がお庭にあるといいな」と思った少年が、想像の翼をふくらませ、おおきな木の上に自分だけのすてきな小屋をつくるというお話です。
この絵本は、「おおきな木がお庭にあるといいな」と思った少年が、想像の翼をふくらませ、おおきな木の上に自分だけのすてきな小屋をつくるというお話です。
おおきな木に長い長いはしごをかけて登っていく場面など、2ページを続きで使って、ページをめくるごとに、上へ上へと場面が移っていくので、わくわくします。
作った小屋のすみには台所もあり、まん中にはテーブルが一つと、小さいいすが一つあります。ここでホットケーキを焼いてたべたりするのです。
そのとなりには、もう一つ小さなへやをつくって、ここにはベッドをおきます。
季節ごとにお部屋の様子が変わります。花びんに生けた花や、寝室の布団の柄、窓から見た風景なども違い、それを見つけるのも楽しい。
子どもたちもきっと、ページをめくっていきながら、めいめいが想像の翼をふくらませて、自分だけの小屋を作ってみたくなるのではないでしょうか。
 作家の柳田邦男さんは、「絵本との出会いは、人生に三度」と言われます。一度目は自分が子どもの時、次は子どもを育てる時、そして三度目は、人生後半になり感受性が錆びついてしまった時や、重い病気になった時。
作家の柳田邦男さんは、「絵本との出会いは、人生に三度」と言われます。一度目は自分が子どもの時、次は子どもを育てる時、そして三度目は、人生後半になり感受性が錆びついてしまった時や、重い病気になった時。
たのしい絵本でした。三度目の貴重な出会いに感謝。
偕成社(1971年 ・1刷/2000年・118刷)1000円
おおきな木に長い長いはしごをかけて登っていく場面など、2ページを続きで使って、ページをめくるごとに、上へ上へと場面が移っていくので、わくわくします。
作った小屋のすみには台所もあり、まん中にはテーブルが一つと、小さいいすが一つあります。ここでホットケーキを焼いてたべたりするのです。
そのとなりには、もう一つ小さなへやをつくって、ここにはベッドをおきます。
季節ごとにお部屋の様子が変わります。花びんに生けた花や、寝室の布団の柄、窓から見た風景なども違い、それを見つけるのも楽しい。
子どもたちもきっと、ページをめくっていきながら、めいめいが想像の翼をふくらませて、自分だけの小屋を作ってみたくなるのではないでしょうか。
たのしい絵本でした。三度目の貴重な出会いに感謝。
偕成社(2017年12月)1600円
日本の児童書のファンタジーの第一人者である著者。『天と地の方程式』(全3巻)以来、待ち望んでいた久しぶりの大作で、期待に胸をふくらませながらページを開きました。
『古事記』は、現存する日本最古の歴史書で、天地の始まりから、七世紀の推古天皇の時代までの歴史を記した全三巻からなります。本書では、上巻につづられている神話の部分を、絵物語として一冊にまとめられています。
私が小学生の時、教科書に載っていた、「いなばの白うさぎ」や「海幸山幸」は、とても印象に残ったお話でした。それと、教科書に載っていたかどうかは記憶が確かではないのですが、「天の岩戸」「ヤマタノオロチ」なども、よく知っていたお話でした。
ですが、その数々の物語が、『古事記』に出てくるお話だったとは、大人になるまで知らなかったのです。
それぞれが独立したお話のように思っていたのが、それらはじつは、一つにつながった長い物語の一部だったのです。
本書は、“文章が語る物語と、絵が語る物語が一体となって展開するような新しい本を作りたい”と企画され、実現されたものです。
“たくさんの子どもたちの心にとどき、読みつがれていくように”という願いが込められたこの本を、ぜひ本欄でも紹介したいと思いました。
〜時をこえて うたいつがれる歌の数々・作曲家 中山晋平〜
日野多香子・作 こさか しげる・絵
PHPこころのノンフィクション(小学上級以上)・PHP研究所(1988年)
幼い頃にいつとはなしに覚え、口ずさんできた童謡の数々。なのに、作曲者の名前をほとんど知ることもなく今日まで来てしまったものがいかに多いか。本書を読んで、あらためてそのことに気づかされる思いでした。
「船頭小唄」「波浮の港」「出船の港」「鉾をおさめて」、有名な「東京音頭」も中山晋平の作曲です。
書生として住み込んだ島村抱月宅。この島村との出会いが中山に大きな影響を与えます。
「日本はいま、急激な近代化の道を歩んでいる。けれども、西洋のものなら何でもいいといった、かたよった考え方はいけない。日本には日本にしかない、すばらしいものが、あるはずなのだからね」「大衆をはなれたところに、真の芸術はないのだよ」
島村抱月引き入る「芸術座」で上演されたトルストイの「復活」の中で歌われた「カチューシャの唄」も、中山の作曲によるもので、童謡よりも先に作曲され、一世を風靡し、作曲家としての記念すべき第一歩となりました。
小手鞠るい・著
原書房(2018年4月)1300円
すぐそばには、畑でとれたぶどうからワインをつくっている、ココ・ファーム・ワイナリーの施設もあります。
こころみ学園は、知的障碍をかかえて生きる人たちが生活する施設です。
「たとえ障碍を持った人でも、だれもが持っている力を出しきって、せいいっぱいに生きること、それが大事。障碍を持っていても、人がほんとうに人らしく生きられる施設を、みんなでやってみよう。」
こころみ学園では、ぶどう畑の作業に加えて、しいたけ栽培の作業もあります。冬には、山に登ってしいたけの原木にする木をチェーンソーで切り倒し、枝を払い、長さを切りそろえます。そのあと、原木をかついで、山からおろしていきます。子どもたちは、一日におよそ30回〜40回も、山を登ったりおりたりします。
『リフカの旅』 カレン・ヘス/作 伊藤比呂美+西更/訳
理論社(2015年)1400円
 この物語は、著者の叔母であるルーシー(リフカ)の少女時代の旅の経験の記憶にもとづいて書かれています。
この物語は、著者の叔母であるルーシー(リフカ)の少女時代の旅の経験の記憶にもとづいて書かれています。
ロシアに住んでいたリフカ一家は、ユダヤ人迫害を逃れて、アメリカへ移住することを決心します。その旅の途中で、チフスに感染して命を落としそうになったり、ワルシャワでは白癬に感染して、家族と一緒にアメリカに渡ることを許可されずに一人残され、治るまでの日々を、HIAS(ヘブライ移民援助協会)に紹介されたベルギーの親切な一家の世話を受け、治療しながら、渡航出来る日を待ちわびます。
 やっとアメリカ行きの船に乗れたリフカに、その後も様々な新しい体験と試練が待ち受けています。嵐に遭って遭難し助けられて、やっと移民局のあるエルス島に到着しますが、ここでもまた、入国が許可されず留め置かれることになります。このままロシアに送り返されるのは、絶対にいやです。
やっとアメリカ行きの船に乗れたリフカに、その後も様々な新しい体験と試練が待ち受けています。嵐に遭って遭難し助けられて、やっと移民局のあるエルス島に到着しますが、ここでもまた、入国が許可されず留め置かれることになります。このままロシアに送り返されるのは、絶対にいやです。
 希望を失わず、自分で試練を乗り越えていこうとするリフカという少女が、大好きになってしまいました。人生には自分の力では変えられない、どうしようもないこともいろいろあります。でも、あきらめずに試練に向かっていくことで、乗り越えられることもたくさんあるのだということを、この本に教えられました。
希望を失わず、自分で試練を乗り越えていこうとするリフカという少女が、大好きになってしまいました。人生には自分の力では変えられない、どうしようもないこともいろいろあります。でも、あきらめずに試練に向かっていくことで、乗り越えられることもたくさんあるのだということを、この本に教えられました。
理論社(2015年)1400円
ロシアに住んでいたリフカ一家は、ユダヤ人迫害を逃れて、アメリカへ移住することを決心します。その旅の途中で、チフスに感染して命を落としそうになったり、ワルシャワでは白癬に感染して、家族と一緒にアメリカに渡ることを許可されずに一人残され、治るまでの日々を、HIAS(ヘブライ移民援助協会)に紹介されたベルギーの親切な一家の世話を受け、治療しながら、渡航出来る日を待ちわびます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
元気な本棚 ほっこり 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
元気な本棚 ほっこりのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170684人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90045人
- 3位
- mixi バスケ部
- 37855人