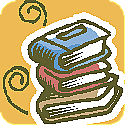〔目次〕
1 『にほん よいくに』 葉室頼昭・著 冨山房インターナショナル
2 『生きているだけで 100点満点』 ー「いのちの授業」のDVD付き
日野原重明・著 ダイヤモンド社
3 『 盆まねき 』 富安陽子・作 高橋和枝・絵 偕成社
4 『だいじょうぶ 3組 』 乙武洋匡・著 講談社
5・6『うさぎの残念賞』(松谷みよ子おはなし集・2 より)
松谷みよ子・作 ポプラ社
『ぼうしねこはほんとねこ』 あまんきみこ・作 黒井 健・絵 ポプラ社
7 岩波の子どもの本
『やまのこどもたち』石井桃子・文 深沢紅子・絵 岩波書店
『やまのたけちゃん』
8 『山のトムさん』 石井桃子・作 深沢紅子 ほか・画 福音館文庫
9 『ふたつの月の物語』 富安陽子・作 講談社
10 〜15歳の寺子屋〜
『森をつくる』 C・W ニコル/著 講談社
11 〜15歳の寺子屋〜
『15歳の日本語上達法』 金田一秀穂/著 講談社
『道しるべ』 瀬戸内寂聴/著
1 〜15歳の寺子屋〜
『「フラフラ」のすすめ』 益川敏英/著 講談社
13 『みんなの論語塾』―「 論語」は心の伴奏者!
安岡定子/著 講談社
14 「親子で楽しむ『こども論語塾』」1〜3 安岡定子/著 田部井文雄/監修
明治書院(2008〜2010年)
15 「親子で楽しむ『こども論語塾』」1〜3 ― 〈あとがき〉から
16 『木の声が聞こえますか』 日本初の女性樹木医・塚本こなみ物語
池田まき子/著 岩崎書店
17 『奇跡の樹』 よみがえった大フジのおはなし
絵・文=葉 祥明 原作=塚本こなみ 下野新聞社
18 『クマに森を返そうよ』 沢田俊子・著 汐文社
19 志茂田景樹さんの児童書を初めて読みました。
20 フォトメルヘン
『ヤマネのやじろうとこじろう』 志茂田景樹・作 西村 豊・写真
KIBA BOOK(株式会社志茂田景樹事務所)
21 志茂田景樹さん ―「心起こし」のための方法として、読み聞かせに優るものはない
22 『どんぐりっと』
『どんぐりっとのコンサート』
志茂田景樹・作 ささめやゆき・絵 ポプラ社
23 『美輪神さまの秘密』 横山充男・作 大庭賢哉・絵 文研出版
24 『あの日とおなじ空』 安田 夏菜・作 藤本 四郎・絵 文研出版
25 『春さんのスケッチブック』 依田逸夫・作 藤本四郎・絵 汐文社
26 『ぼくは プロ・ナチュラリスト』― 「自然へのとびら」をひらく仕事
佐々木 洋・著 旬報社
27≪村岡花子・訳の児童書、著書≫
『ヘレン・ケラー』 偕成社 など
28 『スズメの大研究』 ― 人間にいちばん近い鳥のひみつ
国松俊英・文 関口シュン・絵 PHP研究所
29 『神さまのいる村』― 白間津大祭物語
かわな 静・作 山口マオ・絵 ひくまの出版
30〜31 鬼が瀬物語 (第一部〜四部)
第一部 『魔の海に炎たつ』
第二部 『さいはての潮に叫ぶ」
第三部 『あかつきの波濤を切る』
第四部 『夕焼け空に東風よ吹け』
岡崎ひでたか・作 小林 豊・画 くもん出版
32 『アヤカシさん』 富安陽子・作 野見山響子・画
福音館書店
33 『スペシャル・ガール』 沢田俊子・文 汐文社
34 お米の魅力 つたえたい!
『米と話して365日』 谷本雄治・著 こぐれ けんじろう・絵 文渓堂
35 『山のメイちゃん』 青木雅子・文 藤本四郎・絵 佼成出版社
『ムササビ ムーちゃん』 井上豊子・文 村上 勉・絵 佼成出版社
36 『アンモナイトの森で』 少女チヨとヒグマの物語
市川洋介・作 水野ぷりん・絵 学研教育出版
37 『アンモナイトの森で』の挿し絵を描かれた、水野ぷりんさん
38 『ヒグマの原野』 ― 「森の新聞 」シリーズ(20)
青井俊樹・著 フレーベル館
39 『動物と話せる男』― 宮崎学のカメラ人生
塩澤実信・文 北島新平・絵 理論社
|
|
|
|
コメント(39)
冨山房インターナショナル(2011年3月)1800円+税
『神道のこころ』などでご紹介ずみの葉室頼昭さんが、子どもたちに立派な日本人になってほしいという願いをこめて、亡くなられる前まで書き続けられた本です。
ぜひとも読みたいと、以前図書館で探してもらった本なのですが、一般には出回っていなかったのか、取り寄せてもらうことが出来なくて、残念に思っていました。最近の新聞広告で、冨山房から出版されたことを知り、さっそく読んでみました。
戦後、理屈だけの教育を受けたために、一生続けて努力をしていくのが人生であるということを忘れ、なんでも頭の知識で理解しようとしているので、間違った判断をし失敗することが多く、自分の思うとおりにならないと相手を傷つけるということを大人でも子どもでも平気でやっているので、現在のような乱れた国になってしまった。
さし絵は、「現代の絵ではなく、まだ心がみだれていないころの日本人の絵が描ける人」と、著者がおっしゃっていたという、森島冨美子さんが描かれています。
日野原重明・著 ダイヤモンド社(2010年9月)1300円
このようなご高齢で、全国の小学校で、この「いのちの授業」を続けておられるということ。夢を持っていても思うようにならない世の中で、思いを持ちつづけ、そしてそれを実行することがどれだけ大変なことかを考えると、あらためて、日野原さんが人としてどんなに素晴らしい方であるかに気づかされ、胸がいっぱいになりました。
日野原さんの語り口をはじめ、生徒さん達の表情がいきいきしていて、保護者も、教室の後ろや、入れない方たちは廊下で(戸や窓が開け放たれ、授業風景を見ることが出来ます)、熱心に授業風景を見守っておられます。約38分の内容です。
偕成社(2011年7月)1000円+税
今年、なっちゃんは不思議な出来事に会いました。盆踊りの夜に、おじいちゃんの弟で、戦争で亡くなったという、しゅんすけさんに出会うのです。
あとがきを読むと、作者がこの本を書くにいたった深い思いが伝わってきます。しゅんすけさんは実在の人物がモデルで、作者のお父さんのお兄さんにあたるそうです。
そして、“「お盆」というのは、一度死んだ人を、心の中で生きつづけさせるための行事”と書かれているのが、深く心に残りました。
(単行本・1400円+税 講談社文庫・600円)
ずっと気になっていた本ですが、ようやく読めました。
本書は、乙武さんが2007年4月〜2010年3月まで、東京都杉並区立杉並第四小学校教諭として教壇に立たれた体験をもとに書かれたということです。2012年には『ありがとう 3組 』も出版されています。
乙武さんがモデルの新任教諭・赤尾慎之介が、介助員の白石に手伝ってもらいながら受け持った、5年3組の一年間がえがかれています。
本書は児童書のコーナーにありますが、大人、子どもと線を引かず、多くの人に読まれるべき本だと感じます。
学校でいじめ問題が噴出しています。心痛むことです。もう子育てを終えたから関係ないということでなく、大人として少しでも子どもたちの心に寄り添っていこうとすることが大切なのではと思い、この本を手に取りました。
雛まつりを含め、日本の伝統行事をテーマにした本は、“クリスマス”の絵本などの数の多さと比べるととても少なく、残念なことに思います。児童書の書き手となる方は、この欠けた部分の大切さに気付き、補うべく、新たな本を生み出してほしいと、切に願うものです。日本の文化の良さを伝える本を、ぜひ、家庭でも子どもさんに語ってほしいと願い、今回取り上げました。
松谷みよ子・作 ポプラ社(1200円)
うさぎのおもち屋さんが、ペッタラコ、ペッタラコと、おひなさまのおもちをつきました。
まっ白なおもち、もち草のにおいのする緑色のおもち、ももの花のしるをしぼっていれたもも色のおもち。おてつだいしたうさぎの子どもたちは、ごほうびをもらいます。まだ小さくておてつだいできなかった、あっこちゃんうさぎは“残念賞”に、お月様の色のかわいいチヨッキをもらいます。
ポプラ社(900円)
空色タクシーの松井さんは、ぼうしをかぶったふしぎなねこを、のせました。
そのねこは、とちゅうで女の子をのせると、大きな門のあるおやしきまでいってくれるよう、松井さんにたのみました。今日は雛まつり。なのに、女の子のお母さんは病気で入院しているのです。ねこは3月3日に飾られなかった雛人形がいる、ひなの里に、女の子をつれていきます。
『やまのこどもたち』石井桃子・文 深沢紅子・絵 岩波書店
『やまのたけちゃん』
戦後出版されてから長く親しまれてきている、“岩波の子どもの本シリーズ”ですが、まだ読んでいない本もあります。挿し絵に惹かれて借りて帰りました。
石井桃子さんの文がとてもいい。深沢紅子(こうこ)さんの絵とは初めての出会いで、すっかりファンになってしまいました。
戦後、石井桃子さんは、宮城県の田舎に入って開墾生活をされたということだし、深沢紅子さんも郷里盛岡に近い雫石村で開墾生活をされたということで、村の生活の様子が生きいきとえがかれています。
秋の学校の運動会がやってきました。まだ小学校に入学前のたけちゃんも、家族といっしょに出かけます。深沢さんの絵を見ていると、子どものころがとてもなつかしく思い出されました。
小学生になった、たけちゃんは、村の自然の中でのびのびと毎日をおくります、失敗もみんな大切な体験。
『山のトムさん』 石井桃子・作 深沢紅子 ほか画
福音館文庫(2011年)700円
≪北国の山の中で開墾生活をはじめたトシちゃんの家に、ネズミ退治のため、雄ネコがもらわれてきた。野性味のある行動でふりまわしてくれる、そのトムのおかげで、家族には笑いが絶えなくなり―。 ほがらかかつ懸命に生きた作者の精神の記録。≫
(裏表紙 紹介文より)
このお話は、まずこんなふうに始まります。
トムさん、おまえは、もう九つ。
長さは、前後の前足を、
ぐっとのばして、障子のはば。
重さは、おなかぺこぺこの
ときで、一貫五十です。
ネズミなんかは、あいてじゃない。
ウサギもヘビも、くるならこい!
なんのおそるることやあらん。
トムこそ、お山の大将です。
でも、おぼえてはいませんか、
小鳥のように手のひらや、
人形のふとんでねたことを?
さあ、日だまりのえんがわで、
タヌキねいりなんかしてないで、
ちょっとこっちへおいでなさい。
ここに、あなたの本があります。
いっぺんで、本の中に引き込まれてしまいました。
トムの背中は黒、おなかが白、鼻のところのぽちぽちは『千島』のよう。
本文の挿し絵が白黒でも、いっこうに大丈夫!
講談社(2012年10月)1400円
富安陽子さんは、現在活躍されている日本の児童文学作家の中で、一番注目している方です。富安さんは、古来から日本人の中に脈々と受け継がれて来たもの、日本の伝統・文化などがストーリーに織り込まれた数多くの児童書を生み出されている、貴重な作家なのです。次世代を担う子ども達に、日本の伝統・文化が途切れてしまわないように伝えていくことは、とても大切なことなのですが、そのような内容の本は、残念なことにとても少ないのです。
最近では、本書の他に、2011年に出版された『盆まねき』など、素晴らしい内容の本が世に出て、とても嬉しく思いました。
(表紙カバー裏の紹介文より)
酒井駒子さんの装画も、物語のイメージにぴったり合っています。
〜15歳の寺子屋〜
 『森をつくる』 C・W ニコル/著
『森をつくる』 C・W ニコル/著
講談社(2013年3月)1000円
本書をきっかけに、〈15歳の寺子屋〉というシリーズのことを知りました。
巻末の「編集部からみなさんへ」では、本書に込められた願いが書かれています。
《江戸時代、「寺子屋」では、僧侶、書家、医師、武士、職人など、さまざまな人が「先生」になり、その教えは知識にとどまらず、実務や人間教育にまで及ぶ、学びの「場」となりました。そのような「場」として、学校とはまた違う「出会い」の役割をこの本が果たしてくれることを、そしてみなさんが、いきいきとした喜びにあふれる人生を歩んでいくことを、私たちは心から願っています。》(一部抜粋)
 C・W ニコルさんは、イギリス西部のウェールズで生まれ、40歳から日本に居を構え、1995年には日本国籍を取り、日本人となられました。
C・W ニコルさんは、イギリス西部のウェールズで生まれ、40歳から日本に居を構え、1995年には日本国籍を取り、日本人となられました。
黒姫の森を再生するため、「幽霊森」と呼ばれている場所を買いとり、「アファンの森」と名付けて、さまざまな困難な問題を乗り越え、時間をかけて森づくりに取り組んでこられました。2002年には、「一般財団法人C・Wニコル・アファンの森財団」が発足。約7600平方メートルの土地からはじまった森が、このときには13,200平方メートルにまでなっていました。
 最後にこう書かれています。
最後にこう書かれています。
森は、100年、200年、300年、400年という、人間が想像できないようなサイクルの中で生きています。このような長い時間を、人間はだれも経験出来ません。でもある苗木の100年後の姿を子孫に見てもらいたいと思ったら、いまの自分にできることがたくさんあることに気づくはずです。
森は未来です。何十年、何百年後に命をつなぐ未来なのです。
とくに未来そのものである子どもたちに、この森を贈ります。
講談社(2013年3月)1000円
本書をきっかけに、〈15歳の寺子屋〉というシリーズのことを知りました。
巻末の「編集部からみなさんへ」では、本書に込められた願いが書かれています。
《江戸時代、「寺子屋」では、僧侶、書家、医師、武士、職人など、さまざまな人が「先生」になり、その教えは知識にとどまらず、実務や人間教育にまで及ぶ、学びの「場」となりました。そのような「場」として、学校とはまた違う「出会い」の役割をこの本が果たしてくれることを、そしてみなさんが、いきいきとした喜びにあふれる人生を歩んでいくことを、私たちは心から願っています。》(一部抜粋)
黒姫の森を再生するため、「幽霊森」と呼ばれている場所を買いとり、「アファンの森」と名付けて、さまざまな困難な問題を乗り越え、時間をかけて森づくりに取り組んでこられました。2002年には、「一般財団法人C・Wニコル・アファンの森財団」が発足。約7600平方メートルの土地からはじまった森が、このときには13,200平方メートルにまでなっていました。
森は、100年、200年、300年、400年という、人間が想像できないようなサイクルの中で生きています。このような長い時間を、人間はだれも経験出来ません。でもある苗木の100年後の姿を子孫に見てもらいたいと思ったら、いまの自分にできることがたくさんあることに気づくはずです。
森は未来です。何十年、何百年後に命をつなぐ未来なのです。
とくに未来そのものである子どもたちに、この森を贈ります。
〜15歳の寺子屋〜シリーズ 講談社 1000円
 『15歳の日本語上達法』 金田一秀穂/著(2010年1月)
『15歳の日本語上達法』 金田一秀穂/著(2010年1月)
 『道しるべ』 瀬戸内寂聴/著(2012年6月)
『道しるべ』 瀬戸内寂聴/著(2012年6月)
15歳の寺子屋シリーズを続けて読んでいます。
大人の生き方についても、いろいろ考えさせられます。若者たちの心にどう寄り添っていけばよいのか、人生の良きお手本たる生き方を示せているのか・・・・・。
どの本にも著者の心のぬくもりが感じられ、心温められました。
『15歳の日本語上達法』は、毎日何気なく使っている言葉について、金田一先生の 楽しいお話をとおしてたくさんの発見がありました。(私も、こんな授業を受けられたらよかったな。)
『道しるべ』も、大変感銘を受けた一冊です。
珠玉の言葉が散りばめられた本書は、著者の、若者たちへの渾身のメッセージが伝わってきて、読後、心の垢を落としたような清々しい気持ちになりました。
15歳の寺子屋シリーズを続けて読んでいます。
大人の生き方についても、いろいろ考えさせられます。若者たちの心にどう寄り添っていけばよいのか、人生の良きお手本たる生き方を示せているのか・・・・・。
どの本にも著者の心のぬくもりが感じられ、心温められました。
『15歳の日本語上達法』は、毎日何気なく使っている言葉について、金田一先生の 楽しいお話をとおしてたくさんの発見がありました。(私も、こんな授業を受けられたらよかったな。)
『道しるべ』も、大変感銘を受けた一冊です。
珠玉の言葉が散りばめられた本書は、著者の、若者たちへの渾身のメッセージが伝わってきて、読後、心の垢を落としたような清々しい気持ちになりました。
〜15歳の寺子屋〜
 『「フラフラ」のすすめ』 益川敏英/著
『「フラフラ」のすすめ』 益川敏英/著
講談社(2009年)1000円
益川さんといえば、ノーベル物理学賞を受賞した日本を代表する科学者。しかも科学の分野は苦手な私にはとっつきにくく少しためらいがありましたが、思い切って手に取ってみました。
 はじめにこう書かれています。
はじめにこう書かれています。
「小学生のぼくは、あまり成績のよくない劣等生でした。だからこそ、ぼくの子どものころの経験は、みなさんの参考になるのではないか、と思うんです。」
そして、「さまざまなことに好奇心を燃やして、いったい自分が本当に好きなものは何なのか、それをフラフラしながら探すことの楽しさ、大切さについて、いっしょに考えていきましょう。」とあります。
さまざまなエピソードを交えながらのお話に、著者の人間味あふれる人柄を想像させられました。
 この〈15歳の寺子屋シリーズ〉を数冊読みましたが(次回紹介予定の『みんなの論語塾』を含めて)、どの本にも共通して書かれているのは、「自分でものを考えることの大切さ」についてです。
この〈15歳の寺子屋シリーズ〉を数冊読みましたが(次回紹介予定の『みんなの論語塾』を含めて)、どの本にも共通して書かれているのは、「自分でものを考えることの大切さ」についてです。
正しいと言われていることが、本当にそうなのか、疑ってみる。どの著者も、一番伝えたいこととして、「自分の頭で考えることの大切さ」を書かれています。
本書にも「世の中の動きに関心を持つ。自分の意見をはっきりと言えるように、世の中の動きを理解するための基礎力も、いまのうちからぜひ身につけておいてほしい。」とあります。
この〈15歳の寺子屋〉シリーズを、この欄で是非紹介したいと思った一番の理由は、そこにあるのです。
折しも、特定秘密保護法案の採決が強行されました。この先どうなるのか、次世代を担う若者たちに渡すのは、暗闇の未来だというのか?
日本人1人ひとりが、霊性を高め、霊性の低い政治家を世に送り出すことがなくなるようにしなければならないと思う。
若い人たちは、決して絶望したり、投げやりにならないで欲しい。そして、「自分でものを考える力」を養って、未来を作っていってほしいと願います。
正しいことが身近にないなら、自分から近づいて行かねばならない。そのために、読書は大きな役割を果たしてくれると信じています。
 〈15歳の寺子屋〉は、ページ数もそんなに多くなく、気軽に楽しんで読めるシリーズです。プレゼントにもいいのではないでしょうか。
〈15歳の寺子屋〉は、ページ数もそんなに多くなく、気軽に楽しんで読めるシリーズです。プレゼントにもいいのではないでしょうか。
講談社(2009年)1000円
益川さんといえば、ノーベル物理学賞を受賞した日本を代表する科学者。しかも科学の分野は苦手な私にはとっつきにくく少しためらいがありましたが、思い切って手に取ってみました。
「小学生のぼくは、あまり成績のよくない劣等生でした。だからこそ、ぼくの子どものころの経験は、みなさんの参考になるのではないか、と思うんです。」
そして、「さまざまなことに好奇心を燃やして、いったい自分が本当に好きなものは何なのか、それをフラフラしながら探すことの楽しさ、大切さについて、いっしょに考えていきましょう。」とあります。
さまざまなエピソードを交えながらのお話に、著者の人間味あふれる人柄を想像させられました。
正しいと言われていることが、本当にそうなのか、疑ってみる。どの著者も、一番伝えたいこととして、「自分の頭で考えることの大切さ」を書かれています。
本書にも「世の中の動きに関心を持つ。自分の意見をはっきりと言えるように、世の中の動きを理解するための基礎力も、いまのうちからぜひ身につけておいてほしい。」とあります。
この〈15歳の寺子屋〉シリーズを、この欄で是非紹介したいと思った一番の理由は、そこにあるのです。
折しも、特定秘密保護法案の採決が強行されました。この先どうなるのか、次世代を担う若者たちに渡すのは、暗闇の未来だというのか?
日本人1人ひとりが、霊性を高め、霊性の低い政治家を世に送り出すことがなくなるようにしなければならないと思う。
若い人たちは、決して絶望したり、投げやりにならないで欲しい。そして、「自分でものを考える力」を養って、未来を作っていってほしいと願います。
正しいことが身近にないなら、自分から近づいて行かねばならない。そのために、読書は大きな役割を果たしてくれると信じています。
〜15歳の寺子屋〜
 『みんなの論語塾』―「 論語」は心の伴奏者!
『みんなの論語塾』―「 論語」は心の伴奏者!
安岡定子/著 講談社(2010年)1000円
安岡定子さんは1960年東京都生まれ。漢学者である故安岡正篤のお孫さんにあたられます。現在、安岡活学塾の講師としての都内での講座の他、全国各地での定例講座で、子どもやその保護者らに『論語』を講義されています。
 いま、『論語』は静かなブームを呼んでいて、日本のあちこちで「子、日わく(のたまわく)・・・・・」と声を張り上げて素読をしている幼稚園児や小学生が、どんどん増えているということです。
いま、『論語』は静かなブームを呼んでいて、日本のあちこちで「子、日わく(のたまわく)・・・・・」と声を張り上げて素読をしている幼稚園児や小学生が、どんどん増えているということです。
著者は、“多感な時期にある十代のみなさんにこそ、『論語』の世界に親しんでほしい。なぜなら『論語』にはさまざまな悩みを抱える中高生のみなさんにとって、これからどう生きていけばいいのかを教えてくれるヒントがたくさん詰まっているからです。”と書かれています。
相変わらず論語の入り口でうろうろしているような私にも、この本は大変楽しく読め、入門編としてうれしい1冊でした。
 著者が『論語』のなかでいちばん好きな言葉は、〈徳は弧ならず、必ず隣有り〉だということです。
著者が『論語』のなかでいちばん好きな言葉は、〈徳は弧ならず、必ず隣有り〉だということです。
「どんなときも、思いやりの気持ちを持っている人は、けっしてひとりぼっちにはならない。きっとあなたと同じようなやさしい気持ちを持った友人があらわれて、あなたのことを理解し、助けの手を差し伸べてくれるはずだから」
安岡定子/著 講談社(2010年)1000円
安岡定子さんは1960年東京都生まれ。漢学者である故安岡正篤のお孫さんにあたられます。現在、安岡活学塾の講師としての都内での講座の他、全国各地での定例講座で、子どもやその保護者らに『論語』を講義されています。
著者は、“多感な時期にある十代のみなさんにこそ、『論語』の世界に親しんでほしい。なぜなら『論語』にはさまざまな悩みを抱える中高生のみなさんにとって、これからどう生きていけばいいのかを教えてくれるヒントがたくさん詰まっているからです。”と書かれています。
相変わらず論語の入り口でうろうろしているような私にも、この本は大変楽しく読め、入門編としてうれしい1冊でした。
「どんなときも、思いやりの気持ちを持っている人は、けっしてひとりぼっちにはならない。きっとあなたと同じようなやさしい気持ちを持った友人があらわれて、あなたのことを理解し、助けの手を差し伸べてくれるはずだから」
親子で楽しむ『こども論語塾』1〜3 安岡定子/著 田部井文雄/監修
明治書院(2008〜2010年)1500円
いま、『論語』は静かなブームを呼んでいて、日本のあちこちで「子、日わく(のたまわく)・・・・・」と声を張り上げて素読をしている幼稚園児や小学生が、どんどん増えているということです。調べてみたら沢山の本が出版されています。さっそくその中から、家庭で楽しんで読めるような本を図書館で借りてみました。
小さなお子さんが初めて手に取る『論語』として、まさに最適の本だと思います。プレゼントにもお薦めです。
第2巻のあとがきにこんなことが書かれていました。とても良かったので、前回の本の紹介で充分に伝えきれなかった点を補えるかなと思って取り上げてみました。
「毎晩寝る前に、子供と一緒に1ページずつ読んでいます。」
「大切な言葉の詰まっている本ですね。」
「昔。学校で習った言葉を懐かしく思い出しました。」
「『論語』って、いいこと書いてあるんですね。初めて知りました。」
大人の方々のこのような声と共に、お子さんたちからは、率直な意見が聞かれまし た。
「2500年前の言葉なのに、ちっとも古い感じがしないね。」
「孔子ってすごいね。」と。
また、
「入学祝に、おじいちゃんからもらったの。」
「もう全部覚えちゃった。」
こんな可愛らしいお子さんたちとの出会いもありました。
(中略)
大きな声で元気に素読をすると、漢文独特の美しいリズムが、自然に体の中に入っていきます。そして数々の名言・名文が、いつの間にか心の奥にたまっていきます。それらは、人生の様々な場面で、お子さんたちの支えとなり、助けとなるでしょう。
そしてこの本の中から多くの方々が、一生の宝物となる言葉を見つけてくださったなら、こんなに嬉しいことはありません。
『木の声が聞こえますか』 日本初の女性樹木医・塚本こなみ物語
池田まき子/著 岩崎書店(2010年)
『奇跡の樹』 よみがえった大フジのおはなし
絵・文=葉 祥明 原作=塚本こなみ
下野新聞社(2002年)1300円
 表紙を埋め尽くす美しい大藤の写真が印象的で、手に取ってみました。
表紙を埋め尽くす美しい大藤の写真が印象的で、手に取ってみました。
塚本こなみさんは、女性で初めてその資格が認められた「樹木医」で、不可能だとされていた大藤の移植を手掛け、移植場所で見事によみがえらせた方です。
栃木県足利市の早川農園では、4本の大藤をはじめ180本もの藤、ツツジやシャクナゲなどが美しく咲いていましたが、街の再開発計画のために引っ越しをしなくてはならなくなりました。そして、他の造園業者に断られた大藤の移植を塚本さんに頼まれたのです。
樹齢130年の大藤の移植は、2年がかりでした。いままで誰も手掛けたことのない大掛かりなもので、試行錯誤を繰り返し、よりよい方法を模索しながらの日々でした。大勢の職人さんたちが力を結集しました。
大藤の移植作業、引っ越し、そして新しい土地で再び美しい花を咲かせ、見事に蘇るまでの詳しい過程を知り、この気の遠くなるような一大事業を成し遂げられことを本当にすごいことだと感じました。
 「あしかがフラワーパーク」では5月初めに藤の季節の本番を迎え、満開の藤のトンネルはまるでおとぎの国のようだと、お客さんの感嘆の声が聞かれるといいます。本書にも素敵なカラー写真が掲載されています。私も是非一度訪れてみたいと夢見ています。
「あしかがフラワーパーク」では5月初めに藤の季節の本番を迎え、満開の藤のトンネルはまるでおとぎの国のようだと、お客さんの感嘆の声が聞かれるといいます。本書にも素敵なカラー写真が掲載されています。私も是非一度訪れてみたいと夢見ています。
 池田まきこさんが塚本こなみさんを取材するきっかけとなったのが、『奇跡の樹』(絵・文=葉 祥明 原作=塚本こなみ)で、あしかがフラワーパーク5周年を記念して出版されたということを知りました。さっそく図書館で借りてみました。とっても素敵な絵本でした。
池田まきこさんが塚本こなみさんを取材するきっかけとなったのが、『奇跡の樹』(絵・文=葉 祥明 原作=塚本こなみ)で、あしかがフラワーパーク5周年を記念して出版されたということを知りました。さっそく図書館で借りてみました。とっても素敵な絵本でした。
池田まき子/著 岩崎書店(2010年)
『奇跡の樹』 よみがえった大フジのおはなし
絵・文=葉 祥明 原作=塚本こなみ
下野新聞社(2002年)1300円
塚本こなみさんは、女性で初めてその資格が認められた「樹木医」で、不可能だとされていた大藤の移植を手掛け、移植場所で見事によみがえらせた方です。
栃木県足利市の早川農園では、4本の大藤をはじめ180本もの藤、ツツジやシャクナゲなどが美しく咲いていましたが、街の再開発計画のために引っ越しをしなくてはならなくなりました。そして、他の造園業者に断られた大藤の移植を塚本さんに頼まれたのです。
樹齢130年の大藤の移植は、2年がかりでした。いままで誰も手掛けたことのない大掛かりなもので、試行錯誤を繰り返し、よりよい方法を模索しながらの日々でした。大勢の職人さんたちが力を結集しました。
大藤の移植作業、引っ越し、そして新しい土地で再び美しい花を咲かせ、見事に蘇るまでの詳しい過程を知り、この気の遠くなるような一大事業を成し遂げられことを本当にすごいことだと感じました。
汐文社(2013年3月)1400円
<みなさんは、クマにどんなイメージをもっていますか。
「ツキノワグマはどんぐりが大好きな、おとなしくてやさしい動物です」
くまと森と人を守る活動をしている森山さんは、こう語ります。
最近、クマが人里に現れた、というニュースが増えています。
なぜ、森で暮らしているはずのクマが、人里に現れ、
ときには人間を襲うようなことが起きているのでしょうか。>
昔の人たちは、クマをはじめ、野生の動物たちとうまく共存していました。そのために、知恵を使っていました。山すそにクマ止めとして柿の木を植えたのもそのひとつです。柿の木はクマだけでなく、他の動物や鳥、虫たちもみんなあてにしていました。が、昨今、役所が、柿の木を切るように指導しているところが増えています。
人間は、すでに、山の中の実がなる木も次々切ってしまっています。柿の木もなくなれば、エサを求めて、里をうろうろすることになる。クマは、そうなったのが人間のせいだと訴えることもできないまま、一方的に殺されています。
また、クマが山の中の自分の巣にいるにもかかわらず、危害を加えられては、という無知な恐怖から、わざわざクマを殺しに行くということも、人間たちはしているのです。
2012年度11月には、すでに2978頭もの野生のクマが捕まえられて殺されました。うち、ツキノワグマ2400頭、ヒグマは578頭です(環境庁発表による)
この本一冊読むことで、大切なことすべてが理解できるのではないかと感じました。
すべての年代の方に是非読んでほしいと願います。プレゼントにもいいのでは。
『クマともりとひと』(合同出版)には、子どもたちが、兵庫県のクマを守ろうと立ち上がったときのことが記されています。
『日本熊森協会』は、『NPO法人奥山保全トラスト』を立ち上げるなど、今も自然と野生動物を守る活動に力を合わせてがんばっています。
きっかけがあり、志茂田景樹さんの児童書に初めてふれることが出来ました(『ヤマネのやじろうとこじろう』)。 とても素敵な本でした。
それまでは直木賞作家ということしか知らず、奇抜な服装と、冗談でつけたような名前から、あまりいい印象を持っていなかったのです。
巻末の著者のプロフィールに、「絵本の読み聞かせボランティアを盛んに行い、その普及に取り組んでいる」とあり、またも驚きました。それで、著者のことをもっと詳しく知りたくてインターネットで調べてみました。目からウロコの気づきがありました。
家庭における童話 絵本の読み聞かせの必要性を痛感して、1999年(平成11年)、妻と共に「よい子に読み聞かせ隊」を結成する。
以後、テレビタレント活動、小説執筆をセーブし、絵本 読み聞かせ隊長として、 読み聞かせボランティアメンバーとともに全国で活動を行っている。2014年6月までに行われた読み聞かせ公演は1700回に達する。
童話・絵本執筆も手がけるほか、不登校の子どもたちの支援や心療内科を考える会など、社会的活動にも熱心である。
2014年3月『キリンがくる日』(ポプラ社)で第19回絵本日本賞の読者賞を受賞。
志茂田さんの著書は、株式会社・志茂田景樹事務所内にあるKIBA BOOKから出版されています。シンボルマークは、KIBA BOOKの「K」志茂田景樹の「K」「S」を表現し、出版界の「大柱」となるべき新メディア時代の「大樹」として、新たなるKIBA BOOKの挑戦的な心象意匠だということです。
いろいろなことを知っていくうちに、どこにも寄り掛からない一匹狼のイメージが浮かびました。真剣そのものの生き方、突き抜けたもの、気概ということばも、頭に浮かんできました。
志茂田景樹さんのホームページで、全国各地での読み聞かせや講演などについて知ることが出来ます。
「よい子に読み聞かせ隊」の絵本にも、読み聞かせの写真が掲載されていますが、明るいブルーの上着に、ぴったりフィットしたピンクのズボン、襟もととクツもピンク。人間離れした姿は、想像の翼羽ばたく世界からやって来た案内人のような感じです。
体型もスリムで、和食、自然食を心がけていらっしゃることもあるのでは、と思いました。
『ヤマネのやじろうとこじろう』 志茂田景樹・作 西村 豊・写真
KIBA BOOK(株式会社志茂田景樹事務所)2001年初版
小さなかわいいヤマネさんに導かれて、志茂田景樹さんの絵本・児童書、そして「よいこに読み聞かせ隊」の活動について知ることが出来ました。
ちょうど、かわいいヤマネのことをもっと知りたいと、図書館の児童書の科学読み物のコーナーで探して読んでいたところでした。この本は作家別に分類された児童書のコーナーにあったのですが、ヤマネが題名についていたので、目についたのです。
まず、作家が志茂田景樹さんとあり、こんな本も書かれるのかとびっくり。写真もたくさん載っていて、とてもたのしそうなお話です。ここでまず、一つ目のウロコが落ちました。
その後のことは、前回に書いたとおりです。
写真・右は、読み聞かせをする、志茂田景樹さんご夫妻
そのことをおとなに、とくにちいさな子を持つ若い親たちにわかってもらいたい、家庭での読み聞かせをどんどんやってほしいという強い願いから、はじめ妻に手伝ってもらいながら、ひとりでやっていた読み聞かせ行脚でしたが、ひとりまたひとりとボランティアメンバーが増えていきました。
そして1999年8月にメンバーが十数人になったので「よい子に読み聞かせ隊」を結成し、本格的な読み聞かせ活動を開始し、今日に至っています。読み聞かせの普及で豊かな心を起こされた子どもたちは、かならずや、未来を明るく豊かな社会に変えていくことでしょう。”
“「よい子に読み聞かせ隊」は、0歳からの読み聞かせをおすすめします。ことばはわからなくても、お話の内容は理解できなくても、お父さんお母さんの深い愛がちいさなお子さんの心をつつんで、すくすく成長する力をあたえます。
それは、きっとお子さんの感受性の畑をゆたかにたがやすことでしょう。”
読み聞かせ隊の活動もですが、大人の本の著者が、それに割く時間を大きく削ってまでも、子どもの本の創作に力を入れるというのは聞いたことがありません。(児童書作家が、一般書の方に転向されたケースは知っているのですが) このことに私は大変感銘を受けるのです。
パソコンに向かい、本の紹介を発信することが、今の自分に出来る唯一のことなのですが、微々たることでも出来ることから、これからも続けていきたいと思っています。
『どんぐりっと』
『どんぐりっとのコンサート』
志茂田景樹・作 ささめやゆき・絵
ポプラ社(2000年・2001年)各1000円
『どんぐりっと』は、著者が子どもたちのために初めて書き下ろした童話だということです。
 おじいちゃんは、悪い夢をみて ねむるのがこわい まりーちゃんに、むかしばなしをはじめました。
おじいちゃんは、悪い夢をみて ねむるのがこわい まりーちゃんに、むかしばなしをはじめました。
“むかし どんぐりっとの湖のほとりに、大きなどんぐりの木があったんじゃ。ある日のこと ものすごいあらしがきて、どんぐりの大木をはげしくゆすったんじゃ。いっぱいいっぱいなっていた どんぐりの実は、つぎからつぎに、まっくらな空へ ふきあげられていったんじゃ。最後にひとつだけ、どんぐりの実がのこって、どうしてもはなれんかった。大あらしが どんぐりの大木をふきたおしたとき、そのどんぐりの実は、じぶんから みずうみへとんだんじゃ。
たったひとつ みずうみへとんだ どんぐりの実は、まものから いい子を守る妖精になった。それが どんぐりっとじゃ。”
 どんぐりっとは、みどりの ぼうしをかぶり、あかい はんそでの しゃつを きて、きいろの はんずぼんを はいています。そして、星のついた つえをにぎっています。
どんぐりっとは、みどりの ぼうしをかぶり、あかい はんそでの しゃつを きて、きいろの はんずぼんを はいています。そして、星のついた つえをにぎっています。
どんぐりっとは、つえをふりかざして 、まものの“ つのやまねこ”とたたかい、追いはらいます。そして、まりーちゃんの心に つのやまねこがうえていった 悪夢のもとを、星ですいとってあげます。星は黒くなってしまいますが、つえを高くかざすと、空から星がひとつふってきて、つえのあたまに くっつき、もとどおりになります。
 このお話を読んでいて、アンパンマンを思い出しました。お話は第2話の『どんぐりっとのコンサート』までで、あとは書かれていないようです。どんぐりっとも、アンパンマンに劣らず、すてきなキャラクターだと思うので、もっと続けてほしい気もしました。
このお話を読んでいて、アンパンマンを思い出しました。お話は第2話の『どんぐりっとのコンサート』までで、あとは書かれていないようです。どんぐりっとも、アンパンマンに劣らず、すてきなキャラクターだと思うので、もっと続けてほしい気もしました。
どんぐりっとは、悪夢のもとを つえの先の星ですいとってくれますが、お話を読む人の心の内も浄化してくれるような気がしました。
この本は、残念ながら品切れ・重版未定状態ですが、図書館に行けば見ることができます。
『どんぐりっとのコンサート』
志茂田景樹・作 ささめやゆき・絵
ポプラ社(2000年・2001年)各1000円
『どんぐりっと』は、著者が子どもたちのために初めて書き下ろした童話だということです。
“むかし どんぐりっとの湖のほとりに、大きなどんぐりの木があったんじゃ。ある日のこと ものすごいあらしがきて、どんぐりの大木をはげしくゆすったんじゃ。いっぱいいっぱいなっていた どんぐりの実は、つぎからつぎに、まっくらな空へ ふきあげられていったんじゃ。最後にひとつだけ、どんぐりの実がのこって、どうしてもはなれんかった。大あらしが どんぐりの大木をふきたおしたとき、そのどんぐりの実は、じぶんから みずうみへとんだんじゃ。
たったひとつ みずうみへとんだ どんぐりの実は、まものから いい子を守る妖精になった。それが どんぐりっとじゃ。”
どんぐりっとは、つえをふりかざして 、まものの“ つのやまねこ”とたたかい、追いはらいます。そして、まりーちゃんの心に つのやまねこがうえていった 悪夢のもとを、星ですいとってあげます。星は黒くなってしまいますが、つえを高くかざすと、空から星がひとつふってきて、つえのあたまに くっつき、もとどおりになります。
どんぐりっとは、悪夢のもとを つえの先の星ですいとってくれますが、お話を読む人の心の内も浄化してくれるような気がしました。
この本は、残念ながら品切れ・重版未定状態ですが、図書館に行けば見ることができます。
『美輪神さまの秘密』 横山充男・作 大庭賢哉・絵(小学5年生以上)
文研出版(2006年)1300円
 もうすぐ5年生になる太田種友一家は、美輪山のふもとにあるお父さんの故郷に引っ越してきました。
もうすぐ5年生になる太田種友一家は、美輪山のふもとにあるお父さんの故郷に引っ越してきました。
そこで種友は、友達から宝物の隠し場所と思われる地図を見せられ、調べているうち、神さまと自然とのつながりについて気づいていくことになります。
 登場人物は、亡くなったおばあちゃんの妹で、巫女ばあさんと呼ばれている太田種子、なにやら秘密がありそうな美青年のシコオさん、お父さんとお母さん、神さまとお話ができる種友の妹のみるく、種友の友達。そして美輪山の蛇神さまも出現します。
登場人物は、亡くなったおばあちゃんの妹で、巫女ばあさんと呼ばれている太田種子、なにやら秘密がありそうな美青年のシコオさん、お父さんとお母さん、神さまとお話ができる種友の妹のみるく、種友の友達。そして美輪山の蛇神さまも出現します。
皆は、美輪山に無理やり保養センターを作ろうとする坂本議員らの動きを、力を合わせて阻止しようとします。
たつみや章さんの<神さま3部作>とよばれている作品、『ぼくの稲荷山戦記』『夜の神話』『水の伝説』と共通するものがあります。
このお話では、美輪山のご神体として蛇が登場しますが、『ぼくの稲荷山戦記』では、お稲荷様のお遣いの白いキツネが、『夜の神話』では七福神が登場します。こういったお話は、日本人としてすでに自分の中にあるものが、すんなり受け入れさせてくれるような気がします。
 皆で力を合わせて、美輪山の神さまと自然を守ろうとする心を、この本を読んでくれる、未来を担う少年・少女たちに託したいと思いました。
皆で力を合わせて、美輪山の神さまと自然を守ろうとする心を、この本を読んでくれる、未来を担う少年・少女たちに託したいと思いました。
文研出版(2006年)1300円
そこで種友は、友達から宝物の隠し場所と思われる地図を見せられ、調べているうち、神さまと自然とのつながりについて気づいていくことになります。
皆は、美輪山に無理やり保養センターを作ろうとする坂本議員らの動きを、力を合わせて阻止しようとします。
たつみや章さんの<神さま3部作>とよばれている作品、『ぼくの稲荷山戦記』『夜の神話』『水の伝説』と共通するものがあります。
このお話では、美輪山のご神体として蛇が登場しますが、『ぼくの稲荷山戦記』では、お稲荷様のお遣いの白いキツネが、『夜の神話』では七福神が登場します。こういったお話は、日本人としてすでに自分の中にあるものが、すんなり受け入れさせてくれるような気がします。
『あの日とおなじ空』 安田 夏菜・作 藤本 四郎・絵
文研出版(2014年5月)1200円
 小学3年生のダイキは、兄と二人で飛行機に乗って、沖縄のひいおばあちゃんのところに行きました。
小学3年生のダイキは、兄と二人で飛行機に乗って、沖縄のひいおばあちゃんのところに行きました。
その日の夕食に、グルクンという魚が出ましたが、片方だけ目玉がありません。ひいばあちゃんや、親戚のミクちゃんは、「これはキジムナーのしわざだよ」と、教えてくれました。キジムナーはいいマジムンで、人間が大好きだからちっともこわがらなくてもいい、ということも。
ひいばあちゃんは、キジムナーを見たことがあるといいます。まだ日本が戦争をしていたころのことです。ダイキにもっととせがまれて話しはじめたひいばあちゃんですが、途中からどうしても話せなくなってしまいます。戦争のころ、ひいばあちゃんになにが起きたのでしょうか。
 ある日ダイキは、ガジュマルの木の下で、声の出ないキジムナーに出会います。キジムナーはダイキに、木の幹にあいた穴を示します。そこをのぞいたダイキが見たのは、戦争の時代のおばあちゃんの家族の様子でした。見ているうちに、ダイキは木の穴に落ちてしまいます。そして落ちていったところは、戦争の真っ最中でした。
ある日ダイキは、ガジュマルの木の下で、声の出ないキジムナーに出会います。キジムナーはダイキに、木の幹にあいた穴を示します。そこをのぞいたダイキが見たのは、戦争の時代のおばあちゃんの家族の様子でした。見ているうちに、ダイキは木の穴に落ちてしまいます。そして落ちていったところは、戦争の真っ最中でした。
 この本の著者・安田夏菜さんは戦争を知らない世代の方ですが、素晴らしい本を書いてくださいました。本を読む年齢のめやすとしては、小学中級からとなっています。
この本の著者・安田夏菜さんは戦争を知らない世代の方ですが、素晴らしい本を書いてくださいました。本を読む年齢のめやすとしては、小学中級からとなっています。
キジムナーを登場させ、戦争のことはバーンとおもてに出さないで、ひとりの少年の不思議な体験を通しての心の成長が描かれているので、この年齢の子どもたちにも、受け止めやすいのではないかと感じました。
本の内容と一体となった、藤本四郎さんの挿し絵も素晴らしかったです。
 戦争を体験された人が亡くなられていき、このままでは体験を伝える人がいなくなってしまうと、危機感をいだく声が高まっています。どうしたらよいのか?本当に真剣に考えなければならないことです。
戦争を体験された人が亡くなられていき、このままでは体験を伝える人がいなくなってしまうと、危機感をいだく声が高まっています。どうしたらよいのか?本当に真剣に考えなければならないことです。
平和への願いが込められた児童書や絵本を、子どもたちに手渡すことも、ひとつの方法ではないかと思います。本書もプレゼントに是非お薦めしたい本のひとつです。
文研出版(2014年5月)1200円
その日の夕食に、グルクンという魚が出ましたが、片方だけ目玉がありません。ひいばあちゃんや、親戚のミクちゃんは、「これはキジムナーのしわざだよ」と、教えてくれました。キジムナーはいいマジムンで、人間が大好きだからちっともこわがらなくてもいい、ということも。
ひいばあちゃんは、キジムナーを見たことがあるといいます。まだ日本が戦争をしていたころのことです。ダイキにもっととせがまれて話しはじめたひいばあちゃんですが、途中からどうしても話せなくなってしまいます。戦争のころ、ひいばあちゃんになにが起きたのでしょうか。
キジムナーを登場させ、戦争のことはバーンとおもてに出さないで、ひとりの少年の不思議な体験を通しての心の成長が描かれているので、この年齢の子どもたちにも、受け止めやすいのではないかと感じました。
本の内容と一体となった、藤本四郎さんの挿し絵も素晴らしかったです。
平和への願いが込められた児童書や絵本を、子どもたちに手渡すことも、ひとつの方法ではないかと思います。本書もプレゼントに是非お薦めしたい本のひとつです。
『春さんのスケッチブック』 依田逸夫・作 藤本四郎・絵
汐文社(2008年)1400円
 『あの日とおなじ空』との出会いが、挿し絵画家・藤本四郎さんのお名前を知るきっかけになり、藤本さんの挿し絵をもっと見たくて図書館で何冊か借りて帰りました。本書もその中の1冊なのですが、題名から想像していた内容からは想像できなかった出会いがありました。まさか、『無言館』と戦没画学生のことが出てくるとは、思ってもみなかったのです。
『あの日とおなじ空』との出会いが、挿し絵画家・藤本四郎さんのお名前を知るきっかけになり、藤本さんの挿し絵をもっと見たくて図書館で何冊か借りて帰りました。本書もその中の1冊なのですが、題名から想像していた内容からは想像できなかった出会いがありました。まさか、『無言館』と戦没画学生のことが出てくるとは、思ってもみなかったのです。
 6年生のツヨシは、父親がすすめた中学受験の、3つの志望校すべてに失敗し、無気力な日々を送っていました。そんなある日、ついに父親と衝突し、ほほが赤くはれ上がるほど殴られたツヨシは、長野県上田の塩田平に住む春おばさん(おばあちゃんの妹にあたる)のところに、家出してしまいます。
6年生のツヨシは、父親がすすめた中学受験の、3つの志望校すべてに失敗し、無気力な日々を送っていました。そんなある日、ついに父親と衝突し、ほほが赤くはれ上がるほど殴られたツヨシは、長野県上田の塩田平に住む春おばさん(おばあちゃんの妹にあたる)のところに、家出してしまいます。
春さんの家に来るとき、丘の上にあった美術館『無言館』。春さんは悩みを打ち明けるツヨシに、「あそこは、自分の力では運命を変えることのできなかった人たちの絵が集めてあってね。あふれるような才能があって、生きていればすばらしい画家になったにちがいない若い人たちの絵があるんだよ」と、話します。
静かに立ち上がった春さんが、奥の部屋から持ってきたのは、一冊の色あせたスケッチブックでした。そこに描かれていた若い女性は、60年前の春おばさんでした。春おばさんは語りはじめます。
春さんに誘われて、次の日ツヨシは無言館を訪れます。
汐文社(2008年)1400円
春さんの家に来るとき、丘の上にあった美術館『無言館』。春さんは悩みを打ち明けるツヨシに、「あそこは、自分の力では運命を変えることのできなかった人たちの絵が集めてあってね。あふれるような才能があって、生きていればすばらしい画家になったにちがいない若い人たちの絵があるんだよ」と、話します。
静かに立ち上がった春さんが、奥の部屋から持ってきたのは、一冊の色あせたスケッチブックでした。そこに描かれていた若い女性は、60年前の春おばさんでした。春おばさんは語りはじめます。
春さんに誘われて、次の日ツヨシは無言館を訪れます。
佐々木 洋・著 旬報社(2014年7月)1500円
プロ・ナチュラリストというのは、わかりやすく言えば、プロフェッショナルの自然案内人のことで、佐々木 洋さんは、その第1号なのです。
佐々木さんは、毎日のように、いろいろな場所で、いろいろな人々に、いろいろな方法を使って、自然のすばらしさを伝え続けています。
この「プロ・ナチュラリスト」という言葉は、佐々木さんが、国の機関である特許庁に登録されていて、許可なく勝手に使ってはいけないことになっています。なぜかといえば、まず、自然のすばらしさを伝えるプロフェッショナルがいることを、世の中の人たちに広く知っていただきたいから。また、この仕事を、心から自然を愛する人だけの仕事にしたいと思ったからなのです。
ちょうどそのころ、東京都の板橋区の石神井川で、背中に矢がささったオナガガモが見つかった事件がありました。この事件を通して、人間と野生生物とのつきあい方についてとても考えさせられました。
「自然の一部である人間」が自然界でしていることをつねに見つめ、それをより良い方向に向けられるために努力していこうと強く思ったのです。
佐々木さんは仕事のホームグラウンドを東京の都心部に決めました。
山に住んで、街に色々な情報を伝えてくれる自然観察家や自然愛好家は多いのですが、佐々木さんは、あえて逆の立場をとり、街にすんで、山にも情報を伝えています。
今回のNHKの朝の連続テレビ小説「花子とアン」の放映が、村岡花子さんの業績が見直されるきっかけになったのではないかと、とても嬉しく思いました。
村岡花子さんは、他にも多くの児童書を翻訳されています。「花子とアン」の中でも、『王子と乞食』『少女パレアナ』などが紹介されていました。
本村岡花子・訳のモンゴメリの著作には、他に次のような作品があります。
『可愛いエミリー』『エミリーはのぼる』『エミリーの求めるもの』
『パットお嬢さん』『丘の家のジェーン』など
他の作家の作品では、エレナ・ポーター・作『少女パレアナ』『スウねえさん』などや、
ディケンズ、ジーン・ポーター、オルコット、ケート・D・ウィギンなどの作品も翻訳しています。
ミクシーでは、以前に日記や《元気な本棚・外国の児童書 その2》で村岡花子・著の『ハリエット・B・ストウ』をご紹介したことがあります。
モンゴメリ以外の作家の作品については、『少女パレアナ』と『スウ姉さん』は読んだことがありますが、村岡・訳であったかどうかさえ、憶えていません。
それで、他の作家の作品や、村岡花子さんの著書も読んでみたくなり、まず1冊借りてみました。
最近の新聞で、本書が偕成社文庫(800円)として再販されたばかりであることを知りましたが、図書館に単行本がありますので、そちらを読むことにしました。ヘレンケラーの伝記は、数多く出ていますが、本書は高学年以上の人向きでしょうか。
写真もいろいろ掲載されていますが、晩年のポートレートのヘレンの目が、明るく堂々とした光をたたえ、しっかり前を向いて見開かれていて、まるで見えているかのようで、ヘレンのそれまでの生き方すべてをこの目が語っていると思い、素晴らしいと感じました。
ヘレン・ケラーは、3度来日していますが、3度目の来日の時に何度も通訳をつとめられたのが、村岡花子さんでした。一緒の写真も掲載されていました。
『スズメの大研究』 ― 人間にいちばん近い鳥のひみつ
国松俊英・文 関口シュン・絵
PHP研究所(2004年)1250円
≪スズメはいつも人間の近くにいて親しみのある鳥です。
けれど、何を食べ、どこに巣を作り、どんな生活をしているのか、
本当の姿は意外と知られていません。
みんなの知らないスズメの生態から人間とのかかわりまでを広くさぐった一冊
この本でスズメが大好きになります。≫ (表紙カバー紹介文より)
 むかしは、カヤぶき屋根の家があり、スズメはそこに穴を見つけたり、また新しく穴をあけて巣を作りました。
むかしは、カヤぶき屋根の家があり、スズメはそこに穴を見つけたり、また新しく穴をあけて巣を作りました。
かわらの屋根はスズメが大好きなところです。棟がわら(鬼瓦がわら)やかわらの下にできたすきまを見つけて巣をつくります。
ところが現代になって、コンクリートのビルや、むかしのようなかわらを使わない家がふえ、スズメが巣を作る場所が少なくなりました。
スズメたちは、雨どい、えんとつの中、スピーカーの中、非常ベルの内側、排気口、ベランダのエアコンのすきまなど、べつの場所をさがして、巣を作るようになりました。
ひながかえったばかりのころ、親鳥がえさを運んでくる回数は、1日90回くらいです。ふ化して10日目くらいには、親鳥がえさを運んでくる回数は、1日300回以上になり、なんと2分30秒に1回、えさを運んでくることになります。
私の場合は、1日5回食事の支度をしています。スーパーに買い出しに出かけるのを合わせても6回です。調理の時間を考慮しても、ずっとかかりきりになっているわけではありません。スズメはえらい!
スズメのことわざ、スズメを使ったことば、スズメの家紋、スズメの名前がついた植物などについての<コラム>もあり、楽しい発見がいっぱい。
 イギリスや西ヨーロッパの国々に多く生息するイエスズメの数が大きく減ってきているといいます。日本のスズメも、少なくなってきているということです。
イギリスや西ヨーロッパの国々に多く生息するイエスズメの数が大きく減ってきているといいます。日本のスズメも、少なくなってきているということです。
著者が1995年ごろ、宮沢賢治の作品に出てくる鳥について調べたところ、鳥がいなくなていたり、数が少なくなっていたりしたそうです。
小鳥がいなくなり、けものも姿を消し、小さな生きものはみんないなくなりつつあります。
終わりには、こう書かれています。
「スズメの姿と鳴き声がいつまでも消えないように、わたしたちの身近な環境を大切に守っていきたい。スズメも人も地球の仲間なのです。」
国松俊英・文 関口シュン・絵
PHP研究所(2004年)1250円
≪スズメはいつも人間の近くにいて親しみのある鳥です。
けれど、何を食べ、どこに巣を作り、どんな生活をしているのか、
本当の姿は意外と知られていません。
みんなの知らないスズメの生態から人間とのかかわりまでを広くさぐった一冊
この本でスズメが大好きになります。≫ (表紙カバー紹介文より)
かわらの屋根はスズメが大好きなところです。棟がわら(鬼瓦がわら)やかわらの下にできたすきまを見つけて巣をつくります。
ところが現代になって、コンクリートのビルや、むかしのようなかわらを使わない家がふえ、スズメが巣を作る場所が少なくなりました。
スズメたちは、雨どい、えんとつの中、スピーカーの中、非常ベルの内側、排気口、ベランダのエアコンのすきまなど、べつの場所をさがして、巣を作るようになりました。
ひながかえったばかりのころ、親鳥がえさを運んでくる回数は、1日90回くらいです。ふ化して10日目くらいには、親鳥がえさを運んでくる回数は、1日300回以上になり、なんと2分30秒に1回、えさを運んでくることになります。
私の場合は、1日5回食事の支度をしています。スーパーに買い出しに出かけるのを合わせても6回です。調理の時間を考慮しても、ずっとかかりきりになっているわけではありません。スズメはえらい!
スズメのことわざ、スズメを使ったことば、スズメの家紋、スズメの名前がついた植物などについての<コラム>もあり、楽しい発見がいっぱい。
著者が1995年ごろ、宮沢賢治の作品に出てくる鳥について調べたところ、鳥がいなくなていたり、数が少なくなっていたりしたそうです。
小鳥がいなくなり、けものも姿を消し、小さな生きものはみんないなくなりつつあります。
終わりには、こう書かれています。
「スズメの姿と鳴き声がいつまでも消えないように、わたしたちの身近な環境を大切に守っていきたい。スズメも人も地球の仲間なのです。」
『神さまのいる村』― 白間津大祭物語
かわな 静・作 山口マオ・絵
ひくまの出版(2006年)1500円
図書館の児童書のコーナーで見つけた1冊の本が、「白間津のおおまち(大祭)」のことを知るきっかけになりました。
祭りまでの50日余りには、数々の試練が待っています。毎日夜が明けないうちに裸足で海に砂を取りに行き、神社にお供えする「ショゴリ」や、踊りの練習があります。
また、2人には、厳しい精進潔斎の勤めが課せられ、「穢れを避ける」ために、家族とは別火の生活を過ごす事になります。学校の給食も取ることが出来ず、外食時には弁当持参です。仲立ちの世話をするものは、老人に限られ、母親といえども世話をすることは出来なくなり、かわって祖母がこの役を担います。
これらを乗り越えて、2人の少年たちは立派に役目を果たします。
左の表紙写真は、「日天・月天」
中は、行列の先頭で露払いの役に相当する「トヒイライの振込み」
右は、魔物退治の役と云われる「エンヤボウ」。トヒイライの舞が付けた道の後の草を薙いでいる型であるとも言われている。
詩集に『浜ひるがおはパラボラアンテナ』 『ひもの屋さんの空』(いずれもジュニア・ポエム双書 銀の鈴社)などがあります。
第一部『魔の海に炎たつ』
第二部『さいはての潮に叫ぶ』
岡崎ひでたか・作 小林 豊・画
くもん出版(1300円)
<鬼瀬>は、房総半島(千葉県)南端の沖合の浅瀬で、黒潮がその流れや速度を複雑に変え、古来より多くのいのちをのみこむ魔の海域でした。
お話は明治の初期にはじまり、漁師のいのちを守る遭難しない船を造るという夢を一途に貫く、船大工満吉の波乱に満ちた生涯が描かれています。久しぶりの男性的な物語で、引き込まれて読んでいます。
千葉県を舞台にしたお話『白間津大祭物語』との出会いで、今さらながらですが、千葉県についてほとんど何も知らなかったことに気づきました。インターネットで白間津大祭について調べている時に、千葉県が舞台になっているお話が他にもいろいろ紹介されているのを見つけ、本書のことを知りました。
第三部『あかつきの波濤を切る』
第四部『夕焼け空に東風よ吹け』
岡崎ひでたか・作 小林 豊・画
くもん出版(1300円)
『鬼が瀬物語』(4部作)では、ひとりの船大工の一生を中心にすえて、小さな漁村の人々の喜びや悲しみ、生きざまなどが描かれています。
漁船改良の夢をようやく果たし、全国にヤンノウ型漁船の優秀性が認められ、時を同じくして、空前のマグロの豊漁期を迎え、豊の浦は繁栄にわきます。
ところが、鴈治郎という男の出現により、しだいに船主たちは金銭に支配されていきます。船乗りたちの命を守ることを願って改良した船なのに、性能がよくなった分無理を要求され、漁師たちはそれに従わざるをえませんでした。船の遭難事故が相次ぎ、多くの漁師たちの命が失われます。当時の村の記録によると、10年間で合計49隻が遭難にあい、212人もの犠牲を出しています。
“3部までの読者の方から、「満吉やヤエ(満吉の妻)を幸せにしてやってください」 「気のいい漁師たちも幸せにしてやってください」という希望が、たくさん寄せられたということです。
ですが、漁師や船大工の立場からすれば、やはり歴史の真実を書ききるしかありませんでした。犠牲になった漁師たちの無念さ、家族の悲しさを印象深く書くのが書き手としてのつとめだと思いました、
人間がお金に支配される世は冷たい世の中です。働く人たちが人間としてたいせつにされ、働きがいがある世の中になってほしい。懸命に働く人たちには幸せになってもらいたい。
満吉やヤエの心が、『鬼が瀬物語』を通して、時代や仕事のちがいを超えて、今日なお多くの人の心に生きつづけることができるなら、わたしとしてはこんなにうれしいことはありません。”
福音館書店(2014年10月)1400円
メイおばさんは、子どものころから、アヤカシが見える。秘密を守る鍵、秘密を開く鍵のアヤカシさんは、アヤカシの本性は、ある“物”で、アヤカシはその仮の姿なのだ、といいます。
レストランの象牙のピアノのアヤカシ、忘れ物の傘のアヤカシ、喫茶店の女主人の頭に乗っかっている鳩は鳩時計のアヤカシでした。アヤカシが、二人に訴えたいことは・・・・・。
そして、不思議な手毬に導かれて入った家で見たものは、メイの少女時代へと記憶をさかのぼり、大切な忘れていたものを見つけます。
画家・野見山響子さんのゴム版画が素晴らしい。本文の挿し絵は白黒になっています。これだけの表現が可能なことに、素人である私は驚きました。
福音館は、ていねいな本作りをされることで定評のある出版社。次の作品をまた楽しみに待ちたいと思います。
汐文社(2007年)1300円
内戦続きだった西アフリカのリベリア共和国で、暴行を受けて、歩けなくなったマーサちゃん。「日本で治療を受けさせたい」と手を差しのべたのは、国境なき医師団・看護師としてリベリアを訪れた美木朋子さんでした。
「マーサと同じように苦しんでいる子どもたちは何万人もいる。わたしには、この国の状況は何も変えられないかもしれない。でも、せめて出会った人にだけでも、自分ができる精一杯のことをしたい」 (カヴァー裏紹介文より)
マーサちゃんの看護をしていたブライアンは、引き継ぎのときに朋子さんにこんな言葉を言い残しました。
「彼女はスペシャル・ガールだ。くれぐれもこの子をよろしくたのむ」
マーサちゃんと朋子さんの結びつきは、ヘレン・ケラーとサリバン先生の関係を連想させました。ヘレンとサリバン先生のたゆまない努力は、障害に苦しむ世界の多くの人々を助けることにつながっていったのです。
その後マーサちゃんはどうしているでしょうか? 近況を知りたい気がします。沢田俊子さんが、また本にしてくれないかしら・・・・・。
『米と話して365日』 谷本雄治・著 こぐれ けんじろう・絵
文渓堂(2014年11月)1300円
今日本では、日本の農家にとっても、お米屋さんにとっても、たくさんの厳しい課題を抱えてす。
スーパーマーケットが増えたり、昔にくらべて1人あたりのお米の消費量も減ってきています。「減反」で田んぼが減り、将来の見通しが立たず、若者は農業に背をむけていきます。
出版社や新聞社からも声がかかり、テレビやラジオにも何度も出演されていたりして、有名なお米屋さんなのだそうです。
佼成出版社(2008年)1300円
『ムササビ ムーちゃん』 井上豊子・文 村上 勉・絵
佼成出版社(2005年)1300円
“みんなみんな、大切ないのち。動物たちからの、すばらしい「いのちのメッセージ」が、あなたの心にとどきますように。”とあり、大変共感しました。
りえちゃんは小学3年生。お父さんは「鳥獣保護員」をしています。ある日、ニホンカモシカの赤ちゃんが保護され、お父さんに託されます。1年後に山に帰すまで、家族で世話をすることになり、りえちゃんは大喜びです。
和智まるさんというおばあさん一家と、ムササビの子ムーちゃんの、実際にあったお話です。
ある日庭で、生まれたてのムササビの赤ちゃんが見つかりました。木の上に巣があるようで、そこから落ちてしまったのです。よく見ると、目や口から血がでています。
「助けてあげてよ。おばあちゃん、おねがい!」
まるさんは、なんとしてもこの子を助けるんだと、決心します。
私が幼い頃に出会った一冊の絵本、宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』は、一番深く心に残っている本です。細かいところまでは忘れてしまっても、ゴーシュと動物たちの間に垣根がなくて、心をかよい合わせているのが理屈でなく伝わってきて、その小さな部屋の壁が、生きているように温度を持っているようで、手をのばしてさわってみたい、と思いました。そのとき感じた「ぬくもり」はずっと私の心に残り、その後の人生で殺伐とした思いを何度も経験するたびに私を助けてくれました。
子どもの心には、動物と人間がなかよく心をかよわせるというような本も、すっと入ってきます。幼い時に、そんな本との出会いがあったらどんなにいいでしょう。絵本・児童書は、“子どもの心起こし”となる大切な役目を持っているのだという思いを、あらためて強くしました。
『アンモナイトの森で』 少女チヨとヒグマの物語
市川洋介・作 水野ぷりん・絵
学研教育出版(2010年)1200円
北海道の中央部に近いそのあたりの土地は、深い森や沢が広がる無人の土地でした。それが、明治にはいって、ひとりのきこりが、山の中で偶然石炭を発見し、やがて炭鉱の町として開けていきました。
チヨの父親は、農作業や山仕事のかたわら、炭焼きをしています。そのへんの山のことを幼いころから身につけて育ったチヨには、生まれながらに、他の人間にはない特別なものを持っていました。普通は警戒して、人に近よらないキタキツネやエゾリス、そしてエゾシカまでが、チヨのそばに平気でよってきました。
ある日チヨは、知らない森にはいりこんで、一頭のヒグマに出会いました。以前に一度出会ったことのあるヒグマでした。ヒグマは、チヨに帰る道をおしえます。
見おぼえのない沢に出たとき、チヨはその先がどうなっているかたしかめたいと思いました。そして崖崩れがあった場所に来たとき奇妙な石を見つけ、持って帰りました。千代の父親が鉱山技師の人に見せるとアンモナイトの化石であることがわかりました。
それから何年もたってから、化石のことを知った調査隊がやってきます。千代はその場所へ案内しますが、金目当てで欲に目がくらんだ人たちが、調査隊に取り入り、ヒグマを退治することになります。調査隊を山に案内したことを悔やみ、苦しんだチヨは・・・・・
本書は、第18回<小川未明文学賞>大賞受賞作品。
<日本の伝統文化が好きで、落語も歌舞伎、能や狂言、文楽も好き。日本独自の構図、色の使い方など、自分の絵のなかにとりいれたいなぁと思っています。西洋からのものがあふれる時代ですが、日本の子どもたちには日本人らしい感性も身につけて育ってもらいたいなぁ、日本を語れる人になって、世界にはばたいてほしいなぁ、と思っています。>
(ネット掲載のメッセージより)
表紙写真は『かさじぞう』です。役割を決めて読んでいくだけで、手軽に劇遊びができるユニークな絵本です。水野ぷりんさんの着物姿のお写真もすてきだったので、拝借して載せました。
青井俊樹・著 フレーベル館(1998年)1500円
クマをとおして見えてくる自然界全体。その中にはもちろん人間も含まれています。そのことに気づいてから、もっと知りたいという思いに動かされて、本を探すようになりました。
フレーベル館から出版されている「森の新聞」シリーズには、たくさんの生きものたちが登場します。
≪ヒグマときくと、どうもうでおそろしい動物というイメージが定着しました。でも、ヒグマはほんとうにおそろしい動物なのでしょうか。
人間の生活範囲がひろがり、ヒグマの暮らすところにまで人間が入りこむようになり、その結果、人間とヒグマのあいだに、衝突が起きたりしています。いま、その衝突を減らし、いかにして 人間もヒグマも、ともに安心して暮らせるようにするかが、課題になっています。
第20号『ヒグマの原野』は、1996年につかまえたオスグマに電波発信機をつけて放し、2年間以上、必死に追跡調査したドキュメントです。そこから、じつに驚くべき新発見がありました。はたしてヒグマは、人間の危険な敵なのでしょうか、それとも、アイヌがいったようにキムン・カムイ(山の神様)なのでしょうか。≫ (文中より抜粋)
今までに読んだ本には、クマが開けることができないような頑丈なゴミ箱を作ったり、ゴミを外に放置しないようにと呼びかける取り組みがされていることも、紹介されていました。こういった取り組みが世間一般に広がるようにと願っています。
塩澤実信・文 北島新平・絵
理論社(1990年)1200円
写真家・宮崎学さんの本を続けて読んでいます。
『動物と話せる男』(塩澤実信・文)は、長野県伊那谷で生まれ育った宮崎さんの幼少時代から、動物写真家として独立するまでのこと、貴重な作品の数々が撮影された背景などを知ることが出来るということで、是非とも読みたいと思いました。
中学校を出て、アルバイトをしながら、伊那谷に生きるさまざまな動物たちの写真を撮り続けますが、過酷な条件を押しての撮影で身体をこわし入院。希望を失い自殺を考えたことも。そんな日々を乗り越え、写真雑誌に応募した作品が入選します。
ある時、伊那谷に集まるカラスのことで訊ねてきた人がありました。大阪の千趣会という出版社の編集長・廣岡正勝という人です。カラスの大群を絵本にする企画があって、誰かこのあたりで動物に詳しい人がないかさがし、人づてに宮崎さんのことを聞いて来られたのです。2度目に廣岡氏は、絵本を担当される児童文学者の今江祥智氏とともに伊那谷を訪れました。そしてこの2人は、名伯楽として宮崎さんの才能を伸ばし、後押しをしてくれることになるのです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
元気な本棚 ほっこり 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
元気な本棚 ほっこりのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90004人
- 3位
- 酒好き
- 170654人