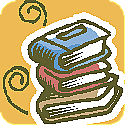<その1>が20まで来ましたので、続きはこちらをごらん下さい。
本の紹介も気楽に書き込んでくださいね
6番目の『さんねん峠』は、朝鮮の昔話ですが、在日の女性により日本で出版された絵本です。迷いましたが、結局このコーナーに入れました。
1 『夜明け前から暗くなるまで』 ナタリー・キンジー・ワーノック/文
メアリー・アゼアリアン/絵 千葉茂樹/訳 BL出版
2 『ルイーザ・メイとソローさんのフルート』
ジュリー・ダンラップ・&メアリベス・ロルビエッキ/作
メアリー・アゼアリアン/絵 長田 弘/訳 BL出版
3 『レイチェル』 エミリー・エアリク/文 ウェンデル・マイナー/絵 BL出版
4 『モーゼスおばあさんの四季』 W.ニコラ-リサ/編・詩 加藤恭子・和田敦子/訳 BL出版
6 『山になった巨人』− 白頭山ものがたり リュウ チェスウ 作・絵
イ サンクム/まつい ただし 共訳 福音舘書店
7 『さんねん峠』− 朝鮮のむかしばなし 李錦玉・作 朴民宣・絵 岩崎書店
8 『くまさんのキルトは セリーナのたからもの』
バーバラ・スマッカー/作 ジャネット・ウィルソン/絵
田中治美/訳 ぬぷん児童図書出版
9 『ふゆのはなし』 エルンスト・クライドルフ/文・絵
大塚勇三/訳 福音舘書店
10 『モンゴルの黒い髪』 バーサンスレン・ボロルマー/絵・文
長野ヒデ子/訳 石風社
11 《モンゴルの絵本》
『ぼくのうちはゲル』 バーサンスレン・ボロルマー
長野ヒデ子/訳 石風社
『バートルのこころのはな』 イチンノロブ・ガンバートル/作
バーサンスレン・ボロルマー/絵
津田紀子/訳 小学館
『おかあさんとわるいキツネ』イチンノロブ・ガンバートル/文
バーサンスレン・ボロルマー/絵
津田紀子/訳 福音舘書店
12 『トゥース・フェアリー』ー 妖精さん、わたしの歯をどうするの?
ピーター・コリントン/作・絵 BL出版
13 『聖なる夜に』 A Small Miracle ピーター・コリントン/作・絵
BL出版
14 『ワンガリと平和の木』 ジャネット・ウィンター/作・絵
福本友美子/訳 BL出版
『ワンガリ・マータイさんとケニアの木々』
ドナ・ジョー・ナポリ/作 カディール・ネルソン/絵
千葉茂樹/訳 すずき出版
15 『あたまにつまった 石ころが』 キャロル・オーティス・ハースト/文
ジェイムズ・スティーブンソン/絵
千葉茂樹/訳 光村教育図書
16 『みどりの船』 クェンティン・ブレイク/作 千葉茂樹/訳
あかね書房
17 『みつばちじいさんの旅』 フランク・ストックトン/作 モーリス・センダック/絵
光吉夏弥/訳 童話舘出版
18 『十長生をたずねて』 チェ・ヒャンラン/作・絵
おおたけきよみ/訳 岩崎書店
19 『アンデルセン自伝』 イブ・スパング・オルセン/絵
乾 侑美子/訳 あすなろ書房
20 インドの絵本 『10にんのきこり』 A.ラマチャンドラン/作
田島伸二/訳 講談社
21 『どうぶつたちは しっている』
イーラ/写真 マーガレット・ワイズ・ブラウン/文
寺村摩耶子/訳 文遊社(2014年4月)
22 『蛙となれよ冷やし瓜』 一茶の人生と俳句
マシュー・ゴラブ/文 カズコ・G・ストーン/絵
脇 明子/訳 岩波書店
23 『ヘレン・ケラーのかぎりない夢』
ドリーン・ラパポート/文 マット・タヴァレス/絵
もりうち すみこ/訳 国土社
24 『 ゆきの まちかどに 』 ケイト・ディカミロ/作
バグラム・イバトーリーン/絵
もりやま みやこ/訳 ポプラ社
|
|
|
|
コメント(25)
メアリー・アゼアリアン/絵
千葉茂樹/訳 BL出版(2006年)
それと、ターシャ・チューダーの家も、確かバーモンド州にあったことを思い出しました。
アゼアリアンは版画で絵本の挿絵を手がけています。以前ご紹介した『雪の写真家ベントレー』の挿絵も彼女によるものです。
影絵にも共通していることですが、版画も、細かいタッチは無理で荒削りな分、力強さがあり、独特の味わいになって、人の心をとらえるように思います。
ジュリー・ダンラップ&メアリベス・ロルビエッキ/作
メアリー・アゼアリアン/絵 長田 弘/訳 BL出版(2006年)
ルイーザ・メイとは、ルイーザ・メイ・オルコットのことで、南北戦争時代を生きた四人の姉妹の物語『若草物語』を書いた人です。ソローは、アメリカの作家・思想家・詩人・博物学者です。代表作『森の生活』は、2年2ヶ月におよぶ森での一人暮らしの記録をまとめたものであり、その思想は後の時代の詩人や作家に大きな影響を与えました。
ルイーザは死ぬまで、断続的にですが、コンコードに住みつづけます。ソローは1862年に結核のため世を去っています。
ソローを讃えて、ルイーザは「ソローさんのフルート」という詩を書き、「森の天才が逝った」と悲しんだということです。
エミリー・エアリク/文 ウェンデル・マイナー/絵
池本佐恵子/訳 BL出版(2005年)1400円+税
レイチェル・カーソンの伝記絵本です。
カーソンといえば、まず『沈黙の春』が思い浮かびます。
今日の環境保護運動は『沈黙の春』の出版で始まったといわれます。
“「センス・オブ・ワンダー」を持ち続け、真理を探究し続けたレイチェル。その生涯を物語る本書の中には、混迷の現代に生きる子どもたちへのメッセージ ― 言葉の力、組織を持たないたったひとりの人間に秘められた力、そして何よりも、自分を信じ自分の心に忠実に生きることの大切さ ― が輝いています。”
レイチェル・カーソンの著書には、他に『センス・オブ・ワンダー』『われらをめぐる海』などがあります。ご紹介した絵本はプレゼントにしても素適なのでは。
W.ニコラ-リサ/編・詩 加藤恭子・和田敦子/訳
BL出版(2003年)
農家の普通の主婦として、料理に掃除洗濯、缶詰作り、刺繍などに勤しんできたモーゼスが、絵を描くようになり、それがアマチュアの絵画収集家の目にとまり、最初の個展が開かれたのは80歳の時だったといいます。
年齢を重ねても、明るく、人の役に立って生きている、あるいは生きた人の存在を知ることは、私自身のこれからの生き方を考える上でも、希望と力強い励ましをいただけるように思います。
年寄りだからといって、もうだめだとか、引っ込んでいようというのは、せっかくこれまで生きてきて、経験を積み重ねてきて得たものがあるというのに、もったいないことだと思うのです。次の時代を担う若い人たちに伝えていかねばならない大切なことがあるのではないでしょうか。
前置きが長くなってしまいました。そんなわけで、モーゼスおばあさんのこともずっと心にあり、詳しく知ることが出来たらと思っていましたが、絵本が出ていることを知り、心待ちにして読んでみました。
“モーゼスおばあさんの作品を長年知っていたが、自伝をみつけて目をとおしてから、本当にすばらしいと思いはじめた。モーゼスおばあさんの自然を愛する心、そしてまわりの人々や出来事への感謝の気持ちが私の心を打った。と同時に、彼女はニューヨーク北部の地方という世界のほんの小さな一角を、めぐりくる季節ごとに、おどろくほど細かく描いたのだとわかりました。”
それぞれの絵には自伝からの引用がつけてあり、子供たちへのてがかりとして、声にだして読めるように、編者自身の詩が添えられています。
イ サンクム/まつい ただし 共訳
福音舘書店(2100円+税)
松居直さんは、敗戦の経験から、絵本の編集者として、これからの子どもに何をどう語り伝えればよいのかと自問自答を繰り返し、そのなかで、当時はわが国の絵本出版ではほとんど顧みられていないアジアの各民族の昔話や物語を、読者に紹介してゆこうと考えられました。そしてまず隣り人である韓国と中国の人々のことを、単なる知識としてでなく、人間や文化や風土の違いを知り、また通じ合うところを心で感じとってもらうことが大切だと考えられました。
この本が出版されるまでの経緯が、『絵本のよろこび』(松居 直・著 NHK出版)に詳しく書かれていて感銘を受けました。
『さんねん峠』− 朝鮮のむかしばなし 李錦玉・作 朴民宣・絵
岩崎書店(1981年第1刷・2006年第29刷〜)1200円+税
表紙の絵は、おじいさんが石につまずいてまさに転ばんとする瞬間で、なにかユーモラスです。おおらかな物語と、朝鮮の農村の風景や人々の暮らしが伝わってくる絵が、とてもよかったです。
“朝鮮はわたしたちにとって、もっとも古くからの近い隣国であることを知らない人はいない。日本の風俗、習慣はもちろんのこと、文化のすべてが朝鮮をぬきにして語れない。
にもかかわらず、明治以降のわたしたちの目は、西欧にすっかり向いてしまっただけでなく、日韓併合という他民族を抑圧するという一時期もあって、一部では蔑視さえもしていた事実があったことはいなめない。(中略)
60〜70万人朝鮮の人たちが、この日本でいっしょに生活している。これほど親しい朝鮮の文化がほとんど紹介されていないことをまず不思議に思うべきではないか。”
『くまさんのキルトは セリーナのたからもの』
バーバラ・スマッカー/作 ジャネット・ウィルソン/絵
田中治美/訳 ぬぷん児童図書出版(1997年)1200円+税
先日紹介した『勇気は私たちの祖国』では、信仰を守るためにロシアに移り、ウクライナに定住したメノナイト派の人々が、1917年に起こったロシア革命と内戦を耐え、信仰を守るためにカナダに移り住むまでが、ピーター少年とその家族をとおして描かれています。
祖母は、家族が着ていた服の端切れをつなぎあわせたキルトのベッドカバーを作って、セリーナに持たせます。思い出のいっぱいつまったカバーを大切に持って、セリーナはカナダに旅立ちます。
全ページがキルト作家、ルーシー・アン・ホリディの手によるキルトで縁どられています。ていねいに、ていねいに心を込めて作られた絵本です。プレゼントにもいいのでは。
大塚勇三/訳 福音舘書店(1971年初版)
エルンスト・クライドルフは、1863年、スイス生まれの詩人作家です。
スイスの人々が今もこよなく愛し、誇りとしている彼の絵本の数々は、20世紀の初めごろにかかれました。
<絵本がだんだん「自然」から離れて人工的になってゆく。スマートで楽しく、甘い後味の絵本が多くなった。しかし、どこか空ろである。通り抜けるのには楽しいが、後に何も残らない。>
それに対して、いつの時代にも読者に語りかけるものを持った作品として、いくつかあげられている中に、クライドルフ作品があり、こう書かれています。
<アルプスの高原に咲く花々にたとえられる透明な美しさをたたえ、現代の物の生活になれきって感覚の鈍ってしまった私たちが、全くといってよいくらい失ってしまった清澄な光と影の織りなす神秘と幻想の世界が、そこには確然とある。>
『モンゴルの黒い髪』 バーサンスレン・ボロルマー/絵・文
長野ヒデ子/訳 石風社(2004年)1300円+税
 モンゴルを舞台にした絵本といえば、赤羽末吉さんの『スーホの白い馬』が、よく知られています。何度読んでも心の深いところが揺り動かされるような作品です。
モンゴルを舞台にした絵本といえば、赤羽末吉さんの『スーホの白い馬』が、よく知られています。何度読んでも心の深いところが揺り動かされるような作品です。
ですが、同じアジアの国なのに、モンゴルについてかかれた絵本といえばこの作品しか知らず、これではいけないと思って探してみました。今日ご紹介する絵本をかいた、バーサンスレン・ボロルマーは、1982年生まれのモンゴル人の女性です。
 昔、平和に暮していたモンゴルの遊牧民がいました。ところが、悪いことをたくらんでいる者たちが、草原を奪おうとたくらみ、4羽の邪悪なカラスをゆかせることにしました。
昔、平和に暮していたモンゴルの遊牧民がいました。ところが、悪いことをたくらんでいる者たちが、草原を奪おうとたくらみ、4羽の邪悪なカラスをゆかせることにしました。
そのはなしを、1羽のカササギが聞き、おおいそぎでモンゴルの人々に知らせに飛んでゆきました。
はなしを聞いたモンゴルの男たちは、敵を追いはらうために戦いにいくことにしましたが、あとに残る家族をカラスからどう守るかが心配です。
「カラスが自分たちより強いと思ってふるえあがっておそれるものをつくったらどうだろう。」
女たちは黒い髪を二つに束ねて大きなつばさのようにし、かざりをつけました。
ついに邪悪なカラスたちがやってきましたが、女たちはひるみません。4羽のカラスは大きなつばさにおびえて、逃げてゆきました。
 この表紙のような衣装をまとった作者の写真が紹介されています。本物の髪に似せて作られた頭の飾りは、とてもダイナミックです。大きな目と、はつらつとした雰囲気が印象的な女性でした。
この表紙のような衣装をまとった作者の写真が紹介されています。本物の髪に似せて作られた頭の飾りは、とてもダイナミックです。大きな目と、はつらつとした雰囲気が印象的な女性でした。
長野ヒデ子/訳 石風社(2004年)1300円+税
ですが、同じアジアの国なのに、モンゴルについてかかれた絵本といえばこの作品しか知らず、これではいけないと思って探してみました。今日ご紹介する絵本をかいた、バーサンスレン・ボロルマーは、1982年生まれのモンゴル人の女性です。
そのはなしを、1羽のカササギが聞き、おおいそぎでモンゴルの人々に知らせに飛んでゆきました。
はなしを聞いたモンゴルの男たちは、敵を追いはらうために戦いにいくことにしましたが、あとに残る家族をカラスからどう守るかが心配です。
「カラスが自分たちより強いと思ってふるえあがっておそれるものをつくったらどうだろう。」
女たちは黒い髪を二つに束ねて大きなつばさのようにし、かざりをつけました。
ついに邪悪なカラスたちがやってきましたが、女たちはひるみません。4羽のカラスは大きなつばさにおびえて、逃げてゆきました。
『ぼくのうちはゲル』 バーサンスレン・ボロルマー
長野ヒデ子/訳 石風社(2006年)1500円+税
『バートルのこころのはな』 イチンノロブ・ガンバートル/作
バイサンスレン・ボロルマー/絵
津田紀子/訳 小学館(2011年)1400円+税
『おかあさんとわるいキツネ』イチンノロブ・ガンバートル/文
バーサンスレン・ボロルマー/絵
津田紀子/訳 福音舘書店(2011年)1400円+税
3冊とも、先だってご紹介した『モンゴルの黒い髪』をかいた、バーサンスレン・ボロルマーによる絵本です。うち2冊は、夫のイチンノロブ・ガンバートルとのコンビで創作されたものです。
“ゲル”はモンゴルの家族が住む、まるい家です。やなぎの木で組まれ、羊の皮とフェルトでおおいます。人々は季節ごとに家をたたんでは移動し、新しい土地につくと、そこでまた組み立てて暮します。
モンゴルの伝説をもとにしてかかれた絵本。あとがきには、こう書かれています。
<自分のことを生み、育ててくれたおかあさんの恩というのは、とても大きいものです。モンゴルの人びとは、その大きな恩を敬って、「おかあさんのお乳は、花のしずくを集めてわかしていれた、一杯のお茶ほどに貴重である」と言い伝えてきました。>
主人公のバートルという少年が、おじいさんから聞いた“こころのはな”をさがしに、勇気を出してよるの森をぬけていき、こわさにうち勝ってとうとう“こころのはな”をみつけ、朝露を集めておかあさんにもって帰ります。
モンゴルの北のはてには、タイガとよばれる深い森がひろがっています。そこには、あかちゃんをねらう悪いキツネたちがすんでいました。
あかちゃんを一人でゲルの中に残して、外で働かなければならないおかあさんが、知恵をしぼってキツネからあかちゃんを守ります。
ピーター・コリントン/作・絵 BL出版(1998年)1500円+税
先日ご紹介した、『人生に大切なことは すべて絵本から教わった』(末盛千枝子・著)の中で、イギリスの絵本作家・コリントンの『聖なる夜に』などが紹介されていました。この本については書かれていなかったのですが、図書館で検索してみて見つけました。
いろんな妖精がいますが、トゥース・フェアリー(歯の妖精)とは、はじめてです。私は、ちょうど歯医者通いをしていて、絵本を読むときぐらいは、歯のことを忘れたいなあと思ったのですが、結局借りてしまいました。
妖精は、その歯で、なんとピアノの鍵盤を作るのです! 人間の弾くピアノの鍵盤には、象牙を用いたりしますが・・・
ただ、歯が抜けた少女が、大人びていてかわいくなく、それだけがちょっと違和感でした。
BL出版(2000年)1300円+税
おばあさんはアコーディオンを持って街に出かけていき、お金をかせごうとしますが、誰も耳を傾けないで通り過ぎていきます。しかたなく、おばあさんはアンティークショップに行き、アコーディオンを売ってわずかなお金を得ますが、ひったくりに遭い、お金を盗られてしまいます。
そして、追いかけていった先の教会から、泥棒が献金箱を盗って逃げようとしているのを見つけ、必死で献金箱を取り返して教会の中に入り、中から鍵をかけます。
教会の中は、クリスマス用にまつられている人形の聖人達が、倒され、床にころがっています。おばあさんは聖人達をもとに戻してやり、献金箱をそばに置いて雪道を帰っていきますが、力つきて倒れてしまいます。
聖人達は、おばあさんの家で美味しいクリスマスの料理を作り、もみの木を運んできて飾り付けをし、お金を置いて帰っていきます。
目が覚めたおばあさんの驚きと喜び。正しく生きる人に、小さな奇跡がおこったのです。
静かな深い感動をおぼえた絵本です。クリスマスまで待てなくて紹介してしまいました。
福本友美子/訳 BL出版(2010年)1400円+税
『ワンガリ・マータイさんとケニアの木々』
ドナ・ジョー・ナポリ/作 カディール・ネルソン/絵
千葉茂樹/訳 すずき出版(2011年)1900円+税
ニ冊とも、2004年にノーベル平和賞を受賞した、ワンガリ・マータイさんの伝記絵本です。
マータイさんは、アフリカのケニア山のふもとのみどりゆたかな村に生まれました。ところが、大きくなってアメリカ留学からもどると、木は切り倒され、あれた畑には何一つ育っていません。大きな建物をつくるためにどんどん木は切り倒され、かわりに新しい木を植える人はだれもいなかったのです。
なんとかしなければと、マータイさんは、家の裏にまず7本の苗を植えることからはじめました。
マータイさんは、根気よくあきらめずに木を植える運動を続けていきました。その間、何度も逮捕されましたが、決して活動をやめようとはしませんでした。
読み語りやプレゼントにもお薦めしたい本です。
マータイさんの活動についての詳しいことは、ここでは省きます。
この本を読んだ子どもたちの心に蒔かれた種が、将来花開く時が来ることを願い、夢みています。
『あたまにつまった 石ころが』 キャロル・オーティス・ハースト/文
ジェイムズ・スティーブンソン/絵
千葉茂樹/訳 光村教育図書(2002年)1400円+税
 ほんとうにあったお話です。
ほんとうにあったお話です。
著者のお父さんは、子どものころ石を集めていました。ひまを見つけては石をさがして歩き、「あいつは、ポケットにもあたまのなかにも石ころがつまっているのさ」と言われていました。
大人になるとガソリンスタンドをはじめたお父さんは、石を集めつづけ、店のなかには棚を作り、石を並べ、ラベルをつけました。
それから、大恐慌が起こり、仕事がこなくなり、古い家に引越しました。石も屋根裏部屋に運び込みました。仕事が見つからず、雨がふっている日には、科学博物館にでかけ、石が陳列されている部屋ですごしたりしました。そして、博物館の館長の女性と知り合った縁で、博物館の管理人になり、それから専門家として認められて鉱物学部長になります。
そして、館長の女性が退職するとその後を継いで、なんと館長に就任するのです。
著者はあとがきの中で、「父ほど幸福な人生を送った人を、わたしはほかに知りません」と書かれています。
以前紹介した『雪の写真家 ベントレー』(BL出版)を思い出しました。それに、この本も確か千葉茂樹さんの訳でした。
 本のはじめの献辞には、著者の身近な人の名前に続けて、“あたまに石のつまったすべての人に”と書かれていました。
本のはじめの献辞には、著者の身近な人の名前に続けて、“あたまに石のつまったすべての人に”と書かれていました。
ジェイムズ・スティーブンソン/絵
千葉茂樹/訳 光村教育図書(2002年)1400円+税
著者のお父さんは、子どものころ石を集めていました。ひまを見つけては石をさがして歩き、「あいつは、ポケットにもあたまのなかにも石ころがつまっているのさ」と言われていました。
大人になるとガソリンスタンドをはじめたお父さんは、石を集めつづけ、店のなかには棚を作り、石を並べ、ラベルをつけました。
それから、大恐慌が起こり、仕事がこなくなり、古い家に引越しました。石も屋根裏部屋に運び込みました。仕事が見つからず、雨がふっている日には、科学博物館にでかけ、石が陳列されている部屋ですごしたりしました。そして、博物館の館長の女性と知り合った縁で、博物館の管理人になり、それから専門家として認められて鉱物学部長になります。
そして、館長の女性が退職するとその後を継いで、なんと館長に就任するのです。
著者はあとがきの中で、「父ほど幸福な人生を送った人を、わたしはほかに知りません」と書かれています。
以前紹介した『雪の写真家 ベントレー』(BL出版)を思い出しました。それに、この本も確か千葉茂樹さんの訳でした。
あかね書房(1998年)1600円+税
夏休みを、いなかのおばさんの家ですごすうちにたいくつしはじめていた姉弟は、壁を乗りこえてとなりのおやしきの庭にもぐりこみます。そして、奥へ奥へとすすむうちに、びっくりするようなものが目のまえにあらわれます。
子どもの成長にとって、遊びは大切で、欠くべからざるものです。今の子どもたちは、自由に遊べる環境にもめぐまれず、わくわくする冒険をしてみたくても、あこがれに終ってしまうことが多いのではないでしょうか。この姉弟のように、思いっきり冒険を楽しむことができたら、どんなに素晴らしいことでしょう。
『みつばちじいさんの旅』 フランク・ストックトン/作
モーリス・センダック/絵
光吉夏弥/訳 童話舘出版(1998年)1,238円+税
 むかし、みつばちじいさんというおじいさんがいました。いつもみつばちといっしょにくらしていたので、そうよばれていたのです。
むかし、みつばちじいさんというおじいさんがいました。いつもみつばちといっしょにくらしていたので、そうよばれていたのです。
おじいさんは、小さな小屋にすんでいましたが、小屋の中はあっちもこっちも、みつばちの巣だらけでした。おじいさんの顔や手は、かたくてごつごつしていたので、みつばちは木や石はささないように、おじいさんをさそうなどとはしませんでした。
ある日、ひとりのわかい魔法つかいがおじいさんの小屋にたちよました。魔法つかいは、おじいさんが、なにかの生まれかわりであるといい、もう一ど、もとのすがたにもどらなければならない、といいますが、もとのすがたがなんなのかはわかりません。おじいさんはそれをさがしに旅にでかけます。
いろんな目にあいながら旅をつづけ、ある日、りゅうにつかまった赤んぼうをたすけ、お母さんの手にかえします。おじいさんは、赤んぼうに強くひきよせられ、自分は赤ん坊の生まれかわりにちがいないとおもい、魔法使いにもう一ど赤んぼうにもどしてもらい、助けた赤んぼうといっしょに育ててもらいます。
 さて、大きくなったおじいさんは、いったいどうなったでしょうか?
さて、大きくなったおじいさんは、いったいどうなったでしょうか?
センダックの絵がとてもいい。赤んぼうにもどったおじいさんの顔がもとのままで、ぜんぜん可愛くないのが可笑しい。
モーリス・センダック/絵
光吉夏弥/訳 童話舘出版(1998年)1,238円+税
おじいさんは、小さな小屋にすんでいましたが、小屋の中はあっちもこっちも、みつばちの巣だらけでした。おじいさんの顔や手は、かたくてごつごつしていたので、みつばちは木や石はささないように、おじいさんをさそうなどとはしませんでした。
ある日、ひとりのわかい魔法つかいがおじいさんの小屋にたちよました。魔法つかいは、おじいさんが、なにかの生まれかわりであるといい、もう一ど、もとのすがたにもどらなければならない、といいますが、もとのすがたがなんなのかはわかりません。おじいさんはそれをさがしに旅にでかけます。
いろんな目にあいながら旅をつづけ、ある日、りゅうにつかまった赤んぼうをたすけ、お母さんの手にかえします。おじいさんは、赤んぼうに強くひきよせられ、自分は赤ん坊の生まれかわりにちがいないとおもい、魔法使いにもう一ど赤んぼうにもどしてもらい、助けた赤んぼうといっしょに育ててもらいます。
センダックの絵がとてもいい。赤んぼうにもどったおじいさんの顔がもとのままで、ぜんぜん可愛くないのが可笑しい。
『あなはほるもの おっこちるとこ』― 岩波の子どもの本
クラウス・文 センダック・絵 わたなべ しげお・訳
今さら私などが紹介するまでもない、よく親しまれている絵本ですが・・・。
 かおは いろんな かおを するためにあるの
かおは いろんな かおを するためにあるの
ては つなぐために あるの
じめんは おにわを つくるために あるの
だきあうために うでが あるのよ
 ケーキの かすを ゆかに おとさないように
ケーキの かすを ゆかに おとさないように
ひざが ついているんだよ
 ねこは こねこを うんでくれる どうぶつ
ねこは こねこを うんでくれる どうぶつ
 たのしい絵本です。子どものころに持っていた新鮮な感受性、遊び心を、大人になっても忘れないで持ち続けることは、なかなかむずかしいこと。でも、幼い子たちに絵本を語って聞かせることなどをとおして、また子どものころの生きいきした気分を思い出すことができる。絵本との出会いは、一度だけでなく、二度、三度と可能なのです。
たのしい絵本です。子どものころに持っていた新鮮な感受性、遊び心を、大人になっても忘れないで持ち続けることは、なかなかむずかしいこと。でも、幼い子たちに絵本を語って聞かせることなどをとおして、また子どものころの生きいきした気分を思い出すことができる。絵本との出会いは、一度だけでなく、二度、三度と可能なのです。
クラウス・文 センダック・絵 わたなべ しげお・訳
今さら私などが紹介するまでもない、よく親しまれている絵本ですが・・・。
ては つなぐために あるの
じめんは おにわを つくるために あるの
だきあうために うでが あるのよ
ひざが ついているんだよ
『十長生をたずねて』 チェ・ヒャンラン/作・絵 おおたけきよみ/訳
岩崎書店(2010年)1500円+税
おじいちゃんとわたしは、だいのなかよしです。
でもこのごろ、おじいちゃんは元気がなく、わたしとあそんでくれません。
そして、とうとう入院してしまいました。
おじいちゃんのいないお部屋で、おさいほう道具のなかのきんちゃくぶくろを手にとり、そっとなでてみると、つるがパタパタととびでてきました。
つるは、『十長生』について、おしえてくれます。わたしは、十長生をあつめておじいちゃんにもっていってあげようと、つるの背中にのって飛び立ちました。
美しい絵本です。鶴や太陽、不老草、水などは布や刺繍で表わされ、鹿と竹は螺鈿細工です。原画はもっと素適だろうなあと想像します。
乾 侑美子/訳 あすなろ書房(1996年)1800円
イブ・スパング・オルセンはアンデルセンと同じデンマーク人の画家です。陰影のある少し暗い色調が、物語の内容の深い部分までを表現しているようで、引き込まれます。
デンマークのオーデンセの小さな貧しい家に、結婚したばかりの、若い靴屋の夫婦が住んでいました。靴屋は、靴作りの仕事台と花嫁をむかえるベッドを、自分で作りました。ベッドの枠に使ったのは、ほんのすこし前に亡くなった伯爵が横たわっていた柩の台でした。1805年4月2日、ひとりの元気なあかんぼうがそこにねかされていました。それがハンス・クリスチャン・アンデルセンです。
ハンスは両親に可愛がられて育ちましたが、早くに父が亡くなり、母はせんたく女として働きにいきました。ハンスはひとり家にいて、父の作ってくれた人形劇の舞台で遊び、人形の服を縫ったり劇の本を読んだりしてすごしました。
第1章は、ハンスが14歳でコペンハーゲンへ旅立つところまでが、えがかれています。
インドの絵本 『10にんのきこり』 A.ラマチャンドラン/作
田島伸二/訳 講談社(2007年)1500円+税
最近ご紹介した韓国の絵本『十長生をたずねて』が、私に、知らなかった大切なこと、目を開かなければならないことへと導いてくれました。
『十長生をたずねて』は、APPA(アジア・太平洋出版連合・加盟国16ヵノ国)が毎年実施している出版賞の、児童書部門銀賞を受賞しています。
村上春樹さんが、尖閣諸島を巡る中日間の紛争に、「魂が行き来する道を塞いではならない」と、朝日新聞へ寄稿されたメッセージが大きな反響を呼んでいますが、この優しく美しい本も、出版をとおしての文化の交流の大切さを教えてくれました。家族を思う気持ちは、どこの国でも同じです。読後の余韻の中で、少女とその家族の幸せを 祈らずにはいられませんでした。
この本を読んだことと、村上春樹さんのメッセージに深い共感を覚え、アジア・太平洋の国々の作家による児童書を読んでみようと思いました。
 今日ご紹介する『10にんのきこり』は、インドの絵本です。
今日ご紹介する『10にんのきこり』は、インドの絵本です。
10にんのきこりが、森に木を切りにいきました。森には10本の木がありました。1番めのきこりが1本の木を切りました。残りは9本です。
2番めのきこりが2本目の木を切りました。残りは8本です。
「まだ ある。まだ ある。」と切っていき、最後の木が切りたおされるとトラがあらわれ、10にんのきこりをみんな、たべてしまいました。
のこりは 0 です。
それから トラは グーグーとねむりました
 インドは、0を発見した国として知られています。インドでは子どものころ、九九のように19+19といった2けたの掛け算まで暗記するということです。0を発見した国の国民は、数学が得意なことで有名なのだそうです。
インドは、0を発見した国として知られています。インドでは子どものころ、九九のように19+19といった2けたの掛け算まで暗記するということです。0を発見した国の国民は、数学が得意なことで有名なのだそうです。
 作者は1935年生まれ。学生時代から、伝統的なインドの絵画や壁画を学びました。豊かな自然や文化や伝統がどんどん失くなったり、壊されたりしていることを心配し、子どもの絵本の中に残していきたいと思って、絵本を描き始めたそうです。
作者は1935年生まれ。学生時代から、伝統的なインドの絵画や壁画を学びました。豊かな自然や文化や伝統がどんどん失くなったり、壊されたりしていることを心配し、子どもの絵本の中に残していきたいと思って、絵本を描き始めたそうです。
この本の、“森の木々がなくなると、トラが現れる”というお話にも、自然の豊かさを大事にする想像力を育んでほしいという願いが込められています。
田島伸二/訳 講談社(2007年)1500円+税
最近ご紹介した韓国の絵本『十長生をたずねて』が、私に、知らなかった大切なこと、目を開かなければならないことへと導いてくれました。
『十長生をたずねて』は、APPA(アジア・太平洋出版連合・加盟国16ヵノ国)が毎年実施している出版賞の、児童書部門銀賞を受賞しています。
村上春樹さんが、尖閣諸島を巡る中日間の紛争に、「魂が行き来する道を塞いではならない」と、朝日新聞へ寄稿されたメッセージが大きな反響を呼んでいますが、この優しく美しい本も、出版をとおしての文化の交流の大切さを教えてくれました。家族を思う気持ちは、どこの国でも同じです。読後の余韻の中で、少女とその家族の幸せを 祈らずにはいられませんでした。
この本を読んだことと、村上春樹さんのメッセージに深い共感を覚え、アジア・太平洋の国々の作家による児童書を読んでみようと思いました。
10にんのきこりが、森に木を切りにいきました。森には10本の木がありました。1番めのきこりが1本の木を切りました。残りは9本です。
2番めのきこりが2本目の木を切りました。残りは8本です。
「まだ ある。まだ ある。」と切っていき、最後の木が切りたおされるとトラがあらわれ、10にんのきこりをみんな、たべてしまいました。
のこりは 0 です。
それから トラは グーグーとねむりました
この本の、“森の木々がなくなると、トラが現れる”というお話にも、自然の豊かさを大事にする想像力を育んでほしいという願いが込められています。
イーラ/写真 マーガレット・ワイズ・ブラウン/文
寺村摩耶子/訳 文遊社(2014年4月)
イーラの本名はカミーラ・コフラー。1911年オーストリアのウイーン生まれ。彫刻を学んだ後、動物専門の写真家になります。1955年インドで没。
マーガレット・ワイズ・ブラウンは1910年アメリカ・ニューヨーク州生まれ。子どもの本の作家として100冊以上の絵本を発表。1952年没。
2人は写真を使った物語絵本という新しいジャンルを確立しました。この絵本はその記念すべき第1作で、1944年、戦下に生まれました。
どうぶつたちは みました!
みんな みんな さわいでいます。
いったい何を見たのでしょうか!?
ページをめくっていくと、左のページはあざやかなトマト色の紙、右のページには動物たちのモノクロ写真で構成されていて、とても斬新で古さをまったく感じさせません。
動物たちのアップの写真は、シカの毛並や、雄鶏のトサカ、カバの口の中など、細かいところまではっきり捉えられていて、生き生きとしてとても印象的です。
幼い頃の、こんな絵本との出会いは、きっと豊かな感性をはぐくんでくれることでしょう。
『蛙となれよ冷やし瓜』 一茶の人生と俳句
マシュー・ゴラブ/文 カズコ・G・ストーン/絵
脇 明子/訳 岩波書店(2014年8月)1600円
 新刊です。ユニークで、挿し絵も素晴らしく、とても丁寧に作られていて、この絵本に出会えてとても嬉しく思いました。
新刊です。ユニークで、挿し絵も素晴らしく、とても丁寧に作られていて、この絵本に出会えてとても嬉しく思いました。
この絵本が生まれた経緯が、訳者によるあとがきに書かれていますので、一部をピックアップしてみます。
 この本は、アメリカで出版された絵本を翻訳したものです。
この本は、アメリカで出版された絵本を翻訳したものです。
アメリカの小学校では、ぴったりした言葉を探しながら文を書く練習の手始めに、ハイクを作る勉強をすることが多いのです。
でも、アメリカの自然は日本とずいぶんちがいますから、日本の俳句が四季それぞれの美しさや、虫や草花などのいきいきとした姿を大切にしてきたということは、あまり理解されていないそうです。それを残念に思ったのが、日本からアメリカに渡って絵本作家になったカズコ・G・ストーンさんで、ストーンさんの思いに共鳴して、いっしょにこの絵本の構想を練り、文章を担当したのが、大学で日本文化を学び、しばらく日本で暮らしたこともある、マシュー・ゴラブさんでした。
 ゴラブさんのやさしい英語で、一茶の俳句が小さな文字で入っています。訳者の脇明子さんは、ゴラブさんが一茶の俳句の魅力をどんなふうにアメリカの子どもたちに手渡そうとしているのかを感じ取る助けにもなるかと、思い切って訳されたそうです。
ゴラブさんのやさしい英語で、一茶の俳句が小さな文字で入っています。訳者の脇明子さんは、ゴラブさんが一茶の俳句の魅力をどんなふうにアメリカの子どもたちに手渡そうとしているのかを感じ取る助けにもなるかと、思い切って訳されたそうです。
また、訳者は、何よりも味わっていただきたいのは、ストーンさんが、1枚1枚に愛情をこめて描いた、日本の風景や生きものたちの、こまやかな美しさである。日本に住んでいてさえ見失いがちなこの美しさを、ぜひとも多くのみなさんに再発見していただければ、と書かれています。
 先日ご紹介した『ランドセル俳人の五・七・五』の著者、小林凛君は、小林一茶が好きで俳号を小林とされたということです。本の感動の余韻が残っているところに、この本に出会い、あらためて俳句って素晴らしいなあ、日本人ていいなあ、と思いました。俳句を詠むことは、限りなく広く深い世界とつながることなのですね。
先日ご紹介した『ランドセル俳人の五・七・五』の著者、小林凛君は、小林一茶が好きで俳号を小林とされたということです。本の感動の余韻が残っているところに、この本に出会い、あらためて俳句って素晴らしいなあ、日本人ていいなあ、と思いました。俳句を詠むことは、限りなく広く深い世界とつながることなのですね。
題名の『蛙となれよ冷やし瓜』は、「人来たら蛙となれよ冷やし瓜」から取ってあります。
(あるとき、瓜が冷やしてあるのを通りすがりに見た一茶は、じきにだれかに食べられてしまうのだろうな、と残念に思いました。ぴょんと跳んで逃げることができたら、食べられずにすむのに!)
この絵本を、どのトピックに載せようかと迷いました。
俳句絵本ですが、アメリカの絵本の翻訳ですし、やはり外国の絵本のコーナーに掲載することにしました。
マシュー・ゴラブ/文 カズコ・G・ストーン/絵
脇 明子/訳 岩波書店(2014年8月)1600円
この絵本が生まれた経緯が、訳者によるあとがきに書かれていますので、一部をピックアップしてみます。
アメリカの小学校では、ぴったりした言葉を探しながら文を書く練習の手始めに、ハイクを作る勉強をすることが多いのです。
でも、アメリカの自然は日本とずいぶんちがいますから、日本の俳句が四季それぞれの美しさや、虫や草花などのいきいきとした姿を大切にしてきたということは、あまり理解されていないそうです。それを残念に思ったのが、日本からアメリカに渡って絵本作家になったカズコ・G・ストーンさんで、ストーンさんの思いに共鳴して、いっしょにこの絵本の構想を練り、文章を担当したのが、大学で日本文化を学び、しばらく日本で暮らしたこともある、マシュー・ゴラブさんでした。
また、訳者は、何よりも味わっていただきたいのは、ストーンさんが、1枚1枚に愛情をこめて描いた、日本の風景や生きものたちの、こまやかな美しさである。日本に住んでいてさえ見失いがちなこの美しさを、ぜひとも多くのみなさんに再発見していただければ、と書かれています。
題名の『蛙となれよ冷やし瓜』は、「人来たら蛙となれよ冷やし瓜」から取ってあります。
(あるとき、瓜が冷やしてあるのを通りすがりに見た一茶は、じきにだれかに食べられてしまうのだろうな、と残念に思いました。ぴょんと跳んで逃げることができたら、食べられずにすむのに!)
この絵本を、どのトピックに載せようかと迷いました。
俳句絵本ですが、アメリカの絵本の翻訳ですし、やはり外国の絵本のコーナーに掲載することにしました。
ドリーン・ラパポート/文 マット・タヴァレス/絵
もりうち すみこ/訳 国土社(2014年8月)1500円
見る・聞く・話す・読む・書く・学ぶ夢に挑戦した、ヘレン・ケラーの生涯を、ヘレンの残した希望にみちたことばでつづる絵本です。
「わたしたちは、目や耳で考えるわけではありません。
考える力は、見える聞こえるとは別の能力なのです」
「この世界に ことばがあることを知って、
わたしのたましいは めざめました。
光と 希望と よろこびをえて、闇から ときはなたれたのです」
<真に見習うべきことは、ヘレンが自分のもっている能力を最大限に生かしたこと。そし何より、最もすぐれた能力である知性をつかって世の中を理解し、よりよい世界へと変えていこうとしたことなのです>
目が見えず、耳が聞こえなくても、太陽のぬくもりや風を感じ、雨をからだに受けたり、触れる、嗅ぐ、味わうなど、さまざまな能力が人間にはそなわっているのです。
著者、画家により心血注いで作られ、そして訳者、編集の方、印刷、製本をされた方たち、多くの方ったちの力が集まってこの素晴らしい絵本が生まれた。世の中悪い出来事もたくさん起こっていますが、一方で人間はこんな素晴らしいことも出来るのですね。この美しく、力強いメッセージが込められた絵本を、ぜひ多くの方に知っていただきたいと思いました。
バグラム・イバトーリーン/絵
もりやま みやこ/訳 ポプラ社(2008年)1400円
フランシスは、眠いのをいっしょうけんめいがまんして、真夜中にベッドをぬけだし、窓から通りを見下ろしました。
「あのひとたち、みちばたでねているのよ。ゆきがふっているのに」
つぎのひのあさ、フランシスはおかあさんにいいました。」
でもおかあさんは、教会でのクリスマスのお芝居のことであたまがいっぱいでした。
フランシスは、イエス様がお生まれになったことを知らせる天使の役をすることになっているのです。
フランシスとおかあさんが教会にでかけるとき、オルガンひきとさるは、まだ通りにいました。フランシスは、さるのカップにコインを一まいいれて、「クリスマスのおしばいをみにきてね。」と言います。
オルガンひきはほほえみましたが、その目はかなしそうでした。
オルガンひきのことが頭をはなれないフランシスは、せりふがでてこなくて、かたまってしまいます。
そのとき、うしろのとびらがひらいて、オルガンひきがそっとはいってきました。
フランシスはにっこりして、大きな声でよびかけました。
「うれしい おしらせです。よろこびをおとどけします!」
少女の純真な心にうたれました。最後は、劇が終わったあとの教会でのパーティーの場面です。その中には、オルガンひきの晴れやかな笑顔も見られます。心の琴線にふれてくる絵本でした。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
元気な本棚 ほっこり 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
元気な本棚 ほっこりのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6462人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19244人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208300人