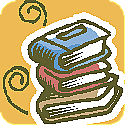〔目次〕
1 C・V・オールズバーグの絵本
『名前のない人』 村上春樹・訳 河出書房新社
『ゆめのおはなし』 さいごうようこ・訳 徳間書店
2 『青い花のじゅうたん』 トミー・デ・パオラ/再話・絵 評論社
3 『雪の写真家 ベントレー』ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン/作
メアリー・アゼアリアン/絵 千葉茂樹/訳 BL出版
4 『にぐるまひいて』 ドナルド・ホール/文 バーバラ・クーニー/絵
もきかずこ/訳 ほるぷ出版
5 『カーリンヒェンのおうちはどこ』 アンネゲルト・フックスフーバー/ 池田香代子/訳 一声社
6 『手の中のすずめ』 アンネゲルト・フックスフーバー/作・絵
平野卿子/訳 ほるぷ出版
7 <フックスフーバーの絵本二冊>
『友だちのほしかった大おとこの話+友だちのほしかったネズミの話』
高橋洋子・訳 偕成社
『わすれられた庭』 酒寄 進一・訳 福武書店
8 『おとうさんの庭』 ポール・フライシュマン/文 バグラム・イバトゥ リーン/絵 藤本 朝巳/訳 岩波書店
9〜11 『ジョニー・アップルシード』ーりんごの木を植えた男 リーブ・リン ドバーグ/詩
キャシー・ジェイコブセン/絵 稲本 正/訳 アーバン・コミュニ ケーションズ
12 『むぎばたけ』 アリスン・アトリー/作 矢川澄子/訳 片山健/絵 福 音館
13 『急行「北極号』 C・V・オールズバーグ 絵と文
村上春樹 訳 あすなろ書房(1500円)
『サンタクロースっているんでしょうか?』 偕成社(800円)
14 『うれしいな おかあさんといっしょ』 熊田千佳慕・文と絵 小学館保育絵本
(日本の絵本なのですが、いっしょに紹介します)
『だっこのえほん』 ヒド・ファン・ヘネヒテン/作・絵 のざか えつこ/訳 フレーベル館
『ぎゅっ』 ジェズ・オールバラ/作・絵 徳間書店
16 『紙しばい屋さん』 アレン・セイ 作/絵 ほるぷ出版
17 『おじいさんの旅』 アレン。セイ 作/絵 ほるぷ出版
18 『じてんしゃの へいたいさん』 アレン・セイ/作・絵 新世研
19〜20『さんねんねたろう』 ダイアン・スナイダー/作 アレン・セイ/絵 新世研
|
|
|
|
コメント(21)
クリス・ヴァン・オールズバーグは1949年、ミシガン州生まれ。現代アメリカ合衆国を代表する絵本作家で、アメリカの絵本の最高賞であるカルデコット賞を二度にわたって受賞しています。彼の作品は、以前、カムカムだよりで、クリスマスのお話「急行・北極号」をご紹介したことがあります(カルデコット賞受賞)が、今日は彼の他の作品について、簡単にですが、ご紹介できたらとおもいます。
彼の作品はどれも不思議で、ちょっとどきどきしながら、お話の世界に引き込まれていき、個性的な絵とともに、強い印象が心に残ります。
秋の初めのある日農夫がたおれている男を見つけ家につれて帰り、介抱しますが、その男は記憶をなくしてしまっていて、自分の名前も思い出せません。名前のない人と農夫の家族はうちとけて、楽しい日々を過ごしますが…。名前のない人とはいったいだれなのでしょう?
ある夜のこと、ウォルターがねむるベッドが未来へ飛んだ。でも未来はウォルターが考えていたようなハイテクのかっこいい未来じゃなかったんだ。街はゴミにうもれ、木は切られ、巨大なえんとつからは、くさいけむりがもくもくでている。わたりどりの休む湖はなくなり、エベレスト山のてっぺんにはネオンがかがやくホテルがたっていた。このまま、ベッドがもとの世界にもどらなかったらどうしよう……。(表紙裏の紹介文より)
“ブルーボンネット”―『青い花のじゅうたん』
“ブルーボンネット”と呼ばれる花があります。アメリカのテキサス州の州歌になっています。開拓者が、この植物の美しい青い花を見て、女性がかぶっていた青いボンネット(帽子の一種)に似ていることから、つけられた名前ではないかということです。ルピナスとか、バッファロー・クローバーとか、ウルフ・フラワーとか、いろいろな名前で呼ばれているそうです。
『ルピナスさん』(バーバラ・クーニー 作/絵 ほるぷ出版)という絵本があります。
アリスという少女がいました。アリスは、夜になるとおじいさんからよく、遠い国のお話をきかせてもらいました。お話が終わるとアリスはいいました。
「大きくなったら遠い国へいき、そしておばあさんになったら、海のそばの町に住むことにする。」おじいさんは「それだけでなく、もう一つしなくてはならないことがある。“世界を美しくする”ために、なにかしてもらいたいのだよ。」といいます。アリスは約束します。
おばあさんになったアリスは、ルピナスの種をまき、それは一面に美しい花を咲かせます。
絵本のあとがきにはこう書かれています。《クーニーは、ルピナスの花とかさねあわせて、独立心にあふれた一女性の人生を物語にしましたが、特別な人間の、特別な人生を語ったわけではありません。生きるということの意味を、ルピナスさんとよばれた一女性のすがたをかりて、わたくしたちに語りかけているのだとおもいます。》
この間、図書館で『青い花のじゅうたん』(トミー・デ・パオラ 再話/絵 評論社)という絵本を見つけ、“ブルーボンネット”がルピナスの花であることを知り、うれしくて借りて帰りました。
先住民コマンチ族の伝説に基づいたこの物語は、ブルーボンネットの由来について語られています。
『ルピナスさん』は大好きな絵本ですが、アメリカの人がルピナスの花を好む心情をわかるところまでは、いっていなかったのです。日本人からすれば、万葉のころから、四季折々の花に託する思いが歌に詠まれてきたように、日本の風土にあった花の方が、よりぴったり心情に合っているのでしょう。
この『青い花のじゅうたん』との出会いで、“アメリカンボンネット”(ルピナス)の美しさは、アメリカの風土の中で見て、そこで暮らしている人の、この花に託する思いを理解してこそ、生きいきと感じられるのだろうと、想像できるようになりました。
ささやかな発見ですが、キラッとひかる何かを見つけられたようで、とても嬉しかったのです。
“ブルーボンネット”と呼ばれる花があります。アメリカのテキサス州の州歌になっています。開拓者が、この植物の美しい青い花を見て、女性がかぶっていた青いボンネット(帽子の一種)に似ていることから、つけられた名前ではないかということです。ルピナスとか、バッファロー・クローバーとか、ウルフ・フラワーとか、いろいろな名前で呼ばれているそうです。
『ルピナスさん』(バーバラ・クーニー 作/絵 ほるぷ出版)という絵本があります。
アリスという少女がいました。アリスは、夜になるとおじいさんからよく、遠い国のお話をきかせてもらいました。お話が終わるとアリスはいいました。
「大きくなったら遠い国へいき、そしておばあさんになったら、海のそばの町に住むことにする。」おじいさんは「それだけでなく、もう一つしなくてはならないことがある。“世界を美しくする”ために、なにかしてもらいたいのだよ。」といいます。アリスは約束します。
おばあさんになったアリスは、ルピナスの種をまき、それは一面に美しい花を咲かせます。
絵本のあとがきにはこう書かれています。《クーニーは、ルピナスの花とかさねあわせて、独立心にあふれた一女性の人生を物語にしましたが、特別な人間の、特別な人生を語ったわけではありません。生きるということの意味を、ルピナスさんとよばれた一女性のすがたをかりて、わたくしたちに語りかけているのだとおもいます。》
この間、図書館で『青い花のじゅうたん』(トミー・デ・パオラ 再話/絵 評論社)という絵本を見つけ、“ブルーボンネット”がルピナスの花であることを知り、うれしくて借りて帰りました。
先住民コマンチ族の伝説に基づいたこの物語は、ブルーボンネットの由来について語られています。
『ルピナスさん』は大好きな絵本ですが、アメリカの人がルピナスの花を好む心情をわかるところまでは、いっていなかったのです。日本人からすれば、万葉のころから、四季折々の花に託する思いが歌に詠まれてきたように、日本の風土にあった花の方が、よりぴったり心情に合っているのでしょう。
この『青い花のじゅうたん』との出会いで、“アメリカンボンネット”(ルピナス)の美しさは、アメリカの風土の中で見て、そこで暮らしている人の、この花に託する思いを理解してこそ、生きいきと感じられるのだろうと、想像できるようになりました。
ささやかな発見ですが、キラッとひかる何かを見つけられたようで、とても嬉しかったのです。
外へ出ると、毎日落ち葉が舞い散り、日ごとに冬らしくなっていきます。雪が舞い散るのも間近ですね。きょうはそんな季節にふさわしい本を一冊ご紹介したいと思います。(2008年12月13日)
 「雪の写真家 ベントレー」 ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン/作 メアリー・アゼアリアン/絵 千葉茂樹/訳 BL出版
「雪の写真家 ベントレー」 ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン/作 メアリー・アゼアリアン/絵 千葉茂樹/訳 BL出版
 ウィルソン・ベントレーは、1865年、アメリカのバーモンド州の豪雪地帯にある村に生まれました。ウィルソン(ウイリー)はなによりも雪が好きでした。蝶やりんごの花もきれいだけれど、雪の美しさは、どんなものにもけっしてまけない。そうおもっていました。
ウィルソン・ベントレーは、1865年、アメリカのバーモンド州の豪雪地帯にある村に生まれました。ウィルソン(ウイリー)はなによりも雪が好きでした。蝶やりんごの花もきれいだけれど、雪の美しさは、どんなものにもけっしてまけない。そうおもっていました。
蝶だったらあみでつかまえて見せてあげられる。りんごの花だったらつんできて見せてあげられる。でも雪はそうはいきません。とけてしまうから。
かあさんからもらった顕微鏡で観察した雪の結晶の美しさをなんとかしてみんなにも知ってもらいたいと、スケッチをしてみました。でも雪はいつも、スケッチが出来上がるまえにとけてしまいます。
 16歳になったウイリーは顕微鏡つきのカメラがあることを知り、かあさんに話します。17歳のとき、とうさんとかあさんは、ためていたお金で、カメラを買うことにきめました。10頭の乳牛よりも値段の高いカメラでした。
16歳になったウイリーは顕微鏡つきのカメラがあることを知り、かあさんに話します。17歳のとき、とうさんとかあさんは、ためていたお金で、カメラを買うことにきめました。10頭の乳牛よりも値段の高いカメラでした。
何回も失敗し、工夫をかさね、ついにウイリーは雪の結晶を映す方法を見つけだします。しかし、雪の写真に興味をもつ人などだれもいません。「雪なんて、土とおなじで、めずらしくもない。写真なんかいらないよ」
 ウイリーは雪の研究を続けました。雪の結晶の写真を人にあげたり、安くわけてあげたりしました。誕生日のプレゼントには、特別の写真をおくりました。夜になると、幻燈会をひらくこともありました。
ウイリーは雪の研究を続けました。雪の結晶の写真を人にあげたり、安くわけてあげたりしました。誕生日のプレゼントには、特別の写真をおくりました。夜になると、幻燈会をひらくこともありました。
やがてウィリーは、雪について書いた文章や写真を雑誌で発表するようになりました。雪について講演をすることもありました。小さな村で暮らすひとりの農夫が、世界的な「雪の専門家」としてみとめられたのです。それでも、ウイリーがお金持ちになることはありませんでした。少しでもお金があれば、ぜんぶ写真に使ってしまうのですから。ウイリーにとって、雪こそが宝物だったのです。
1926年までに、ウイリーは写真のために15000ドルのお金を使った。いっぽう、写真やスライドを売って得たお金は、4000ドルにすぎなかったといいます。
<これは家族の愛情に見守られ、ひたむきに雪を追いつづけたベントレーの生涯を、美しいぬくもりのある版画とともにつづった心あたたまる伝記絵本です>―千葉茂樹
 さいごのページに、ベントレーがカメラにむかっている写真とともに、雪の結晶の写真が3つ掲載されています。写真を見てみたい場合は、写真集が出ていると思いますが、また調べてみます。
さいごのページに、ベントレーがカメラにむかっている写真とともに、雪の結晶の写真が3つ掲載されています。写真を見てみたい場合は、写真集が出ていると思いますが、また調べてみます。
蝶だったらあみでつかまえて見せてあげられる。りんごの花だったらつんできて見せてあげられる。でも雪はそうはいきません。とけてしまうから。
かあさんからもらった顕微鏡で観察した雪の結晶の美しさをなんとかしてみんなにも知ってもらいたいと、スケッチをしてみました。でも雪はいつも、スケッチが出来上がるまえにとけてしまいます。
何回も失敗し、工夫をかさね、ついにウイリーは雪の結晶を映す方法を見つけだします。しかし、雪の写真に興味をもつ人などだれもいません。「雪なんて、土とおなじで、めずらしくもない。写真なんかいらないよ」
やがてウィリーは、雪について書いた文章や写真を雑誌で発表するようになりました。雪について講演をすることもありました。小さな村で暮らすひとりの農夫が、世界的な「雪の専門家」としてみとめられたのです。それでも、ウイリーがお金持ちになることはありませんでした。少しでもお金があれば、ぜんぶ写真に使ってしまうのですから。ウイリーにとって、雪こそが宝物だったのです。
1926年までに、ウイリーは写真のために15000ドルのお金を使った。いっぽう、写真やスライドを売って得たお金は、4000ドルにすぎなかったといいます。
<これは家族の愛情に見守られ、ひたむきに雪を追いつづけたベントレーの生涯を、美しいぬくもりのある版画とともにつづった心あたたまる伝記絵本です>―千葉茂樹
ドナルド・ホール/ぶん バーバラ・クーニー/え もきかずこ/やく
ドナルド・ホールは、自分の作品を朗読して国中を歩く詩人として知られています。「にぐるまひいて」は、人から人へと語り継がれてきたお話だそうです。バーバラ・クーニーが美しい絵を描いて、1979年に出版され、1980年度のコルデコット賞を受賞しました。日本語に翻訳、出版されたのは、翌年の1980年で、版を重ねて現在に至っています。
それから うちじゅう みんなで
この いちねんかんに みんなが つくり そだてたものを
なにもかも にぐるまに つみこんだ。」
にぐるまには、ひつじの毛をつめた袋とひつじの毛で編んだショール、手袋、みんなで作ったろうそく、しらかばのほうき、いろいろな野菜、楓ざとう、がちょうのはねなどがつぎつぎと積まれます。
とうさんは、荷車を牛に引かせて、10日がかりで市場につきます。丘をこえ、谷をぬけ、小川をたどり、農場や村をいくつもすぎて。
色々なものを売り、最後に荷車と牛も売り、今度は買い物をして帰ります。農場や村をいくつもすぎ、小川をたどり、谷をぬけ、丘をこえて、むすこと、むすめと、かあさんがまちわびている家に帰ります。
こうしてまた一年がすぎていきます。
自然の移りかわりに添って生きる家族の暮らしが淡々と描かれていますが、心に沁みてくるものがあります。心豊かな生き方とは?忘れてしまいがちな大切なことを、この本を開くことで思い出せる時間を持てるのです。
図書館でクーニーの作品を検索していて、児童書の挿絵を書いている作品で、まだ知らなかったものを二冊見つけて借りて帰りました。
その一冊は、「若草物語」です。学習研究社から出された、学研世界名作シリーズの中の一冊です。1974年と古いもので、書庫に入っていました。なにしろクーニーの挿絵による若草物語ですから、うきうきしながらページをめくって見ています。子どものころに読んだ若草物語は、誰の挿絵だったかしら?今になって覚えておけばよかったなあと思います。マイミクの皆さまは、どんな思い出をお持ちですか?
もう一冊のも素適な本でした。またぜひ皆さまにご紹介できればと思っています
(もう一冊は『ちいさな曲芸師 バーナビー』です。《外国の児童書》のコーナーに掲載しましたので、よかったら見てください。2009年10月10日)
戦争で家を焼かれたカーリンヒェンは、ひとりぼっちで逃げ、いろんな人に助けを求めます。
カーリンヒェンは、静かでおだやかな村にたどりつき、助けを求めますが、警察を呼ばれてしまいます。必死で逃げて、森のむこうの石くい族のくににたどりつきますが、ここにもいられません。
しっぽ鳥のくに、霧ガラスのくに、どこへいっても居場所はありません。
お金大好き人のくににやってきますが、食べ物をくれる人はだれもいませんでした。
カーリンヒェンは、どこにいけばいいのかわかりません。おまけに雨がふってきました。
「おいで、パンをわけてあげるよ。
おまえははらぺこで、つかれているんだろう?
木の上は、雨にぬれていないし、あたたかいよ」
「あなたは だれ?」
「おれは おばかさんだよ」
「やさしい人を あばかさん というのなら、
わたしも、あなたのような おばかさんになりたいわ」
世界には、“難民”とよばれる人々が、2000万人、あるいは2300万人いるといわれています。その半分くらいは、カーリンヒェンのような子どもです。理由はさまざまです。ある人びとは地震や大洪水のために。またある人びとは、作物が取れなかったり、食べ物が底をついたために。戦争にまきこまれそうになって逃げてきた人びとも。
この絵本は、もしも、カーリンヒェンのような子が、あなたのいるところへ逃げてきたら、どうしますか?と問いかけています。
純真な子どもたちなら、この本の中で、カーリンヒェンといっしょになっていろんな思いをし、最後にあたたかく受け入れてくれる人に出会え、居場所をみつけるまでの旅をする過程で、きっと自分のなかに答を見出してくれるのではないかと思うのです。
訳者の池田香代子さんは、大きく話題になった「世界がもし100人の村だったら」という作品も書かれています。
前回紹介した『カーリンヒェンのおうちはどこ』は、私にとって、フックスフーバーさんの本との初めての出会いでしたが、これは次に読んだ本です。今回と次回は、フックスフーバーさんの本をご紹介したいと思います。
1940年、東ドイツのマクデブルグに生まれ、工芸美術学校で学んだのち、1968年からイラストレーターおよび絵本作家として活動をはじめる。作品は、さまざまな国で翻訳され、ドイツ国内をはじめ外国の賞をいくども受けている。彼女の3人のお子さんたちは彼女の絵本がたいそうお気に入りで、学校なんかよりずっと好きだったとか。
『おかあさんといっしょにお使いにきて、まいごになってしまったティム。ティムには、ただのひとごみがしだいにまほうの森のようにおもえてきます。おまけに、この森には、おそろしいけものまでいるではありませんか。そして、どこかうえのほうからは、ひそひそささやくきみのわるい声。ティムは、すっかりおびえてしまいます。
おかあさん、どこにいるの?
ところが、そのときティムは、ちいさなすずめのあかちゃんをみつけたのです。……。
ひとりぼっちになったとたん、見なれたなんでもないものが、とつぜんなにかおそろしいものに見えてきてしまう……こんな経験は、子どもならだれでもあるのではないでしょうか。フックスフーバー独特の雰囲気のある絵は、幼い子どもの心象風景をあざやかに描きだしています。
しかし、この作品をさらに深みのあるものにしているのは、なんといっても、ティムが、自分よりずっとちいさな生きものとであったことで、まほうの森からぬけだしていくところだといえるでしょう。「おおきい自分」にあたえられた使命感、すなわち、相手をはげまし、かばう立場に身をおいたことによって、ティムのまほうの森は、消えていきます。そして、このささやかな体験は、ティムにひとつの自信をあたえるのです。(後略)』
フックスフーバーさんの絵は美しいだけでなく、力強さがあって、そこがとてもいいなあと思います。バーバラ・クーニーの絵も大好きですが、彼女の絵もまた別の良さがあって、とても大好きになりました。
手にとってみて、まずおもしろい形態(?)の本であることに気がつきます。
《出会いの絵本》という副題がついているのですが、普通は裏表紙になっているところも表紙になっていて、両側から読んでいくようになっています。
二つの表紙の一方には「友だちのほしかった大おとこの話」とあり、もう一方の表紙には「友だちのほしかったネズミの話」とあります。
森にすむ大おとこは、体が大きいにもかかわらず、たいへんこわがりでした。でもそのことを知らない動物達からこわがられ、どこへいってもにげられてしまいます。
西の森に、ゆうかんなネズミがすんでいました。でも、こわいもの知らずのネズミなんて、ネズミらしくないんだものと、だれも友だちになりたがりませんでした。ネズミは友だちをさがしに旅にでます。
大おとことネズミは本のまんなかで出会います。
意表を突くアイディアがとても新鮮でした。この本は、ドイツ児童文学賞を受賞しています。
カティという少女が、パン屋さんにおつかいに行きました。つぎつぎにお客がきて、カティをおしのけてパンを買っていきます。
やっと買えて帰り道、いつも通る“へい”のところにやってきました。カティはそこを通るたび、へいのむこうがどうなっているか見てみたくて、入り口があればなあと思っていたのです。
するとどうでしょう! 目のまえに、青いドアがあらわれました。
そっと中をのぞいてみると、大きな庭があり、白いじゃり道が森のおくへとつづいています。
入り口には木のみきのようなふくをきた小人がたっています。
「ようこそ」
「ここはあなたの庭?」
「ここは、わすれられた庭といってね、みんながわすれたり、なくしたりしたものがあつまっているところなんだ―」
このお話が、絵本でなく物語だったら、じゅうぶん一冊の本が書けると思うほど、スケールの大きいファンタジーでした。
(2009年6月19日)
 『おとうさんの庭』 ポール・フライシュマン/文 バグラム・イバトゥリーン/絵 藤本朝巳/訳 岩波書店(2006年)
『おとうさんの庭』 ポール・フライシュマン/文 バグラム・イバトゥリーン/絵 藤本朝巳/訳 岩波書店(2006年)
アメリカの開拓時代を舞台にした絵本です。
 むかし、あるところに、ひとりの農夫がすんでいました。
むかし、あるところに、ひとりの農夫がすんでいました。
農夫はあかあかともえるまきストーブのように、こころのあたたかいひとでした。どうぶつたちをこよなくかわいがり、ひよこや子ぶたや子牛が大きくそだっていくのを見るのが、なによりのたのしみでした。
農夫には三人のむすこがいました。三人はたいそうはたらきもので、一日じゅう、うたいながらはたらきました。農夫はどうぶつたちのせわをしながら、うたをうたい、はなしかけ、どうぶつたちがそだっていくのをみては、にっこりしたものです。
ある春のこと、種をまいても、ちっとも雨がふりません。どうぶつたちのえさも、親子の食べる物もなくなり、にわとりを売り、ぶたを売り、牛を売り、しまいには、農場も売ることになりました。
農夫の親子は、いけがきにかこまれた、ちっぽけな小屋にうつりすみました。
やがて、まちにまった雨がふりだしました。ふたたび緑がもどってきましたが、動物達を買いもどすお金もありません。
 ある日のこと、農夫はいけがきのていれをしていて、ふといけがきが牛のかたちに見えました。おんどりやひつじのむれに見えるものもあります。農夫は動物のかたちにいけがきをかりこんでいきました。農夫の口から、ふたたび、歌があふれてきました。
ある日のこと、農夫はいけがきのていれをしていて、ふといけがきが牛のかたちに見えました。おんどりやひつじのむれに見えるものもあります。農夫は動物のかたちにいけがきをかりこんでいきました。農夫の口から、ふたたび、歌があふれてきました。
むすこたちがだんだん大きくなってきました。
農夫は長男にはなしかけました。
「世の中にでていくときがやってきたようだね」
「とうさん、ぼくはどんな仕事をしたらいいでしょうか」
農夫ははさみをとりだすと、いけがきを低くかりこみ、「毎日しっかり見て、よく観察することだ。いけがきは、きっとおまえに答えをだしてくれるよ。もちろん、おまえがじぶんで、かりこみをしなくてはならないがね」
何週間も、長男はいけがきを見つめてかんがえました。そして見えたものは―。
次男も、三男も、同じようにして、なりたいものを見つけ、でかけていきました。
ひとりぼっちになった農夫は、またいけがきを動物たちのすがたにかりこんでいきました。
さて、ある夏のこと、農夫のもとに、むすこたちが帰ってきました。息子たちはいけがきを見て、お父さんのこころのねがいを感じ、むねがいっぱいになりました。
 翌朝農夫は外にでてみて、びっくりしました。そこには、三人のむすこたちからのおくりものが―。長男からはほんもののにわとり、次男からはほんもののぶた、そして三男からはほんものの牛が。
翌朝農夫は外にでてみて、びっくりしました。そこには、三人のむすこたちからのおくりものが―。長男からはほんもののにわとり、次男からはほんもののぶた、そして三男からはほんものの牛が。
この物語には、アメリカ開拓時代の人々のきびしい生活のようすが描かれています。
あとがきにはこう書かれています。
「しかし、であるからこそ、つらい生活のただ中で、<夢を持つ>ということがどんなに大切なことなのか、また夢を実現できたら、その感謝のしるしとして人は何をなすべきかなど、この物語は素朴に教えてくれます。」
アメリカの開拓時代を舞台にした絵本です。
農夫はあかあかともえるまきストーブのように、こころのあたたかいひとでした。どうぶつたちをこよなくかわいがり、ひよこや子ぶたや子牛が大きくそだっていくのを見るのが、なによりのたのしみでした。
農夫には三人のむすこがいました。三人はたいそうはたらきもので、一日じゅう、うたいながらはたらきました。農夫はどうぶつたちのせわをしながら、うたをうたい、はなしかけ、どうぶつたちがそだっていくのをみては、にっこりしたものです。
ある春のこと、種をまいても、ちっとも雨がふりません。どうぶつたちのえさも、親子の食べる物もなくなり、にわとりを売り、ぶたを売り、牛を売り、しまいには、農場も売ることになりました。
農夫の親子は、いけがきにかこまれた、ちっぽけな小屋にうつりすみました。
やがて、まちにまった雨がふりだしました。ふたたび緑がもどってきましたが、動物達を買いもどすお金もありません。
むすこたちがだんだん大きくなってきました。
農夫は長男にはなしかけました。
「世の中にでていくときがやってきたようだね」
「とうさん、ぼくはどんな仕事をしたらいいでしょうか」
農夫ははさみをとりだすと、いけがきを低くかりこみ、「毎日しっかり見て、よく観察することだ。いけがきは、きっとおまえに答えをだしてくれるよ。もちろん、おまえがじぶんで、かりこみをしなくてはならないがね」
何週間も、長男はいけがきを見つめてかんがえました。そして見えたものは―。
次男も、三男も、同じようにして、なりたいものを見つけ、でかけていきました。
ひとりぼっちになった農夫は、またいけがきを動物たちのすがたにかりこんでいきました。
さて、ある夏のこと、農夫のもとに、むすこたちが帰ってきました。息子たちはいけがきを見て、お父さんのこころのねがいを感じ、むねがいっぱいになりました。
この物語には、アメリカ開拓時代の人々のきびしい生活のようすが描かれています。
あとがきにはこう書かれています。
「しかし、であるからこそ、つらい生活のただ中で、<夢を持つ>ということがどんなに大切なことなのか、また夢を実現できたら、その感謝のしるしとして人は何をなすべきかなど、この物語は素朴に教えてくれます。」
アメリカの開拓時代のことを描いたお話は、大人の本でも、児童書でもきっと数えきれないくらいあるのでしょう。前向きな生き方、夢を感じさせられるものが多く、生きる力をもらえるような気がします。
200年ほど前のアメリカは、まだ町は東海岸にあるだけでしたが、自分自身の土地を求めて、勇敢な人々は西へ、西へと旅をしていきました。そんな開拓地にりんごの木を植えた男は、ジョン・チャップマン。人呼んで「ジョニー・アップルシード」といいました。実在の人物です。200年もの間、人から人へと語り継がれてきたお話です。
ジョン・チャップマンは1774年、マサチューセッツ州レオミンスターで生まれ、父はアメリカの独立戦争で戦いました。子ども時代については、たぶんコネティカット州・バレーで育てられたのだろうということ以外、ほとんど知られていません。
1797年、彼が23歳のころ、ペンシルベニア州から、オハイオ州、インディアナ州北部へと、有名な「りんごの木を植える旅」に出発しました。
彼は、これらの州を旅するだけでなく、これらの州に自分自身の土地を持っていました。辺境の地に住む人々にりんごの木を分けるため、その土地に苗床や養樹園を作っていたのです。
また次回に。
彼が最初にアメリカにリンゴ園を作ったわけではありませんが、りんごを辺境の地までもたらしたという点で、とても重要な役割を果たしたということは、まぎれもない事実です。
彼はまた、キリスト教の宣教師でもあり、旅の先々で信仰を説き、布教に努めました。さらに彼は、スウェーデンの哲学者、エマニュエル・スウェーデンボルグの支持者で、「自然との共生」のうちに質素に暮らさなければならないと考えていたようです。
彼は、身なりや財産にはまったくといっていいほど関心を示さなかったといいます。そして、人類、すべての生物に対して、大きな愛をもって接しました。
余裕のない人々には無償でりんごの木を贈り、熊や狼、ガラガラヘビからスズメバチにいたるまでの野生の動物たちに対する親切な心は、はっきりと記録に残っています。
だからこそ彼は、インディアンたちにも尊敬され、彼らの間を自由に行き来できたのでした。
とりわけジョン・チヤップマンは子供が好きなことで知られています。訪問した家の子供たちに自分の冒険談を話して、旅先での多くの時間を過ごしました。
彼は1845年、インディアナ州フォートウェーンという町(
(2009年6月26日)
 この絵本を読む日本の読者に、「詩」を書いたリーブ・リンドバーグと、画家のキャシー・ジェイコブセンのメッセージが寄せられています。
この絵本を読む日本の読者に、「詩」を書いたリーブ・リンドバーグと、画家のキャシー・ジェイコブセンのメッセージが寄せられています。
この絵本で初めて知ったのですが、リーブ・リンドバーグは、太平洋無着陸横断飛行で有名なチャールズ・リンドバーグの娘さんだそうです。
その内容を少しご紹介します。
 真の自然保護論者は、自然のバランスを守るために、地球から受ける恵みのいくらかを、行動を通して地球にかえさなければいけないと考えます。ジョン・チャップマンもその一人でした。彼は、ただあちこち種を蒔いて歩くだけのロマンティックな伝説上の旅行者ではなく、惜しみなく分かち与える教師であり、農業技術者でもあり、開拓者たちに進むべき道を示し、未来のためにりんごを植え、よく育つよう世話をした人なのです
真の自然保護論者は、自然のバランスを守るために、地球から受ける恵みのいくらかを、行動を通して地球にかえさなければいけないと考えます。ジョン・チャップマンもその一人でした。彼は、ただあちこち種を蒔いて歩くだけのロマンティックな伝説上の旅行者ではなく、惜しみなく分かち与える教師であり、農業技術者でもあり、開拓者たちに進むべき道を示し、未来のためにりんごを植え、よく育つよう世話をした人なのです
 キャシー・ジェイコブセンの曾おじいさんは、家のとなりにりんごの木々を植え、その中の一本は、105年後の今(この絵本の出版当時)でも実をつけているということです。
キャシー・ジェイコブセンの曾おじいさんは、家のとなりにりんごの木々を植え、その中の一本は、105年後の今(この絵本の出版当時)でも実をつけているということです。
“もっともっと多くの人々が、開発行為に対して深い責任を持ち、地球の環境に関心を払い始めれば、ジョニー・アップルシードはとても喜ぶだろうと思います”と述べられています。
 訳者の稲本正さんは、1945年、富山県生まれの工芸家です。
訳者の稲本正さんは、1945年、富山県生まれの工芸家です。
「人間と自然の共生」をめざし、飛騨の高山で工芸村「オーク・ヴィレッジ」での活動をはじめ、さまざまな活動を展開。著書も「緑の生活」「森からの発想」「森に育てられて」など多数。
「木を植えた男」という素適なお話があります。アニメ映画や絵本で有名です。ただ、主人公は実在の人物ではなく、物語にあるように、ドングリをいきなり荒地に植えても、それがそのまま大森林になるということはありえない、まず苗床を作って、そこでできた苗を山に移植しなくてはならないそうです。
この実在の人物をどう浮かび上がらせるか、それは非常に困難な作業だったそうです。稲本さんは、アメリカの子供に与えたのと同じ夢を日本の子供たちにも与えたいという思いをもってこの絵本を訳されました。
 最後に訳者はこう書かれています。
最後に訳者はこう書かれています。
“この物語が気に入った人も、そうでない人も、ぜひとも何か一本の木を植えてほしい。そうすればその体験が、言葉の壁や習慣の違い、そして時代と距離を越えて、謎に満ちた「ジョニー・アップルシード」を知る、一番の手掛かりになるだろうから。”
この絵本で初めて知ったのですが、リーブ・リンドバーグは、太平洋無着陸横断飛行で有名なチャールズ・リンドバーグの娘さんだそうです。
その内容を少しご紹介します。
“もっともっと多くの人々が、開発行為に対して深い責任を持ち、地球の環境に関心を払い始めれば、ジョニー・アップルシードはとても喜ぶだろうと思います”と述べられています。
「人間と自然の共生」をめざし、飛騨の高山で工芸村「オーク・ヴィレッジ」での活動をはじめ、さまざまな活動を展開。著書も「緑の生活」「森からの発想」「森に育てられて」など多数。
「木を植えた男」という素適なお話があります。アニメ映画や絵本で有名です。ただ、主人公は実在の人物ではなく、物語にあるように、ドングリをいきなり荒地に植えても、それがそのまま大森林になるということはありえない、まず苗床を作って、そこでできた苗を山に移植しなくてはならないそうです。
この実在の人物をどう浮かび上がらせるか、それは非常に困難な作業だったそうです。稲本さんは、アメリカの子供に与えたのと同じ夢を日本の子供たちにも与えたいという思いをもってこの絵本を訳されました。
“この物語が気に入った人も、そうでない人も、ぜひとも何か一本の木を植えてほしい。そうすればその体験が、言葉の壁や習慣の違い、そして時代と距離を越えて、謎に満ちた「ジョニー・アップルシード」を知る、一番の手掛かりになるだろうから。”
2007.11 読書サロン まっちゃん
まだ少し早いかも知れませんが、クリスマスにお薦めの素敵なお話を二つ。
『急行「北極号』 C・V・オールズバーグ 絵と文
村上春樹 訳 あすなろ書房(1500円)
サンタを待つ少年のもとにあらわれたのは、白い蒸気につつまれた謎めいた汽車でした。急行「北極号」に乗り、少年は幻想的な旅へと出かけます。
『サンタクロースっているんでしょうか?』 偕成社(800円)
1897年、ニューヨーク・サン新聞あてに、バージニアという八歳の少女から手紙が届きました。
「サンタクロースって、ほんとうに、いるんでしょうか?」
少女の質問に愛情をこめて答えた社説は、今では古典のようになって、クリスマスの時期が近づくと、アメリカの新聞や雑誌にくり返し掲載されるということです。1977年に日本語にも翻訳され、版を重ねて現在に至っています。
クリスマスがテーマの子どもの本は、図書館で見ても、じつに沢山出版されていますが、中には、正直なところ内容も絵もいまいちだなあと感じるものもあります。ついでにあげれば、日本の「ひな祭り」をテーマにした本は、探しても、こんなにと思うほど数が少ないのです。残念なことです。
またついでにあげれば、絵本や児童書で、食べ物の出てくる場面は、私も好きでわくわくしてしまうのですが、圧倒的に洋食が多いということ(食事にしろおやつにしろ)です。これが悪いわけではないけれど、ちょっとさびしい気がします。日本の伝統的なおやつが出てくる本をとおして、日本人の心も伝えてくれるようなお話がもっと出てきてくれないものかと思うのです。
大人たちは、安易な本作りを考えなおしてほしい。未来をになう子どもたちに伝えていかなければならないものが、もっとあるのではと思うのです。
まだ少し早いかも知れませんが、クリスマスにお薦めの素敵なお話を二つ。
『急行「北極号』 C・V・オールズバーグ 絵と文
村上春樹 訳 あすなろ書房(1500円)
サンタを待つ少年のもとにあらわれたのは、白い蒸気につつまれた謎めいた汽車でした。急行「北極号」に乗り、少年は幻想的な旅へと出かけます。
『サンタクロースっているんでしょうか?』 偕成社(800円)
1897年、ニューヨーク・サン新聞あてに、バージニアという八歳の少女から手紙が届きました。
「サンタクロースって、ほんとうに、いるんでしょうか?」
少女の質問に愛情をこめて答えた社説は、今では古典のようになって、クリスマスの時期が近づくと、アメリカの新聞や雑誌にくり返し掲載されるということです。1977年に日本語にも翻訳され、版を重ねて現在に至っています。
クリスマスがテーマの子どもの本は、図書館で見ても、じつに沢山出版されていますが、中には、正直なところ内容も絵もいまいちだなあと感じるものもあります。ついでにあげれば、日本の「ひな祭り」をテーマにした本は、探しても、こんなにと思うほど数が少ないのです。残念なことです。
またついでにあげれば、絵本や児童書で、食べ物の出てくる場面は、私も好きでわくわくしてしまうのですが、圧倒的に洋食が多いということ(食事にしろおやつにしろ)です。これが悪いわけではないけれど、ちょっとさびしい気がします。日本の伝統的なおやつが出てくる本をとおして、日本人の心も伝えてくれるようなお話がもっと出てきてくれないものかと思うのです。
大人たちは、安易な本作りを考えなおしてほしい。未来をになう子どもたちに伝えていかなければならないものが、もっとあるのではと思うのです。
『うれしいな おかあさんといっしょ』 熊田千佳慕・文と絵 小学館保育絵本 (日本の絵本なのですが、いっしょに紹介します)
『だっこのえほん』 ヒド・ファン・ヘネヒテン/作・絵 のざか えつこ/訳 フレーベル館
『ぎゅっ』 ジェズ・オールバラ/作・絵 徳間書店
動物の親子の絵本です。熊田千佳慕さんの絵は、精密で、それでいて冷たくなくあたたかみがあり、子どもだからといって手抜きしないで描かれていて、幼いころにこのような絵にふれる機会があることは、しあわせなことではないかと思いました。
チンパンジーのだっこは ふんわりあったか…
カメのだっこは ひなたでのんびり。
アヒルのだっこは くちばしですりすり…
カニのだっこはとてもたいへん、カチャ パチャ カチャ。
さいごは、ぼくとママのやさしいだっこ!
おなかの あかちゃんもいっしょにね。
おさんぽしていたおさるのジョジョくんは、みんなが「ぎゅっ」としているのを見て、ママがこいしくなりました。
みんなしあわせそうなかお、うらやましいなあ。そこへおかあさんがやってきました。二人はしっかり「ぎゅっ」!
幼児虐待のニュースがあとを絶ちません。悲しいことです。どうしてこんなことになってしまったのでしょう。
子育ては、元来親だけでなく、まわりのみんながかかわるべきものなのではないでしょうか。母親だけ、あるいは、父母だけでかかえ込み、閉塞感の中での子育てでは行き詰ってしまう。でも、具体的にどうすればよいのか、と考え込んでみても、力のない自分をおもいしらされるばかりです。
子どもたちがあたたかいふれあいの機会をたくさんもって、育ってくれることを願います。
『紙しばい屋さん』 アレン・セイ 作/絵 ほるぷ出版(2007年)
 久しぶりで素適な絵本、そしてその絵本を描かれた素晴らしい絵本作家を知ることが出来、嬉しく思いました。
久しぶりで素適な絵本、そしてその絵本を描かれた素晴らしい絵本作家を知ることが出来、嬉しく思いました。
アレンさんは1937年横浜生まれ。中学生時代に東京で漫画家の野呂新平に師事し、絵を学び、16歳で渡米。兵役を経て写真家に。本業のかたわら、小説なども執筆。1972年に初めての絵本を出版。50歳をむかえた頃から絵本創作に専念し、『おじいさんの旅』でコルデコット賞(アメリカの絵本に与えられる最高の賞)を受賞されています。
 アレンさんは<日本語版によせて>の中で「横浜で過ごした人生の最初の6年間の楽しみは、主に紙芝居だった。そして、もしもそれがなかったら大変つまらない子ども時代だったと思う。」と書かれています。以下その内容からの紹介です。
アレンさんは<日本語版によせて>の中で「横浜で過ごした人生の最初の6年間の楽しみは、主に紙芝居だった。そして、もしもそれがなかったら大変つまらない子ども時代だったと思う。」と書かれています。以下その内容からの紹介です。
 「戦争がはじまり、紙しばい屋さんが来なくなり、田舎に疎開し、ぼくの子供時代は失われてしまったのです。
「戦争がはじまり、紙しばい屋さんが来なくなり、田舎に疎開し、ぼくの子供時代は失われてしまったのです。
16歳でアメリカに渡り、初めての絵本が出版された時には35歳。二冊目は紙芝居をテーマにして書くつもりでしたが、その時はアメリカの読者に理解してもらえないだろうと思い、かわりに落語の話を英語で語り直しました。
あれから32年が過ぎ、その間にアメリカでは日本文化が広がり、今なら紙芝居の話もわかってもらえるだろうと、手がけた作品です。そして、小さかったぼくが毎日胸を躍らせたあの紙芝居はもう二度と見ることのできないものだと思いながら作った本です。」
 昔の日本の懐かしい風景、風俗が描かれ、作者の思いが伝わってきて、胸がいっぱいになりました。
昔の日本の懐かしい風景、風俗が描かれ、作者の思いが伝わってきて、胸がいっぱいになりました。
アレンさんは1937年横浜生まれ。中学生時代に東京で漫画家の野呂新平に師事し、絵を学び、16歳で渡米。兵役を経て写真家に。本業のかたわら、小説なども執筆。1972年に初めての絵本を出版。50歳をむかえた頃から絵本創作に専念し、『おじいさんの旅』でコルデコット賞(アメリカの絵本に与えられる最高の賞)を受賞されています。
16歳でアメリカに渡り、初めての絵本が出版された時には35歳。二冊目は紙芝居をテーマにして書くつもりでしたが、その時はアメリカの読者に理解してもらえないだろうと思い、かわりに落語の話を英語で語り直しました。
あれから32年が過ぎ、その間にアメリカでは日本文化が広がり、今なら紙芝居の話もわかってもらえるだろうと、手がけた作品です。そして、小さかったぼくが毎日胸を躍らせたあの紙芝居はもう二度と見ることのできないものだと思いながら作った本です。」
前回に続き、アレン・セイの作品です。『紙しばい屋さん』より前に出版。自伝的作品になっています。コルデコット賞受賞作です。
これは、日本からアメリカに渡った個人の物語だが、
他の多くの移住者の物語でもあると同時に、
ぼくたち自身の物語でもある。
ぼくたちは何処にいようと、ほかの何処かが恋しい。
誰といようと、ほかの誰かが恋しい。
作品はある時、作者を越える。
この絵本は、
普遍的な人間の「郷愁」の心を瑞々しくすくいとり、
すべての人々の物語になった。
(表紙見開きより)
<『おじいさんの旅』が絵本として成功したということは、ぼくにとってまったくの驚きだった。これは、あまりにも個人的な話だと思っていたのだ。後になってぼくは、ここに描いた移民の国、アメリカでの自分の人生のエッセンスが、他の無数のアメリカ人のそれと重なっていることに初めて気がつくことになる。
「あなたは私の父の話を本にして下さいました」「この話はまったく私の祖父の話と同じです」「どうしてあなたは、私の家族のことをこんなに御存知なんでしょう」と、多くの声が寄せられた。>
水田 まり 訳 新世研(1998年)
アレン・セイの作品に心ひかれて、続けて読んでいます。
アメリカやヨーロッパの本には、初めに、その本を捧げる人の名前が書かれているのを見ますが、この本には、「森田せんせいに」と書かれていて、肖像写真風の絵があります。梅の柄の和服に無地の羽織を着てメガネをかけた、にこやかな笑顔の年配の女性です。
朝早くから運動会の準備を皆でやり、いろいろな競技があり、うれしい賞品ももらえます。お昼になると、生徒の家族もいっしょの楽しいお弁当の時間。お重には、ならづけ、たまごやき、おすし、かまぼこなど。ほかに果物やいろいろなおかしもあります。
午後の競技の時、ふたりのアメリカ兵が、こちらをみています。ひとりは白人、もうひとりは黒人。兵隊さんたちは、こちらにやって来て、校長先生の自転車を指さします。乗っていいかたずねているようです。
もりた きよみ/訳 新世研(2000年)
《『三年寝太郎』は、「百姓は生かさず殺さず」をモットーに厳しい年貢取立てを続けた、徳川幕府への反抗心から生まれました。どうせあくせく働いたとて豊かにならぬなら、いっそ寝たまま暮してやろう、と長い昼寝を決め込んだ寝太郎は、三年目に突如がばと起き出して潅漑治水を進め、農民を救ったという伝説です。
これには異聞があり、『となりの寝太郎』を基調にしたもの。この絵本がまさにそれです。「士農工商」の第二の地位に置かれながら一向に豊かにならない農民が、第四の地位ながらも私腹を肥やしている商人を利用して一攫千金を狙う、という皮肉がこめられていると思われます。
ですが、ダイアン・スナイダーの物語はそのような含みは奥深くにしまい込み、ユーモアたっぷりの語り口で大人も子どもも楽しませてくれます。特に本書では太郎の母親に強烈なキャラクターを与えて成功しました。スナイダーは幼少の一時期を日本で過ごしたことがあり、多数の民話や伝説を見聞きしました。》
冒頭の、長良川の鵜飼いの風景、貧乏な寝太郎の家の破れ障子や火鉢。左官屋さんが壁塗りをしているところ、大工さんたちが家を建てている様子など。アメリカ人には日本の文化を知ってもらえることになるでしょうし、日本人にはなつかしく心に伝わってきます。
遠い国で日本に思いを馳せ、日本の物語を紹介してくださる方がいて、それが日本語に翻訳され、読むことができる。目に見えないつながりを感じ、あたたかい気持ちになりました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
元気な本棚 ほっこり 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
元気な本棚 ほっこりのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170671人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89536人