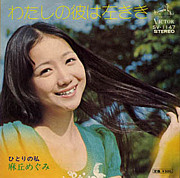先日のお料理教室で、話しに出たことを上げておきます。
他にもあるんですが、もう一度確認しないと意味不明なものもあるので、一部割愛します。
2010/5/30
1.食材と保存について
(1)青唐辛子
・冷凍することもできますが、できれば使い切る方がいい。
・作り置きできる料理にチャトニがあります。青唐辛子を多くしてチャトニを作ればしばらく保存できます。
(2)カレーリーフ
・乾燥したものでもそのまま冷凍します。ジップロックに入れて冷凍すれば何ヶ月も保ちます。
・ただし、油に入れる時はパチパチはねるので、蓋を使います。
・また、焦げやすいので弱火にします。
・カレーリーフはなかなか生が手に入りませんから、乾燥したもの冷凍のものでもないよりはましです。
・余り味はしませんが、好き嫌いではなく体にいいので食べてください。
(3)マスタードシード
・インドでは白いマスタードは見たことがありません。
(4)油について
・ごま油を使うとコクがでて良いです。長持ちします。
・サラダ油としては、サンフラワー(ひまわり)オイル、ピーナツオイルがインドでは一般的です。
(5)お米について
・タイ米はダメです。ビリヤニがパラパラに仕上がりません。
(6)スパイスについて
・マサラというのは色んな意味があるが、色んなスパイスを混ぜてペーストにしたもの
・今回ビリヤニにターメリックを使っていますが、もし手に入ればジーラ(クミン)を使ってください。ジーラを使うと色が茶色く仕上がります。
・野菜にはマスタードを使うことが多く、肉にはシナモン、カルダモンが多く使われます。
・ベイリーフは割らずに入れます。
・カルダモンもそのまま。大きければ割ります。
・ビリヤニのスパイスにコリアンダー(パウダー)を使ってもいい。コリアンダーシードはどちらかというと肉用のスパイス。
(7)玉子
・丸ごと入れてご飯で隠す
・割ると黄身がくずれてご飯に臭いが移り、時間が経つと臭くなる。玉子は固ゆでにし、半熟にすることはありません。インド人は、すしや刺身などの生ものが嫌いです。
(8)ココナツ
・ココナツはファインを使うのがよい。ミルク缶は余ってしまって使い切れないし、パウダーも余ったらすぐ悪くなってしまうからです。ファインであれば、長持ちするし、ジップロックで冷凍すれば何年でも保ちます。ケーキにも使えます。
(9)野菜
・ニンジン、インゲン、ジャガイモは野菜カレーの伝統的な食材です。
2.インド人の食事と好みについて
・ライタはヨーグルトのサラダみたいなものですが、ビリヤニに付けて食べます。日本にはご飯にヨーグルトをかける習慣がないので慣れない方は無理に作る必要はありません。
・ビリヤニは炊き込んだものも炒めたものもビリヤニと言います。炊き込んだ方が味が染みていて美味しいのですが、凄く時間がかかります。何回も炒めたりミキサーにかけたりしなければならず、ご飯を炊く前にかかる準備に時間がかかります。
・インドでは「ビリヤニと魚料理は次の日が美味しい」と言われています。ラターさん本人は余り翌日食べることはしないらしいが、それでも昼と夜に食べると言うことはあるらしい。
・味が染みるので少し塩が強くてもいい。
・デザートの硬さの好みは、日本人よりインド人のほうがゆるめが好きなようです。砂糖の量は日本人の好みの2倍から3倍入れます。
3.調理方法について
・トマトチャトニは、生臭いようなら、炒め不足です。ちゃんと炒めれば冷蔵庫で1週間保ちます。できるだけ細かくしてマスタードのつぶつぶが無くなるくらいにします。
・フェネル、ココナツ、カシューナッツ、水をミキサーにかけますが、ここでよくミキサーにかけないといくら煮てもざらつきが残ります。本場の味も、少しざらつきは残る程度。
炒める順番
・ジンジャーガーリックペーストは玉ねぎがきつね色になってから入れます。
(きつね色と言っているが、まったくきつね色になっておらず、透明になったくらい)
・トマトと肉は肉が先。
トマトを先に入れると肉に火が通りにくく肉の臭さみが残る。トマトはつぶしながら入れる。
・カシューナッツとレーズンは、まずカシューナッツを炒めてからレーズンを入れます。始めからレーズンを入れると焦げてしまいます。
他にもあるんですが、もう一度確認しないと意味不明なものもあるので、一部割愛します。
2010/5/30
1.食材と保存について
(1)青唐辛子
・冷凍することもできますが、できれば使い切る方がいい。
・作り置きできる料理にチャトニがあります。青唐辛子を多くしてチャトニを作ればしばらく保存できます。
(2)カレーリーフ
・乾燥したものでもそのまま冷凍します。ジップロックに入れて冷凍すれば何ヶ月も保ちます。
・ただし、油に入れる時はパチパチはねるので、蓋を使います。
・また、焦げやすいので弱火にします。
・カレーリーフはなかなか生が手に入りませんから、乾燥したもの冷凍のものでもないよりはましです。
・余り味はしませんが、好き嫌いではなく体にいいので食べてください。
(3)マスタードシード
・インドでは白いマスタードは見たことがありません。
(4)油について
・ごま油を使うとコクがでて良いです。長持ちします。
・サラダ油としては、サンフラワー(ひまわり)オイル、ピーナツオイルがインドでは一般的です。
(5)お米について
・タイ米はダメです。ビリヤニがパラパラに仕上がりません。
(6)スパイスについて
・マサラというのは色んな意味があるが、色んなスパイスを混ぜてペーストにしたもの
・今回ビリヤニにターメリックを使っていますが、もし手に入ればジーラ(クミン)を使ってください。ジーラを使うと色が茶色く仕上がります。
・野菜にはマスタードを使うことが多く、肉にはシナモン、カルダモンが多く使われます。
・ベイリーフは割らずに入れます。
・カルダモンもそのまま。大きければ割ります。
・ビリヤニのスパイスにコリアンダー(パウダー)を使ってもいい。コリアンダーシードはどちらかというと肉用のスパイス。
(7)玉子
・丸ごと入れてご飯で隠す
・割ると黄身がくずれてご飯に臭いが移り、時間が経つと臭くなる。玉子は固ゆでにし、半熟にすることはありません。インド人は、すしや刺身などの生ものが嫌いです。
(8)ココナツ
・ココナツはファインを使うのがよい。ミルク缶は余ってしまって使い切れないし、パウダーも余ったらすぐ悪くなってしまうからです。ファインであれば、長持ちするし、ジップロックで冷凍すれば何年でも保ちます。ケーキにも使えます。
(9)野菜
・ニンジン、インゲン、ジャガイモは野菜カレーの伝統的な食材です。
2.インド人の食事と好みについて
・ライタはヨーグルトのサラダみたいなものですが、ビリヤニに付けて食べます。日本にはご飯にヨーグルトをかける習慣がないので慣れない方は無理に作る必要はありません。
・ビリヤニは炊き込んだものも炒めたものもビリヤニと言います。炊き込んだ方が味が染みていて美味しいのですが、凄く時間がかかります。何回も炒めたりミキサーにかけたりしなければならず、ご飯を炊く前にかかる準備に時間がかかります。
・インドでは「ビリヤニと魚料理は次の日が美味しい」と言われています。ラターさん本人は余り翌日食べることはしないらしいが、それでも昼と夜に食べると言うことはあるらしい。
・味が染みるので少し塩が強くてもいい。
・デザートの硬さの好みは、日本人よりインド人のほうがゆるめが好きなようです。砂糖の量は日本人の好みの2倍から3倍入れます。
3.調理方法について
・トマトチャトニは、生臭いようなら、炒め不足です。ちゃんと炒めれば冷蔵庫で1週間保ちます。できるだけ細かくしてマスタードのつぶつぶが無くなるくらいにします。
・フェネル、ココナツ、カシューナッツ、水をミキサーにかけますが、ここでよくミキサーにかけないといくら煮てもざらつきが残ります。本場の味も、少しざらつきは残る程度。
炒める順番
・ジンジャーガーリックペーストは玉ねぎがきつね色になってから入れます。
(きつね色と言っているが、まったくきつね色になっておらず、透明になったくらい)
・トマトと肉は肉が先。
トマトを先に入れると肉に火が通りにくく肉の臭さみが残る。トマトはつぶしながら入れる。
・カシューナッツとレーズンは、まずカシューナッツを炒めてからレーズンを入れます。始めからレーズンを入れると焦げてしまいます。
|
|
|
|
コメント(5)
2010.6.27
○ラッサム
・インド人はラッサムは健康にいいスープだと考えている。だからヒングも使うし、スパイスをこがさないよう注意する。ニンニクもヒングも焦がさない方が良い。
・何度も沸騰させずに、一回煮立ったところで止める。
・今回教えてもらったのはタミルのラッサム。地域によっても色んな味のラッサムがあるらしい。アジャンタのラッサムよりは随分薄くて物足りない印象だが家庭料理としてはこれで十分だという。シディークのラッサムがこんな感じだった。
○ヒング
・インドの人でもヒングの臭いは嫌いなのだそうだ。体にいいから使うだけ。
(そうは言っても大阪都島「ティラガ」の店長は大好きだって言ってたな)
・1回買えば長持ちするし、孫の代まで使える(冗談)
・ラッサムが体にいいというイメージなのはヒングを使うから。
・風邪の子供には、バナナにヒングを振りかけて食べさせるといいと言われている。
・風邪の時にはご飯にも入れて食べるとおばあさんから聞いた。
○サンバル
・サンバルによく似たタルカダールというものが北インドにもあるが、豆はムングダールを使う。
・地方によっても少しずつ異なるが、トゥールダルを使うのはタミルの味。バンガロールのサンバルはもっと水っぽくて、野菜やトマト、砂糖を入れて甘くする。チェンマイの人は敬遠して食べない。
・サンバルに向く野菜は、大根、キャロット、インゲン、なす(下手すると色が茶色くなるので、腕が付いてからがいい)、ジャガイモ(これも上手になったら)、オクラもいい、野菜のマンゴー、ドラムスティックdrumstickも合う。他に何も入れずに大きく切った玉ねぎを入れてもいい。いカボチャは入れないらしい
○アブラムについて
・南インドにはアブラムというパパドのような物がある。パパドは焼いて食べるがアブラムは油で揚げる。
・Anil社のHAPPALAを使った。
・アブラムはご飯と一緒に食べるものなので味は余り付いていない。辛いカレーに辛い物を使うのはよくない。
・油に入れるとはじめ周りが反り上がって丸まってくる。オーっと歓声が上がる。少し開くように整えてからひっくり返すと丸まった部分が元に戻ってほぼ平らになる。
・パパドを揚げると、アブラムより少しもろい。
・パパドは通常タンドールで焼くらしい。
○タマリンドについて
・10〜15分くらい水に浸しておけば軟らかくなる
・種や繊維は手で取り除き、料理にはそのジュースだけを使う。や繊維をきちんと取り除いておく。そうしないと味が悪くなる。
・料理の最後に入れるのが基本。最後に入れないと酸っぱさが飛んでしまうから。
・タマリンドが無い時はトマト多くすればいい。
○ご飯の炊き方(炊飯器)
・バスマティ 1:1.8〜2(ただしビリヤニに炒めるなら1:1.2〜1.5と少な目にすること)
・日本米 1:1.3〜1.5
・ポンニーアリシは南インドの割とポピュラーなお米。日本ではほとんど手に入らない。これは1:2.3〜2.5くらい多くの水を使う。アリシはタミル語でお米のこと。
○ギーについて
・ギーはコクを出したい時に使います
・サンバルは豆でコクを出しているのて使わない。
・ラッサムはさっぱり爽やかな味がいいので使わない。
・ポリヤルには基本的に使わない。
・ギーは、ドーサや北インドでは肉系の風味とコクを出したい時に使います
・ビリヤニも良いです
・ギーを使うことで辛い物でも少しマイルドに押さえられます。
・チャパティーにギーと砂糖を混ぜて付けて食べることがある。
○マスタードの中のウーラッド豆
・店ではマスタードシードに白い豆(ウーラッド)を入れているが、家庭ではそんなことはしない。マスタードをパチパチはねるまで炒めると豆が焦げはじめる。パチパチさせる前に次の調理が行えるよう、パチパチしはじめるサインのために入れているようだ。
○ラッサム
・インド人はラッサムは健康にいいスープだと考えている。だからヒングも使うし、スパイスをこがさないよう注意する。ニンニクもヒングも焦がさない方が良い。
・何度も沸騰させずに、一回煮立ったところで止める。
・今回教えてもらったのはタミルのラッサム。地域によっても色んな味のラッサムがあるらしい。アジャンタのラッサムよりは随分薄くて物足りない印象だが家庭料理としてはこれで十分だという。シディークのラッサムがこんな感じだった。
○ヒング
・インドの人でもヒングの臭いは嫌いなのだそうだ。体にいいから使うだけ。
(そうは言っても大阪都島「ティラガ」の店長は大好きだって言ってたな)
・1回買えば長持ちするし、孫の代まで使える(冗談)
・ラッサムが体にいいというイメージなのはヒングを使うから。
・風邪の子供には、バナナにヒングを振りかけて食べさせるといいと言われている。
・風邪の時にはご飯にも入れて食べるとおばあさんから聞いた。
○サンバル
・サンバルによく似たタルカダールというものが北インドにもあるが、豆はムングダールを使う。
・地方によっても少しずつ異なるが、トゥールダルを使うのはタミルの味。バンガロールのサンバルはもっと水っぽくて、野菜やトマト、砂糖を入れて甘くする。チェンマイの人は敬遠して食べない。
・サンバルに向く野菜は、大根、キャロット、インゲン、なす(下手すると色が茶色くなるので、腕が付いてからがいい)、ジャガイモ(これも上手になったら)、オクラもいい、野菜のマンゴー、ドラムスティックdrumstickも合う。他に何も入れずに大きく切った玉ねぎを入れてもいい。いカボチャは入れないらしい
○アブラムについて
・南インドにはアブラムというパパドのような物がある。パパドは焼いて食べるがアブラムは油で揚げる。
・Anil社のHAPPALAを使った。
・アブラムはご飯と一緒に食べるものなので味は余り付いていない。辛いカレーに辛い物を使うのはよくない。
・油に入れるとはじめ周りが反り上がって丸まってくる。オーっと歓声が上がる。少し開くように整えてからひっくり返すと丸まった部分が元に戻ってほぼ平らになる。
・パパドを揚げると、アブラムより少しもろい。
・パパドは通常タンドールで焼くらしい。
○タマリンドについて
・10〜15分くらい水に浸しておけば軟らかくなる
・種や繊維は手で取り除き、料理にはそのジュースだけを使う。や繊維をきちんと取り除いておく。そうしないと味が悪くなる。
・料理の最後に入れるのが基本。最後に入れないと酸っぱさが飛んでしまうから。
・タマリンドが無い時はトマト多くすればいい。
○ご飯の炊き方(炊飯器)
・バスマティ 1:1.8〜2(ただしビリヤニに炒めるなら1:1.2〜1.5と少な目にすること)
・日本米 1:1.3〜1.5
・ポンニーアリシは南インドの割とポピュラーなお米。日本ではほとんど手に入らない。これは1:2.3〜2.5くらい多くの水を使う。アリシはタミル語でお米のこと。
○ギーについて
・ギーはコクを出したい時に使います
・サンバルは豆でコクを出しているのて使わない。
・ラッサムはさっぱり爽やかな味がいいので使わない。
・ポリヤルには基本的に使わない。
・ギーは、ドーサや北インドでは肉系の風味とコクを出したい時に使います
・ビリヤニも良いです
・ギーを使うことで辛い物でも少しマイルドに押さえられます。
・チャパティーにギーと砂糖を混ぜて付けて食べることがある。
○マスタードの中のウーラッド豆
・店ではマスタードシードに白い豆(ウーラッド)を入れているが、家庭ではそんなことはしない。マスタードをパチパチはねるまで炒めると豆が焦げはじめる。パチパチさせる前に次の調理が行えるよう、パチパチしはじめるサインのために入れているようだ。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
BANAIE 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
BANAIEのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人