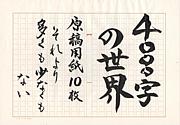空気が冷たく乾燥している。
いつの間にか、秋は終わりかけていた。落ち葉が歩道の側溝に溜まって、風に揺れている。
空は水色に透き通っていた。だが形治の気分は沈んでいた。金がないからだ。財布が軽い。空気の冷たさは骨の髄を震わせるし、空の青さは、あっけらかんとしている。職安からの帰り道はいつも、世の中のすべてが自分を嘲っているように感じられた。
家に帰っても、真知子はいなかった。仕事に出ていて、帰ってくるのはいつも五時半過ぎだった。まだあと三時間近くある。
形治はコーヒーを入れて、ハローワークから持ち帰った求人用紙の束に目を通し始めた。だが、眼で見た内容が、頭の中に入ってこない。部屋の中が静かすぎて、耳にうるさいほどだった。アパートの他の住人も仕事中で部屋にいないのか、物音ひとつしない。この世の中に独りぼっちでいるような気分になって、形治は少し身震いした。
結婚して一ヶ月。
仕事なんかすぐに見つかると思い、五件ほど会社を回って面接したが、今のところ良い返事はなかった。
真知子は、口に出しては何も言わない。だが昨日、溜まっている洗濯物を見て、彼女はすこし立ち尽くしていた。その姿を見て、形治は落ちこんだ。職を見つけるまではなるべく家事をこなそうと思っていたのに、ついつい洗濯を先延ばしにしてしまっていた。
だが真知子は何も言わない。
「柿をもらってきたから、食べようよ」
真知子は昨夜、食後にそう言って、柿をむき始めた。彼女の実家はアパートのすぐ近くにあり、そこで取れた柿をもらってきたのだそうだ。
包丁で切り落とされてゆく柿の皮が、皿の上に次々と落ちる。熟した実をほおばると、柔らかく甘かった。オレンジ色のとろとろの実を嚥下すると、何故か無性に力がぬけた。
何でだろう、と形治は思いながら、何気なく、顔をそむけた。「どうしたの?」と真知子が問いかけてくる。彼女はまだ二十三歳だったが、年の割には落ち着いている。形治は、時々、同い年であるはずの自分が、あまりに幼く感じられることがあった。
真知子が覗き込んでくる。形治は何でもないと肩をすくめて、また柿へ手を伸ばした。
三ヶ月程前、形治は上司とトラブルを起こして、印刷会社を辞めた。営業成績の悪さを指摘され、嫌気が差して辞表を提出したのだが、一番の原因は、日頃から何かと彼に文句をつけてきたその上司が、形治の取ってきた契約を横取りし続けていたことだった。
争い事は好きではなかった。出来れば平穏無事に、のんびりと生きて行きたかったのだが、一年以上にも及ぶ嫌がらせには耐え兼ねた。何かが、腹の奥底に溜まっていた。それは怒りだったし、悔しさでもあったのだが、その実もっと種類の違う、得体の知れぬもののようにも思われた。
「成績、いつまでたっても伸びないねえ」
と、上司に言われた瞬間に、腹の奥底に沈殿していた何かが破裂したように感じられた。彼は即座に辞表を書き、上司の胸に投げつけた。
真知子と結婚したのは、その翌月である。
彼女は高校時代の同級生で、付き合いは五年ほどだった。早かったな、と思う一方、よく続いたな、とも形治は思う。
彼は常日頃から、恋愛とは烈しく感情を揺さぶられるものだと盲目的に信じており、その信条からすれば、とっくに別れていてもおかしくない付き合い方をしていた。そこまで熱狂的に入れ込むわけではなく、かといって完全に冷えているわけでもない、微妙な距離感を保った間柄は、恋人というよりも友人に近かった。彼自身、それが恋心なのか友情なのか分からないまま付き合っていた
そんな彼女が、形治の失業を知った途端、向こうからプロポーズしてきたのだった。不思議でならない形治は「なんで?」と聞いてみたが、真知子はただ「いいじゃん」と言うばかりで、すでに婚姻届を用意していた。
形治は婚姻届を受け取り、二日間、迷った。真知子は、いくら理由を問いただしても、はっきりとした言明を避ける。それが当然のことのような顔をしている。職を失って、貯金もあまりない彼氏が魅力的とは、形治にはとうてい思えないのだが、真知子はただ、「魅力的とか、そういうことじゃないでしょ」と言うばかりだった。
二日後、二人で市役所に婚姻届を持っていった。窓口で、町報と新聞のお喜び欄に名前を載せるか、と聞かれ、彼らはお互いの顔を見ると、揃って首を横に振った。
小さな鉄工所へ面接に行った。スーツは着慣れているが、油やら何やらで汚れた作業着を着る従業員とすれ違うと、なんだか場違いのような気がした。事務所に通され、まだ三十代後半のように見える社長と向かい合う。履歴書を渡すと、いきなり渋面を作られた。
「六年間、印刷所の営業をねえ……うちはきついよ、肉体労働だし、この時期不況だから、給料もあんまり期待できないし……」
形治は高校時代、空手部に所属していて、一応黒帯も持っているし、ランニングを日課にもしている。そんなことをアピールしたところでタカが知れているが、他に何を強調すれば良いのか分からなかった。とにかく、頑張りますと連呼して、事務所を出た。
鉄工所に駐車場はなく、車は近くの川原に停めていた。形治はその川原へ向かって歩きながら、白い息を吐いた。
空はあいかわらず青い。青くて、広い。堤防にあがって周囲を見渡す。田舎町には、視線を遮る遮蔽物はなく、視界のどこまでも、大きな川と、青い空が伸びていた。
どこかから子供の笑い声が聞こえてくる。見ると、陸橋の下で、十四、五歳ほどの子供が二人、キャッチボールをしていた。
すると不意に、片方の子供が大暴投をして、ボールが形治の足許に飛んできた。
何気なく拾うと、ボールは軽かった。買ったばかりなのか、まだ白く、そんなに汚れていない。形治はボールをじっと見つめた。真新しいゴムの感触が、掌に痛く感じられた。
「すみませーん」
と子供が頭を下げて、駆け寄ってくる。形治はそれを手で制した。胸のうちに、あの不快な、吐気にも似た何かが感じられた。何故か、嫌味を言う上司の顔と、洗濯物の前に立ち尽くす、真知子の後ろ姿が思い出された。
「投げるよ」
と形治は声をかけて、振りかぶった。軽く投げるつもりだったのに、身体中に鬱積した泥のような感情が疼いて、吐気がした。気づくと歯を食いしばり、吐気を振りきるように、全力投球してしまっていた。
ボールは放物線を描いて、川の中にボチャンと落ちた。その音ではっと我に返った。
「ああごめーん!」
「何するんスかあ」
形治は平謝りし、すぐに近くのスポーツ店で二人にボールを買い与えた。道中、二人は中学校をサボって暇潰しをしていたと語った。お兄さんは仕事中でしょ、と聞かれて、俺もサボり中、と答えた。三人は意気投合し、日が暮れるまで、川原でキャッチボールをし続けた。
家に帰ると、すでに六時を過ぎていた。夕飯の準備をしていた真知子は、形治の顔を見るなり、「なんたら鉄工所から電話があったよ」と言った。
「何だって?」
「採用だって。来月から」
「そっか」と形治は答えた。肩透かしを食らったような気分だった。
夕飯はカレーライスとサラダだった。テレビを見ながら、黙々と食べた。食後に、「また柿もらっちゃった」と真知子は言って、台所に立つ。柿をむく真知子の後ろ姿は、いつもと変わらない。形治は冷たい空気を浴びたくなり、窓を開けてベランダに立った。見事な満月が、暗い夜空に浮かんでいた。
「外で食べる?」
真知子が言って、椅子を二脚運んでくる。二人はベランダに並んで坐った。
隣の部屋か階下から、テレビの音が聞こえてくる。くぐもった笑い声は、どこか遠くの異国から届いているように感じられた。アパートのそこら中に人の気配を感じるのに、二人のいるベランダだけが、闇の中で孤立しているように思われた。
真知子は「寒いね」と笑い、柿をほおばって、「就職おめでとう」と言った。形治はすぐに返答できず、少し言葉につまった後、言った。
「どうして俺と結婚しようと思ったの?」
真知子は満月を見上げて、柿を食べながら答えた。
「さあね。どうしてかしらね」
「俺じゃなくても良かったじゃん」
「結婚なんてしたくなかった?」
形治はまた答えにつまった。結婚したかったのか、したくなかったのか、自分でもよく分からない。言葉を探しながら、柿を口に含んだ。とろとろに熟した実は甘い。
「よく分からないけど、して良かったと思う」
「そうだね。私も分からないけど」
四個あった柿は、すぐになくなった。
二人は寒さに震えながら、眠くなるまでお喋りをし続けた。
おわり
|
|
|
|
|
|
|
|
4000字の世界 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
4000字の世界のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人