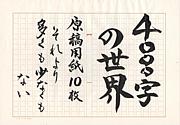川のそばに、一本の柳の木が立っている。
空に、まるくくりぬいたみたいな満月があって、うすい雲がかかっていたけども、小川のこまかい波だとか、川べりの砂利だとか、柳の葉の輪郭とかを、とても丁寧に、濡らすように光らせていて、ぼくは欄干に寄りかかって、それらをうっとりと眺めながら、どうしてか、これから好きな人と会うというのに、もう立ち去られてしまったようなさびしさを感じていた。
でも不思議と、さびしいときというのは、妙な具合に笑いがこみあげてくるもので、ひどく力のない、ぎゅうぎゅうに絞った濡れ布巾の、最後の一滴みたいな、残りかすみたいな笑い声が出てきて、ぼくはそれをいとも簡単に、橋の上から川に落とす。
これはようするにぼくが酔っているということで、小学校の教師のくせに、みっともない話なのだけれども、酒の力がないと彼女には会えないから、しかたのないことと考えて、月の光と、両岸の道路に立つ街灯の光を受けてひかる、橋の下の水面に見入る。
川の波頭は、めまぐるしく変わるくせに同じ形をくりかえし、同じ形でいながらめまぐるしく変わった。
酔いにまかせて、欄干に寄りかかった腕に顔を寝かせ、世のなかを横に見てみれば、地面が壁になって、壁から伸びる柳の木の、あのすべてが真下にたれさがるやわらかい枝が、横に突き抜けてきたように見える。枝が垂れているのじゃなくて、慣性の法則によって真横に引っぱられている感じに見える。ぼくは、柳の木というものから、無気力の美徳というか、肩の力の抜けた、飄々とした格好の良さみたいなものを感じていたのに、これではやる気満々みたいで、気に食わないから顔をもどすと、柳はやっぱり見慣れた姿で、祭りの夜に、浴衣を着た粋な女の、すずしげな首元がぼくを誘う、あの独特の色香が戻ってきて、うれしい。
月の夜に見る柳の木は、いつもそこにあって、たまに風に吹かれたりすると、小川のせせらぎに、枝葉のこすれる、ささやくような声を合わせて、川と柳の密談めいた姿を見せる。そうしたとき、ぼくは目をみはって、揺れる枝葉のあいだに、ゆらゆらと覗く、人の腕を見る。
この腕はたぶん女のもので、白くて、ほそくて、枝とおなじように垂れていて、でも微妙に、風に揺れる枝の動きとはちがう、わたしにはわたしの決まりごとがあるの、とでも言いたげな、ちょっとテンポのずれた、すこしわがままな揺れ方をするから、なまいきなんだな、とぼくは思う。腕の根元は、枝々の陰に隠れていて、見えそうで見えない。でも目を凝らすのもなんだか悪い。世のなかには知らなくていいこともいっぱいあるのに、ぼくらはすぐに知ろうとしすぎるから、謙虚な気持ちで、腕の動き方を見ていると、その腕が、なにかを呼んでいるみたいに、おいで、おいで、という風に、川に向かってそろえた指を、やわらかく蠢かせている。するとぼくはかなしくなって、たぶん、川下の、ぼくのいる橋の下のあたりに向かって、いつまでも呼びかけている腕に、口があればいいのにね、声で呼べればいいのにね、と同情して、呼びかけられているほうも、答えてあげればいいのに、きっとそうもできない事情があって、腕はそのことを知りながら、いつまでも呼びつづけているんだなと、なんだかすべてを知った風な、たぶんほかの人から見れば、とても鼻につくようなことを思っている。
すると緩慢に車が近づいてきて、ゆっくりとうしろを通りすぎていった。
まぶしいヘッドライトが、でこぼこしている橋を通る車の動きにあわせて、危なっかしく視線を揺らめかせている。ものすごい徐行で通りすぎていった車の、後部座席の窓には誰かが張りついていて、じっとこちらを見ていたようだけれど、ぼくは光に目がくらんでいて、なかなかはっきりしない、夜寝るときに明かりを消した後の、あの残光みたいなものに惑わされていた。
ゆらゆらと遠ざかってゆく車の、うしろの窓にいた、たぶん子供の目に、自分がどんな風に見えていたのか気にかかる。
それというのも、ぼくは酔っ払いだし、橋の欄干に寄りかかって、いまにも眠ってしまいそうだから、よけいな心配をかけてしまったかもしれないと思うからで、大人の、つまり車を運転していた誰かの心配なんてどうでもいいのだけれど、見ず知らずの子供の心配をあおるのは、なんだかひどくかわいそうな気がして、心が痛んだ。
ぼくはこの世の、ありとあらゆる子供たちを、仲間のように感じていて、クラスの教え子たちが黒板に向かって、あの愛らしくまるいチョークで描く、気弱そうな曲線や、必要のない大胆な筆圧なんかが好きで、彼女にそういうことを語ると、嫌がられるけれども、しかたがないなあって感じに笑ってくれるから、無邪気さをよそおうずるさを、割合はっきりと意識しながら、ぼくは一緒になって笑う。今日もきっと、ふたりでそんな風に、人の目をはばかって、こそこそと、いろんな人を騙したり裏切ったりするんだろうと思うと、うれしいのにかなしい、かなしいのにうれしい、どちらから読んでも意味が通じる回文みたいな、意味が通じるのに一見するとひどくばらばらみたいな、そんな心持ちになる。たけやぶやけた、とか、ごまたまご、とか、表記するときは必ずひらがなになるような発音で、ゆっくりとはっきりと言葉にするときの、ばかみたいにあけすけな喋り方で、彼女と笑い合うときのことを考えると、また再び、もうすでに立ち去られてしまったような、取り残されたさびしさみたいなものがこみあげてきた。
風を頬に感じ、酔いがさめてきているのを感じる。
いやだなこれは、と首を横に振り、ふと橋のたもとを見ると、木製の電信柱にとりつけられた街灯の下、男がひとり立っていた。
その男というのが、彼女の父親だったものだから、ぼくはびっくり仰天しながらも、気づかなかったフリをして、腕に顔を突っ伏してしまう。彼女の父親は、仕事帰りなのかスーツを着ていて、こつこつと、とても几帳面な革靴の音をたてながら、うしろをゆっくりと行き過ぎる。
彼女の父親は町の顔役だから、ぼくは知っているけれども、向こうはぼくのことなんて知らないはずで、けども、じっと観察されているような、服と背中のあいだの空気が、じっとりと湿るような、嫌な暑苦しさを感じた。
靴音が聞こえなくなってから顔をあげると、すっかり酔いがさめてしまって、なにもかも投げ出したくなってしまう。これから来るはずの彼女を突き飛ばしてしまいたくなってしまう。すると、欄干の冷たさが、やけに際立って感じられる。
寄りかかっている橋の欄干は、石でできていて、硬くて冷たくて、自分の腕がいやに繊細な、きもちわるいぐらいにやわらかい、別の生き物みたいな気がして、こわくなる。腕の内側の、陽にあたらないからってとりすました白い皮膚に、こまかな砂利がくいこんでいて、腕を持ちあげると、ぱらぱらと落ちて、やわらかい皮膚に、小さなへこみがいっぱいできて、ひとり黙々とおののいていると、どこかでいきなり猫が鳴いた。その鳴き方というのが、赤ん坊が叫んでいるような、発情している声だったので、夜がわびしく、よりいっそう、海の底みたいにずんずんと深くなる。でもぼくは、ネコヤナギっていう花があったなあと、あんまり関係のないことを思う。つぼみから出てきたばかりの、あの猫の尾のような綿毛につつまれる、ちょっとした冗談みたいな花穂を思い浮かべ、おなじヤナギという名がつくというのに、しだれ柳とはくらぶべくもない、上向きにやる気あふれる花穂はあまり好きじゃないのだけれど、たしか先週、家からそれを持ってきて教室に飾った、いきもの係の女の子は、ネコヤナギが大好きなんだと言っていた。そのことを思い出すと、あの花穂はいかにも子供らしく、いたいけで健気で、この世のあらゆる子供たちを仲間のように感じながら、象徴的に子供の姿を模したネコヤナギが嫌いだというのは、いかにもぼく自身の欺瞞というか、ずるいところなんだと思う。
するとまた猫が鳴いて、風が吹いた。柳の枝葉がこすれてささやき、川のせせらぎとあいまった。
満月にかかっていた雲は晴れていた。
すべてが青白く、平明に照らされていた。
酔いは完全にさめているのに、まだ感覚がにぶっているみたいな、瞼はひらいていても、変なフィルターがかかっているみたいな景色で、おもわず涙ぐみそうになったとき、また柳の枝葉のあいだから女の腕が伸びて、しかもそれは二本も三本もあって、見る間に増えてゆき、みんな一斉に、こちらに向かってゆっくりと、おいで、おいで、と手を蠢かせていて、彼女たちは、橋の下なんかじゃなく、ぼく自身に向かって呼びかけているんだと気づいた途端、ぼくは捕まえられたような気分になった。
いやだ、いやだ、と思って首を横に振り、ふと川の左岸を見ると、彼女が橋に向かって歩いてくるのが見えた。彼女はうつむいていて、長い髪の毛の合間から、うれしげな目をこちらに向けているはずなのに、その顔からまた片腕が生えて、柳の腕みたいにしんなりとではなく、もっとはっきりと、まっすぐにこちらに手を伸ばしていて、物欲しげに指を開いていたから、ぼくはもう、だめだな、と思って、彼女や柳に背中を向けた。
了
|
|
|
|
|
|
|
|
4000字の世界 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
4000字の世界のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6478人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19254人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人