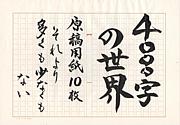仕事がおわり、これからデートだとはりきる同僚とわかれて帰途についた夜、健史はふいに、消え入りたくなった。
灯油ストーブにあたりながらバラエティー番組を観ていた時分にはなにも感じなかったのだが、沸かした湯船につかってふと、先ほど観たテレビの内容と、子供のころに見た影絵とが頭のなかで重なった。画面のなかでは芸人が全身黒タイツを着てくんずほぐれつしており、その様が、黒い指の影のからまり合う様を思い起こさせたのである。
彼に影絵を披露した女子中学生は、成人式をむかえた後、顔も知らない誰かのもとへと嫁いでいった。
そのことを思い出した途端、愉快だった気分が一掃された。天井から滴がひとつ湯船に落ちて、その音がいやにおおきく聞こえた。健史は湯のなかで身体を小さく、できるだけコンパクトにまとめてしまいたくなって、膝をきつく抱きしめた。
風呂あがりに一服していると侑子がやってきたので、そうした自分の思いを語ったところ、
「ようするに誰かと付き合いたいんでしょう」
と言われて戸惑った。彼女は彼のポテトチップスを奪いとって食べていて、右手の人差し指と親指とに塩がついたままになっていた。健史はその塩が彼女の体内で生成されており、なぜか指の腹にだけにじみ出てきて結晶化しているのだと想像しながら、
「そういうわけではないのだけど」
「そうなのよきっと。そうに決まってる」
侑子はいつだって断定する。
彼女はアパートの隣人で、おなじ二十六歳であり、それだけの理由で仲良くなったのだが、健史は彼女に関するそれ以上のことを何も知らなかった。
侑子はどんな問題も偏見で決めつけた。健史は彼女の自分勝手なふるまいを見るにつけ、鋭い草の葉で指を切ってしまったような驚きを感じるのだった。
「私の友達を紹介してあげるわ」
と彼女は言うなり携帯電話で誰かとの約束を取りつけてしまった。侑子は彼の反応を待ちもせず、自分の部屋へと戻っていった。
健史は、むかし影絵を披露してくれた女子中学生の名前を、おぼえていない。
彼女はいつも、平日の夜に遊びにきた。健史の両親は共働きで帰りがおそく、親が仲の良い近所の友人に頼んでそうしていたのだった。一緒にテレビを観たり、マンガを読んだりした。影絵遊びはその一環だったのだが、他に何もすることがない時の暇つぶしとして、たった一回したことがあっただけで、思い出すことはあまりなかった。
にもかかわらず、掘り起こしてみれば鮮烈な印象がある。
障子戸のむこうで、懐中電灯の灯りを前に、彼女の指が犬や狐の形をとる。指の影はきゃしゃにほそ長く、複雑にからまりあった。あまりにやわらかい動きをするため、健史はやましさのようなものを感じた。こわいと思ったのだが、そう口にすることすら許されないような気がして、ただじっとそれを見ていた。障子戸のかたわらで膝立ちになり、これは何の動物でしょうと、彼女は笑いながら言った。その腕だけが和紙の向こうで姿を変えている。
肘から先だけが影となってうごめく。
翌日にはまたテレビを観たりマンガを読んだりした。彼女との交流は、しかし一ヶ月ほどしか続かなかった。母が仕事を辞めたためで、健史はすぐに彼女のことを忘れた。高校生の頃、母親から「ほらあのお姉さん結婚したんだってよ」と聞かされたが、お姉さんが誰だったのか一瞬思い出せなかった。
記憶力は侑子もひどい。
彼女は週末になると健史の部屋にやってきて、くだらない会話をして帰るのだが、今日もいつもと同じようにそうしていると、ふいに携帯電話が鳴った。彼女は電話に出て投げやりに答えた。こぼれ落ちるセリフをすくいとるだけで充分、会話の内容が知れた。彼に紹介するという女性がやってきたのに、侑子は約束そのものを忘れていたのだった。
やってきた女性は茶色い髪を巻き毛にしたり、睫毛が異様に長かったり、ネイルアートが派手だったりして健史を気後れさせたが、話してみると意外と楽しかった。そして彼は、侑子もまた爪先をデコレーションしていることに、いまはじめて気づいた。ポテトチップスの塩がついているのを見ていたはずなのに、どうして爪に目がいかなかったのかと、不思議に感じた。
侑子の友達は三時間ほど雑談した後、門限をすぎたとあわてて立ちあがった。父親が厳しいのだというが、こんな格好を容認しながら門限を規定する厳しさとは、いったい何なのだろう、と彼は思った。
侑子がしきりに送っていけというので、ちかくの駅まで彼女を送ってゆくことになった。その道すがら、彼女は言った。
「侑子ってちょっとおかしいよね。色々辛いのは分かるけどさあ」
その色々が何なのか聞く前に駅についた。電車が来ていると言って友人は駆けだし、振り向きながら両手を振った。小首をかしげて笑顔をつくる彼女のポーズに、健史はあいまいな笑顔しか返せなかった。
アパートから駅までの距離はおよそ五分ほどだったが、その間を往復するだけで健史の身体はすっかり冷えた。彼は真っ先に熱を奪われるつま先を靴下のなかで縮こまらせ、両手に息を吹きかけた。
震えながら帰ってみると、アパートの前に白いワンボックスカーがとまっていた。
侑子の部屋の前では四十歳ほどの男が、彼女にすねを蹴られて悶絶していた。侑子はおおきな音をたてて扉を閉めた。とり残された男はしばらくその場にうずくまっていたが、健史が近づいてきたことに気づいて何でもない風をよそおい、車に乗りこみ、アパートを去っていった。
走り去る車のうしろの窓に、「赤ちゃんが乗っています」とプリントされたシールが貼られていた。
健史は自分の部屋にもどり、少しばかり本を読んだが、どうにも侑子の様子が気にかかった。アパートの壁はうすく、静かにしていると、隣人の生活音がよく響くはずなのだが、侑子の部屋からは一切の物音が聞こえてこない。無人のようとも違う、それは夜に降る雪の静寂に似ている。
匂いたつような孤独のけはいがする。
しかし、部屋をたずねてみると、侑子は平気そうな顔をしていた。
健史は彼女の部屋に入ってテレビをつけた。彼はカーペットの敷かれた床に坐り、彼女はベッドに寝ころがって肘をついた。テレビは南極の氷が溶け出しているといって、流氷を映す。流氷にはペンギンが立っている。他のペンギンが海中から勢いよく飛び出し、流氷のうえにぶざまに着地している。
健史は笑ったが侑子は無表情だった。
健史はふと思いたってテレビを消し、
「懐中電灯ない?」
と聞いた。侑子は玄関の靴箱を指差した。彼は靴箱のなかにしまいこまれていた懐中電灯をとりだし、テーブルのうえにちらばっているスーパーのうすい広告チラシを手にとって、部屋の電気を消した。
侑子は彼の行動を見守っている。
懐中電灯をつけてテーブルに置き、左手にチラシを持って、裏側の面を彼女に見せるようにした。そして右手で犬の横顔をつくって、その影を映す。
「犬」
健史はそう言ったが、侑子は無表情なままだった。彼はすこし思案し、犬の口を尖らせるような形をつくって、「狐」といった。侑子の能面は変わらず、健史はぼんやりと中空に目線を泳がせてから、手首をそらせるような形をとってさらに「ペンギン」といった。
手の甲がつりそうだった。映った影はどこからどう見ても謎のポーズにふるえる人の手そのもので、侑子はふいを突かれたようにふき出した。
翌日仕事へ行くと、以前デートだと浮かれていた同僚が、うれしそうに話しかけてきた。狙っていた女性をホテルへ連れこんだと得意満面に語っていて、健史の肩を小突いたが、彼は相槌を打つだけだった。どうすればペンギンの影絵ができるのか、そのことで頭がいっぱいだったのである。
彼は同僚との会話をてきとうにごまかしながら、自分の手を背中に隠し、ぎこちなく動かし続けていた。
おわり
|
|
|
|
|
|
|
|
4000字の世界 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
4000字の世界のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人