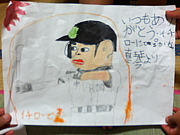小学校の通知表が
「とてもよい」
「よい」
「もう少し」
という3つの欄のいずれかに○印を付ける様になったのはいつころからでしたっけ?
この評価、どういう基準で付けられているのでしょうか?
子どもが昨日学校から持ち帰ってきましたが、前期に比べて4つも評価が落ちてます。
評価方法からして前期と比べられるものではないのかもしれませんが、後期は結構頑張っていたのに、苦手も少しずつ克服出来てるはずなのに、何故?
小学校の通知表は絶対評価になったんじゃなかったでしたっけ?
それとも、児童一人一人に対して、苦手項目をチェックするような評価方法なんでしょうか?(後者なら今回の評価は納得いきましが)
何故?って先生に聞くべき?
けど、学校の先生にそんな事聞いたら、「今時の親は・・・」なんて思われそう。(塾の先生になら聞けるのに。)
大体、算数の図形が苦手と分かってるなら先生! 春休みの宿題は、5年の復習!なんて大雑把なこと言わないで、一人一人に、「教科書のここを!」「ドリルのここを!」と指導して欲しいんですが、そこまで要求してはいけませんか?
「とてもよい」
「よい」
「もう少し」
という3つの欄のいずれかに○印を付ける様になったのはいつころからでしたっけ?
この評価、どういう基準で付けられているのでしょうか?
子どもが昨日学校から持ち帰ってきましたが、前期に比べて4つも評価が落ちてます。
評価方法からして前期と比べられるものではないのかもしれませんが、後期は結構頑張っていたのに、苦手も少しずつ克服出来てるはずなのに、何故?
小学校の通知表は絶対評価になったんじゃなかったでしたっけ?
それとも、児童一人一人に対して、苦手項目をチェックするような評価方法なんでしょうか?(後者なら今回の評価は納得いきましが)
何故?って先生に聞くべき?
けど、学校の先生にそんな事聞いたら、「今時の親は・・・」なんて思われそう。(塾の先生になら聞けるのに。)
大体、算数の図形が苦手と分かってるなら先生! 春休みの宿題は、5年の復習!なんて大雑把なこと言わないで、一人一人に、「教科書のここを!」「ドリルのここを!」と指導して欲しいんですが、そこまで要求してはいけませんか?
|
|
|
|
コメント(6)
あのですねえ・・・小学校教師の立場で書きます。
現在の通知票などの成績は、設定した「評価基準」に到達したかどうかによって評定されます。したがって、特定の主観が入らざるをえない教科や領域(たとえば芸術系の教科など)の以外は、主観を入れようがないようなシステムに変わっています。
「評価基準」は学校によって異なります。
それと、ややこしい話になりますが、「評価規準」と「評価基準」というふたつがありまして、「規準」は「のりじゅん」、「基準」は「もとじゅん」と学校では呼ばれます。
「のりじゅん」は、評価する内容や観点を明らかにしたもの。
「もとじゅん」は、その到達度(評定の「カッティングライン」)を明らかにしたもの。
現在の成績のシステムは、こんなふうになってるんですよ!
かつては、相対評価でしたから、全体の中でどれぐらいのポジションにいてるのかで評定されていましたが・・・。
春休みの復習の観点なんて、どんどん担任に質問したらいいと思います。
それに応えるのは、担任の仕事です!!
現在の通知票などの成績は、設定した「評価基準」に到達したかどうかによって評定されます。したがって、特定の主観が入らざるをえない教科や領域(たとえば芸術系の教科など)の以外は、主観を入れようがないようなシステムに変わっています。
「評価基準」は学校によって異なります。
それと、ややこしい話になりますが、「評価規準」と「評価基準」というふたつがありまして、「規準」は「のりじゅん」、「基準」は「もとじゅん」と学校では呼ばれます。
「のりじゅん」は、評価する内容や観点を明らかにしたもの。
「もとじゅん」は、その到達度(評定の「カッティングライン」)を明らかにしたもの。
現在の成績のシステムは、こんなふうになってるんですよ!
かつては、相対評価でしたから、全体の中でどれぐらいのポジションにいてるのかで評定されていましたが・・・。
春休みの復習の観点なんて、どんどん担任に質問したらいいと思います。
それに応えるのは、担任の仕事です!!
「もとじゅん」の公開は、今、少しずつ進んでいるという状況だと思います。
前にも書いたように学校によって異なるのですが、私の経験からいえば(地域差があるので難しいですが)、ペーパーテストに通常の小テストや授業の様子、提出物などを加味して数値化して、「A」が90%以上、「B」が60%以上というところが多いのではと思います。
「のりじゅん」は、通知票の項目がありますよね。それと学習指導要領に記載されている各教科の「内容」がほぼこれに当たります。
小学校の場合は、通知票の各教科の中にいくつかの観点があるかと思います。現在多くの学校は「観点別」になっていて、言葉はいろいろですが、「興味・関心・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」という4つに分かれていると思います。4つ以上の場合は、保護者に分かりやすくするために、どれかを2つ以上に分けていることになります。
学校によっては、通知票の項目が単元別になっているところもありますが、単元別の通知票では学校に卒業後5年間保存される成績表(「学習指導要録」といいます)との整合性の確保が難しいので、単元別通知票の学校はどんどん減っている状況にあるかと思います。
何が分かりにくくしているかというと、評価基準の公開がまだまだ進んでいない状況にあることと、保護者たちが育ってきた環境が相対評価だったため、絶対評価(到達度評価)がイメージされにくいということの2つがあるのではと思います。
上記を読んでくださったうえで通知票に納得できない状況が起こった場合には、
(1)ペーパーテストや提出物などを確認する。
(2)普段の授業態度を確認する。(家での様子と学校との様子が違うことは普通です。)
(3)担任に質問する。
(4)評価基準の公開を求める。
の順番で進めるべきかなと思います。
特に大事なのは、「(3)担任に質問する」場合に、担任を飛ばして管理職や教育委員会に行かないことです。仮にどんなにたよりない担任であっても、現場の最前線にいてるのは担任なので、管理職や教育委員会では、日常の教室のことをほとんど分かっていないのですから。
制度的な問題や担任の勤務に関する問題などで、まず担任と何度も話して、いくら話してもらちが開かない場合は、管理職へということになりますが・・・。
前にも書いたように学校によって異なるのですが、私の経験からいえば(地域差があるので難しいですが)、ペーパーテストに通常の小テストや授業の様子、提出物などを加味して数値化して、「A」が90%以上、「B」が60%以上というところが多いのではと思います。
「のりじゅん」は、通知票の項目がありますよね。それと学習指導要領に記載されている各教科の「内容」がほぼこれに当たります。
小学校の場合は、通知票の各教科の中にいくつかの観点があるかと思います。現在多くの学校は「観点別」になっていて、言葉はいろいろですが、「興味・関心・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」という4つに分かれていると思います。4つ以上の場合は、保護者に分かりやすくするために、どれかを2つ以上に分けていることになります。
学校によっては、通知票の項目が単元別になっているところもありますが、単元別の通知票では学校に卒業後5年間保存される成績表(「学習指導要録」といいます)との整合性の確保が難しいので、単元別通知票の学校はどんどん減っている状況にあるかと思います。
何が分かりにくくしているかというと、評価基準の公開がまだまだ進んでいない状況にあることと、保護者たちが育ってきた環境が相対評価だったため、絶対評価(到達度評価)がイメージされにくいということの2つがあるのではと思います。
上記を読んでくださったうえで通知票に納得できない状況が起こった場合には、
(1)ペーパーテストや提出物などを確認する。
(2)普段の授業態度を確認する。(家での様子と学校との様子が違うことは普通です。)
(3)担任に質問する。
(4)評価基準の公開を求める。
の順番で進めるべきかなと思います。
特に大事なのは、「(3)担任に質問する」場合に、担任を飛ばして管理職や教育委員会に行かないことです。仮にどんなにたよりない担任であっても、現場の最前線にいてるのは担任なので、管理職や教育委員会では、日常の教室のことをほとんど分かっていないのですから。
制度的な問題や担任の勤務に関する問題などで、まず担任と何度も話して、いくら話してもらちが開かない場合は、管理職へということになりますが・・・。
くまおやじさんへ
> 「A」が90%以上、「B」が60%以上・・・
納得行きました!
そうなら確かにそんなもの(今回の通知表)かもしれません。
どちらかと言えば前期が良く付きすぎてるとも言えそうです。
> 特に大事なのは、「(3)担任に質問する」場合に、担任を飛ばして管理職や教育委員会に行かないことです。仮にどんなにたよりない担任であっても、現場の最前線にいてるのは担任なので、管理職や教育委員会では、日常の教室のことをほとんど分かっていないのですから。
「まずは担任の先生に」、とは良く言われていることなので、大概の親御さんはそうしていると思います。ところが、現場の担任の先生が、教室のことを分かっていないとか、知らない振りをすると言うことが、現実にあります・・・
そんな先生に当ってしまったら・・・最悪です。
幸いうちの子の先生はそうではありませんが。
> 春休みの復習の観点なんて、どんどん担任に質問したらいいと思います。
それに応えるのは、担任の仕事です!!
そうですか。(^^) だったら聞いてみます! うちの先生が、くまおやじさんのような考えの先生でありますようにと祈りつつ。(^^)
BENさんへ
> 不満疑問、今までいろいろ積み重なった結果なのでしょうね。
> 信頼したくても信頼できないと・・・。
> でなければ、学年末にこの疑問は出てこないはずですよね。
私の先生不審は子供の頃からです。
先生が勝手に誤解して、酷いことを言われたもので…
それまでは、将来先生になりたいとも思っていましたが、その時、先生には絶対なりたくない、私には無理と思いました。変わりに私が母親になったら自分の子どもだけはしっかり見つめて理解してあげようと、小学生で思ってました。
> もし、来年もこの先生が担任になられるのでしたら・・・。
それが、持ち上がりではなさそうです。
私が小学生の頃は、クラス替えのない学年は大抵持ち上がりだったのに、最近は違う事が多いのでしょうか?毎年担任の先生は変わっています。
> あたって砕けろで、疑問をぶつけてみてはいかがでしょうか。
> だめかな?と、思ったら、すぐに撤退しましょう(汗
> 深追いは禁物ですよ。
これ、よくよく分かってるんですが、どうも私、撤退=負けのように感じてしまって、途中で引くのが嫌なんですよね…(苦笑) なので、最初からぶつからないようにしていますが。(笑)
やまださんへ
> ボクは、客観性を実感できないなぁ・・・
> もっとよく見てみようかな。
良くご覧になってみました?(^^)
どうでした?
また、主観が入りそうな教科については私も
「先生にはそう見えてるんだな〜」くらいに思って見てます。
> 「A」が90%以上、「B」が60%以上・・・
納得行きました!
そうなら確かにそんなもの(今回の通知表)かもしれません。
どちらかと言えば前期が良く付きすぎてるとも言えそうです。
> 特に大事なのは、「(3)担任に質問する」場合に、担任を飛ばして管理職や教育委員会に行かないことです。仮にどんなにたよりない担任であっても、現場の最前線にいてるのは担任なので、管理職や教育委員会では、日常の教室のことをほとんど分かっていないのですから。
「まずは担任の先生に」、とは良く言われていることなので、大概の親御さんはそうしていると思います。ところが、現場の担任の先生が、教室のことを分かっていないとか、知らない振りをすると言うことが、現実にあります・・・
そんな先生に当ってしまったら・・・最悪です。
幸いうちの子の先生はそうではありませんが。
> 春休みの復習の観点なんて、どんどん担任に質問したらいいと思います。
それに応えるのは、担任の仕事です!!
そうですか。(^^) だったら聞いてみます! うちの先生が、くまおやじさんのような考えの先生でありますようにと祈りつつ。(^^)
BENさんへ
> 不満疑問、今までいろいろ積み重なった結果なのでしょうね。
> 信頼したくても信頼できないと・・・。
> でなければ、学年末にこの疑問は出てこないはずですよね。
私の先生不審は子供の頃からです。
先生が勝手に誤解して、酷いことを言われたもので…
それまでは、将来先生になりたいとも思っていましたが、その時、先生には絶対なりたくない、私には無理と思いました。変わりに私が母親になったら自分の子どもだけはしっかり見つめて理解してあげようと、小学生で思ってました。
> もし、来年もこの先生が担任になられるのでしたら・・・。
それが、持ち上がりではなさそうです。
私が小学生の頃は、クラス替えのない学年は大抵持ち上がりだったのに、最近は違う事が多いのでしょうか?毎年担任の先生は変わっています。
> あたって砕けろで、疑問をぶつけてみてはいかがでしょうか。
> だめかな?と、思ったら、すぐに撤退しましょう(汗
> 深追いは禁物ですよ。
これ、よくよく分かってるんですが、どうも私、撤退=負けのように感じてしまって、途中で引くのが嫌なんですよね…(苦笑) なので、最初からぶつからないようにしていますが。(笑)
やまださんへ
> ボクは、客観性を実感できないなぁ・・・
> もっとよく見てみようかな。
良くご覧になってみました?(^^)
どうでした?
また、主観が入りそうな教科については私も
「先生にはそう見えてるんだな〜」くらいに思って見てます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
生徒・保護者・先生をつなぐ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
生徒・保護者・先生をつなぐのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人