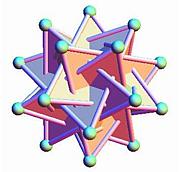|
|
|
|
コメント(22)
公式?
数学の面白さ、存在意義は、このように一般化していろんなことに応用していくというところにあります
物理法則を数式で表せば、物体の運動に関して、未来のことが計算予測できます
sinπ=0やcosπ=−1は三角関数の定義そのものです
本来これは公式として暗記するものではありません
三角関数という概念を理解していれば覚える必要などありません
ところで13や14を表せない特殊な方法があったとしても、それは数学として一般化されていない特殊解法みたいなものですね
特殊解法が無意味ではありません
一般化された明快なものがあれば特殊解法を丸覚えしなくていいのです
いわばそれが数学です
数学の面白さ、存在意義は、このように一般化していろんなことに応用していくというところにあります
物理法則を数式で表せば、物体の運動に関して、未来のことが計算予測できます
sinπ=0やcosπ=−1は三角関数の定義そのものです
本来これは公式として暗記するものではありません
三角関数という概念を理解していれば覚える必要などありません
ところで13や14を表せない特殊な方法があったとしても、それは数学として一般化されていない特殊解法みたいなものですね
特殊解法が無意味ではありません
一般化された明快なものがあれば特殊解法を丸覚えしなくていいのです
いわばそれが数学です
元来は、どれかの数字を、指定された個数だけしか使わずに、
できるだけ簡単な数式で様々な整数を表そうというパズルです。
歴史的には、4個の4だけで、0から1000まで表そうという、
ボール(人名)の出題が有名(1881年)。
これが、西暦年数の数字でやろうという「数楽オリンピック」(1948年)などに発展していきます。
1を1個というのは、究極的に個数を減らしたわけですが、
こうなると、簡単な記号では、なかなか限界があります。
バズリスト高木茂男氏の提案(1985年)では、
階乗や総和(Σn=1+2+3+……n)までを認めることになっていますが、
この程度ではまだ無理なので、ガウスの記号や、三角関数、二重階乗、等を使うことにしました。
出題者自身の解答例です。
0=log1
1=1
2=[√√cot1°]
3=Σ[√√cot1°]
4=[√√cot .1°]
5=[√√(ΣΣ[√√cot1°])]
6=Σ[√√cot1°]!
7=[√cot1°]
8=[√(ΣΣΣ[√√cot1°])]!!
9=[cot(ΣΣ[√√cot1°])°]
10=Σ[√√cot .1°]
11=[√√√(ΣΣΣΣΣΣ[√√cot1°])]
12=[√√(ΣΣΣΣΣ[√√cot1°])]
13=?
14=?
15=Σ[√√(ΣΣ[√√cot1°])]
ここでは、cot1°=57.28996……
を利用して、唯一の「1」に、大きな数を作る役目をになってもらっています。
「e」や「π」の利用も考えましたが、これはすでにひとつの数であるところから、
記号とはいえ、使わずにすませようと考えた次第です。
できるだけ簡単な数式で様々な整数を表そうというパズルです。
歴史的には、4個の4だけで、0から1000まで表そうという、
ボール(人名)の出題が有名(1881年)。
これが、西暦年数の数字でやろうという「数楽オリンピック」(1948年)などに発展していきます。
1を1個というのは、究極的に個数を減らしたわけですが、
こうなると、簡単な記号では、なかなか限界があります。
バズリスト高木茂男氏の提案(1985年)では、
階乗や総和(Σn=1+2+3+……n)までを認めることになっていますが、
この程度ではまだ無理なので、ガウスの記号や、三角関数、二重階乗、等を使うことにしました。
出題者自身の解答例です。
0=log1
1=1
2=[√√cot1°]
3=Σ[√√cot1°]
4=[√√cot .1°]
5=[√√(ΣΣ[√√cot1°])]
6=Σ[√√cot1°]!
7=[√cot1°]
8=[√(ΣΣΣ[√√cot1°])]!!
9=[cot(ΣΣ[√√cot1°])°]
10=Σ[√√cot .1°]
11=[√√√(ΣΣΣΣΣΣ[√√cot1°])]
12=[√√(ΣΣΣΣΣ[√√cot1°])]
13=?
14=?
15=Σ[√√(ΣΣ[√√cot1°])]
ここでは、cot1°=57.28996……
を利用して、唯一の「1」に、大きな数を作る役目をになってもらっています。
「e」や「π」の利用も考えましたが、これはすでにひとつの数であるところから、
記号とはいえ、使わずにすませようと考えた次第です。
ww
記号は自由てw
おこちゃま設定でなんでも解決して、そんなことになんの意味があるのか
ここ大人のコミュでしょ?
違うのかな
クイズというのは、だれにでも明確なきびしい制約の中で、優れたアイデアで解決するところに面白さがあるのです
マイルールで奇妙な設定を取り入れて、奇抜な記号を自由に使って解決なんてクイズでもなんでもない
おこちゃまの寝言です
くだらない
ある特定の数を記号で表すことに問題があると思うなら、eやπを数字で表してごらんなさい
そうするとこれらの数が記号である必然性が理解できることでしょう
.1
そんなこと言っておきながら、なにこれw こういう記号まで自由に使ってたらなんでもできるわw
以下、同類のことだが
>階乗や総和(Σn=1+2+3+……n)までを認めることになっていますが、 この程度ではまだ無理なので、ガウスの記号や、三角関数、二重階乗、等を使うことにしました。
ガウスの記号は、n-1以上n未満を全部nにしてしまおう、という人為的設定です
その間の実数はなんでもかんでもnでしかないっていうことですよ
使い方次第では数学的に利用価値がないわけでもありませんが
このクイズのようなことに使うために数学ではガウスの記号を取り入れるわけではありませんよ
Σnや階乗も、強いて言えば、1からnまでの自然数の総和や総乗をただ簡略化しただけの記号であり、実際は1からnまでの数字が計算されるということですから
数字を使って計算してるのよ
簡略記号なんだからね
.1がなにを意味するかしらないが、0.111111・・・のことなら、この数を記述しただけでしかない
それを簡略化したというマイルールのおこちゃま設定です
クイズというなら、ひろいお外で通用する客観性や一般性がないとどうしようもないのです
特殊な設定が前提されるなら、せめてそれを共有した状態で、奇抜なアイデアで解決されるべきことです
それがクイズというもの
ルールや設定があいまいならクイズなど成立していないし、そんなものをクイズなどとは言わないのです
奇抜なおこちゃま設定をのぞいたら、この回答のどこにクイズとしての面白さや価値があるというのかね
くだらないんだよ
まあ、自由ですけどね(笑
記号は自由てw
おこちゃま設定でなんでも解決して、そんなことになんの意味があるのか
ここ大人のコミュでしょ?
違うのかな
クイズというのは、だれにでも明確なきびしい制約の中で、優れたアイデアで解決するところに面白さがあるのです
マイルールで奇妙な設定を取り入れて、奇抜な記号を自由に使って解決なんてクイズでもなんでもない
おこちゃまの寝言です
くだらない
ある特定の数を記号で表すことに問題があると思うなら、eやπを数字で表してごらんなさい
そうするとこれらの数が記号である必然性が理解できることでしょう
.1
そんなこと言っておきながら、なにこれw こういう記号まで自由に使ってたらなんでもできるわw
以下、同類のことだが
>階乗や総和(Σn=1+2+3+……n)までを認めることになっていますが、 この程度ではまだ無理なので、ガウスの記号や、三角関数、二重階乗、等を使うことにしました。
ガウスの記号は、n-1以上n未満を全部nにしてしまおう、という人為的設定です
その間の実数はなんでもかんでもnでしかないっていうことですよ
使い方次第では数学的に利用価値がないわけでもありませんが
このクイズのようなことに使うために数学ではガウスの記号を取り入れるわけではありませんよ
Σnや階乗も、強いて言えば、1からnまでの自然数の総和や総乗をただ簡略化しただけの記号であり、実際は1からnまでの数字が計算されるということですから
数字を使って計算してるのよ
簡略記号なんだからね
.1がなにを意味するかしらないが、0.111111・・・のことなら、この数を記述しただけでしかない
それを簡略化したというマイルールのおこちゃま設定です
クイズというなら、ひろいお外で通用する客観性や一般性がないとどうしようもないのです
特殊な設定が前提されるなら、せめてそれを共有した状態で、奇抜なアイデアで解決されるべきことです
それがクイズというもの
ルールや設定があいまいならクイズなど成立していないし、そんなものをクイズなどとは言わないのです
奇抜なおこちゃま設定をのぞいたら、この回答のどこにクイズとしての面白さや価値があるというのかね
くだらないんだよ
まあ、自由ですけどね(笑
詳細については、高木茂男「パズル百科」(1985・講談社文庫)が参考になります。
「数芸」にかかわる歴史や具体例、記号による作例の等級などについて書かれています。
こちらの方が古い本ですが、
平山諦「東西数学物語」(1956)が、現在も1973年の増補新版で新刊があります。
元々、数作りのパズルでは、四則計算だけでやってみようというところから出発して、
それではたちまち詰まってしまうので、√などを取り入れて、拡張してきました。
しかし、初歩的な記号だけで書かれた式の方が優秀であるという原則は変わりません。
「数楽オリンピック」を考案した、境新(1908-64)の場合、
記号について、やはり「これはどうか?」という疑問のあるものがあり、
没後にルールとしてこれはやめよう、という記号を整理したのが高木氏というわけです。
2乗を表すのに、「V」と書いたり、総和を表すのに、○で囲む、階乗を「L」(古い記号)、
とするなどが改正されました。
小数点については、0.1=.1とすることには、違和感があります。
ただし実用例としては、数表に散見されますので、パズルに採用されているのだと思います。
循環小数は、もちろん1の上に点を書く形が正当です。
「数芸」にかかわる歴史や具体例、記号による作例の等級などについて書かれています。
こちらの方が古い本ですが、
平山諦「東西数学物語」(1956)が、現在も1973年の増補新版で新刊があります。
元々、数作りのパズルでは、四則計算だけでやってみようというところから出発して、
それではたちまち詰まってしまうので、√などを取り入れて、拡張してきました。
しかし、初歩的な記号だけで書かれた式の方が優秀であるという原則は変わりません。
「数楽オリンピック」を考案した、境新(1908-64)の場合、
記号について、やはり「これはどうか?」という疑問のあるものがあり、
没後にルールとしてこれはやめよう、という記号を整理したのが高木氏というわけです。
2乗を表すのに、「V」と書いたり、総和を表すのに、○で囲む、階乗を「L」(古い記号)、
とするなどが改正されました。
小数点については、0.1=.1とすることには、違和感があります。
ただし実用例としては、数表に散見されますので、パズルに採用されているのだと思います。
循環小数は、もちろん1の上に点を書く形が正当です。
まあ、これで、どうして汎用できる方法が出た段階で、
自作例を引っ込めようとしたかがご理解いただけると思います。
こういう数作りのパズルは、個々の例をどう作っていくかがおもしろいので、
何にでもできる方法ができてしまうと、おもしろさは消えるんです。
「4つの4」に対して、ディラックがどんな整数にでもあてはまる式を考案したとき、
未知の部分に対する興味はほとんど失われ、パズルを知らない人への出題になってしまいました。
以後は、どれだけディラックに依存しないで、式を作れるか、に興味が移ったと思います。
記号を節約したいとは思うものの、どれだけそれは可能なのか、
パズルの趣旨を尊重しながらどこまで拡張してもよいか。
興味は尽きません。
自作例を引っ込めようとしたかがご理解いただけると思います。
こういう数作りのパズルは、個々の例をどう作っていくかがおもしろいので、
何にでもできる方法ができてしまうと、おもしろさは消えるんです。
「4つの4」に対して、ディラックがどんな整数にでもあてはまる式を考案したとき、
未知の部分に対する興味はほとんど失われ、パズルを知らない人への出題になってしまいました。
以後は、どれだけディラックに依存しないで、式を作れるか、に興味が移ったと思います。
記号を節約したいとは思うものの、どれだけそれは可能なのか、
パズルの趣旨を尊重しながらどこまで拡張してもよいか。
興味は尽きません。
>>[20]
数学の決まり事として無理数や超越数を表す記号は定数(数学定数)と言います
しかし、定数といっても無理数や超越数は整数みたいに数値を完全に書くことも計算することもできません
日常言語として定まった数(定数)というにはわたしは語弊があるように思います
無理数や超越数は数値で表す場合はおおよその値しか書けないという特殊な性質の数です
つまり、整数とは違って記号で書くことに妥当性がある数
そのことを短く伝えようとして、定数(定まった数)ではないと表現したコメントです
その直後の文章でも言わんとすることの意味を補填してます
コメントは前後をみないと部分的に切り取ってみたらおかしい文章でも
前後をみたら意味がわかることなんていくらでもありますよ
数学の決まり事として無理数や超越数を表す記号は定数(数学定数)と言います
しかし、定数といっても無理数や超越数は整数みたいに数値を完全に書くことも計算することもできません
日常言語として定まった数(定数)というにはわたしは語弊があるように思います
無理数や超越数は数値で表す場合はおおよその値しか書けないという特殊な性質の数です
つまり、整数とは違って記号で書くことに妥当性がある数
そのことを短く伝えようとして、定数(定まった数)ではないと表現したコメントです
その直後の文章でも言わんとすることの意味を補填してます
コメントは前後をみないと部分的に切り取ってみたらおかしい文章でも
前後をみたら意味がわかることなんていくらでもありますよ
数学遊戯ですからね。
数学の諸記号は、もちろん遊戯のために作られたものではないし、
もっとシリアスな用途のためのものであることは承知しています。
それを使って、遊びのために転用してみようというわけ。
数学にはこんな記号も使われるんだ、ということを知っていくのも楽しいものです。
本職の数学者に言わせれば、そりゃ噴飯ものでしょうね。
何も、数字や記号に無理に設定や制限をもうけて表現して、
それが何の役に立つのか、と言われたら、役には立たないでしょう。
日本人は数学が嫌いだ、と言いながら、実は数学が好きだし、数学で遊んでもいる。
和算の数学遊戯で親しみながら、
江戸時代の日本は、当時としては非常に高い水準の数学を発展させました。
そんなふうに、遊戯と学問が、どこかで根っこでつながって行けたらいいな、と思います。
子どもだったら、こういうのが大好きですね。あと、子どもの心をもつオトナとか。
本来とはちがう用途であっても、数学のおもしろさに興味を持てれば、
それが教育的効果として、どこかで何らかの役に立つかもしれません。
「おこちゃま」なんて言われましたが、むしろ、その志向を的確に指摘していただけたのだと思っています。
今ちょうど、「サイン・コサイン」について、ずいぶんと騒がしいところですが、
政治家にあのような発言をされないためにも、
数学の効用をもっと世の中に広く知ってもらえればと思います。
数学の諸記号は、もちろん遊戯のために作られたものではないし、
もっとシリアスな用途のためのものであることは承知しています。
それを使って、遊びのために転用してみようというわけ。
数学にはこんな記号も使われるんだ、ということを知っていくのも楽しいものです。
本職の数学者に言わせれば、そりゃ噴飯ものでしょうね。
何も、数字や記号に無理に設定や制限をもうけて表現して、
それが何の役に立つのか、と言われたら、役には立たないでしょう。
日本人は数学が嫌いだ、と言いながら、実は数学が好きだし、数学で遊んでもいる。
和算の数学遊戯で親しみながら、
江戸時代の日本は、当時としては非常に高い水準の数学を発展させました。
そんなふうに、遊戯と学問が、どこかで根っこでつながって行けたらいいな、と思います。
子どもだったら、こういうのが大好きですね。あと、子どもの心をもつオトナとか。
本来とはちがう用途であっても、数学のおもしろさに興味を持てれば、
それが教育的効果として、どこかで何らかの役に立つかもしれません。
「おこちゃま」なんて言われましたが、むしろ、その志向を的確に指摘していただけたのだと思っています。
今ちょうど、「サイン・コサイン」について、ずいぶんと騒がしいところですが、
政治家にあのような発言をされないためにも、
数学の効用をもっと世の中に広く知ってもらえればと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
数学の面白い問題や話 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
数学の面白い問題や話のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75482人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6444人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208287人