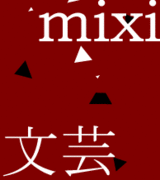水村美苗 著 母の遺産、 新聞小説
中央公論社 刊 2012年初版、2012年八刷
ISBN978-4-12-004375-5-C0093
昨年か一昨年日本に帰省した折に求めたものだ。 水村の著作には親しんでいる。
水村の経歴にについてはウィキペディアの記述に譲る
https:/
自分は30になってからヨーロッパに渡った者ではあるけれど彼女は12歳の時に渡米して以来の当時のいわゆる帰国子女でその後日米欧文学に親しみ主要大学で近代日本文学を専門に講じてきた経歴をもち著述に身を置く作家である。 90年代の初頭、漱石の未完の小説を文体をそのままに続けようとして現した「続明暗」で文壇に登場したらしいのだが自分との接点はその次の横書き文庫版の「私小説」だった。 海外に身を置き少なくとも当時日本の主要な文芸雑誌に毎月眼を通していた自分にとっては文学で横書きと言うことには違和感を得たもののその内容には甚だ興味を覚えた記憶がある。 その後、ブロンテにインスピレーションを得た「本格小説」には十分楽しませて貰うともに自分の近くに当時日本の生え抜きエリート外交官が住んでいたものだから彼にそれを見せて貸すと彼の夫人があとで、これはまるで私たちの世界だったじゃないのというコメントを寄せられてなるほど、こういうことも実際にあったのか、という感慨に捉えられたものだ。 尚その外交官の家系については戦前戦中戦後と彼の運命も含めて波乱万丈だったのだが小説に限ると夫人の方が専らに興味深かったと記憶する。 彼の部下がスキャンダルに連座して収監されその間に体力・知力を磨き退職を余儀なくさせられた後の文筆活動には目を見張るものがある。 ここでは政治の馬鹿さ加減が国益に貢献する有能な外交官たちをはじき飛ばし、あとには面白くもなんともない凡庸な外交官たちをハーグに送ってきた25年ほどを見てきた中でその外交官だけが原稿もなく自由闊達に話し、そこにいるだれもを虜にする稀有な人材であったことはひとえにただの外交官試験をうけただけでなった人間ではなく何代にも亘って外交の世界を自分のものとしてきた家系、血がそうさせたもので、だから国益のために田中真紀子外務大臣へのレクチャーで土建屋の娘にそんな性格が嫌われたのではないかという憶測も湧く所以もそこにある。
『日本語が亡びるとき』ではその趣旨には海外に長く生活していて自分の言葉の意味を考えさせられ戦後の言葉の変遷、オーディオ・ヴィシュアル時代における言葉の分析等にはそこに身を置いて分析研究してきた単なる言語学に収まらない逆に言えば日本社会に警鐘を鳴らす役目を意識した作だと感じた。 だから後、彼女に対する批判の主なものが世界に視座を置く論者でもなくただ単に井の中の蛙でしかないことにため息をつかずにはいられなかった。 外に出てそこに身を置かねば分からぬ、感じられないことがいくつかあるのだ。 種類は違ってもそれは例えば、感覚・刺激を基として作業を続けている赤坂真理著「東京プリズン」にも通底する部分がある。 尚、「日本語が亡びるとき」についてはネットで彼女を大国主義者と断じた次の興味深い評論も見られる。
http://
本作に於いては「本格小説」に次いでの「新聞小説」であるからその表現媒体にも十分考慮し、時代、歴史、われらが住む現在につなげる結構にして尚且つロマンでもなければならず、ロマンという保守的な「本格小説」の流れにして現在に繋がる部分に重点を置く考慮がなされなければ戦後70年、誰が好き好んで今の新聞小説で明治以来の文学の系譜を読むだろうか。 そこに目の前の餌、として伏線化させたのが、「あたみーのかいがんさんぽすーる、かんいーちおみやーのふたりーずーれー」だったのだ。 このテーマは人類普遍の要素を含んでおり現代、ポスト何乗目かのモダニズム時代にも当然形を変えピチピチと生き続けているものであるから読売新聞の読者を40歳以上が主体だと想定すれば今の世の中にも明治から続く家族のサーガとしては甚だ興味深いものであり、とりわけ賢かったのは524頁あるなかで200頁あたりから今の社会に溢れる現象対策に移っていることだ。
西欧といっても各国にデコボコがあるものの概ね公共にゆだねようとしてきた70年代からの社会福祉、とりわけ今顕在している老人医療に眼点を起きそれがこの経済不況下でまたもやリヴィジョニストたちの跋扈によって緊縮財政にあえぐヨーロッパではあるが、日本に置いては私が身をもって経験もしてきた福祉インフラを作って来なかった日本の中に身を置く女性の視点には読者の半分以上が女性だっただろうということまでも思いが行き読者たちが自分、自分の周りにあることとして読んでいる姿が思いやられる。 つまり、明治以来の世界でどのように女が自分というものを威厳をもって生き延びられるかという軌跡を家族の紆余曲折を交えて小説の形で現したことが本格小説ということなのだろう。
帯にある「親の介護、夫婦の危機、忍び寄る更年期、老後資金の計算、、、、」という惹句で20代の女性に冷や水を浴びせるとともに若い世代の若い「愛」の諸相を経験したものとしてそこに提示する手法は女のものだなあ、と感心した。 男がこういう小説を書いたとするとどのようなものになるのだろうかとおもうと思わず苦笑が漏れるようでもあり、日本で屈指の経済学者(思想家)である水村のパートナーの一定の距離を置いた意見も反映されているものとみてここでのこと細かい計算は傾聴に値する。 そこには「細雪」の牧岡家を念頭に置いていることは確かで谷崎と言う男性作家が描く女系家族とは趣の変わった女性作家の手になるものであり男の読者である自分が感じたのは本作の男たちはある意味マッチョで豪放か優しく彼女らに幾何かの距離をもって接するように多少の両極化を感じるのは主人公が切って捨てる男の性格を自分が持っているのだろうかと自問するとき、ああ、これはある種お嬢様の視点なのだとも納得し、それがロマンなのだとも自分とは違う世界を垣間見させてもらったことに想いが行く。 少年の時に垣間見た少女漫画雑誌の目に星、周りに鳥が飛び交う世界は全く縁のなかった男にはある種、棄てられた男に同情心を持たなくもないし、そのようにして海外に出て勉学に励む若い男女の学者を何人も見てきたのだが年齢が違うのと入れ替わり立ち代わり2,3年で通り過ぎていくので彼らの内部までは知己を得る機会は少なかったものの、外交官として勉強している者の中には外交官試験に通って派遣されてきたものの乏しい海外経験をもとにして中小出版社からガイドブックを出しさっさと辞めていった女性外交官の卵、自分はアートを極めたかったのに面白くないからと当時まだ町田町蔵と名乗りその後芥川賞を取った町田康のパンク・ロックと詩に傾倒し辞めていった男のことなども思い出す。 あとで大使館員からあなたと話すと辞めていく若いのがいるから困ると苦情を言われたことも思い出し、つまり彼らにとっては大志をもって国益に値する活動に身を投じる気概があってもこの時代の組織がそんな若者の士気を削がせるものとなっているということなのだろうと受け取った。 そんな若者には切羽詰まって目の前しか見えないのかとも思うもののいつの世も我々は目の前の世界のことに追われて走り回っているのだ。 ロマンに水を差すのが巷に言われる「金の切れ目が縁の切れ目」ということで本作に出てくる金勘定の数字をみて、ああ、やはりこれはロマンなのだと年金生活者は嘆息する。
表紙の題字、遺産の「産」に添えられたダイヤの指輪のことで思い出すことが二つある。 一つは子どもの頃に親しんだ中田ダイマル・ラケットかの漫才で間貫一がお宮にいうセリフだ。 「高利貸し、とみやまのダイヤモンドに眼がくらみ、、、、」というところを「ダイナマイトに眼がくらみ、、、」で大笑いするのだがそれもあながち違ったものでもないように思うことだ。 明治開国以来その意味を求め続けている「愛」をダイヤモンドがダイナマイト級に破壊するかどうかという命題なのだ。 皆が口にするものの日本語では曖昧模糊とした「愛」をどのように破壊できるのだろうか。
もう一つこのダイヤモンドについて本作にも関連して思い出すのは60年代アメリカの女優・歌手ジュリー・ロンドン歌う「Diamonds Are a Girl's Best Friend」だ。 ネットで見つけたその訳を下に牽く。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
DIAMONDS ARE A GIRL'S BEST FRIEND
[ヴァース1]
フランス人は愛のために死ぬと言うわね、
彼らは喜んで決闘に臨むの、
でも私は生きている男の方がいいわ、
高価な宝石をくれるから。
[リフレイン1]
手の甲に口づけするなんて
極めてヨーロッパ風ね、
でもダイアモンドが女の子の最良の友よ。
口づけは素晴らしいことかもしれない、
でもそれじゃ家賃は払えないのね
あんたのつつましいアパートの。
それに簡易食堂の料金さえも、(★)
男はいずれ冷たくなるわ
女の子が年をとるとともに
最後には魅力も失せるのよ。
でもスクエアカットやペアシェイプ (pear-shape)、
これらの石は姿が衰えることはないの、
ダイアモンドが女の子の最良の友よ。
(ティファニー!
カルティエ!
ブラック・スター!
フロスト・ゴーラム!
ハリー・ウィンストンのことを話して、
全部教えて!)
[ヴァース2]
お行儀のよいランデヴーは
少女の心臓の鼓動を速める、
でもランデヴーが終わった時でも、
これらの石は輝きを保っているわ。
[リフレイン2]
いつか若い娘にも
弁護士が必要な時が来るかも、
そんな時はダイアモンドが女の子の最良の友よ。
いつかこんなことが起きるかも
冷徹な雇い主が
あなたをナイスと思う時が、
でもアイス(ice=宝石)は取らなきゃ目が出ないわよ(no dice)。
彼はあなたの男
株価が高い間はね、
でも下がり始めたら気を付けるのよ。
そうなったらあの嫌らしい奴らは
配偶者の元に帰ってしまうの、
ダイアモンドが女の子の最良の友よ。
[リフレイン3(映画ヴァージョン)]
恋の話も聞くけど
完全なプラトニックな恋のことを
そうなってもダイアモンドが女の子の最良の友よ。
それで私が思うに
関係性を続けなきゃいけない恋なら
それはそれで賢い賭けよね
可愛い娘ちゃんが太いフランスパンになるようなら。
時はたつもの、
それにつれて若さもなくなるわ、
そしたら腰が曲がってまっすぐにならなくなるわ。
でも硬くなった背中や
しなやかさを失った膝でも、
ティファニーの前ではしゃきっとするわよ。
ダイアモンドが! ダイアモンドが!
私の言うのは模造ダイヤじゃないのよ!
ダイアモンドが女の子の最良の友よ。
※: 歌詞ソースはReading Lyricsを参考にした。映画では、ヴァース2は歌われていない。3番の歌詞は映画だけのものらしく、インターネットを参考にした。
★ Automat:自動販売式のカフェテリア(小銭を入れて小さなガラス窓の裏の食べ物を取るような方式の食堂。1930年代に流行した装置で、昔のアメリカ映画などで時々見られる風景。
作詞: レオ・ロビン Leo Robin
作曲: ジューリー・スタイン Jule Styne
出典: 舞台ミュージカル Gentlemen Prefer Blondes (1949) でキャロル・チャニング (Carol Channing) が歌った。
映画版 「紳士は金髪がお好き」(1953) では、マリリン・モンローが歌った。(この映画は、著作権更新手続きが行われず、パブリック・ドメイン扱いになっているらしく、ミス・モンローの映像がYouTubeで見ることが出来る)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上である。
西欧文化に精通している著者にはキーボードに向かうBGMとしてこの歌を流し、「あたみーのーかいがんさんぽーするー貫一お宮のふたりずーれ」に関連したロマンの整合性を探る縁としていたのかどうか自分には知る由もない。
|
|
|
|
|
|
|
|
mixi文芸 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-