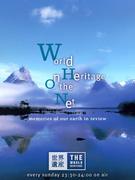日本には、文化遺産11件と自然遺産3件があります。
日本の世界遺産の多くが「木の文化」であるにも関わらず、千年の命を保ってきた秘密は何なのでしょうか。地震による倒壊例は歴史上ないという五重塔、豪雪地帯の白川郷の合掌造りなど等、先人たちが自然と向きあうなかで育んできた技術と知恵は素晴らしいものばかりです。
また、樹齢千年をこえる屋久杉が林立する「屋久島」、天然のブナの覆われる「白神山地」、素晴らしい生態系が残る「知床」には、豊かな自然とその貴重な歴史が刻み込まれています。
皆さんは、
△どこを訪ねましたか?
△どこが好きですか?
△どのようなロマンを感じましたか?
日本の世界遺産! かけがえのない日本人の遺産について語り合いましょう!
○私が好きな世界遺産は、紀伊山地の中の「高野山」です。(詳細はコメント欄に記載)
日本の世界遺産の多くが「木の文化」であるにも関わらず、千年の命を保ってきた秘密は何なのでしょうか。地震による倒壊例は歴史上ないという五重塔、豪雪地帯の白川郷の合掌造りなど等、先人たちが自然と向きあうなかで育んできた技術と知恵は素晴らしいものばかりです。
また、樹齢千年をこえる屋久杉が林立する「屋久島」、天然のブナの覆われる「白神山地」、素晴らしい生態系が残る「知床」には、豊かな自然とその貴重な歴史が刻み込まれています。
皆さんは、
△どこを訪ねましたか?
△どこが好きですか?
△どのようなロマンを感じましたか?
日本の世界遺産! かけがえのない日本人の遺産について語り合いましょう!
○私が好きな世界遺産は、紀伊山地の中の「高野山」です。(詳細はコメント欄に記載)
|
|
|
|
コメント(840)
(ニュース)〜「部材ひとつひとつに価値がある」世界遺産・厳島神社の五重塔 25年ぶりの保存・修復工事を公開 広島・宮島
(RCC中国放送・3/6 一部転載)
世界遺産の宮島・厳島神社で、五重塔の保存・修復工事が行われています。
工事用の足場とネットで覆われているのは、厳島神社の五重塔です。高さおよそ29メートル。室町時代の1407年に建立されたもので、国の重要文化財に指定されています。
2000年の台風によって屋根の檜皮ぶきが破損しましたが、これまで鉄板による応急処置を行っていました。先月から始まった25年ぶりの保存・修復工事では、屋根の檜皮ぶきを全面的にふき替えたり、壁の朱塗りを上塗りしたりする予定です。
工事費は、2億5千万円で厳島神社では2027年10月に工事を終えたいとしています。
(RCC中国放送・3/6 一部転載)
世界遺産の宮島・厳島神社で、五重塔の保存・修復工事が行われています。
工事用の足場とネットで覆われているのは、厳島神社の五重塔です。高さおよそ29メートル。室町時代の1407年に建立されたもので、国の重要文化財に指定されています。
2000年の台風によって屋根の檜皮ぶきが破損しましたが、これまで鉄板による応急処置を行っていました。先月から始まった25年ぶりの保存・修復工事では、屋根の檜皮ぶきを全面的にふき替えたり、壁の朱塗りを上塗りしたりする予定です。
工事費は、2億5千万円で厳島神社では2027年10月に工事を終えたいとしています。
「ポータブル世界遺産センター 世界遺産 古都奈良の文化財 旅するパネル展」2025年5月18日まで開催
(PR TIMES・3/11 一部転載)
平城宮いざない館では、企画展「ポータブル世界遺産センター 世界遺産 古都奈良の文化財 旅するパネル展」(会期2025年3月8日〜2025年5月18日)を開催しています。
東大寺、興福寺、春日大社、春日山原始林、元興寺、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡の8つからなる世界遺産「古都奈良の文化財」。
1998年に世界遺産に登録され、2028年には登録から30周年を迎えます。本展では、各資産の魅力や価値、さらにゆかりのある人物について写真とイラスト、文章で紹介しております。本展を通じて、奈良の歴史と文化の奥深さを知り、奈良の文化財の価値を感じていただければと考えております。
(PR TIMES・3/11 一部転載)
平城宮いざない館では、企画展「ポータブル世界遺産センター 世界遺産 古都奈良の文化財 旅するパネル展」(会期2025年3月8日〜2025年5月18日)を開催しています。
東大寺、興福寺、春日大社、春日山原始林、元興寺、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡の8つからなる世界遺産「古都奈良の文化財」。
1998年に世界遺産に登録され、2028年には登録から30周年を迎えます。本展では、各資産の魅力や価値、さらにゆかりのある人物について写真とイラスト、文章で紹介しております。本展を通じて、奈良の歴史と文化の奥深さを知り、奈良の文化財の価値を感じていただければと考えております。
日本人が知っている日本の世界遺産のトップは「原爆ドーム」―クロスマーケティング調査 : 年代上がるほど高い認知度・訪問経験
(Japan Data・3/22 一部転載)
○きっとテレビや新聞、ウェブサイトで何度となく見たことがある原爆ドーム。実際にその場を訪れてみると、画面を通してみるのとは全く違う何かが伝わってくる。日本人が最もよく知っている日本の世界遺産は、決して忘れてはいけない世界遺産でもある。
○日本には文化遺産21件、自然遺産5件の計26件の世界遺産が登録されている。
マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティング(東京都新宿区)が、全国の20歳〜69歳を対象に「日本に世界遺産がいくつあると思うか」聞いたところ、「26」と正しく答えることができたのはわずか2.8%。実際より少ない「25」以下の数字を回答した人が63.7%に上り、「0」と回答した人も2.6%いた。
世界遺産であることを知っているのは「原爆ドーム」61.6%がトップ。「厳島神社」54.1%、「屋久島」53.8%、「富岡製糸場と絹産業遺産群」53.6%が5割を超えた。
ちなみに、最も最近の2024年7月に登録が決定した「佐渡島の金山」が世界遺産であることを知っていたのは38.5%にとどまった。26件中、最も知っている割合が低かったのは「国立西洋美術館(ル・コルビュジエの建築作品)」11.2%だった。
全体的に年代が上がるほど、世界遺産であることを知っている割合も高くなる。
○行ったことがある世界遺産も「原爆ドーム」36.7%がトップ。「厳島神社」「古都京都の文化財」「法隆寺地域の仏教建造物」「日光の社寺」「古都奈良の文化財」「姫路城」が2割台で続いた。訪問経験も年代が上がるほど高い傾向だった。
○調査は3月中旬にウェブ経由で実施。20代から60代まで各220人ずつからの有効回答を集計した。
(Japan Data・3/22 一部転載)
○きっとテレビや新聞、ウェブサイトで何度となく見たことがある原爆ドーム。実際にその場を訪れてみると、画面を通してみるのとは全く違う何かが伝わってくる。日本人が最もよく知っている日本の世界遺産は、決して忘れてはいけない世界遺産でもある。
○日本には文化遺産21件、自然遺産5件の計26件の世界遺産が登録されている。
マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティング(東京都新宿区)が、全国の20歳〜69歳を対象に「日本に世界遺産がいくつあると思うか」聞いたところ、「26」と正しく答えることができたのはわずか2.8%。実際より少ない「25」以下の数字を回答した人が63.7%に上り、「0」と回答した人も2.6%いた。
世界遺産であることを知っているのは「原爆ドーム」61.6%がトップ。「厳島神社」54.1%、「屋久島」53.8%、「富岡製糸場と絹産業遺産群」53.6%が5割を超えた。
ちなみに、最も最近の2024年7月に登録が決定した「佐渡島の金山」が世界遺産であることを知っていたのは38.5%にとどまった。26件中、最も知っている割合が低かったのは「国立西洋美術館(ル・コルビュジエの建築作品)」11.2%だった。
全体的に年代が上がるほど、世界遺産であることを知っている割合も高くなる。
○行ったことがある世界遺産も「原爆ドーム」36.7%がトップ。「厳島神社」「古都京都の文化財」「法隆寺地域の仏教建造物」「日光の社寺」「古都奈良の文化財」「姫路城」が2割台で続いた。訪問経験も年代が上がるほど高い傾向だった。
○調査は3月中旬にウェブ経由で実施。20代から60代まで各220人ずつからの有効回答を集計した。
世界遺産の福岡県宗像市「沖ノ島」題材、8年がかりで写真集「神坐す」出版
(西日本新聞・4/13 一部転載)
世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群を構成する福岡県宗像市の離島、沖ノ島の写真集「神坐(かみいま)す」(小学館)が出版された。
撮影したのは写真家の山村善太郎さん(81)=神戸市在住。玄界灘の沖合約60キロに浮かび、厳しく制限されている沖ノ島の上陸許可を得て8年がかりで仕上げた。
「自然への畏怖(いふ)、畏敬(いけい)を感じた。写真集を通して、僕の思いが共有できたらうれしい」と話している。
写真集「神坐す」に収めたのは、巨石や磐座などの祭事遺跡、勾玉(まがたま)などの遺物、星空と島影の夜景など多岐にわたり、カラーとモノクロで紹介している。山村さんが印象に残っている一枚がある。
夜空を15秒露光して撮ると、鳥がはばたいているかのような雲が映った。「写真家なら、ある程度の写り具合は想像がつくが、想像を超えていた。自分の腕ではない、(神に)撮らせてもらってるんだなと感じた」と撮影を振り返った。
(西日本新聞・4/13 一部転載)
世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群を構成する福岡県宗像市の離島、沖ノ島の写真集「神坐(かみいま)す」(小学館)が出版された。
撮影したのは写真家の山村善太郎さん(81)=神戸市在住。玄界灘の沖合約60キロに浮かび、厳しく制限されている沖ノ島の上陸許可を得て8年がかりで仕上げた。
「自然への畏怖(いふ)、畏敬(いけい)を感じた。写真集を通して、僕の思いが共有できたらうれしい」と話している。
写真集「神坐す」に収めたのは、巨石や磐座などの祭事遺跡、勾玉(まがたま)などの遺物、星空と島影の夜景など多岐にわたり、カラーとモノクロで紹介している。山村さんが印象に残っている一枚がある。
夜空を15秒露光して撮ると、鳥がはばたいているかのような雲が映った。「写真家なら、ある程度の写り具合は想像がつくが、想像を超えていた。自分の腕ではない、(神に)撮らせてもらってるんだなと感じた」と撮影を振り返った。
京都 世界遺産の下鴨神社で流鏑馬神事 葵祭の安全祈
(京都 NEWS WEB・5/3 一部転載)
今月開かれる京都の三大祭りの1つ「葵祭」を前に5月3日、世界遺産の下鴨神社で祭りの安全を祈る流鏑馬(やぶさめ)の神事が行われました。
京都市左京区の下鴨神社では、毎年5月15日に行われる葵祭の安全を祈願するため5月3日に流鏑馬の神事が行われます。
神事は、境内の「馬場」で行われ平安貴族や武士の衣装に身を包んだ「射手」が、100メートルおきに置かれたおよそ50センチ四方の3つの的に向かって馬で駆け抜けながら連続して矢を放ちます。
京都市内から来た女性は、「初めて見ましたが躍動感と的が割れたときの迫力がすごかったです。伝統的な衣装もすばらしかったです」と話していました。
(京都 NEWS WEB・5/3 一部転載)
今月開かれる京都の三大祭りの1つ「葵祭」を前に5月3日、世界遺産の下鴨神社で祭りの安全を祈る流鏑馬(やぶさめ)の神事が行われました。
京都市左京区の下鴨神社では、毎年5月15日に行われる葵祭の安全を祈願するため5月3日に流鏑馬の神事が行われます。
神事は、境内の「馬場」で行われ平安貴族や武士の衣装に身を包んだ「射手」が、100メートルおきに置かれたおよそ50センチ四方の3つの的に向かって馬で駆け抜けながら連続して矢を放ちます。
京都市内から来た女性は、「初めて見ましたが躍動感と的が割れたときの迫力がすごかったです。伝統的な衣装もすばらしかったです」と話していました。
軍艦島の活気をCGで再現 長崎市、世界遺産登録10年で制作
(日経新聞・5/7 一部)
長崎市は5月7日までに、同市の端島(通称・軍艦島)が石炭採掘で栄えた1970年代の様子をCG(コンピューターグラフィックス)で再現した仮想現実(VR)映像を制作した。
観光客らに無料アプリで公開している。島などで構成する世界遺産「明治日本の産業革命遺産」が、今夏で登録から10年を迎えるのに合わせた。担当者は「当時の活気を感じ、遺産の価値を再認識してもらう機会になれば」と話している。
映像は、スマートフォンなどでアプリ「ストリートミュージアム」をダウンロードし、島内の所定の場所で起動すると見られる。360度見回せる再現CGが静止画で表示され、現在の光景と見比べて楽しめる。現地に行かない場合は、CGアニメとして再生する機能もある。
(日経新聞・5/7 一部)
長崎市は5月7日までに、同市の端島(通称・軍艦島)が石炭採掘で栄えた1970年代の様子をCG(コンピューターグラフィックス)で再現した仮想現実(VR)映像を制作した。
観光客らに無料アプリで公開している。島などで構成する世界遺産「明治日本の産業革命遺産」が、今夏で登録から10年を迎えるのに合わせた。担当者は「当時の活気を感じ、遺産の価値を再認識してもらう機会になれば」と話している。
映像は、スマートフォンなどでアプリ「ストリートミュージアム」をダウンロードし、島内の所定の場所で起動すると見られる。360度見回せる再現CGが静止画で表示され、現在の光景と見比べて楽しめる。現地に行かない場合は、CGアニメとして再生する機能もある。
世界遺産「平泉」で土壌被害相次ぐ 地下にある遺構が破壊される恐れも 犯人の正体は?
(河北新報・5/17 一部転載)
世界遺産「平泉の文化遺産」を構成する岩手県平泉町の毛越寺、中尊寺、観自在王院跡の3カ所で、イノシシが土壌を掘り起こす被害が相次いで確認された。
地下にある平安時代の遺構が破壊される恐れがあり、町や寺など関係機関は協力してイノシシからの危機を防ごうと、対策に本腰を入れ始めた
花菖蒲園で被害を初めて確認。栽培地のアヤメの列が荒らされていた。常行堂北側の弁財天池付近でも地面の掘り起こしが見つかった。
被害箇所から数十メートル先には、平安時代の庭園遺構が眠る大泉が池がある。寺は侵入防止対策として、庭園北側のトレールウオーキングコース約400メートルに侵入防止効果が期待される青色テープを張り巡らせた。さらに効果が期待できるワイヤメッシュの設置を急ぐ方針だ。
(河北新報・5/17 一部転載)
世界遺産「平泉の文化遺産」を構成する岩手県平泉町の毛越寺、中尊寺、観自在王院跡の3カ所で、イノシシが土壌を掘り起こす被害が相次いで確認された。
地下にある平安時代の遺構が破壊される恐れがあり、町や寺など関係機関は協力してイノシシからの危機を防ごうと、対策に本腰を入れ始めた
花菖蒲園で被害を初めて確認。栽培地のアヤメの列が荒らされていた。常行堂北側の弁財天池付近でも地面の掘り起こしが見つかった。
被害箇所から数十メートル先には、平安時代の庭園遺構が眠る大泉が池がある。寺は侵入防止対策として、庭園北側のトレールウオーキングコース約400メートルに侵入防止効果が期待される青色テープを張り巡らせた。さらに効果が期待できるワイヤメッシュの設置を急ぐ方針だ。
世界遺産「軍艦島」 日本の近代化を支えた廃墟の島 封印されたままの昭和 長崎県長崎市
(産経新聞・5/19 一部転載 )
桟橋に打ち付ける波音だけが響く「封印された島」は、「昭和」で時が止まっているようだった。
「軍艦島」。長崎半島の沖に浮かぶ周囲約1200メートルの島は、かつて海底炭鉱で栄えた。長崎市に属し、正式名を「端島(はしま)」という。島影が戦艦「土佐」に似ていたことからそう呼ばれている。
軍艦島の歴史は明治初めまでさかのぼる。昭和49年の閉山まで、採掘された石炭は約1570万トン。採掘現場は海面下1千メートルまで及んだという。最盛期の人口は約5300人。人口密度世界一の島だった。
炭鉱の労働は過酷だったが生活は豊かだった。20代を島で過ごした、長崎市の熊正五郎さんは「テレビや洗濯機、何でも一番よか品物ば買いよったもんね」と当時の暮らしぶりを懐かしむ。
さらに「毎週、長崎まで連絡船で遊びに行きよった」とも。他の職種では、どんなに残業をしても、炭鉱での収入にはかなわなかったという。
閉山から35年。島は今年1月、「九州・山口の近代化産業遺産群」の一つとして世界遺産の暫定リストに入り、4月には上陸観光が解禁された。長崎市によると予想を上回る人気だという。
(産経新聞・5/19 一部転載 )
桟橋に打ち付ける波音だけが響く「封印された島」は、「昭和」で時が止まっているようだった。
「軍艦島」。長崎半島の沖に浮かぶ周囲約1200メートルの島は、かつて海底炭鉱で栄えた。長崎市に属し、正式名を「端島(はしま)」という。島影が戦艦「土佐」に似ていたことからそう呼ばれている。
軍艦島の歴史は明治初めまでさかのぼる。昭和49年の閉山まで、採掘された石炭は約1570万トン。採掘現場は海面下1千メートルまで及んだという。最盛期の人口は約5300人。人口密度世界一の島だった。
炭鉱の労働は過酷だったが生活は豊かだった。20代を島で過ごした、長崎市の熊正五郎さんは「テレビや洗濯機、何でも一番よか品物ば買いよったもんね」と当時の暮らしぶりを懐かしむ。
さらに「毎週、長崎まで連絡船で遊びに行きよった」とも。他の職種では、どんなに残業をしても、炭鉱での収入にはかなわなかったという。
閉山から35年。島は今年1月、「九州・山口の近代化産業遺産群」の一つとして世界遺産の暫定リストに入り、4月には上陸観光が解禁された。長崎市によると予想を上回る人気だという。
白川郷・五箇山、30周年記念し「世界遺産サミット」 11月南砺で
(朝日新聞・5/24 一部転載)
白川郷・五箇山の合掌造り集落が今年、世界文化遺産登録30周年となるのを機に、集落のある富山県南砺市と岐阜県白川村が5月23日、共同で記念事業を行う実行委員会を立ち上げた。11月に同市で「世界遺産サミット」、12月に同村で記念式典を開くなど、連携してイベントや文化事業を進めていく。
合掌造り集落は1995年12月に世界遺産に登録された。昨年、白川郷に208万人、五箇山相倉・菅沼集落に22万5千人の観光客が訪れた。コロナ禍で一時、客数は落ち込んだが、インバウンド(外国人の訪日旅行)が好調で、復調しつつある。
この日、南砺市役所であった会議には、田中幹夫市長、岩本一也副村長のほか、世界遺産担当の富山、岐阜県の課長ら20人が出席。サミットは11月29、30日に南砺であり、「地域づくりと世界遺産」などをテーマに専門家や地元の保存会などが集まって講演会やパネルディスカッションを開く。12月14日には白川で30周年の記念式典・シンポジウムがあり、集落のある荻町や地元の子どもたちが伝承活動、保存活動などを報告する。
(朝日新聞・5/24 一部転載)
白川郷・五箇山の合掌造り集落が今年、世界文化遺産登録30周年となるのを機に、集落のある富山県南砺市と岐阜県白川村が5月23日、共同で記念事業を行う実行委員会を立ち上げた。11月に同市で「世界遺産サミット」、12月に同村で記念式典を開くなど、連携してイベントや文化事業を進めていく。
合掌造り集落は1995年12月に世界遺産に登録された。昨年、白川郷に208万人、五箇山相倉・菅沼集落に22万5千人の観光客が訪れた。コロナ禍で一時、客数は落ち込んだが、インバウンド(外国人の訪日旅行)が好調で、復調しつつある。
この日、南砺市役所であった会議には、田中幹夫市長、岩本一也副村長のほか、世界遺産担当の富山、岐阜県の課長ら20人が出席。サミットは11月29、30日に南砺であり、「地域づくりと世界遺産」などをテーマに専門家や地元の保存会などが集まって講演会やパネルディスカッションを開く。12月14日には白川で30周年の記念式典・シンポジウムがあり、集落のある荻町や地元の子どもたちが伝承活動、保存活動などを報告する。
「飛鳥・藤原の宮都」世界遺産登録に向け 橿原市 奈良県内初の世界遺産条例制定へ
(奈良テレビ放送・6/4 一部転載)
橿原市は、2026年の世界遺産登録を目指す「飛鳥・藤原の宮都」について、遺産の保存・活用に向けた理念などを盛り込んだ条例を制定すると発表しました。
「飛鳥・藤原の宮都」は中国や朝鮮半島との交流を通じて日本で初めて中央集権体制に基づく宮都が成立した過程を示す遺産で、明日香村・橿原市・桜井市にある宮殿跡や寺院跡、古墳などあわせて19の資産で構成されています。このうち橿原市は「藤原宮跡」や「本薬師寺跡」など4つの資産が市内にあります。
橿原市の亀田市長は6月2日、世界遺産登録に向けて県内で初めて「世界遺産条例」を制定すると明らかにしました。条例案には「基本理念」として、世界遺産の保存・活用は遺産が持つ普遍的な価値を維持または向上させて将来の世代へ引き継いでいくことや、行政や民間の関係者が緊密に連携することなどが盛り込まれました。
(奈良テレビ放送・6/4 一部転載)
橿原市は、2026年の世界遺産登録を目指す「飛鳥・藤原の宮都」について、遺産の保存・活用に向けた理念などを盛り込んだ条例を制定すると発表しました。
「飛鳥・藤原の宮都」は中国や朝鮮半島との交流を通じて日本で初めて中央集権体制に基づく宮都が成立した過程を示す遺産で、明日香村・橿原市・桜井市にある宮殿跡や寺院跡、古墳などあわせて19の資産で構成されています。このうち橿原市は「藤原宮跡」や「本薬師寺跡」など4つの資産が市内にあります。
橿原市の亀田市長は6月2日、世界遺産登録に向けて県内で初めて「世界遺産条例」を制定すると明らかにしました。条例案には「基本理念」として、世界遺産の保存・活用は遺産が持つ普遍的な価値を維持または向上させて将来の世代へ引き継いでいくことや、行政や民間の関係者が緊密に連携することなどが盛り込まれました。
絶景!世界遺産・新緑の森 ヤクシマシャクナゲ咲き始め華やかな季節 鹿児島
(MBC南日本放送・6/6 一部転載)
6月に入り、屋久島の森は華やかな季節を迎えようとしています。
標高1380メートル。森の中を流れる清流、淀川です。この季節は、新緑が水面に映えて美しい風景を見せてくれます。橋を渡る登山者が思わず立ち止まる場所です。
目指すのは、標高1660メートルの黒味岳を望む展望所。咲き始めたヤクシマシャクナゲに出会えるかもしれません。ヤクシマシャクナゲは屋久島固有の植物。
標高の高い場所に自生し、通常見られるシャクナゲよりも、小ぶりです。ことしのヤクシマシャクナゲの開花は去年より少し遅めのようです。
ヤクシマシャクナゲは屋久島の山の神と里の人々をつなぐ花として知られています。
山の神に五穀豊穣などを願う「岳参り」の時に、神の許しを得てヤクシマシャクナゲを少しだけいただいて里に持って帰るのです。
(MBC南日本放送・6/6 一部転載)
6月に入り、屋久島の森は華やかな季節を迎えようとしています。
標高1380メートル。森の中を流れる清流、淀川です。この季節は、新緑が水面に映えて美しい風景を見せてくれます。橋を渡る登山者が思わず立ち止まる場所です。
目指すのは、標高1660メートルの黒味岳を望む展望所。咲き始めたヤクシマシャクナゲに出会えるかもしれません。ヤクシマシャクナゲは屋久島固有の植物。
標高の高い場所に自生し、通常見られるシャクナゲよりも、小ぶりです。ことしのヤクシマシャクナゲの開花は去年より少し遅めのようです。
ヤクシマシャクナゲは屋久島の山の神と里の人々をつなぐ花として知られています。
山の神に五穀豊穣などを願う「岳参り」の時に、神の許しを得てヤクシマシャクナゲを少しだけいただいて里に持って帰るのです。
平和、笑顔の未来願い 児童がメッセージ 世界遺産の日ちなみ・平泉
(au Webポータル・6/28 一部転載)
平泉町が主催する「平和の祈り」は6月27日、世界遺産「平泉の文化遺産」の構成資産となっている同町の毛越寺で開かれた。同町と近隣の小学生による合唱や世界平和へのメッセージ朗読などが行われ、町内外からの参列者が争いのない世界の実現や被災地の安寧を願った。
争いを収めて仏教文化を発展させた平泉の文化遺産の理念に基づき、2015年から世界遺産登録日の「平泉世界遺産の日」(29日)にちなんで開催している。今年は約250人が参列。本堂前に設けられた会場で町内8寺院の僧侶が練行と法要を営み、参列者も合掌、焼香した。
(au Webポータル・6/28 一部転載)
平泉町が主催する「平和の祈り」は6月27日、世界遺産「平泉の文化遺産」の構成資産となっている同町の毛越寺で開かれた。同町と近隣の小学生による合唱や世界平和へのメッセージ朗読などが行われ、町内外からの参列者が争いのない世界の実現や被災地の安寧を願った。
争いを収めて仏教文化を発展させた平泉の文化遺産の理念に基づき、2015年から世界遺産登録日の「平泉世界遺産の日」(29日)にちなんで開催している。今年は約250人が参列。本堂前に設けられた会場で町内8寺院の僧侶が練行と法要を営み、参列者も合掌、焼香した。
『万田坑』や『三角西港』 世界文化遺産登録10周年でPRキャンペーン開催へ【熊本】
(テレビ熊本・7/02 一部転載)
『万田坑』や『三角西港』が世界文化遺産に登録されて7月、10周年を迎えます。
熊本県と荒尾市、宇城市は7月2日、記者会見を開き、「歴史を未来に残していくために合同でキャンペーンを行い、魅力をPRしていく」としました。
『明治日本の産業革命遺産』は、幕末から明治にかけて進んだ急速な産業化の歴史を物語る遺跡群です。
荒尾市の『万田坑』と宇城市の『三角西港』を含む8つの県、11の市の資産で構成されていて、7月8日に世界文化遺産の登録から10周年を迎えます。
これをきっかけに県内外の多くの人に『万田坑』と『三角西港』を知ってもらおうと、熊本県と荒尾市、宇城市が合同でキャンペーンを行うことを発表しました。
(テレビ熊本・7/02 一部転載)
『万田坑』や『三角西港』が世界文化遺産に登録されて7月、10周年を迎えます。
熊本県と荒尾市、宇城市は7月2日、記者会見を開き、「歴史を未来に残していくために合同でキャンペーンを行い、魅力をPRしていく」としました。
『明治日本の産業革命遺産』は、幕末から明治にかけて進んだ急速な産業化の歴史を物語る遺跡群です。
荒尾市の『万田坑』と宇城市の『三角西港』を含む8つの県、11の市の資産で構成されていて、7月8日に世界文化遺産の登録から10周年を迎えます。
これをきっかけに県内外の多くの人に『万田坑』と『三角西港』を知ってもらおうと、熊本県と荒尾市、宇城市が合同でキャンペーンを行うことを発表しました。
世界遺産登録から10年「韮山反射炉」 減る来場者、ピーク時の1割強に 価値発信の模索続く
(静岡新聞DIGITAL・7/8 一部転載)
伊豆の国市の世界遺産韮山反射炉は、7月8日で登録10年となる。登録以降、来場者数には陰りが見え、現状はピーク時に対して約1割強と落ち込む。
市や関係団体は、国内外の観光客を呼び込んだり、教育分野での普及を実施しようとしたりするなど、文化財としての価値発信と集客増の両立への模索が続く。
市によると、登録された2015年度の入場者数は72万人を突破したが、集客が大きく落ち込んだ新型コロナウイルス禍後も回復が弱く、24年度は9万7千人ほど。市は登録以降、反射炉にちなんだグッズ配布やキーホルダーを製作する鋳物体験教室などの施策やイベントを展開しているが、抜本的な改善には至っていない。市は10周年記念として、10月に反射炉に関するシンポジウムを開く予定。
(静岡新聞DIGITAL・7/8 一部転載)
伊豆の国市の世界遺産韮山反射炉は、7月8日で登録10年となる。登録以降、来場者数には陰りが見え、現状はピーク時に対して約1割強と落ち込む。
市や関係団体は、国内外の観光客を呼び込んだり、教育分野での普及を実施しようとしたりするなど、文化財としての価値発信と集客増の両立への模索が続く。
市によると、登録された2015年度の入場者数は72万人を突破したが、集客が大きく落ち込んだ新型コロナウイルス禍後も回復が弱く、24年度は9万7千人ほど。市は登録以降、反射炉にちなんだグッズ配布やキーホルダーを製作する鋳物体験教室などの施策やイベントを展開しているが、抜本的な改善には至っていない。市は10周年記念として、10月に反射炉に関するシンポジウムを開く予定。
彦根城世界遺産登録へ 滋賀県と彦根市が文化庁に推薦書案提出
(滋賀 NEWS WEB・7/11 一部転載 )
彦根城の世界文化遺産への登録を目指す滋賀県と彦根市は、政府がユネスコに提出する推薦書の案を7月11日、文化庁に提出したと明らかにしました。
今後、文化庁の審議会で検討され、ことし9月末までに国内の推薦候補となるかどうか決まる見通しです。
「彦根城」は、長く城郭が維持され、御殿なども数多く残ることから江戸時代の大名の統治の仕組みを象徴する存在だとして、滋賀県と彦根市が世界文化遺産への登録を目指しています。
登録にふさわしいかどうかは、ユネスコの諮問機関である「イコモス」が評価しますが、「彦根城」は去年の事前評価で、世界遺産の評価基準を満たす可能性を示唆された一方、「彦根城」単独で大名による統治の仕組みを十分に表現できているのか、という課題も指摘されました。
(滋賀 NEWS WEB・7/11 一部転載 )
彦根城の世界文化遺産への登録を目指す滋賀県と彦根市は、政府がユネスコに提出する推薦書の案を7月11日、文化庁に提出したと明らかにしました。
今後、文化庁の審議会で検討され、ことし9月末までに国内の推薦候補となるかどうか決まる見通しです。
「彦根城」は、長く城郭が維持され、御殿なども数多く残ることから江戸時代の大名の統治の仕組みを象徴する存在だとして、滋賀県と彦根市が世界文化遺産への登録を目指しています。
登録にふさわしいかどうかは、ユネスコの諮問機関である「イコモス」が評価しますが、「彦根城」は去年の事前評価で、世界遺産の評価基準を満たす可能性を示唆された一方、「彦根城」単独で大名による統治の仕組みを十分に表現できているのか、という課題も指摘されました。
屋久島や知床、西表島… 世界自然遺産への立ち入り制限、模索が続く
(朝日新聞・7/16 一部転載)
ユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界自然遺産に登録された沖縄県竹富町の西表島で3月、一部の名所について、観光客の立ち入り制限が始まった。別の登録地域では、制限を見直す動きもある。貴重な生物や生態系を守りつつ、観光などの地域経済をどう発展させるか、模索が続く。
「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」(鹿児島・沖縄両県)は2021年7月、世界自然遺産となった。うち西表島は、ユネスコの世界遺産委員会からオーバーツーリズム(観光公害)対策の強化を求められたため、特に自然環境を保全する必要がある5カ所で、1日の立ち入り人数を30〜200人にした。
たとえば、観光客の人気が高く、1日350人が押し寄せたこともあるという「ピナイサーラの滝(ヒナイ川)」は200人、「サンガラの滝(西田川)」は100人、「テドウ山」は30人を上限とした。
(朝日新聞・7/16 一部転載)
ユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界自然遺産に登録された沖縄県竹富町の西表島で3月、一部の名所について、観光客の立ち入り制限が始まった。別の登録地域では、制限を見直す動きもある。貴重な生物や生態系を守りつつ、観光などの地域経済をどう発展させるか、模索が続く。
「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」(鹿児島・沖縄両県)は2021年7月、世界自然遺産となった。うち西表島は、ユネスコの世界遺産委員会からオーバーツーリズム(観光公害)対策の強化を求められたため、特に自然環境を保全する必要がある5カ所で、1日の立ち入り人数を30〜200人にした。
たとえば、観光客の人気が高く、1日350人が押し寄せたこともあるという「ピナイサーラの滝(ヒナイ川)」は200人、「サンガラの滝(西田川)」は100人、「テドウ山」は30人を上限とした。
世界自然遺産・奄美大島の「森」の魅力を世に知らしめた写真家・浜田太、会心の一枚
(BE-PAL.NET・7/24 一部転載)
2021年7月26日に世界自然遺産に登録された奄美大島。島の中央部に位置する亜熱帯の森、金作原(きんさくばる)には巨大なシダ植物のヒカゲヘゴが群生し、まるでジュラシックパークの世界に迷いこんだかのよう。
1980年代後半、当時は誰も注目していなかった金作原の森に分け入り、貴重な動植物を撮影し、魅力を発信し続けた写真家がいた。
○奄美の原始の森「金作原」
ヒカゲヘゴは世界最大のシダ植物だ。10メートル以上に育ち、頂からは数メートルを超える葉が、放射状に生えている。
葉っぱが枯れると、柄ごときれいに落ちて、幹には葉痕が残る。その丸い模様がウロコのようで、原始の森の植物っぽい。
沖縄本島のやんばるの森でも八重山諸島でもおなじみのシダだけど、その北限ははっきりしていて、奄美大島の中部とされている。
金作原は、まさにその北限に位置している森。巨大なヒカゲヘゴが群生しており、ありふれたたとえだが、恐竜の森に迷い込んだ気分にさせてくれる。
○1枚のポスターがきっかけで奄美の森が注目される
その金作原を有名にしたのは、地元出身の写真家・浜田太さんだ。これははっきりしている。
・浜田太(はまだふとし)
1953年奄美大島生まれの写真家。世界ではじめてアマミノクロウサギの生態解明に挑み、写真撮影のに成功した。おもな写真集に『時を超えていきるアマミノクロウサギ』『奄美 光と水の物語』(ともに小学館)など。
彼は若い頃、東京で撮影助手の仕事をしていたが、ある日「故郷を撮らずしてなんぞ写真家か」と一念発起、奄美に戻り、まずはアマミノクロウサギの生態写真に挑戦し始めた。
80年代の後半の話だ。
ちなみに奄美の人はあまり森には入らない。なんせ奄美の森は、林道を少しはずれると、笑っちゃうくらいの急斜面だ。森のセラピーだの森林浴だのっていったい何?どこの世界の話?って気分になる。
リアリズムの森なのだ。猛毒のハブがうじゃうじゃいるわ、ケンムンという妖怪がいたずらをしかけるわで誰も好んで寄り付かない。
そんな森にひとりで分け入り、何日も泊まってくるというのは、どんだけ勇気があるのかアホなのかと島の人たちは驚いた。
金作原という土地の名前は知っていても、実際は誰も知らなかった。だから金作原を「発見」したのは浜田さんと言っていい。
浜田さんはただ撮るだけではなく、うら若きモデルを連れてきて薄物一枚だけで森に立たせ、奄美観光物産協会のポスターに仕立てた。
このポスターは話題となり、金作原の名は奄美や鹿児島で知られるようになった。1991年のことだ。
奄美は海だけでなく、森という貴重な財産がある!地元の人が森に注目する大きなきっかけになったのだ。
エコツアーと写真家の後悔
あれから34年、いま金作原に行くにはエコツアーガイドの同行が条件となっている。つまり地元の有料ガイドツアーに申し込まないと行くことができない。
観光客が押し寄せて、自然に負荷がかかるのを軽減するための措置だそうだ。これも奄美大島が世界自然遺産登録を目指した(2021年登録)影響なのだろうか。
うっかり者の浜田さんはガイドになる申請を忘れていた。「おれも閉め出されちゃったんだよ」と酒を飲んではぼやいている。
(BE-PAL.NET・7/24 一部転載)
2021年7月26日に世界自然遺産に登録された奄美大島。島の中央部に位置する亜熱帯の森、金作原(きんさくばる)には巨大なシダ植物のヒカゲヘゴが群生し、まるでジュラシックパークの世界に迷いこんだかのよう。
1980年代後半、当時は誰も注目していなかった金作原の森に分け入り、貴重な動植物を撮影し、魅力を発信し続けた写真家がいた。
○奄美の原始の森「金作原」
ヒカゲヘゴは世界最大のシダ植物だ。10メートル以上に育ち、頂からは数メートルを超える葉が、放射状に生えている。
葉っぱが枯れると、柄ごときれいに落ちて、幹には葉痕が残る。その丸い模様がウロコのようで、原始の森の植物っぽい。
沖縄本島のやんばるの森でも八重山諸島でもおなじみのシダだけど、その北限ははっきりしていて、奄美大島の中部とされている。
金作原は、まさにその北限に位置している森。巨大なヒカゲヘゴが群生しており、ありふれたたとえだが、恐竜の森に迷い込んだ気分にさせてくれる。
○1枚のポスターがきっかけで奄美の森が注目される
その金作原を有名にしたのは、地元出身の写真家・浜田太さんだ。これははっきりしている。
・浜田太(はまだふとし)
1953年奄美大島生まれの写真家。世界ではじめてアマミノクロウサギの生態解明に挑み、写真撮影のに成功した。おもな写真集に『時を超えていきるアマミノクロウサギ』『奄美 光と水の物語』(ともに小学館)など。
彼は若い頃、東京で撮影助手の仕事をしていたが、ある日「故郷を撮らずしてなんぞ写真家か」と一念発起、奄美に戻り、まずはアマミノクロウサギの生態写真に挑戦し始めた。
80年代の後半の話だ。
ちなみに奄美の人はあまり森には入らない。なんせ奄美の森は、林道を少しはずれると、笑っちゃうくらいの急斜面だ。森のセラピーだの森林浴だのっていったい何?どこの世界の話?って気分になる。
リアリズムの森なのだ。猛毒のハブがうじゃうじゃいるわ、ケンムンという妖怪がいたずらをしかけるわで誰も好んで寄り付かない。
そんな森にひとりで分け入り、何日も泊まってくるというのは、どんだけ勇気があるのかアホなのかと島の人たちは驚いた。
金作原という土地の名前は知っていても、実際は誰も知らなかった。だから金作原を「発見」したのは浜田さんと言っていい。
浜田さんはただ撮るだけではなく、うら若きモデルを連れてきて薄物一枚だけで森に立たせ、奄美観光物産協会のポスターに仕立てた。
このポスターは話題となり、金作原の名は奄美や鹿児島で知られるようになった。1991年のことだ。
奄美は海だけでなく、森という貴重な財産がある!地元の人が森に注目する大きなきっかけになったのだ。
エコツアーと写真家の後悔
あれから34年、いま金作原に行くにはエコツアーガイドの同行が条件となっている。つまり地元の有料ガイドツアーに申し込まないと行くことができない。
観光客が押し寄せて、自然に負荷がかかるのを軽減するための措置だそうだ。これも奄美大島が世界自然遺産登録を目指した(2021年登録)影響なのだろうか。
うっかり者の浜田さんはガイドになる申請を忘れていた。「おれも閉め出されちゃったんだよ」と酒を飲んではぼやいている。
熊本県の世界文化遺産「万田坑・三角西港」が登録10周年(PR TIMES)
(PR TIMES・8/2 一部転載)
「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録10周年を記念し、多彩な記念事業を展開。
熊本県では、「三池炭鉱万田坑」(荒尾市)と「三角西港」(宇城市)を含む「明治日本の産業革命遺産」が、世界文化遺産としてユネスコに登録されてから2025年で10周年を迎えることを記念し、各種記念事業を展開してまいります。特設Webサイトの開設をはじめ、記念ポスターの制作、スタンプラリーや展示会など、県内外に向けてその価値と魅力を再発信する一年となります。
10周年を迎える「明治日本の産業革命遺産」とは
「明治日本の産業革命遺産」は、幕末から明治期にかけて、日本が急速に近代国家へと成長する過程で中核をなした製鉄・製鋼、造船、石炭産業の発展を示す全国8県11市に点在する23の構成資産から成る、世界文化遺産です。
2015年7月にユネスコの世界遺産委員会で登録が決定され、2025年7月で10周年を迎えます。熊本県からは、荒尾市の「三池炭鉱万田坑」と宇城市の「三角西港」が構成資産として登録されており、現在も多くの来訪者が歴史的背景や建築美にふれています。
(PR TIMES・8/2 一部転載)
「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録10周年を記念し、多彩な記念事業を展開。
熊本県では、「三池炭鉱万田坑」(荒尾市)と「三角西港」(宇城市)を含む「明治日本の産業革命遺産」が、世界文化遺産としてユネスコに登録されてから2025年で10周年を迎えることを記念し、各種記念事業を展開してまいります。特設Webサイトの開設をはじめ、記念ポスターの制作、スタンプラリーや展示会など、県内外に向けてその価値と魅力を再発信する一年となります。
10周年を迎える「明治日本の産業革命遺産」とは
「明治日本の産業革命遺産」は、幕末から明治期にかけて、日本が急速に近代国家へと成長する過程で中核をなした製鉄・製鋼、造船、石炭産業の発展を示す全国8県11市に点在する23の構成資産から成る、世界文化遺産です。
2015年7月にユネスコの世界遺産委員会で登録が決定され、2025年7月で10周年を迎えます。熊本県からは、荒尾市の「三池炭鉱万田坑」と宇城市の「三角西港」が構成資産として登録されており、現在も多くの来訪者が歴史的背景や建築美にふれています。
三重津海軍所跡の世界遺産登録10年で記念イベント
(朝日新聞・7/30 )
佐賀市の「三重津海軍所跡」が構成資産の一つとなっている「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録から10年を迎えた今夏、記念イベントが目白押しだ。地域の歴史に改めて目を向けてもらい、次世代へ引き継ごうと、趣向を凝らす。
世界遺産登録からちょうど10年となる7月8日、「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」では、有明海と船の歴史を振り返る企画展が始まり、祝いの式典が開かれた。地域住民らが見守るなか、地元の中川副小学校の児童が司会を務め、みこし担ぎやくす玉割りで会場を盛り上げた。
三重津海軍所は、幕末に佐賀藩が早津江川の岸辺に設けた西洋式海軍の拠点。教育訓練施設のほか、購入した外国船の修繕のため、有明海の干満差を生かし陸上で作業できるようにした「ドライドック」を整備し、国産初の実用蒸気船「凌風丸」も建造した。
企画展では、有明海の成り立ちや干潟の生き物を紹介しているほか、三重津と福岡県の三池港が有明海の干満差をどう利用したか比較できる模型などを展示。勝海舟が長崎伝習所の受講内容を書き残したノート「海舟手帳」などの資料もある。
(朝日新聞・7/30 )
佐賀市の「三重津海軍所跡」が構成資産の一つとなっている「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録から10年を迎えた今夏、記念イベントが目白押しだ。地域の歴史に改めて目を向けてもらい、次世代へ引き継ごうと、趣向を凝らす。
世界遺産登録からちょうど10年となる7月8日、「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」では、有明海と船の歴史を振り返る企画展が始まり、祝いの式典が開かれた。地域住民らが見守るなか、地元の中川副小学校の児童が司会を務め、みこし担ぎやくす玉割りで会場を盛り上げた。
三重津海軍所は、幕末に佐賀藩が早津江川の岸辺に設けた西洋式海軍の拠点。教育訓練施設のほか、購入した外国船の修繕のため、有明海の干満差を生かし陸上で作業できるようにした「ドライドック」を整備し、国産初の実用蒸気船「凌風丸」も建造した。
企画展では、有明海の成り立ちや干潟の生き物を紹介しているほか、三重津と福岡県の三池港が有明海の干満差をどう利用したか比較できる模型などを展示。勝海舟が長崎伝習所の受講内容を書き残したノート「海舟手帳」などの資料もある。
ユネスコ世界遺産が悲鳴:日本各地で進む「オーバーツーリズム」問題
〜訪日観光客の増加により、日本の世界遺産は静けさと持続可能性を失いつつあります〜
(TRT Global・8/15 一部転載)
2024年、富士山はかつてない観光客の数に直面し、登山道では放置されたごみが自然景観を損なう深刻な問題となっています。その対策として、吉田ルートでは予約制と課金制度が導入され、1日の登山者数を4,000人に制限する措置が取られました。
岐阜県の世界遺産・白川郷では、約1,500人の住民に対して年間およそ200万人が訪れ、ごみの持ち帰り・騒音・無断立ち入りといった問題が目立つようになっています。
それに対応して、ライトアップ時の完全予約制の導入や、村民による放水銃を使った防火訓練の徹底など、観光と住民が共存できる仕組みづくりが着実に進められています。
沖縄県竹富町にある西表島では、ユネスコの世界自然遺産登録を受けて、2025年3月から「特定自然観光資源」として指定された5カ所(ピナイサーラの滝など)において、1日あたりの入域者数を200人〜30人に制限する制度が導入されました。
この取り組みは自然環境の保全を目的としており、認定ガイドの同行か、事前講習の受講が必須とされていることが、地元自治体の公式サイトで案内されています。
北海道小樽市の「船見坂」では、映画の撮影地として注目を集める中、2025年1月に観光客が線路内に立ち入り、列車にはねられて死亡する事故が起きたと報じられています。
これを受け、地元自治体は周辺に複数の警備員を配置し、危険行為やマナー違反の防止に取り組んでいると、CNNなどが伝えています。
増加する観光客と地元住民の生活コストの格差を背景に、観光施設をはじめとする各所で「二層価格制度」の導入が検討されていると、大和総研の報告が伝えています。
例えば、姫路城では市民に対しては現行の1,000円を維持し、外国人観光客などのその他の訪問者には2,500円を適用する方針が示されています。
こうした制度は観光収入の安定確保と過密緩和の両面で効果的である可能性があると指摘されています。
〜訪日観光客の増加により、日本の世界遺産は静けさと持続可能性を失いつつあります〜
(TRT Global・8/15 一部転載)
2024年、富士山はかつてない観光客の数に直面し、登山道では放置されたごみが自然景観を損なう深刻な問題となっています。その対策として、吉田ルートでは予約制と課金制度が導入され、1日の登山者数を4,000人に制限する措置が取られました。
岐阜県の世界遺産・白川郷では、約1,500人の住民に対して年間およそ200万人が訪れ、ごみの持ち帰り・騒音・無断立ち入りといった問題が目立つようになっています。
それに対応して、ライトアップ時の完全予約制の導入や、村民による放水銃を使った防火訓練の徹底など、観光と住民が共存できる仕組みづくりが着実に進められています。
沖縄県竹富町にある西表島では、ユネスコの世界自然遺産登録を受けて、2025年3月から「特定自然観光資源」として指定された5カ所(ピナイサーラの滝など)において、1日あたりの入域者数を200人〜30人に制限する制度が導入されました。
この取り組みは自然環境の保全を目的としており、認定ガイドの同行か、事前講習の受講が必須とされていることが、地元自治体の公式サイトで案内されています。
北海道小樽市の「船見坂」では、映画の撮影地として注目を集める中、2025年1月に観光客が線路内に立ち入り、列車にはねられて死亡する事故が起きたと報じられています。
これを受け、地元自治体は周辺に複数の警備員を配置し、危険行為やマナー違反の防止に取り組んでいると、CNNなどが伝えています。
増加する観光客と地元住民の生活コストの格差を背景に、観光施設をはじめとする各所で「二層価格制度」の導入が検討されていると、大和総研の報告が伝えています。
例えば、姫路城では市民に対しては現行の1,000円を維持し、外国人観光客などのその他の訪問者には2,500円を適用する方針が示されています。
こうした制度は観光収入の安定確保と過密緩和の両面で効果的である可能性があると指摘されています。
世界遺産の富岡製糸場「今しか見られない」エリア特別公開 ツアーで国宝も「建物の構造間近に」
(東京新聞・9/1 一部転載)
群馬県富岡市は、世界文化遺産の富岡製糸場(同市富岡)で保存整備工事中の乾燥場・繭扱場と、通常は非公開エリアの国宝、東置繭所2階内部の特別公開ツアーを実施している。
乾燥場・繭扱場は生糸の原料となる繭を荷受けし、繭を高温で熱して長期保存可能にするために乾燥させる施設。
木造3棟で昭和初期までに建てられた。2014年2月の大雪で繭扱場が半壊したため、つながっている乾燥場の2棟とまとめて保存整備を進めている。基礎工事が完了し、現在は2027年度中の供用開始に向けて建物本体工事が始まっている。
(東京新聞・9/1 一部転載)
群馬県富岡市は、世界文化遺産の富岡製糸場(同市富岡)で保存整備工事中の乾燥場・繭扱場と、通常は非公開エリアの国宝、東置繭所2階内部の特別公開ツアーを実施している。
乾燥場・繭扱場は生糸の原料となる繭を荷受けし、繭を高温で熱して長期保存可能にするために乾燥させる施設。
木造3棟で昭和初期までに建てられた。2014年2月の大雪で繭扱場が半壊したため、つながっている乾燥場の2棟とまとめて保存整備を進めている。基礎工事が完了し、現在は2027年度中の供用開始に向けて建物本体工事が始まっている。
世界遺産・白川郷にクマ スペイン人観光客、背後から襲われ軽傷
(毎日新聞・10/5 一部転載)
10月5日午前8時半ごろ、岐阜県白川村荻町の展望台行きシャトルバス乗り場付近で、スペイン人の男性観光客が背後からクマに襲われ、右上腕を擦りむく軽傷を負った。
現場は世界遺産・白川郷のエリア内で、村は付近の村道や遊歩道を全面通行止めにして注意を呼びかけている。
村によると、逃げたクマは体長1メートル程度だったといい、子グマとみられる。村長をトップとする村熊被害対策本部を設置し、警察や猟友会と共に付近をパトロールしたり、わなを仕掛けたりするなどの対策を取っている。村内でクマによる人的被害は2014年以来だという。
村産業課の担当者は「今の時期は木の実などが人里にもあり、食べに来た可能性がある」と話している。
(毎日新聞・10/5 一部転載)
10月5日午前8時半ごろ、岐阜県白川村荻町の展望台行きシャトルバス乗り場付近で、スペイン人の男性観光客が背後からクマに襲われ、右上腕を擦りむく軽傷を負った。
現場は世界遺産・白川郷のエリア内で、村は付近の村道や遊歩道を全面通行止めにして注意を呼びかけている。
村によると、逃げたクマは体長1メートル程度だったといい、子グマとみられる。村長をトップとする村熊被害対策本部を設置し、警察や猟友会と共に付近をパトロールしたり、わなを仕掛けたりするなどの対策を取っている。村内でクマによる人的被害は2014年以来だという。
村産業課の担当者は「今の時期は木の実などが人里にもあり、食べに来た可能性がある」と話している。
世界遺産の近くにクマ出没、見学休止 縄文遺跡群の青森・小牧野遺跡
(朝日新聞記事・10/9 i一部転載)
青森市教育委員会は10月8日、世界遺産に登録されている小牧野遺跡(同市野沢小牧野)の見学を休止し、閉鎖すると発表した。11月中旬からの冬季閉鎖期間をおよそ1カ月前倒しするかたちで、2026年4月末まで閉鎖する。
小牧野遺跡は21年7月、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一つとして世界文化遺産に登録されている。
市教委によると、7日に同市駒込でクリ拾いをしていた人がクマに襲われ、けがをする被害が発生。遺跡の周辺にもクリの木が多く、近隣でクマの目撃情報も寄せられているという。
そのため、えさを求めるクマが人と遭遇する恐れがあることから、来訪者の安全を考慮し閉鎖を決めた。遺跡からの出土品を展示している「縄文の学び舎・小牧野館」は通常通り開館するという。
(朝日新聞記事・10/9 i一部転載)
青森市教育委員会は10月8日、世界遺産に登録されている小牧野遺跡(同市野沢小牧野)の見学を休止し、閉鎖すると発表した。11月中旬からの冬季閉鎖期間をおよそ1カ月前倒しするかたちで、2026年4月末まで閉鎖する。
小牧野遺跡は21年7月、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一つとして世界文化遺産に登録されている。
市教委によると、7日に同市駒込でクリ拾いをしていた人がクマに襲われ、けがをする被害が発生。遺跡の周辺にもクリの木が多く、近隣でクマの目撃情報も寄せられているという。
そのため、えさを求めるクマが人と遭遇する恐れがあることから、来訪者の安全を考慮し閉鎖を決めた。遺跡からの出土品を展示している「縄文の学び舎・小牧野館」は通常通り開館するという。
上空からの『鍵穴』に世界遺産の価値実感…仁徳天皇陵古墳を一望、観光気球の運行始まる
(朝日新聞記事・10/9 一部転載)
世界遺産に登録されている国内最大の前方後円墳・ 大山だいせん 古墳(仁徳天皇陵古墳、堺市)を空から眺める観光気球の運行が7日、始まった。4日からの開始予定だったが、悪天候のため延期されていた。7日は快晴の下、来場者は地上からは大きすぎて見られない「鍵穴」の形をした古墳の全体像を観覧し、大阪の新たなシンボルを体感した。
2019年の 百舌鳥もず ・古市古墳群の世界遺産登録を機に堺市が「観光の起爆剤に」と計画。近くの大仙公園にある発着場から上空100メートルまで一気に上がると、「世界三大墳墓」の一つにも数えられる仁徳天皇陵古墳を中核とする百舌鳥古墳群の大小44基の古墳の眺望を楽しめる。
大阪市住吉区の大学3年生の女性は「上空から古墳の全景を見て『こんなに大きかったのか』と驚いた。気球に乗るのは初めてだけど、すごくきれいな景観に感動した」と話した。
(朝日新聞記事・10/9 一部転載)
世界遺産に登録されている国内最大の前方後円墳・ 大山だいせん 古墳(仁徳天皇陵古墳、堺市)を空から眺める観光気球の運行が7日、始まった。4日からの開始予定だったが、悪天候のため延期されていた。7日は快晴の下、来場者は地上からは大きすぎて見られない「鍵穴」の形をした古墳の全体像を観覧し、大阪の新たなシンボルを体感した。
2019年の 百舌鳥もず ・古市古墳群の世界遺産登録を機に堺市が「観光の起爆剤に」と計画。近くの大仙公園にある発着場から上空100メートルまで一気に上がると、「世界三大墳墓」の一つにも数えられる仁徳天皇陵古墳を中核とする百舌鳥古墳群の大小44基の古墳の眺望を楽しめる。
大阪市住吉区の大学3年生の女性は「上空から古墳の全景を見て『こんなに大きかったのか』と驚いた。気球に乗るのは初めてだけど、すごくきれいな景観に感動した」と話した。
世界遺産登録 30周年祝う 相倉合掌集落で式典
(中日新聞・10/22 一部転載)
南砺市の世界遺産・相倉合掌造り集落は10月19日、世界遺産登録30周年を祝う記念式典を同集落で開いた。1日限定で集落周辺を巡るバスを運行し、式典の来賓や住民らが朝もやが漂う日本の原風景の秋を堪能した。
世界遺産登録の石碑が設置されている駐車場で行った式典には住民など約50人が出席した。竹森高司区長や松本謙一市教育長、集落の子どもたちがテープカットで登録30周年とバスの出発を祝った。
竹森区長は「2家族が移住され、住民が暮らす貴重な世界遺産を子どもたちに今後も守っていってほしい」とあいさつ。松本教育長は「生きた史跡を後世に継承するべく保存活動と魅力発信に努めたい」と祝辞を述べた。
(中日新聞・10/22 一部転載)
南砺市の世界遺産・相倉合掌造り集落は10月19日、世界遺産登録30周年を祝う記念式典を同集落で開いた。1日限定で集落周辺を巡るバスを運行し、式典の来賓や住民らが朝もやが漂う日本の原風景の秋を堪能した。
世界遺産登録の石碑が設置されている駐車場で行った式典には住民など約50人が出席した。竹森高司区長や松本謙一市教育長、集落の子どもたちがテープカットで登録30周年とバスの出発を祝った。
竹森区長は「2家族が移住され、住民が暮らす貴重な世界遺産を子どもたちに今後も守っていってほしい」とあいさつ。松本教育長は「生きた史跡を後世に継承するべく保存活動と魅力発信に努めたい」と祝辞を述べた。
世界遺産「軍艦島」の保存/整備で清水建設と長崎市が協定 高耐久木造拠点を新設へ
(BUILT・10/22 一部転載)
清水建設は2025年10月15日、長崎市と連携協定を締結し、世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄/製鋼、造船、石炭産業」の構成資産である「端島炭坑(軍艦島)」の保存/整備と、公開活用に向けた取り組みを開始すると発表した。
取り組みの第一弾として、島内に木造平屋の研究拠点を設置する。2025年11月に着工し、同年12月の竣工後に設備関係の試用と調整を経て、2026年3月の運用開始を目指す。
端島には建築史的に価値ある建物群が残っており、清水建設が新築/改修を担った「三菱端島砿業所30号アパート」は、大正期に建設された日本最古の鉄筋コンクリート造集合住宅とされている。
また、端島に所在する多くの建物を清水建設が建設、保全してきた経緯から、世界遺産登録に際しては、歴史的資料として保管してきた図面類を長崎市に提供した。
(BUILT・10/22 一部転載)
清水建設は2025年10月15日、長崎市と連携協定を締結し、世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄/製鋼、造船、石炭産業」の構成資産である「端島炭坑(軍艦島)」の保存/整備と、公開活用に向けた取り組みを開始すると発表した。
取り組みの第一弾として、島内に木造平屋の研究拠点を設置する。2025年11月に着工し、同年12月の竣工後に設備関係の試用と調整を経て、2026年3月の運用開始を目指す。
端島には建築史的に価値ある建物群が残っており、清水建設が新築/改修を担った「三菱端島砿業所30号アパート」は、大正期に建設された日本最古の鉄筋コンクリート造集合住宅とされている。
また、端島に所在する多くの建物を清水建設が建設、保全してきた経緯から、世界遺産登録に際しては、歴史的資料として保管してきた図面類を長崎市に提供した。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|