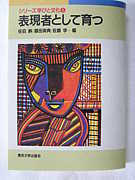このトピックでは、『音楽って何だろう(安永徹対談集)』(安永徹、三善晃他:新潮社)について紹介します。
この本は、ベルリンフィルコンサートマスターの安永徹氏と石井真木、三善晃、徳永二男、徳永武一郎の4氏との対談を収録しているもので、この中では三善晃氏との対談が非常におもしろかった。何回読み直しても新しい発見があります。1990年に発行された本なので、現在は多分書店で見ることはできないと思われる本です。そこで、できるだけ引用文を紹介して、実際にこの本を入手しなくともある程度中身が分かるように詳しく紹介したいと思います。なお、この本の紹介は、私の日記の2006年9月ごろに3本立てていますので、そちらもご覧ください。ちなみにそのアドレスもお示しします。
http://
http://
http://
まず、この三善晃氏との対談の中で、アンサンブルの練習の際に使う言語について述べている非常に興味深い部分がありますので、ご紹介します。
−−
編集部 そうしますと、安永さんはベルリンでは、ドイツ人の思考方法で考えるということになりますか。
安永 それは場合によりけりですね。ドイツ人といっしょだとドイツ語が出てくるんですけれども、日本人だとドイツ語は全然出てこないんです。ですから仮にいまドイツ語でしゃべりなさいと言われても、じっと考えないと出てこない。
ということは、ドイツ語でしゃべっている間はドイツ語的に発想しているんですね。そういう時は、非常に論理的ではっきりしていて明快です。ドイツ語だとザッハリヒというんですけれど即物的ですね、そういう考え方をしている自分に気づく。しかし日本人の顔を見ていると、日本語しか出てこないし、発想も日本語的です。自分でどうこうしようと思わないでも、使っている言葉によって変わっているみたいですね。
三善 いまのお話はとても面白いです。この頃、いろいろな文化圏のことを熟知していて、日本文化圏も含めて、通文化的に生きていると自分では思っている人がずいぶんいるんですね。その人たちは、安永さんみたいに、相手と使う国語によって思考まで変わっていくという告白は絶対しないんですね。けれども、言葉の認識とは、もう考え方そのものなんですね。
安永 そうですね。
三善 世界の分節の仕方は一人の中でも変わっているはずであって、一人が固有に連続的・通文化的に生きているわけじゃない。
安永 それはあり得ないことだと思いますね。たとえばぼくの場合、演奏会の前に練習するとしますね。ぼくは向こうでも室内楽をやっていますし、こちらへ帰ってもやりますが、おもしろいことには、向こうでやる場合とこちらでやる場合とでは、自分自身が違うんですね。
というのは、向こうではドイツ語で練習し、こちらでは日本語で練習するわけです。そうすると、自分のアイディア、思いつきが変わるんです。そのへんが自分ですごく不思議な気がします。
−−
この最後の安永さんの発言が特に興味深いと思います。この中の、「アイディア、思いつき」というのは、そのサンサンブルをどういう音楽にしていくかについてのアイディア、思いつきを指すものと考えられます。すると、ドイツ語を話すアンサンブル仲間とドイツ語で練習しているときは、ドイツ語的なアイディア、思いつきが生まれる。日本語を話すアンサンブル仲間と日本語で練習しているときは、日本語的なアイディア、思いつきが生まれる。そういうことを言っているのだと理解されます。
ヨーロッパなどで長く住んで、そこでドイツ人と深く接してきた人ならではの見解であるといえます。この安永さんの見解に従うと、プロアマ含めてもっぱら日本人仲間でしかアンサンブルをしたことのない人は、本人が意識していなくとも、日本語の発想の範囲内でしか音楽つくりのアイディアが浮かばないし、日本語の発想の範囲内でしかアイディアの交換できないと考えられます。
クラシック音楽のアンサンブルをやる人は、みなたとえばドイツ語文化圏での合奏体験が必要だ、とまで結論付けるといいすぎになると思いますが、言葉の認識とは、考え方そのものであるため、私たちが日本語をしゃべることにより、日本語の思考の拘束を受け、日本語の発想の範囲内でしか音楽つくりのアイディアが浮かばないしアイディアの交換できない可能性があることは自覚しておくことが必要かと思います。
この本の別の箇所に、「プロセス的存在」という言葉が出てくる部分があります。次にここを引用にてご紹介します。
−−
三善 (中略)各国の国際コンクールの様子を見ても事実そうです。若い音楽家たちが、世界でどのように活躍しているかを見ればすぐ分かります。東南アジアの人たちももう相当な数ですし、南米の人も多い。いまや同じ地平でお互いの音楽を聴き合うようになっていると思うんです。
なぜそうなったかと言うと、一つは、ヨーロッパの中でヨーロッパ人を連帯せしめていた何らかの価値体系が崩壊したからだと思うんですね。ジュリア・クリスティヴァの言葉を借りれば、人間がみなプロセス的存在になっている。宗教ですら人間を連帯させることができなくなっている。
プロセスは訴訟のことも指すんですね。つまり訴訟では裁判の度に自分を弁護証明しなければいけないし、裁判を繰り返すごとに状況が変わっていく。ヨーロッパも含めて全世界が、こういう意味のプロセス的状況になってきた。
−−
この三善さんの発言は、国際コンクールが乱立し、演奏者の国籍が様々になり、ヨーロッパの音楽だからといってヨーロッパ人が弾かなければならない必然が存在しなくなっている、という(対談の)文脈の中でなされているものです。
ここで、問題の「プロセス的存在」という言葉が登場しているわけですが、私の理解ではこういうことだと思います。つまり、ある人を指してその人はどういう人間かを判定しようとする場合、その人が今何をやっているのか、何に取り組んでいるのか、その取り組みの中からどういう成果が出たのか、そういういわば現在進行形の形でしか人の人格を表現することが出来なくなっている、そういう状況を指すわけです。
たとえば今企業の勤労管理システムに「成果主義」というのがあります。これは、その人がその1年間にどれだけの成果をあげたかによってその人の勤労者としての価値を値踏みし、賃金を支給する勤労管理の方式です。このような勤労管理の方式の下では、「現在成果をあげようとして奮闘努力している者」という角度からしかその人の人格を評価しません。つまり、
目標が与えられる→目標に向かって奮闘努力する→成果が評価される→賃金が査定される
こういった一連のプロセスの文脈の中でしかその勤労者の存在意義が評価されない、そういう存在がプロセス的存在です。
そうすると、プロセス的存在としての演奏家とはどういうことかというと、「これこれこういう演奏活動のスタイルで演奏活動を展開中の演奏家」という角度から理解された演奏家ということです。例えばヨーロッパ人演奏家だからヨーロッパ人演奏家としてのくくり方でくくれるという考え方は通用しない、ということになります。
そして、日本を含め世界の演奏界がこのようなプロセス的存在になってきているため、たとえば日本の音楽教育が、小さな技術主義でヨーロッパに追いつけ追い越せを目標にしていてはだめだ、一人ひとりが何をどう弾きたいのかと問われている、としています。そうすると、音楽教育の現場も、このような世界のプロセス的存在化傾向を受容し、一人ひとりの学生生徒をどう育てるのかを考えていかねばならない、としています。
さきごろ行なわれたサッカーW杯ドイツ大会でも似たようなことを感じますね。ご存知のように日本代表チームは、オーストラリア、クロアチア、ブラジルと1次リーグで対戦しましたが、それらの対戦を見ても、日本選手は自分達がどういうサッカーをしたいのか、そのしたいサッカーのイメージが伝わってこない感じがします。その後ジーコ監督の後任として着任したオシム監督も、着任当時「日本のサッカーは壊れた自動車のようだ」と形容しています。「その自動車がどのような走りでどこへ行きたいのかがわからない」ということでしょう。
また、別の機会でも、オシム監督が次のようなことを言っています。「日本の選手は、個々の技術を個別に取り上げてプレーさせるとほんとうにうまくやってのけるが、実際の試合の流れの中でそれをやっていくことができない」。やはり、試合の流れという時間軸の中で技術や能力を織り込んでいく才覚が不足しているということだと思われます。これと同じことが演奏家が作品を演奏することでも起こりうるのではないでしょうか。すなわち、個々の技術要素の実行なら非常にうまくやってのける。そのエチュードのその練習問題はそつなくやっていける。ところがそういった技術の集積を、一つの作品を芸術的に表現しようとする流れの中では使いこなせない、ということが起こりうると考えられます。
安永さんのコメントやオシム監督のコメントからわかることは、結局演奏家一人ひとりが現在進行形のプロセスの中に自分の演奏家としての生き方を探求しなければならない。そういう現在進行形のプロセスの中に真の音楽表現がある。「プロセス的存在」という言葉にはそういう意味があるようです。
次に、自分の演奏家としての生き方を探求しながら音楽を学んでいる学生に、では教師はどういう教え方をすればいいのか、という問題に言及している部分をご紹介します。
−−
安永 (中略)自分はこういう演奏がいいと思うので、それを模範にしてやっていますと言われて聴いてみると、ずいぶん違うということがよくある。そういう場合に、あなたはこう思っているんでしょうけれども、それが違うように表れているよ、そういうふうに弾きたいんだったらこうしなさいとアドヴァイスしてあげる先生というのが必要じゃないかと思うんですね。先生自身が持っている個人的な感覚で、それは違うよって言うんじゃなくて、生徒の資質を見抜いて、生徒に合わせてやるべきなんですね。
それはどういうことかといいますと、演奏のほうになりますけれども、自分の楽器というのは自分の体と一メートルも離れていないんですね。ヴァイオリンの場合はもっと近いし、管楽器もピアノもそうです。そうしますと、自分の出している音というのが分からないんですね。批評できない。自分の音を聴いても、自分のクセってものに気づかないわけです。テープを聴いても、そのクセが耳を通り過ぎてしまうんですね。
そういうところを分かった上で直してやるというのが、個性を伸ばすという意味からいくと、望ましい教育なわけです。
−−
ここで提起される問題は、音楽教師(例えばヴァイオリン教師)はいったい何を教えるのか、ということです。この場合の音楽教師は、例えば安永さんのように、音大生やその卒業生など専門家をめざすレベルの高い生徒さんを教える場合の教師を指すものとします。
すると、まず考えられる解答の選択肢としては、次の3つくらいでしょう。
(1)その楽器(例えばヴァイオリン)の演奏技術を教える。
(2)音楽を教える。
(3)その生徒を教える(指導する)。
さて、どれなのかということです。
まず、(1)のその楽器の演奏技術を教える、というとらえ方では不十分であることは明らかです。なぜかというと、音大生やその卒業生など専門家をめざすレベルの高い生徒さんの場合、その段階に達するまでにすでに相当程度の技術の蓄積はしているからです。だから、いまさら演奏技術をみっちり教わっても、それだけでは不十分であると考えられます。
(2)の音楽を教える、というとらえ方は、ある程度いい線をいっていますが、これもやはり不十分であると考えます。確かに音楽を学ぶことは必要なのです。だが、音楽を学んで、ではその生徒さんはどういう演奏家として成長していけばいいのか、その方向性が見えてくるという保証はあるのか、という問題があるのです。
すると、やはり究極的には(3)のその生徒を教える(指導する)ということだと思うんです。
「教える」ということの意味をこの「その生徒を教える」という意味にとるとき、その教える対象である「その生徒」はみなそれぞれ「その生徒」であるわけです。つまり、「その生徒」はみなそれぞれ、体格も違うし、生い立ちも違うし、音楽性も違うし、技術の長所や弱点も違うし、その人が演奏家として人生をつむいでいくときの望ましい方向性も違うと考えられる。
すると、教師としては、その生徒その生徒の人間をよく見つめて、「この生徒にはどういう指導が必要か」、「この生徒にはどういう演奏家としての成長の方向性がふさわしいか」ということを考えて、指導のメニューや方針を、「その生徒」ごとにテイラーメイドする力量が求められると思います。
「教師」と「師」は違うと思うのですよ。「師」というのは、その弟子その弟子の人間をよく見きわめて、その弟子ごとに指導のメニューや方針をテイラーメイドする幅広い力量がある人のことを言うと思われます。だから、しばしば、「師」は弟子にとって人生の「師」でもあるのです。
囲碁の世界に木谷実という人がいます。この人は生涯、棋風が4度も変わったといいます。さらに、多数の弟子を持ち、その弟子の持っている段位の合計が300段を超えるらしいです。この300段という数字は、いかに多人数の優秀な弟子を育成したかを物語っています。こういった事実は、棋士としての木谷実という人が、いかに幅広い人間性を持った偉大な師であったかを物語っています。囲碁の世界にせよ、音楽の世界にせよ、「師」であるためにはこのような幅の広い力量が要求されるのではないでしょうか。
この安永さんの発言のあと、対談者の三善さんが、教育者は体験の幅の広さがぜひとも必要だ、という意味のことをおっしゃっています。つまり、自ら弾く(演奏活動をするということ)、たくさん聴く、楽譜をとことん見る、そういった音のリアリティについての実体験の幅を広げ続けることが必要だ、とおっしゃっています。安永さんのこの見解は、「師」となるものに何が求められるのかということとそっくり重なることがお解りいただけることでしょう。
この対談の中には、さらに音楽教育に関連して安永さんの「自分を確立することが大事だ」という主張があります。その部分をご紹介します。
−−
そういう意味で、ぼくも学生のころは一般教養なんてどうでもいいや、とにかく音楽を弾かなきゃいけないと考えていたんですが、これは間違いだったと思います。人と飲んだり食ったり議論をしたりすることが自分の視野を広げることだと単純に思っていましたが、まず自分を確立することが大事なんですね。そのためには、先生がいまおっしゃったように、哲学なり歴史なり物理なりを勉強し把握して、自分の世界観、あるいは音楽観といったものを作り上げていくことが必要になってくるわけです。逆に言うと、学生のほうにそういう心構えを植えつけていく先生がいなければいけない。
−−
音楽家にとって「まず自分を確立することが大事」というのは全くその通りですが、しかし音楽の勉強の初等中等段階では、「自分を確立しなさい」などといっても不可能ですね。なぜかというと、音楽家としての自分を見出すための素材がまだ十分に自己の中に蓄積されていないからです。
やはり、ある程度の技術や能力を蓄積して音楽家としての自分を見出すための素材が自己の中に形成されて、初めて「音楽家としての自己を確立する」という営みのスタートラインにつくことができるわけです。この段階に来て、音楽の学びのプロセスがようやく「折り返し地点」に来たと言えるのではないでしょうか。
このことは、逆に言うと、初等中等段階の音楽教育では、「この先に『音楽家としての自己を確立する』という重要な折り返し地点がある」ということを念頭において行なわれるべきであるということを私たちに教えていると言えるでしょう。
この本は、ベルリンフィルコンサートマスターの安永徹氏と石井真木、三善晃、徳永二男、徳永武一郎の4氏との対談を収録しているもので、この中では三善晃氏との対談が非常におもしろかった。何回読み直しても新しい発見があります。1990年に発行された本なので、現在は多分書店で見ることはできないと思われる本です。そこで、できるだけ引用文を紹介して、実際にこの本を入手しなくともある程度中身が分かるように詳しく紹介したいと思います。なお、この本の紹介は、私の日記の2006年9月ごろに3本立てていますので、そちらもご覧ください。ちなみにそのアドレスもお示しします。
http://
http://
http://
まず、この三善晃氏との対談の中で、アンサンブルの練習の際に使う言語について述べている非常に興味深い部分がありますので、ご紹介します。
−−
編集部 そうしますと、安永さんはベルリンでは、ドイツ人の思考方法で考えるということになりますか。
安永 それは場合によりけりですね。ドイツ人といっしょだとドイツ語が出てくるんですけれども、日本人だとドイツ語は全然出てこないんです。ですから仮にいまドイツ語でしゃべりなさいと言われても、じっと考えないと出てこない。
ということは、ドイツ語でしゃべっている間はドイツ語的に発想しているんですね。そういう時は、非常に論理的ではっきりしていて明快です。ドイツ語だとザッハリヒというんですけれど即物的ですね、そういう考え方をしている自分に気づく。しかし日本人の顔を見ていると、日本語しか出てこないし、発想も日本語的です。自分でどうこうしようと思わないでも、使っている言葉によって変わっているみたいですね。
三善 いまのお話はとても面白いです。この頃、いろいろな文化圏のことを熟知していて、日本文化圏も含めて、通文化的に生きていると自分では思っている人がずいぶんいるんですね。その人たちは、安永さんみたいに、相手と使う国語によって思考まで変わっていくという告白は絶対しないんですね。けれども、言葉の認識とは、もう考え方そのものなんですね。
安永 そうですね。
三善 世界の分節の仕方は一人の中でも変わっているはずであって、一人が固有に連続的・通文化的に生きているわけじゃない。
安永 それはあり得ないことだと思いますね。たとえばぼくの場合、演奏会の前に練習するとしますね。ぼくは向こうでも室内楽をやっていますし、こちらへ帰ってもやりますが、おもしろいことには、向こうでやる場合とこちらでやる場合とでは、自分自身が違うんですね。
というのは、向こうではドイツ語で練習し、こちらでは日本語で練習するわけです。そうすると、自分のアイディア、思いつきが変わるんです。そのへんが自分ですごく不思議な気がします。
−−
この最後の安永さんの発言が特に興味深いと思います。この中の、「アイディア、思いつき」というのは、そのサンサンブルをどういう音楽にしていくかについてのアイディア、思いつきを指すものと考えられます。すると、ドイツ語を話すアンサンブル仲間とドイツ語で練習しているときは、ドイツ語的なアイディア、思いつきが生まれる。日本語を話すアンサンブル仲間と日本語で練習しているときは、日本語的なアイディア、思いつきが生まれる。そういうことを言っているのだと理解されます。
ヨーロッパなどで長く住んで、そこでドイツ人と深く接してきた人ならではの見解であるといえます。この安永さんの見解に従うと、プロアマ含めてもっぱら日本人仲間でしかアンサンブルをしたことのない人は、本人が意識していなくとも、日本語の発想の範囲内でしか音楽つくりのアイディアが浮かばないし、日本語の発想の範囲内でしかアイディアの交換できないと考えられます。
クラシック音楽のアンサンブルをやる人は、みなたとえばドイツ語文化圏での合奏体験が必要だ、とまで結論付けるといいすぎになると思いますが、言葉の認識とは、考え方そのものであるため、私たちが日本語をしゃべることにより、日本語の思考の拘束を受け、日本語の発想の範囲内でしか音楽つくりのアイディアが浮かばないしアイディアの交換できない可能性があることは自覚しておくことが必要かと思います。
この本の別の箇所に、「プロセス的存在」という言葉が出てくる部分があります。次にここを引用にてご紹介します。
−−
三善 (中略)各国の国際コンクールの様子を見ても事実そうです。若い音楽家たちが、世界でどのように活躍しているかを見ればすぐ分かります。東南アジアの人たちももう相当な数ですし、南米の人も多い。いまや同じ地平でお互いの音楽を聴き合うようになっていると思うんです。
なぜそうなったかと言うと、一つは、ヨーロッパの中でヨーロッパ人を連帯せしめていた何らかの価値体系が崩壊したからだと思うんですね。ジュリア・クリスティヴァの言葉を借りれば、人間がみなプロセス的存在になっている。宗教ですら人間を連帯させることができなくなっている。
プロセスは訴訟のことも指すんですね。つまり訴訟では裁判の度に自分を弁護証明しなければいけないし、裁判を繰り返すごとに状況が変わっていく。ヨーロッパも含めて全世界が、こういう意味のプロセス的状況になってきた。
−−
この三善さんの発言は、国際コンクールが乱立し、演奏者の国籍が様々になり、ヨーロッパの音楽だからといってヨーロッパ人が弾かなければならない必然が存在しなくなっている、という(対談の)文脈の中でなされているものです。
ここで、問題の「プロセス的存在」という言葉が登場しているわけですが、私の理解ではこういうことだと思います。つまり、ある人を指してその人はどういう人間かを判定しようとする場合、その人が今何をやっているのか、何に取り組んでいるのか、その取り組みの中からどういう成果が出たのか、そういういわば現在進行形の形でしか人の人格を表現することが出来なくなっている、そういう状況を指すわけです。
たとえば今企業の勤労管理システムに「成果主義」というのがあります。これは、その人がその1年間にどれだけの成果をあげたかによってその人の勤労者としての価値を値踏みし、賃金を支給する勤労管理の方式です。このような勤労管理の方式の下では、「現在成果をあげようとして奮闘努力している者」という角度からしかその人の人格を評価しません。つまり、
目標が与えられる→目標に向かって奮闘努力する→成果が評価される→賃金が査定される
こういった一連のプロセスの文脈の中でしかその勤労者の存在意義が評価されない、そういう存在がプロセス的存在です。
そうすると、プロセス的存在としての演奏家とはどういうことかというと、「これこれこういう演奏活動のスタイルで演奏活動を展開中の演奏家」という角度から理解された演奏家ということです。例えばヨーロッパ人演奏家だからヨーロッパ人演奏家としてのくくり方でくくれるという考え方は通用しない、ということになります。
そして、日本を含め世界の演奏界がこのようなプロセス的存在になってきているため、たとえば日本の音楽教育が、小さな技術主義でヨーロッパに追いつけ追い越せを目標にしていてはだめだ、一人ひとりが何をどう弾きたいのかと問われている、としています。そうすると、音楽教育の現場も、このような世界のプロセス的存在化傾向を受容し、一人ひとりの学生生徒をどう育てるのかを考えていかねばならない、としています。
さきごろ行なわれたサッカーW杯ドイツ大会でも似たようなことを感じますね。ご存知のように日本代表チームは、オーストラリア、クロアチア、ブラジルと1次リーグで対戦しましたが、それらの対戦を見ても、日本選手は自分達がどういうサッカーをしたいのか、そのしたいサッカーのイメージが伝わってこない感じがします。その後ジーコ監督の後任として着任したオシム監督も、着任当時「日本のサッカーは壊れた自動車のようだ」と形容しています。「その自動車がどのような走りでどこへ行きたいのかがわからない」ということでしょう。
また、別の機会でも、オシム監督が次のようなことを言っています。「日本の選手は、個々の技術を個別に取り上げてプレーさせるとほんとうにうまくやってのけるが、実際の試合の流れの中でそれをやっていくことができない」。やはり、試合の流れという時間軸の中で技術や能力を織り込んでいく才覚が不足しているということだと思われます。これと同じことが演奏家が作品を演奏することでも起こりうるのではないでしょうか。すなわち、個々の技術要素の実行なら非常にうまくやってのける。そのエチュードのその練習問題はそつなくやっていける。ところがそういった技術の集積を、一つの作品を芸術的に表現しようとする流れの中では使いこなせない、ということが起こりうると考えられます。
安永さんのコメントやオシム監督のコメントからわかることは、結局演奏家一人ひとりが現在進行形のプロセスの中に自分の演奏家としての生き方を探求しなければならない。そういう現在進行形のプロセスの中に真の音楽表現がある。「プロセス的存在」という言葉にはそういう意味があるようです。
次に、自分の演奏家としての生き方を探求しながら音楽を学んでいる学生に、では教師はどういう教え方をすればいいのか、という問題に言及している部分をご紹介します。
−−
安永 (中略)自分はこういう演奏がいいと思うので、それを模範にしてやっていますと言われて聴いてみると、ずいぶん違うということがよくある。そういう場合に、あなたはこう思っているんでしょうけれども、それが違うように表れているよ、そういうふうに弾きたいんだったらこうしなさいとアドヴァイスしてあげる先生というのが必要じゃないかと思うんですね。先生自身が持っている個人的な感覚で、それは違うよって言うんじゃなくて、生徒の資質を見抜いて、生徒に合わせてやるべきなんですね。
それはどういうことかといいますと、演奏のほうになりますけれども、自分の楽器というのは自分の体と一メートルも離れていないんですね。ヴァイオリンの場合はもっと近いし、管楽器もピアノもそうです。そうしますと、自分の出している音というのが分からないんですね。批評できない。自分の音を聴いても、自分のクセってものに気づかないわけです。テープを聴いても、そのクセが耳を通り過ぎてしまうんですね。
そういうところを分かった上で直してやるというのが、個性を伸ばすという意味からいくと、望ましい教育なわけです。
−−
ここで提起される問題は、音楽教師(例えばヴァイオリン教師)はいったい何を教えるのか、ということです。この場合の音楽教師は、例えば安永さんのように、音大生やその卒業生など専門家をめざすレベルの高い生徒さんを教える場合の教師を指すものとします。
すると、まず考えられる解答の選択肢としては、次の3つくらいでしょう。
(1)その楽器(例えばヴァイオリン)の演奏技術を教える。
(2)音楽を教える。
(3)その生徒を教える(指導する)。
さて、どれなのかということです。
まず、(1)のその楽器の演奏技術を教える、というとらえ方では不十分であることは明らかです。なぜかというと、音大生やその卒業生など専門家をめざすレベルの高い生徒さんの場合、その段階に達するまでにすでに相当程度の技術の蓄積はしているからです。だから、いまさら演奏技術をみっちり教わっても、それだけでは不十分であると考えられます。
(2)の音楽を教える、というとらえ方は、ある程度いい線をいっていますが、これもやはり不十分であると考えます。確かに音楽を学ぶことは必要なのです。だが、音楽を学んで、ではその生徒さんはどういう演奏家として成長していけばいいのか、その方向性が見えてくるという保証はあるのか、という問題があるのです。
すると、やはり究極的には(3)のその生徒を教える(指導する)ということだと思うんです。
「教える」ということの意味をこの「その生徒を教える」という意味にとるとき、その教える対象である「その生徒」はみなそれぞれ「その生徒」であるわけです。つまり、「その生徒」はみなそれぞれ、体格も違うし、生い立ちも違うし、音楽性も違うし、技術の長所や弱点も違うし、その人が演奏家として人生をつむいでいくときの望ましい方向性も違うと考えられる。
すると、教師としては、その生徒その生徒の人間をよく見つめて、「この生徒にはどういう指導が必要か」、「この生徒にはどういう演奏家としての成長の方向性がふさわしいか」ということを考えて、指導のメニューや方針を、「その生徒」ごとにテイラーメイドする力量が求められると思います。
「教師」と「師」は違うと思うのですよ。「師」というのは、その弟子その弟子の人間をよく見きわめて、その弟子ごとに指導のメニューや方針をテイラーメイドする幅広い力量がある人のことを言うと思われます。だから、しばしば、「師」は弟子にとって人生の「師」でもあるのです。
囲碁の世界に木谷実という人がいます。この人は生涯、棋風が4度も変わったといいます。さらに、多数の弟子を持ち、その弟子の持っている段位の合計が300段を超えるらしいです。この300段という数字は、いかに多人数の優秀な弟子を育成したかを物語っています。こういった事実は、棋士としての木谷実という人が、いかに幅広い人間性を持った偉大な師であったかを物語っています。囲碁の世界にせよ、音楽の世界にせよ、「師」であるためにはこのような幅の広い力量が要求されるのではないでしょうか。
この安永さんの発言のあと、対談者の三善さんが、教育者は体験の幅の広さがぜひとも必要だ、という意味のことをおっしゃっています。つまり、自ら弾く(演奏活動をするということ)、たくさん聴く、楽譜をとことん見る、そういった音のリアリティについての実体験の幅を広げ続けることが必要だ、とおっしゃっています。安永さんのこの見解は、「師」となるものに何が求められるのかということとそっくり重なることがお解りいただけることでしょう。
この対談の中には、さらに音楽教育に関連して安永さんの「自分を確立することが大事だ」という主張があります。その部分をご紹介します。
−−
そういう意味で、ぼくも学生のころは一般教養なんてどうでもいいや、とにかく音楽を弾かなきゃいけないと考えていたんですが、これは間違いだったと思います。人と飲んだり食ったり議論をしたりすることが自分の視野を広げることだと単純に思っていましたが、まず自分を確立することが大事なんですね。そのためには、先生がいまおっしゃったように、哲学なり歴史なり物理なりを勉強し把握して、自分の世界観、あるいは音楽観といったものを作り上げていくことが必要になってくるわけです。逆に言うと、学生のほうにそういう心構えを植えつけていく先生がいなければいけない。
−−
音楽家にとって「まず自分を確立することが大事」というのは全くその通りですが、しかし音楽の勉強の初等中等段階では、「自分を確立しなさい」などといっても不可能ですね。なぜかというと、音楽家としての自分を見出すための素材がまだ十分に自己の中に蓄積されていないからです。
やはり、ある程度の技術や能力を蓄積して音楽家としての自分を見出すための素材が自己の中に形成されて、初めて「音楽家としての自己を確立する」という営みのスタートラインにつくことができるわけです。この段階に来て、音楽の学びのプロセスがようやく「折り返し地点」に来たと言えるのではないでしょうか。
このことは、逆に言うと、初等中等段階の音楽教育では、「この先に『音楽家としての自己を確立する』という重要な折り返し地点がある」ということを念頭において行なわれるべきであるということを私たちに教えていると言えるでしょう。
|
|
|
|
|
|
|
|
音楽書を読み込もう! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
音楽書を読み込もう!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人