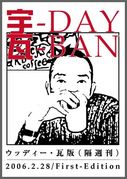「夢の美術館:大阪コレクションズ」
03月25日(日)、中之島美術館にて「夢の美術館:大阪コレクションズ」へ。withハニー。大阪コレクションズつーだけあって、近年開館予定の「大阪市立近代美術館」、「国立国際美術館」、サントリーミュージアム「天保山」という市内の三大美術館が共同出展。
モジリアニの裸婦をはじめ、シュルレアリスムの帝王ダリやマグリット、エルンスト、印象派の巨匠セザンヌ、キュビスム期のピカソやクレーから、モダンアートの旗手ウォーホールまで、広く浅く的な展覧会であった。
まあ、広く浅くという今回の品揃えは、20世紀の美術史全体を俯瞰するにはもってこいで、本を斜め読みする感じで、居並ぶ大作の間を銀バエのように飛び回った。
とはいえ、やっぱ僕の目玉はマルセル・デュシャンの「トランクの箱」。「トランク」と「箱」…意味合いが被ってるところからしていい(「トランクの中の箱」と記載されることもある)。2年程前に、マイミク久保夫とここへデュシャン展を観に来た際にこの作品に出会って以来、2度目の本物との接近遭遇。
「トランクの箱」を最初に観た時から、僕は即座に「おぉ、これってi-Bookと同じ質感を醸し出してるじぇ」と看破した。
僕のi-Bookには、自分の作品はもちろん、好きな絵画やCDのジャケ画像、i-Tuneに入った、自身のバンド楽曲なども含んだ何百ものお気に入り曲、お気に入りのアーティストのライブ映像や映画、TV番組などの動画、はたまた「青空文庫」つーフリーサイトから落とした文豪の小説など、山の様なお気に入りデータが入っている。
自分のお気に入りをすべて鞄に詰めて持ち歩くことへの悦楽が、このデュシャンの箱からはヒシヒシと感じられたのだ。実際それを持ち歩いてどうするの?つー野暮なことが問題なのではない。持ち歩くことそれ自体が目的なのである。
同時に、ひとつ一つ緻密に造り込まれたミニチュアへの欲望…。そこには“小さなコピー”に価値を見い出すような、例えば箱庭や盆栽にも通じる嗜好がある。現代で言えば膨大な数量が出回っているフィギアの魅惑が、その感覚を継承しているのかも知れない。
そして、ミニチュアへの欲望は明らかな“所有欲”の顕現であり、すべてを持ち歩くことで完結するi-Bookとの類似性と連携している。
「トランクの箱」のみを納めた陳列ケースの周りを、動物園のトラのようにグルグル廻りながら、ふとこれは、ピカソとは逆方向の芸術の佇まいなのだと思った。生の奔流から逃走し、限定された非現実世界の構築へと、マテリアルやディテ−ルの細部へと向かう芸術。たぶん、この日同様に作品を展示されていたダリやマグリッド、エルンストもそうであったろう。ピカソの絵画を炸裂だとすると、こっちは圧縮というか、凝結というか、濃縮というか。
そういう観点での理解が難しいのがウォーホールだろうなどとと思い当たると、今さらながら彼の創作活動が芸術という総体の特異点であったこと、真に革命的であったことなどが分かる。もったいぶった先達とはそのフィールドがまったく違う。言い古されてはいるが絵ではなくイメージ、システム。器官なき身体。偉大なるファイン(ポップ)アート・スゥィンドル。
また、デュシャンの「トランクの箱」とそっくりの質感を持っていて、一目で好きになったのが、今回初めて名前を聞いのであるが、ジョゼフ・コーネル(1903-1972/アメリカ)つー人による一連の「箱+コラージュ作品」。
箱の中にガラスや鏡、雑誌の切り抜き、セルロイド、人形、パイプなどを配置し、遂には宇宙までもを詰め込んだ幾つかの立体作品は、奇妙な郷愁であっという間に僕を魅了してしまったのだ。
奇妙な郷愁…子供の頃、昆虫採集して標本箱を作った時のワクワク感とか、団地のベランダの下にある土を四角く掘ってそこに板を敷き、小さなオモチャや人形なんかをレイアウトした“秘密基地”の悦楽、或いは、子供の頃観た男の子ながらにちょいドキドキした「持ち運び出来るりかちゃんハウス」的な佇まい、と言ってもいい。そんな感覚を強烈に思い出した。先述した「トランクの箱」にもそういうところがある。
「箱は想像力が君臨していた日々の遺宝箱なのだ。むろん箱たちは、子供のころの夢想に立ち戻るよう私たちを誘っている。」
※チャールズ・シミック(コーネルを盲目的に敬愛している詩人)による評論「コーネルの箱」より
----------
小林秀雄は「絵画論」つー好エッセイで、或るゴッホの絵を、画集で観た時にはそんな感覚は起きなかったが、同じ絵の本物を美術館で観た瞬間にその何十号もある画面から薫り立つ生々しい情感に打たれ、何時間もその場に立ち尽くしたと語っていたが、僕にはそんな経験はない。
一緒に行ったハニーは嵯峨美の油絵科出身であり、絵というものが存在の根幹に関わっている部分もあるからか、小林秀雄と同じように、実際の展覧会で或る絵を忘我して眺め続け、気がつくとバーッと泣いていたてなことがあったという。
う〜ん、一度その感じを味わってみたいもんだ。多分、ラジオから流れて来た初めの歌に感じ入り、無心に聴き入ってしまう感じに似ているのかも。
そういや昔、小学生や中学生、いや高校になっても、美術の本に乗っているしかつめらしい(と当時は思えた)巨匠の絵画の数々について、「僕は死ぬまでにこの絵を理解できんのかなー」などと考え「たぶん分かんねーだろーな」などと思ってちょっと悲しくなったりしたが、なんの、その後分かりやすいダリを突破口に、マグリッド、ピカソ、ルオー、ゴッホ、モジリアニ、ベーコン、梅原龍三郎、岡本太郎、ウォーホールと教科書に載っているような有名ドコロにはほぼリスペクトした。いや、分かったとは言わない。感じたのである。子供の頃、岡本太郎の「太陽の塔」に夢中になったのと大差ない感じ方ではあるが。
好き嫌いはある。いや、感じるか感じないか。例えば僕のオヤジは絵が好きで、自らも無数のスケッチを残しており、展覧会となれば出かけて行き、ダリやマグリッドは大好きらしいが、ピカソは受け付けない。この辺り人の嗜好って面白えと思う。僕的には印象派と呼ばれる画家はどうもコナイ。今のところ。
思うに芸術には2つのベクトルがあるのでは。
ひとつは世界をコンパクトに(どれほど号数の大きなカンバスとはいえ)、自分の解釈として取り込み所有しようとする芸術。これはダリやマグリッドなどシュールレアリズムの作家陣。印象派もこっちか。どちらかと言えば静的な芸術。額縁の中に収まり、一種の夢としてそこで完結する絵画。
もうひとつは世界の中で炸裂して粉々になり、そこに小さいながらも風穴を明けて、自分を解放しようとする芸術。動的な芸術。額縁の外にはみ出す、線そのものが枠外へ逃走するような絵画。こちらはピカソやゴッホを筆頭に、ミロなどの多くの抽象作家の他、アンディ・ウォーホールも、システム論的にこちらのように思われる。
もちろんどちらとは言えない折衷的な立場もあるし、大抵の作家はその2つのベクトルを移行しながら創造するのかも知れない。
(ウッディー:07-03.28)
----------
PS/
とか何とか「トランクの箱」と絡めてi-Bookのこと語ってたら、なんと!そのi-Bookがぶっこわれた。「MACアングラ道」てな本に触発されて、ウィンドウズメディアプレイヤーをダウンロードした瞬間から動きがアヤシクなり、システム入れ替えたりしても症状は悪化するばかり。ついに立ち上がらなくなり、アップルストアに相談に行くと、たぶんボード換えなけりゃダメでしょうつーことになってしまった。2001年製G3を中古で買ったやつなんだが、毎日鞄に入れて持ち歩いてても一度も故障しなかっただけにショック。修理は4万5千円程度、データの吸い出し(HDがイカレてなければ)だけでも2万弱かかるらしい。アップルよ、このドンブリ勘定的な修理価格の設定、なんとかなんないの?ストアの雰囲気や対応はイイ感じなのにさー。
------------------------------
「蟲師」
04月01日(日)、寺町のMOVIXにて「蟲師」を観る。
むしし、つってもケンケンの忍び笑いではない(古)。
映画館は予想外にほぼ満席状態で、最前列左右しか空いていない。ちらほら聴こえてくる評価はイマイチなのになんで?と渋々チケットを買って思い出した。2枚で¥1,000!そーか毎月01日は映画の日なのさ。+主演のオダギリジョー人気っつーとこか。原作は女流漫画家・漆原友紀。監督はあの大友克洋らしい。
いや、面白かったよ。途中僕はちょっと寝たけど(画面に近すぎて目廻った)。自然の気や陰陽の力など、あの水木しげるが妖怪(精霊)のカタチを借りて表した森羅万象を司ることどもを、この原作者は空気中に無数に漂う“蟲”の仕業として描いているのだろう。ひょっとして空中生物説が取り沙汰されているUFOや、昨今話題のスカイフィッシュも“蟲”の一種かも?
“蟲師”は全国を行脚しながら、そんな“蟲”どもを駆逐し、制御し、時には操ることで、小さな病気から大病までを治療して報酬を手にする術者である。
まあ、話は濃密なんだけど役者はあっさりし過ぎの感あり。多分たけしの「座頭市」がアリにした、時代劇パツキンで登場する主役のオダギリジョーは、無難な路線で可も不可もなくってとこ。ライフカードのCMのが存在感あるねー。旅の道ずれ役は僕の邦楽フェイバリットのひとつ「ヴァイブレーター」で、あの超濃い寺島しのぶとりっぱにタメはってた大森南朋。脇に徹していい味。しかし、主役のオカン役の江角マキコは…声が「ショムニ」そのままで馴染まないことこの上なし。なんでココに江角マキコなんだろう?
余談だが江角マキコと米倉涼子って何か似てね?存在感的に。
今回、原作者が女性と知ってふと思ったのだが、そもそも分類され、体系化された“妖怪(精霊)”という発想は男性的なのかも。比べて、すべての媒介としてのフワフワとした、一定のカタチを持たない“蟲”は、女性的で秀逸な解釈なのかも知れない。この新しい解釈は興味深い。
(ウッディー:07-04.06)
03月25日(日)、中之島美術館にて「夢の美術館:大阪コレクションズ」へ。withハニー。大阪コレクションズつーだけあって、近年開館予定の「大阪市立近代美術館」、「国立国際美術館」、サントリーミュージアム「天保山」という市内の三大美術館が共同出展。
モジリアニの裸婦をはじめ、シュルレアリスムの帝王ダリやマグリット、エルンスト、印象派の巨匠セザンヌ、キュビスム期のピカソやクレーから、モダンアートの旗手ウォーホールまで、広く浅く的な展覧会であった。
まあ、広く浅くという今回の品揃えは、20世紀の美術史全体を俯瞰するにはもってこいで、本を斜め読みする感じで、居並ぶ大作の間を銀バエのように飛び回った。
とはいえ、やっぱ僕の目玉はマルセル・デュシャンの「トランクの箱」。「トランク」と「箱」…意味合いが被ってるところからしていい(「トランクの中の箱」と記載されることもある)。2年程前に、マイミク久保夫とここへデュシャン展を観に来た際にこの作品に出会って以来、2度目の本物との接近遭遇。
「トランクの箱」を最初に観た時から、僕は即座に「おぉ、これってi-Bookと同じ質感を醸し出してるじぇ」と看破した。
僕のi-Bookには、自分の作品はもちろん、好きな絵画やCDのジャケ画像、i-Tuneに入った、自身のバンド楽曲なども含んだ何百ものお気に入り曲、お気に入りのアーティストのライブ映像や映画、TV番組などの動画、はたまた「青空文庫」つーフリーサイトから落とした文豪の小説など、山の様なお気に入りデータが入っている。
自分のお気に入りをすべて鞄に詰めて持ち歩くことへの悦楽が、このデュシャンの箱からはヒシヒシと感じられたのだ。実際それを持ち歩いてどうするの?つー野暮なことが問題なのではない。持ち歩くことそれ自体が目的なのである。
同時に、ひとつ一つ緻密に造り込まれたミニチュアへの欲望…。そこには“小さなコピー”に価値を見い出すような、例えば箱庭や盆栽にも通じる嗜好がある。現代で言えば膨大な数量が出回っているフィギアの魅惑が、その感覚を継承しているのかも知れない。
そして、ミニチュアへの欲望は明らかな“所有欲”の顕現であり、すべてを持ち歩くことで完結するi-Bookとの類似性と連携している。
「トランクの箱」のみを納めた陳列ケースの周りを、動物園のトラのようにグルグル廻りながら、ふとこれは、ピカソとは逆方向の芸術の佇まいなのだと思った。生の奔流から逃走し、限定された非現実世界の構築へと、マテリアルやディテ−ルの細部へと向かう芸術。たぶん、この日同様に作品を展示されていたダリやマグリッド、エルンストもそうであったろう。ピカソの絵画を炸裂だとすると、こっちは圧縮というか、凝結というか、濃縮というか。
そういう観点での理解が難しいのがウォーホールだろうなどとと思い当たると、今さらながら彼の創作活動が芸術という総体の特異点であったこと、真に革命的であったことなどが分かる。もったいぶった先達とはそのフィールドがまったく違う。言い古されてはいるが絵ではなくイメージ、システム。器官なき身体。偉大なるファイン(ポップ)アート・スゥィンドル。
また、デュシャンの「トランクの箱」とそっくりの質感を持っていて、一目で好きになったのが、今回初めて名前を聞いのであるが、ジョゼフ・コーネル(1903-1972/アメリカ)つー人による一連の「箱+コラージュ作品」。
箱の中にガラスや鏡、雑誌の切り抜き、セルロイド、人形、パイプなどを配置し、遂には宇宙までもを詰め込んだ幾つかの立体作品は、奇妙な郷愁であっという間に僕を魅了してしまったのだ。
奇妙な郷愁…子供の頃、昆虫採集して標本箱を作った時のワクワク感とか、団地のベランダの下にある土を四角く掘ってそこに板を敷き、小さなオモチャや人形なんかをレイアウトした“秘密基地”の悦楽、或いは、子供の頃観た男の子ながらにちょいドキドキした「持ち運び出来るりかちゃんハウス」的な佇まい、と言ってもいい。そんな感覚を強烈に思い出した。先述した「トランクの箱」にもそういうところがある。
「箱は想像力が君臨していた日々の遺宝箱なのだ。むろん箱たちは、子供のころの夢想に立ち戻るよう私たちを誘っている。」
※チャールズ・シミック(コーネルを盲目的に敬愛している詩人)による評論「コーネルの箱」より
----------
小林秀雄は「絵画論」つー好エッセイで、或るゴッホの絵を、画集で観た時にはそんな感覚は起きなかったが、同じ絵の本物を美術館で観た瞬間にその何十号もある画面から薫り立つ生々しい情感に打たれ、何時間もその場に立ち尽くしたと語っていたが、僕にはそんな経験はない。
一緒に行ったハニーは嵯峨美の油絵科出身であり、絵というものが存在の根幹に関わっている部分もあるからか、小林秀雄と同じように、実際の展覧会で或る絵を忘我して眺め続け、気がつくとバーッと泣いていたてなことがあったという。
う〜ん、一度その感じを味わってみたいもんだ。多分、ラジオから流れて来た初めの歌に感じ入り、無心に聴き入ってしまう感じに似ているのかも。
そういや昔、小学生や中学生、いや高校になっても、美術の本に乗っているしかつめらしい(と当時は思えた)巨匠の絵画の数々について、「僕は死ぬまでにこの絵を理解できんのかなー」などと考え「たぶん分かんねーだろーな」などと思ってちょっと悲しくなったりしたが、なんの、その後分かりやすいダリを突破口に、マグリッド、ピカソ、ルオー、ゴッホ、モジリアニ、ベーコン、梅原龍三郎、岡本太郎、ウォーホールと教科書に載っているような有名ドコロにはほぼリスペクトした。いや、分かったとは言わない。感じたのである。子供の頃、岡本太郎の「太陽の塔」に夢中になったのと大差ない感じ方ではあるが。
好き嫌いはある。いや、感じるか感じないか。例えば僕のオヤジは絵が好きで、自らも無数のスケッチを残しており、展覧会となれば出かけて行き、ダリやマグリッドは大好きらしいが、ピカソは受け付けない。この辺り人の嗜好って面白えと思う。僕的には印象派と呼ばれる画家はどうもコナイ。今のところ。
思うに芸術には2つのベクトルがあるのでは。
ひとつは世界をコンパクトに(どれほど号数の大きなカンバスとはいえ)、自分の解釈として取り込み所有しようとする芸術。これはダリやマグリッドなどシュールレアリズムの作家陣。印象派もこっちか。どちらかと言えば静的な芸術。額縁の中に収まり、一種の夢としてそこで完結する絵画。
もうひとつは世界の中で炸裂して粉々になり、そこに小さいながらも風穴を明けて、自分を解放しようとする芸術。動的な芸術。額縁の外にはみ出す、線そのものが枠外へ逃走するような絵画。こちらはピカソやゴッホを筆頭に、ミロなどの多くの抽象作家の他、アンディ・ウォーホールも、システム論的にこちらのように思われる。
もちろんどちらとは言えない折衷的な立場もあるし、大抵の作家はその2つのベクトルを移行しながら創造するのかも知れない。
(ウッディー:07-03.28)
----------
PS/
とか何とか「トランクの箱」と絡めてi-Bookのこと語ってたら、なんと!そのi-Bookがぶっこわれた。「MACアングラ道」てな本に触発されて、ウィンドウズメディアプレイヤーをダウンロードした瞬間から動きがアヤシクなり、システム入れ替えたりしても症状は悪化するばかり。ついに立ち上がらなくなり、アップルストアに相談に行くと、たぶんボード換えなけりゃダメでしょうつーことになってしまった。2001年製G3を中古で買ったやつなんだが、毎日鞄に入れて持ち歩いてても一度も故障しなかっただけにショック。修理は4万5千円程度、データの吸い出し(HDがイカレてなければ)だけでも2万弱かかるらしい。アップルよ、このドンブリ勘定的な修理価格の設定、なんとかなんないの?ストアの雰囲気や対応はイイ感じなのにさー。
------------------------------
「蟲師」
04月01日(日)、寺町のMOVIXにて「蟲師」を観る。
むしし、つってもケンケンの忍び笑いではない(古)。
映画館は予想外にほぼ満席状態で、最前列左右しか空いていない。ちらほら聴こえてくる評価はイマイチなのになんで?と渋々チケットを買って思い出した。2枚で¥1,000!そーか毎月01日は映画の日なのさ。+主演のオダギリジョー人気っつーとこか。原作は女流漫画家・漆原友紀。監督はあの大友克洋らしい。
いや、面白かったよ。途中僕はちょっと寝たけど(画面に近すぎて目廻った)。自然の気や陰陽の力など、あの水木しげるが妖怪(精霊)のカタチを借りて表した森羅万象を司ることどもを、この原作者は空気中に無数に漂う“蟲”の仕業として描いているのだろう。ひょっとして空中生物説が取り沙汰されているUFOや、昨今話題のスカイフィッシュも“蟲”の一種かも?
“蟲師”は全国を行脚しながら、そんな“蟲”どもを駆逐し、制御し、時には操ることで、小さな病気から大病までを治療して報酬を手にする術者である。
まあ、話は濃密なんだけど役者はあっさりし過ぎの感あり。多分たけしの「座頭市」がアリにした、時代劇パツキンで登場する主役のオダギリジョーは、無難な路線で可も不可もなくってとこ。ライフカードのCMのが存在感あるねー。旅の道ずれ役は僕の邦楽フェイバリットのひとつ「ヴァイブレーター」で、あの超濃い寺島しのぶとりっぱにタメはってた大森南朋。脇に徹していい味。しかし、主役のオカン役の江角マキコは…声が「ショムニ」そのままで馴染まないことこの上なし。なんでココに江角マキコなんだろう?
余談だが江角マキコと米倉涼子って何か似てね?存在感的に。
今回、原作者が女性と知ってふと思ったのだが、そもそも分類され、体系化された“妖怪(精霊)”という発想は男性的なのかも。比べて、すべての媒介としてのフワフワとした、一定のカタチを持たない“蟲”は、女性的で秀逸な解釈なのかも知れない。この新しい解釈は興味深い。
(ウッディー:07-04.06)
|
|
|
|
|
|
|
|
ウッディー瓦版/ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ウッディー瓦版/のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人