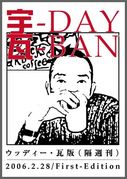去る3月10日(土)夜8時より、中書島のカレーハウス「オアシス」にてアイリー入江が大学時代から今日まで撮りためた8mmフィルム一挙上映会へ。
花園大学在学中「映画研究会」に所属していたアイリー入江は、ルイス・ブニュエルのシュールレアリズム映画やパンクロックのアティテュード、松任谷由美の叙情性等に強く影響を受けた8mm映画を多数制作。自ら脚本、絵コンテ、監督、撮影、現像、編集を手掛けている他、何作かでは主演もこなした。
デジタル機器を使えば撮影や編集が格段に容易となった現代、自らデジタルビデオを購入するにはしたが、それで撮影するのはもっぱら子供の記念映像や自らが関わったライブの記録くらいで、もう10年以上も本格的な映画作品を撮っていないアイリー入江のスタンスからは、闇の中に揺らぎながら浮かぶ、淡い光幕としての映像の質感、輪郭のぼやけたほの明るさ、ジーカタカタという有機的なリールの回転音への偏愛など、アナログな8mm映画というスタイルに対するこだわりが伺える。
また、自らが生まれ育った中書島という幻想的かつ迷路のような街、賽の河原を持つ宇治川の流れる土地、京阪沿線へのあくなき執着も作品の強烈な個性となっている。京阪の宇治川鉄橋は現実と黄泉をつなぐ結界として表現され、彼の映画に頻出する。
----------
さて、京阪「中書島」駅前から駅前商店街を真直ぐ進み、突き当たりの中華料理屋を右に折れてすぐまた左へ折れ、数本目の路地を再度右へ折れて、古いスナックのような(というか、実際古いスナックを改装したに違いあるまい)佇まいのドアを開く。
カウンターも入れておよそ10数帖程の薄ら明るい空間に、見覚えのある顔が並んでいる。「おっ、今日は彼女は?」「来てないの?よかったー、じゃウソつかなくていいのか」「だってアンタ、三十代ってことになってるんでしょ」などなど店に入るといきなりの一斉射撃の的となる。なんでやねん!ちなみにハニーはこの上映会に来たがってはいたのだが、残念ながら休日出勤。
アイリー入江と同級で花園大学の映画研究会のメンバーにして共に8mm映画に傾倒し、アイデアを出したり主演をこなすなど、アイリー作品に関わりの深い原秀樹の他、同じく映画研究会関係者男女数名、この前MICAでタイバンした稲富氏、オットコマエの16才ガイ君など、アイリーファミリー勢揃い。
「オアシス」を経営するのは感じのいい初老の女性。故・寺山修司やその婦人の友人で、自らも「天井桟敷」の構成員であったらしい。以前は新宿ゴールデン街でバーを営んでいたらしく、そこの常連であった各界の著名人にも顔の知られた有名なママであったが、少し前に中書島へと流れて来て(?)このカレーハウスを開いたという。アイリーは彼女を“師匠”と呼び、彼女もまた、近所のMICAでアイリーのライブがあると足を運ぶ、そんな仲のようだ。
実のところ、僕は寺山修司についてほとんど知らない。あの圧倒的なアングラ感と東北特有の“情熱的な暗さ”…違うな…“暗い情熱”と人間的な濃さ(三上寛や友川かずきに代表される)、地に足の付いた(てか、みっちり根を張った)土俗性がこれまで僕を寄せつけなかった。多分近寄ると飲み込まれそうな危険を動物的に感知していたのだろう。唯一、あくまでも前衛ではない「あしたのジョー」の主題歌や、力石徹のテーマの歌詞だけが、僕の中にドロドロと入って来て血肉化していた。(共に寺山修司:作詞)
とはいえ、寺山修司の詩や演劇がアイリーに少なからず影響を与えているのでは…というのは何となくイメージで分かる。ただ、アイリーの作品は楽曲(詩)にしろ映画にしろ、それがいかに寺山風で暗くても(だいたい暗めだが)、根底にはオプティミスムがある、と感じる。僕がアイリー作品に惹かれるのは、その辺りが大きいようだ。
だいたい、僕は“マイナーコード”がベースとなった楽曲が苦手である。マイナーコードはメジャーコードの味付けとしてのみ存在し、マイナーそれ自体の暗い響きを主張し過ぎてはならない。アイリーの楽曲はほとんどがメジャーコードを基調としていることも、詰まるところオプティミスムの為せる技だと思う。
いや…ペシミズムはギリギリのところでオプティミスムへと裏返るのか…あ〜いやだいやだ、も〜世の中ど〜でもい〜か、おもろけりゃ、みたいな。高杉普作いわく「面白きこともなき世を面白く」ってか。
この辺むずかしーよなー。“暗い情熱”“マイナーコード”つえばニルヴァーナがそうなんだけど、あの音楽は例外的に大好きだし。ニルヴァーナのロックンロールはニーチェの言う「悲劇」に似てるんだよねー、どうやら。
----------
…話が反れた。
そう、アイリー入江の8mmフィルム上映会である。カウンターの止まり木でビール片手にビーフカレー(¥800也。うめえよ!)を啜ってると、程なく店内の照明が落とされ、上映会の始まり始まり。
香ばしいカレーとビールの匂いが渦巻く小さな暗がりで、イイ年をした男どもが雁首揃えて正面に仮設された小さな銀幕に目を凝らしている変な風景は、何だか地下組織の密議のようで、その場にいることが奇妙に心地よく、ちょっとワクワク。
アイリー作品は基本的に無声映画なので、原英樹が映写機のスタートボタンを押すのと同時に、アイリー本人が、その前におかれたラジカセのスイッチを入れてBGMを流すという仕組み。「いくで、せ〜のぉ…」“ガチャ”「あっちょおまって、あかんずれた」「まきもどすわ」“カタタタ”「もいっかい、もいっかい」てな調子。メチャアナログではあるがこの感じ、嫌いじゃない。何か懐かしい。
8時から3時間程の内に、おそらく10作品以上がタドタドしい感じで上映されたと思うが、僕はそのほとんど を知っていたにしろ、怪し気でちょっと可愛い上映会の雰囲気をたっぷり愉しませてもらった。
--------------------
さて、自分の映画について、本人のアイリーはこう囁く。(当日配布された本人自筆のパンフレットより)
<本編>上映順不同
「永遠の都」1998年製作/
New Age Production 製作。現在のところ、入江政行の最新作。タイトルは、釘宮君の唄からいただいた。橋を爆破しようと試みる人々の話のようだが、実は単なる中書島の風景映画。この映画は、1998年の2月に出来たわけだが、この映画の前の映画となると、1989年春に製作の、花紀行にさかのぼる。音楽は、釘宮君、野下君、ミュート・ビート。
----------
「花紀行」1989年製作/
ひょつとしたら、入江政行の永遠の最新作に、なっていたかも知れないし、かも知れぬ作品。音楽は、松任谷由美。実は、けっこうユーミンのファンなんだよ。一番好きなアルバムは、パールピアスです。もちろん、ひこうき雲もミスリムも好きだよ。また、好きな歌のベスト3なら、ベルベット・イースター、たぶんあなたはむかえにこない、花紀行、となります。ところで、僕がユーミンのファンだと人に言うと、けっこう、ひんしゅくをかうのはなぜだろうか。
----------
「プラネタリウム」1988年製作/
その昔、読売テレビのCINEMA大好き、というコンテストに出品したのだが、何の反応もなく落選した作品。1988年の花園大学学生会館が映っている。フィルムポエジーですな。原作は須原敬三氏。あの稲冨君のバンド、ドールハウスではベースを担当していました。現在、ギューンカセット代表。ラッキーチャチャチャプロダクション製作。
----------
「未来は霧の中に」1989年製作/
題名通りのこの映画、もはや何も言うことはありません。この映画のワンシーンは、その昔、週刊朝日の巻頭カラーのグラビアに掲載されました。音楽は山口冨士夫の、気をつけろ。ですが、題名はユーミンの歌からいただきました。
----------
「夕焼け番長」1987年製作/
春乱プロダクションの第2回作品。君は、夕焼け番長を見たか!
----------
「花が咲いて」1984年制作/
入江政行が19歳の時に初めて作った8ミリフィルム映画。題はジャックスからいただいた。音楽は、ジャックスと早川義夫。作った時は、シュルレアリスム映画のつもりだったが、今、見ると単なる風景映画かもしれないしかもしれぬ。でも本当は、安易に主人公が自殺してしまうことも含めて青春映画なんだろうと思う。みんな若かったし、これもまた仕方のないことだとも思う。花が咲いて・何かいいことないかな・埋葬の映画三本で初期三部作となっています。
----------
「何かいいことないかな」1984年制作/
入江政行が19歳の夏に、弟と二人で制作した2作目の映画。音楽は、ザ・スターリン。期限切れのフィルム2本で作ったらしく、制作費は1500円ですんだらしい。懐かしい中書島の風景映画。
----------
「埋葬(夜の果ての旅)」1985年制作/
「人々は夕焼けの向こうに明日があると思っているが、今日という日がまたあるだけだ。明日というからには、今日よりいい日を考えてしまうのは僕の幻想だろうか。僕達が明日に出会うためには、長く暗い夜に息を殺して明日を待たなければならない。僕は待ちくたびれてしまったが、僕は待つよりほかに能がない。」実はギャング映画なのだが誰も気づいてくれない。落ちぶれ果てたギャングとヒットマン、そして、あちらとこちらを行き来する謎の男。今となっては、撮影と編集のミスもまた楽しいものです。入江政行19歳最後の作品。
----------
「冬の唄〜ながみやのりこ どこへ行く」1989年製作/
昭和64年1月2日に撮影された8ミリフィルム映画。しかしながら、2007年3月10日カレーハウス・オアシスでの上映会が初上映でした。音楽はNICO。撮影場所は入江の映画ではお馴染の所ばっかり。また、桂川の堤防かと言われても仕方がないし、また、木津川の河川敷かと言われても仕方がない。この風景が好きなのだよ。なお、白い椅子が出てくるが、これはその昔、信楽の陶器祭で買ったのでした。映画だと思わず、窓の外から見えた風景を眺めるという感じで見てください。
--------------------
<未上映>予定されていたが時間不足のため。
「Love Song ☆≡」1987年製作/
「灯りを消せ。俺達が発光体だ。」から始まり、リチャード・ヘルのブランク・ジェネレーションの歌が流れる映画。宇治の花火大会へ梅田君と撮影に行ったのだが彼の名前はどこにも出てこない。この映画、あまり上映の機会にめぐまれず、今までに1〜2回上映されただけかもしれない。ピアノの音楽はエリック・サティ。DEAD END PRODUCTION 製作。
----------
「グッド・バイ」1988年製作/
1988年の夏に1日で撮影。パンを食べる梅田君のシーンは、別の日に10分撮影して終了。映画の中では何の説明もないが、ヤマザキパンの工場で働いていて、その後、音信不通になった友達にひそかに捧げられている。ヤマザキパンの工場の塀の所で、梅田君がヤマザキパンのチョココルネを食べるのもそういうことなのでした。ところが、梅田君の名前はこの映画のクレジットには出てきません。実は入江政行のお気に入りの映画。(ベスト5を選ぶなら、花が咲いて・何かいいことないかな・埋葬・グッドバイ・永遠の都)Pale Blue Eye Pro 製作。
--------------------
<ライブ映像>
「奇妙丸〜ライブ映像」
----------
「蟻地獄〜ライブ映像」
--------------------
なる程。では、僕も何かしら囁いてみよう。
やはり、文句なしに面白いのは「未来は霧の中に」というユーミンの曲名をタイトルにした短編。ほんの10分程ではあるが、山口富士夫の「気をつけろ」をBGMに起用したドライヴ感溢れる好作である。一度観たらたぶん忘れられない。
昭和天皇崩御の翌日、記帳所が設けられた天皇家所縁の古墳(?場所はよく分からない。宇治近辺?)に、頭に天皇崩御の見出付新聞を丸めてスッポリと被り、新聞から切り抜いた甲本ヒロヒト氏(ウソ、単なるヒロヒト氏だよ〜ん)の肖像を張り付けた謎の男が体をくねらせ、ネックに花をあしらったフォークギターをかき鳴らしながら登場。
珍しがって後をついて来た数人の子供をハメルンの笛吹きの如く引き連れ、記帳所へと、古墳正面のだだっぴろく長い石段を、ギターを振りかざし体をのけぞらせながらヨロヨロと登って行く。記帳を終えて降りて来る人は全員ヒキまくり。かまわず登っていく男。気をつけろぉおぉ〜オォ、まっぴらごめんだぜぇ〜〜エェ、ギャギャギャ〜ンン、と炸裂しまくる山口富士夫のボーカル&ギターリフ。
やがて男は石段の上にある神社の境内入り口に辿り着き、立哨していた警官に取り押さえられ、連行されるという顛末。その後、画面は真っ白に燃え上がり「この後、警官に取り囲まれ、撮影中止にされた」というテロップが写される。ただこれだけの映画であるが、タイムリーにしてアナーキーであり、これはアイリーの佳作のひとつであることは間違いない。
謎の男を演じたのはアイリーの弟、入江リョウジ(だと思う)。アイリーは自分の映画の主演に度々弟を起用しており、こういう家内制手工業的な趣きがアイリー作品に妙な濃密さを醸し出しているのでは。
----------
また、僕が“トレインマン”つー役所で出演している「永遠の都」は、現在のところアイリー最後の8mm作品。光る石の破片やハト時計を改造した爆弾など、手製の小物等にもこだわった力の入った作品である。
シュールレアリズム的な造型を持った巨大工場の夕暮れ、その赤い空の破片の様にも見える、オレンジに光る石を手に隠し持った“マントの男”。彼は川の畔に住む“爆弾屋”に、電車の鉄橋を爆破しようとして何度も失敗している(爆発しない!)自作の爆弾の改造を依頼する。
一方、幻想と現実が入れ子状になった街、中書島に流れて来た旅の男“トレインマン”と、そのボストンバッグを狙う“盗人”。やがて迷路のような街の路地裏で4人は遭遇し、ひともんちゃくの後“マントの男”はひょんなことから“トレインマン”のボストンバッグからこぼれた光る石を手に入れる。
“マントの男”は、街を後にした“トレインマン”の乗る電車が鉄橋を渡る刹那に爆破しようと、“爆弾屋”と共に鉄橋のたもとへ。手に入れた光る石を改造した爆弾に接続して鉄橋の足元に仕掛け、急いで堤防の影に身を潜める。電車が鉄橋へと差し掛かる…5,4,3,2,1…やはり爆発しない。やれやれ、といった風情の2人。ここで「ルパン三世vol.1/第4話:脱獄のチャンスは一度」にオマージュを捧げるシーンが挿入され、彼方に堤防の上の細い道路を、幻想と現実の細い隙間から現われた女が自転車に乗って“マントの男”とすれ違い、彼方に奇妙な建物の見える風景の中を遠ざかって行く…。
実は「永遠の都」には僕の“トラベリンマン”というマンガのテイストが採り入れられている。これは、〜オレはトラベリンマン、魂の旅行者だ〜というモノローグで始まる9コマ完結(現在全20話)の変型マンガで、僕がかれこれ20年程も前に描いていたもの。
当時自分のバンドのライブ時に配布する小冊子に載せたり(当時はマックなんてなかったのでコピー&切り張り&コピー!)、大阪のフリーペーパー「ジャングルライフ」や、京都のフリーペーパー「中村コーエン兄弟」にも何度か採用され、今だにミクシー内の「ウッディー漫画館」にアップされている息の長いつーか使い廻し的な作品である。ちなみに「ナニワ金融道」の故・青木雄二が“トラベリンマン”を評価したというのは有名な話だ(?)。
魂の旅行者である麦わら帽子の痩せた男、“トラベリンマン”は、ボストンバッグの中に石をぎっしり詰めて持ち歩いていて、第一話で盗人がこのボストンバッグをひったくるのだが、ボストンバッグの設定とこのシーンは、そのまま「永遠の都」活かされている。ちょっとうれしい。
※本号から始まる連載コミック「トラベリンマン」に、この第一話を掲載。
多分アイリーは“トラベリンマン”を間違って“トレインマン”と命名したのだろう。“トレインマン=電車男!”つー語感も、なかなかいいと思うけどねー。
----------
また、映画作品に混じって2本のライブ映像が流され、その内の一本は僕がかれこれ10年以上も前に組んでいた“奇妙丸”の拾得での演奏風景であった。アイリーの「パラノイアスター」を演奏しており、BGMには実際の演奏を納めたカセットが流された。
----------
ところで、アイリー作品の出演者はほぼ全員がサングラスを掛けている。やけにバカでかい形状のとか一時期流行ってた丸いのとか。つまり、アイリーの映画では、役者は目の前に小さな闇を張り付けて演技しているって訳だ。
目の前の闇としてのサングラスには何か特別なフォース(力)、魔法がある、そんな気がする。こういうことではないだろうか。8mm映像の光幕を浮かび上がらせる闇と、目の前に浮かぶサングラス小さな闇は、魔法の渦巻く場として内側と外側から相似形を成しているのではなかろうか。今僕が言ったことは訳が分からないが詩的である。それでいいのだ。
僕がカッコイイと思ったベスト“サングラッサー賞”はなんたって、ジョニー・ロットン。盲人用の小さなサングラスがメチャクチャカッコよかった。そーいやビートたけしも自分が主役やる時は小さなサングラスしてるよねー。あれもカッコイイ。座頭市の時はサングラスならぬ盲目だったけど。
…そう、サングラス。最近は街でもめったに見なくなったけどねー。 …グラサンを掛けよう、町へ出よう。←テラヤマツナガリ。
(ウッディー:07-0402)
花園大学在学中「映画研究会」に所属していたアイリー入江は、ルイス・ブニュエルのシュールレアリズム映画やパンクロックのアティテュード、松任谷由美の叙情性等に強く影響を受けた8mm映画を多数制作。自ら脚本、絵コンテ、監督、撮影、現像、編集を手掛けている他、何作かでは主演もこなした。
デジタル機器を使えば撮影や編集が格段に容易となった現代、自らデジタルビデオを購入するにはしたが、それで撮影するのはもっぱら子供の記念映像や自らが関わったライブの記録くらいで、もう10年以上も本格的な映画作品を撮っていないアイリー入江のスタンスからは、闇の中に揺らぎながら浮かぶ、淡い光幕としての映像の質感、輪郭のぼやけたほの明るさ、ジーカタカタという有機的なリールの回転音への偏愛など、アナログな8mm映画というスタイルに対するこだわりが伺える。
また、自らが生まれ育った中書島という幻想的かつ迷路のような街、賽の河原を持つ宇治川の流れる土地、京阪沿線へのあくなき執着も作品の強烈な個性となっている。京阪の宇治川鉄橋は現実と黄泉をつなぐ結界として表現され、彼の映画に頻出する。
----------
さて、京阪「中書島」駅前から駅前商店街を真直ぐ進み、突き当たりの中華料理屋を右に折れてすぐまた左へ折れ、数本目の路地を再度右へ折れて、古いスナックのような(というか、実際古いスナックを改装したに違いあるまい)佇まいのドアを開く。
カウンターも入れておよそ10数帖程の薄ら明るい空間に、見覚えのある顔が並んでいる。「おっ、今日は彼女は?」「来てないの?よかったー、じゃウソつかなくていいのか」「だってアンタ、三十代ってことになってるんでしょ」などなど店に入るといきなりの一斉射撃の的となる。なんでやねん!ちなみにハニーはこの上映会に来たがってはいたのだが、残念ながら休日出勤。
アイリー入江と同級で花園大学の映画研究会のメンバーにして共に8mm映画に傾倒し、アイデアを出したり主演をこなすなど、アイリー作品に関わりの深い原秀樹の他、同じく映画研究会関係者男女数名、この前MICAでタイバンした稲富氏、オットコマエの16才ガイ君など、アイリーファミリー勢揃い。
「オアシス」を経営するのは感じのいい初老の女性。故・寺山修司やその婦人の友人で、自らも「天井桟敷」の構成員であったらしい。以前は新宿ゴールデン街でバーを営んでいたらしく、そこの常連であった各界の著名人にも顔の知られた有名なママであったが、少し前に中書島へと流れて来て(?)このカレーハウスを開いたという。アイリーは彼女を“師匠”と呼び、彼女もまた、近所のMICAでアイリーのライブがあると足を運ぶ、そんな仲のようだ。
実のところ、僕は寺山修司についてほとんど知らない。あの圧倒的なアングラ感と東北特有の“情熱的な暗さ”…違うな…“暗い情熱”と人間的な濃さ(三上寛や友川かずきに代表される)、地に足の付いた(てか、みっちり根を張った)土俗性がこれまで僕を寄せつけなかった。多分近寄ると飲み込まれそうな危険を動物的に感知していたのだろう。唯一、あくまでも前衛ではない「あしたのジョー」の主題歌や、力石徹のテーマの歌詞だけが、僕の中にドロドロと入って来て血肉化していた。(共に寺山修司:作詞)
とはいえ、寺山修司の詩や演劇がアイリーに少なからず影響を与えているのでは…というのは何となくイメージで分かる。ただ、アイリーの作品は楽曲(詩)にしろ映画にしろ、それがいかに寺山風で暗くても(だいたい暗めだが)、根底にはオプティミスムがある、と感じる。僕がアイリー作品に惹かれるのは、その辺りが大きいようだ。
だいたい、僕は“マイナーコード”がベースとなった楽曲が苦手である。マイナーコードはメジャーコードの味付けとしてのみ存在し、マイナーそれ自体の暗い響きを主張し過ぎてはならない。アイリーの楽曲はほとんどがメジャーコードを基調としていることも、詰まるところオプティミスムの為せる技だと思う。
いや…ペシミズムはギリギリのところでオプティミスムへと裏返るのか…あ〜いやだいやだ、も〜世の中ど〜でもい〜か、おもろけりゃ、みたいな。高杉普作いわく「面白きこともなき世を面白く」ってか。
この辺むずかしーよなー。“暗い情熱”“マイナーコード”つえばニルヴァーナがそうなんだけど、あの音楽は例外的に大好きだし。ニルヴァーナのロックンロールはニーチェの言う「悲劇」に似てるんだよねー、どうやら。
----------
…話が反れた。
そう、アイリー入江の8mmフィルム上映会である。カウンターの止まり木でビール片手にビーフカレー(¥800也。うめえよ!)を啜ってると、程なく店内の照明が落とされ、上映会の始まり始まり。
香ばしいカレーとビールの匂いが渦巻く小さな暗がりで、イイ年をした男どもが雁首揃えて正面に仮設された小さな銀幕に目を凝らしている変な風景は、何だか地下組織の密議のようで、その場にいることが奇妙に心地よく、ちょっとワクワク。
アイリー作品は基本的に無声映画なので、原英樹が映写機のスタートボタンを押すのと同時に、アイリー本人が、その前におかれたラジカセのスイッチを入れてBGMを流すという仕組み。「いくで、せ〜のぉ…」“ガチャ”「あっちょおまって、あかんずれた」「まきもどすわ」“カタタタ”「もいっかい、もいっかい」てな調子。メチャアナログではあるがこの感じ、嫌いじゃない。何か懐かしい。
8時から3時間程の内に、おそらく10作品以上がタドタドしい感じで上映されたと思うが、僕はそのほとんど を知っていたにしろ、怪し気でちょっと可愛い上映会の雰囲気をたっぷり愉しませてもらった。
--------------------
さて、自分の映画について、本人のアイリーはこう囁く。(当日配布された本人自筆のパンフレットより)
<本編>上映順不同
「永遠の都」1998年製作/
New Age Production 製作。現在のところ、入江政行の最新作。タイトルは、釘宮君の唄からいただいた。橋を爆破しようと試みる人々の話のようだが、実は単なる中書島の風景映画。この映画は、1998年の2月に出来たわけだが、この映画の前の映画となると、1989年春に製作の、花紀行にさかのぼる。音楽は、釘宮君、野下君、ミュート・ビート。
----------
「花紀行」1989年製作/
ひょつとしたら、入江政行の永遠の最新作に、なっていたかも知れないし、かも知れぬ作品。音楽は、松任谷由美。実は、けっこうユーミンのファンなんだよ。一番好きなアルバムは、パールピアスです。もちろん、ひこうき雲もミスリムも好きだよ。また、好きな歌のベスト3なら、ベルベット・イースター、たぶんあなたはむかえにこない、花紀行、となります。ところで、僕がユーミンのファンだと人に言うと、けっこう、ひんしゅくをかうのはなぜだろうか。
----------
「プラネタリウム」1988年製作/
その昔、読売テレビのCINEMA大好き、というコンテストに出品したのだが、何の反応もなく落選した作品。1988年の花園大学学生会館が映っている。フィルムポエジーですな。原作は須原敬三氏。あの稲冨君のバンド、ドールハウスではベースを担当していました。現在、ギューンカセット代表。ラッキーチャチャチャプロダクション製作。
----------
「未来は霧の中に」1989年製作/
題名通りのこの映画、もはや何も言うことはありません。この映画のワンシーンは、その昔、週刊朝日の巻頭カラーのグラビアに掲載されました。音楽は山口冨士夫の、気をつけろ。ですが、題名はユーミンの歌からいただきました。
----------
「夕焼け番長」1987年製作/
春乱プロダクションの第2回作品。君は、夕焼け番長を見たか!
----------
「花が咲いて」1984年制作/
入江政行が19歳の時に初めて作った8ミリフィルム映画。題はジャックスからいただいた。音楽は、ジャックスと早川義夫。作った時は、シュルレアリスム映画のつもりだったが、今、見ると単なる風景映画かもしれないしかもしれぬ。でも本当は、安易に主人公が自殺してしまうことも含めて青春映画なんだろうと思う。みんな若かったし、これもまた仕方のないことだとも思う。花が咲いて・何かいいことないかな・埋葬の映画三本で初期三部作となっています。
----------
「何かいいことないかな」1984年制作/
入江政行が19歳の夏に、弟と二人で制作した2作目の映画。音楽は、ザ・スターリン。期限切れのフィルム2本で作ったらしく、制作費は1500円ですんだらしい。懐かしい中書島の風景映画。
----------
「埋葬(夜の果ての旅)」1985年制作/
「人々は夕焼けの向こうに明日があると思っているが、今日という日がまたあるだけだ。明日というからには、今日よりいい日を考えてしまうのは僕の幻想だろうか。僕達が明日に出会うためには、長く暗い夜に息を殺して明日を待たなければならない。僕は待ちくたびれてしまったが、僕は待つよりほかに能がない。」実はギャング映画なのだが誰も気づいてくれない。落ちぶれ果てたギャングとヒットマン、そして、あちらとこちらを行き来する謎の男。今となっては、撮影と編集のミスもまた楽しいものです。入江政行19歳最後の作品。
----------
「冬の唄〜ながみやのりこ どこへ行く」1989年製作/
昭和64年1月2日に撮影された8ミリフィルム映画。しかしながら、2007年3月10日カレーハウス・オアシスでの上映会が初上映でした。音楽はNICO。撮影場所は入江の映画ではお馴染の所ばっかり。また、桂川の堤防かと言われても仕方がないし、また、木津川の河川敷かと言われても仕方がない。この風景が好きなのだよ。なお、白い椅子が出てくるが、これはその昔、信楽の陶器祭で買ったのでした。映画だと思わず、窓の外から見えた風景を眺めるという感じで見てください。
--------------------
<未上映>予定されていたが時間不足のため。
「Love Song ☆≡」1987年製作/
「灯りを消せ。俺達が発光体だ。」から始まり、リチャード・ヘルのブランク・ジェネレーションの歌が流れる映画。宇治の花火大会へ梅田君と撮影に行ったのだが彼の名前はどこにも出てこない。この映画、あまり上映の機会にめぐまれず、今までに1〜2回上映されただけかもしれない。ピアノの音楽はエリック・サティ。DEAD END PRODUCTION 製作。
----------
「グッド・バイ」1988年製作/
1988年の夏に1日で撮影。パンを食べる梅田君のシーンは、別の日に10分撮影して終了。映画の中では何の説明もないが、ヤマザキパンの工場で働いていて、その後、音信不通になった友達にひそかに捧げられている。ヤマザキパンの工場の塀の所で、梅田君がヤマザキパンのチョココルネを食べるのもそういうことなのでした。ところが、梅田君の名前はこの映画のクレジットには出てきません。実は入江政行のお気に入りの映画。(ベスト5を選ぶなら、花が咲いて・何かいいことないかな・埋葬・グッドバイ・永遠の都)Pale Blue Eye Pro 製作。
--------------------
<ライブ映像>
「奇妙丸〜ライブ映像」
----------
「蟻地獄〜ライブ映像」
--------------------
なる程。では、僕も何かしら囁いてみよう。
やはり、文句なしに面白いのは「未来は霧の中に」というユーミンの曲名をタイトルにした短編。ほんの10分程ではあるが、山口富士夫の「気をつけろ」をBGMに起用したドライヴ感溢れる好作である。一度観たらたぶん忘れられない。
昭和天皇崩御の翌日、記帳所が設けられた天皇家所縁の古墳(?場所はよく分からない。宇治近辺?)に、頭に天皇崩御の見出付新聞を丸めてスッポリと被り、新聞から切り抜いた甲本ヒロヒト氏(ウソ、単なるヒロヒト氏だよ〜ん)の肖像を張り付けた謎の男が体をくねらせ、ネックに花をあしらったフォークギターをかき鳴らしながら登場。
珍しがって後をついて来た数人の子供をハメルンの笛吹きの如く引き連れ、記帳所へと、古墳正面のだだっぴろく長い石段を、ギターを振りかざし体をのけぞらせながらヨロヨロと登って行く。記帳を終えて降りて来る人は全員ヒキまくり。かまわず登っていく男。気をつけろぉおぉ〜オォ、まっぴらごめんだぜぇ〜〜エェ、ギャギャギャ〜ンン、と炸裂しまくる山口富士夫のボーカル&ギターリフ。
やがて男は石段の上にある神社の境内入り口に辿り着き、立哨していた警官に取り押さえられ、連行されるという顛末。その後、画面は真っ白に燃え上がり「この後、警官に取り囲まれ、撮影中止にされた」というテロップが写される。ただこれだけの映画であるが、タイムリーにしてアナーキーであり、これはアイリーの佳作のひとつであることは間違いない。
謎の男を演じたのはアイリーの弟、入江リョウジ(だと思う)。アイリーは自分の映画の主演に度々弟を起用しており、こういう家内制手工業的な趣きがアイリー作品に妙な濃密さを醸し出しているのでは。
----------
また、僕が“トレインマン”つー役所で出演している「永遠の都」は、現在のところアイリー最後の8mm作品。光る石の破片やハト時計を改造した爆弾など、手製の小物等にもこだわった力の入った作品である。
シュールレアリズム的な造型を持った巨大工場の夕暮れ、その赤い空の破片の様にも見える、オレンジに光る石を手に隠し持った“マントの男”。彼は川の畔に住む“爆弾屋”に、電車の鉄橋を爆破しようとして何度も失敗している(爆発しない!)自作の爆弾の改造を依頼する。
一方、幻想と現実が入れ子状になった街、中書島に流れて来た旅の男“トレインマン”と、そのボストンバッグを狙う“盗人”。やがて迷路のような街の路地裏で4人は遭遇し、ひともんちゃくの後“マントの男”はひょんなことから“トレインマン”のボストンバッグからこぼれた光る石を手に入れる。
“マントの男”は、街を後にした“トレインマン”の乗る電車が鉄橋を渡る刹那に爆破しようと、“爆弾屋”と共に鉄橋のたもとへ。手に入れた光る石を改造した爆弾に接続して鉄橋の足元に仕掛け、急いで堤防の影に身を潜める。電車が鉄橋へと差し掛かる…5,4,3,2,1…やはり爆発しない。やれやれ、といった風情の2人。ここで「ルパン三世vol.1/第4話:脱獄のチャンスは一度」にオマージュを捧げるシーンが挿入され、彼方に堤防の上の細い道路を、幻想と現実の細い隙間から現われた女が自転車に乗って“マントの男”とすれ違い、彼方に奇妙な建物の見える風景の中を遠ざかって行く…。
実は「永遠の都」には僕の“トラベリンマン”というマンガのテイストが採り入れられている。これは、〜オレはトラベリンマン、魂の旅行者だ〜というモノローグで始まる9コマ完結(現在全20話)の変型マンガで、僕がかれこれ20年程も前に描いていたもの。
当時自分のバンドのライブ時に配布する小冊子に載せたり(当時はマックなんてなかったのでコピー&切り張り&コピー!)、大阪のフリーペーパー「ジャングルライフ」や、京都のフリーペーパー「中村コーエン兄弟」にも何度か採用され、今だにミクシー内の「ウッディー漫画館」にアップされている息の長いつーか使い廻し的な作品である。ちなみに「ナニワ金融道」の故・青木雄二が“トラベリンマン”を評価したというのは有名な話だ(?)。
魂の旅行者である麦わら帽子の痩せた男、“トラベリンマン”は、ボストンバッグの中に石をぎっしり詰めて持ち歩いていて、第一話で盗人がこのボストンバッグをひったくるのだが、ボストンバッグの設定とこのシーンは、そのまま「永遠の都」活かされている。ちょっとうれしい。
※本号から始まる連載コミック「トラベリンマン」に、この第一話を掲載。
多分アイリーは“トラベリンマン”を間違って“トレインマン”と命名したのだろう。“トレインマン=電車男!”つー語感も、なかなかいいと思うけどねー。
----------
また、映画作品に混じって2本のライブ映像が流され、その内の一本は僕がかれこれ10年以上も前に組んでいた“奇妙丸”の拾得での演奏風景であった。アイリーの「パラノイアスター」を演奏しており、BGMには実際の演奏を納めたカセットが流された。
----------
ところで、アイリー作品の出演者はほぼ全員がサングラスを掛けている。やけにバカでかい形状のとか一時期流行ってた丸いのとか。つまり、アイリーの映画では、役者は目の前に小さな闇を張り付けて演技しているって訳だ。
目の前の闇としてのサングラスには何か特別なフォース(力)、魔法がある、そんな気がする。こういうことではないだろうか。8mm映像の光幕を浮かび上がらせる闇と、目の前に浮かぶサングラス小さな闇は、魔法の渦巻く場として内側と外側から相似形を成しているのではなかろうか。今僕が言ったことは訳が分からないが詩的である。それでいいのだ。
僕がカッコイイと思ったベスト“サングラッサー賞”はなんたって、ジョニー・ロットン。盲人用の小さなサングラスがメチャクチャカッコよかった。そーいやビートたけしも自分が主役やる時は小さなサングラスしてるよねー。あれもカッコイイ。座頭市の時はサングラスならぬ盲目だったけど。
…そう、サングラス。最近は街でもめったに見なくなったけどねー。 …グラサンを掛けよう、町へ出よう。←テラヤマツナガリ。
(ウッディー:07-0402)
|
|
|
|
|
|
|
|
ウッディー瓦版/ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ウッディー瓦版/のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37863人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人