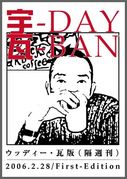10月末の日曜日、ハニーに誘われ京都近代美術館まで“プライス・コレクション「若冲と江戸絵画展」”つー展覧会を観に行った。プライス〜てな冠が付くので“絵画たたき売り”の感もあったが、プライスさんつー大金持ちのアメリカ人が収集した日本画のコレクション大公開〜ってな催しらしい。
正直言って、僕は江戸絵画を始め浮世絵や墨絵など、日本の伝統芸術に興味らしい興味を持ったことはこれまで一度もなかった。まだ“書”なんかの方に面白みを感じていたような気がする。
しかし、今回、半ば付き合いで観た「若冲と江戸絵画展」は予想GUYに面白く、美術館内を歩いている間中、そして、後日に至るまで、僕は頭の中を巡る無知蒙昧な思索と戯れ続けた。無知蒙昧な思索というのは、そもそも僕は日本画の歴史や系譜にはゼンゼンウトく、催しの冠にもなっている画人、伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)という名前さえ初耳だったし、他の作家にしろ、写楽や北斎、円山応挙など、大メジャーどころしか知らず、しかも、それにしたってほんの僅かな情報しか持っていないという点に於いてだ。
さて、タイトル通りにこの展覧会の中枢をなすのは伊藤若冲の作品群であるが、この画人の筆による、数枚の衝立に一筆入魂の勢いで描かれた鮮烈かつ滑らかな曲線と、変にリアルでコミカルな表情が印象的な鶴の連作(本文下の画像)は、大いに僕の興味を引いたのである。
無論、展示されている若冲の画は、この鶴の連作のように、筆の勢いで描かれたシンプルものよりも、百科事典の図録のように緻密に描き込まれ、絢爛たる、または、燻し銀のような着色が成された(上の3作品のような)ものの方が多かったが、若冲以外の作品をも含めて、僕が気になったのは線、である。
今更のようであるが線、なのだ。若冲の描く鶴の丸い体の線、細い嘴の線、繊細な起伏に富んだ脚の爪先の線。また、長沢蘆雪(ながさわろせつ)という人による、大きな画面いっぱいに描かれた巨大な象を描く線、巨大な虎を描く線。浮世絵や版画の、絢爛たる色を区切り、閉じ込める多種多様、縦横無尽に画面を走る線…。伸びやかな曲線、ぎくしゃくとした表情のある線、木の枝を、松葉を描く引っ掻くような線…。
一色一色を、つまり多種多様な光を丹念に塗り重ねて世界を構築していく一般的な西洋絵画とは違って、まずはこの世界を線で区切り、分割してモノの形を切り取り、浮かび上がらせる我が国古来の描画手法を、僕は今回の展覧会で改めて再確認したのだ。余り興味のなかった日本の伝統芸術の中でも、僕が結構好きだった棟方志功の版画や円空の彫刻なども、よく考えてみればどちらもその骨格は線、デアル。
円空なんて彫刻、つまり立体なのに主役は線なんだからムチャクチャだよなー。そう言えば太古の縄文土器なんかも、立体にして主役は線…いや、あれは文様か。
そう、我が国の芸術の主役は光ではなく線、である。モノの形をパッと捉え、その筆の勢いのまま表出させる、後には痕跡としての線が残る…。それは、形を写し取るのではなく、そのものの形そのものが持つ聖なる勢い、存在のスピードを絵筆で絡め取り紙へと投げ付け、再生する行為のようにも思える。“形”の再生ではなく“勢い”の再生…西洋絵画で近いことをやったのはピカソか、はたまたゴッホか。思うに、一本ビシャッと引かれる線は、その瞬間にビシャッと感じた証である。ドゥルーズの言う“逃走の線”ってやつかも。
ところで、今述べたように目に見えるものを光の積み重ねではなく、線の区切り、勢いとして捉えた我が国古来の精神は、実は平成の今の世にも脈々と受け継がれ、未だ現代に通用する表現法としてその確固たる地位を固持している。
“マンガ”がそれだ。そう、手塚治虫を始祖として以来日本独自の進化を遂げ、このデジタル全盛の世の中においても膨大な需要を誇り、その水準の高さを世界中が認める我が国の二次元・アナログマンガは、おそらくこの日、僕が観た江戸絵画の最新の発展型であり、動的な線(ピアズリーの様な静的かつ繊細な線ではなく)を骨格とした芸術の最たるものなのである。しかも基本モノクロ、ツートンカラーなのがスゴイ。まさに墨絵の域だ。
例えば、僕はその絵の前で頭がクラッとしたのであるが、超有名どころである円山応挙が描いた深山に落つる滝…その寂々たる幽玄の世界図は、空間構成的に近代以降の漫画のコマ割の感性とどこかで通じ合っている気がした。
まあ、“漫画”という言葉は岩波国語辞典で検索すれば“単純軽妙な手法で描かれ、こっけい味・風刺などをこめ、ある程度の誇張をともなう絵”とあり、北斎辺りまで行けば完璧な漫画だ、と言うのは多くの人が認めるところであるが、僕が言うのはそういう“漫画”ではなく、現代のストーリー“マンガ”である。若冲の方法がダイレクトに手塚治虫へ、松本零士へ、さらに井上雄彦にまで繋がっている、と言いたいのだ。
若冲の絵は、この前神戸の展覧会で観た“ジャコメッティ”の座右の銘らしい“観えるがままに描く”を超え、“刹那を、感じたままに描く”というのに近い。“観えるがままに描く”と線は増え、“刹感じたままに描く”と線は減る、そんな感じか。
線は一瞬で引ける、だから刹那を、その“気”を採らまえることが出来る。そいういうことなのだが、それとは別に、ふと観た庭の鶏があたかも鳳凰の如く見えることもあるだろう。ひとつの生き物とは、例えそれが一羽の鶏であっても、一匹のノミであっても、存在として実はどこかしら怪物的なものなのだ。生きるということの、それに伴う動きや形態の謎めき。そこで今度は、その鶏が鳳凰に見えた刹那を取らまえて描く。ジッと見詰め続ければ「なあんだ、鶏か」てなことになるに違いないのだが、「うおっ、鳳凰!?」と見まごうた刹那を、その勢いを、垣間見えた怪物性を描く。
この場合は単純な線のみでの表現は難しい。鳳凰の複雑な意匠、細部への描き込みと丹念な着色が必要だ。しかしながら、それらの要素を包み込み、支え、加速させるのは目まぐるしく、網の目の如く張り巡らされた、流れる線のスピード感である。百科事典の図録の様な若冲の細密画からは、そんな印象を受けた。
マンガ繋がりで言えば、上記画像中央の若冲の鶏の絵は、谷岡ヤスジの「アーサーッ!!」の元ネタではあるまいか。見張りのおばちゃんがいなければ太陽の横にマジックで大きく「アーサーッ!!」と書いてやりたい衝動に駆られてしまった。
最小限の線でソンという宇宙を描き切る大天才、ヤスジ御大が、同じく大天才、若冲を知っており、その影響を受けていたとしても全然不思議ではない。
僕にとってヤスジと若冲はキレイに並び立つ両雄である。ジャンジャン。
(ウッディー:06-11/01)
正直言って、僕は江戸絵画を始め浮世絵や墨絵など、日本の伝統芸術に興味らしい興味を持ったことはこれまで一度もなかった。まだ“書”なんかの方に面白みを感じていたような気がする。
しかし、今回、半ば付き合いで観た「若冲と江戸絵画展」は予想GUYに面白く、美術館内を歩いている間中、そして、後日に至るまで、僕は頭の中を巡る無知蒙昧な思索と戯れ続けた。無知蒙昧な思索というのは、そもそも僕は日本画の歴史や系譜にはゼンゼンウトく、催しの冠にもなっている画人、伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)という名前さえ初耳だったし、他の作家にしろ、写楽や北斎、円山応挙など、大メジャーどころしか知らず、しかも、それにしたってほんの僅かな情報しか持っていないという点に於いてだ。
さて、タイトル通りにこの展覧会の中枢をなすのは伊藤若冲の作品群であるが、この画人の筆による、数枚の衝立に一筆入魂の勢いで描かれた鮮烈かつ滑らかな曲線と、変にリアルでコミカルな表情が印象的な鶴の連作(本文下の画像)は、大いに僕の興味を引いたのである。
無論、展示されている若冲の画は、この鶴の連作のように、筆の勢いで描かれたシンプルものよりも、百科事典の図録のように緻密に描き込まれ、絢爛たる、または、燻し銀のような着色が成された(上の3作品のような)ものの方が多かったが、若冲以外の作品をも含めて、僕が気になったのは線、である。
今更のようであるが線、なのだ。若冲の描く鶴の丸い体の線、細い嘴の線、繊細な起伏に富んだ脚の爪先の線。また、長沢蘆雪(ながさわろせつ)という人による、大きな画面いっぱいに描かれた巨大な象を描く線、巨大な虎を描く線。浮世絵や版画の、絢爛たる色を区切り、閉じ込める多種多様、縦横無尽に画面を走る線…。伸びやかな曲線、ぎくしゃくとした表情のある線、木の枝を、松葉を描く引っ掻くような線…。
一色一色を、つまり多種多様な光を丹念に塗り重ねて世界を構築していく一般的な西洋絵画とは違って、まずはこの世界を線で区切り、分割してモノの形を切り取り、浮かび上がらせる我が国古来の描画手法を、僕は今回の展覧会で改めて再確認したのだ。余り興味のなかった日本の伝統芸術の中でも、僕が結構好きだった棟方志功の版画や円空の彫刻なども、よく考えてみればどちらもその骨格は線、デアル。
円空なんて彫刻、つまり立体なのに主役は線なんだからムチャクチャだよなー。そう言えば太古の縄文土器なんかも、立体にして主役は線…いや、あれは文様か。
そう、我が国の芸術の主役は光ではなく線、である。モノの形をパッと捉え、その筆の勢いのまま表出させる、後には痕跡としての線が残る…。それは、形を写し取るのではなく、そのものの形そのものが持つ聖なる勢い、存在のスピードを絵筆で絡め取り紙へと投げ付け、再生する行為のようにも思える。“形”の再生ではなく“勢い”の再生…西洋絵画で近いことをやったのはピカソか、はたまたゴッホか。思うに、一本ビシャッと引かれる線は、その瞬間にビシャッと感じた証である。ドゥルーズの言う“逃走の線”ってやつかも。
ところで、今述べたように目に見えるものを光の積み重ねではなく、線の区切り、勢いとして捉えた我が国古来の精神は、実は平成の今の世にも脈々と受け継がれ、未だ現代に通用する表現法としてその確固たる地位を固持している。
“マンガ”がそれだ。そう、手塚治虫を始祖として以来日本独自の進化を遂げ、このデジタル全盛の世の中においても膨大な需要を誇り、その水準の高さを世界中が認める我が国の二次元・アナログマンガは、おそらくこの日、僕が観た江戸絵画の最新の発展型であり、動的な線(ピアズリーの様な静的かつ繊細な線ではなく)を骨格とした芸術の最たるものなのである。しかも基本モノクロ、ツートンカラーなのがスゴイ。まさに墨絵の域だ。
例えば、僕はその絵の前で頭がクラッとしたのであるが、超有名どころである円山応挙が描いた深山に落つる滝…その寂々たる幽玄の世界図は、空間構成的に近代以降の漫画のコマ割の感性とどこかで通じ合っている気がした。
まあ、“漫画”という言葉は岩波国語辞典で検索すれば“単純軽妙な手法で描かれ、こっけい味・風刺などをこめ、ある程度の誇張をともなう絵”とあり、北斎辺りまで行けば完璧な漫画だ、と言うのは多くの人が認めるところであるが、僕が言うのはそういう“漫画”ではなく、現代のストーリー“マンガ”である。若冲の方法がダイレクトに手塚治虫へ、松本零士へ、さらに井上雄彦にまで繋がっている、と言いたいのだ。
若冲の絵は、この前神戸の展覧会で観た“ジャコメッティ”の座右の銘らしい“観えるがままに描く”を超え、“刹那を、感じたままに描く”というのに近い。“観えるがままに描く”と線は増え、“刹感じたままに描く”と線は減る、そんな感じか。
線は一瞬で引ける、だから刹那を、その“気”を採らまえることが出来る。そいういうことなのだが、それとは別に、ふと観た庭の鶏があたかも鳳凰の如く見えることもあるだろう。ひとつの生き物とは、例えそれが一羽の鶏であっても、一匹のノミであっても、存在として実はどこかしら怪物的なものなのだ。生きるということの、それに伴う動きや形態の謎めき。そこで今度は、その鶏が鳳凰に見えた刹那を取らまえて描く。ジッと見詰め続ければ「なあんだ、鶏か」てなことになるに違いないのだが、「うおっ、鳳凰!?」と見まごうた刹那を、その勢いを、垣間見えた怪物性を描く。
この場合は単純な線のみでの表現は難しい。鳳凰の複雑な意匠、細部への描き込みと丹念な着色が必要だ。しかしながら、それらの要素を包み込み、支え、加速させるのは目まぐるしく、網の目の如く張り巡らされた、流れる線のスピード感である。百科事典の図録の様な若冲の細密画からは、そんな印象を受けた。
マンガ繋がりで言えば、上記画像中央の若冲の鶏の絵は、谷岡ヤスジの「アーサーッ!!」の元ネタではあるまいか。見張りのおばちゃんがいなければ太陽の横にマジックで大きく「アーサーッ!!」と書いてやりたい衝動に駆られてしまった。
最小限の線でソンという宇宙を描き切る大天才、ヤスジ御大が、同じく大天才、若冲を知っており、その影響を受けていたとしても全然不思議ではない。
僕にとってヤスジと若冲はキレイに並び立つ両雄である。ジャンジャン。
(ウッディー:06-11/01)
|
|
|
|
コメント(1)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ウッディー瓦版/ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ウッディー瓦版/のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人