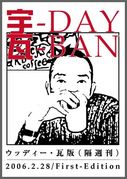“ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。(鴨長明「方丈記」)”
テクノやハウスなど、単調なリズムの反復を基本とするデジタルな音楽は、和風に言えば“ゆく河の流れ”に似ている。
いつ終わるとも知れず延々と反復されるブッといリズムは一見、単調に聴こえ、だからテクノやハウスはどうも退屈で…という輩も多いだろう。が、この単調なリズムが全体を貫いているからこそ、そこにあたかも一本の河を点景とするような壮大な音のランドスケープが生まれ、その安定感に乗っかって、リズムの奔流から細部に至る目まぐるしい変化や様々な音響のカット・アップと戯れ、共に揺れ、漂うことが出来るのである。
反復するリズム以外の音素は、まさに浮かび、消え、結ぶうたかたのようだ。それはさながら一本の河を取り巻く水流の音や水面の輝き、水の匂い、鳥の囀りや虫の鳴き声に似ているのかも知れない。
一本の河とそれを取り巻く自然のサウンド…ってか。普段なら僕的にはあんま好きでもない話だ。しかしながら、テクノにしろハウスにしろ、実は思いの他、オーガニックな音楽のように思えたりする(僕の好きなものはそうだ)。あのミニマル・テクノの雄、ジェフミルズが炸裂させる燻し銀の如きマシンナーズ・サウンドでさえもが、金属的でありながらどこか柔らかく、そして温かい。それも、ある種のロックのようにやたらに熱くはなく、人肌を思わせるナマ温かさである。
その感覚は僕が冒頭で「方丈記」になぞらえたように、テクノやハウスが絶え間なく、しかし淡々と流れる“ゆく河の流れ”のようなイメージを第一印象とする音楽であることと無関係ではないだろう。もちろん、大抵のDJプレイには途中に何度かのハイライトが仕掛けられており、その盛り上がりは仄暗いフロアになくてはならないものには違いないが、そもそもDJによるパーティーそのものが、多くのロックやロックンロール、クラシックに比べると遙かに淡々とした、言ってみれば地味なものであると言える。
しかしながら僕にとっては仄暗いフロアで司祭のようなDJによってプレイされるこれらの音楽の淡々とした流れ、ナマ温かさ、地味さは実に心地がよい。そこにはコマーシャル(営利的)なものからは程遠いコマーシャル(業務的)な音がある。
いや、営利的であることが悪い訳では全然ない。才能あるアーティストがいて、そいつが造る音楽は才能にあふれているので売れて当然であり、不可避的に営利的であるということになる。そうではなくて、こういうのが世のバカ共に受けそうだな、売れそうだな、というところから始まる営利的なものから、これらの音楽は程遠いように思われるのだ。
同時にこれらの音楽は“踊らせるための音楽”として驚くほど業務的である。それを造るアーティストに職人技という地味な言葉が最も似合う音楽のジャンルは、まちがいなくDJにプレイされるテクノやハウスであろう。コクピットのようなDJブースや、ターンテーブル、サンプラー、ヘッドホン、血管のように絡み合うシールド類等の小物がそのイメージに拍車を掛ける。
去る5月6日、ゴールデンウィークも押し迫った土曜日の深夜から日曜の明け方にかけて、木屋町にある京都観光ビル地下の“HATIHATI”というクラブで開催された、デトロイト発ハウスミュージックのオリジネーターのひとり、ムーディーマン(不機嫌な男)のDJライブにまや(彼女)と2人で参加した。
ライブ自体は午後10時スタートであったが、どうせ大御所の出番はオソオソからだろうとのんびり目に出掛け、途中西院でメシを食い、僕等が会場に到着したのは夜中の12時過ぎ。まだ閑散としているクラブのステージに向かって右のピーカー前辺りに陣取り、前座のDJプレイをバックに、ハイネケンをガブ飲みしつつユラユラ踊ったり、壁際にへたり込んでタバコを葺かしたり…この時間もユルユルと愉しいのだ。
二日ほど前に、前売りのチケットを受け取りに行った時に知ったのだが、“HATIHATI”は普段はフロアにテーブルが並ぶ、やや高級なイメージのインドネシア料理店。たまにこういう単発のイベントを組むようだが、アジアンテイストのインテリアでまとめられた空間がテクノのパーティーにもすんなりと馴染んでしまうのが不思議である。
午前2時過ぎ。じわじわと人が入り、フロアが少し窮屈に感じる程に埋まり出した頃、ラフな感じで頭にタオルを被ったケニー・ディクソン・jrことムーディーマンがノッソリ登場。タオルがでかいので、顔のほとんどが覆われて見えなく、エレファントマンのようでもある。歓声に答えてマイクを手に持ち、以外に甘い声でオーディエンスに何かを語り掛けるが、かろうじて聞こえる“キョート”以外の単語はさっぱり分からない。しかしながら、そのプレイはそれまでの前座のDJとは明らかに一線を画しているのだ。
突如、ドゥバシッ・ズシズシ・ドタドッ・ズシッシとニガーなループが地鳴りし、そのリズムを縫い合わせるように、ズビズビッ・ビッビッ・バンバン・ンパンぺペッと、やはりニガーなベースが咆吼する。キャウイン・クイィーン・クカクッ・キィクィーンと何かの演奏から採集されたギターが、まるでダークな色の宝石を取り囲む金属の装飾のように散りばめられる。ステージのソデでは彼のワイフ(多分)がテーブルに腰掛け、脚をブラブラさせながら亭主の仕事ブリを眺めている。
僕はサンプリングの元ネタなどにはまったく無知であり、何かの有名なループが挟み込まれた途端に“ウォ〜ッ!”と盛り上がるフロアのノリにはさっぱり付いてっていない感があるが、それはともかく御大のプレイが際立って個性的であることは分かる。多分僕がムーディーマンのことを知らなかったとしても、何人かの前座DJと彼のプレイの間に横たわる歴然とした格差を訝しく思ったに違いない。
匂いのキツイものに対して“鼻にツーンと来る”という言い方があるが、ムーディーマンのプレイは“身体全体にツーンと来る”。まあ、スピーカーの真ん前で踊ってるんだし、身体にキテも当然といや当然なのだが、おそらく単なる音量の問題ではない。音の素材自体が放つ臭気(いや“音気”と言うべきか?それとも“覇気”?)はもちろん、それぞれのサンプルの組み合わせ方やコントラスト、間合いの取り方などが交錯し、増幅・干渉し合って、その音響は“身体全体にツーンと来る”ものになるのだろう。
エレファント・ムーディーマンは相変わらずタオルを頭に乗せたまま小首を傾げてヘッドホンからのリズムをキープし、延々と、アノ手コノ手で黒いループを放ち続ける。そう、黒いループだ。“身体全体にツーンと来る”黒いループ。そして、黒いということは、限りなく透明である、ということでもある。夜、夜空を見上げればよく分かるだろう。あの宇宙の黒さは限りのない透明さの集積であり、それはムーディーマンの放つ“身体全体にツーンと来る”黒いループが、なぜ透明感に満ちているのかを理解する手がかりでもあろう。
実はこのムーディーマン、去年の夏にもバンド編成で来日して話題になった。僕はライブには行けなかったが、その頃どこかで読んだレビューの内容に少なからず興味を持ち、「サイレント・オブ・ザ・シークレット・ガーデン=秘密の庭の静寂」というアルバムを買った。で、そのテクノだかハウスだか分からないズビズバ・ベースとピロリン・ピアノが共存するディープかつイノセントで美しい内容にドップリとハマッてしまい、ふと思い立って和歌山の雑賀崎まで旅に出掛けたりしたのである。
そこには、夏の海と空と雲に照らされて輝く「秘密の庭の静寂」があったのだ。和歌浦の断崖に付き出した、その小さな緑の半島には休日なのに不思議に人影もなく、足元の岩場をザーーーッと這い回る無数のフナムシでさえが、奇跡的な生き物のように思えたりした。
現在も生まれ育ったデトロイトを離れず、家族と共に貧民街に住み続け、黒人という立場からアメリカという国やその音楽産業に対して一石を投じる姿勢を忘れない音楽的扇動者としてのムーディーマンの一面は、こう言うと怒られるかも知れないが僕にはゼンゼン興味がない。
ムーディーマンが「サイレント・オブ・ザ・シークレット・ガーデン」で表現している、燃える宝石のように激しく、土臭く、静寂の音に満ちた美しいものを存分に享受できるだけでいいじゃん、と思うのだ。ただ、何かの思想的な破片だかカケラだかが知らず知らず神経のどこかに突き刺さり、そこから予想外の浸食が始まる、ということもままあるんだけどね。
スピーカーに頭をくっつけると巨大な振動板に押し出された空気のカタマリが髪の毛をバフッ、バフッと直撃する。ほぼオートマティックにカックンカックンと踊りまくり、ぶっ倒れ、壁際に座り込みつつ、ハイネケンの泡の中に浮かぶボーと覚醒した頭で、ハテ?もともとは超弩級のフォーキーであり、現在はロックンロールの猿を自認する自分が今、何故テクノやハウスなんぞという、一見それらからまったく隔絶された音楽に陶酔しているのか?等と考え始める。
あらゆる言葉は感情からの逃走を目指す、というのは僕のオリジナル(だと思うんだけど)な考えである。もっとも初源的な言葉は、おそらく感情の発動、精神の軋みを源泉とし、その軋みから逃れようとするベクトルを持って発せられた。言葉を発することは感情を切断することでもあり、その刹那、精神は感情を振り払い自由へと逃れ去る。
----------
衝動と感情は相反するものであり(中略)我々の雑多な衝動はほとんどの場合充足されない。あの女とヤリてーとか、野郎ブッ殺す!とか思っても現社会では即実行に移すわけにはいかない。そこで挫折した衝動のエネルギーは行き場をなくし、充足の代償として感情へと劣化、変質するのである。例えば俺のあのコに対する気持ちはもっと純粋なんだ、とか汝の敵を愛せ、てな具合に巧妙に他者を回避し閉じた世界の中で自己弁護的な物語を紡ぎ出す。つまり感情とは、だからそれがどれほど晴れ晴れとしたものであっても、どこかに“負性”を抱えているのである。
(ニュールーディーズクラブ:1997/ウッディー)
----------
上記の拙文に従えば、感情とは挫折した衝動である。
本来的な生の発露(要求)である衝動は生きている以上間断なく発露するものであり、しかし上記に示した通り、その衝動はほとんど充足されることはなく、発露した衝動の殆どは感情へと劣化、変質する。
だから、我々は日々暮らしていく中であらゆるシーンに於いて感情に押し流されざるを得なく、その負性を自分に納得が行くようドラマ化しようと躍起になっている。つまり、自分で素晴らしいと認識している感情でさえもが、その元を辿れば挫折した衝動のなれの果てにすぎなく、素晴らしいと感じているのは、挫折を認めたくないがゆえの、無意識的な自己弁護ドラマ化の結果なのである。感情とは生を抱き込み、衰弱させることによって自らの負性を忘却しようとする必要悪なのだ。
思うのだが、クラッシックからロック、パンク、テクノ、民族音楽、歌謡曲、演歌を含めて世の音楽にはその感情を納得行くように正当化し、さらなるドラマ化を促すものと、生にまとわりつく感情をズタズタに切断し、そこから出来るだけ遠くへ逃走し、本来的な衝動を喚起させようとするものの二つがある。
僕の音楽の聴き方を問えば、最も初期には前者であり、自らが音楽を創り、表現するようになってからは圧倒的に後者であったと思われる。
つまり、僕が他人の歌を聴いたり、自らが曲を作り歌うこととは、感情に没入するためではなく、明らかにそれを振り払うためなのだ。それは自身が“そのことに気付いて以来”一貫している。
先に、言葉を発することは感情を切断することでもあり、その刹那、精神は感情を振り払い自由へと逃れ去る、と書いたが、ある時期からの僕にとっては、自身の中へと音楽をブチ込むことも、自身から音楽を発することも、同じく感情を切断することであって、決して感情に陶酔しようとするベクトルを持たない。
ボブ・ディランの“誰もがブルーズに入り込もうとしているが、オレはそこから出て行こうとしているんだ”という言葉は、僕の言いたいことをズバリと言い切ってしまっていて、とても気持ちがいい。
超弩級のフォーキーであった頃の僕が、当時はそれほど自覚的でなく中期の吉田拓郎から聴き取ろうとしていたもの、その後、ストーンズの「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」を大きな皮切りに、キース・リチャーズの佇まいやボブ・ディラン、ジョン・レノンの作品や歌唱から感得し切ったロックンロール、それをもっと先鋭化したものに思えたセックス・ピストルズのパンクロックはすべて感情からの逃走し、衝動を喚起させようとするベクトルを持った音楽に違いなかった。
そして、パンク以降の僕が急速に接近したハウスやテクノも同じく、(いや、ひょっとするともっと分かりやすいかたちで)感情に背を向け、(ゆく河の流れのように淡々と)逃走し続ける音楽であるという最も基本的な一点において、音楽的に物心ついて以降の僕の心象風景とキレイに連鎖するのである。隔絶などとはとんでもなかった。そこには何の矛盾もない。
まとめておくが、言葉も音楽も、結果的に生の奔流が感情から逃走し、衝動たりえようとする、その為に発せられ、または鳴り響くように(発せられ続け、鳴り響き続けるように)僕には思えるのだ。
午前4時過ぎ、パーティーはまだまだ続く。ステージのソデのテーブルに腰掛け、ずっと脚をブラブラさせていたムーディーマンのワイフ(多分)もプレイの長さにあきれ果てて帰ってしまった。まやは僕の横っちょで腰をグルングルンさせて可愛く踊っている。途中、ループをさせっぱなしにしたムーディーマンがピーカーの横をすり抜け、トイレに行った際僕らのすぐ側を通り抜けたが、“鼻にツーンと来る”汗臭さではなく、彼が甘くて清々しい、香料のような匂いを漂わせていたのはちょっと以外だった。
オーケー、スピノザよ、このオレ様を出来る限り細かく砕いてバラ撒き、音素そのものにブチ当たらせてくれ。頼むぜ。
(ウッディー:06-05/11)
テクノやハウスなど、単調なリズムの反復を基本とするデジタルな音楽は、和風に言えば“ゆく河の流れ”に似ている。
いつ終わるとも知れず延々と反復されるブッといリズムは一見、単調に聴こえ、だからテクノやハウスはどうも退屈で…という輩も多いだろう。が、この単調なリズムが全体を貫いているからこそ、そこにあたかも一本の河を点景とするような壮大な音のランドスケープが生まれ、その安定感に乗っかって、リズムの奔流から細部に至る目まぐるしい変化や様々な音響のカット・アップと戯れ、共に揺れ、漂うことが出来るのである。
反復するリズム以外の音素は、まさに浮かび、消え、結ぶうたかたのようだ。それはさながら一本の河を取り巻く水流の音や水面の輝き、水の匂い、鳥の囀りや虫の鳴き声に似ているのかも知れない。
一本の河とそれを取り巻く自然のサウンド…ってか。普段なら僕的にはあんま好きでもない話だ。しかしながら、テクノにしろハウスにしろ、実は思いの他、オーガニックな音楽のように思えたりする(僕の好きなものはそうだ)。あのミニマル・テクノの雄、ジェフミルズが炸裂させる燻し銀の如きマシンナーズ・サウンドでさえもが、金属的でありながらどこか柔らかく、そして温かい。それも、ある種のロックのようにやたらに熱くはなく、人肌を思わせるナマ温かさである。
その感覚は僕が冒頭で「方丈記」になぞらえたように、テクノやハウスが絶え間なく、しかし淡々と流れる“ゆく河の流れ”のようなイメージを第一印象とする音楽であることと無関係ではないだろう。もちろん、大抵のDJプレイには途中に何度かのハイライトが仕掛けられており、その盛り上がりは仄暗いフロアになくてはならないものには違いないが、そもそもDJによるパーティーそのものが、多くのロックやロックンロール、クラシックに比べると遙かに淡々とした、言ってみれば地味なものであると言える。
しかしながら僕にとっては仄暗いフロアで司祭のようなDJによってプレイされるこれらの音楽の淡々とした流れ、ナマ温かさ、地味さは実に心地がよい。そこにはコマーシャル(営利的)なものからは程遠いコマーシャル(業務的)な音がある。
いや、営利的であることが悪い訳では全然ない。才能あるアーティストがいて、そいつが造る音楽は才能にあふれているので売れて当然であり、不可避的に営利的であるということになる。そうではなくて、こういうのが世のバカ共に受けそうだな、売れそうだな、というところから始まる営利的なものから、これらの音楽は程遠いように思われるのだ。
同時にこれらの音楽は“踊らせるための音楽”として驚くほど業務的である。それを造るアーティストに職人技という地味な言葉が最も似合う音楽のジャンルは、まちがいなくDJにプレイされるテクノやハウスであろう。コクピットのようなDJブースや、ターンテーブル、サンプラー、ヘッドホン、血管のように絡み合うシールド類等の小物がそのイメージに拍車を掛ける。
去る5月6日、ゴールデンウィークも押し迫った土曜日の深夜から日曜の明け方にかけて、木屋町にある京都観光ビル地下の“HATIHATI”というクラブで開催された、デトロイト発ハウスミュージックのオリジネーターのひとり、ムーディーマン(不機嫌な男)のDJライブにまや(彼女)と2人で参加した。
ライブ自体は午後10時スタートであったが、どうせ大御所の出番はオソオソからだろうとのんびり目に出掛け、途中西院でメシを食い、僕等が会場に到着したのは夜中の12時過ぎ。まだ閑散としているクラブのステージに向かって右のピーカー前辺りに陣取り、前座のDJプレイをバックに、ハイネケンをガブ飲みしつつユラユラ踊ったり、壁際にへたり込んでタバコを葺かしたり…この時間もユルユルと愉しいのだ。
二日ほど前に、前売りのチケットを受け取りに行った時に知ったのだが、“HATIHATI”は普段はフロアにテーブルが並ぶ、やや高級なイメージのインドネシア料理店。たまにこういう単発のイベントを組むようだが、アジアンテイストのインテリアでまとめられた空間がテクノのパーティーにもすんなりと馴染んでしまうのが不思議である。
午前2時過ぎ。じわじわと人が入り、フロアが少し窮屈に感じる程に埋まり出した頃、ラフな感じで頭にタオルを被ったケニー・ディクソン・jrことムーディーマンがノッソリ登場。タオルがでかいので、顔のほとんどが覆われて見えなく、エレファントマンのようでもある。歓声に答えてマイクを手に持ち、以外に甘い声でオーディエンスに何かを語り掛けるが、かろうじて聞こえる“キョート”以外の単語はさっぱり分からない。しかしながら、そのプレイはそれまでの前座のDJとは明らかに一線を画しているのだ。
突如、ドゥバシッ・ズシズシ・ドタドッ・ズシッシとニガーなループが地鳴りし、そのリズムを縫い合わせるように、ズビズビッ・ビッビッ・バンバン・ンパンぺペッと、やはりニガーなベースが咆吼する。キャウイン・クイィーン・クカクッ・キィクィーンと何かの演奏から採集されたギターが、まるでダークな色の宝石を取り囲む金属の装飾のように散りばめられる。ステージのソデでは彼のワイフ(多分)がテーブルに腰掛け、脚をブラブラさせながら亭主の仕事ブリを眺めている。
僕はサンプリングの元ネタなどにはまったく無知であり、何かの有名なループが挟み込まれた途端に“ウォ〜ッ!”と盛り上がるフロアのノリにはさっぱり付いてっていない感があるが、それはともかく御大のプレイが際立って個性的であることは分かる。多分僕がムーディーマンのことを知らなかったとしても、何人かの前座DJと彼のプレイの間に横たわる歴然とした格差を訝しく思ったに違いない。
匂いのキツイものに対して“鼻にツーンと来る”という言い方があるが、ムーディーマンのプレイは“身体全体にツーンと来る”。まあ、スピーカーの真ん前で踊ってるんだし、身体にキテも当然といや当然なのだが、おそらく単なる音量の問題ではない。音の素材自体が放つ臭気(いや“音気”と言うべきか?それとも“覇気”?)はもちろん、それぞれのサンプルの組み合わせ方やコントラスト、間合いの取り方などが交錯し、増幅・干渉し合って、その音響は“身体全体にツーンと来る”ものになるのだろう。
エレファント・ムーディーマンは相変わらずタオルを頭に乗せたまま小首を傾げてヘッドホンからのリズムをキープし、延々と、アノ手コノ手で黒いループを放ち続ける。そう、黒いループだ。“身体全体にツーンと来る”黒いループ。そして、黒いということは、限りなく透明である、ということでもある。夜、夜空を見上げればよく分かるだろう。あの宇宙の黒さは限りのない透明さの集積であり、それはムーディーマンの放つ“身体全体にツーンと来る”黒いループが、なぜ透明感に満ちているのかを理解する手がかりでもあろう。
実はこのムーディーマン、去年の夏にもバンド編成で来日して話題になった。僕はライブには行けなかったが、その頃どこかで読んだレビューの内容に少なからず興味を持ち、「サイレント・オブ・ザ・シークレット・ガーデン=秘密の庭の静寂」というアルバムを買った。で、そのテクノだかハウスだか分からないズビズバ・ベースとピロリン・ピアノが共存するディープかつイノセントで美しい内容にドップリとハマッてしまい、ふと思い立って和歌山の雑賀崎まで旅に出掛けたりしたのである。
そこには、夏の海と空と雲に照らされて輝く「秘密の庭の静寂」があったのだ。和歌浦の断崖に付き出した、その小さな緑の半島には休日なのに不思議に人影もなく、足元の岩場をザーーーッと這い回る無数のフナムシでさえが、奇跡的な生き物のように思えたりした。
現在も生まれ育ったデトロイトを離れず、家族と共に貧民街に住み続け、黒人という立場からアメリカという国やその音楽産業に対して一石を投じる姿勢を忘れない音楽的扇動者としてのムーディーマンの一面は、こう言うと怒られるかも知れないが僕にはゼンゼン興味がない。
ムーディーマンが「サイレント・オブ・ザ・シークレット・ガーデン」で表現している、燃える宝石のように激しく、土臭く、静寂の音に満ちた美しいものを存分に享受できるだけでいいじゃん、と思うのだ。ただ、何かの思想的な破片だかカケラだかが知らず知らず神経のどこかに突き刺さり、そこから予想外の浸食が始まる、ということもままあるんだけどね。
スピーカーに頭をくっつけると巨大な振動板に押し出された空気のカタマリが髪の毛をバフッ、バフッと直撃する。ほぼオートマティックにカックンカックンと踊りまくり、ぶっ倒れ、壁際に座り込みつつ、ハイネケンの泡の中に浮かぶボーと覚醒した頭で、ハテ?もともとは超弩級のフォーキーであり、現在はロックンロールの猿を自認する自分が今、何故テクノやハウスなんぞという、一見それらからまったく隔絶された音楽に陶酔しているのか?等と考え始める。
あらゆる言葉は感情からの逃走を目指す、というのは僕のオリジナル(だと思うんだけど)な考えである。もっとも初源的な言葉は、おそらく感情の発動、精神の軋みを源泉とし、その軋みから逃れようとするベクトルを持って発せられた。言葉を発することは感情を切断することでもあり、その刹那、精神は感情を振り払い自由へと逃れ去る。
----------
衝動と感情は相反するものであり(中略)我々の雑多な衝動はほとんどの場合充足されない。あの女とヤリてーとか、野郎ブッ殺す!とか思っても現社会では即実行に移すわけにはいかない。そこで挫折した衝動のエネルギーは行き場をなくし、充足の代償として感情へと劣化、変質するのである。例えば俺のあのコに対する気持ちはもっと純粋なんだ、とか汝の敵を愛せ、てな具合に巧妙に他者を回避し閉じた世界の中で自己弁護的な物語を紡ぎ出す。つまり感情とは、だからそれがどれほど晴れ晴れとしたものであっても、どこかに“負性”を抱えているのである。
(ニュールーディーズクラブ:1997/ウッディー)
----------
上記の拙文に従えば、感情とは挫折した衝動である。
本来的な生の発露(要求)である衝動は生きている以上間断なく発露するものであり、しかし上記に示した通り、その衝動はほとんど充足されることはなく、発露した衝動の殆どは感情へと劣化、変質する。
だから、我々は日々暮らしていく中であらゆるシーンに於いて感情に押し流されざるを得なく、その負性を自分に納得が行くようドラマ化しようと躍起になっている。つまり、自分で素晴らしいと認識している感情でさえもが、その元を辿れば挫折した衝動のなれの果てにすぎなく、素晴らしいと感じているのは、挫折を認めたくないがゆえの、無意識的な自己弁護ドラマ化の結果なのである。感情とは生を抱き込み、衰弱させることによって自らの負性を忘却しようとする必要悪なのだ。
思うのだが、クラッシックからロック、パンク、テクノ、民族音楽、歌謡曲、演歌を含めて世の音楽にはその感情を納得行くように正当化し、さらなるドラマ化を促すものと、生にまとわりつく感情をズタズタに切断し、そこから出来るだけ遠くへ逃走し、本来的な衝動を喚起させようとするものの二つがある。
僕の音楽の聴き方を問えば、最も初期には前者であり、自らが音楽を創り、表現するようになってからは圧倒的に後者であったと思われる。
つまり、僕が他人の歌を聴いたり、自らが曲を作り歌うこととは、感情に没入するためではなく、明らかにそれを振り払うためなのだ。それは自身が“そのことに気付いて以来”一貫している。
先に、言葉を発することは感情を切断することでもあり、その刹那、精神は感情を振り払い自由へと逃れ去る、と書いたが、ある時期からの僕にとっては、自身の中へと音楽をブチ込むことも、自身から音楽を発することも、同じく感情を切断することであって、決して感情に陶酔しようとするベクトルを持たない。
ボブ・ディランの“誰もがブルーズに入り込もうとしているが、オレはそこから出て行こうとしているんだ”という言葉は、僕の言いたいことをズバリと言い切ってしまっていて、とても気持ちがいい。
超弩級のフォーキーであった頃の僕が、当時はそれほど自覚的でなく中期の吉田拓郎から聴き取ろうとしていたもの、その後、ストーンズの「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」を大きな皮切りに、キース・リチャーズの佇まいやボブ・ディラン、ジョン・レノンの作品や歌唱から感得し切ったロックンロール、それをもっと先鋭化したものに思えたセックス・ピストルズのパンクロックはすべて感情からの逃走し、衝動を喚起させようとするベクトルを持った音楽に違いなかった。
そして、パンク以降の僕が急速に接近したハウスやテクノも同じく、(いや、ひょっとするともっと分かりやすいかたちで)感情に背を向け、(ゆく河の流れのように淡々と)逃走し続ける音楽であるという最も基本的な一点において、音楽的に物心ついて以降の僕の心象風景とキレイに連鎖するのである。隔絶などとはとんでもなかった。そこには何の矛盾もない。
まとめておくが、言葉も音楽も、結果的に生の奔流が感情から逃走し、衝動たりえようとする、その為に発せられ、または鳴り響くように(発せられ続け、鳴り響き続けるように)僕には思えるのだ。
午前4時過ぎ、パーティーはまだまだ続く。ステージのソデのテーブルに腰掛け、ずっと脚をブラブラさせていたムーディーマンのワイフ(多分)もプレイの長さにあきれ果てて帰ってしまった。まやは僕の横っちょで腰をグルングルンさせて可愛く踊っている。途中、ループをさせっぱなしにしたムーディーマンがピーカーの横をすり抜け、トイレに行った際僕らのすぐ側を通り抜けたが、“鼻にツーンと来る”汗臭さではなく、彼が甘くて清々しい、香料のような匂いを漂わせていたのはちょっと以外だった。
オーケー、スピノザよ、このオレ様を出来る限り細かく砕いてバラ撒き、音素そのものにブチ当たらせてくれ。頼むぜ。
(ウッディー:06-05/11)
|
|
|
|
|
|
|
|
ウッディー瓦版/ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ウッディー瓦版/のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90068人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208325人
- 3位
- 酒好き
- 170698人