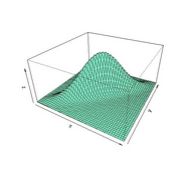|
|
|
|
コメント(153)
Q.5件法の質問項目一つに対してt検定をしようとしています.合計得点ならば,t検定(or分散分析)でも良いと思いますが,どうですか?
A.そもそも,5件法等というものは順序尺度なので,その意味で合計得点に対しt検定等を行うことは真に厳密に言えば間違っているそうです.ただし,これを間隔尺度とみなして分析を行なっているわけです.
それで,この質問では得点範囲が狭いからノンパラメトリックの方がいいのかもとという意見があるように思えますが,違うそうです.
ノンパラメトリックかパラメトリックかを選ぶ基準は,正規分布しているか否かではなく,間隔とみなせるか否かです.その意味で,ケース・バイ・ケースです.
ただし,正規分布していないと仮定されるデータに対してはノン・パラの方が良いと思います.ただ,わざわざ正規分布の検定をしても,例数によっては棄却される可能性もある(t検定前のF検定,SEMにおけるχ2検定と同じ理屈です)ので,注意が必要です.原口先生からの回答は分散分析でも良いと思いますと書いてあるだけで,説明がなかったので補足します.
また,検出力という観点からはパラメトリックよりもノン・パラメトリックの方が低くなります.つまり,パラメトリックで有意差が出てもノン・パラで有意差が出ないこともあります.
また,ノン・パラは間隔尺度に対しても使うことができるので,どんな場合でもノン・パラで統計をかけ有意差が出ると文句は言えなくなります.
A.そもそも,5件法等というものは順序尺度なので,その意味で合計得点に対しt検定等を行うことは真に厳密に言えば間違っているそうです.ただし,これを間隔尺度とみなして分析を行なっているわけです.
それで,この質問では得点範囲が狭いからノンパラメトリックの方がいいのかもとという意見があるように思えますが,違うそうです.
ノンパラメトリックかパラメトリックかを選ぶ基準は,正規分布しているか否かではなく,間隔とみなせるか否かです.その意味で,ケース・バイ・ケースです.
ただし,正規分布していないと仮定されるデータに対してはノン・パラの方が良いと思います.ただ,わざわざ正規分布の検定をしても,例数によっては棄却される可能性もある(t検定前のF検定,SEMにおけるχ2検定と同じ理屈です)ので,注意が必要です.原口先生からの回答は分散分析でも良いと思いますと書いてあるだけで,説明がなかったので補足します.
また,検出力という観点からはパラメトリックよりもノン・パラメトリックの方が低くなります.つまり,パラメトリックで有意差が出てもノン・パラで有意差が出ないこともあります.
また,ノン・パラは間隔尺度に対しても使うことができるので,どんな場合でもノン・パラで統計をかけ有意差が出ると文句は言えなくなります.
Q.ある療法に参加する人へアンケートをしました.そこで,「○○は××だと思う」という答えに対し○か×で回答してもらいました.その後,その療法に参加した後に同じ質問をし,回答が変化したかどうかを調べたいと思います.どんな統計をかけたらいいでしょうか?
A.マクニマーの検定をしてください.
マクニマー(マクネマーとも)の検定は二項検定と等価です.STARでもできます.STARの場合は変化した人数を直接確率計算に入れてください.
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/JavaScript/McNemar.html
が楽だと思います.
あと,要説―の方は何故か,χ2検定で答えを書いてますが,お勧めできません.なので,テクニカルの方を参照してください.
参考
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Hiritu/McNemar-test.html
A.マクニマーの検定をしてください.
マクニマー(マクネマーとも)の検定は二項検定と等価です.STARでもできます.STARの場合は変化した人数を直接確率計算に入れてください.
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/JavaScript/McNemar.html
が楽だと思います.
あと,要説―の方は何故か,χ2検定で答えを書いてますが,お勧めできません.なので,テクニカルの方を参照してください.
参考
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Hiritu/McNemar-test.html
Q.水準別誤差項とプールする誤差項ってどう違うの?
A.これは,二要因分散分析で問題になることです.なぜこれが問題になるかというと,検出力(有意差を出しやすくする力)をあげるためです.
まず,この問題が出てくる場合について整理すると,交互作用が出た場合です.交互作用が出なければ問題としてあがってきません.
交互作用が出た場合は,水準ごとに平均値の差を調べていくことになります.例えば,男性ごとに国語・理科・社会の点数を調べるなどです.そのための第一歩である単純主効果の検定から,この問題は出てきます.
まず,分散分析の原理を少しおさらいすると,偶然の誤差より,水準の誤差が大きいときに水準による差が出たと判断するのが分散分析です.分散分析とは,偶然の誤差による分散と水準の差による分散を比べることに由来しています.
さて,誤差項をプールする方法は,誤差項をプールします.なぜプールするかというと,外れ値など異常な値からの影響を少なくするためです.分散が小さくなれば,検出力は上がります.つまり,せっかく多くの被験者をとったんだから,その全部の結果を使って誤差を調べようという方略です.
それに対し,水準別誤差項とは,二要因分散分析を一要因の分散分析が二つあるものだとみなします.これは,水準ごとに分散の等質性が満たされない場合に用いると検出力が上がります.
男性・女性×国語・算数・理科の場合を考えると,男性と女性において三つの教科の点数の分散(個人差)が等しいならば,多くのデータを用いて誤差を測定したほうが,間違いが少なくなります.逆に,男性において分散(個人差)が大きい場合は,全体を合計すると女性において誤差として見積もる値が不当に大きくなり,検出力が落ちます.
二群以上の等分散の検定はバートレットの検定か,レーベンの検定で行います.
ただし,実際上はそれほど検定の結果に差は出ないことと,心理学の領域では分散が等質な場合はほとんどありえないことが示唆されており,簡便な水準別誤差項を用いて何か不都合である場合はないと思います.
以下に,この件についてまとめたので参照下さい.
大学の授業で習った方法は,プールした誤差項を用いる方法である.プールするとは統合するという意味である.STARは誤差項をプールしない方法(水準別誤差項)を用いている.授業では誤差項をプールすると習ったが,実はしない方が簡単であり,そこまで結果は変わらない.また,水準別誤差項を進める人も多い.(というか,誤差項をプールする方法は普通のソフトではできない.)
誤差項をプールする必要があるのは交互作用が有意になった後の単純主効果の検定からである.つまり,交互作用が有意にならない場合は両者に違いはない.また,主効果の検定も同じである.さて,誤差項は対応が増えるたびに,その中から被験者の要因を取り出していくことを思い出して欲しい.対応がまったくない場合は,誤差項は一つであり,プール(統合)する必要はない.しかし,対応が増え,誤差項がから被験者の要因が取り出されると,それをもとに戻す必要がある.これがプールである.
分散分析の前提条件は各水準における分散の等質性であった.しかし,これが仮定できない場合も分散分析は正常な判断を下すことが知られている.この時,分散の等質性が保障できないならば水準別誤差項を,保障できるならばプールされた誤差項を用いたほうが検出力は上がる.以下に卒業論文でしっかりとした統計処理を行ない方への指針を3つ述べる.
?水準別誤差項を利用する方法としてはSTARが計算する水準別誤差項を用いてHSD検定をやりなおす方法が良い.STARでは多重比較を行なう前に,その多重比較で用いられるMSe(誤差項)を出力する.プールした誤差項の代わりにこれを用いる.また,その際には修正されたステューデント化された範囲を用いない.この方法を用いれば水準別誤差項を用いてHSDを計算することができる.
?次に,他の多重比較法を用いる方法である.例えば,ボンフェローニの法(ホルムの法)である.この方法は水準別誤差項・プールされた誤差項のどちらにも使うことができる.また,プールされた誤差項が良いならば,ANOVA4を用いると良い.これは,プールされた誤差項を用いライアン法で多重比較をしてくれる.また,決定版統計解析を用いるのも良い.こちらは,唯一プールされた誤差項を用いてHSD検定を行えるソフトである.また,水準別誤差項の結果,等分散の検定(バートレットの検定など)もできる.
?一要因の分散分析に分解する方法である.注意する点としては,水準ごとに誤差項を計算するからといって,二要因の分散分析を一要因の分散分析の総和であると考えることは厳密に言えば間違っている.というのも,ABsタイプにおいては,誤差項をプールする必要はないがその中には,全ての被験者の情報が入っており,一要因分散分析に落とすと,情報量が落ちるからである.また,nが一定でない場合も一致しない.しかし,多くの統計ソフト(SAS,SPSS)では,二要因分散分析において単純主効果が有意になった際の多重比較を行なうことができないので,この方法を用いるしかない.この方法では,若さ検出力が落ちる.
また,反復測定デザインにおいては多変量分散分析が適している場合があることを最後に付け加えておく.
A.これは,二要因分散分析で問題になることです.なぜこれが問題になるかというと,検出力(有意差を出しやすくする力)をあげるためです.
まず,この問題が出てくる場合について整理すると,交互作用が出た場合です.交互作用が出なければ問題としてあがってきません.
交互作用が出た場合は,水準ごとに平均値の差を調べていくことになります.例えば,男性ごとに国語・理科・社会の点数を調べるなどです.そのための第一歩である単純主効果の検定から,この問題は出てきます.
まず,分散分析の原理を少しおさらいすると,偶然の誤差より,水準の誤差が大きいときに水準による差が出たと判断するのが分散分析です.分散分析とは,偶然の誤差による分散と水準の差による分散を比べることに由来しています.
さて,誤差項をプールする方法は,誤差項をプールします.なぜプールするかというと,外れ値など異常な値からの影響を少なくするためです.分散が小さくなれば,検出力は上がります.つまり,せっかく多くの被験者をとったんだから,その全部の結果を使って誤差を調べようという方略です.
それに対し,水準別誤差項とは,二要因分散分析を一要因の分散分析が二つあるものだとみなします.これは,水準ごとに分散の等質性が満たされない場合に用いると検出力が上がります.
男性・女性×国語・算数・理科の場合を考えると,男性と女性において三つの教科の点数の分散(個人差)が等しいならば,多くのデータを用いて誤差を測定したほうが,間違いが少なくなります.逆に,男性において分散(個人差)が大きい場合は,全体を合計すると女性において誤差として見積もる値が不当に大きくなり,検出力が落ちます.
二群以上の等分散の検定はバートレットの検定か,レーベンの検定で行います.
ただし,実際上はそれほど検定の結果に差は出ないことと,心理学の領域では分散が等質な場合はほとんどありえないことが示唆されており,簡便な水準別誤差項を用いて何か不都合である場合はないと思います.
以下に,この件についてまとめたので参照下さい.
大学の授業で習った方法は,プールした誤差項を用いる方法である.プールするとは統合するという意味である.STARは誤差項をプールしない方法(水準別誤差項)を用いている.授業では誤差項をプールすると習ったが,実はしない方が簡単であり,そこまで結果は変わらない.また,水準別誤差項を進める人も多い.(というか,誤差項をプールする方法は普通のソフトではできない.)
誤差項をプールする必要があるのは交互作用が有意になった後の単純主効果の検定からである.つまり,交互作用が有意にならない場合は両者に違いはない.また,主効果の検定も同じである.さて,誤差項は対応が増えるたびに,その中から被験者の要因を取り出していくことを思い出して欲しい.対応がまったくない場合は,誤差項は一つであり,プール(統合)する必要はない.しかし,対応が増え,誤差項がから被験者の要因が取り出されると,それをもとに戻す必要がある.これがプールである.
分散分析の前提条件は各水準における分散の等質性であった.しかし,これが仮定できない場合も分散分析は正常な判断を下すことが知られている.この時,分散の等質性が保障できないならば水準別誤差項を,保障できるならばプールされた誤差項を用いたほうが検出力は上がる.以下に卒業論文でしっかりとした統計処理を行ない方への指針を3つ述べる.
?水準別誤差項を利用する方法としてはSTARが計算する水準別誤差項を用いてHSD検定をやりなおす方法が良い.STARでは多重比較を行なう前に,その多重比較で用いられるMSe(誤差項)を出力する.プールした誤差項の代わりにこれを用いる.また,その際には修正されたステューデント化された範囲を用いない.この方法を用いれば水準別誤差項を用いてHSDを計算することができる.
?次に,他の多重比較法を用いる方法である.例えば,ボンフェローニの法(ホルムの法)である.この方法は水準別誤差項・プールされた誤差項のどちらにも使うことができる.また,プールされた誤差項が良いならば,ANOVA4を用いると良い.これは,プールされた誤差項を用いライアン法で多重比較をしてくれる.また,決定版統計解析を用いるのも良い.こちらは,唯一プールされた誤差項を用いてHSD検定を行えるソフトである.また,水準別誤差項の結果,等分散の検定(バートレットの検定など)もできる.
?一要因の分散分析に分解する方法である.注意する点としては,水準ごとに誤差項を計算するからといって,二要因の分散分析を一要因の分散分析の総和であると考えることは厳密に言えば間違っている.というのも,ABsタイプにおいては,誤差項をプールする必要はないがその中には,全ての被験者の情報が入っており,一要因分散分析に落とすと,情報量が落ちるからである.また,nが一定でない場合も一致しない.しかし,多くの統計ソフト(SAS,SPSS)では,二要因分散分析において単純主効果が有意になった際の多重比較を行なうことができないので,この方法を用いるしかない.この方法では,若さ検出力が落ちる.
また,反復測定デザインにおいては多変量分散分析が適している場合があることを最後に付け加えておく.
Q.ある尺度を因子分析し,4つの因子を抽出しました.この4つの因子分析の尺度得点に対して,男女の差を見たいと思います.この場合,4回t検定を行ってよいのですか?
A.まず,この場合重要なのは,抽出された因子は同じ得点範囲を持つとしても別の測度であることです.t検定や多重比較を行なう場合は,単位(測度)が同じでなければなりません.
例えば,体重と身長をt検定にかけ,この学級では身長の方が有意に平均値が高いとする人はいないでしょう.
しかし,心理学においては,しばしば同一の単位にあるかのように錯覚してしまうものが多いです.例えば,A群にAという不安に関する質問紙尺度を用いて測定を行い,B群にBという不安に関する質問紙尺度を行なったとします.このとき,このA,Bという尺度は,得点範囲が同じであっても平均値を比較することはできません.よって,平均値の差の検定はできないことになります.
さて,この問題ですが,一見t検定を繰返すことは奇妙なことのように感じます.しかし,これは単位が違うので二要因の分散分析ではできません.この例で言えば,因子1と因子2は違うモノサシです.よって,t検定で良いと思います.
参考
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/mb-arc/arc021/241.html
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/mb-arc/arc035/07978.html
A.まず,この場合重要なのは,抽出された因子は同じ得点範囲を持つとしても別の測度であることです.t検定や多重比較を行なう場合は,単位(測度)が同じでなければなりません.
例えば,体重と身長をt検定にかけ,この学級では身長の方が有意に平均値が高いとする人はいないでしょう.
しかし,心理学においては,しばしば同一の単位にあるかのように錯覚してしまうものが多いです.例えば,A群にAという不安に関する質問紙尺度を用いて測定を行い,B群にBという不安に関する質問紙尺度を行なったとします.このとき,このA,Bという尺度は,得点範囲が同じであっても平均値を比較することはできません.よって,平均値の差の検定はできないことになります.
さて,この問題ですが,一見t検定を繰返すことは奇妙なことのように感じます.しかし,これは単位が違うので二要因の分散分析ではできません.この例で言えば,因子1と因子2は違うモノサシです.よって,t検定で良いと思います.
参考
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/mb-arc/arc021/241.html
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/mb-arc/arc035/07978.html
Q.二要因の分散分析は、交互作用だけ見れば、あとは一要因の分散分析で代用できるの?
A.これは、なんとも言い難いです。SPSS等を使っていれば、二要因までなら、一要因に落とさない方が良いと思います。
二要因の分散分析で、交互作用が出ると単純主効果の検定を行います。このときに、誤差項を用いて検定を行いますが、この時二つの考え方があり、
?全被験者の誤差項を用いる(誤差項をプールする方法)、
?分けた水準の誤差項を用いる(水準別誤差項)
という二つの方法があります。
大学の講義では?を習っています。?の方法は、全被験者において分散の等質性が確保できない場合には検定結果が怪しくなるそうです。また、?の方法では、多くの被験者から推定した方が誤差項の値が安定するという考え方をよりどころにしています。
分散分析後の多重比較を考えると?の方法は煩雑になります。
特に、被験者内要因が増えると、誤差項から分離した被験者の効果をプールしたりと煩雑になることが予想されます。妥協案としては、多重比較の必要性がない場合(例えば、交互作用が出ても、多重比較をしない二つの水準にしか関心がない場合…pre-postデザイン等)には?を、多重比較が必須な実験計画の場合は?を行えばどうでしょうか?また、?を選択した場合は論文で水準別誤差項による…と断った方が良いと思います。また、交互作用が有意にならなかった場合の主効果の検定は一要因の分散分析と同じになります。
※追記
水準別誤差項の方法ですが,二要因分散分析を,一要因分散分析に落とした場合には,水準別誤差項になりません.水準別誤差項を用いた場合における単純主効果の検定で,一要因分散分析と誤差項が一致するのは,AsBタイプの時の単純主効果の検定における要因Aの単純主効果の検定とsABタイプにおける単純主効果の検定のみです.
理論ではなく,どう対処すればよいかという話ですが,誤差項をプールする計算が煩雑で嫌ならば,STARで分析を行ないましょう.この時,多重比較でMSe=という欄には水準別誤差項が出力されています.よって,この数値を用いればプールする必要はありません.また,この時qの修正項もつかいません.単純にq√(MSe/n)の式で良いです.注意点としては,qを計算するときの自由度は単純主効果の検定表を読まなければならないことです.単純主効果の検定の欄に水準別誤差項とその自由度,MSが出力されています.
そして,これも嫌ならば,ANOVA4を使ってください.こちらはプールされた誤差項を用いて単純主効果の検定を行っています.注意点としては,sABタイプのプールの方法がテクニカルブックと一致しません.これは,全ての誤差項をプールしているようです.(テクニカルブックのsABタイプの分散分析表下に注釈があります.)また,このANOVA4にもMSe=という場所があります.よってここを参照してHSD検定をしなおすことも考えられます.ANOVA4の多重比較法はライアン法です.(ライアン法でも良いと思いますが.)
また,水準別誤差項を用いるかプールした誤差項を用いるかは,三郡以上の等分散の検定であるバートレットの検定かレーベンの検定を用います.これはSPSS,SAS,Rに頼らざるを得ませんが….
ただし,等分散の検定はしなくても過去の文献等から等分散が分かっている場合(等分散が仮定できる場合)はしなくても良いそうです.
また,SPSSを用いる場合は,誤差項をプールする方法があります.方法としてはシンタックスというプログラムを少し書き換えなければいけません.
SASでは,適当な文献が見当たりません.妥協案として,交互作用が出た場合に全てのセルで多重比較を行なう方法が考えられます.一要因に分解して単純主効果の検定をするのも良いと思います.
参考
http://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/
http://www.hju.ac.jp/~kiriki/anova4/index_js.html
http://home.hiroshima-u.ac.jp/nittono/ANOVA_JSPP2004.pdf
http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~hoshino/spss/index-j.html
http://www.u-gakugei.ac.jp/~kishilab/SPSSindex.htm
A.これは、なんとも言い難いです。SPSS等を使っていれば、二要因までなら、一要因に落とさない方が良いと思います。
二要因の分散分析で、交互作用が出ると単純主効果の検定を行います。このときに、誤差項を用いて検定を行いますが、この時二つの考え方があり、
?全被験者の誤差項を用いる(誤差項をプールする方法)、
?分けた水準の誤差項を用いる(水準別誤差項)
という二つの方法があります。
大学の講義では?を習っています。?の方法は、全被験者において分散の等質性が確保できない場合には検定結果が怪しくなるそうです。また、?の方法では、多くの被験者から推定した方が誤差項の値が安定するという考え方をよりどころにしています。
分散分析後の多重比較を考えると?の方法は煩雑になります。
特に、被験者内要因が増えると、誤差項から分離した被験者の効果をプールしたりと煩雑になることが予想されます。妥協案としては、多重比較の必要性がない場合(例えば、交互作用が出ても、多重比較をしない二つの水準にしか関心がない場合…pre-postデザイン等)には?を、多重比較が必須な実験計画の場合は?を行えばどうでしょうか?また、?を選択した場合は論文で水準別誤差項による…と断った方が良いと思います。また、交互作用が有意にならなかった場合の主効果の検定は一要因の分散分析と同じになります。
※追記
水準別誤差項の方法ですが,二要因分散分析を,一要因分散分析に落とした場合には,水準別誤差項になりません.水準別誤差項を用いた場合における単純主効果の検定で,一要因分散分析と誤差項が一致するのは,AsBタイプの時の単純主効果の検定における要因Aの単純主効果の検定とsABタイプにおける単純主効果の検定のみです.
理論ではなく,どう対処すればよいかという話ですが,誤差項をプールする計算が煩雑で嫌ならば,STARで分析を行ないましょう.この時,多重比較でMSe=という欄には水準別誤差項が出力されています.よって,この数値を用いればプールする必要はありません.また,この時qの修正項もつかいません.単純にq√(MSe/n)の式で良いです.注意点としては,qを計算するときの自由度は単純主効果の検定表を読まなければならないことです.単純主効果の検定の欄に水準別誤差項とその自由度,MSが出力されています.
そして,これも嫌ならば,ANOVA4を使ってください.こちらはプールされた誤差項を用いて単純主効果の検定を行っています.注意点としては,sABタイプのプールの方法がテクニカルブックと一致しません.これは,全ての誤差項をプールしているようです.(テクニカルブックのsABタイプの分散分析表下に注釈があります.)また,このANOVA4にもMSe=という場所があります.よってここを参照してHSD検定をしなおすことも考えられます.ANOVA4の多重比較法はライアン法です.(ライアン法でも良いと思いますが.)
また,水準別誤差項を用いるかプールした誤差項を用いるかは,三郡以上の等分散の検定であるバートレットの検定かレーベンの検定を用います.これはSPSS,SAS,Rに頼らざるを得ませんが….
ただし,等分散の検定はしなくても過去の文献等から等分散が分かっている場合(等分散が仮定できる場合)はしなくても良いそうです.
また,SPSSを用いる場合は,誤差項をプールする方法があります.方法としてはシンタックスというプログラムを少し書き換えなければいけません.
SASでは,適当な文献が見当たりません.妥協案として,交互作用が出た場合に全てのセルで多重比較を行なう方法が考えられます.一要因に分解して単純主効果の検定をするのも良いと思います.
参考
http://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/
http://www.hju.ac.jp/~kiriki/anova4/index_js.html
http://home.hiroshima-u.ac.jp/nittono/ANOVA_JSPP2004.pdf
http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~hoshino/spss/index-j.html
http://www.u-gakugei.ac.jp/~kishilab/SPSSindex.htm
Q.二要因分散分析(2x2)をしています.二要因とも対応がない場合です.要因A:進学を希望する・しない,要因B:未来志向性の得点が高い・低いです.分析の結果交互作用が出ました.しかし,私が調べたいのは,進学を希望しなおかつ得点が高い群(A1 at B1)と進学を希望しないで未来志向性が低い群(A2 at B2)なのです.どうすれば良いでしょうか?
A.まず,この場合に注意することは,従属変数が何であるかです.この場合は,学校生活への満足感でした.このような場合は,2x2の4群に分け,一要因の分散分析をします.こうすれば,質問にあるような比較ができます.ただし,これは二要因の分散分析がABsタイプであることが必要です.対応がどちらかにでもある場合でもできますが,その場合は検出力が落ちますし,好ましくない分析方法だと考えられます.
A.まず,この場合に注意することは,従属変数が何であるかです.この場合は,学校生活への満足感でした.このような場合は,2x2の4群に分け,一要因の分散分析をします.こうすれば,質問にあるような比較ができます.ただし,これは二要因の分散分析がABsタイプであることが必要です.対応がどちらかにでもある場合でもできますが,その場合は検出力が落ちますし,好ましくない分析方法だと考えられます.
Q.分散分析で主効果が有意になり,多重比較しましたが,多重比較で一つも有意差が出ませんでした.これって変ですか?
A.分散分析と多重比較は,もともと別の統計処理です.なので,このような結果が出ることは不思議なようですがありえます.たとえいて言うなら,ある風景を見たときなんか変だなぁと感じて,よくよく小さな物事を見ても別に変な所はないと感じるといった状況だそうです.なので,分散分析は有意になったが,多重比較の結果,有意な差は出なかったと書きます.
また,実は逆の場合も実は存在します.多重比較には事前比較と事後比較というものがあります.前者は分散分析の前に多重比較を行なう方法で,後者は分散分析後に行なうものです.特定の仮説があるならば,事前比較を行なってよいということになります.なので,分散分析を行なわずに多重比較を行なってもかまいません.例えば,統制群を用いた場合などです.これはダネットの方法を用います.
A.分散分析と多重比較は,もともと別の統計処理です.なので,このような結果が出ることは不思議なようですがありえます.たとえいて言うなら,ある風景を見たときなんか変だなぁと感じて,よくよく小さな物事を見ても別に変な所はないと感じるといった状況だそうです.なので,分散分析は有意になったが,多重比較の結果,有意な差は出なかったと書きます.
また,実は逆の場合も実は存在します.多重比較には事前比較と事後比較というものがあります.前者は分散分析の前に多重比較を行なう方法で,後者は分散分析後に行なうものです.特定の仮説があるならば,事前比較を行なってよいということになります.なので,分散分析を行なわずに多重比較を行なってもかまいません.例えば,統制群を用いた場合などです.これはダネットの方法を用います.
Q.例えば,X1という変数の50点以上,X2という変数の50点以上で2x2の4群に分け,クロス集計をしたいんですけど.
A.エクセルだったら,ピボット・テーブルという方法があります.個人的には無駄な出力が多い上に良く分からないのですが….他にも以下のような方法があります.
A1にはX1の変数,B1にはX2の変数が入っていると考えてみてください.
C1のセルに「=if(A1>=50,"1","0")」
D1のセルに「=if(A2>=50,"1","0")」
と入力します.これで,X1,X2の得点によって0か1の区別を作ったセルが二つできます.これを三つ目のセルでくっつけます.
Eのセルには,「=C1*10+D1」か「=C1&D1」とします.
後者は,応用情報処理で習った気がしますね….
それで,できた「01」「11」などを数えます.
00,01,10,11等のセルを作っておき.
「=countif(ナンバリングした範囲,01と書いたセル)」
とすれば,簡単にできます.
文章だとちょっと分かりにくいですが…
ナンバリングした範囲は絶対参照にしておくと,後はコピペでできますね.ちなみに,絶対参照にするにはF4キーを押すと簡単にできます.
A.エクセルだったら,ピボット・テーブルという方法があります.個人的には無駄な出力が多い上に良く分からないのですが….他にも以下のような方法があります.
A1にはX1の変数,B1にはX2の変数が入っていると考えてみてください.
C1のセルに「=if(A1>=50,"1","0")」
D1のセルに「=if(A2>=50,"1","0")」
と入力します.これで,X1,X2の得点によって0か1の区別を作ったセルが二つできます.これを三つ目のセルでくっつけます.
Eのセルには,「=C1*10+D1」か「=C1&D1」とします.
後者は,応用情報処理で習った気がしますね….
それで,できた「01」「11」などを数えます.
00,01,10,11等のセルを作っておき.
「=countif(ナンバリングした範囲,01と書いたセル)」
とすれば,簡単にできます.
文章だとちょっと分かりにくいですが…
ナンバリングした範囲は絶対参照にしておくと,後はコピペでできますね.ちなみに,絶対参照にするにはF4キーを押すと簡単にできます.
Q.ある実験の前後で4つのカテゴリーの人数が変化したいかをしりたいんですが….2つならマクニマーの検定ですけど,どうするんですか?
A.マクニマーの検定には,拡張版があり,3x3でも4x4でもできます.この場合に,注意することはカテゴリーに順位があることと,ある実験の前後で人が同じ(対応関係がある)ことが必要です.
例えば,A,B,C,Dでカテゴリーの順位があったとします.この時,実験前にAで実験後にCである人…などと言うように,16パターンに分類できます.(0人のパターンがあっても良いです.)この4x4のクロス表に対してマクニマーの検定の拡張版を行います.
帰無仮説は,順位が上がった人=順位が下がった人です.棄却されれば,有意に順位が上がった人が多いと判断します.
ソフトとしては,SPSS,Rでできるようです.
SPSSとRではデフォルトの定義式が違うようですね.ただ,青木教授の関数を使えばRでもSPSSと同じ出力を得ることができるようです.
また,エクセルのマクロでもできます.
参考
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/stats-by-excel/vba/html/McNemar.html
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Hiritu/McNemar-test.html
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Average/sign-test.html
A.マクニマーの検定には,拡張版があり,3x3でも4x4でもできます.この場合に,注意することはカテゴリーに順位があることと,ある実験の前後で人が同じ(対応関係がある)ことが必要です.
例えば,A,B,C,Dでカテゴリーの順位があったとします.この時,実験前にAで実験後にCである人…などと言うように,16パターンに分類できます.(0人のパターンがあっても良いです.)この4x4のクロス表に対してマクニマーの検定の拡張版を行います.
帰無仮説は,順位が上がった人=順位が下がった人です.棄却されれば,有意に順位が上がった人が多いと判断します.
ソフトとしては,SPSS,Rでできるようです.
SPSSとRではデフォルトの定義式が違うようですね.ただ,青木教授の関数を使えばRでもSPSSと同じ出力を得ることができるようです.
また,エクセルのマクロでもできます.
参考
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/stats-by-excel/vba/html/McNemar.html
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Hiritu/McNemar-test.html
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Average/sign-test.html
Q.因子分析で斜交回転をしました.何を載せたほうがいいですか?特に説明分散とか,共通性とかが分かりません.
A.まず,斜交回転の場合,因子パタンの表を載せしょう.これは,直行解の時の因子負荷行列に相当します.斜交解の場合は参照構造とか色々出てきますが,まずこれです.
次に大事なのは,因子間相関です.因子間相関は,因子パタンの下にでも載せると良いと思います.
さて,共通性・説明分散なんですが,これをちょっと難しいです.まず,斜交回転というのは,因子間に相関を認めていることになります.因子分析は大まかにx=f*a+e みたいな雰囲気でできています.直行解の場合は因子の重み(f)同士は影響をし合ってませんが,斜交解の場合はfの重みが相関の分だけかぶります.よって,直行解と同じようには共通性等の計算はできないことになります.
さて,共通性ですが,共通性に関してはSASでは「最終的な共通性」として出力されています.これは,直行解の時のように単純な二乗和になっていません.よって,エクセルでは計算できません.
次に説明分散ですが.予備知識として知っておいたほうがいいことをまとめます.まず,説明分散=寄与,説明率=寄与率です.どちらかと言うと後者の方が本には載っていることが多いです.そして,寄与率とは,その因子がどれくらいの説明力を持っているかを示す指標です. (寄与を項目数で割り,100かけたものです.)
さて,寄与率の推定では,「他の因子の影響を除去した場合(参考構造に基づく)」,「他の因子の影響を無視した場合(因子構造に基づく)」の二通りの考え方ができます.前者は,相関でかぶった分は全部取る.後者は,相関を無視して足し合わせる方法です.このとき,寄与率は前者<後者になります.また,この両者とも累積寄与率とは一致しません.つまり,この両者とも完全な寄与率ではないということです.斜交解では寄与率を計算することはできず,この両者の近似値により寄与率を予想するしか手はないそうです.
最近のSASでは,両方の寄与が計算されます.
また,累積寄与率は,回転に関わらず一致しているので,SASの初期解の部分に書いてあるものを参照します.
最後に,豊田氏は,二つの寄与率を解釈するのは難しいので累積寄与率だけのせればよいと述べています.
また,未確認なのですが,寄与を直行解と同じ二乗和で計算する「直接的全寄与」というものがあるようです.詳しくは,千野先生のページ参照.
参考
共分散構造分析[入門編]p281
Q&Aで知る統計データ解析 Q73
http://koko15.hus.osaka-u.ac.jp/~kano/lecture/faq/q4/index.htm
http://www.aichi-gakuin.ac.jp/~chino/multivar/chapter3/sec3-4-3.html
A.まず,斜交回転の場合,因子パタンの表を載せしょう.これは,直行解の時の因子負荷行列に相当します.斜交解の場合は参照構造とか色々出てきますが,まずこれです.
次に大事なのは,因子間相関です.因子間相関は,因子パタンの下にでも載せると良いと思います.
さて,共通性・説明分散なんですが,これをちょっと難しいです.まず,斜交回転というのは,因子間に相関を認めていることになります.因子分析は大まかにx=f*a+e みたいな雰囲気でできています.直行解の場合は因子の重み(f)同士は影響をし合ってませんが,斜交解の場合はfの重みが相関の分だけかぶります.よって,直行解と同じようには共通性等の計算はできないことになります.
さて,共通性ですが,共通性に関してはSASでは「最終的な共通性」として出力されています.これは,直行解の時のように単純な二乗和になっていません.よって,エクセルでは計算できません.
次に説明分散ですが.予備知識として知っておいたほうがいいことをまとめます.まず,説明分散=寄与,説明率=寄与率です.どちらかと言うと後者の方が本には載っていることが多いです.そして,寄与率とは,その因子がどれくらいの説明力を持っているかを示す指標です. (寄与を項目数で割り,100かけたものです.)
さて,寄与率の推定では,「他の因子の影響を除去した場合(参考構造に基づく)」,「他の因子の影響を無視した場合(因子構造に基づく)」の二通りの考え方ができます.前者は,相関でかぶった分は全部取る.後者は,相関を無視して足し合わせる方法です.このとき,寄与率は前者<後者になります.また,この両者とも累積寄与率とは一致しません.つまり,この両者とも完全な寄与率ではないということです.斜交解では寄与率を計算することはできず,この両者の近似値により寄与率を予想するしか手はないそうです.
最近のSASでは,両方の寄与が計算されます.
また,累積寄与率は,回転に関わらず一致しているので,SASの初期解の部分に書いてあるものを参照します.
最後に,豊田氏は,二つの寄与率を解釈するのは難しいので累積寄与率だけのせればよいと述べています.
また,未確認なのですが,寄与を直行解と同じ二乗和で計算する「直接的全寄与」というものがあるようです.詳しくは,千野先生のページ参照.
参考
共分散構造分析[入門編]p281
Q&Aで知る統計データ解析 Q73
http://koko15.hus.osaka-u.ac.jp/~kano/lecture/faq/q4/index.htm
http://www.aichi-gakuin.ac.jp/~chino/multivar/chapter3/sec3-4-3.html
Q.ある実験における処遇の効果を調べるために,被験者を実験群・統制群の二群に分けました.両群とも実験前と実験後に質問紙に解答してもらいました.この時,分析にt検定を用いて,事前事後における統制群と実験群の平均値の差を調べることは不適ではないでしょうか?
A.その通りです.これは二要因の分散分析を行なうべきです.(または,反復測定ANOVA,共分散分析)このような実験・調査計画を不等価事前事後デザインといいます.
この場合,統制群は事前事後テストにおいて,変化がないか,もしくは実験群と逆の方向に平均値が移動することが考えられます.
不等価事前事後デザインの際に,処遇に効果があったかどうかを調べる分析方法がありますが,これは二要因分散分析における交互作用の検定と数理的には同じです.
分散分析では,事前事後×統制・実験の全ての誤差より検定を行いますが,t検定では当該二つにおいてのみしか考慮しません.また,統制群・実験群が実験の前後で変化したか否かも検討しなければなりません.
不等価事前事後デザインでの分析での質問は他にもあるので参照してください.
参考
心理学研究法入門―調査・実験から実践まで
A.その通りです.これは二要因の分散分析を行なうべきです.(または,反復測定ANOVA,共分散分析)このような実験・調査計画を不等価事前事後デザインといいます.
この場合,統制群は事前事後テストにおいて,変化がないか,もしくは実験群と逆の方向に平均値が移動することが考えられます.
不等価事前事後デザインの際に,処遇に効果があったかどうかを調べる分析方法がありますが,これは二要因分散分析における交互作用の検定と数理的には同じです.
分散分析では,事前事後×統制・実験の全ての誤差より検定を行いますが,t検定では当該二つにおいてのみしか考慮しません.また,統制群・実験群が実験の前後で変化したか否かも検討しなければなりません.
不等価事前事後デザインでの分析での質問は他にもあるので参照してください.
参考
心理学研究法入門―調査・実験から実践まで
Q.ある実験をして,その効果を調べるために実験の前後で質問紙を取りました.そして,この二つの質問紙の点数の差を,その大きさで三群に分け,その比率をχ2検定によって検定しました.この際,同じ被験者に対して4回の反復測定を行なっており,χ2検定をした際の度数は延べ人数(N=被験者×4)でした.
A.まず,χ2検定は独立したものでないと測れません.つまり,カテゴリーが全て別の人でなければなりません.例えば,男性と女性,携帯を持つ人,持たない人…等です.
この場合は,反復測定をしています.これを延べ人数にしたことですが,ある被験者にとって4回の試行はそれぞれ独立ではないのです.例えば,1回目に1群に分類された人は,2回目の試行でも1群に分類される人が多いです.(そう仮定を置くのが自然ですし,結果としてそうなっています.)このような場合はχ2検定はできません.
結局,これは適切には多相に拡張された反復測定χ2検定を使わないといけません.(1x3x4ですね.)そして,この方法は,まだまだ開発途上のようで,実用化レベルとしてはないようです.
※重み付き最小二乗法を用いたχ2検定だそうです.
原口先生の代案としては,パラメトリック検定で代用するというものでした.カテゴリーを順序尺度以上とみなし,分散分析・t検定を行う…ということです.
まず,質問紙の結果(順序尺度)を名義尺度まで落としたのがまずかったと思います.尺度は,比率>間隔>順序>名義の順で情報量が違います.そして,一般に比率に近い方が検出力は高いうえに,統計的手法が発展しています.なるだけ,情報量が多い尺度のまま分析を行なうほうが良いです.
A.まず,χ2検定は独立したものでないと測れません.つまり,カテゴリーが全て別の人でなければなりません.例えば,男性と女性,携帯を持つ人,持たない人…等です.
この場合は,反復測定をしています.これを延べ人数にしたことですが,ある被験者にとって4回の試行はそれぞれ独立ではないのです.例えば,1回目に1群に分類された人は,2回目の試行でも1群に分類される人が多いです.(そう仮定を置くのが自然ですし,結果としてそうなっています.)このような場合はχ2検定はできません.
結局,これは適切には多相に拡張された反復測定χ2検定を使わないといけません.(1x3x4ですね.)そして,この方法は,まだまだ開発途上のようで,実用化レベルとしてはないようです.
※重み付き最小二乗法を用いたχ2検定だそうです.
原口先生の代案としては,パラメトリック検定で代用するというものでした.カテゴリーを順序尺度以上とみなし,分散分析・t検定を行う…ということです.
まず,質問紙の結果(順序尺度)を名義尺度まで落としたのがまずかったと思います.尺度は,比率>間隔>順序>名義の順で情報量が違います.そして,一般に比率に近い方が検出力は高いうえに,統計的手法が発展しています.なるだけ,情報量が多い尺度のまま分析を行なうほうが良いです.
Q.ある変数A,Bがあります.Aが高い人ほど,Bが高いと思いますが,選択肢(C)の回答によっては,Aの得点が低くても,Bの得点が高いということを調べたいのですが….
A.まず,変数A,Bで相関を分析しましょう.その時,散布図を描くのを忘れないで下さい.散布図を描けば,相関係数が低かったり,高かったりする理由がもっと分かると思います.
次に,Aの点数が高い群(H群)がBの点数が高いかを調べてください.この場合,相関の分析と結果が食い違うかも知れません.(相関が0に近いが,H群は,Bの得点が高い…これはある程度理想どおりの結果が出た場合です.)
次に,Aの点数が低い群(L群)を更に,選択肢(C)で群分けして,それを分散分析するのはどうでしょうか?
いわゆる,多変量解析による(共分散構造分析になると思いますが)分析では,恐らく煩雑になると思います.地道ですが,この方法が良いと思います.
A.まず,変数A,Bで相関を分析しましょう.その時,散布図を描くのを忘れないで下さい.散布図を描けば,相関係数が低かったり,高かったりする理由がもっと分かると思います.
次に,Aの点数が高い群(H群)がBの点数が高いかを調べてください.この場合,相関の分析と結果が食い違うかも知れません.(相関が0に近いが,H群は,Bの得点が高い…これはある程度理想どおりの結果が出た場合です.)
次に,Aの点数が低い群(L群)を更に,選択肢(C)で群分けして,それを分散分析するのはどうでしょうか?
いわゆる,多変量解析による(共分散構造分析になると思いますが)分析では,恐らく煩雑になると思います.地道ですが,この方法が良いと思います.
Q.ある質問項目に対して,二種類の教示を用意しました.この同じ質問項目の得点の差を計算し,因子分析しようと考えています.どうでしょうか?
A.まず,二つの尺度の差が何らかの意味を持つものかどうかを考えてください.例えば,「あなたの現在について」,「あなたの未来について」と言えば,比較できますが「あなたがAさんだったら…」と「あなたにとって重要な…」では差に意味があるとは思えません.
そして,この場合因子分析をしても意味がありません.このような分析においてみたいものは,因子ごとにどんな差が見られるかだと思いますので,検証的因子分析において配置不変性が確認できたら,多母集団同時分析(平均構造を推定する)を行います.
A.まず,二つの尺度の差が何らかの意味を持つものかどうかを考えてください.例えば,「あなたの現在について」,「あなたの未来について」と言えば,比較できますが「あなたがAさんだったら…」と「あなたにとって重要な…」では差に意味があるとは思えません.
そして,この場合因子分析をしても意味がありません.このような分析においてみたいものは,因子ごとにどんな差が見られるかだと思いますので,検証的因子分析において配置不変性が確認できたら,多母集団同時分析(平均構造を推定する)を行います.
Q.相関係数が0.1で有意になっています.これは一般的な解釈としては,相関が弱いことになりますが論文の中には,相関関係がみられたと書いてあることが多くあります.これはいったい,どういう意味なのでしょうか?
A.まず,相関係数の有意性検定とは,得られた相関係数が有意でないかどうかを検定しています.相関係数の有意性検定が有意になるかどうかはn(サンプル・サイズ)がいくつであるか?によって決まります.この結果,有意であると結論付けられたとき,その相関係数は「0ではない」と言えます.
次に,0ではないことと,相関係数が大きい,小さいという議論は別の問題であることに注意してください.この意味で,結果において「有意な相関係数が得られた」と記述することは間違っていません.
次に,考察についてですが,これは各研究分野によって違うために,一概には言えません.例えば,生物など厳密な科学性が要求されている学問領域では,0.8程度あったとしても,あまり大きいと見られないかもしれませんs.逆に心理など様々な要因が考えられる領域では0.3程度でも何かしらの関係があると考えることが多い印象を受けます.
また,学問領域のほかにも,研究対象によっても解釈が違う場合があります.例えば,「うつ」には,生物学的な要因が80%程度関係があると分かっていたとします.この時に,「うつ」の生物学的な要因以外の要因の中で何が関係があるかを調べるといった研究を行うとします.このとき,生物学的な要因は「うつ」に対して,20%以上の影響力を持っていません.相関係数に換算して考えると,0.5を下回ります.このように,研究する対象によっても,その解釈が変わることがあります.
以上のような点を考慮するために,先行研究をレビューし,得られた相関係数が自分の研究領域でどのような価値を持っているかと考えることは非常に重要です.
最後に,一般的な相関係数の解釈の留意点についても忘れないようにしてください.特に,0.1の相関係数で有意であり,先行研究でも0.1程度あれば良いとなっていたとしても,0.1では1%しか説明できていません.よって,結果の記述として「有意な相関が見られた」と記述することは正しいですが,考察において因果関係が見られたなどと強く主張することは避けるべきです.何らかの影響関係が示唆されたなどと弱い言い方しかできません.この他にも第三の変数の影響や,階層相関,相関係数の三段論法等にも注意してください.
A.まず,相関係数の有意性検定とは,得られた相関係数が有意でないかどうかを検定しています.相関係数の有意性検定が有意になるかどうかはn(サンプル・サイズ)がいくつであるか?によって決まります.この結果,有意であると結論付けられたとき,その相関係数は「0ではない」と言えます.
次に,0ではないことと,相関係数が大きい,小さいという議論は別の問題であることに注意してください.この意味で,結果において「有意な相関係数が得られた」と記述することは間違っていません.
次に,考察についてですが,これは各研究分野によって違うために,一概には言えません.例えば,生物など厳密な科学性が要求されている学問領域では,0.8程度あったとしても,あまり大きいと見られないかもしれませんs.逆に心理など様々な要因が考えられる領域では0.3程度でも何かしらの関係があると考えることが多い印象を受けます.
また,学問領域のほかにも,研究対象によっても解釈が違う場合があります.例えば,「うつ」には,生物学的な要因が80%程度関係があると分かっていたとします.この時に,「うつ」の生物学的な要因以外の要因の中で何が関係があるかを調べるといった研究を行うとします.このとき,生物学的な要因は「うつ」に対して,20%以上の影響力を持っていません.相関係数に換算して考えると,0.5を下回ります.このように,研究する対象によっても,その解釈が変わることがあります.
以上のような点を考慮するために,先行研究をレビューし,得られた相関係数が自分の研究領域でどのような価値を持っているかと考えることは非常に重要です.
最後に,一般的な相関係数の解釈の留意点についても忘れないようにしてください.特に,0.1の相関係数で有意であり,先行研究でも0.1程度あれば良いとなっていたとしても,0.1では1%しか説明できていません.よって,結果の記述として「有意な相関が見られた」と記述することは正しいですが,考察において因果関係が見られたなどと強く主張することは避けるべきです.何らかの影響関係が示唆されたなどと弱い言い方しかできません.この他にも第三の変数の影響や,階層相関,相関係数の三段論法等にも注意してください.
Q.ある質問項目があります.7件法です.1-7点として点数化しています.1点であるほど,その行動を男性的役割である.7点であるほど,その行動を女性的役割であると判断しているとします.この時,ある行動を男性的もしくは女性的役割であると判断しているかを調べるには,どうしたらよいでしょうか?
A.この時,4点をとれば,それが中性的であると判断しています.このことを利用して,ある行動に対する得点が4と同じか否かを統計的に判断すればよいでしょう.これは,一条件における標本平均と母平均の検定を使用すればよいでしょう.以下のURLの母分散が未知の場合です.
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Average/Mean1.html
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/JavaScript/ie-mean2.html
でできます.
A.この時,4点をとれば,それが中性的であると判断しています.このことを利用して,ある行動に対する得点が4と同じか否かを統計的に判断すればよいでしょう.これは,一条件における標本平均と母平均の検定を使用すればよいでしょう.以下のURLの母分散が未知の場合です.
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Average/Mean1.html
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/JavaScript/ie-mean2.html
でできます.
Q.ある事柄が成功したか失敗したかを聞きました.その後,その時の条件について?〜?で選んでもらいました.この時,成功する条件は何か?失敗する条件は何か?もしくは,条件によって成功するか,失敗するかは変わらないか?を調べたいと思います.どうすればよいでしょうか?
A.2x3のχ2検定を使います.(成功・失敗)×(条件?,条件?,条件?)です.この時,帰無仮説は「成功と失敗で,条件?〜?の比率は変わらない」となります.もし,この帰無仮説が棄却されれば,成功と失敗で条件による違いが見られることになります.この後,残差分析をすればよいでしょう.χ2検定〜残差分析はSTARでできます.
A.2x3のχ2検定を使います.(成功・失敗)×(条件?,条件?,条件?)です.この時,帰無仮説は「成功と失敗で,条件?〜?の比率は変わらない」となります.もし,この帰無仮説が棄却されれば,成功と失敗で条件による違いが見られることになります.この後,残差分析をすればよいでしょう.χ2検定〜残差分析はSTARでできます.
Q.因子分析を行ない.尺度得点を計算しました.尺度得点は合計点(各項目の合計点)で出すのが普通ですが,平均点(各尺度の合計点を項目数で割る)でも良いのですか?また,この尺度得点を従属変数にし,他の群わけ変数を独立変数とし,分散分析を行おうと思いますが,その結果に違いは出ますか?
A.結論的には,どちらでも良いです.また,分散分析の結果は変わりません.なぜかと言うと,項目の合計点を項目数で割るか割らないかの違いなので,分散分析で用いられる分散比は変わりません.
しかし,一般的には合計得点が用いられるようです.
また,従属変数が違う場合(例えば,因子1と因子2)などは平均値を比較できません.この事に注意してください.
A.結論的には,どちらでも良いです.また,分散分析の結果は変わりません.なぜかと言うと,項目の合計点を項目数で割るか割らないかの違いなので,分散分析で用いられる分散比は変わりません.
しかし,一般的には合計得点が用いられるようです.
また,従属変数が違う場合(例えば,因子1と因子2)などは平均値を比較できません.この事に注意してください.
Q.ある二つの質問項目があります.この質問項目の高低によって,群を4つに分け,他の尺度を従属変数にし一要因の分散分析を行いました.しかし,この群分け変数は,2x2の格子のように考えることもできます.そうすると二要因の分散分析だと思います.両者は何が違うのでしょうか?
A.哲学が違うだけです.一要因の分散分析を用いる方法では,4群は完全に独立であり,従属変数の違いを1つの次元で考えています.しかし,後者の二要因の分散分析では二つの次元で捉えようとしています.二要因の分散分析では,?Aの主効果,?Bの主効果,?交互作用という分析ができます.これは,一要因分散分析の内容を包括的に見ているわけではありません.この事に注意してください.
具体的には,HH,HL,LH,LL群として四群を表現すると,二要因分散分析では,HLとLHの比較はできません.どちらも,利点がありますので,とりあえずは両者の結果を出してみると良いと思います.
A.哲学が違うだけです.一要因の分散分析を用いる方法では,4群は完全に独立であり,従属変数の違いを1つの次元で考えています.しかし,後者の二要因の分散分析では二つの次元で捉えようとしています.二要因の分散分析では,?Aの主効果,?Bの主効果,?交互作用という分析ができます.これは,一要因分散分析の内容を包括的に見ているわけではありません.この事に注意してください.
具体的には,HH,HL,LH,LL群として四群を表現すると,二要因分散分析では,HLとLHの比較はできません.どちらも,利点がありますので,とりあえずは両者の結果を出してみると良いと思います.
Q.因子分析をし,因子1(F1)が10項目,因子2(F2)が5項目です.
因子分析の尺度得点は各項目ごとの平均点ではだめなの?
A.いいです.普通は合計点を使いますが,平均点でも良いです.平均点だと,他の群分け変数を用い,ある因子における各項目の平均得点の平均得点に差があるかどうかを検定するときに,「平均の平均」ってどうなのかな?と考えたりするようですが,数学的には項目数で平均と標準偏差が除されているだけなので,F値は全く変わりません.
しかし,注意すべきことがあります.例えば,性別×各因子と言うように,従属変数が違う(例えば,F1とF2の因子は,項目内容が違います.)場合は,平均値を比べることができません.このような目的を行うために,平均の平均を用いる場合はだめです.これは,従属変数が違うためです.
因子分析の尺度得点は各項目ごとの平均点ではだめなの?
A.いいです.普通は合計点を使いますが,平均点でも良いです.平均点だと,他の群分け変数を用い,ある因子における各項目の平均得点の平均得点に差があるかどうかを検定するときに,「平均の平均」ってどうなのかな?と考えたりするようですが,数学的には項目数で平均と標準偏差が除されているだけなので,F値は全く変わりません.
しかし,注意すべきことがあります.例えば,性別×各因子と言うように,従属変数が違う(例えば,F1とF2の因子は,項目内容が違います.)場合は,平均値を比べることができません.このような目的を行うために,平均の平均を用いる場合はだめです.これは,従属変数が違うためです.
Q.フィッシャーの正確確率計算の後,残差分析をしていいのかな?
A.いいと思います(たぶん).正確確率計算はχ2検定の正確な場合です.可能なら,χ2検定より,フィッシャーの方法を用いたほうが,良いです.2x2より大きい場合はRを用いるか,
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/exact/fisher/getpar.html
で行ってください.
残差分析は,STARを用いるか,Rの青木先生の関数でできます.
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/R/my-chisq-test.html
この残差分析ですが,期待値との残差を調整し,計算するもので,χ2検定とは全く別の検定方法です.これが,たぶん,使ってよいという根拠です.
A.いいと思います(たぶん).正確確率計算はχ2検定の正確な場合です.可能なら,χ2検定より,フィッシャーの方法を用いたほうが,良いです.2x2より大きい場合はRを用いるか,
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/exact/fisher/getpar.html
で行ってください.
残差分析は,STARを用いるか,Rの青木先生の関数でできます.
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/R/my-chisq-test.html
この残差分析ですが,期待値との残差を調整し,計算するもので,χ2検定とは全く別の検定方法です.これが,たぶん,使ってよいという根拠です.
Q.重回帰分析をする前には、必ず相関分析をしないといけないの?
A.かならずしてください。特に、説明変数間に高い相関が見られる場合(多重共線性疑い)などが分かります。また、目的変数と説明変数の相関と、重回帰分析における偏回帰係数(β)の値が大きく異なるときも、この多重共線性の疑いがあります。最終的には、VIF等で判断しても良いですが、このあたりの事情を知っておくと、結果や考察についての論説の強さがおのずと変わってくると思います。
また、目的変数と説明変数の相関が全くないのならば、偏回帰係数も多くの場合は、有意になりません。ただし、抑制変数として機能している場合もあるために、単純には判断できません。そこは、他の説明変数と相関があるかどうかで考えます。また、抑制変数等になっている場合は、パス解析に移行するといいと思います。
結局、重回帰分析というのは、説明変数間にはほとんど相関係数がなく、目的変数とのみ相関がある状態が最も好ましいといえます。しかし、このような状態はあまりないため、どの程度、この状態になっているかを事前に知るうえで、相関行列の吟味が必要となってきます。
また、「結果」に、相関行列は必ずしも報告する必要はありません。
A.かならずしてください。特に、説明変数間に高い相関が見られる場合(多重共線性疑い)などが分かります。また、目的変数と説明変数の相関と、重回帰分析における偏回帰係数(β)の値が大きく異なるときも、この多重共線性の疑いがあります。最終的には、VIF等で判断しても良いですが、このあたりの事情を知っておくと、結果や考察についての論説の強さがおのずと変わってくると思います。
また、目的変数と説明変数の相関が全くないのならば、偏回帰係数も多くの場合は、有意になりません。ただし、抑制変数として機能している場合もあるために、単純には判断できません。そこは、他の説明変数と相関があるかどうかで考えます。また、抑制変数等になっている場合は、パス解析に移行するといいと思います。
結局、重回帰分析というのは、説明変数間にはほとんど相関係数がなく、目的変数とのみ相関がある状態が最も好ましいといえます。しかし、このような状態はあまりないため、どの程度、この状態になっているかを事前に知るうえで、相関行列の吟味が必要となってきます。
また、「結果」に、相関行列は必ずしも報告する必要はありません。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
お助け☆久留米大心理学科 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
お助け☆久留米大心理学科のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 相棒
- 59292人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209461人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19959人