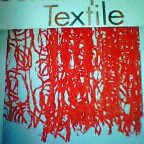【【ブログ抜粋】】ニッポンデザインはじまりモノガタリ
2007年『CasaBRUTUS』10月号のために書いた「知ってると得をする。日本デザインのはじまり物語。」
をアップします。この原稿を書いたこと自体すっかり忘れていました。ファイルの中から見つけ出し、
読んでいたら、加筆したくなったので、アップします。アップしてから更新していきます。
紙幅の関係で、1950年代までで、1960年代は東京五輪だけ触れていますが、この終わり方が
中途半端、グッドデザイン制度のこととか触れないといけないし、せめて大阪万博まで話を
もっていきたいと思っています。
______________
日本デザイン──明治から東京五輪まで。
日本には素晴らしいデザインの伝統があります。桂離宮や琳派の洗練、小紋や家紋の抽象、
茶の湯の前衛、根付の精妙、畳の合理的なモジュール性など枚挙にいとまがありません。
しかし、そもそもデザインという言葉には、下絵とか設計という意味があります。実際に作る前に
あらかじめ形や機構を決めること。産業革命が進行して、大量生産が可能になると、形を構想し
設計する人と、モノを工場で作る人が分業化していきます。
量産品の設計図はエンジニアだけで作ることもありますが、製品の装飾を施したり、美しい形態に
したい場合に、描画や造形の専門家が必要となりました。
そこでデザイナーという職業が誕生します。デザインは産業社会が進展していくなか、
急速に重要性を増していきました。
そう考えると、設計と実制作がまだ未分化であった江戸時代以前のデザインは、美の源流で
あっても、厳密な意味でのデザインとはやや違ったものになります。
ですから日本デザインのお話しは、明治時代から始まることになります。工業製品だけでなく、
グラフィックデザインや服飾デザインや建築まで話を広げる必要は、重々承知しています。が、
誌面の関係でここではプロダクトデザインを中心に話を進めたいと思います。
殖産興業のための工芸──明治
この物語に最初に登場するのは職人でも絵師でもなく、おサムライさんです。元佐賀藩士、
納富介次郎。納富は政府が1873年(明治6年)にウィーン万博へ派遣したメンバーのひとりでした。
ジャパネスク(日本趣味)流行の気運が高まるなか、日本の伝統的な工芸品は、ウィーンの人たちに
強い関心を引き、商人から引き合いも多かったそうです。
納富たちは、日本の工芸品が外貨を獲得する輸出品として大いに有望であることを
目の当たりにしたのです。【【続く11月1日分】】http://
2007年『CasaBRUTUS』10月号のために書いた「知ってると得をする。日本デザインのはじまり物語。」
をアップします。この原稿を書いたこと自体すっかり忘れていました。ファイルの中から見つけ出し、
読んでいたら、加筆したくなったので、アップします。アップしてから更新していきます。
紙幅の関係で、1950年代までで、1960年代は東京五輪だけ触れていますが、この終わり方が
中途半端、グッドデザイン制度のこととか触れないといけないし、せめて大阪万博まで話を
もっていきたいと思っています。
______________
日本デザイン──明治から東京五輪まで。
日本には素晴らしいデザインの伝統があります。桂離宮や琳派の洗練、小紋や家紋の抽象、
茶の湯の前衛、根付の精妙、畳の合理的なモジュール性など枚挙にいとまがありません。
しかし、そもそもデザインという言葉には、下絵とか設計という意味があります。実際に作る前に
あらかじめ形や機構を決めること。産業革命が進行して、大量生産が可能になると、形を構想し
設計する人と、モノを工場で作る人が分業化していきます。
量産品の設計図はエンジニアだけで作ることもありますが、製品の装飾を施したり、美しい形態に
したい場合に、描画や造形の専門家が必要となりました。
そこでデザイナーという職業が誕生します。デザインは産業社会が進展していくなか、
急速に重要性を増していきました。
そう考えると、設計と実制作がまだ未分化であった江戸時代以前のデザインは、美の源流で
あっても、厳密な意味でのデザインとはやや違ったものになります。
ですから日本デザインのお話しは、明治時代から始まることになります。工業製品だけでなく、
グラフィックデザインや服飾デザインや建築まで話を広げる必要は、重々承知しています。が、
誌面の関係でここではプロダクトデザインを中心に話を進めたいと思います。
殖産興業のための工芸──明治
この物語に最初に登場するのは職人でも絵師でもなく、おサムライさんです。元佐賀藩士、
納富介次郎。納富は政府が1873年(明治6年)にウィーン万博へ派遣したメンバーのひとりでした。
ジャパネスク(日本趣味)流行の気運が高まるなか、日本の伝統的な工芸品は、ウィーンの人たちに
強い関心を引き、商人から引き合いも多かったそうです。
納富たちは、日本の工芸品が外貨を獲得する輸出品として大いに有望であることを
目の当たりにしたのです。【【続く11月1日分】】http://
|
|
|
|
|
|
|
|
MODERN FABRIC 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
MODERN FABRICのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75486人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6445人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208288人