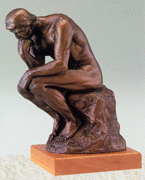学校教育についてはよく知らないの無責任なことを書くかもしれませんが,居酒屋気分ということでご了承ください。
現在,学校では,自分で考えることを重視するあまり,教えない,説明が書かれていないことが多いように思います。
自分で考えることはとてもいいことです。ただ,解き方や理論を発見しましょう,考え出しましょう,のように導き,説明がきちんと書かれていない,教えないことがあるのではないでしょうか。特に理科で感じます。
そういうことを考え出すことができれば,それは理想的です。しかし,天才たちが何年も取り組んで編み出した理論や解き方をふつうの生徒たちが簡単に考えつくことはかなり難しいことです。
私は,若い頃はとにかく知識を多く頭に詰め込んでいくことは悪いことではないと思います。ただ,それの理屈も学びながらです。先人たちが苦労して獲得した理論を知識として蓄えることも大切です。
現在,学校では,自分で考えることを重視するあまり,教えない,説明が書かれていないことが多いように思います。
自分で考えることはとてもいいことです。ただ,解き方や理論を発見しましょう,考え出しましょう,のように導き,説明がきちんと書かれていない,教えないことがあるのではないでしょうか。特に理科で感じます。
そういうことを考え出すことができれば,それは理想的です。しかし,天才たちが何年も取り組んで編み出した理論や解き方をふつうの生徒たちが簡単に考えつくことはかなり難しいことです。
私は,若い頃はとにかく知識を多く頭に詰め込んでいくことは悪いことではないと思います。ただ,それの理屈も学びながらです。先人たちが苦労して獲得した理論を知識として蓄えることも大切です。
|
|
|
|
コメント(8)
変な?!平等指向は必要ないな。訓練しなければ、しつけなければ成らないことは、どんな学問でもあります。その「しつけ」や作法が出来ないと考えることも、学ぶ事も出来ません。今の公立小中学校では、集団活動というか色々な人と接する、コミュニケーション能力、決まりの作り方、社会的マナーなどを伝えるだけで十分です!その集団活動でのしつけをされた上で、どうぞ、日本型学問の入り口を、動機づけをしてほしいな〜一歩、「学校」に踏み入れたところから、校門を出るまで、責任もって次世代を背負う子供達に、集団生活の作法をシッカと身につけさせて頂きたいな〜研究授業にしても、そのとき、その場限りが多いのは、周知の事実。たまに付属に行って、たった一回やそこらの授業ですごい!って言われても、それは一回だから出来る技…。学習は連続する日々の学習習慣を経て、初めてわかる!ことがある。だから喜びもある様な気がいたしますね。小さな塾で、「受験」って手段を使いながら、安心して、じっくり取り組める学問の入り口の扉を子供達と開け続けたいモノですね。日々戦いです!
SSJさん、こんにちは。
お褒めの言葉を有り難うございます。居酒屋さんでってことで、勢い書いたものでして…
「日本型学問」…は「形態」って言葉がいつの間にか消えておりまして、言葉足らずで、私がいつも使うことばだったので、言葉の概念規定をしておりませんでした。済みません。
書きたかったのは、明るい挨拶から教室が始まり、黒板に対して、クラス全員が学習時間の数分前に着席し、一斉に授業が始まるが、黒板の板書に集中し、ノートを取り、質問は挙手。相手の話に耳を傾け、一つのテーマをみんなで考え、丁寧な言葉で会話がなされる。声を出すときはクラスで声を揃えようとする。終わりは静かに、心を落ち着け、挨拶で終わり、質問ある時は、その旨伝え、質問を。決して奇声を発せず、こちらも声をあらげることなぞなし。
U,S,Aや中国、ヨーロッパからの研究視察に来られると、そんな風景は奇妙に映ったらしい。決して現代的な教育現場では見られないらしく、これが日本教育、いや日本製品の完成度の高さの秘密であると恐れたというエピソード有り。なんの本だったかな〜発達段階で中3生までは…と感じていますが…現状(私の感覚では小学高学年までだとおもいますが、最近は…)
私どもの塾は小さいが、挨拶だけはしっかり、今でもこだわってます。授業時間中の静けさは、地元高校の先生の折り紙付き。「静かであること」と「じっくり取り組む」事は相関があるような気がいたします。こちらも学問の入り口までは、と真摯な気持ちで当たりたい。教育は人の、先人達の歴史を次世代に伝える智慧だと思っていますので、少なからず敬意を払い、こちらも伝えると言うのを形で表したモノを私は「日本型学問形態」と規定しております。ただのこだわりとノスタルジアかな〜決して軍隊ではないですが、時にその教育の一端は必要なことではないかな〜と再構築しております。居酒屋会話でした。
お褒めの言葉を有り難うございます。居酒屋さんでってことで、勢い書いたものでして…
「日本型学問」…は「形態」って言葉がいつの間にか消えておりまして、言葉足らずで、私がいつも使うことばだったので、言葉の概念規定をしておりませんでした。済みません。
書きたかったのは、明るい挨拶から教室が始まり、黒板に対して、クラス全員が学習時間の数分前に着席し、一斉に授業が始まるが、黒板の板書に集中し、ノートを取り、質問は挙手。相手の話に耳を傾け、一つのテーマをみんなで考え、丁寧な言葉で会話がなされる。声を出すときはクラスで声を揃えようとする。終わりは静かに、心を落ち着け、挨拶で終わり、質問ある時は、その旨伝え、質問を。決して奇声を発せず、こちらも声をあらげることなぞなし。
U,S,Aや中国、ヨーロッパからの研究視察に来られると、そんな風景は奇妙に映ったらしい。決して現代的な教育現場では見られないらしく、これが日本教育、いや日本製品の完成度の高さの秘密であると恐れたというエピソード有り。なんの本だったかな〜発達段階で中3生までは…と感じていますが…現状(私の感覚では小学高学年までだとおもいますが、最近は…)
私どもの塾は小さいが、挨拶だけはしっかり、今でもこだわってます。授業時間中の静けさは、地元高校の先生の折り紙付き。「静かであること」と「じっくり取り組む」事は相関があるような気がいたします。こちらも学問の入り口までは、と真摯な気持ちで当たりたい。教育は人の、先人達の歴史を次世代に伝える智慧だと思っていますので、少なからず敬意を払い、こちらも伝えると言うのを形で表したモノを私は「日本型学問形態」と規定しております。ただのこだわりとノスタルジアかな〜決して軍隊ではないですが、時にその教育の一端は必要なことではないかな〜と再構築しております。居酒屋会話でした。
123さん、ありがとうございます。
「静かであること」と「じっくり取り組む」事には相関がある。これも同感。ただ、私の場合はそれに気が付くのにずいぶん時間がかかりましたが。遠回りしたのは私の受けた『民主教育』の影響かとも・・。私は1958年生まれ。多分、Yojiさんと123さんの中間かな。自由はよいことという教育でしたね。教育の手法も封建的と言われた瞬間に抹殺される時代でした。
現在、私の塾は個別ですが私語は一切ありません。そのような雰囲気を作り上げました。質問しずらいのでは、という懸念はありますが何を優先するかと言う問題ですから。
私語と、勉強に関する話題との境界線はかなり難しい。だから、私の塾ではトイレに立つときと質問するとき、其の他、緊急事態のときを除いては生徒の声は聞かれません。
個別に来ているので、隣の生徒が何年生でどこの中学の生徒かも多分知らないのではないでしょうか。だから、イベントもしません。(つい、書き過ぎました。トピックからは外れてませんよね。)
「静かであること」と「じっくり取り組む」事には相関がある。これも同感。ただ、私の場合はそれに気が付くのにずいぶん時間がかかりましたが。遠回りしたのは私の受けた『民主教育』の影響かとも・・。私は1958年生まれ。多分、Yojiさんと123さんの中間かな。自由はよいことという教育でしたね。教育の手法も封建的と言われた瞬間に抹殺される時代でした。
現在、私の塾は個別ですが私語は一切ありません。そのような雰囲気を作り上げました。質問しずらいのでは、という懸念はありますが何を優先するかと言う問題ですから。
私語と、勉強に関する話題との境界線はかなり難しい。だから、私の塾ではトイレに立つときと質問するとき、其の他、緊急事態のときを除いては生徒の声は聞かれません。
個別に来ているので、隣の生徒が何年生でどこの中学の生徒かも多分知らないのではないでしょうか。だから、イベントもしません。(つい、書き過ぎました。トピックからは外れてませんよね。)
どのトピックに書けば良いのか分からなかったので、こちらにお尋ねします。
あ、私は教師でも何でもない普通の一般人(以下)なので、お手柔らかにお願いします( ̄◇ ̄;)
小学生の【算数】から百分率の問題を例に出してみます。
・195cmは、150cmの【 】%です。
これらの問題を教えていた時、「これは掛け算?割り算?」と聞かれました。
私は、まず「何の数値を聞かれているの?単位?それともパーセンテージ?」と聞き返しましたが、「…(問題を眺め、【 】%という記述を見て)、パーセンテージ?」と、自信なさげ。
比べる量と、もとにする量の区別がつかない様なのです。「もとにする量はどれ?」と聞いても、ウーンと唸り、195cmや150cmを指差して、私の顔を見るだけです。
特に割り算を用いて算出しなければならない場合、割る数と割られる数が逆になると、あり得ない数字が!(;┰_┰)
そして、少し言い回し方を変えた問い
・60kgの105%は、【 】kgです。
など、もとにする量を先に書いてあるか、後に書いてあるかで、混乱する様なのです。
これは国語力から教えねばならんかいな?と、述語から主語を探すやり方を教えましたが、イマイチ。
YOJIさんの「田の字」を使おうにも、当てはめる数値を間違ってしまえば意味がありません。
何か良い教え方はないでしょうか?(Ω△Ω)
あ、私は教師でも何でもない普通の一般人(以下)なので、お手柔らかにお願いします( ̄◇ ̄;)
小学生の【算数】から百分率の問題を例に出してみます。
・195cmは、150cmの【 】%です。
これらの問題を教えていた時、「これは掛け算?割り算?」と聞かれました。
私は、まず「何の数値を聞かれているの?単位?それともパーセンテージ?」と聞き返しましたが、「…(問題を眺め、【 】%という記述を見て)、パーセンテージ?」と、自信なさげ。
比べる量と、もとにする量の区別がつかない様なのです。「もとにする量はどれ?」と聞いても、ウーンと唸り、195cmや150cmを指差して、私の顔を見るだけです。
特に割り算を用いて算出しなければならない場合、割る数と割られる数が逆になると、あり得ない数字が!(;┰_┰)
そして、少し言い回し方を変えた問い
・60kgの105%は、【 】kgです。
など、もとにする量を先に書いてあるか、後に書いてあるかで、混乱する様なのです。
これは国語力から教えねばならんかいな?と、述語から主語を探すやり方を教えましたが、イマイチ。
YOJIさんの「田の字」を使おうにも、当てはめる数値を間違ってしまえば意味がありません。
何か良い教え方はないでしょうか?(Ω△Ω)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
セルフラーニング 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-