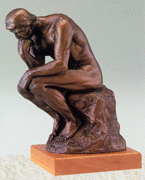はじめまして帳に
くるんさんから
>>もっと楽しんで勉強してもらいたいと思っているのですが
というコメントをいただきました。
ぼくは、
>> 楽しく学習してもらいたい、
願いは同じです。
と、気軽な気持ちでコメントを返しました。
そしてあとで「楽しく勉強する、楽しく学習する」、というのはどういうことだろうかなと考えてみました。
いまぼくの頭の中に三つあります。
一つは、子どもの好きなことをさせるということです。以前サドベリーの学校について意見を交換し合いました。その学校では子どもが好きなことだけをさせるそうです。そうする中で自分で何を学んだらいいのかを見つけ、そしてその時に学べばいいというのです。
一つの試みとしては面白いかも知れません。しかし実行するのは、今の日本では難しいと思います。
二つ目は、ゲームのような子どもの楽しいことをさせながら、それの中に学ぶことを紛れ込ませるということです。
すごろくをしながら、数の概念を教えていく。
買い物ごっこをするなかで、足し算引き算を教える。
などが考えられます。
このコミュで以前意見交換をした、漫画で学ぶなどもその中の一つでしょう。
それはうまくいけば面白いものです。漫画で学ぶというのは、僕自身が好きですし、結構有効な方法だと思います。
三つ目は、学ぶこと自体が面白い、学ぶこと自体が楽しいとすることです。
わかるというのは、楽しいことです。
塾に入ってしばらくすると、「わかると面白いね」という言葉をよく耳にします。これまではわからなかったから面白くなかったのですね。それがわかるようになると勉強そのものが面白く感じるのです。
面白いというのは楽しいとつながると考えて今書き込んでいます。
だからどのようにすれば、子どもたちがわかるようになるのか、というのがその場合の課題になります。
僕はそれを大切にしています。子どもたちがわかる学習をするにはどうすればいいのかということです。
そのための一つの方法が、セルフラーニングです。セルフラーニングだと個人で自分のペースで学ぶことができます。ほかの子と歩調を合わせるのではなく、自分がわかるように学習を進めていく。そうすると子どもたちもわかって、そして楽しく学習をすることができるのではないでしょうか。
また、ビール片手に、気軽な気持ちで意見を交換し合いましょう。
くるんさんから
>>もっと楽しんで勉強してもらいたいと思っているのですが
というコメントをいただきました。
ぼくは、
>> 楽しく学習してもらいたい、
願いは同じです。
と、気軽な気持ちでコメントを返しました。
そしてあとで「楽しく勉強する、楽しく学習する」、というのはどういうことだろうかなと考えてみました。
いまぼくの頭の中に三つあります。
一つは、子どもの好きなことをさせるということです。以前サドベリーの学校について意見を交換し合いました。その学校では子どもが好きなことだけをさせるそうです。そうする中で自分で何を学んだらいいのかを見つけ、そしてその時に学べばいいというのです。
一つの試みとしては面白いかも知れません。しかし実行するのは、今の日本では難しいと思います。
二つ目は、ゲームのような子どもの楽しいことをさせながら、それの中に学ぶことを紛れ込ませるということです。
すごろくをしながら、数の概念を教えていく。
買い物ごっこをするなかで、足し算引き算を教える。
などが考えられます。
このコミュで以前意見交換をした、漫画で学ぶなどもその中の一つでしょう。
それはうまくいけば面白いものです。漫画で学ぶというのは、僕自身が好きですし、結構有効な方法だと思います。
三つ目は、学ぶこと自体が面白い、学ぶこと自体が楽しいとすることです。
わかるというのは、楽しいことです。
塾に入ってしばらくすると、「わかると面白いね」という言葉をよく耳にします。これまではわからなかったから面白くなかったのですね。それがわかるようになると勉強そのものが面白く感じるのです。
面白いというのは楽しいとつながると考えて今書き込んでいます。
だからどのようにすれば、子どもたちがわかるようになるのか、というのがその場合の課題になります。
僕はそれを大切にしています。子どもたちがわかる学習をするにはどうすればいいのかということです。
そのための一つの方法が、セルフラーニングです。セルフラーニングだと個人で自分のペースで学ぶことができます。ほかの子と歩調を合わせるのではなく、自分がわかるように学習を進めていく。そうすると子どもたちもわかって、そして楽しく学習をすることができるのではないでしょうか。
また、ビール片手に、気軽な気持ちで意見を交換し合いましょう。
|
|
|
|
コメント(5)
Yojiさん ありがとうございます。
大変失礼ながら、今気付きました。
私自身も何気なく思っているままに書いたのですが、こんなに深く考えていただいていたことに気付かず、申し訳なく思いつつもとても嬉しく感じます
私の考える勉強することを楽しむというのも三つ目にあげていただいた、楽しさのことです 。私は教え始めてまだ1年で経験も浅く、それぞれの子供達にどう対応するべきか悩む日々です
。私は教え始めてまだ1年で経験も浅く、それぞれの子供達にどう対応するべきか悩む日々です
セルフラーニングはとっても大切だと思っています。ただ、主体性を持って自ら勉強しようという姿勢に子供を持っていくのが難しい 。とくに高学年の女の子…。
。とくに高学年の女の子…。
理解力はあると思うのですが、忍耐力がないのでしょうか?。問題を解こうとしない… 。レベルを下げて簡単にしても、よくできるねってほめてみても、ここで頑張らないとって励ましてみても…。
。レベルを下げて簡単にしても、よくできるねってほめてみても、ここで頑張らないとって励ましてみても…。
エンジンさえかかれば、きっとできるので「できた 楽しい
楽しい 」を感じてもらえそうなのですが…
」を感じてもらえそうなのですが…
経験が浅くて、なんとなくコメントできずにいたのですが、これからまた相談させていただこうと思います。よろしくお願いいたします

大変失礼ながら、今気付きました。
私自身も何気なく思っているままに書いたのですが、こんなに深く考えていただいていたことに気付かず、申し訳なく思いつつもとても嬉しく感じます
私の考える勉強することを楽しむというのも三つ目にあげていただいた、楽しさのことです
セルフラーニングはとっても大切だと思っています。ただ、主体性を持って自ら勉強しようという姿勢に子供を持っていくのが難しい
理解力はあると思うのですが、忍耐力がないのでしょうか?。問題を解こうとしない…
エンジンさえかかれば、きっとできるので「できた
経験が浅くて、なんとなくコメントできずにいたのですが、これからまた相談させていただこうと思います。よろしくお願いいたします
今の指導要領では「意欲、関心」を重視しています。
通知表の一番上の欄はこれ。
先日、この欄だけがB評価(他はA)だという生徒のお母さんの相談を受けました。授業中に手を上げたり、理科の実験に積極的に参加したりすると上がりますよ、と答えておきました。
何かおかしい。
評価するようになれば、人は動くだろうという安易な発想に嫌悪します。
文部科学省の指導がきついのだと思いますが、最近は期末テストの最後の問題がその生徒の授業に対する感想欄になっています。沢山書くほど評価が上がるらしい。
今後この傾向は強まるでしょうね。
(先日誰だったかこの傾向を評価していましたが、私は憂いています。)
言うまでもなく、生徒の意欲や関心が上がらないという現実に対する分かりやすい形での行政の対応でしょう。(トピずれはご容赦を。真夏の居酒屋ですから。)
通知表の一番上の欄はこれ。
先日、この欄だけがB評価(他はA)だという生徒のお母さんの相談を受けました。授業中に手を上げたり、理科の実験に積極的に参加したりすると上がりますよ、と答えておきました。
何かおかしい。
評価するようになれば、人は動くだろうという安易な発想に嫌悪します。
文部科学省の指導がきついのだと思いますが、最近は期末テストの最後の問題がその生徒の授業に対する感想欄になっています。沢山書くほど評価が上がるらしい。
今後この傾向は強まるでしょうね。
(先日誰だったかこの傾向を評価していましたが、私は憂いています。)
言うまでもなく、生徒の意欲や関心が上がらないという現実に対する分かりやすい形での行政の対応でしょう。(トピずれはご容赦を。真夏の居酒屋ですから。)
「塾に通っている人の50%の人が満足しているとその塾は大成功!」というお話を聞いたことがあります。
「満足=楽しい」かどうかはわかりませんが、確かに勉強していて楽しいと感じる人はいます。
多分、何かが確実に動いているという実感が持てる人かなと思います。やっていることに意味を感じる。=分かる。いやにならない。やらされている感がない。充実感が感じられる。
自分自身の仕事に対するモチベーションを考えた時、一番の喜びは生徒たちが動いたと感じるときなんですね。
なんとなく親の要望にこたえるためにやってきた塾で、自分から進んで勉強しだす姿を見る。分かった喜びを分かち合える、成績が上がった時をともに喜べる。一定の時間共に燃える。そんなときはとても達成感にあふれます。
そういう経験が仕事に対するエネルーギー源になっているなあと思います。
若いころはたくさんの生徒がいて教室が大きくなることをなんとなく夢見ていましたが、それは案外しんどいだけで、達成感がないものだと分かった時、方向が変わってしまった。
小さな教室で一人ひとりを確実に変えていく。こっちのほうがよほど面白く深い。そうだ楽しさの中に必要な要素は、「深さ」だ。
生徒が求めているのも案外、先生との関わりの深さかもしれないな。自分をしっかり見つめてくれる対象がいるとき、学習もまた楽しくなるのかもしれないですね。
毎日本当に暑い! クーラーの中で昼寝をするのがすごく気持ちがいいなあ。
>>>評価するようになれば、人は動くだろうという安易な発想に嫌悪します。
…そうか、民生児童委員をしているときに、ちょうどゆとり教育に入ろうとしているときです。学校の先生と教育にかかわりのある人たち向けに講演会があったんですね。ゆとり教育に対する目標を聞きながら「すごい」と思いましたね。講演者は文部科学省の若い人でした。私もその意味をよく理解して協力したいと思いましたね。
日本では大意が下に伝わらない。子ども会にしても自治会にしても育友会にしても、県単位の会合で話し合われていることとクラスや地域で話し合われていることとの差がありすぎです。
どんな規則を決めても、それを行う人の道徳観が低ければ、どんなふうにでも曲げてしまえる。
要は人のありようが大切なんですね。だから意欲や関心が前向きな人が後々伸びる。
何でも書けばいい? 何でも手を挙げればいい? というのはちょっと違うように思います。もっとまともに深いところで判断されているのではないかと思いますがね。
学校の懇談の後に私も追うように懇談をしていますが、今年の評価は姑息な手段ではなく、人物が評価されたと今回は思いましたね。
私自身が単細胞なところがあるので…すみません。
「満足=楽しい」かどうかはわかりませんが、確かに勉強していて楽しいと感じる人はいます。
多分、何かが確実に動いているという実感が持てる人かなと思います。やっていることに意味を感じる。=分かる。いやにならない。やらされている感がない。充実感が感じられる。
自分自身の仕事に対するモチベーションを考えた時、一番の喜びは生徒たちが動いたと感じるときなんですね。
なんとなく親の要望にこたえるためにやってきた塾で、自分から進んで勉強しだす姿を見る。分かった喜びを分かち合える、成績が上がった時をともに喜べる。一定の時間共に燃える。そんなときはとても達成感にあふれます。
そういう経験が仕事に対するエネルーギー源になっているなあと思います。
若いころはたくさんの生徒がいて教室が大きくなることをなんとなく夢見ていましたが、それは案外しんどいだけで、達成感がないものだと分かった時、方向が変わってしまった。
小さな教室で一人ひとりを確実に変えていく。こっちのほうがよほど面白く深い。そうだ楽しさの中に必要な要素は、「深さ」だ。
生徒が求めているのも案外、先生との関わりの深さかもしれないな。自分をしっかり見つめてくれる対象がいるとき、学習もまた楽しくなるのかもしれないですね。
毎日本当に暑い! クーラーの中で昼寝をするのがすごく気持ちがいいなあ。
>>>評価するようになれば、人は動くだろうという安易な発想に嫌悪します。
…そうか、民生児童委員をしているときに、ちょうどゆとり教育に入ろうとしているときです。学校の先生と教育にかかわりのある人たち向けに講演会があったんですね。ゆとり教育に対する目標を聞きながら「すごい」と思いましたね。講演者は文部科学省の若い人でした。私もその意味をよく理解して協力したいと思いましたね。
日本では大意が下に伝わらない。子ども会にしても自治会にしても育友会にしても、県単位の会合で話し合われていることとクラスや地域で話し合われていることとの差がありすぎです。
どんな規則を決めても、それを行う人の道徳観が低ければ、どんなふうにでも曲げてしまえる。
要は人のありようが大切なんですね。だから意欲や関心が前向きな人が後々伸びる。
何でも書けばいい? 何でも手を挙げればいい? というのはちょっと違うように思います。もっとまともに深いところで判断されているのではないかと思いますがね。
学校の懇談の後に私も追うように懇談をしていますが、今年の評価は姑息な手段ではなく、人物が評価されたと今回は思いましたね。
私自身が単細胞なところがあるので…すみません。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
セルフラーニング 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-