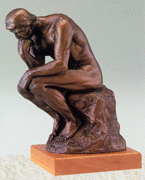いろいろな試験に向けて勉強している人のために,このトピを立てました。
セルフラーニングの参加者Dr.NEROさんの日記に次の本が紹介されていたので読みました。
社会人の「勉強の技術」―ここで“能力”の差がつく! (知的生きかた文庫) (1998/09)
高島 徹治 / 三笠書房
価格:¥ 520(税込)
いい本でした。理解を重視するという点でも私の考えと似ていて共感を持って読み進めることができました。
その中に「過去問勉強法(p110〜)」という節があるので,その中から抜き書きしてみます。
テキストを開いて勉強を始める前に,まずやっておかなければならないことがある。それは「前々年の問題」をやってみるということだ。
一般的に試験というものは,過去何年,あるいは何十年にわたって行われている場合が多いから,当然,過去に出された問題というものがある。これを,ふつう「過去問(過去に出題された問題の略)といっている。
勉強しようとしている科目を知るためには,過去問に当たってみるのが一番よい方法なのだ。
過去問を検討すれば,どの項目から,何回くらい,どの程度むずかしい問題が出題されているかを把握できる。また,出題の傾向がどう移り変わっているかもわかる。
二回目の利用は,ひとわたりテキストを学習しおえたあとでの,アウトプット(出力)演習である。
記憶を定着させるためには,仕入れた知識をもとに,問題を数多くこなすアウトプットの演習が必要になる。
最後にもう一度,「過去問」を利用する
試験日の一週間前,いままでとっておいて一度も目を通したことのない直前年度の問題を,試験と同じ時間でやってみるのだ。
(抜き書きは以上)
私(Yoji)は,過去問をかなり活用しています。
あさってから高校受験夏期学習が始まります。
そのときに,過去問をさせます。生徒はびっくりします。「えー,まだ習っていないのに」と。
分からなくていもいい。とにかく,高校入試とはどういうものなのかをつかんでもらう。
その中で,相似,三平方の定理,二次関数はあなたたちはまだ習っていないが,必ず出るということが分かるだろう,というようなことを確認するのです。
そうすることによって,これから半年間の勉強の方向が決まります。
セルフラーニングの参加者Dr.NEROさんの日記に次の本が紹介されていたので読みました。
社会人の「勉強の技術」―ここで“能力”の差がつく! (知的生きかた文庫) (1998/09)
高島 徹治 / 三笠書房
価格:¥ 520(税込)
いい本でした。理解を重視するという点でも私の考えと似ていて共感を持って読み進めることができました。
その中に「過去問勉強法(p110〜)」という節があるので,その中から抜き書きしてみます。
テキストを開いて勉強を始める前に,まずやっておかなければならないことがある。それは「前々年の問題」をやってみるということだ。
一般的に試験というものは,過去何年,あるいは何十年にわたって行われている場合が多いから,当然,過去に出された問題というものがある。これを,ふつう「過去問(過去に出題された問題の略)といっている。
勉強しようとしている科目を知るためには,過去問に当たってみるのが一番よい方法なのだ。
過去問を検討すれば,どの項目から,何回くらい,どの程度むずかしい問題が出題されているかを把握できる。また,出題の傾向がどう移り変わっているかもわかる。
二回目の利用は,ひとわたりテキストを学習しおえたあとでの,アウトプット(出力)演習である。
記憶を定着させるためには,仕入れた知識をもとに,問題を数多くこなすアウトプットの演習が必要になる。
最後にもう一度,「過去問」を利用する
試験日の一週間前,いままでとっておいて一度も目を通したことのない直前年度の問題を,試験と同じ時間でやってみるのだ。
(抜き書きは以上)
私(Yoji)は,過去問をかなり活用しています。
あさってから高校受験夏期学習が始まります。
そのときに,過去問をさせます。生徒はびっくりします。「えー,まだ習っていないのに」と。
分からなくていもいい。とにかく,高校入試とはどういうものなのかをつかんでもらう。
その中で,相似,三平方の定理,二次関数はあなたたちはまだ習っていないが,必ず出るということが分かるだろう,というようなことを確認するのです。
そうすることによって,これから半年間の勉強の方向が決まります。
|
|
|
|
コメント(12)
1: SSJ さん
さっそくのコメント,ありがとうございます。
「ビビる」という言葉があったので,
最初の年,過去問をさせてみて,私自身がおおいにビビりました。こんなにできない連中を,ぼくはあと半年で高校を合格させるだけの力をつけさせることができるだろうか,と。
生徒の方が意外に平気でしたね。
その後の半年で,子どもたちの伸びること,伸びること。すごい勢いです。
今では,私は平気です。
少し生徒をビビらせます。
模擬テストで,学校の成績がよかったり,志望校の判定がよい子にでも,
「いまの成績はいいかもしれないけど,あなたは入試問題をこんなにも解くことができないんだよ。いまの力では合格できないのは,あなたも分かるだろう。もちろん,他の生徒も同じだ。
マラソンに例えると,いま折り返し地点。あなたは確かにトップグループにいる。しかし,まだゴールしたわけではない。ちょっとペースを落とすとすぐに後ろの人に抜かれてしまう。それが過去問題を解くことでわかるだろう」
とね。少しビビらせる。しかし,みんなも同じだから,大丈夫だとフォローする,といった感じですね。
さっそくのコメント,ありがとうございます。
「ビビる」という言葉があったので,
最初の年,過去問をさせてみて,私自身がおおいにビビりました。こんなにできない連中を,ぼくはあと半年で高校を合格させるだけの力をつけさせることができるだろうか,と。
生徒の方が意外に平気でしたね。
その後の半年で,子どもたちの伸びること,伸びること。すごい勢いです。
今では,私は平気です。
少し生徒をビビらせます。
模擬テストで,学校の成績がよかったり,志望校の判定がよい子にでも,
「いまの成績はいいかもしれないけど,あなたは入試問題をこんなにも解くことができないんだよ。いまの力では合格できないのは,あなたも分かるだろう。もちろん,他の生徒も同じだ。
マラソンに例えると,いま折り返し地点。あなたは確かにトップグループにいる。しかし,まだゴールしたわけではない。ちょっとペースを落とすとすぐに後ろの人に抜かれてしまう。それが過去問題を解くことでわかるだろう」
とね。少しビビらせる。しかし,みんなも同じだから,大丈夫だとフォローする,といった感じですね。
私も過去問に賛成!ですよ〜使い方もいろいろですが…
夏に限定…
中学入試クラス…受験希望校の一年分だけさせます。
この夏の目標を明確にさせるため…で、そ の子のレベルや入会時期、仕上がり具合に もよりますが、動機づけと目標に…合格ラ インはここよ〜なんて…「喧嘩をするには まず、相手を知らないと…」なんて理屈で すわ〜全単元終わっているときは、夏に第 一志望校の過去問ばかり十年分をひたすら させ、解説ばかりの夏!ですね〜
公立高校コース…夏前に、昨年度分ホヤホヤ?のを5教科やらせ 未習事項を削除させ、50点に換算。今年 度の合格最低点数を伝えて、この夏の動機 付け
県外私立組… 過去問の夏です!
大学入試コース …センター用マーク模試もありますが、昨年度 のセンター試験問題を夏、受験予定科目一度や らせて点数を確認!夏、まずすることをの 計画に。履修コースの変更を志望校に合わ せて計画させ、問題集の選定と計画表を作 ります。
やっぱり、動機付けと指針、スランプ脱出には過去問がよろしいようで…。しっかり使わせます!漫然と過ごさせない、目標と今の位置をはっきりさせて、前に進ませるために…。こちらも不安ですし、こちらが不安と云うことは生徒も不安…何と云ってもお母さん方を納得させるにはわからないことで、こちらのペースに巻き込むのが安心です!保護者の方々には内緒ですが…。沢山いらっしゃったのですね〜YOJIさんのコミュは…。しかし、三者納得できるモノ、物差しは過去問ですから〜!目標もはっきりしますし、見えないモノと戦うのは不安!不満!ですから〜明確に…「次は模試だ〜!合格判定を見るのではなく、どこがこの夏出来て、出来なかったことはどこだ〜って明確にするために…秋から劇的に伸びる筈!」
なんてドラゴン○のようなことは前からいってま〜す!あの漫画が出てからやりにくい…です(笑い!)
夏に限定…
中学入試クラス…受験希望校の一年分だけさせます。
この夏の目標を明確にさせるため…で、そ の子のレベルや入会時期、仕上がり具合に もよりますが、動機づけと目標に…合格ラ インはここよ〜なんて…「喧嘩をするには まず、相手を知らないと…」なんて理屈で すわ〜全単元終わっているときは、夏に第 一志望校の過去問ばかり十年分をひたすら させ、解説ばかりの夏!ですね〜
公立高校コース…夏前に、昨年度分ホヤホヤ?のを5教科やらせ 未習事項を削除させ、50点に換算。今年 度の合格最低点数を伝えて、この夏の動機 付け
県外私立組… 過去問の夏です!
大学入試コース …センター用マーク模試もありますが、昨年度 のセンター試験問題を夏、受験予定科目一度や らせて点数を確認!夏、まずすることをの 計画に。履修コースの変更を志望校に合わ せて計画させ、問題集の選定と計画表を作 ります。
やっぱり、動機付けと指針、スランプ脱出には過去問がよろしいようで…。しっかり使わせます!漫然と過ごさせない、目標と今の位置をはっきりさせて、前に進ませるために…。こちらも不安ですし、こちらが不安と云うことは生徒も不安…何と云ってもお母さん方を納得させるにはわからないことで、こちらのペースに巻き込むのが安心です!保護者の方々には内緒ですが…。沢山いらっしゃったのですね〜YOJIさんのコミュは…。しかし、三者納得できるモノ、物差しは過去問ですから〜!目標もはっきりしますし、見えないモノと戦うのは不安!不満!ですから〜明確に…「次は模試だ〜!合格判定を見るのではなく、どこがこの夏出来て、出来なかったことはどこだ〜って明確にするために…秋から劇的に伸びる筈!」
なんてドラゴン○のようなことは前からいってま〜す!あの漫画が出てからやりにくい…です(笑い!)
私もたしか(うろ覚えなんですが)、大学入試のとき、つまり高3のときに、少し早めに志望校の過去問を入手して、自分自身に発破をかけていたと思います。
初見はもちろんわけがわからない。そこでそのレベルに近づくために基礎からひたすら取り組んでいく。ある程度まで行ったら、再び過去問を見てみる。やはりまだわからない。だが、以前よりは分かるような気がする。そしてまた基礎から・・・の繰り返しでモチベーションをあげ、入試に立ち向かっていたような気がします。
そういった経験から、私も受験に向かう生徒に対しては過去問をやらせてみたいのですが、どうも生徒も講師も及び腰というか、逃げ腰というか、弱気というか・・・、取り組むなんて・・・という雰囲気があります。過去問の件だけではありませんが・・・。
自分の意見、想いに論理的な裏づけがないため、強く主張できずにもどかしい思いをしております。(なんだか、もどかしいってたくさん言っているような気がする・・・ )
)
初見はもちろんわけがわからない。そこでそのレベルに近づくために基礎からひたすら取り組んでいく。ある程度まで行ったら、再び過去問を見てみる。やはりまだわからない。だが、以前よりは分かるような気がする。そしてまた基礎から・・・の繰り返しでモチベーションをあげ、入試に立ち向かっていたような気がします。
そういった経験から、私も受験に向かう生徒に対しては過去問をやらせてみたいのですが、どうも生徒も講師も及び腰というか、逃げ腰というか、弱気というか・・・、取り組むなんて・・・という雰囲気があります。過去問の件だけではありませんが・・・。
自分の意見、想いに論理的な裏づけがないため、強く主張できずにもどかしい思いをしております。(なんだか、もどかしいってたくさん言っているような気がする・・・
3: 123さん
さすがですね。ケースバイケースで使い分けていますね。
「目標と今の位置をはっきりさせ」ということは,分かっていましたが,「スランプ脱出」にもいいのですか。そういう使い方はまだやったことがないですね。
4: Jody さん
英検や漢字検定は,もう過去問ですよね。
特に低い級は,繰り返し似たような問題が出てくるので。
私のところでは,2週間前から過去問題をさせます。並べ替えの問題などは,過去問をしていないと,設問の意味も分からない生徒が多いです。
最初はまったくできなかった子がどんどん点数をとるようになります。
5: おりじんさん
おりじんさんの過去問の使っての経験はいいですね。そのようにうまく過去問を使わないと合格という目標には,到達できないと思いますね。
難しいからということで,及び腰になったのでは,合格は遠ざかるだけだと思うのですが。
さすがですね。ケースバイケースで使い分けていますね。
「目標と今の位置をはっきりさせ」ということは,分かっていましたが,「スランプ脱出」にもいいのですか。そういう使い方はまだやったことがないですね。
4: Jody さん
英検や漢字検定は,もう過去問ですよね。
特に低い級は,繰り返し似たような問題が出てくるので。
私のところでは,2週間前から過去問題をさせます。並べ替えの問題などは,過去問をしていないと,設問の意味も分からない生徒が多いです。
最初はまったくできなかった子がどんどん点数をとるようになります。
5: おりじんさん
おりじんさんの過去問の使っての経験はいいですね。そのようにうまく過去問を使わないと合格という目標には,到達できないと思いますね。
難しいからということで,及び腰になったのでは,合格は遠ざかるだけだと思うのですが。
自分の資格取得についての過去問対策をやっています。
勿論、過去と同じ問題は本試験で出題されません。
なので、過去問を丸覚えしても無駄です。
ところが、お馬鹿な私は何度もやると覚えちゃうんです。
内容ではなくて、雰囲気で「これは確かこの選択肢だったぞ!」って・・・
だから、二度目以降は正解率が上がります。
でも、本当のところはちゃんと理解していないと自分でも感じています。
結局の所、何度も間違える→極限的にこの分野は理解していない
と判明できますが・・・。
過去問だけの勉強ではなくて、やはり+αが必要ですね。
過去問の使い方の工夫について勉強になりました。
(自分だけでなく、子供の受験にも役立ちそうです)
セルフラーニングは、奥が深く色々な角度から楽しんでいます。
有難うございます。そして、今後とも宜しくお願い致します。
勿論、過去と同じ問題は本試験で出題されません。
なので、過去問を丸覚えしても無駄です。
ところが、お馬鹿な私は何度もやると覚えちゃうんです。
内容ではなくて、雰囲気で「これは確かこの選択肢だったぞ!」って・・・
だから、二度目以降は正解率が上がります。
でも、本当のところはちゃんと理解していないと自分でも感じています。
結局の所、何度も間違える→極限的にこの分野は理解していない
と判明できますが・・・。
過去問だけの勉強ではなくて、やはり+αが必要ですね。
過去問の使い方の工夫について勉強になりました。
(自分だけでなく、子供の受験にも役立ちそうです)
セルフラーニングは、奥が深く色々な角度から楽しんでいます。
有難うございます。そして、今後とも宜しくお願い致します。
私は答えを覚えるくらい過去問を解きまくるというのが、合格への道だと思っています。
とはいっても、入手できる過去問数が少なく、その問題レベル自体も低いのなら、あまり意味が無いかもしれませんが、10年分くらいの過去問があり、その問題レベルも高いものならば、一巡して戻ってくる頃には最初の問題も解答もあらかた忘れているはずです。
それでも何度も何度も解いているうちに、問題と解答を覚えてしまう頃には、もうすでにその問題と解答の意味内容を完全に理解してしまっていると思います。
もちろん、過去問だけに取り組むのではなく、過去問を考えて解けて、ミスであっても解答を見て理解できるレベルに到達しているということが前提です。
あとその過去問の答え方が選択肢の少ない選択問題だと、この方法はあまり効果を発揮しないかもしれません。
とはいっても、入手できる過去問数が少なく、その問題レベル自体も低いのなら、あまり意味が無いかもしれませんが、10年分くらいの過去問があり、その問題レベルも高いものならば、一巡して戻ってくる頃には最初の問題も解答もあらかた忘れているはずです。
それでも何度も何度も解いているうちに、問題と解答を覚えてしまう頃には、もうすでにその問題と解答の意味内容を完全に理解してしまっていると思います。
もちろん、過去問だけに取り組むのではなく、過去問を考えて解けて、ミスであっても解答を見て理解できるレベルに到達しているということが前提です。
あとその過去問の答え方が選択肢の少ない選択問題だと、この方法はあまり効果を発揮しないかもしれません。
どうしてもこれだけは皆さんに聞きたいのです。
確かに過去問をやらせるのは手っ取り早く「得点力」をつける最良の方法だと思います。実際私も、生徒に入試や模擬テストの過去問を沢山やらせています。手がつかない生徒にはやらせませんが。
ただ、手っ取り早く得点力を上げるだけで良いのでしょうか。
特に、英検などは受験準備として過去問しかしない生徒も多いと思います。部活などで忙しい生徒は3年分くらいの過去問を試験の直前に慌ててとりくむのがやっとでしょう。
それでもなんとか受かってしまう英検って何なんだと思います。
当塾の中3生で英検準2級の生徒がいますが、6月の模擬テストの英語(中1,2の範囲)は63点でした。この事実。
確かに過去問をやらせるのは手っ取り早く「得点力」をつける最良の方法だと思います。実際私も、生徒に入試や模擬テストの過去問を沢山やらせています。手がつかない生徒にはやらせませんが。
ただ、手っ取り早く得点力を上げるだけで良いのでしょうか。
特に、英検などは受験準備として過去問しかしない生徒も多いと思います。部活などで忙しい生徒は3年分くらいの過去問を試験の直前に慌ててとりくむのがやっとでしょう。
それでもなんとか受かってしまう英検って何なんだと思います。
当塾の中3生で英検準2級の生徒がいますが、6月の模擬テストの英語(中1,2の範囲)は63点でした。この事実。
さすが,SSJさん,きびしいご意見です。
その通りだと思います。
英検は,改訂のたびにレベルが下がっています。多くの生徒を受検させるために,合格証書を乱発しているんではないか,と勘ぐりたくなるくらいです。
特に下のクラスはひどい。まったく分からなくても5級に合格できる。
私は,矛盾とは知りながらも,過去問をさせて,検定や高校入試に受かるように導いています。
ふだんの学習では,試験に出るからやるんではない,役にたつからということで学ぶのではない,といいながらも,
定期テスト対策や,高校入試対策では,何が出るか対策を取りながら,勉強をさせています。
理想はさておき,子どもたちの点数を上げたい,合格させたい,という気持ちが先に立ちます。
塾の宿命でもありますか。
このように,矛盾しながらも,
ふだんは点数軽視,テスト前は点数重視という態度をとっているのが現実です。
その通りだと思います。
英検は,改訂のたびにレベルが下がっています。多くの生徒を受検させるために,合格証書を乱発しているんではないか,と勘ぐりたくなるくらいです。
特に下のクラスはひどい。まったく分からなくても5級に合格できる。
私は,矛盾とは知りながらも,過去問をさせて,検定や高校入試に受かるように導いています。
ふだんの学習では,試験に出るからやるんではない,役にたつからということで学ぶのではない,といいながらも,
定期テスト対策や,高校入試対策では,何が出るか対策を取りながら,勉強をさせています。
理想はさておき,子どもたちの点数を上げたい,合格させたい,という気持ちが先に立ちます。
塾の宿命でもありますか。
このように,矛盾しながらも,
ふだんは点数軽視,テスト前は点数重視という態度をとっているのが現実です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
セルフラーニング 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-