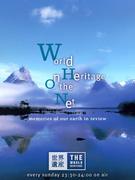世界無形文化財とは、2003年の第32回ユネスコ総会で採択された「無形文化遺産保護条約」に基づいて登録される予定の、世界的に価値の高い無形の文化財です。
文化庁が7/30、ユネスコに提案する無形文化遺産候補14件を発表しました。この候補については来年9月に、書類審査を経て条約国会議で承認され「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表(代表リスト)」への記載が決定されます。
〜 候補14件 〜
?祇園祭の山鉾巡行(京都) ?神事芸能「題目立」(奈良) ?日立風流物(茨城)
?甑島のトシドン(鹿児島) ?早池峰神楽(岩手) ?秋保の田植踊(宮城)
?チャッキラコ(神奈川) ?大日堂舞楽(秋田) ?アイヌ古式舞踊(北海道)
?奥能登のあえのこと(石川) ?石州半紙(島根) ?小千谷縮・越後上布(新潟)
?雅楽 ?木造彫刻修理
(注)条約発効前にユネスコが「人類の口承および無形遺産に関する傑作」の宣言をしている「能楽」「人形浄瑠璃文楽」「歌舞伎」の3件は、代表リストに統合されることが既に決まっています。
〜 無形文化遺産に興味がある方とか!何かご存知の方!宜しくお願いいたします 〜
○今回、提案される前記の無形文化遺産の各候補は、どんなものでしょうか ?
○その実態とか、保存活動の状況とか、ニュースとか、写真など、無形文化遺産候補に関わることについて、自由に伝えてください。
文化庁が7/30、ユネスコに提案する無形文化遺産候補14件を発表しました。この候補については来年9月に、書類審査を経て条約国会議で承認され「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表(代表リスト)」への記載が決定されます。
〜 候補14件 〜
?祇園祭の山鉾巡行(京都) ?神事芸能「題目立」(奈良) ?日立風流物(茨城)
?甑島のトシドン(鹿児島) ?早池峰神楽(岩手) ?秋保の田植踊(宮城)
?チャッキラコ(神奈川) ?大日堂舞楽(秋田) ?アイヌ古式舞踊(北海道)
?奥能登のあえのこと(石川) ?石州半紙(島根) ?小千谷縮・越後上布(新潟)
?雅楽 ?木造彫刻修理
(注)条約発効前にユネスコが「人類の口承および無形遺産に関する傑作」の宣言をしている「能楽」「人形浄瑠璃文楽」「歌舞伎」の3件は、代表リストに統合されることが既に決まっています。
〜 無形文化遺産に興味がある方とか!何かご存知の方!宜しくお願いいたします 〜
○今回、提案される前記の無形文化遺産の各候補は、どんなものでしょうか ?
○その実態とか、保存活動の状況とか、ニュースとか、写真など、無形文化遺産候補に関わることについて、自由に伝えてください。
|
|
|
|
コメント(268)
ユネスコ無形文化遺産「日立風流物」5年ぶり披露 茨城 日立
(茨城 NEWS WEB・4/6 転載)
ユネスコの無形文化遺産に登録されている茨城県日立市の郷土芸能「日立風流物」が5年ぶりに披露されました。
「日立風流物」は江戸時代に始まったとされる郷土芸能で、からくりが仕掛けられた高さ15メートル重さ5トンの山車で人形芝居を披露します。
世界の伝統文化などを保護するユネスコの無形文化遺産に登録されており、毎年この時期に「日立さくらまつり」で披露されてきましたが、新型コロナの影響で披露されるのは5年ぶりとなります。
このうち、「風流太閤記」という演目では織田信長を模したからくり人形がやりで応戦する「本能寺の変」の場面などが演じられました。
そして山車を180度回転させると、「風流花咲爺」という演目の舞台に早変わりし、花咲じいさんの人形が枯れ木に灰をまいて桜の花を咲かせる様子を披露しました。
会場を訪れた人たちは通りに咲き始めた桜と一緒に写真を撮って楽しんでいました。
常陸太田市の50代の女性は「からくり人形の仕掛けにとても驚きました。また見に来たいです」と話していました。
また、山車を披露した「日立郷土芸能保存会北町」の鈴木司支部長は「5年ぶりに多くの人が集まりうれしかったです。地元が誇る郷土芸能としてこれからも伝えていきたい」と話していました。
日立風流物は7日も日立さくらまつりで披露されます。
(茨城 NEWS WEB・4/6 転載)
ユネスコの無形文化遺産に登録されている茨城県日立市の郷土芸能「日立風流物」が5年ぶりに披露されました。
「日立風流物」は江戸時代に始まったとされる郷土芸能で、からくりが仕掛けられた高さ15メートル重さ5トンの山車で人形芝居を披露します。
世界の伝統文化などを保護するユネスコの無形文化遺産に登録されており、毎年この時期に「日立さくらまつり」で披露されてきましたが、新型コロナの影響で披露されるのは5年ぶりとなります。
このうち、「風流太閤記」という演目では織田信長を模したからくり人形がやりで応戦する「本能寺の変」の場面などが演じられました。
そして山車を180度回転させると、「風流花咲爺」という演目の舞台に早変わりし、花咲じいさんの人形が枯れ木に灰をまいて桜の花を咲かせる様子を披露しました。
会場を訪れた人たちは通りに咲き始めた桜と一緒に写真を撮って楽しんでいました。
常陸太田市の50代の女性は「からくり人形の仕掛けにとても驚きました。また見に来たいです」と話していました。
また、山車を披露した「日立郷土芸能保存会北町」の鈴木司支部長は「5年ぶりに多くの人が集まりうれしかったです。地元が誇る郷土芸能としてこれからも伝えていきたい」と話していました。
日立風流物は7日も日立さくらまつりで披露されます。
ユネスコ無形文化遺産「跡部の踊り念仏」の披露 長野 佐久
(首都圏 NEWS WEB・4/8 一部転載)
おととし、ユネスコの無形文化遺産に登録された民俗芸能「風流踊」のひとつで、長野県佐久市に鎌倉時代から伝わるとされる「跡部の踊り念仏」を披露する定例会が市内の寺で行われました。
「跡部の踊り念仏」は、鎌倉時代の僧侶、一遍上人がいまの佐久市を訪れた際に、弟子たちとともに念仏を唱えながら跳ねて踊ったことが始まりとされています。
日本各地で伝えられてきた、お囃子にあわせて踊る「風流踊」の1つとして、おととし、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。
定例会は、地元の保存会が毎年この時期に開いていて、会場となった西方寺の本堂には、「道場」と呼ばれる囲いが設けられ、踊り手が輪になって太鼓のまわりを歩きながら念仏を唱えました。
そして、太鼓の調子が速くなると、踊り手はかねを打ち鳴らしたり飛び跳ねたりして踊り念仏は最高潮に達しました。 また、ことしは地元の子どもたちも踊りの輪に加わり、練習の成果を披露しました。
(首都圏 NEWS WEB・4/8 一部転載)
おととし、ユネスコの無形文化遺産に登録された民俗芸能「風流踊」のひとつで、長野県佐久市に鎌倉時代から伝わるとされる「跡部の踊り念仏」を披露する定例会が市内の寺で行われました。
「跡部の踊り念仏」は、鎌倉時代の僧侶、一遍上人がいまの佐久市を訪れた際に、弟子たちとともに念仏を唱えながら跳ねて踊ったことが始まりとされています。
日本各地で伝えられてきた、お囃子にあわせて踊る「風流踊」の1つとして、おととし、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。
定例会は、地元の保存会が毎年この時期に開いていて、会場となった西方寺の本堂には、「道場」と呼ばれる囲いが設けられ、踊り手が輪になって太鼓のまわりを歩きながら念仏を唱えました。
そして、太鼓の調子が速くなると、踊り手はかねを打ち鳴らしたり飛び跳ねたりして踊り念仏は最高潮に達しました。 また、ことしは地元の子どもたちも踊りの輪に加わり、練習の成果を披露しました。
粋な庵唄、開幕告げ 城端曳山祭・宵祭
(富山新聞・5/5 転載)
ユネスコ無形文化遺産で、国重要無形民俗文化財の城端曳山祭(ひきやままつり)(南砺市)は5月4日、宵祭で幕を開けた。
当番町の西上町をはじめ、曳山を持つ6町の関係者が、江戸端唄(はうた)の流れをくむ男女の恋心を表現した庵(いおり)唄を披露し、篠(しの)笛と三味線の粋な音色が見物客を魅了した。
城端神明宮の春季大祭で、御旅所(おたびしょ)の市城端伝統芸能会館じょうはな座に神輿3基が運ばれた。南町の獅子舞、児童生徒の浦安の舞が奉納された。城端小4年生が讃歌「城端祭」を合唱し、6町が庵唄を披露した。
城端曳山会館前の特設会場では、東上町の曳山と庵屋台が飾られ、各町の庵唄が披露された。今年から演奏で女性の参加が認められ東下町で2人、西上町で1人が男衆に加わる。
各町は曳山の御神像を降ろし、山宿で飾った。5日の本祭では曳山6基と庵屋台がまちなかを練る。
(富山新聞・5/5 転載)
ユネスコ無形文化遺産で、国重要無形民俗文化財の城端曳山祭(ひきやままつり)(南砺市)は5月4日、宵祭で幕を開けた。
当番町の西上町をはじめ、曳山を持つ6町の関係者が、江戸端唄(はうた)の流れをくむ男女の恋心を表現した庵(いおり)唄を披露し、篠(しの)笛と三味線の粋な音色が見物客を魅了した。
城端神明宮の春季大祭で、御旅所(おたびしょ)の市城端伝統芸能会館じょうはな座に神輿3基が運ばれた。南町の獅子舞、児童生徒の浦安の舞が奉納された。城端小4年生が讃歌「城端祭」を合唱し、6町が庵唄を披露した。
城端曳山会館前の特設会場では、東上町の曳山と庵屋台が飾られ、各町の庵唄が披露された。今年から演奏で女性の参加が認められ東下町で2人、西上町で1人が男衆に加わる。
各町は曳山の御神像を降ろし、山宿で飾った。5日の本祭では曳山6基と庵屋台がまちなかを練る。
「郡上おどり」開幕、熱い夜に響く手拍子 8月には「徹夜」も
(朝日新聞デジタル・7/14 一部転載)
国の重要無形民俗文化財で、ユネスコ無形文化遺産に登録されている「郡上おどり」が7月13日夜、岐阜県郡上市八幡町で開幕した。
浴衣姿の踊り手たちが市内外から郡上八幡旧庁舎記念館前に集まり、おはやしを奏でる「屋形」を中心に幾重にも輪をつくりながら、手拍子の音を響かせた。
郡上おどり保存会の山田会長は「完全にコロナ禍前に戻り、若者や外国人旅行者の方々が大勢参加してくれるのではないか」と話し、今夏の盛り上がりに期待した。
8月13〜16日に「徹夜おどり」があり、9月7日の「おどり納め」まで、計30夜にわたり開かれる。
(朝日新聞デジタル・7/14 一部転載)
国の重要無形民俗文化財で、ユネスコ無形文化遺産に登録されている「郡上おどり」が7月13日夜、岐阜県郡上市八幡町で開幕した。
浴衣姿の踊り手たちが市内外から郡上八幡旧庁舎記念館前に集まり、おはやしを奏でる「屋形」を中心に幾重にも輪をつくりながら、手拍子の音を響かせた。
郡上おどり保存会の山田会長は「完全にコロナ禍前に戻り、若者や外国人旅行者の方々が大勢参加してくれるのではないか」と話し、今夏の盛り上がりに期待した。
8月13〜16日に「徹夜おどり」があり、9月7日の「おどり納め」まで、計30夜にわたり開かれる。
ユネスコ無形文化遺産に登録 綾川町で「滝宮の念仏踊」
(香川 NEWS WEB・8/25 一部転載)
花笠をかぶった人たちがうちわや楽器を持って踊る、ユネスコの無形文化遺産「滝宮の念仏踊」が香川県綾川町で行われました。
「滝宮の念仏踊」は、菅原道真が干ばつで苦しむ農民のために雨乞いをして、大雨が降ったことを喜んだ人々が感謝のために踊ったのが始まりとされ、全国各地に伝わる「風流踊」のひとつとしてユネスコの無形文化遺産に登録されています。
ことし、綾川町の滝宮神社では、町内に11ある踊組のうち、3組が踊りを披露しました。
花笠をかぶり、錦のはかまと陣羽織を身につけ、大きなうちわをもった「下知」と呼ばれる踊り手が、囃子に合わせてうちわをひらめかせながら軽やかな踊りを奉納しました。
(香川 NEWS WEB・8/25 一部転載)
花笠をかぶった人たちがうちわや楽器を持って踊る、ユネスコの無形文化遺産「滝宮の念仏踊」が香川県綾川町で行われました。
「滝宮の念仏踊」は、菅原道真が干ばつで苦しむ農民のために雨乞いをして、大雨が降ったことを喜んだ人々が感謝のために踊ったのが始まりとされ、全国各地に伝わる「風流踊」のひとつとしてユネスコの無形文化遺産に登録されています。
ことし、綾川町の滝宮神社では、町内に11ある踊組のうち、3組が踊りを披露しました。
花笠をかぶり、錦のはかまと陣羽織を身につけ、大きなうちわをもった「下知」と呼ばれる踊り手が、囃子に合わせてうちわをひらめかせながら軽やかな踊りを奉納しました。
(ニュース)「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産で県内からも喜びの声
(Gooニュース・12/05 )
日本酒や焼酎などの「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録され、石川県内からも喜びの声が聞かれました。
南米パラグアイで開かれているユネスコの政府間委員会は、日本時間の12月5日午前4時前、日本の「伝統的酒造り」を無形文化遺産に正式に登録することを決めました。
「伝統的酒造り」は杜氏(とうじ)や蔵人などが「こうじ菌」を用い、日本各地の気候風土に合わせた伝統的な酒造りの技術で、日本酒や焼酎、泡盛などの製造に受け継がれてきました。登録を受けて金沢市内の日本酒販売店からも喜びの声が聞かれました。
金沢地酒蔵 嶋田美友さん:
「和食が登録された時も和食文化が海外に広まっているって聞いたのでこれを機に日本酒もたくさん飲んでいただけたらいいなと思います」
日本の無形文化遺産は伝統的酒造りで23件目になります。
(Gooニュース・12/05 )
日本酒や焼酎などの「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録され、石川県内からも喜びの声が聞かれました。
南米パラグアイで開かれているユネスコの政府間委員会は、日本時間の12月5日午前4時前、日本の「伝統的酒造り」を無形文化遺産に正式に登録することを決めました。
「伝統的酒造り」は杜氏(とうじ)や蔵人などが「こうじ菌」を用い、日本各地の気候風土に合わせた伝統的な酒造りの技術で、日本酒や焼酎、泡盛などの製造に受け継がれてきました。登録を受けて金沢市内の日本酒販売店からも喜びの声が聞かれました。
金沢地酒蔵 嶋田美友さん:
「和食が登録された時も和食文化が海外に広まっているって聞いたのでこれを機に日本酒もたくさん飲んでいただけたらいいなと思います」
日本の無形文化遺産は伝統的酒造りで23件目になります。
(ニュース)〜原爆ドーム 世界遺産登録から28年「存在意義を高められるかは私たちにかかっている」核兵器廃絶と界の恒久平和実現の誓い 新たに
(RCC中国放送・12/10一部転載)
原爆ドームが世界遺産に登録されて28年となるのを記念する集会が昨夜、広島市で開かれました。
広島市の原爆ドーム前で開かれた「世界遺産登録記念集会」です。県被団協や連合広島などの団体が登録の翌年から毎年、開いていてことしは団体の関係者や被爆者など63人が集まりました。
参加者たちは犠牲者に黙とうを捧げ世界遺産登録の意義を再確認して核兵器の廃絶と世界の恒久平和実現の誓いを新たにしました
集会では「ノーベル平和賞受賞の意義を踏まえ唯一の戦争被爆国として『核兵器廃絶』に向けた行動力を高めなければならない」としたアピール文が採択されました。
(RCC中国放送・12/10一部転載)
原爆ドームが世界遺産に登録されて28年となるのを記念する集会が昨夜、広島市で開かれました。
広島市の原爆ドーム前で開かれた「世界遺産登録記念集会」です。県被団協や連合広島などの団体が登録の翌年から毎年、開いていてことしは団体の関係者や被爆者など63人が集まりました。
参加者たちは犠牲者に黙とうを捧げ世界遺産登録の意義を再確認して核兵器の廃絶と世界の恒久平和実現の誓いを新たにしました
集会では「ノーベル平和賞受賞の意義を踏まえ唯一の戦争被爆国として『核兵器廃絶』に向けた行動力を高めなければならない」としたアピール文が採択されました。
(ニュース)〜伝統的な「鵜飼漁と海女漁」 “ユネスコ無形文化遺産”登録めざし協議会立ち上げ 岐阜・三重・石川の5市が連携
(CBCテレビ・2/1 一部転載)
鵜飼漁や海女漁の伝統的な漁を行っている、岐阜市など5つの自治体が、ユネスコの無形文化遺産の登録に向け1日、協議会を立ち上げました。
2月1日に発足した協議会は、鵜飼漁を行う岐阜市と関市、海女漁を行う三重県・鳥羽市と志摩市、それに石川県・輪島市の5つの自治体で構成され、伝統的な漁法技術をユネスコ無形文化遺産に登録することを目指します。
当日は自然環境の変化などで存続が危ぶまれている現状について報告されました。
協議会では2028年度以降の登録を目標に、課題の洗い出しなどを進め、今後も議論を重ねていく考えです。
(CBCテレビ・2/1 一部転載)
鵜飼漁や海女漁の伝統的な漁を行っている、岐阜市など5つの自治体が、ユネスコの無形文化遺産の登録に向け1日、協議会を立ち上げました。
2月1日に発足した協議会は、鵜飼漁を行う岐阜市と関市、海女漁を行う三重県・鳥羽市と志摩市、それに石川県・輪島市の5つの自治体で構成され、伝統的な漁法技術をユネスコ無形文化遺産に登録することを目指します。
当日は自然環境の変化などで存続が危ぶまれている現状について報告されました。
協議会では2028年度以降の登録を目標に、課題の洗い出しなどを進め、今後も議論を重ねていく考えです。
日本の「書道」 ユネスコの無形文化遺産に再提案 文化庁
(NHKニュース・3/27 一部転載)
文化庁は、筆や墨などを使って、伝統的な筆遣いで手書きする日本の「書道」について、去年に続いてユネスコの無形文化遺産に提案することを決めました。
これは、4日開かれた文化庁の文化審議会の部会で決まりました。
「書道」は、筆や墨、すずりなどを使って漢字や仮名を伝統的な筆遣いや技法で手書きするもので、去年、ユネスコの無形文化遺産に提案されていましたが、各国からユネスコの年間の審査件数の上限を上回る提案があったため、審査が見送られていました。
一度見送られた提案は、次の年に優先して審査されることになっていて、文化庁によりますと「書道」については来年11月ごろに審議される見込みだということです。
文化庁は、政府の正式な決定を経て、今月末までに提案書をユネスコに提出する予定です。
ユネスコの無形文化遺産には、日本からは去年登録された「伝統的酒造り」などこれまでに23件が登録されています。
(NHKニュース・3/27 一部転載)
文化庁は、筆や墨などを使って、伝統的な筆遣いで手書きする日本の「書道」について、去年に続いてユネスコの無形文化遺産に提案することを決めました。
これは、4日開かれた文化庁の文化審議会の部会で決まりました。
「書道」は、筆や墨、すずりなどを使って漢字や仮名を伝統的な筆遣いや技法で手書きするもので、去年、ユネスコの無形文化遺産に提案されていましたが、各国からユネスコの年間の審査件数の上限を上回る提案があったため、審査が見送られていました。
一度見送られた提案は、次の年に優先して審査されることになっていて、文化庁によりますと「書道」については来年11月ごろに審議される見込みだということです。
文化庁は、政府の正式な決定を経て、今月末までに提案書をユネスコに提出する予定です。
ユネスコの無形文化遺産には、日本からは去年登録された「伝統的酒造り」などこれまでに23件が登録されています。
世界文化遺産の賀茂御祖神社(下鴨神社)「糺の森」で世界無形文化遺産の「能楽」を上演。第十回を記念し、世界初演となる新作能『糺(ただす)』5月24日(土)開催
(下鴨神社糺能保存会・4/9 一部転載)
下鴨神社糺能保存会は、2025年5月24日(土)、世界文化遺産の賀茂御祖神社(下鴨神社)「糺の森」で第十回「糺能(ただすのう)」を開催いたします。
「糺能」とは、今から約550年前の寛正五年(1464)に将軍足利義政をはじめとする錚々たる大名の前で行われた「糺河原勧進猿楽」を、賀茂御祖神社第34回式年遷宮(2015)の折に550年ぶりに再興させたものです。
賀茂御祖神社・舞殿(重要文化財)を舞台とした野外能で、2019年には令和の御大典を記念し、賀茂祭(葵祭)の後儀として「糺能」と改め、毎年開催してまいりました。
賀茂御祖神社では、2100年前から遷宮が始まり、令和18年(2036)斎行の遷宮にて第60回目となります。さらに後一条天皇の宣旨により遷宮の制度が20年毎の式年として第1回目が長元9年(1036)4月13日に斎行されてより、第35回式年遷宮にて一千年の佳節となります。
神と人との間の千年のいとなみを振り返り、自然と文化のすがたをもういちど見つめ直したいと考え、本年の「糺能」は第十回を記念し、また1000年の節目へ向けて、新作能『糺』を上演いたします。
(下鴨神社糺能保存会・4/9 一部転載)
下鴨神社糺能保存会は、2025年5月24日(土)、世界文化遺産の賀茂御祖神社(下鴨神社)「糺の森」で第十回「糺能(ただすのう)」を開催いたします。
「糺能」とは、今から約550年前の寛正五年(1464)に将軍足利義政をはじめとする錚々たる大名の前で行われた「糺河原勧進猿楽」を、賀茂御祖神社第34回式年遷宮(2015)の折に550年ぶりに再興させたものです。
賀茂御祖神社・舞殿(重要文化財)を舞台とした野外能で、2019年には令和の御大典を記念し、賀茂祭(葵祭)の後儀として「糺能」と改め、毎年開催してまいりました。
賀茂御祖神社では、2100年前から遷宮が始まり、令和18年(2036)斎行の遷宮にて第60回目となります。さらに後一条天皇の宣旨により遷宮の制度が20年毎の式年として第1回目が長元9年(1036)4月13日に斎行されてより、第35回式年遷宮にて一千年の佳節となります。
神と人との間の千年のいとなみを振り返り、自然と文化のすがたをもういちど見つめ直したいと考え、本年の「糺能」は第十回を記念し、また1000年の節目へ向けて、新作能『糺』を上演いたします。
”ユネスコ無形文化遺産” 伝統の「大垣まつり」開催 岐阜
(岐阜ニュースWeb・5/13 一部転載)
ユネスコの無形文化遺産に登録されている伝統の「大垣まつり」が、5月10日と11日、行われ、大勢の見物客でにぎわいました。
「大垣まつり」は、江戸時代初期から続く伝統の祭りで、2016年にはユネスコの無形文化遺産に登録されました。
雨の影響で、ことしは5月10日の午後から始まり、11日は高さが4メートルから5メートルほどある13輌の「※ヤマ」が、大垣駅前など市の中心部を巡行しました。
このうち伝馬町の「※ヤマ」では、子どもが「※ヤマ」の前方にある舞台で舞を披露し、見物客が写真を撮るなどしていました。
伝馬町では、少子化に伴ってほかの地域に住む子どもからも参加を募ったということです。
(岐阜ニュースWeb・5/13 一部転載)
ユネスコの無形文化遺産に登録されている伝統の「大垣まつり」が、5月10日と11日、行われ、大勢の見物客でにぎわいました。
「大垣まつり」は、江戸時代初期から続く伝統の祭りで、2016年にはユネスコの無形文化遺産に登録されました。
雨の影響で、ことしは5月10日の午後から始まり、11日は高さが4メートルから5メートルほどある13輌の「※ヤマ」が、大垣駅前など市の中心部を巡行しました。
このうち伝馬町の「※ヤマ」では、子どもが「※ヤマ」の前方にある舞台で舞を披露し、見物客が写真を撮るなどしていました。
伝馬町では、少子化に伴ってほかの地域に住む子どもからも参加を募ったということです。
神楽のユネスコ無形文化遺産登録に向け、東京で総決起大会を開催
(選挙ドットコム・5/23 一部転載)
神楽のユネスコ無形文化遺産登録に向け、東京で総決起大会を開催しました。
主催は、神楽の保存団体等からなる「全国神楽継承・振興協議会」と、その取組を後押しする「神楽継承・振興知事同盟」。
国会からも、担当省である文部科学省の野中厚文部科学副大臣や、西村康稔神楽伝承国会議員連盟会長をはじめ30人ほどの議員本人に出席いただき、それぞれ熱い激励やエールをいただきました。
総決起大会に先立ち、高千穂の夜神楽(下川登神楽)から「戸取の舞」を興梠史慎さんに披露いただきました。
総決起大会の後、あべ俊子文部科学大臣と森山裕自民党幹事長に要望活動を行いました。
*総決起大会における宣言文は省略です。
(選挙ドットコム・5/23 一部転載)
神楽のユネスコ無形文化遺産登録に向け、東京で総決起大会を開催しました。
主催は、神楽の保存団体等からなる「全国神楽継承・振興協議会」と、その取組を後押しする「神楽継承・振興知事同盟」。
国会からも、担当省である文部科学省の野中厚文部科学副大臣や、西村康稔神楽伝承国会議員連盟会長をはじめ30人ほどの議員本人に出席いただき、それぞれ熱い激励やエールをいただきました。
総決起大会に先立ち、高千穂の夜神楽(下川登神楽)から「戸取の舞」を興梠史慎さんに披露いただきました。
総決起大会の後、あべ俊子文部科学大臣と森山裕自民党幹事長に要望活動を行いました。
*総決起大会における宣言文は省略です。
伝統的酒造り、万博でPR 関西の酒蔵、酒造家が集合
(共同通信・6/16 一部転載)
2024年に国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に日本の「伝統的酒造り」が登録されたことを記念し、大阪国税局が6月16日、大阪・関西万博会場で酒造りの魅力を発信するイベントを開いた。関西2府4県の酒蔵、酒造家が参加し、今月28日まで開催する。
「酒造り技術の保存会」会長で小西酒造(兵庫県伊丹市)15代当主の小西新右衛門さんらが、日本酒造りに欠かせないこうじや伝統技術をPR。「造り手の技、苦労も世界の人々に知ってもらい、飲んでもらいたい」と話した。
イベントは「大阪ヘルスケアパビリオン」1階で開催。先着25人を対象に、試飲付きのセミナーを1日4回開く。
(共同通信・6/16 一部転載)
2024年に国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に日本の「伝統的酒造り」が登録されたことを記念し、大阪国税局が6月16日、大阪・関西万博会場で酒造りの魅力を発信するイベントを開いた。関西2府4県の酒蔵、酒造家が参加し、今月28日まで開催する。
「酒造り技術の保存会」会長で小西酒造(兵庫県伊丹市)15代当主の小西新右衛門さんらが、日本酒造りに欠かせないこうじや伝統技術をPR。「造り手の技、苦労も世界の人々に知ってもらい、飲んでもらいたい」と話した。
イベントは「大阪ヘルスケアパビリオン」1階で開催。先着25人を対象に、試飲付きのセミナーを1日4回開く。
「近江湖南のサンヤレ踊り」を含む「風流ふりゅう踊おどり」はユネスコ無形文化遺産に登録済
(草津市歴史文化財・6/18 一部転載)
ユネスコ(UNESCO)は、国連の中で文化・教育・科学技術等を所掌する国際機関です。世界遺産条約が対象としている有形の文化遺産と並び、無形文化遺産も国際的に保護しようとする意識の高まりの中、平成15年に「無形文化遺産保護条約」が採択されました。
令和4年11月、モロッコで開催されたユネスコ政府間委員会において、全国41件の民俗芸能が「風流踊」として代表一覧表に記載されることが決議されました。
○風流踊ふりゅうおどり
風流踊は、華やかな、人目を惹くという「風流」の精神を体現し、衣装や持ちものに趣向をこらして、歌や笛、太鼓、鉦などの囃子に合わせて踊る民俗芸能です。
除災や死者供養、豊作祈願、雨ごいなど、安寧な暮らしを願う人々の祈りが込められています。
○草津のサンヤレ踊り
サンヤレ踊りは、毎年5月3日に草津市内の7地域(矢倉・下笠・片岡・長束・志那・吉田・志那中)で行われています。
各地域の踊りの様相はそれぞれ異なりますが、太鼓や鞨鼓、摺鉦、ササラなどの打楽器を中心とした楽器を持って踊り、その周囲を笹や榊、扇子などの採物とりものを持った者がこれを取り囲み囃はやし歌うもので、リズミカルに短い詞を繰り返す歌詞の中に「サンヤレ」という囃子詞があることから、これが踊りの名称となっていると思われます。
(草津市歴史文化財・6/18 一部転載)
ユネスコ(UNESCO)は、国連の中で文化・教育・科学技術等を所掌する国際機関です。世界遺産条約が対象としている有形の文化遺産と並び、無形文化遺産も国際的に保護しようとする意識の高まりの中、平成15年に「無形文化遺産保護条約」が採択されました。
令和4年11月、モロッコで開催されたユネスコ政府間委員会において、全国41件の民俗芸能が「風流踊」として代表一覧表に記載されることが決議されました。
○風流踊ふりゅうおどり
風流踊は、華やかな、人目を惹くという「風流」の精神を体現し、衣装や持ちものに趣向をこらして、歌や笛、太鼓、鉦などの囃子に合わせて踊る民俗芸能です。
除災や死者供養、豊作祈願、雨ごいなど、安寧な暮らしを願う人々の祈りが込められています。
○草津のサンヤレ踊り
サンヤレ踊りは、毎年5月3日に草津市内の7地域(矢倉・下笠・片岡・長束・志那・吉田・志那中)で行われています。
各地域の踊りの様相はそれぞれ異なりますが、太鼓や鞨鼓、摺鉦、ササラなどの打楽器を中心とした楽器を持って踊り、その周囲を笹や榊、扇子などの採物とりものを持った者がこれを取り囲み囃はやし歌うもので、リズミカルに短い詞を繰り返す歌詞の中に「サンヤレ」という囃子詞があることから、これが踊りの名称となっていると思われます。
>[236] トモトモ
>「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産で県内から・・・
酒造りに無形遺産の認定書 文化庁、登録記念式典
(共同通信・7/20 一部転載)
文化庁は7月18日、日本酒や焼酎といった「伝統的酒造り」の国連教育科学文化機関(ユネスコ)無形文化遺産登録を記念する式典を東京都内で開いた。日本酒造杜氏組合連合会(日杜連)など関係団体の代表者らに、登録認定書のレプリカを手渡した。
都倉俊一文化庁長官は「酒造りが継承されてきたのは関係者のたゆまない努力によるもので、敬意を表する」とあいさつ。日杜連の石川達也会長は「登録を機に、業界がより一層一体感を持ち、守りつないでいきたい」と意気込んだ。
伝統的酒造りは、こうじ菌を使い、蒸したコメなどの原料を発酵させる日本古来の技術。各地の風土や気候などに合わせて杜氏らが手作業で洗練し、受け継いできた。
>「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産で県内から・・・
酒造りに無形遺産の認定書 文化庁、登録記念式典
(共同通信・7/20 一部転載)
文化庁は7月18日、日本酒や焼酎といった「伝統的酒造り」の国連教育科学文化機関(ユネスコ)無形文化遺産登録を記念する式典を東京都内で開いた。日本酒造杜氏組合連合会(日杜連)など関係団体の代表者らに、登録認定書のレプリカを手渡した。
都倉俊一文化庁長官は「酒造りが継承されてきたのは関係者のたゆまない努力によるもので、敬意を表する」とあいさつ。日杜連の石川達也会長は「登録を機に、業界がより一層一体感を持ち、守りつないでいきたい」と意気込んだ。
伝統的酒造りは、こうじ菌を使い、蒸したコメなどの原料を発酵させる日本古来の技術。各地の風土や気候などに合わせて杜氏らが手作業で洗練し、受け継いできた。
ユネスコ無形文化遺産「八戸三社大祭」開催!
(八戸市・7/24 一部転載)
青森県八戸市では、豊作祈願を願う祭礼行事「八戸三社大祭」が2025年7月31日(木)〜2025年8月4日(月)の日程で開催されます。
八戸三社大祭は発祥300年以上の歴史と伝統を誇る行事で、市民によって粛々と引き継がれてきた、八戸を代表する夏祭りです。
おがみ神社、長者山新羅神社、神明宮からなる三神社の厳かな神輿行列と、神話や歌舞伎を題材に各山車組が制作した27台にも及ぶ山車の合同運行は豪華絢爛な山車絵巻です。神輿行列では虎舞や大神楽など多彩な民俗芸能が目白押しで、八戸の歴史と伝統が凝縮された5日間となります。
中の人出は100万人以上で、青森県で開催される夏祭りの中でも有数の規模です。
(八戸市・7/24 一部転載)
青森県八戸市では、豊作祈願を願う祭礼行事「八戸三社大祭」が2025年7月31日(木)〜2025年8月4日(月)の日程で開催されます。
八戸三社大祭は発祥300年以上の歴史と伝統を誇る行事で、市民によって粛々と引き継がれてきた、八戸を代表する夏祭りです。
おがみ神社、長者山新羅神社、神明宮からなる三神社の厳かな神輿行列と、神話や歌舞伎を題材に各山車組が制作した27台にも及ぶ山車の合同運行は豪華絢爛な山車絵巻です。神輿行列では虎舞や大神楽など多彩な民俗芸能が目白押しで、八戸の歴史と伝統が凝縮された5日間となります。
中の人出は100万人以上で、青森県で開催される夏祭りの中でも有数の規模です。
>[236] トモトモ
>「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産で県内から・・・
「伝統的酒造り」ユネスコ無形文化遺産登録記念式典を開催〜ユネスコからの登録認定書授与を受け中央会理事よりコメント〜
(PR TIMES・7/24 一部転載)
日本酒造杜氏組合連合会、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会とともに中央会及び関係者が参加
全国約1,600の日本の伝統ある酒類(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん)メーカーが所属する日本酒造組合中央会(以下、中央会)では、「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会」(登録無形文化財『伝統的酒造り』のわざの保持団体)及び日本酒造杜氏組合連合会と協力し、「伝統的酒造り」について国連教育科学文化機関(以下、ユネスコ)の無形文化遺産代表一覧表への登録に向けた取り組みをともに行ってきました。
登録後も後世へつなぎ継承していくための活動を継続して行っております。
>「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産で県内から・・・
「伝統的酒造り」ユネスコ無形文化遺産登録記念式典を開催〜ユネスコからの登録認定書授与を受け中央会理事よりコメント〜
(PR TIMES・7/24 一部転載)
日本酒造杜氏組合連合会、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会とともに中央会及び関係者が参加
全国約1,600の日本の伝統ある酒類(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん)メーカーが所属する日本酒造組合中央会(以下、中央会)では、「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会」(登録無形文化財『伝統的酒造り』のわざの保持団体)及び日本酒造杜氏組合連合会と協力し、「伝統的酒造り」について国連教育科学文化機関(以下、ユネスコ)の無形文化遺産代表一覧表への登録に向けた取り組みをともに行ってきました。
登録後も後世へつなぎ継承していくための活動を継続して行っております。
最高峰の日本酒400点が集結し今年の出来栄えを披露!「令和6酒造年度全国新酒鑑評会 公開きき酒会」を開催
〜ユネスコ無形文化遺産登録元年、伝統の酒造り技術を味覚で体感〜
(PR TIMES・7/16 一部転載)
全国約1,600の日本の伝統ある酒類(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん)メーカーが所属する日本酒造組合中央会(以下、中央会)では、令和6酒造年度全国新酒鑑評会入賞酒400点が味わえる機会として、2025年7月12日(土)に、サンシャインシティ(東京・池袋)にて『令和6酒造年度全国新酒鑑評会 公開きき酒会(以下、公開きき酒会)』を開催しました。
今年の「公開きき酒会」では、ユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」登録後初となる令和6酒造年度に製造された入賞酒が披露され、例年以上の注目を集めました。当日はチケットも完売し1,221名の方が来場、日本酒ファンだけでなく、大学生や訪日外国人なども多く来場しました。
○入賞酒約400点をセルフで試飲 日本酒の個性を五感で味わう特別な3時間!
『公開きき酒会』の会場には、造り手が持てる技術を尽くした貴重な吟醸酒の原酒約400点が地域別に展示され、来場者はセルフサービス形式で自由にテイスティングを楽しみました。
○はじめてのきき酒コーナー」で日本酒の味や香りの違いを体験
会場内で人気だったのが、きき酒を楽しむ方法をレクチャーする「はじめてのきき酒コーナー」で、4つのタイプから自分好みの味と香りを探しだす体験や、全国新酒鑑評会で専門家が実際に行っている味や香りを評価するシートを活用した比較体験にも多くの方が参加しました。
○酒造りを支える技術や裏側を学べるパネル展示
会場内では「伝統的酒造り」の紹介展示をはじめ、日本酒グッズコーナーや、酒瓶などのリサイクルの仕組みを学べる啓発コーナーも併設されました。
また、酒類総合研究所の職員が常駐し、研究成果や酒造技術について来場者にわかりやすく解説する「酒類総合研究所紹介コーナー」ではパネル展示も行われ注目を集めました。
○今後の「公開きき酒会」の展望について
海外や若者に向けて、日本酒がどう変わっていっているのか、時代の変化や技術の進化、米の違いを含めた酒蔵のチャレンジの方向性や背景をもっと知って頂けるようアピールしていきたい。」とコメントし日本酒に関心を持つ国内外の人にアピールしました。
〜ユネスコ無形文化遺産登録元年、伝統の酒造り技術を味覚で体感〜
(PR TIMES・7/16 一部転載)
全国約1,600の日本の伝統ある酒類(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん)メーカーが所属する日本酒造組合中央会(以下、中央会)では、令和6酒造年度全国新酒鑑評会入賞酒400点が味わえる機会として、2025年7月12日(土)に、サンシャインシティ(東京・池袋)にて『令和6酒造年度全国新酒鑑評会 公開きき酒会(以下、公開きき酒会)』を開催しました。
今年の「公開きき酒会」では、ユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」登録後初となる令和6酒造年度に製造された入賞酒が披露され、例年以上の注目を集めました。当日はチケットも完売し1,221名の方が来場、日本酒ファンだけでなく、大学生や訪日外国人なども多く来場しました。
○入賞酒約400点をセルフで試飲 日本酒の個性を五感で味わう特別な3時間!
『公開きき酒会』の会場には、造り手が持てる技術を尽くした貴重な吟醸酒の原酒約400点が地域別に展示され、来場者はセルフサービス形式で自由にテイスティングを楽しみました。
○はじめてのきき酒コーナー」で日本酒の味や香りの違いを体験
会場内で人気だったのが、きき酒を楽しむ方法をレクチャーする「はじめてのきき酒コーナー」で、4つのタイプから自分好みの味と香りを探しだす体験や、全国新酒鑑評会で専門家が実際に行っている味や香りを評価するシートを活用した比較体験にも多くの方が参加しました。
○酒造りを支える技術や裏側を学べるパネル展示
会場内では「伝統的酒造り」の紹介展示をはじめ、日本酒グッズコーナーや、酒瓶などのリサイクルの仕組みを学べる啓発コーナーも併設されました。
また、酒類総合研究所の職員が常駐し、研究成果や酒造技術について来場者にわかりやすく解説する「酒類総合研究所紹介コーナー」ではパネル展示も行われ注目を集めました。
○今後の「公開きき酒会」の展望について
海外や若者に向けて、日本酒がどう変わっていっているのか、時代の変化や技術の進化、米の違いを含めた酒蔵のチャレンジの方向性や背景をもっと知って頂けるようアピールしていきたい。」とコメントし日本酒に関心を持つ国内外の人にアピールしました。
最高峰の日本酒400点が集結し今年の出来栄えを披露!「令和6酒造年度全国新酒鑑評会 公開きき酒会」を開催
〜ユネスコ無形文化遺産登録元年、伝統の酒造り技術を味覚で体感〜
(PR TIMES・7/16 一部転載)
全国約1,600の日本の伝統ある酒類(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん)メーカーが所属する日本酒造組合中央会(以下、中央会)では、令和6酒造年度全国新酒鑑評会入賞酒400点が味わえる機会として、2025年7月12日(土)に、サンシャインシティ(東京・池袋)にて『令和6酒造年度全国新酒鑑評会 公開きき酒会(以下、公開きき酒会)』を開催しました。
今年の「公開きき酒会」では、ユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」登録後初となる令和6酒造年度に製造された入賞酒が披露され、例年以上の注目を集めました。当日はチケットも完売し1,221名の方が来場、日本酒ファンだけでなく、大学生や訪日外国人なども多く来場しました。
○入賞酒約400点をセルフで試飲 日本酒の個性を五感で味わう特別な3時間!
『公開きき酒会』の会場には、造り手が持てる技術を尽くした貴重な吟醸酒の原酒約400点が地域別に展示され、来場者はセルフサービス形式で自由にテイスティングを楽しみました。
○はじめてのきき酒コーナー」で日本酒の味や香りの違いを体験
会場内で人気だったのが、きき酒を楽しむ方法をレクチャーする「はじめてのきき酒コーナー」で、4つのタイプから自分好みの味と香りを探しだす体験や、全国新酒鑑評会で専門家が実際に行っている味や香りを評価するシートを活用した比較体験にも多くの方が参加しました。
○酒造りを支える技術や裏側を学べるパネル展示
会場内では「伝統的酒造り」の紹介展示をはじめ、日本酒グッズコーナーや、酒瓶などのリサイクルの仕組みを学べる啓発コーナーも併設されました。
また、酒類総合研究所の職員が常駐し、研究成果や酒造技術について来場者にわかりやすく解説する「酒類総合研究所紹介コーナー」ではパネル展示も行われ注目を集めました。
○今後の「公開きき酒会」の展望について
海外や若者に向けて、日本酒がどう変わっていっているのか、時代の変化や技術の進化、米の違いを含めた酒蔵のチャレンジの方向性や背景をもっと知って頂けるようアピールしていきたい。」とコメントし日本酒に関心を持つ国内外の人にアピールしました。
〜ユネスコ無形文化遺産登録元年、伝統の酒造り技術を味覚で体感〜
(PR TIMES・7/16 一部転載)
全国約1,600の日本の伝統ある酒類(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん)メーカーが所属する日本酒造組合中央会(以下、中央会)では、令和6酒造年度全国新酒鑑評会入賞酒400点が味わえる機会として、2025年7月12日(土)に、サンシャインシティ(東京・池袋)にて『令和6酒造年度全国新酒鑑評会 公開きき酒会(以下、公開きき酒会)』を開催しました。
今年の「公開きき酒会」では、ユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」登録後初となる令和6酒造年度に製造された入賞酒が披露され、例年以上の注目を集めました。当日はチケットも完売し1,221名の方が来場、日本酒ファンだけでなく、大学生や訪日外国人なども多く来場しました。
○入賞酒約400点をセルフで試飲 日本酒の個性を五感で味わう特別な3時間!
『公開きき酒会』の会場には、造り手が持てる技術を尽くした貴重な吟醸酒の原酒約400点が地域別に展示され、来場者はセルフサービス形式で自由にテイスティングを楽しみました。
○はじめてのきき酒コーナー」で日本酒の味や香りの違いを体験
会場内で人気だったのが、きき酒を楽しむ方法をレクチャーする「はじめてのきき酒コーナー」で、4つのタイプから自分好みの味と香りを探しだす体験や、全国新酒鑑評会で専門家が実際に行っている味や香りを評価するシートを活用した比較体験にも多くの方が参加しました。
○酒造りを支える技術や裏側を学べるパネル展示
会場内では「伝統的酒造り」の紹介展示をはじめ、日本酒グッズコーナーや、酒瓶などのリサイクルの仕組みを学べる啓発コーナーも併設されました。
また、酒類総合研究所の職員が常駐し、研究成果や酒造技術について来場者にわかりやすく解説する「酒類総合研究所紹介コーナー」ではパネル展示も行われ注目を集めました。
○今後の「公開きき酒会」の展望について
海外や若者に向けて、日本酒がどう変わっていっているのか、時代の変化や技術の進化、米の違いを含めた酒蔵のチャレンジの方向性や背景をもっと知って頂けるようアピールしていきたい。」とコメントし日本酒に関心を持つ国内外の人にアピールしました。
栄で蟹江町PRイベント開催中!ユネスコ無形文化遺産を体感しよう!須成祭稚児衣装が見事
(Yahoo!ニュース・7/29 一部転載)
UR都市機構が、日本全国のまちの魅力を発信するために設けた“ひと”と“まち”のマッチングスペース『まちのたね』(名古屋市中区)では、8月3日(日)まで「【愛知県蟹江町】ユネスコ無形文化遺産 須成祭PR」が開かれています。
名古屋の方々に蟹江町の魅力を知ってもらいたいと蟹江町ふるさと振興課が企画しました。
○ユネスコ無形文化遺産登録“須成祭”へ!
会場では8月3日から始まる須成祭についてパネルで紹介。ユネスコ無形文化遺産に登録されているお祭りを彩る豪華絢爛な稚児衣装の展示も。
期間中の土日には蟹江町職員や観光交流センター“祭人”の職員が来場し、清酒、みりん、焼酎などの特産品の試飲販売も予定されています。
(Yahoo!ニュース・7/29 一部転載)
UR都市機構が、日本全国のまちの魅力を発信するために設けた“ひと”と“まち”のマッチングスペース『まちのたね』(名古屋市中区)では、8月3日(日)まで「【愛知県蟹江町】ユネスコ無形文化遺産 須成祭PR」が開かれています。
名古屋の方々に蟹江町の魅力を知ってもらいたいと蟹江町ふるさと振興課が企画しました。
○ユネスコ無形文化遺産登録“須成祭”へ!
会場では8月3日から始まる須成祭についてパネルで紹介。ユネスコ無形文化遺産に登録されているお祭りを彩る豪華絢爛な稚児衣装の展示も。
期間中の土日には蟹江町職員や観光交流センター“祭人”の職員が来場し、清酒、みりん、焼酎などの特産品の試飲販売も予定されています。
国東市の楽庭八幡社で「吉弘楽」 ユネスコ無形文化遺産登録の太鼓踊り、楽人が披露
(大分合同新聞・7/28 一部転載)
大分県国東市武蔵町吉広地区に伝わる古式ゆかしい太鼓踊り「吉弘楽(よしひろがく)」(国指定重要無形民俗文化財)が7月27日、同地区の楽庭(がくにわ)八幡社であった。
国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録された伝統芸能を一目見ようと、県内外から大勢の観光客らが訪れた。
踊りは午前と午後の2回あり、太鼓や笛、かねの音が響く中、「楽人」と呼ばれる踊り手らが腰みのや旗差し物を身に着けて披露。額に汗を浮かべながら1時間以上かけて全14演目を終えると、境内は大きな拍手に包まれた。
(大分合同新聞・7/28 一部転載)
大分県国東市武蔵町吉広地区に伝わる古式ゆかしい太鼓踊り「吉弘楽(よしひろがく)」(国指定重要無形民俗文化財)が7月27日、同地区の楽庭(がくにわ)八幡社であった。
国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録された伝統芸能を一目見ようと、県内外から大勢の観光客らが訪れた。
踊りは午前と午後の2回あり、太鼓や笛、かねの音が響く中、「楽人」と呼ばれる踊り手らが腰みのや旗差し物を身に着けて披露。額に汗を浮かべながら1時間以上かけて全14演目を終えると、境内は大きな拍手に包まれた。
ユネスコ無形文化遺産「戸畑祇園大山笠」夏の夜を彩る…「ヨイトサ」法被姿の男衆が勇壮に
(読売新聞オンライン・7/27 一部転載)
ユネスコの無形文化遺産で、巨大な提灯山笠で知られる「戸畑祇園大山笠」の競演会が7月26日夜、北九州市戸畑区で開かれた。
太鼓や鉦のお囃子に合わせて「光のピラミッド」が揺れ動き、夏の夜を幻想的に彩った。
同区役所前の会場には、309個の提灯を12段に飾り付けた大山笠(高さ約10メートル、重さ約2.5トン)3基と、中学生が担ぐ一回り小さい小若山笠4基が集合。法被姿の男衆が山笠を担ぎ、「ヨイトサ、ヨイトサ」のかけ声で勇壮に街を練り歩くと、大勢の見物客から歓声が上がった。
(読売新聞オンライン・7/27 一部転載)
ユネスコの無形文化遺産で、巨大な提灯山笠で知られる「戸畑祇園大山笠」の競演会が7月26日夜、北九州市戸畑区で開かれた。
太鼓や鉦のお囃子に合わせて「光のピラミッド」が揺れ動き、夏の夜を幻想的に彩った。
同区役所前の会場には、309個の提灯を12段に飾り付けた大山笠(高さ約10メートル、重さ約2.5トン)3基と、中学生が担ぐ一回り小さい小若山笠4基が集合。法被姿の男衆が山笠を担ぎ、「ヨイトサ、ヨイトサ」のかけ声で勇壮に街を練り歩くと、大勢の見物客から歓声が上がった。
夏の伝統行事「日田祇園」 約300年の歴史でユネスコの無形文化遺産 8基の山鉾が市内を巡行
(TOSテレビ大分・7/27 一部転載)
大分県日田市では夏の伝統行事「日田祇園」が7/27まで開催されています。
「日田祇園」は疫病や風水害を払う祭りとして約300年の歴史があり、2016年にはユネスコの無形文化遺産にも登録されています。
26日から日田市で開催されていて豆田地区と隈・竹田地区を合わせて8基の山鉾が練り歩いています。それぞれの地区には威勢のいい掛け声とお囃子が響き、訪れた見物客は写真を撮るなどして楽しんでいました。
日田祇園は提灯を飾り付けた山鉾が巡行する「晩山」が豆田地区で27日午後6時半ごろから、そして、隈・竹田地区で午後7時半ごろからいずれも午後9時ごろまで行われ、フィナーレを迎えます。
(TOSテレビ大分・7/27 一部転載)
大分県日田市では夏の伝統行事「日田祇園」が7/27まで開催されています。
「日田祇園」は疫病や風水害を払う祭りとして約300年の歴史があり、2016年にはユネスコの無形文化遺産にも登録されています。
26日から日田市で開催されていて豆田地区と隈・竹田地区を合わせて8基の山鉾が練り歩いています。それぞれの地区には威勢のいい掛け声とお囃子が響き、訪れた見物客は写真を撮るなどして楽しんでいました。
日田祇園は提灯を飾り付けた山鉾が巡行する「晩山」が豆田地区で27日午後6時半ごろから、そして、隈・竹田地区で午後7時半ごろからいずれも午後9時ごろまで行われ、フィナーレを迎えます。
「温泉文化」登録へ正念場 政府に働きかけ強める ユネスコ無形文化遺産
(読売オンライン・7/31 一部転載)
群馬県が2028年の実現を目標に掲げる「温泉文化」の国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)無形文化遺産登録の機運醸成に向けた動きが、正念場を迎えている。
今年は国内候補が選ばれる見通しで、山本知事を中心とした精力的な活動が実を結ぶか注目されている。
県から始まった取り組みは全国的な盛り上がりを見せている。今年は勝負の年だ」。みなかみ町の法師温泉「長寿館」会長で「登録を実現する会」の岡村興太郎会長は、先月10日に渋川市伊香保町伊香保の旅館「福一」で開かれた決起集会で知事ら関係者約100人に訴えた。
(読売オンライン・7/31 一部転載)
群馬県が2028年の実現を目標に掲げる「温泉文化」の国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)無形文化遺産登録の機運醸成に向けた動きが、正念場を迎えている。
今年は国内候補が選ばれる見通しで、山本知事を中心とした精力的な活動が実を結ぶか注目されている。
県から始まった取り組みは全国的な盛り上がりを見せている。今年は勝負の年だ」。みなかみ町の法師温泉「長寿館」会長で「登録を実現する会」の岡村興太郎会長は、先月10日に渋川市伊香保町伊香保の旅館「福一」で開かれた決起集会で知事ら関係者約100人に訴えた。
無形文化遺産の盆踊り「大の阪」未来につなぐ…中学生が継承団体から講習
〜 8月14日より16日 魚沼市・八幡宮境内 〜
(新潟日報・7/31 一部転載)
国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録されている魚沼市堀之内地域の盆踊り「大(だい)の阪(さか)」が8月14〜16日、八幡宮境内で行われる。
地元の堀之内中学校の生徒たちが住民から講習を受け、伝統芸能の継承に取り組んでいる。
大の阪は江戸時代、縮商人によって京阪地方からもたらされたとされる。1998年に国重要無形文化財に指定。2022年には全国41件の民俗芸能「風流踊(ふりゅうおどり)」の一つとしてユネスコの文化遺産に登録された。
〜 8月14日より16日 魚沼市・八幡宮境内 〜
(新潟日報・7/31 一部転載)
国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録されている魚沼市堀之内地域の盆踊り「大(だい)の阪(さか)」が8月14〜16日、八幡宮境内で行われる。
地元の堀之内中学校の生徒たちが住民から講習を受け、伝統芸能の継承に取り組んでいる。
大の阪は江戸時代、縮商人によって京阪地方からもたらされたとされる。1998年に国重要無形文化財に指定。2022年には全国41件の民俗芸能「風流踊(ふりゅうおどり)」の一つとしてユネスコの文化遺産に登録された。
豪華絢爛な山車が夏の夜彩る 青森・八戸三社大祭始まる ユネスコ無形文化遺産
(産経新聞・7/31 一部転載)
青森県八戸市で7月31日、国連教育科学文化機関(ユネスコ)無形文化遺産の「八戸三社大祭」が始まった。約300年の歴史があり、東北を代表する夏祭りの一つとして知られる。
前夜祭のこの日、おとぎ話や歌舞伎を題材にした豪華絢爛な山車27台がお披露目され、夏の夜を彩った。8月4日まで。
山車には浦島太郎などの手作りの人形が飾り付けられ、からくり装置が施されている。装置が動き、高さ約11メートル、幅8メートルまで広がると、観客から歓声が上がった。おはやしの音色が響き渡り、子供たちが「ヤーレ、ヤーレ」の掛け声で盛り上げた。
豊作を祈る祭りで、2016年にユネスコ無形文化遺産の「山・鉾・屋台行事」に登録された。8月1日からは市中の練り歩きなどを行う。
(産経新聞・7/31 一部転載)
青森県八戸市で7月31日、国連教育科学文化機関(ユネスコ)無形文化遺産の「八戸三社大祭」が始まった。約300年の歴史があり、東北を代表する夏祭りの一つとして知られる。
前夜祭のこの日、おとぎ話や歌舞伎を題材にした豪華絢爛な山車27台がお披露目され、夏の夜を彩った。8月4日まで。
山車には浦島太郎などの手作りの人形が飾り付けられ、からくり装置が施されている。装置が動き、高さ約11メートル、幅8メートルまで広がると、観客から歓声が上がった。おはやしの音色が響き渡り、子供たちが「ヤーレ、ヤーレ」の掛け声で盛り上げた。
豊作を祈る祭りで、2016年にユネスコ無形文化遺産の「山・鉾・屋台行事」に登録された。8月1日からは市中の練り歩きなどを行う。
悪石島の神「ボゼ」を見に来ないか?今年も観光ツアー開催へ
〜 トカラ列島群発地震が落ち着き、住民も賛同 〜
(南日本新聞・8/7 一部転載)
鹿児島県十島村は9月5〜8日、悪石島の伝統行事「ボゼ祭り」を体験できる観光ツアーを実施する。例年開いてきたが、トカラ列島近海を震源とする群発地震が続き中止も検討されていた。地震活動が落ち着き、地元住民の賛同が得られたことから開催を決めた。12日まで参加者を募る。
ボゼは旧暦7月16日の盆最終日に現れ、村人の穢(けがれ)をはらう神。大きな耳と口、長い鼻の仮面をかぶり、ビロウの葉をまとう。2015年に国の重要無形民俗文化財に指定され、18年には国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録されている。
ツアーは3泊4日。9月5日夜に鹿児島港をフェリーとしま2で出発し、宝島と小宝島を巡り、7日に悪石島でボゼ祭りを見学し、8日に鹿児島港に帰港する。
〜 トカラ列島群発地震が落ち着き、住民も賛同 〜
(南日本新聞・8/7 一部転載)
鹿児島県十島村は9月5〜8日、悪石島の伝統行事「ボゼ祭り」を体験できる観光ツアーを実施する。例年開いてきたが、トカラ列島近海を震源とする群発地震が続き中止も検討されていた。地震活動が落ち着き、地元住民の賛同が得られたことから開催を決めた。12日まで参加者を募る。
ボゼは旧暦7月16日の盆最終日に現れ、村人の穢(けがれ)をはらう神。大きな耳と口、長い鼻の仮面をかぶり、ビロウの葉をまとう。2015年に国の重要無形民俗文化財に指定され、18年には国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録されている。
ツアーは3泊4日。9月5日夜に鹿児島港をフェリーとしま2で出発し、宝島と小宝島を巡り、7日に悪石島でボゼ祭りを見学し、8日に鹿児島港に帰港する。
8月開催!岡山県を代表する夏の伝統行事を紹介 ユネスコ無形文化遺産登録や約1,200発の花火が上がる炎の祭典など、地元を盛り上げる夏の風物詩5選
(岡山県・8/9 一部転載)
各地で盆踊りや夏祭りなどさまざまな行事が催される8月。岡山県でも各地で多彩な伝統行事が行われます。
今回は、ユネスコ無形文化遺産に登録された「白石踊」をはじめ、観音山に「和」の火文字が点火される「和文字焼きまつり」など、伝統と風情を感じる岡山県ならではの夏の風物詩5つを紹介します。
観客動員約50万人以上を記録!岡山県下最大級の“夏まつり”「うらじゃ」
岡山県下最大級の夏まつり。「うらじゃ」は、岡山県に古くから伝わる、桃太郎のモデルとされる「吉備津彦命(きびつひこのみこと)」と「温羅(うら)=鬼」との戦いを描いた桃太郎伝説から生まれ、1994年から開催されている歴史ある祭りです。
「温羅伝説」をもとに、鬼のメイクを施した踊り子たちが岡山市内各所にてパレードや演舞場にて踊りを披露する「うらじゃ」の演舞のほか、祭りのクライマックスで観客・踊り子が一緒に踊る「総おどり」や、どなたでもうらじゃメイクが楽しめる「温羅化粧」ブース、子どもも一緒に楽しめるファミリーフェスタなどが開催されます。
本年は30周年を記念してキティちゃんが来岡。サンリオ・スペシャルパレードがお祭りに彩りを添えます。
(岡山県・8/9 一部転載)
各地で盆踊りや夏祭りなどさまざまな行事が催される8月。岡山県でも各地で多彩な伝統行事が行われます。
今回は、ユネスコ無形文化遺産に登録された「白石踊」をはじめ、観音山に「和」の火文字が点火される「和文字焼きまつり」など、伝統と風情を感じる岡山県ならではの夏の風物詩5つを紹介します。
観客動員約50万人以上を記録!岡山県下最大級の“夏まつり”「うらじゃ」
岡山県下最大級の夏まつり。「うらじゃ」は、岡山県に古くから伝わる、桃太郎のモデルとされる「吉備津彦命(きびつひこのみこと)」と「温羅(うら)=鬼」との戦いを描いた桃太郎伝説から生まれ、1994年から開催されている歴史ある祭りです。
「温羅伝説」をもとに、鬼のメイクを施した踊り子たちが岡山市内各所にてパレードや演舞場にて踊りを披露する「うらじゃ」の演舞のほか、祭りのクライマックスで観客・踊り子が一緒に踊る「総おどり」や、どなたでもうらじゃメイクが楽しめる「温羅化粧」ブース、子どもも一緒に楽しめるファミリーフェスタなどが開催されます。
本年は30周年を記念してキティちゃんが来岡。サンリオ・スペシャルパレードがお祭りに彩りを添えます。
8月開催!岡山県を代表する夏の伝統行事を紹介 ユネスコ無形文化遺産登録や約1,200発の花火が上がる炎の祭典など、地元を盛り上げる夏の風物詩5選
(岡山県・8/9 一部転載)
各地で盆踊りや夏祭りなどさまざまな行事が催される8月。岡山県でも各地で多彩な伝統行事が行われます。
今回は、ユネスコ無形文化遺産に登録された「白石踊」をはじめ、観音山に「和」の火文字が点火される「和文字焼きまつり」など、伝統と風情を感じる岡山県ならではの夏の風物詩5つを紹介します。
観客動員約50万人以上を記録!岡山県下最大級の“夏まつり”「うらじゃ」
岡山県下最大級の夏まつり。「うらじゃ」は、岡山県に古くから伝わる、桃太郎のモデルとされる「吉備津彦命(きびつひこのみこと)」と「温羅(うら)=鬼」との戦いを描いた桃太郎伝説から生まれ、1994年から開催されている歴史ある祭りです。
「温羅伝説」をもとに、鬼のメイクを施した踊り子たちが岡山市内各所にてパレードや演舞場にて踊りを披露する「うらじゃ」の演舞のほか、祭りのクライマックスで観客・踊り子が一緒に踊る「総おどり」や、どなたでもうらじゃメイクが楽しめる「温羅化粧」ブース、子どもも一緒に楽しめるファミリーフェスタなどが開催されます。
本年は30周年を記念してキティちゃんが来岡。サンリオ・スペシャルパレードがお祭りに彩りを添えます。
(岡山県・8/9 一部転載)
各地で盆踊りや夏祭りなどさまざまな行事が催される8月。岡山県でも各地で多彩な伝統行事が行われます。
今回は、ユネスコ無形文化遺産に登録された「白石踊」をはじめ、観音山に「和」の火文字が点火される「和文字焼きまつり」など、伝統と風情を感じる岡山県ならではの夏の風物詩5つを紹介します。
観客動員約50万人以上を記録!岡山県下最大級の“夏まつり”「うらじゃ」
岡山県下最大級の夏まつり。「うらじゃ」は、岡山県に古くから伝わる、桃太郎のモデルとされる「吉備津彦命(きびつひこのみこと)」と「温羅(うら)=鬼」との戦いを描いた桃太郎伝説から生まれ、1994年から開催されている歴史ある祭りです。
「温羅伝説」をもとに、鬼のメイクを施した踊り子たちが岡山市内各所にてパレードや演舞場にて踊りを披露する「うらじゃ」の演舞のほか、祭りのクライマックスで観客・踊り子が一緒に踊る「総おどり」や、どなたでもうらじゃメイクが楽しめる「温羅化粧」ブース、子どもも一緒に楽しめるファミリーフェスタなどが開催されます。
本年は30周年を記念してキティちゃんが来岡。サンリオ・スペシャルパレードがお祭りに彩りを添えます。
涼風の盆景 阿南で2つのユネスコ無形文化遺産「風流踊り」
(飯田経済新聞・8/18 一部転載)
和合の念仏踊りは阿南町和合地区で約300年続くお盆の念仏踊りで、毎年8月13日〜16日に行われる。2023年にユネスコ無形文化遺産「風流踊り」として登録された。
今年は大阪関西万博での踊りの披露や、「第45回伝統文化ポーラ賞」の地域賞を受賞。13日は熊野神社で始まり、大屋の宮下家、林松寺と巡った。14日は林松寺の境内に涼やかな風が吹く中、「庭入り」では、ヤッコ、花などの行列に続き、鐘や太鼓の音が里山に響き、「ヤートーセー」のかけ声とともにヒッチキと呼ばれる若い踊り手が2人1組で激しく体をぶつけ合いながら飛び回った。
その後、厳かな「念仏」「和讃(わさん)」の声と太鼓の音が和合の山あいに響いた。ヒッチキ役として参加した高校生の小掠哲生さんは「疲れた。長く続いてきたものなので、外に出てもお盆には帰ってきて踊りたい」と話す。
同踊り保存会の平松三武会長は「山村留学などで移住してきた若い人たちが参加してくれうれしい。万博は30分に凝縮して披露することができた」と振り返る。愛知県から写真を撮りに訪れた男性は「初めて見たが、国の文化財だけあって、なかなか見ることができない踊りで良かった」と感想を話した。
新野の盆踊りは、阿南町新野地区で室町時代から約500年続く「風流踊」とされる盆踊りで、毎年8月14日〜16日の夜から早朝まで踊り明かす。
100種類以上あるという盆唄は太鼓などの鳴り物を使わず、櫓(やぐら)の上で音頭を取る5、6人の「音頭出し」が交代で歌いつなぐ。
14日21時、目抜き通りに集まった住民らが盆唄に合わせ「すくいさ」といわれる踊りで静かに始まった。
浴衣姿の人など老若男女約150人が踊りの輪を作り、会話やあいさつを交えゆったりとした時間が過ぎる。扇子を持って踊るものを含め7種類をランダムに踊り、早朝6時まで続く。
同保存会の林弥寿雄会長は「毎年お盆前後は雨の日が多いが、今年は晴天に恵まれそうで良かった。伝統を受け継いでくれる人がもう少しいてくれるとうれしい」と話す。最後の17日早朝には、鐘と太鼓を打ちながら精霊を送り出す行事を行った。
(飯田経済新聞・8/18 一部転載)
和合の念仏踊りは阿南町和合地区で約300年続くお盆の念仏踊りで、毎年8月13日〜16日に行われる。2023年にユネスコ無形文化遺産「風流踊り」として登録された。
今年は大阪関西万博での踊りの披露や、「第45回伝統文化ポーラ賞」の地域賞を受賞。13日は熊野神社で始まり、大屋の宮下家、林松寺と巡った。14日は林松寺の境内に涼やかな風が吹く中、「庭入り」では、ヤッコ、花などの行列に続き、鐘や太鼓の音が里山に響き、「ヤートーセー」のかけ声とともにヒッチキと呼ばれる若い踊り手が2人1組で激しく体をぶつけ合いながら飛び回った。
その後、厳かな「念仏」「和讃(わさん)」の声と太鼓の音が和合の山あいに響いた。ヒッチキ役として参加した高校生の小掠哲生さんは「疲れた。長く続いてきたものなので、外に出てもお盆には帰ってきて踊りたい」と話す。
同踊り保存会の平松三武会長は「山村留学などで移住してきた若い人たちが参加してくれうれしい。万博は30分に凝縮して披露することができた」と振り返る。愛知県から写真を撮りに訪れた男性は「初めて見たが、国の文化財だけあって、なかなか見ることができない踊りで良かった」と感想を話した。
新野の盆踊りは、阿南町新野地区で室町時代から約500年続く「風流踊」とされる盆踊りで、毎年8月14日〜16日の夜から早朝まで踊り明かす。
100種類以上あるという盆唄は太鼓などの鳴り物を使わず、櫓(やぐら)の上で音頭を取る5、6人の「音頭出し」が交代で歌いつなぐ。
14日21時、目抜き通りに集まった住民らが盆唄に合わせ「すくいさ」といわれる踊りで静かに始まった。
浴衣姿の人など老若男女約150人が踊りの輪を作り、会話やあいさつを交えゆったりとした時間が過ぎる。扇子を持って踊るものを含め7種類をランダムに踊り、早朝6時まで続く。
同保存会の林弥寿雄会長は「毎年お盆前後は雨の日が多いが、今年は晴天に恵まれそうで良かった。伝統を受け継いでくれる人がもう少しいてくれるとうれしい」と話す。最後の17日早朝には、鐘と太鼓を打ちながら精霊を送り出す行事を行った。
ユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」の神秘を探りながら、銘酒を味わう『KABUKIZA酒亭 〜歌舞伎座で日本酒を愉しむ』第一回が開催
(SPICE/スパイス・8/19)
茨城県・月の井酒造店で杜氏を務める石川達也氏を招き、「伝統的酒造りとは何か?」解き明かしながら渾身の酒々を味わうイベント『歌舞伎座で日本酒を愉しむ』が、2025年8月27日(水)歌舞伎座・花篭ホールにて開催される。
2024年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」。江戸時代に完成した「生酛造り」などの伝統的製法で造られた日本酒が近年脚光を浴びている。
竹鶴酒造で長年、「生酛造り」「蓋麹法」などの伝統的酒造りを追求し、流行りの日本酒が一世を風靡する中で、日本酒本来の価値と魅力を問い直してきた石川達也氏は、その立役者。独自の哲学と筋の通った酒造りで、多くの酒徒を魅了し続けてきた。
今回のイベントでは、歌舞伎座のお弁当に受け継がれた伝統の味を肴に、銘酒「月の井」に酔いしれる贅沢を楽しめる。渋谷の燗酒店「えんらい」も出店し、石川達也氏が醸した各年代の熟成酒を取り揃える。今となっては貴重な一本に出会えるかも。
(SPICE/スパイス・8/19)
茨城県・月の井酒造店で杜氏を務める石川達也氏を招き、「伝統的酒造りとは何か?」解き明かしながら渾身の酒々を味わうイベント『歌舞伎座で日本酒を愉しむ』が、2025年8月27日(水)歌舞伎座・花篭ホールにて開催される。
2024年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」。江戸時代に完成した「生酛造り」などの伝統的製法で造られた日本酒が近年脚光を浴びている。
竹鶴酒造で長年、「生酛造り」「蓋麹法」などの伝統的酒造りを追求し、流行りの日本酒が一世を風靡する中で、日本酒本来の価値と魅力を問い直してきた石川達也氏は、その立役者。独自の哲学と筋の通った酒造りで、多くの酒徒を魅了し続けてきた。
今回のイベントでは、歌舞伎座のお弁当に受け継がれた伝統の味を肴に、銘酒「月の井」に酔いしれる贅沢を楽しめる。渋谷の燗酒店「えんらい」も出店し、石川達也氏が醸した各年代の熟成酒を取り揃える。今となっては貴重な一本に出会えるかも。
香川 綾川町 ユネスコ無形文化遺産「滝宮の念仏踊」奉納
(香川 NEWS WEB・8/24 一部転載)
花笠をかぶった人たちがうちわや楽器を持って踊る、ユネスコの無形文化遺産、「滝宮の念仏踊」が香川県綾川町で、8月24日奉納されました。
「滝宮の念仏踊」は、平安時代に讃岐の国司だった菅原道真が、干ばつで苦しむ農民のために雨乞いをして、3日3晩、雨が降り続いたことを喜んだ人々が感謝のために踊ったのが始まりとされます。
綾川町の滝宮神社と滝宮天満宮では、毎年8月下旬にこの踊りが奉納されていて、滝宮天満宮では、町内に11ある踊組のうち3組が踊りを披露しました。
花笠をかぶり錦のはかまと陣羽織を身につけた踊り手たちは、念仏や囃子に合わせて大きなうちわをひらめかせて踊っていました。
(香川 NEWS WEB・8/24 一部転載)
花笠をかぶった人たちがうちわや楽器を持って踊る、ユネスコの無形文化遺産、「滝宮の念仏踊」が香川県綾川町で、8月24日奉納されました。
「滝宮の念仏踊」は、平安時代に讃岐の国司だった菅原道真が、干ばつで苦しむ農民のために雨乞いをして、3日3晩、雨が降り続いたことを喜んだ人々が感謝のために踊ったのが始まりとされます。
綾川町の滝宮神社と滝宮天満宮では、毎年8月下旬にこの踊りが奉納されていて、滝宮天満宮では、町内に11ある踊組のうち3組が踊りを披露しました。
花笠をかぶり錦のはかまと陣羽織を身につけた踊り手たちは、念仏や囃子に合わせて大きなうちわをひらめかせて踊っていました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|