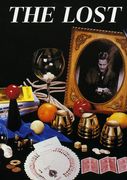CERVON, BRUCE (1941-2007)
本名はアンドリュー・ブルース・セルナヴァ(Andrew Bruce Cernava)。
アメリカを代表するクロースアップマジシャンであり、もっとも成功を収めたクロースアップマジシャンでもある。
25年以上もフルタイムのプロマジシャンとして活躍していた。
彼はハリウッドを中心に映画スターや政治家などのプライベートパーティーなどでマジックを見せることを仕事にしていた。
ボブ・ホープ、シルベスタ・スタローン、サリー・フィールド、ケーリー・グラント、ディック・キャベット、ウディ・アレン、ジェイムス・スチュアートなどなど有名人の目前で演じていた。
テレビではトゥナイトショーなど数々の番組に出演し、バーガーキングのコマーシャルにおいてはマジック指導も行った。
またカルフォルニア州においてはギャンブルテクニックの専門アドバイザーとしての顔もあった。
代表作としては「ハンキーパンキー」「パーペチュアル・ポーカー・ディール」「エアロダイナミックエーセス」「サーボンモンテ」など。
売りネタとしての「ダーティーディール」は、その後のパケットブームの先駆けとなった。
著述家としても多くの現象や手順,技法などを発表している。
『ジニー』、『ポールベアラーズレビュー』、『エピローグ』、『イバイデム』など様々なマジック雑誌ばかりではなく、"The Real Work"、"The Cervon File"、"Ultra Cervon"などの著書もある。
ちなみにマジックが全く書いておらずバーノンの生涯と考えだけをつづったバーノンクロニクル4巻を著したのもサーボンだ。
マジックキャッスルを運営するアカデミー・オブ・マジカル・アーツの運営委員の一人でもあり、そのアカデミーにおいてはベストクロースアップマジシャン賞を二度受賞、レクチャー・オブ・ザ・イヤーにも選ばれている。
日本テレビの企画で1978年8月にスライディーニとともに来日し、テレビで演じている。
その時は、司会の高島忠夫とケイ・アンナにハンキーパンキーやハンカチ燃やし、シルバーとカッパーの交換、指輪のカードケースへの飛行、ルポールの財布などを演じていた。
「1960年代マイク・スキナー、ラリイ・ジェニングスと並んでバーノンの気に入りのマジックキャッスル三羽烏のひとりといわれた。技巧ではマイクに劣り、オリジナリティではラリイに劣るが,見せ方のうまさでは一番であろう。」
松田道弘
高木重朗著『エアロダイナミック・エーセス』立体社1971
ダイ・バーノン
http://
高木重朗
http://
本名はアンドリュー・ブルース・セルナヴァ(Andrew Bruce Cernava)。
アメリカを代表するクロースアップマジシャンであり、もっとも成功を収めたクロースアップマジシャンでもある。
25年以上もフルタイムのプロマジシャンとして活躍していた。
彼はハリウッドを中心に映画スターや政治家などのプライベートパーティーなどでマジックを見せることを仕事にしていた。
ボブ・ホープ、シルベスタ・スタローン、サリー・フィールド、ケーリー・グラント、ディック・キャベット、ウディ・アレン、ジェイムス・スチュアートなどなど有名人の目前で演じていた。
テレビではトゥナイトショーなど数々の番組に出演し、バーガーキングのコマーシャルにおいてはマジック指導も行った。
またカルフォルニア州においてはギャンブルテクニックの専門アドバイザーとしての顔もあった。
代表作としては「ハンキーパンキー」「パーペチュアル・ポーカー・ディール」「エアロダイナミックエーセス」「サーボンモンテ」など。
売りネタとしての「ダーティーディール」は、その後のパケットブームの先駆けとなった。
著述家としても多くの現象や手順,技法などを発表している。
『ジニー』、『ポールベアラーズレビュー』、『エピローグ』、『イバイデム』など様々なマジック雑誌ばかりではなく、"The Real Work"、"The Cervon File"、"Ultra Cervon"などの著書もある。
ちなみにマジックが全く書いておらずバーノンの生涯と考えだけをつづったバーノンクロニクル4巻を著したのもサーボンだ。
マジックキャッスルを運営するアカデミー・オブ・マジカル・アーツの運営委員の一人でもあり、そのアカデミーにおいてはベストクロースアップマジシャン賞を二度受賞、レクチャー・オブ・ザ・イヤーにも選ばれている。
日本テレビの企画で1978年8月にスライディーニとともに来日し、テレビで演じている。
その時は、司会の高島忠夫とケイ・アンナにハンキーパンキーやハンカチ燃やし、シルバーとカッパーの交換、指輪のカードケースへの飛行、ルポールの財布などを演じていた。
「1960年代マイク・スキナー、ラリイ・ジェニングスと並んでバーノンの気に入りのマジックキャッスル三羽烏のひとりといわれた。技巧ではマイクに劣り、オリジナリティではラリイに劣るが,見せ方のうまさでは一番であろう。」
松田道弘
高木重朗著『エアロダイナミック・エーセス』立体社1971
ダイ・バーノン
http://
高木重朗
http://
|
|
|
|
コメント(32)
>ちょっとした違いなのですが、きれいに見せるためのハンドリングやTipsのような物を沢山持っていた方のように思います。
同感です。
彼のマジック自体は大変地味なものばかりです。しかしその地味なはずのマジックでフルタイムプロとして食べてきた事には、なにか重要な意味があるはずなのです。
ジェニングスに関してはファンも多く、たくさん研究されていると思いますが、サーボンに関しては名前はよく知られていてもその内面に関してはほとんど理解されていないのが現状ではないでしょうか。
>1978年年の来日の際のレクチャーで彼の演技見ました。
オーソドックスなスタンダードをキレイに演じるマジシャンという印象がありました。
うらやましいです。
松田道弘氏によればレクチャーラーとしても開拓者の一人であり、そのレクチャーも抜群にうまかったそうですが、実際いかがだったのでしょうか。
同感です。
彼のマジック自体は大変地味なものばかりです。しかしその地味なはずのマジックでフルタイムプロとして食べてきた事には、なにか重要な意味があるはずなのです。
ジェニングスに関してはファンも多く、たくさん研究されていると思いますが、サーボンに関しては名前はよく知られていてもその内面に関してはほとんど理解されていないのが現状ではないでしょうか。
>1978年年の来日の際のレクチャーで彼の演技見ました。
オーソドックスなスタンダードをキレイに演じるマジシャンという印象がありました。
うらやましいです。
松田道弘氏によればレクチャーラーとしても開拓者の一人であり、そのレクチャーも抜群にうまかったそうですが、実際いかがだったのでしょうか。
実は私は、ほとんどサーボンについては知らない。唯一、見たことがあって記憶している姿は、バーノンの初心者向け作品集ビデオの中で、2枚伏せたうち正解はどちらかを当てる、という作品で外れたら中身をあげよう、と自分の太った財布を持ち出し、客の反応を見ながらその財布をどすん、とカードの上において見せるところ、だけなのだ。
そのビデオを見たのは随分昔で、丁度ビデオに物珍しく見たこともないような現象、種を求めて見ていた頃であり、その当時は全くつまらないビデオとの印象しか持ち得なかった。
しかし考えてみれば、種でも現象でもなく、ただ財布を置いて見せる時の、客を見ながらどちらにしようか迷ってみせている時の、あるいはこちらと決心してどすんと置いて見せた時の、サーボン本人だけが脳裏に焼きついているということは、いかにサーボンが優れた演者であるかを物語ることなのだと、今にして思うのだ。
例えば驚愕のモンテとクライマックスがあったとして、後から果たしてこれをやった人はどんな人だったか、思い出せないような演技だったとしたら、それではその人がマジックを見せる意味がないではないか。誰がやったか思い出せないマジック。これほど悲しい見世物はないだろう。
サーボンと同様に、三羽烏の一人であるスキナーの演技を見たのも、ほんの最近である(ジーンムナリが出した03年の演技集の、3巻目とオマケ)。さすがカジノ、ゴールデンナゲットで看板として数十年も見せまくってきただけの事はあり、どの演技を見ても現象はハッキリしていて、その手際はまるで立て板に水、敢然としてよどむところがなく目にも楽しいものであった。しかし、私にはいくらか田舎くさいように見え、サーボンに見られる色気のような美味しさを感じることは出来なかった。
ジェニングスはメディアでの露出も多く、その自前のネタへの磐石な自信からきているのであろう余裕を感じさせるジェニングスの演技とあわせ、これで三羽烏の演技を見比べることができ、(この程度の見比べであるとはいえ)サーボンが一番演技者としてぬきんでていることを感じることが出来た。
私の中では、アメリカマジック史の中で、三羽烏と、マイケルアマーやジェイサンキとの間に入るべき世代の名前が思い出せない。
バーノンの弟子としての三羽烏、バーノンに憧れる若手としてのアマーとバーノンに代表される大文字としての『マジック』を否定して名をはせたサンキとの間に居るべき、三羽烏の継承者としての世代、のことである(人間の年齢的に見れば、この世代を特色付けるほどに年代が離れていないのかもしれないが)。
上記括弧書きのような留保があるにもかかわらず、このこと(三羽烏の次世代が見当たらないこと)は、いかにバーノンと三羽烏が偉大な世代だったかを物語っているように思えてならない。それはつまり、アマーのようなまるでネオクラシックとでも言うべき世代や、バーノンに代表されるメインストリームへのアンチとしてのサンキがでてくるまでは、とても凡百には太刀打ちできないほどに、三羽烏がマジックを完成しつくした事の表れと思える、ということなのだ。
今現在のマジックを取り巻く状況を見るに、サンキのようなアンチとしてのマジックは廃れたとはいえないほどに命脈を保ってこそ居るが、否定をすることで存在を保証されるような、カウンターパートとしてのマジックが本流を奪取するような事態はちょっとなさそうに思える。そして(私がそう感じているだけなのかも知れぬのだが)、アマーのネオクラシックとも言うべき世代をはるかに超えて、もっと根本的に観客に見せている、見られていることに自覚的な、新しい世代が、いまやマジックを受けとめる側である観客側から、求められているように感じている。
そのことを考えるに、今こそサーボンの演技は見られなくてはならないのではないのかと思っていた矢先の、サーボンの死であったのだ。
実際の私は、サーボン以上の存在が大きくあって、サーボンを追悼するほどには思い入れが深くはなく、しかも実際にそのなしてきたことをほとんど知らない。だから縷々考えてきたことが根こそぎ成立しえないことも、充分以上にあることを自覚している。
にもかかわらず、三羽烏の生き残りの死に際して、こうしたことを感じずにはいられなかった。
別に大事な関わりを持たない存在の、単なる追悼ではなく、こうしたことを想起しないわけには、いかなかったのだ。
そのビデオを見たのは随分昔で、丁度ビデオに物珍しく見たこともないような現象、種を求めて見ていた頃であり、その当時は全くつまらないビデオとの印象しか持ち得なかった。
しかし考えてみれば、種でも現象でもなく、ただ財布を置いて見せる時の、客を見ながらどちらにしようか迷ってみせている時の、あるいはこちらと決心してどすんと置いて見せた時の、サーボン本人だけが脳裏に焼きついているということは、いかにサーボンが優れた演者であるかを物語ることなのだと、今にして思うのだ。
例えば驚愕のモンテとクライマックスがあったとして、後から果たしてこれをやった人はどんな人だったか、思い出せないような演技だったとしたら、それではその人がマジックを見せる意味がないではないか。誰がやったか思い出せないマジック。これほど悲しい見世物はないだろう。
サーボンと同様に、三羽烏の一人であるスキナーの演技を見たのも、ほんの最近である(ジーンムナリが出した03年の演技集の、3巻目とオマケ)。さすがカジノ、ゴールデンナゲットで看板として数十年も見せまくってきただけの事はあり、どの演技を見ても現象はハッキリしていて、その手際はまるで立て板に水、敢然としてよどむところがなく目にも楽しいものであった。しかし、私にはいくらか田舎くさいように見え、サーボンに見られる色気のような美味しさを感じることは出来なかった。
ジェニングスはメディアでの露出も多く、その自前のネタへの磐石な自信からきているのであろう余裕を感じさせるジェニングスの演技とあわせ、これで三羽烏の演技を見比べることができ、(この程度の見比べであるとはいえ)サーボンが一番演技者としてぬきんでていることを感じることが出来た。
私の中では、アメリカマジック史の中で、三羽烏と、マイケルアマーやジェイサンキとの間に入るべき世代の名前が思い出せない。
バーノンの弟子としての三羽烏、バーノンに憧れる若手としてのアマーとバーノンに代表される大文字としての『マジック』を否定して名をはせたサンキとの間に居るべき、三羽烏の継承者としての世代、のことである(人間の年齢的に見れば、この世代を特色付けるほどに年代が離れていないのかもしれないが)。
上記括弧書きのような留保があるにもかかわらず、このこと(三羽烏の次世代が見当たらないこと)は、いかにバーノンと三羽烏が偉大な世代だったかを物語っているように思えてならない。それはつまり、アマーのようなまるでネオクラシックとでも言うべき世代や、バーノンに代表されるメインストリームへのアンチとしてのサンキがでてくるまでは、とても凡百には太刀打ちできないほどに、三羽烏がマジックを完成しつくした事の表れと思える、ということなのだ。
今現在のマジックを取り巻く状況を見るに、サンキのようなアンチとしてのマジックは廃れたとはいえないほどに命脈を保ってこそ居るが、否定をすることで存在を保証されるような、カウンターパートとしてのマジックが本流を奪取するような事態はちょっとなさそうに思える。そして(私がそう感じているだけなのかも知れぬのだが)、アマーのネオクラシックとも言うべき世代をはるかに超えて、もっと根本的に観客に見せている、見られていることに自覚的な、新しい世代が、いまやマジックを受けとめる側である観客側から、求められているように感じている。
そのことを考えるに、今こそサーボンの演技は見られなくてはならないのではないのかと思っていた矢先の、サーボンの死であったのだ。
実際の私は、サーボン以上の存在が大きくあって、サーボンを追悼するほどには思い入れが深くはなく、しかも実際にそのなしてきたことをほとんど知らない。だから縷々考えてきたことが根こそぎ成立しえないことも、充分以上にあることを自覚している。
にもかかわらず、三羽烏の生き残りの死に際して、こうしたことを感じずにはいられなかった。
別に大事な関わりを持たない存在の、単なる追悼ではなく、こうしたことを想起しないわけには、いかなかったのだ。
コウスケさんへ
>レクチャーがショーになっているのを見た最初のマジシャンでした。
ちなみに内容はどうだったのでしょう? サーボンと言うとカードマジックの印象が強く、またレクチャーのようなクロースアップとは言いがたい人数の前で演じながら教えていくにはどういったネタだったのでしょうか? 差し支えない範囲で教えていただけないでしょうか?
トリック・ユニバースさんへ
私自身もサーボン師とクリント・イーストウッドは似ているなあ、なんて思いながら映像を見ていました。
わがままかどうかは分かりませんが、片足を椅子にのっけた独特のポーズは真似出来ない雰囲気だなあ、とか思っていました。
考えてみれば、高島忠夫にルポールを演じたとき、賭けを行いますか?と聞いて断られると「やめた、やめた」なんて突き放す演技はわがまま(?)なのかも知れません。
S原さんへ
>私の中では、アメリカマジック史の中で、三羽烏と、マイケルアマーやジェイサンキとの間に入るべき世代の名前が思い出せない。
まだ、ロスにはアール・ネルソン、ジョン・カーニーがいますよ。
エリック・デ・キャンプやボブ・コーラーも正統派として受け継いでいると言えるのではないでしょうか。
Tangoさんへ
>マジックは「何が起きたか」と同時に「誰が演じたか」も記憶にとどめさせなければ意味が無さそうですね。
結局そこにその人個人の何かが必要となってくるのでしょうね。特にサーボン師のマジックは地味なんてもんじゃないほど地味です。でもそれでありながらフルタイムのプロとして長い期間食べていける何かがあったのだと思います。
>レクチャーがショーになっているのを見た最初のマジシャンでした。
ちなみに内容はどうだったのでしょう? サーボンと言うとカードマジックの印象が強く、またレクチャーのようなクロースアップとは言いがたい人数の前で演じながら教えていくにはどういったネタだったのでしょうか? 差し支えない範囲で教えていただけないでしょうか?
トリック・ユニバースさんへ
私自身もサーボン師とクリント・イーストウッドは似ているなあ、なんて思いながら映像を見ていました。
わがままかどうかは分かりませんが、片足を椅子にのっけた独特のポーズは真似出来ない雰囲気だなあ、とか思っていました。
考えてみれば、高島忠夫にルポールを演じたとき、賭けを行いますか?と聞いて断られると「やめた、やめた」なんて突き放す演技はわがまま(?)なのかも知れません。
S原さんへ
>私の中では、アメリカマジック史の中で、三羽烏と、マイケルアマーやジェイサンキとの間に入るべき世代の名前が思い出せない。
まだ、ロスにはアール・ネルソン、ジョン・カーニーがいますよ。
エリック・デ・キャンプやボブ・コーラーも正統派として受け継いでいると言えるのではないでしょうか。
Tangoさんへ
>マジックは「何が起きたか」と同時に「誰が演じたか」も記憶にとどめさせなければ意味が無さそうですね。
結局そこにその人個人の何かが必要となってくるのでしょうね。特にサーボン師のマジックは地味なんてもんじゃないほど地味です。でもそれでありながらフルタイムのプロとして長い期間食べていける何かがあったのだと思います。
あらかじめのおことわり
細かいことはおぼえておりません。
レクチャーノートに書いているトリックは下記のとおりです。
Hanky Panky
Blasted Routine
The Universal Card
Gene Finnell's Needle Trick
Open Prediction
Cervon's Off a Rope
Perpetual Motion Poker Routine
例1
たとえば、Blasted Routine
ワイングラスとコースターを使用するコイントリックです。
手順解説のときに、コースターを動かしながら
寝てしまいます。(もちろん演技)
思わず笑い出しました。
解説でも客を楽しませてくれたのです。
例2
シルバーとカパーの交換現象。
サーボンは、シルバーを何度も何度も何度も客に確認させてから手ににぎります。
シルバーをにぎったあとで、カパーをとりだしてきます。
手ににぎっているのはシルバーだとよくわかります。
普通のマジシャンは、シルバーとカパーを両方とも同時に客に見せてから、それぞれ手ににぎるので、どちらがどちらかわからなくなるのです。
細かいことはおぼえておりません。
レクチャーノートに書いているトリックは下記のとおりです。
Hanky Panky
Blasted Routine
The Universal Card
Gene Finnell's Needle Trick
Open Prediction
Cervon's Off a Rope
Perpetual Motion Poker Routine
例1
たとえば、Blasted Routine
ワイングラスとコースターを使用するコイントリックです。
手順解説のときに、コースターを動かしながら
寝てしまいます。(もちろん演技)
思わず笑い出しました。
解説でも客を楽しませてくれたのです。
例2
シルバーとカパーの交換現象。
サーボンは、シルバーを何度も何度も何度も客に確認させてから手ににぎります。
シルバーをにぎったあとで、カパーをとりだしてきます。
手ににぎっているのはシルバーだとよくわかります。
普通のマジシャンは、シルバーとカパーを両方とも同時に客に見せてから、それぞれ手ににぎるので、どちらがどちらかわからなくなるのです。
コウスケさんへ
レクチャー内容を書いていただきありがとうございます。
いろいろと自分なりに思うことを書きつづりました。補足していただけると嬉しく思います。宜しくお願いします。
>Hanky Panky
白いハンカチを借りてマッチで焦がしてしまう。こげたハンカチにコインが通り抜ける、というギャグを行ってからコインをひっくり返すたびにコインが出現し、最後にタバコとライターが出てくる、というものでしょうか?
だとしたらたぶん、サーボン師の通常営業手順だと思います。この手順は間に入れているのではなく、オープナーだった、という事なのでしょうか。
後に出版された著書には、クライマックスにはタバコとライターではなく、ワイングラス(ドリンク入り)を出現させていたかと思います。
>Blasted Routine
以前、ミスターマジシャンにおいても”ブラステッド”の商品名で売られていたものかと思います。ワイングラス、もしくはシャンパングラスを灰皿(コースター?)に口を下にしてかぶせ、コインが飛行するものでした。
売りネタでありながらネタ臭くなく、結構好きな商品でした。
サーボン師はそれを二段重ねにしたかと記憶していますが、どうだったのでしょう?
>The Universal Card
日本では、なぜか全く流行らなかったカードトリックにこのユニバーサルカードがあります。
おそらく、純粋なクロースアップマジックというよりは、サロンマジックだからかも知れません。
私自身はトムソーニ師のギミックカードを用いる方法が好きでしたが、サーボン師はノーマルカードだったのでしょうか?
>Gene Finnell's Needle Trick
すいません、知らないので教えていただけないでしょうか。タイトルから想像するしかないのですが、針を糸に通してその上にハンカチをかぶせ、おまじないをかけると針が通り抜けている、というものでしょうか?
>Open Prediction
以前、某テレビ番組でサーボンし演じるこのマジックを見たことがあります。見事な解決法に感心したばかりではなく、もっとも
難しいと思われるカードを51枚めくっている動作を退屈させない雰囲気にびっくりしました。
>Cervon's Off a Rope
これは結び解けなのでしょうか? サーボン師のロープトリックは大変珍しいものだと思います。
>Perpetual Motion Poker Routine
これがレクチャーのトリネタだったんですね。実際に演じている人を見たことがないので分からないのですが、こうしたポーカーデモンストレーションはどうなんでしょうか? やはりそれを演じきるだけの技量をサーボン師が持っていた、という事なのでしょう。
こうして考えるとネタものらしさはレクチャーさえも存在していない、という事が理解出来ます。
またこのレクチャー内容であれば、サロン的な状況であっても通じるものであることも理解出来ます。
こうしたレクチャーを受ける人間もある程度マジックを知っている、という事を想定しているのならば、セッティングであり,ちょっとしたコツであり、そうしたものが役にたったことでしょう。
もう一度サーボン師のレクチャービデオなどを見返してみたくなりました。
レクチャー内容を書いていただきありがとうございます。
いろいろと自分なりに思うことを書きつづりました。補足していただけると嬉しく思います。宜しくお願いします。
>Hanky Panky
白いハンカチを借りてマッチで焦がしてしまう。こげたハンカチにコインが通り抜ける、というギャグを行ってからコインをひっくり返すたびにコインが出現し、最後にタバコとライターが出てくる、というものでしょうか?
だとしたらたぶん、サーボン師の通常営業手順だと思います。この手順は間に入れているのではなく、オープナーだった、という事なのでしょうか。
後に出版された著書には、クライマックスにはタバコとライターではなく、ワイングラス(ドリンク入り)を出現させていたかと思います。
>Blasted Routine
以前、ミスターマジシャンにおいても”ブラステッド”の商品名で売られていたものかと思います。ワイングラス、もしくはシャンパングラスを灰皿(コースター?)に口を下にしてかぶせ、コインが飛行するものでした。
売りネタでありながらネタ臭くなく、結構好きな商品でした。
サーボン師はそれを二段重ねにしたかと記憶していますが、どうだったのでしょう?
>The Universal Card
日本では、なぜか全く流行らなかったカードトリックにこのユニバーサルカードがあります。
おそらく、純粋なクロースアップマジックというよりは、サロンマジックだからかも知れません。
私自身はトムソーニ師のギミックカードを用いる方法が好きでしたが、サーボン師はノーマルカードだったのでしょうか?
>Gene Finnell's Needle Trick
すいません、知らないので教えていただけないでしょうか。タイトルから想像するしかないのですが、針を糸に通してその上にハンカチをかぶせ、おまじないをかけると針が通り抜けている、というものでしょうか?
>Open Prediction
以前、某テレビ番組でサーボンし演じるこのマジックを見たことがあります。見事な解決法に感心したばかりではなく、もっとも
難しいと思われるカードを51枚めくっている動作を退屈させない雰囲気にびっくりしました。
>Cervon's Off a Rope
これは結び解けなのでしょうか? サーボン師のロープトリックは大変珍しいものだと思います。
>Perpetual Motion Poker Routine
これがレクチャーのトリネタだったんですね。実際に演じている人を見たことがないので分からないのですが、こうしたポーカーデモンストレーションはどうなんでしょうか? やはりそれを演じきるだけの技量をサーボン師が持っていた、という事なのでしょう。
こうして考えるとネタものらしさはレクチャーさえも存在していない、という事が理解出来ます。
またこのレクチャー内容であれば、サロン的な状況であっても通じるものであることも理解出来ます。
こうしたレクチャーを受ける人間もある程度マジックを知っている、という事を想定しているのならば、セッティングであり,ちょっとしたコツであり、そうしたものが役にたったことでしょう。
もう一度サーボン師のレクチャービデオなどを見返してみたくなりました。
1978年の世界奇術大賞(NTV)での演技。TV放映ではかなりカットされてましたが,ノーカットの手順を記します。
3本ロープ
「三本の同じ長さのロープの長さがバラバラになり,また同一になり,最後は一本に」
銀貨と銅貨
「客の持った銀貨と術者の銅貨の交換。硬貨の消失」
ハンキーパンキー
「ハンカチにコインを包んで,マッチで焦がす。真ん中に穴があくが元に戻る。それから,ハンカチの中からコインが何度か出現。最後はタバコとマッチ箱が出現」
コインの移動
「左手の4枚のコインが一枚ずつ右手に移動」シェル
指輪の移動
「客から借りた指輪が消失。カードケースから出現」
カードマジック
「エースの出現→エアロダイナミックエーセス→エースが絵札に変化→ルポールの財布」
3本ロープ
「三本の同じ長さのロープの長さがバラバラになり,また同一になり,最後は一本に」
銀貨と銅貨
「客の持った銀貨と術者の銅貨の交換。硬貨の消失」
ハンキーパンキー
「ハンカチにコインを包んで,マッチで焦がす。真ん中に穴があくが元に戻る。それから,ハンカチの中からコインが何度か出現。最後はタバコとマッチ箱が出現」
コインの移動
「左手の4枚のコインが一枚ずつ右手に移動」シェル
指輪の移動
「客から借りた指輪が消失。カードケースから出現」
カードマジック
「エースの出現→エアロダイナミックエーセス→エースが絵札に変化→ルポールの財布」
>3本ロープ
「三本の同じ長さのロープの長さがバラバラになり,また同一になり,最後は一本に」
この手順は高木先生のロープの本にサーボン師の方法として記載されていたものかと思いますが、まさかオープナーとは思いませんでした。3本ロープの中でもっともフェアに見えるものの一つかと思います。
サーボン師はロープをどこから出したのでしょう? そしてどこにしまったのでしょう?
ポケットからですか?
そしていったいどんなセリフだったのでしょうか?
本来の3本ロープは3本のバラバラの長さのロープが出てきます。ところがそうしたバラバラの長さのロープを用意する事に一般の方々は違和感を持ちます。その違和感を解消するために”教授の悪夢”というシナリオが生まれました。
スライディーニの場合は一本のロープを三等分する事でそれを解決しました。
サーボン師は,あえて最初から同じ長さのロープを持ってくる事で解決したのでしょう。しかし、最初にロープのマジックを行う事に何か理由があるかと思います。
このあとに銀貨と銅貨の手順に繋がるという事は、それらのコインはどうやって出したのでしょうか? 単純にパースを出してその中からコインを出したのでしょうか? あるいはポケットからそのまんまコインを出したような気もします。
「三本の同じ長さのロープの長さがバラバラになり,また同一になり,最後は一本に」
この手順は高木先生のロープの本にサーボン師の方法として記載されていたものかと思いますが、まさかオープナーとは思いませんでした。3本ロープの中でもっともフェアに見えるものの一つかと思います。
サーボン師はロープをどこから出したのでしょう? そしてどこにしまったのでしょう?
ポケットからですか?
そしていったいどんなセリフだったのでしょうか?
本来の3本ロープは3本のバラバラの長さのロープが出てきます。ところがそうしたバラバラの長さのロープを用意する事に一般の方々は違和感を持ちます。その違和感を解消するために”教授の悪夢”というシナリオが生まれました。
スライディーニの場合は一本のロープを三等分する事でそれを解決しました。
サーボン師は,あえて最初から同じ長さのロープを持ってくる事で解決したのでしょう。しかし、最初にロープのマジックを行う事に何か理由があるかと思います。
このあとに銀貨と銅貨の手順に繋がるという事は、それらのコインはどうやって出したのでしょうか? 単純にパースを出してその中からコインを出したのでしょうか? あるいはポケットからそのまんまコインを出したような気もします。
>3本ロープ
「三本の同じ長さのロープの長さがバラバラになり,また同一になり,最後は一本に」
>この手順は高木先生のロープの本にサーボン師の方法として記載されていたものかと思いますが、まさかオープナーとは思いませんでした。3本ロープの中でもっともフェアに見えるものの一つかと思います。
>サーボン師はロープをどこから出したのでしょう? そしてどこにしまったのでしょう?ポケットからですか?
>そしていったいどんなセリフだったのでしょうか?
ポケツトからいきなり出して,「3本のロープがあります」
という感じ。
最後に1本にしたものは,テーブル陰に捨てました。カバンか箱でもあったのでしょう。
「三本の同じ長さのロープの長さがバラバラになり,また同一になり,最後は一本に」
>この手順は高木先生のロープの本にサーボン師の方法として記載されていたものかと思いますが、まさかオープナーとは思いませんでした。3本ロープの中でもっともフェアに見えるものの一つかと思います。
>サーボン師はロープをどこから出したのでしょう? そしてどこにしまったのでしょう?ポケットからですか?
>そしていったいどんなセリフだったのでしょうか?
ポケツトからいきなり出して,「3本のロープがあります」
という感じ。
最後に1本にしたものは,テーブル陰に捨てました。カバンか箱でもあったのでしょう。
>ポケツトからいきなり出して,「3本のロープがあります」という感じ。
案外そんな感じでいいんですよね。余計な説明はいらないと思います。
ロープマジックをオープナーにするクロースアップマジシャンはわりと欧米では多いかと思います。ロープマジックがマジックの代表だったころの名残なのか、はたまた大人数に良く見えるマジックだからでしょうか。おそらく後者だからだと思います。
それにオープニングのマジックで観客の手伝いを必要とするネタよりは、一方的に説明出来るマジックの方が良いのでしょう。
>RYUSEIさん書込み久しぶりですね。
いろいろと旅に出ていますと書き込みが出来ないんですよ。
こうしてサーボン師のマジックを考えてみると、
ロープ、コイン、カード、財布、指輪、ハンカチ、マッチなど、様々なアイテムが出てくる事が分かります。
カードだけ、コインだけ、というのはあくまでもマニアは喜びますが,一般客は様々なマジックを見たいという欲求があります。彼はそれを満たしているのでしょう。
しかも、不自然な道具は一つもなく特に派手な現象もなく、それらを丁寧に構築している事が理解出来ます。
あえて得意のカードマジックをクライマックスに持って来ているのも素晴らしい事だと思います。
やはり非凡なマジシャンですね。
案外そんな感じでいいんですよね。余計な説明はいらないと思います。
ロープマジックをオープナーにするクロースアップマジシャンはわりと欧米では多いかと思います。ロープマジックがマジックの代表だったころの名残なのか、はたまた大人数に良く見えるマジックだからでしょうか。おそらく後者だからだと思います。
それにオープニングのマジックで観客の手伝いを必要とするネタよりは、一方的に説明出来るマジックの方が良いのでしょう。
>RYUSEIさん書込み久しぶりですね。
いろいろと旅に出ていますと書き込みが出来ないんですよ。
こうしてサーボン師のマジックを考えてみると、
ロープ、コイン、カード、財布、指輪、ハンカチ、マッチなど、様々なアイテムが出てくる事が分かります。
カードだけ、コインだけ、というのはあくまでもマニアは喜びますが,一般客は様々なマジックを見たいという欲求があります。彼はそれを満たしているのでしょう。
しかも、不自然な道具は一つもなく特に派手な現象もなく、それらを丁寧に構築している事が理解出来ます。
あえて得意のカードマジックをクライマックスに持って来ているのも素晴らしい事だと思います。
やはり非凡なマジシャンですね。
高木重朗氏の著書にそのものズバリ『エアロダイナミック・エーセス』という名の小冊子があります。
1971年発行で立体社という聞いたことのない出版社から発行されています。
もちろんサーボン師の作品を中心としているのですが、テーマとしては4A特集となっています。
1、エアロダイナミック・エーセス(ブルース・サーボン)
2、イースター・エーセス(ハンス・トリッカー)
3、カンガルー・エーセス(マイケル・リム)
4、エレベーター・エーセス(カーク・カークハン)
5、ジュビレースション(ステランコ)
エアロダイナミックエーセスにはなんと10ページも割いて詳しく解説されています。『カードマジック事典』における同作品の解説に比べたらなんて親切なことでしょう。
あるいはその為にエアロダイナミックエーセスの真の良さが理解されなかったのかもしれません。
高木先生は1970年4月にニューヨークにおいてサーボン師のレクチャーを受けたそうです。
「この”4枚のA”は1枚ずつAが移る”スローモーション・フォー・エーセス”や“リアル・ゴーン・エーセス”などをさらに進めてAだけで行うようにしたもので新しい型の”4枚のA”です。同種の奇術ラリー・ジェニングス氏やマイク・スキナー氏が考案しています。」
1969年にはアルトン・シャープの著書によってジェニングスのオープントラベラーが発表されています。
それを考えるとそれらの作品を比べて高木先生はサーボン版を評価したのだと思います。
「サーボン氏の方法の特徴は,パームなどの難しい技法を使わないで行えるという点です。」
なんか高木先生の考えの根幹を成す言葉の様な気がします。ちなみに高木バージョンも存在するようで奇術研究57号にあるそうです。
これは私見なのでもちろん反論はあるかと思いますが、エアロダイナミックエーセスは高木氏が指摘したようにスローモーションフォアエースのバリエーションだと思いますが、オープントラベラーはバーノンのトラベラーのバリエーションかと思っているのです。
つまり、”エアロ〜”はエースの”移動現象”、”オープン〜”はエースの”飛行現象”とハンドリングは似ているのですが,それぞれの表現が違っていると解釈しています。
1971年発行で立体社という聞いたことのない出版社から発行されています。
もちろんサーボン師の作品を中心としているのですが、テーマとしては4A特集となっています。
1、エアロダイナミック・エーセス(ブルース・サーボン)
2、イースター・エーセス(ハンス・トリッカー)
3、カンガルー・エーセス(マイケル・リム)
4、エレベーター・エーセス(カーク・カークハン)
5、ジュビレースション(ステランコ)
エアロダイナミックエーセスにはなんと10ページも割いて詳しく解説されています。『カードマジック事典』における同作品の解説に比べたらなんて親切なことでしょう。
あるいはその為にエアロダイナミックエーセスの真の良さが理解されなかったのかもしれません。
高木先生は1970年4月にニューヨークにおいてサーボン師のレクチャーを受けたそうです。
「この”4枚のA”は1枚ずつAが移る”スローモーション・フォー・エーセス”や“リアル・ゴーン・エーセス”などをさらに進めてAだけで行うようにしたもので新しい型の”4枚のA”です。同種の奇術ラリー・ジェニングス氏やマイク・スキナー氏が考案しています。」
1969年にはアルトン・シャープの著書によってジェニングスのオープントラベラーが発表されています。
それを考えるとそれらの作品を比べて高木先生はサーボン版を評価したのだと思います。
「サーボン氏の方法の特徴は,パームなどの難しい技法を使わないで行えるという点です。」
なんか高木先生の考えの根幹を成す言葉の様な気がします。ちなみに高木バージョンも存在するようで奇術研究57号にあるそうです。
これは私見なのでもちろん反論はあるかと思いますが、エアロダイナミックエーセスは高木氏が指摘したようにスローモーションフォアエースのバリエーションだと思いますが、オープントラベラーはバーノンのトラベラーのバリエーションかと思っているのです。
つまり、”エアロ〜”はエースの”移動現象”、”オープン〜”はエースの”飛行現象”とハンドリングは似ているのですが,それぞれの表現が違っていると解釈しています。
このエアロダイナミックエーセスは、正味エアロ〜だけではありません。なんと手順になっているのです。
第三段からなる手順であり、
1、カッティングエーセス(バーノンとは異なり単なるエースオープナー)
2、エアロダイナミックエーセス
3、ポーカーディール(Perpetual Motion Poker Routine)
となっています。
もちろん、これらのマジックが終了したあともリセットされているという特徴があります。
おそらく、そうした部分を高木先生は高く評価したのではないでしょうか。
そう考えたとき、第二段目のエアロ〜そのものがカードの消失と飛行ではなく、むしろポーカーデモンストレーションの一環の様な気がしてきます。
第三段からなる手順であり、
1、カッティングエーセス(バーノンとは異なり単なるエースオープナー)
2、エアロダイナミックエーセス
3、ポーカーディール(Perpetual Motion Poker Routine)
となっています。
もちろん、これらのマジックが終了したあともリセットされているという特徴があります。
おそらく、そうした部分を高木先生は高く評価したのではないでしょうか。
そう考えたとき、第二段目のエアロ〜そのものがカードの消失と飛行ではなく、むしろポーカーデモンストレーションの一環の様な気がしてきます。
>「リセットできるなんていうのは演じる側の勝手な都合だ」
ひとつひとつのマジック,
「カッティングジエーセス」「ポーカーデモンストレーション」
などバーノンの手順の方がはるかに優れているではないか。
まったくもって同感です。
しかし、しかしですぞ、実際に手順をやってみたところ頭の中だけでは分からなかったことがいくつか分かって来た様な気がします。
エアロ〜手順はリセットされている、という事ばかりか、じつは忘れにくい、という利点があるのです。
忘れにくい、というのは覚え易いという事以上に大事なことだと思います。
そして手順構成の新しさ、です。
それまでの手順は一つの現象に関して一演目だったと思います。
つまり一つ一つが独立しているのです。
エアロ〜手順の良さは一つの手順が終わると次の手順の準備が出来上がっている、という事です。一つ一つの手順はそれほどの傑作ではないにせよ、それが連続技となると、ほどよい現象なのです。
おそらく高木先生を含め,当時の関係者が惚れたのはそう言う部分ではなかったか、と思えるのです。
ひとつひとつのマジック,
「カッティングジエーセス」「ポーカーデモンストレーション」
などバーノンの手順の方がはるかに優れているではないか。
まったくもって同感です。
しかし、しかしですぞ、実際に手順をやってみたところ頭の中だけでは分からなかったことがいくつか分かって来た様な気がします。
エアロ〜手順はリセットされている、という事ばかりか、じつは忘れにくい、という利点があるのです。
忘れにくい、というのは覚え易いという事以上に大事なことだと思います。
そして手順構成の新しさ、です。
それまでの手順は一つの現象に関して一演目だったと思います。
つまり一つ一つが独立しているのです。
エアロ〜手順の良さは一つの手順が終わると次の手順の準備が出来上がっている、という事です。一つ一つの手順はそれほどの傑作ではないにせよ、それが連続技となると、ほどよい現象なのです。
おそらく高木先生を含め,当時の関係者が惚れたのはそう言う部分ではなかったか、と思えるのです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-