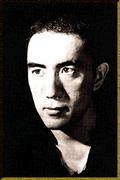三島由紀夫の神秘思想、とも呼ばれる難解な作品です。
三島はこの自作について、こう記述しました。
「このエッセイは、私自身、甚だ長い時間をかけて書き、自分の文学と行動、精神と肉体の関係について、能ふかぎり公平で客観的な立場から分析したものであるが、
この「公平」といふこと、肉体と精神の双方に対して「公平」であるといふ態度ほど、日本知識人にとって難解な態度はないらしく、
このエッセイに深甚な関心を示されたのは、虫明氏や秋山駿氏や少数の人だけであった。」
(「三島由紀夫 文学論集」<昭和45年3月初版>への序文)
むつかしい所・疑問点を、ここに書き込んで下さったら、
私が解釈してみますので、皆様と一緒に考えて行きたいと思います。
三島はこの自作について、こう記述しました。
「このエッセイは、私自身、甚だ長い時間をかけて書き、自分の文学と行動、精神と肉体の関係について、能ふかぎり公平で客観的な立場から分析したものであるが、
この「公平」といふこと、肉体と精神の双方に対して「公平」であるといふ態度ほど、日本知識人にとって難解な態度はないらしく、
このエッセイに深甚な関心を示されたのは、虫明氏や秋山駿氏や少数の人だけであった。」
(「三島由紀夫 文学論集」<昭和45年3月初版>への序文)
むつかしい所・疑問点を、ここに書き込んで下さったら、
私が解釈してみますので、皆様と一緒に考えて行きたいと思います。
|
|
|
|
コメント(17)
久々のコメント ありがとうございます。『こいつぁ春から縁起がいいやぁ』という気分です。
ありがとうございます。『こいつぁ春から縁起がいいやぁ』という気分です。
?まず、中公文庫「太陽と鉄」↓。私もこれを持っています。
http://www.amazon.co.jp/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E3%81%A8%E9%89%84-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%B8%89%E5%B3%B6-%E7%94%B1%E7%B4%80%E5%A4%AB/dp/4122014689
自伝エッセイ「私の遍歴時代」(執筆は昭和39年ごろ)が併載(カップリング)されています。
そして解説が、佐伯彰一氏。←三島文学館の館長をされた英米文学者で、これは魅力です。一部を引きます。
佐伯が主宰者の一人である雑誌に、まず連載の形で発表された「太陽と鉄」について、
「密度の詰まった結晶度の高さと同時に、あまりにもひたむきな疾走ぶりが間々論理的飛躍をともなって、不透明な難解さに途惑いをおぼえずにいられなかった。こうした当時の印象は、再読、三読を重ねた今も、あまり変らない。」
うぅ〜ん。。。日本を代表する英文学者が、「難解」と言うのですから、
やっぱり「太陽と鉄」は、神秘にあふれてますね。
私の考えですが、昭和43年に書かれた「太陽と鉄」には、
もう死への準備にかかっていた三島が、自らの死の、ナゾを解く鍵をそっと忍ばせたから、難解になったのだと思います。
平易な文章で、死へのあこがれ・敗戦後の日本への絶望etc.を書いたら、
自決を世間が予想して、危険人物=テロリスト扱いをし、昭和45年11月25日の衝撃は小さかったと思います。
?もうひとつ、講談社文芸文庫から、3分冊で出ている「三島由紀夫 文学論集」に、「太陽と鉄」が入っています。↓
http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=198439X
高い文庫ですが、さっきの「私の遍歴時代」と共に、その前に書かれた、
日記の形の自伝エッセイ「小説家の休暇」(S30)、「裸体と衣装」(S34)をはじめ、
ざっと48の評論が収録されています。
この本の単行本は、昭和45年3月に発行されました。私はそれを古書店で見つけて、狂喜した次第です。
こっちの魅力は、三島本人が「序文」を書いて、「太陽と鉄」への思いを語っている点です。
さて、私のおすすめは、?です。
「安い・表紙が気味わるくて美しい・解説がいい」という理由で。
ならば、?の三島の「序文」はどうするか?ですが、
ざっと900字弱の短い文章ですので、easy all という人が、ここに書き写してくれるかも?知れません。
(著作権は、問題ないでしょうか?)
あと二つの自伝エッセイは、新潮文庫にも入っています。
?まず、中公文庫「太陽と鉄」↓。私もこれを持っています。
http://www.amazon.co.jp/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E3%81%A8%E9%89%84-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%B8%89%E5%B3%B6-%E7%94%B1%E7%B4%80%E5%A4%AB/dp/4122014689
自伝エッセイ「私の遍歴時代」(執筆は昭和39年ごろ)が併載(カップリング)されています。
そして解説が、佐伯彰一氏。←三島文学館の館長をされた英米文学者で、これは魅力です。一部を引きます。
佐伯が主宰者の一人である雑誌に、まず連載の形で発表された「太陽と鉄」について、
「密度の詰まった結晶度の高さと同時に、あまりにもひたむきな疾走ぶりが間々論理的飛躍をともなって、不透明な難解さに途惑いをおぼえずにいられなかった。こうした当時の印象は、再読、三読を重ねた今も、あまり変らない。」
うぅ〜ん。。。日本を代表する英文学者が、「難解」と言うのですから、
やっぱり「太陽と鉄」は、神秘にあふれてますね。
私の考えですが、昭和43年に書かれた「太陽と鉄」には、
もう死への準備にかかっていた三島が、自らの死の、ナゾを解く鍵をそっと忍ばせたから、難解になったのだと思います。
平易な文章で、死へのあこがれ・敗戦後の日本への絶望etc.を書いたら、
自決を世間が予想して、危険人物=テロリスト扱いをし、昭和45年11月25日の衝撃は小さかったと思います。
?もうひとつ、講談社文芸文庫から、3分冊で出ている「三島由紀夫 文学論集」に、「太陽と鉄」が入っています。↓
http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=198439X
高い文庫ですが、さっきの「私の遍歴時代」と共に、その前に書かれた、
日記の形の自伝エッセイ「小説家の休暇」(S30)、「裸体と衣装」(S34)をはじめ、
ざっと48の評論が収録されています。
この本の単行本は、昭和45年3月に発行されました。私はそれを古書店で見つけて、狂喜した次第です。
こっちの魅力は、三島本人が「序文」を書いて、「太陽と鉄」への思いを語っている点です。
さて、私のおすすめは、?です。
「安い・表紙が気味わるくて美しい・解説がいい」という理由で。
ならば、?の三島の「序文」はどうするか?ですが、
ざっと900字弱の短い文章ですので、easy all という人が、ここに書き写してくれるかも?知れません。
(著作権は、問題ないでしょうか?)
あと二つの自伝エッセイは、新潮文庫にも入っています。
三島由紀夫はナルシストだと言われるが、よくもここまで自分自身のことに拘泥できるものだと思う。押しつけがましい理屈をこねすぎているように感じるのは私だけだろうか。
このくどくどしさは彼の肉体的劣等感がいかに大きなものであったかということだろう。これほど高い知性をもちながら、自分を見据える視点の甘さが同一人物に同居している、というバランスの悪さは悲劇的なまでに滑稽でもある。
≪--しかし、突然、あらゆる幻想は消えた。退屈している認識は不可解なもののみを追い求め、後に、突然その不可解は瓦解し、‥‥胸囲一メートル以上の男は私だったのである。‥‥
かつて向こう岸にいたと思われた人々は、もはや私と同じ岸にいるようになった。既に謎はなく、謎は死だけにあった。≫
彼には気の毒だが、彼は向こう岸にはまだ渡っていない。たとえ胸囲が1メートルを超えたとしても、単にそれは肉がついたというだけの話でしかない。彼は相変わらず、ひ弱なインテリであったと私は思う。ボディビルをして栄養をとれば、誰にでも筋肉がつく。それ以上の意味はない。それだけの努力をしたという事実を評価する人もいるが、私にはただ執着心が強かっただけのことのように思える。自由業者であることと執着心の強さがそれをなしとげさせたのだ。
強さへのあこがれが彼を拳闘や剣道に導いたのは自然の流れだった。このエッセーではまるで彼が剣の極意に到達しているかのような記述がある。彼はハッキリと自分を「武人」として位置付けているのである。
その人が武人であるかどうかはその技量によるものではないとは私も思う。しかし常識のある人なら、自分が一定の技量に達していなければ決して武人を名乗ったりしない。そういう意味で、三島の格闘技における技量が「人並み」の域に達していたかどうかが問題になる。残念ながら、拳闘ではスパーリングをじかに見た石原慎太郎に「まったく才能なし」と酷評されている。彼に言わせれば「決定的に運動神経が欠落している。」ということらしい。このスパーリングについては石原が8ミリ撮影していた、三島はそれを見てさすがに「主観と客観」のズレにがっかりしたという。
剣道についても、人によって評価は分かれるが、その実力は初段に到達しているかどうかというところが本当のところらしい。ちなみに、私の同級生で剣道やっている連中はみな中学校で段をとっている。強い奴は中学生で2段までとったのである。初段程度の腕前で、剣について語るなどはおこがましいと言われても仕方ないだろう。
ドナルド・キーンは三島文学を高く評価しているが、この「太陽と鉄」に関しては酷評している。特に神輿を担いだ体験について述べているくだりについては「嘘である」とまで言っている。
≪幼児、私は神輿の担ぎ手たちが、酩酊のうちに、言うに言われぬ放恣な表情で、顔をのけぞらせ、甚だしいのは担ぎ棒に完全に項をゆだねて、神輿を練りまわす姿を見て、彼らの目に映っているものは何だろうかという謎に、深く心を惑わされたことがある。‥‥‥ずっと後になって、肉体の言葉を学びだしてから、私は進んで神輿を担ぎ、幼児からの謎を解明する機会をようよう得た。その結果わかったことは、彼らはただ空を見ていたのだった。彼らの目には何の幻もなゆく、ただ初秋の絶対の青空があるばかりだった。≫
キーン氏は嘘だと言い切っているが、この件に関してだけ言えば、私はこれは嘘ではないと思う。日本通のキーン氏も神輿を担ぐ行為が日本の若者の通過儀礼であることを理解できていないのだと思う。荒々しい生気に満ちた半裸の男たちの中に身を投じて、思春期の若者はいっぱしの男である自覚をもつのである。思春期をとうに過ぎたオッサンである三島は、やっと手に入れた肉体によって、遅ればせながらその通過儀礼に参加できた、「やっとこちら側に来れた」という喜びを語っているにすぎない。
≪自意識が発見する滑稽さを粉砕するには、肉体の説得力があれば十分なのだ。すぐれた肉体には悲壮なものはあるが、微塵も滑稽なものはないからである。≫
それにしては語りすぎである。だったら、もう黙っていればと言いたくなるのだか゛、この言葉のすぐ後にこう続く。
≪しかし、肉体を終局的に滑稽さから救うものこそ、健全強壮な肉体における死の要素であり、肉体の気品はそれによって支えられねばならなかった。≫
「だから死を選んだのか?」と私は三島に問いたい。それで結局、滑稽さから救われたのか? 私は否だと思う。しかし、まるで自画自賛と言わんばかりのこの「太陽と鉄」というエッセーがある限り、そのことはある種の滑稽さから免れられないような気がするのである。
このくどくどしさは彼の肉体的劣等感がいかに大きなものであったかということだろう。これほど高い知性をもちながら、自分を見据える視点の甘さが同一人物に同居している、というバランスの悪さは悲劇的なまでに滑稽でもある。
≪--しかし、突然、あらゆる幻想は消えた。退屈している認識は不可解なもののみを追い求め、後に、突然その不可解は瓦解し、‥‥胸囲一メートル以上の男は私だったのである。‥‥
かつて向こう岸にいたと思われた人々は、もはや私と同じ岸にいるようになった。既に謎はなく、謎は死だけにあった。≫
彼には気の毒だが、彼は向こう岸にはまだ渡っていない。たとえ胸囲が1メートルを超えたとしても、単にそれは肉がついたというだけの話でしかない。彼は相変わらず、ひ弱なインテリであったと私は思う。ボディビルをして栄養をとれば、誰にでも筋肉がつく。それ以上の意味はない。それだけの努力をしたという事実を評価する人もいるが、私にはただ執着心が強かっただけのことのように思える。自由業者であることと執着心の強さがそれをなしとげさせたのだ。
強さへのあこがれが彼を拳闘や剣道に導いたのは自然の流れだった。このエッセーではまるで彼が剣の極意に到達しているかのような記述がある。彼はハッキリと自分を「武人」として位置付けているのである。
その人が武人であるかどうかはその技量によるものではないとは私も思う。しかし常識のある人なら、自分が一定の技量に達していなければ決して武人を名乗ったりしない。そういう意味で、三島の格闘技における技量が「人並み」の域に達していたかどうかが問題になる。残念ながら、拳闘ではスパーリングをじかに見た石原慎太郎に「まったく才能なし」と酷評されている。彼に言わせれば「決定的に運動神経が欠落している。」ということらしい。このスパーリングについては石原が8ミリ撮影していた、三島はそれを見てさすがに「主観と客観」のズレにがっかりしたという。
剣道についても、人によって評価は分かれるが、その実力は初段に到達しているかどうかというところが本当のところらしい。ちなみに、私の同級生で剣道やっている連中はみな中学校で段をとっている。強い奴は中学生で2段までとったのである。初段程度の腕前で、剣について語るなどはおこがましいと言われても仕方ないだろう。
ドナルド・キーンは三島文学を高く評価しているが、この「太陽と鉄」に関しては酷評している。特に神輿を担いだ体験について述べているくだりについては「嘘である」とまで言っている。
≪幼児、私は神輿の担ぎ手たちが、酩酊のうちに、言うに言われぬ放恣な表情で、顔をのけぞらせ、甚だしいのは担ぎ棒に完全に項をゆだねて、神輿を練りまわす姿を見て、彼らの目に映っているものは何だろうかという謎に、深く心を惑わされたことがある。‥‥‥ずっと後になって、肉体の言葉を学びだしてから、私は進んで神輿を担ぎ、幼児からの謎を解明する機会をようよう得た。その結果わかったことは、彼らはただ空を見ていたのだった。彼らの目には何の幻もなゆく、ただ初秋の絶対の青空があるばかりだった。≫
キーン氏は嘘だと言い切っているが、この件に関してだけ言えば、私はこれは嘘ではないと思う。日本通のキーン氏も神輿を担ぐ行為が日本の若者の通過儀礼であることを理解できていないのだと思う。荒々しい生気に満ちた半裸の男たちの中に身を投じて、思春期の若者はいっぱしの男である自覚をもつのである。思春期をとうに過ぎたオッサンである三島は、やっと手に入れた肉体によって、遅ればせながらその通過儀礼に参加できた、「やっとこちら側に来れた」という喜びを語っているにすぎない。
≪自意識が発見する滑稽さを粉砕するには、肉体の説得力があれば十分なのだ。すぐれた肉体には悲壮なものはあるが、微塵も滑稽なものはないからである。≫
それにしては語りすぎである。だったら、もう黙っていればと言いたくなるのだか゛、この言葉のすぐ後にこう続く。
≪しかし、肉体を終局的に滑稽さから救うものこそ、健全強壮な肉体における死の要素であり、肉体の気品はそれによって支えられねばならなかった。≫
「だから死を選んだのか?」と私は三島に問いたい。それで結局、滑稽さから救われたのか? 私は否だと思う。しかし、まるで自画自賛と言わんばかりのこの「太陽と鉄」というエッセーがある限り、そのことはある種の滑稽さから免れられないような気がするのである。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
三島由紀夫のことをかたつたり 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-