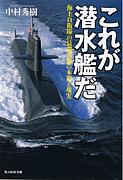6月13日公開の「真夏のオリオン」試写会に行ってきました。
その感想を日記にしましたが、潜水艦関連なので、ご紹介がてら転記します。
公開後、ご覧になって感想など、このトピに書き込んでください、
以下転記
20日に試写会に行って来た。
製作にあたり、資料の鑑定や脚本の監修に多少の関与をしたので、出来上がった作品には興味がある。
一生懸命作った、という印象はある。
青春映画としては面白いが、戦争映画、潜水艦映画としては話にならない。
考証がお粗末であることと、軍事知識潜水艦知識が中途半端。知らないものが内容を理解しないまま、適当に作った、という印象である。
突っ込みどころは満載だが、そのいくつかを列挙した。
潜水艦相手に魚雷を撃ったり、昭和20年夏の時点で、巡潜が数隻哨戒していることや、聴音で距離が分るような無茶はあえて目をつぶっても、以下は許せん。
1 登場人物、特に艦長が軍人らしくない。
深刻な表情だけは上手いが、言動挙措容儀、どれをとっても軍人それも、艦長級の中堅士官にはとても見えない。
2種軍装の似合わないことと、高校生みたいな髪型が頼りない新入社員にしか見えないのだ。
昭和30年代は、どんな大根も軍人役はこなせる、と言われたが。今時の役者は、軍人と侍役は絶望的に似合わない。
兵学校出身の艦長が、「飯、飯」というのも、みっともない話だ。最も見ていられない場面は、戦闘中潜望鏡を放り出して、カレーを掻き込む姿だ。場合によっては軍法会議モノである。
2 号令がいい加減
脚本段階で指摘したのだが、わけのわからん号令が多い。中途半端に正確な号令もあるのだが、意味不明の号令や用語が氾濫。これは、ミリオタコミュでも見られる傾向だ。
浸水したら馬鹿の一つ覚えで「舷外弁閉め」である。意味分ってるのか?舷外弁というのは、数十数百あるのだ。
魚雷発射の号令など、見ていて恥ずかしくなる。発射管と魚雷の混同や、やたら「テーッ」である。
3 回天搭乗員は大尉だけ?
全員搭乗服に大尉の階級章を付けているが、先任者は中尉らしいし、他は下士官という設定である。
ついでに、3種軍装で短剣を吊らないのも気になる。
服装は細かく指摘せざるを得ないのは、服装については十分な調査をしていたからである。
4 回天の無人発進と二基が完全併走
物理的にありえない。馬鹿馬鹿しさを通り過ぎた、滅茶苦茶である。
5 敵駆逐艦(amick級護衛駆逐艦に見えた)の至近距離に何度も浮上する。
訳がわからん。戦闘中に敵の至近距離に浮上する意味が映画のストーリー上からも理解できない。現実には当然ありえない。
おまけに、2度目の浮上では、総員退艦を命じる。
これまたありえない話で、ほんとにやったら艦長は海軍刑法の定めにより死刑である。日本のみならず、世界中の海軍でも、弾がなくなったからと言って、敵の至近距離において、戦うことなく退艦はありえない。
6 僚艦「伊81潜」が、被害を受けて着底しているが。
潜望鏡の鏡体をレンチで叩いてモールスで「伊77潜」と通信する。この意味も理解できない。この場面はいったい何のために挿入されているのだろう。
製作者は、何を言いたいのかわからんが、これまたありえない行動である。
7 人間関係、艦内編成が不自然
機関長や水雷長(特務士官ということはない)が、キャリアの艦長に対してノンキャリという設定に見える。航海長も同じように扱っているようだ。
機関長は機関学校出のいわばキャリアだし、水雷長や航海長も兵学校出身のはずだ。艦長の後輩だから、敬語を使うなど不自然を通り越して、荒唐無稽の茶番である。
製作者は、海軍も潜水艦も分っていない。
8 発令所と司令塔を混同。
潜望鏡があるところを見ると司令塔らしいが、発令所にあるべき装置がそこにもある。発令所が勤務場所の水雷長もいるし、居るべき通信士は居ない。
今の潜水艦と混同している。たぶん、軍事知識のない海上自衛官に取材した結果だろう。
問題は、これだけではないのだが、きりがないのでこの辺にしておこう。
丁寧に一生懸命作っているようだが、詰めが甘すぎるのと、お粗末な原作や脚本を優先して、専門家の意見を無視した結果、荒唐無稽な作品になっちまった。
残念だ。
その感想を日記にしましたが、潜水艦関連なので、ご紹介がてら転記します。
公開後、ご覧になって感想など、このトピに書き込んでください、
以下転記
20日に試写会に行って来た。
製作にあたり、資料の鑑定や脚本の監修に多少の関与をしたので、出来上がった作品には興味がある。
一生懸命作った、という印象はある。
青春映画としては面白いが、戦争映画、潜水艦映画としては話にならない。
考証がお粗末であることと、軍事知識潜水艦知識が中途半端。知らないものが内容を理解しないまま、適当に作った、という印象である。
突っ込みどころは満載だが、そのいくつかを列挙した。
潜水艦相手に魚雷を撃ったり、昭和20年夏の時点で、巡潜が数隻哨戒していることや、聴音で距離が分るような無茶はあえて目をつぶっても、以下は許せん。
1 登場人物、特に艦長が軍人らしくない。
深刻な表情だけは上手いが、言動挙措容儀、どれをとっても軍人それも、艦長級の中堅士官にはとても見えない。
2種軍装の似合わないことと、高校生みたいな髪型が頼りない新入社員にしか見えないのだ。
昭和30年代は、どんな大根も軍人役はこなせる、と言われたが。今時の役者は、軍人と侍役は絶望的に似合わない。
兵学校出身の艦長が、「飯、飯」というのも、みっともない話だ。最も見ていられない場面は、戦闘中潜望鏡を放り出して、カレーを掻き込む姿だ。場合によっては軍法会議モノである。
2 号令がいい加減
脚本段階で指摘したのだが、わけのわからん号令が多い。中途半端に正確な号令もあるのだが、意味不明の号令や用語が氾濫。これは、ミリオタコミュでも見られる傾向だ。
浸水したら馬鹿の一つ覚えで「舷外弁閉め」である。意味分ってるのか?舷外弁というのは、数十数百あるのだ。
魚雷発射の号令など、見ていて恥ずかしくなる。発射管と魚雷の混同や、やたら「テーッ」である。
3 回天搭乗員は大尉だけ?
全員搭乗服に大尉の階級章を付けているが、先任者は中尉らしいし、他は下士官という設定である。
ついでに、3種軍装で短剣を吊らないのも気になる。
服装は細かく指摘せざるを得ないのは、服装については十分な調査をしていたからである。
4 回天の無人発進と二基が完全併走
物理的にありえない。馬鹿馬鹿しさを通り過ぎた、滅茶苦茶である。
5 敵駆逐艦(amick級護衛駆逐艦に見えた)の至近距離に何度も浮上する。
訳がわからん。戦闘中に敵の至近距離に浮上する意味が映画のストーリー上からも理解できない。現実には当然ありえない。
おまけに、2度目の浮上では、総員退艦を命じる。
これまたありえない話で、ほんとにやったら艦長は海軍刑法の定めにより死刑である。日本のみならず、世界中の海軍でも、弾がなくなったからと言って、敵の至近距離において、戦うことなく退艦はありえない。
6 僚艦「伊81潜」が、被害を受けて着底しているが。
潜望鏡の鏡体をレンチで叩いてモールスで「伊77潜」と通信する。この意味も理解できない。この場面はいったい何のために挿入されているのだろう。
製作者は、何を言いたいのかわからんが、これまたありえない行動である。
7 人間関係、艦内編成が不自然
機関長や水雷長(特務士官ということはない)が、キャリアの艦長に対してノンキャリという設定に見える。航海長も同じように扱っているようだ。
機関長は機関学校出のいわばキャリアだし、水雷長や航海長も兵学校出身のはずだ。艦長の後輩だから、敬語を使うなど不自然を通り越して、荒唐無稽の茶番である。
製作者は、海軍も潜水艦も分っていない。
8 発令所と司令塔を混同。
潜望鏡があるところを見ると司令塔らしいが、発令所にあるべき装置がそこにもある。発令所が勤務場所の水雷長もいるし、居るべき通信士は居ない。
今の潜水艦と混同している。たぶん、軍事知識のない海上自衛官に取材した結果だろう。
問題は、これだけではないのだが、きりがないのでこの辺にしておこう。
丁寧に一生懸命作っているようだが、詰めが甘すぎるのと、お粗末な原作や脚本を優先して、専門家の意見を無視した結果、荒唐無稽な作品になっちまった。
残念だ。
|
|
|
|
コメント(73)
>32
了解しました。では、畏れながら質問いたします。よろしく御願いいたします。
>脚本段階で指摘したのだが、わけのわからん号令が多い。中途半端に正確な号令もあるのだが、意味不明の号令や用語が氾濫。
>浸水したら馬鹿の一つ覚えで「舷外弁閉め」である。意味分ってるのか?舷外弁というのは、数十数百あるのだ。
旧軍においては、浸水したときは、どのような手順でどのような号令をかけてゆくこととされていたのでしょうか? また仮に「舷外弁閉め」という号令をかける局面があるとすれば、どのような局面が想定されるでしょうか?
浸水が報告されたら、浸水場所と浸水規模に応じた号令を即時に与えるのが当然でしょう。ただしそれが、実際にどのようになされるのがが、分からない。
浸水を見つけたら、「浸水」と叫んで、持ち場の兵はすぐに止めに入る。これが最初と思いますが、どのように伝える約束になっているのですか?
戦闘中であれば防水扉はあらかじめ閉じられているから、区画された部屋の中で浸水防止に努める。浸水箇所が特定できれば、浸水している管のバルブを兵が勝手に止めることができないことになっているならば、上官の判断で管のバルブを閉めさせる。これでも浸水が止まらないときは、他の可能性を順次つぶしてゆく。状況次第では、各区画の長と艦長の連携で対応する。操艦に与える影響が伴うのであれば、艦長の判断事項となる。これは合っていますか? もしあっている場合は、「○○弁閉め」というような号令の仕方になるのですか?
浸水規模がひどいときは、応援の兵は防水扉を開いてバケツリレーして水を他の部屋に移す(これは無理?)。バランスが悪くなったときは、艦長の号令により、注排水や移水で回復を図るが、それでも間に合わないときは、艦内の物品の移動を急ぐ。また発射管から不要物品を放出して浮力を得る。これらの対処は組織プレーであり、応援にゆくときは自分の持ち場を離れることになるので、艦長の号令でしか動けない。 この手順は合っていますか? もし合っていれば、号令の仕方の例をお教えいただけますか? ...でも、ここまでくると、もう浸水を止めるという対処ではなくなりますね。
浸水の箇所と浸水規模、問題の性質によって、持ち場の臨機応変と、全体をつかさどる艦長の臨機応変が、どのような結果であれ、最終局面を迎えるまで続く。
その局面局面で、それに適した号令(私の業界の用語ではコード)のセットが用意されているのが軍隊というものであろうし、そこに欠落や不整合があったら、致命的。しかし箸の上げ下ろしを伝えるのではなく、状況判断を反復訓練された部下に命令するのだから、これを一言号令すれば、持ち場はどう動けばよいか分かる、という号令もあるのではないか?
了解しました。では、畏れながら質問いたします。よろしく御願いいたします。
>脚本段階で指摘したのだが、わけのわからん号令が多い。中途半端に正確な号令もあるのだが、意味不明の号令や用語が氾濫。
>浸水したら馬鹿の一つ覚えで「舷外弁閉め」である。意味分ってるのか?舷外弁というのは、数十数百あるのだ。
旧軍においては、浸水したときは、どのような手順でどのような号令をかけてゆくこととされていたのでしょうか? また仮に「舷外弁閉め」という号令をかける局面があるとすれば、どのような局面が想定されるでしょうか?
浸水が報告されたら、浸水場所と浸水規模に応じた号令を即時に与えるのが当然でしょう。ただしそれが、実際にどのようになされるのがが、分からない。
浸水を見つけたら、「浸水」と叫んで、持ち場の兵はすぐに止めに入る。これが最初と思いますが、どのように伝える約束になっているのですか?
戦闘中であれば防水扉はあらかじめ閉じられているから、区画された部屋の中で浸水防止に努める。浸水箇所が特定できれば、浸水している管のバルブを兵が勝手に止めることができないことになっているならば、上官の判断で管のバルブを閉めさせる。これでも浸水が止まらないときは、他の可能性を順次つぶしてゆく。状況次第では、各区画の長と艦長の連携で対応する。操艦に与える影響が伴うのであれば、艦長の判断事項となる。これは合っていますか? もしあっている場合は、「○○弁閉め」というような号令の仕方になるのですか?
浸水規模がひどいときは、応援の兵は防水扉を開いてバケツリレーして水を他の部屋に移す(これは無理?)。バランスが悪くなったときは、艦長の号令により、注排水や移水で回復を図るが、それでも間に合わないときは、艦内の物品の移動を急ぐ。また発射管から不要物品を放出して浮力を得る。これらの対処は組織プレーであり、応援にゆくときは自分の持ち場を離れることになるので、艦長の号令でしか動けない。 この手順は合っていますか? もし合っていれば、号令の仕方の例をお教えいただけますか? ...でも、ここまでくると、もう浸水を止めるという対処ではなくなりますね。
浸水の箇所と浸水規模、問題の性質によって、持ち場の臨機応変と、全体をつかさどる艦長の臨機応変が、どのような結果であれ、最終局面を迎えるまで続く。
その局面局面で、それに適した号令(私の業界の用語ではコード)のセットが用意されているのが軍隊というものであろうし、そこに欠落や不整合があったら、致命的。しかし箸の上げ下ろしを伝えるのではなく、状況判断を反復訓練された部下に命令するのだから、これを一言号令すれば、持ち場はどう動けばよいか分かる、という号令もあるのではないか?
>32
まだ映画を観ていませんが、原作とされる小説は読んでいます。また私なりの戦史知識もあるので、そこから所見を述べます。
>1 登場人物、特に艦長が軍人らしくない。
映画を観てから、コメントします。
>3
> ついでに、3種軍装で短剣を吊らないのも気になる。
3種軍装の登場するシーンが、想像できないので、これも映画を観てから。
しかし、軍装の規則についてはもともと分からないので、きちんと理解したい。参考文献があればうれしく思います。
>4 回天の無人発進と二基が完全併走
>物理的にありえない。馬鹿馬鹿しさを通り過ぎた、滅茶苦茶である。
まったく同意します。魚雷のコントロールに手を焼いていたのはどの国も同じ。
>5 敵駆逐艦(amick級護衛駆逐艦に見えた)の至近距離に何度も浮上する。
同意します。そもそもこんなシーンは小説にもなかったと思います。
>6 僚艦「伊81潜」が、被害を受けて着底しているが。
>潜望鏡の鏡体をレンチで叩いてモールスで「伊77潜」と通信する。この意味も理解できない。この場面はいったい何のために挿入されているのだろう。
>製作者は、何を言いたいのかわからんが、これまたありえない行動である。
まったく同意します。このシーンも小説にはなかった。ちなみに伊17は、開戦直後に敵の哨戒圏で僚艦から水中信号をもらい、艦長が、相手をするな、と命令したことを報告していますね。
>7 人間関係、艦内編成が不自然
これも同意します。小説の中でご指摘のような混乱があったかどうかは忘れましたが。
>8 発令所と司令塔を混同。
>潜望鏡があるところを見ると司令塔らしいが、発令所にあるべき装置がそこにもある。発令所が勤務場所の水雷長もいるし、居るべき通信士は居ない。
>今の潜水艦と混同している。たぶん、軍事知識のない海上自衛官に取材した結果だろう。
これはどのような装置を指しておられるのかな? 興味があります。
まだ映画を観ていませんが、原作とされる小説は読んでいます。また私なりの戦史知識もあるので、そこから所見を述べます。
>1 登場人物、特に艦長が軍人らしくない。
映画を観てから、コメントします。
>3
> ついでに、3種軍装で短剣を吊らないのも気になる。
3種軍装の登場するシーンが、想像できないので、これも映画を観てから。
しかし、軍装の規則についてはもともと分からないので、きちんと理解したい。参考文献があればうれしく思います。
>4 回天の無人発進と二基が完全併走
>物理的にありえない。馬鹿馬鹿しさを通り過ぎた、滅茶苦茶である。
まったく同意します。魚雷のコントロールに手を焼いていたのはどの国も同じ。
>5 敵駆逐艦(amick級護衛駆逐艦に見えた)の至近距離に何度も浮上する。
同意します。そもそもこんなシーンは小説にもなかったと思います。
>6 僚艦「伊81潜」が、被害を受けて着底しているが。
>潜望鏡の鏡体をレンチで叩いてモールスで「伊77潜」と通信する。この意味も理解できない。この場面はいったい何のために挿入されているのだろう。
>製作者は、何を言いたいのかわからんが、これまたありえない行動である。
まったく同意します。このシーンも小説にはなかった。ちなみに伊17は、開戦直後に敵の哨戒圏で僚艦から水中信号をもらい、艦長が、相手をするな、と命令したことを報告していますね。
>7 人間関係、艦内編成が不自然
これも同意します。小説の中でご指摘のような混乱があったかどうかは忘れましたが。
>8 発令所と司令塔を混同。
>潜望鏡があるところを見ると司令塔らしいが、発令所にあるべき装置がそこにもある。発令所が勤務場所の水雷長もいるし、居るべき通信士は居ない。
>今の潜水艦と混同している。たぶん、軍事知識のない海上自衛官に取材した結果だろう。
これはどのような装置を指しておられるのかな? 興味があります。
34,35
「しろうと」ではなく、「戦史知識」のある方という前提で
ご質問が、細かいものと抽象的なものが混在しており、回答が難しいので、勝手に答えます。
>「舷外弁閉め」という号令をかける局面があるとすれば、どのような局面が想定されるでしょうか?
私が申し上げているのは、「○○舷外弁閉め」ならわかるが、ただ舷外弁だけでは、数十数百の舷外弁のどれか、わからない、ということです。
>浸水規模がひどいときは、応援の兵は防水扉を開いてバケツリレーして水を他の部屋に移す(これは無理?)。
水中にある潜水艦は、深度に応じた水圧を受けています。たとえば、深度50mなら、平方センチ当たり5キロの圧力です。つまり、1cm程度の穴が空いたら、5キロの圧力で海水が艦内に噴出してくるのです。100mなら10キロ、とても布切れを当てて止まるようなものではなく、その浸水量は大量で、バケツリレーで運べるようなものでもなく、だいいちどこへその水を捨てるのでしょうか?
中学で習った理科程度の知識をもとに考えれば、想像がつくと思います。
その常識から言えば
1 浸水量を減らすには深度を浅くする。
2 各区画を独立して閉鎖し、浸水区画に空気を張って圧力を上げ、艦外との圧力差を少しでも小さくする。これは、深度を浅くしたのと同じ効果がある。
3 電池に海水がかかれば、化学反応で猛毒の塩素が発生する(希硫酸と塩化ナトリウム)から、電池室への浸水を局限する。
戦時中の潜水艦は、艦橋の下に司令塔があったのはご存じでしょう。
日本海軍の場合、司令塔にある装備は、縦舵輪、潜望鏡、方位盤などです。
そのしたの発令所には、潜舵、横舵輪のほか、潜航管制装置があります。潜航指揮は水雷長(先任将校)の責任です。
だから、映画のように、艦長と水雷長が同じ場所にいるのはおかしい。
潜望鏡があるからたぶん司令塔と思われる区画に、潜航管制の諸弁や潜舵や横舵があり、調理員が後からハッチをくぐってカレーを持ってくるなどは、ありえない、ということです。
戦史知識がどの程度のものかはわかりませんが、潜水艦の構造区画程度はご存じでしょうか。
また、海軍士官は常装で短剣を吊る、程度のことも説明が必要でしょうか。
なお私事にわたって恐縮ですが、3カ月ぶりにパースに戻ったばかりで、雑用が多く、あまり丁寧な対応ができませんので、悪しからず。
「しろうと」ではなく、「戦史知識」のある方という前提で
ご質問が、細かいものと抽象的なものが混在しており、回答が難しいので、勝手に答えます。
>「舷外弁閉め」という号令をかける局面があるとすれば、どのような局面が想定されるでしょうか?
私が申し上げているのは、「○○舷外弁閉め」ならわかるが、ただ舷外弁だけでは、数十数百の舷外弁のどれか、わからない、ということです。
>浸水規模がひどいときは、応援の兵は防水扉を開いてバケツリレーして水を他の部屋に移す(これは無理?)。
水中にある潜水艦は、深度に応じた水圧を受けています。たとえば、深度50mなら、平方センチ当たり5キロの圧力です。つまり、1cm程度の穴が空いたら、5キロの圧力で海水が艦内に噴出してくるのです。100mなら10キロ、とても布切れを当てて止まるようなものではなく、その浸水量は大量で、バケツリレーで運べるようなものでもなく、だいいちどこへその水を捨てるのでしょうか?
中学で習った理科程度の知識をもとに考えれば、想像がつくと思います。
その常識から言えば
1 浸水量を減らすには深度を浅くする。
2 各区画を独立して閉鎖し、浸水区画に空気を張って圧力を上げ、艦外との圧力差を少しでも小さくする。これは、深度を浅くしたのと同じ効果がある。
3 電池に海水がかかれば、化学反応で猛毒の塩素が発生する(希硫酸と塩化ナトリウム)から、電池室への浸水を局限する。
戦時中の潜水艦は、艦橋の下に司令塔があったのはご存じでしょう。
日本海軍の場合、司令塔にある装備は、縦舵輪、潜望鏡、方位盤などです。
そのしたの発令所には、潜舵、横舵輪のほか、潜航管制装置があります。潜航指揮は水雷長(先任将校)の責任です。
だから、映画のように、艦長と水雷長が同じ場所にいるのはおかしい。
潜望鏡があるからたぶん司令塔と思われる区画に、潜航管制の諸弁や潜舵や横舵があり、調理員が後からハッチをくぐってカレーを持ってくるなどは、ありえない、ということです。
戦史知識がどの程度のものかはわかりませんが、潜水艦の構造区画程度はご存じでしょうか。
また、海軍士官は常装で短剣を吊る、程度のことも説明が必要でしょうか。
なお私事にわたって恐縮ですが、3カ月ぶりにパースに戻ったばかりで、雑用が多く、あまり丁寧な対応ができませんので、悪しからず。
ふくろうさま
ご説明ありがとうございます。
>「○○舷外弁閉め」ならわかるが、ただ舷外弁だけでは、数十数百の舷外弁のどれか、わからない
なるほど。そういうことですか。どのような部位にどのような名前の舷外弁があるか、私のほうで一度勉強します。それで分からなければまた質問いたします。
>浸水量は大量で、バケツリレーで運べるようなものでもなく、だいいちどこへその水を捨てるのでしょうか?
中学で習った理科程度の知識をもとに考えれば、想像がつくと思います。
これは強烈な勢いですね。了解しました。
#2の「浸水区画に空気を張って圧力を上げ」ですが、深度を浅くできないときに、この手に頼るとしても、人間が耐えられる圧力というのがあるでしょう? 浮力が付くまでの時間稼ぎの一手段ということになるのでしょうか?
司令塔に、発令所にあるべきどんな装置が詰め込まれてしまったか、分かりました。これはちょっとひどいですね。
>潜水艦の構造区画程度
は、承知しているつもりです。各区画内の細かな配置は自信がありませんが。
>海軍士官は常装で短剣を吊る、程度
は、承知しておりますが、問題をご指摘された箇所は、回天搭乗員の項目だったので、回天搭乗員の搭乗時の正装についても何か決まりがあったのかな? と思ったのです。
お忙しい中、ご説明いただき、ありがとうございました。
ご説明ありがとうございます。
>「○○舷外弁閉め」ならわかるが、ただ舷外弁だけでは、数十数百の舷外弁のどれか、わからない
なるほど。そういうことですか。どのような部位にどのような名前の舷外弁があるか、私のほうで一度勉強します。それで分からなければまた質問いたします。
>浸水量は大量で、バケツリレーで運べるようなものでもなく、だいいちどこへその水を捨てるのでしょうか?
中学で習った理科程度の知識をもとに考えれば、想像がつくと思います。
これは強烈な勢いですね。了解しました。
#2の「浸水区画に空気を張って圧力を上げ」ですが、深度を浅くできないときに、この手に頼るとしても、人間が耐えられる圧力というのがあるでしょう? 浮力が付くまでの時間稼ぎの一手段ということになるのでしょうか?
司令塔に、発令所にあるべきどんな装置が詰め込まれてしまったか、分かりました。これはちょっとひどいですね。
>潜水艦の構造区画程度
は、承知しているつもりです。各区画内の細かな配置は自信がありませんが。
>海軍士官は常装で短剣を吊る、程度
は、承知しておりますが、問題をご指摘された箇所は、回天搭乗員の項目だったので、回天搭乗員の搭乗時の正装についても何か決まりがあったのかな? と思ったのです。
お忙しい中、ご説明いただき、ありがとうございました。
>38
軍事問題でも潜水艦でも、ごく普通の常識をフィルターにすれば9割以上が解決します。
浸水区画から他の区画にそこに配置のある乗員を退避させるとどうなるでしょう。
1 退避には一定の時間が必要で、その間浸水には対処しようがない
2 無人の区画ができると、艦の運航や戦闘継続に支障が出る。
3 その代り、加圧圧力には制限がない
4 後でその区画に入る時、加圧した分の圧力を下げねばならないが、無人だと作業に支障が出る可能性がある。
と推定できます。(戦争中の潜水艦の配管や細かい構造は、私も知りません
)
潜水艦の設計はぎりぎりで余裕や無駄はないので、無人区画が生じたら、走ることさえ支障が出るような気がします。
それと、根本的なことですが。
区画加圧を代替、補助手段と考えており(艦外との圧力差を少しでも小さくすると書いたはず)、この手に頼る、と書いた覚えはありません。
加圧すれば解決する、と解釈されたのであれば、私の文章が悪かったのでしょう。訂正します。
軍事問題でも潜水艦でも、ごく普通の常識をフィルターにすれば9割以上が解決します。
浸水区画から他の区画にそこに配置のある乗員を退避させるとどうなるでしょう。
1 退避には一定の時間が必要で、その間浸水には対処しようがない
2 無人の区画ができると、艦の運航や戦闘継続に支障が出る。
3 その代り、加圧圧力には制限がない
4 後でその区画に入る時、加圧した分の圧力を下げねばならないが、無人だと作業に支障が出る可能性がある。
と推定できます。(戦争中の潜水艦の配管や細かい構造は、私も知りません
)
潜水艦の設計はぎりぎりで余裕や無駄はないので、無人区画が生じたら、走ることさえ支障が出るような気がします。
それと、根本的なことですが。
区画加圧を代替、補助手段と考えており(艦外との圧力差を少しでも小さくすると書いたはず)、この手に頼る、と書いた覚えはありません。
加圧すれば解決する、と解釈されたのであれば、私の文章が悪かったのでしょう。訂正します。
今日、ちょっと妙な(?)話を聞きました。
知り合いの女の子(中学生)が「昨日、TVで潜水艦を見た。玉木宏が出てかっこよかった」というのです。詳しく話を聞いてみると「佐藤栄作(!?)が自衛隊の潜水艦に乗ってた。ベッドが狭かった」などと言い出します。「え゛?佐藤栄作って昔の総理大臣で、もう亡くなってるよ」と言うけれど、頑強に「佐藤栄作!」と言い張ります(多分佐藤B作か吉田栄作だと思うのですが…)。
「ほかに覚えていることってない?」と聞いたところ「艦長の部屋が写った」とか「艦長の部下のベッドが出てきた」とか、まるで雲をつかむような話。「あ!部屋の中に水がじゃあじゃあ入って来るのを佐藤栄作が止めてた(たぶん訓練)」とか、もう、話がひっちゃかめっちゃか。けれども、何らかの『真夏のオリオン』のコラボ番組が昨日放映されたようです。「玉木宏が艦長のお墓参りしてた」なんてことも言ってましたから。これは橋本以行氏のことかしら??とにかく相手が子どもで、しかも女の子ですからわけがわからないんです。「ほかに何か覚えてない?」と聞いたところ「あ!トイレがウォシュレット!だった!」とか「玉木宏かっこいい〜〜!」とか、瑣末なことばかり言うので話を聞くのをやめました。
が、昨日、映画とコラボで佐藤B作か吉田栄作かが出演した番組が放映されたようですが、ご存知の方はおられませんか?
知り合いの女の子(中学生)が「昨日、TVで潜水艦を見た。玉木宏が出てかっこよかった」というのです。詳しく話を聞いてみると「佐藤栄作(!?)が自衛隊の潜水艦に乗ってた。ベッドが狭かった」などと言い出します。「え゛?佐藤栄作って昔の総理大臣で、もう亡くなってるよ」と言うけれど、頑強に「佐藤栄作!」と言い張ります(多分佐藤B作か吉田栄作だと思うのですが…)。
「ほかに覚えていることってない?」と聞いたところ「艦長の部屋が写った」とか「艦長の部下のベッドが出てきた」とか、まるで雲をつかむような話。「あ!部屋の中に水がじゃあじゃあ入って来るのを佐藤栄作が止めてた(たぶん訓練)」とか、もう、話がひっちゃかめっちゃか。けれども、何らかの『真夏のオリオン』のコラボ番組が昨日放映されたようです。「玉木宏が艦長のお墓参りしてた」なんてことも言ってましたから。これは橋本以行氏のことかしら??とにかく相手が子どもで、しかも女の子ですからわけがわからないんです。「ほかに何か覚えてない?」と聞いたところ「あ!トイレがウォシュレット!だった!」とか「玉木宏かっこいい〜〜!」とか、瑣末なことばかり言うので話を聞くのをやめました。
が、昨日、映画とコラボで佐藤B作か吉田栄作かが出演した番組が放映されたようですが、ご存知の方はおられませんか?
「亡国のイージス」もありえない設定(物理的に不可能な場面の連続)や、自衛隊の考証もいい加減でした。
こんな映画が許されるのは、自衛隊にも問題があります。
自衛隊には、プライドや矜持がないので、悪意さえなければ、とりあげてくれればありがたい、という態度です。
自衛隊に関する設定、考証については、きっちりというべきなのですが、製作サイドは演出上必要、という印籠を振りかざします。
それを許容する甘さがあるのが問題ですね。
なんてったて、国家機関なのですから。
だから、オリオンでも、回天や昔の潜水艦について、何の知識もないのに、お墨付きを与えてしまう(プロデューサーの言によればですが)のです。
控え目ですが、「丸」8月号には、その辺の指摘をしておきましたので、ご参考まで。
こんな映画が許されるのは、自衛隊にも問題があります。
自衛隊には、プライドや矜持がないので、悪意さえなければ、とりあげてくれればありがたい、という態度です。
自衛隊に関する設定、考証については、きっちりというべきなのですが、製作サイドは演出上必要、という印籠を振りかざします。
それを許容する甘さがあるのが問題ですね。
なんてったて、国家機関なのですから。
だから、オリオンでも、回天や昔の潜水艦について、何の知識もないのに、お墨付きを与えてしまう(プロデューサーの言によればですが)のです。
控え目ですが、「丸」8月号には、その辺の指摘をしておきましたので、ご参考まで。
>gejimさん
多分、此方の番組だと思いますよ!
「真夏のオリオン」公開記念!テレビ史上初!?
日本の主力潜水艦に独占潜入&完全密着SP!
テレビ朝日:6/6(土)25:50〜26:45
ほか、TV朝日系で5・6・7日〜11・12・13日を中心に朝とか深夜に放送していました。
自分も、見ましたが吉田栄作が呉の第一潜郡を訪ね、おやしお型潜水艦の『くろしお』に乗艦して潜水艦の内部を差し障りの無い部分だけ公開していました。あと潜訓の訓練体験もしていました。玉木宏は、橋本船長の遺族や乗員の下を尋ね、その人物像にせまると言った内容の番組でした。
「今、よみがえる戦争の記憶〜映画『真夏のオリオン』」の方は、すいませんが見逃しました!
多分、此方の番組だと思いますよ!
「真夏のオリオン」公開記念!テレビ史上初!?
日本の主力潜水艦に独占潜入&完全密着SP!
テレビ朝日:6/6(土)25:50〜26:45
ほか、TV朝日系で5・6・7日〜11・12・13日を中心に朝とか深夜に放送していました。
自分も、見ましたが吉田栄作が呉の第一潜郡を訪ね、おやしお型潜水艦の『くろしお』に乗艦して潜水艦の内部を差し障りの無い部分だけ公開していました。あと潜訓の訓練体験もしていました。玉木宏は、橋本船長の遺族や乗員の下を尋ね、その人物像にせまると言った内容の番組でした。
「今、よみがえる戦争の記憶〜映画『真夏のオリオン』」の方は、すいませんが見逃しました!
kai さん
参考になりました。
玉木宏が橋本艦長の遺族に話を聞いて、人物像に迫る・・・・
まさに、宣伝以外の何物でもありませんね。
玉木の艦長は、橋本艦長のもっとも遠いところにあり、艦長が生存だったら激怒されたことでしょう。
みかわさんのコメントや、橋本艦長の手記からわかるように、彼はよくいえば硬骨、悪く言えば強引、といった信念と自信の人でした。
部下に敬語を使ったり、無傷の艦を敵前で放棄したり、艦を危険にさらして私情(遭難した僚艦に信号を送る)に負けたり、そんな人物ではありません。
事実を無視して勝手に作ったと言えばいいのに、実像だとか、リアルさだとか宣伝するから、文句をつけたくなるのです。
47 kaiさんのコメントを添削します。
潜水艦コミュとして、間違い指摘ですから、揚げ足取りと取らないでくださいね
橋本船長→橋本艦長
第一潜郡→第一潜水隊群 or 一潜群
参考になりました。
玉木宏が橋本艦長の遺族に話を聞いて、人物像に迫る・・・・
まさに、宣伝以外の何物でもありませんね。
玉木の艦長は、橋本艦長のもっとも遠いところにあり、艦長が生存だったら激怒されたことでしょう。
みかわさんのコメントや、橋本艦長の手記からわかるように、彼はよくいえば硬骨、悪く言えば強引、といった信念と自信の人でした。
部下に敬語を使ったり、無傷の艦を敵前で放棄したり、艦を危険にさらして私情(遭難した僚艦に信号を送る)に負けたり、そんな人物ではありません。
事実を無視して勝手に作ったと言えばいいのに、実像だとか、リアルさだとか宣伝するから、文句をつけたくなるのです。
47 kaiさんのコメントを添削します。
潜水艦コミュとして、間違い指摘ですから、揚げ足取りと取らないでくださいね
橋本船長→橋本艦長
第一潜郡→第一潜水隊群 or 一潜群
みかわさま
潜乗員という言葉は聞いたことがありません。
マイミクさんの日記に、オリオンへの疑問が載っており、それへの回答を転記します。
『14本の魚雷か・・でも戦争末期の日本の物資ではそれを調達するのも大変だっただろうな、食糧を保存するのはどうしてたんだろ、結構食材いっぱいあるんだな』
魚雷は、出来るだけ積んで出ます。映画のモデルの「伊58潜」は、19本積めます。
戦争末期でも、戦前からの魚雷の備蓄もあり、量は十分ありました。
そもそも、回天が、潤沢な魚雷を改造したものだったことからも、それがわかります。
食材は、腐るものと腐らないものがあります。
米、缶詰、ジャガイモ、玉ねぎなどは長期保存がききます。
生鮮食料品である肉、魚、青物は、早めに消費するようです。肉魚を保存する、小さな冷蔵庫はあったはずです。(要確認)
冷房機があったのですから、冷蔵庫は作れたはずです。
『人間関係、妙になれなれしくはないだろうか、ちょっと気持ち悪い位だなあ』
『もしかして潜水艦の中はこういう空気だったのだろうか・・やっぱり緩いよな』
これは、まったく考証が変です。
映画では、水雷長や機関長がノンキャリのベテラン、艦長がキャリア風に描かれています。
しかし、水雷長は、艦長と同じ兵学校出だし、機関長も機関学校出身のキャリアですから、艦長が遠慮する相手ではありません。
第一、旧軍では指揮官が部下に敬語を使うことは考えられません。
この点については、伊呂波会(海軍潜水艦乗りの会)でも、問題視しています。
家族的であることと、なれなれしいこととは別で、海軍を知らない製作者が、今の感覚でおかしな人間関係を構築してしまいました。
機関長が、艦長に「あなた」という二人称代名詞を使うこともあり得ません。
お祖父さんは、ノンキャリ(といえど、戦前の日本社会では十分エリート)でしたが、艦長に「あなたの部下でよかった」などと、暴言を吐くことはなかったはずですし、艦長もお爺さんに敬語など使いはしません。
続く・・
潜乗員という言葉は聞いたことがありません。
マイミクさんの日記に、オリオンへの疑問が載っており、それへの回答を転記します。
『14本の魚雷か・・でも戦争末期の日本の物資ではそれを調達するのも大変だっただろうな、食糧を保存するのはどうしてたんだろ、結構食材いっぱいあるんだな』
魚雷は、出来るだけ積んで出ます。映画のモデルの「伊58潜」は、19本積めます。
戦争末期でも、戦前からの魚雷の備蓄もあり、量は十分ありました。
そもそも、回天が、潤沢な魚雷を改造したものだったことからも、それがわかります。
食材は、腐るものと腐らないものがあります。
米、缶詰、ジャガイモ、玉ねぎなどは長期保存がききます。
生鮮食料品である肉、魚、青物は、早めに消費するようです。肉魚を保存する、小さな冷蔵庫はあったはずです。(要確認)
冷房機があったのですから、冷蔵庫は作れたはずです。
『人間関係、妙になれなれしくはないだろうか、ちょっと気持ち悪い位だなあ』
『もしかして潜水艦の中はこういう空気だったのだろうか・・やっぱり緩いよな』
これは、まったく考証が変です。
映画では、水雷長や機関長がノンキャリのベテラン、艦長がキャリア風に描かれています。
しかし、水雷長は、艦長と同じ兵学校出だし、機関長も機関学校出身のキャリアですから、艦長が遠慮する相手ではありません。
第一、旧軍では指揮官が部下に敬語を使うことは考えられません。
この点については、伊呂波会(海軍潜水艦乗りの会)でも、問題視しています。
家族的であることと、なれなれしいこととは別で、海軍を知らない製作者が、今の感覚でおかしな人間関係を構築してしまいました。
機関長が、艦長に「あなた」という二人称代名詞を使うこともあり得ません。
お祖父さんは、ノンキャリ(といえど、戦前の日本社会では十分エリート)でしたが、艦長に「あなたの部下でよかった」などと、暴言を吐くことはなかったはずですし、艦長もお爺さんに敬語など使いはしません。
続く・・
『潜水艦は自由に行動できるっていうのは当時もそうだったのだろうか』
日本海軍の潜水艦は、不自由な行動を強いられたため、作戦に失敗しています。
「古今の戦争史において、主要な武器がその真の潜在威力を少しも理解把握されずに使用されたという稀有の例を求めるとすれば、それはまさに第二次大戦における日本潜水艦の場合である」(ニミッツ)
詳しくは、「本当の潜水艦の戦い方」http://www.amazon.co.jp/%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AE%E6%BD%9C%E6%B0%B4%E8%89%A6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E6%96%B9%E2%80%95%E5%84%AA%E3%82%8C%E3%81%9F%E7%94%A8%E5%85%B5%E8%80%85%E3%81%8C%E6%93%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E7%95%B0%E3%81%AA%E8%89%A6%E7%A8%AE-%E5%85%89%E4%BA%BA%E7%A4%BENF%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%B8%AD%E6%9D%91-%E7%A7%80%E6%A8%B9/dp/4769824939/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242125581&sr=1-1
に書いてありますが、自由に行動させるべき潜水艦を、不自由に使ったのが、日本海軍の失敗でした。
『モールス信号で海の中で通信できるものなのか』
強力な信号を出す装置があれば、一定の距離(数キロ以下)で可能ですが、映画のようにレンチで艦体を叩くような方法では、至近距離です。
映画の状況はあり得ません。
第一、あの海域は深いので、被害を受けた潜水艦が海底に圧壊しないで存在することは、ありえません。
『モールス信号や器具を落とした音だけで察知されるのに大声で艦内で命令を出しているけれど、そういう声は大丈夫なのだろうか。とても疑問だ。これは絶対調べなければならない』
潜水艦の外へ伝わる音は、艦体を振動させるような音です。
だから、話声やハーモニカは外へは伝わりません。
潜水艦にダイバーが張り付いて、耳をくっつけたらわかりませんけど・・・・
『当時の潜水艦もこんなに潜りっぱなしだったのだろうか』
電池が満タンで、換気が終わっていれば1日から2日はもちます。
『回天から酸素供給ってできるのか・・・ま・・確かに酸素魚雷だったんだろうけど』
純酸素を直接放出するのは、極めて危険なことです。
海上自衛隊の潜水艦にも酸素ボンベはありますが、必ず水をくぐらせるようにしてあります。
火の気に触れると引火、爆発の危険があるからです。
また、酸素だけを放出しても、二酸化炭素を吸収しないと、人間の生理には悪影響があります。
酸素の供給と二酸化炭素の吸収の両方が必要です。
『回天って水深が深くても耐えられるのか・・・』
潜水艦同様と考えていいでしょう。
『敵艦の目の前に浮上って・・・・万一攻撃されたらどうするのだろうか艦長として甘くない?』
『総員退艦って・・・敵の前で? 当時あり得るのだろうか』
あり得ません。
海軍刑法の定めでは、艦長は死刑です。
現実にも、浮上を強いられた潜水艦では、拳銃まで出して交戦を試みています。
日本海軍の潜水艦は、不自由な行動を強いられたため、作戦に失敗しています。
「古今の戦争史において、主要な武器がその真の潜在威力を少しも理解把握されずに使用されたという稀有の例を求めるとすれば、それはまさに第二次大戦における日本潜水艦の場合である」(ニミッツ)
詳しくは、「本当の潜水艦の戦い方」http://www.amazon.co.jp/%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AE%E6%BD%9C%E6%B0%B4%E8%89%A6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E6%96%B9%E2%80%95%E5%84%AA%E3%82%8C%E3%81%9F%E7%94%A8%E5%85%B5%E8%80%85%E3%81%8C%E6%93%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E7%95%B0%E3%81%AA%E8%89%A6%E7%A8%AE-%E5%85%89%E4%BA%BA%E7%A4%BENF%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%B8%AD%E6%9D%91-%E7%A7%80%E6%A8%B9/dp/4769824939/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242125581&sr=1-1
に書いてありますが、自由に行動させるべき潜水艦を、不自由に使ったのが、日本海軍の失敗でした。
『モールス信号で海の中で通信できるものなのか』
強力な信号を出す装置があれば、一定の距離(数キロ以下)で可能ですが、映画のようにレンチで艦体を叩くような方法では、至近距離です。
映画の状況はあり得ません。
第一、あの海域は深いので、被害を受けた潜水艦が海底に圧壊しないで存在することは、ありえません。
『モールス信号や器具を落とした音だけで察知されるのに大声で艦内で命令を出しているけれど、そういう声は大丈夫なのだろうか。とても疑問だ。これは絶対調べなければならない』
潜水艦の外へ伝わる音は、艦体を振動させるような音です。
だから、話声やハーモニカは外へは伝わりません。
潜水艦にダイバーが張り付いて、耳をくっつけたらわかりませんけど・・・・
『当時の潜水艦もこんなに潜りっぱなしだったのだろうか』
電池が満タンで、換気が終わっていれば1日から2日はもちます。
『回天から酸素供給ってできるのか・・・ま・・確かに酸素魚雷だったんだろうけど』
純酸素を直接放出するのは、極めて危険なことです。
海上自衛隊の潜水艦にも酸素ボンベはありますが、必ず水をくぐらせるようにしてあります。
火の気に触れると引火、爆発の危険があるからです。
また、酸素だけを放出しても、二酸化炭素を吸収しないと、人間の生理には悪影響があります。
酸素の供給と二酸化炭素の吸収の両方が必要です。
『回天って水深が深くても耐えられるのか・・・』
潜水艦同様と考えていいでしょう。
『敵艦の目の前に浮上って・・・・万一攻撃されたらどうするのだろうか艦長として甘くない?』
『総員退艦って・・・敵の前で? 当時あり得るのだろうか』
あり得ません。
海軍刑法の定めでは、艦長は死刑です。
現実にも、浮上を強いられた潜水艦では、拳銃まで出して交戦を試みています。
>敵軍の爆雷の爆発震度ってあんなにすぐ自由自在に変更できるものなのでしょうか。
爆雷の調停深度は、投下直前に切ります。信管を工具で回してセットするのですが、投下直前艦長から「調停深度○○」と来まして、「調停よし」と報告を受け、「投下」と相成ります。
>あれほどの爆雷攻撃を受けても回天の弾頭は誘爆しないのでしょうか。
魚雷の弾頭の炸薬は、火をつけても爆発しないほど安定している性質の火薬です。砲弾や爆弾も同じ。
どうして爆発するかというと、信管という発火装置があるためです。信管という小型の爆薬が爆発することで、炸薬を爆発させるのが、武器というものです。
>大戦末期で真剣そのものだったはずですし、ちょっと祖父ちゃんが命をかけた
あの戦いの最中の事を考えると軽すぎるノリのように感じました。
まったくです。戦没者に対する冒涜だと感じます。
伊呂波会でも、怒ってました。
製作側は勝手な宣伝をして、旧海軍の人からも絶賛されている、と言っていますが、それは嘘です。
>大戦が終了後残った潜水艦はすべて破壊されてしまったのでしょうか。
それとも米国に接収されてじつは現存しているのでしょうか。
潜水艦に限らず、一部の艦や航空機は米本土へ回航して調査され、その後破棄されています。戦艦「長門」はビキニの原爆実験に使用。
その他の残存艦は、九州五島沖で、爆破処分されました。
爆雷の調停深度は、投下直前に切ります。信管を工具で回してセットするのですが、投下直前艦長から「調停深度○○」と来まして、「調停よし」と報告を受け、「投下」と相成ります。
>あれほどの爆雷攻撃を受けても回天の弾頭は誘爆しないのでしょうか。
魚雷の弾頭の炸薬は、火をつけても爆発しないほど安定している性質の火薬です。砲弾や爆弾も同じ。
どうして爆発するかというと、信管という発火装置があるためです。信管という小型の爆薬が爆発することで、炸薬を爆発させるのが、武器というものです。
>大戦末期で真剣そのものだったはずですし、ちょっと祖父ちゃんが命をかけた
あの戦いの最中の事を考えると軽すぎるノリのように感じました。
まったくです。戦没者に対する冒涜だと感じます。
伊呂波会でも、怒ってました。
製作側は勝手な宣伝をして、旧海軍の人からも絶賛されている、と言っていますが、それは嘘です。
>大戦が終了後残った潜水艦はすべて破壊されてしまったのでしょうか。
それとも米国に接収されてじつは現存しているのでしょうか。
潜水艦に限らず、一部の艦や航空機は米本土へ回航して調査され、その後破棄されています。戦艦「長門」はビキニの原爆実験に使用。
その他の残存艦は、九州五島沖で、爆破処分されました。
レンチを落とせば、艦体を振動させるので、ある程度音は聞こえます。
(潜水艦艦長だった今井梅一氏が、映画のとおりだったと発言したとのコメントあり)
映画に関して、どのような発言をされたか、直接伺わねばわかりませんが、伊呂波会で怒っているのに、伊呂波会に評価されている、と言い張っているところから、今井さんの発言も疑った方がいいでしょう。
機関室は、よくわかりませんが、あの辺の考証は他の点から想像して、たぶん正確でしょう。ただし、数十名は居た機関科員の姿が見えず、機関長ひとりで頑張っているのは異常です。
機関長は機関運転指揮をするのが仕事で、自ら機械をいじることはありません。
そういった実務は特務士官や下士官兵の仕事です。
回天搭乗員が手伝わねばならない、という無理な設定のため、機関科員を消しているのは、悪質だと思います。
(潜水艦艦長だった今井梅一氏が、映画のとおりだったと発言したとのコメントあり)
映画に関して、どのような発言をされたか、直接伺わねばわかりませんが、伊呂波会で怒っているのに、伊呂波会に評価されている、と言い張っているところから、今井さんの発言も疑った方がいいでしょう。
機関室は、よくわかりませんが、あの辺の考証は他の点から想像して、たぶん正確でしょう。ただし、数十名は居た機関科員の姿が見えず、機関長ひとりで頑張っているのは異常です。
機関長は機関運転指揮をするのが仕事で、自ら機械をいじることはありません。
そういった実務は特務士官や下士官兵の仕事です。
回天搭乗員が手伝わねばならない、という無理な設定のため、機関科員を消しているのは、悪質だと思います。
ふくろうさま
たくさんのご説明をありがとうございます。気になる点もあるのでコメントします。
53
>食材は、腐るものと腐らないものがあります。
>米、缶詰、ジャガイモ、玉ねぎなどは長期保存がききます。
>生鮮食料品である肉、魚、青物は、早めに消費するようです。肉魚を保存する、小さな冷蔵庫はあったはずです。(要確認)
>冷房機があったのですから、冷蔵庫は作れたはずです。
この件ですが、疑問です。大きな水上艦には大型冷凍庫があったと当時の主計兵が述べています(高橋孟、『海軍めしたき物語』、新潮文庫)が、潜水艦については、当時の潜水学校付き軍医官の藤井良知少佐が、次のように述べています。
「気温は電気室は40度を突破して居住区も体温以上の37,8度になるのは日常のことである。湿度は100%をこえて水滴は衣類をしっとりとぬらす。兵器優先から電気冷蔵庫の容積はあまりに小さく,生鮮食料品は出港後数日で消え去り,一週間たてば芽を長くのばしたじゃがいもとたまねぎさえも100人の乗員の食卓から消え去るのである。あとはすべて缶詰と乾燥食料の連続であり,ビタミンB1とCの錠剤が脚気と壊血病から乗員を守るが,これも作戦終了の頃にはかびによるしみがしみこんでいるのである。」
(「亡き戦友を想う」, 昭和十五年桜医会編集委員会(編)『わだつみに戦う』, 1978, pp.131-135.)
たくさんのご説明をありがとうございます。気になる点もあるのでコメントします。
53
>食材は、腐るものと腐らないものがあります。
>米、缶詰、ジャガイモ、玉ねぎなどは長期保存がききます。
>生鮮食料品である肉、魚、青物は、早めに消費するようです。肉魚を保存する、小さな冷蔵庫はあったはずです。(要確認)
>冷房機があったのですから、冷蔵庫は作れたはずです。
この件ですが、疑問です。大きな水上艦には大型冷凍庫があったと当時の主計兵が述べています(高橋孟、『海軍めしたき物語』、新潮文庫)が、潜水艦については、当時の潜水学校付き軍医官の藤井良知少佐が、次のように述べています。
「気温は電気室は40度を突破して居住区も体温以上の37,8度になるのは日常のことである。湿度は100%をこえて水滴は衣類をしっとりとぬらす。兵器優先から電気冷蔵庫の容積はあまりに小さく,生鮮食料品は出港後数日で消え去り,一週間たてば芽を長くのばしたじゃがいもとたまねぎさえも100人の乗員の食卓から消え去るのである。あとはすべて缶詰と乾燥食料の連続であり,ビタミンB1とCの錠剤が脚気と壊血病から乗員を守るが,これも作戦終了の頃にはかびによるしみがしみこんでいるのである。」
(「亡き戦友を想う」, 昭和十五年桜医会編集委員会(編)『わだつみに戦う』, 1978, pp.131-135.)
まとめて回答します。
冷蔵庫の存在については、自信がありませんので、(要確認)としております。
ただ、冷房機の冷媒を冷蔵庫にも使えるのでは、と推理しておりましたが、ご提示の資料からすると、なかったようですね。
潜水艦に主計長(士官)はおりません。
潜水艦の士官は、艦長、水雷長、航海長、砲術長兼通信長、機関長、機関長付(いわゆる機関士)、状況により軍医長です。
烹炊長というのは、調理員の長である下士官のことでしょう。海軍の呼び方は知りませんが、海上自衛隊では調理員長、といいます。
甲標的の安全潜航深度100mは確認しましたが、回天については、想像ですから根拠があれば80mで正しいでしょう。
潜水艦の外に搭載する兵器は、できるだけ潜水艦と同じ安全潜航深度にするよう設計するという、前提があるので、先入観で適当に回答してしまいました。
艦内案内は、他のひどすぎる考証からみれば、小さなウソでしょうね。
前も書きましたが、旧海軍の人たちは、反戦映画でなく、自分たちが肯定的に取り上げられたことに満足して、好意的なコメントをされる紳士が多いので、映画会社が都合よく脚色している恐れは十分にあります。
前に作られた「出口のない海」では、回天会の会長が譲れない点を抗議したのに、無視されて怒っておられました。
私の2冊目で特殊潜航艇がテーマなのに、あえて回天にまで範囲を拡大したのは、その点を公表したかったからでした。
純粋に国難に殉じようとしていた回天搭乗員たちの気持ちを、戦後のねじれた見方で表現していたからです。
冷蔵庫の存在については、自信がありませんので、(要確認)としております。
ただ、冷房機の冷媒を冷蔵庫にも使えるのでは、と推理しておりましたが、ご提示の資料からすると、なかったようですね。
潜水艦に主計長(士官)はおりません。
潜水艦の士官は、艦長、水雷長、航海長、砲術長兼通信長、機関長、機関長付(いわゆる機関士)、状況により軍医長です。
烹炊長というのは、調理員の長である下士官のことでしょう。海軍の呼び方は知りませんが、海上自衛隊では調理員長、といいます。
甲標的の安全潜航深度100mは確認しましたが、回天については、想像ですから根拠があれば80mで正しいでしょう。
潜水艦の外に搭載する兵器は、できるだけ潜水艦と同じ安全潜航深度にするよう設計するという、前提があるので、先入観で適当に回答してしまいました。
艦内案内は、他のひどすぎる考証からみれば、小さなウソでしょうね。
前も書きましたが、旧海軍の人たちは、反戦映画でなく、自分たちが肯定的に取り上げられたことに満足して、好意的なコメントをされる紳士が多いので、映画会社が都合よく脚色している恐れは十分にあります。
前に作られた「出口のない海」では、回天会の会長が譲れない点を抗議したのに、無視されて怒っておられました。
私の2冊目で特殊潜航艇がテーマなのに、あえて回天にまで範囲を拡大したのは、その点を公表したかったからでした。
純粋に国難に殉じようとしていた回天搭乗員たちの気持ちを、戦後のねじれた見方で表現していたからです。
ふくろうさま 丁寧なご回答ありがとうございます。
63
>潜水艦に主計長(士官)はおりません。
>潜水艦の士官は、艦長、水雷長、航海長、砲術長兼通信長、機関長、機関長付(いわゆる機関士)、状況により軍医長です。
>烹炊長というのは、調理員の長である下士官のことでしょう。海軍の呼び方は知りませんが、海上自衛隊では調理員長、といいます。
はい。士官としての主計長はおりません。が、潜水艦内の通称として、「主計長」、と呼んでいたようです。
「主計長」については、そのように通称で呼ばれていた、と回想の中で解説していた文献があったので、調べてのちほどご報告します。でも他の潜水艦では烹炊長と呼んでいた例があったのかなあ。
また、少なくとも伊56や伊58では、軍医長の唯一の部下である衛生兵曹は、通称「看護長」と呼ばれていた。
なお伊58では、潜航するときに最後にハッチを締めるのは、「信号長」の役割だった、とのことです。それから暗号長、聴音長、電機長、連管長。みなさん潜水艦内では下士官兵だったので、これらも通称でしょう。
63
>冷蔵庫の存在については、自信がありませんので、(要確認)としております。
>ただ、冷房機の冷媒を冷蔵庫にも使えるのでは、と推理しておりましたが、ご提示の資料からすると、なかったようですね。
上の文献からは、小さな冷蔵庫があったことは事実でしょう。ただどの程度の大きさと能力だったかは分かりませんが。
斉藤寛、『鉄の棺』であったか、橋本以行、『伊58潜帰投せり』だったか、回天搭乗員のために、アイスクリームを作るエピソードがあります。アイスクリームを作る電力を確保するために、数時間、艦内の冷房を止めて、乗員全員が汗びっしょりで耐える、というくだりがあります。これからすると、たいした能力はなかったものと思われます。
>冷蔵庫の存在については、自信がありませんので、(要確認)としております。
>ただ、冷房機の冷媒を冷蔵庫にも使えるのでは、と推理しておりましたが、ご提示の資料からすると、なかったようですね。
上の文献からは、小さな冷蔵庫があったことは事実でしょう。ただどの程度の大きさと能力だったかは分かりませんが。
斉藤寛、『鉄の棺』であったか、橋本以行、『伊58潜帰投せり』だったか、回天搭乗員のために、アイスクリームを作るエピソードがあります。アイスクリームを作る電力を確保するために、数時間、艦内の冷房を止めて、乗員全員が汗びっしょりで耐える、というくだりがあります。これからすると、たいした能力はなかったものと思われます。
54
>また、酸素だけを放出しても、二酸化炭素を吸収しないと、人間の生理には悪影響があります。
>酸素の供給と二酸化炭素の吸収の両方が必要です。
おっしゃるとおりです。
日本海軍は、二酸化炭素吸収装置の開発で、相当苦労しました。
その前段として、潜水学校では,普通科練習生中2名の有志による「高CO2,低O2の致死限界」に関する実験研究というのを行っていますね。
これによれば、「O2が20%のときはCO2は6.75%が限界」という結果とともに、
「潜水艦としての戦力を保持しうる限界値は,CO2が3%以下かつO2が17%以上」
と結論づけています。
被制圧下の長時間潜航で、どんどん空気汚染が進むと、しまいには身体精神ともに異常をきたす様子は、斉藤寛、『鉄の棺』に詳しく書かれていますね。
>また、酸素だけを放出しても、二酸化炭素を吸収しないと、人間の生理には悪影響があります。
>酸素の供給と二酸化炭素の吸収の両方が必要です。
おっしゃるとおりです。
日本海軍は、二酸化炭素吸収装置の開発で、相当苦労しました。
その前段として、潜水学校では,普通科練習生中2名の有志による「高CO2,低O2の致死限界」に関する実験研究というのを行っていますね。
これによれば、「O2が20%のときはCO2は6.75%が限界」という結果とともに、
「潜水艦としての戦力を保持しうる限界値は,CO2が3%以下かつO2が17%以上」
と結論づけています。
被制圧下の長時間潜航で、どんどん空気汚染が進むと、しまいには身体精神ともに異常をきたす様子は、斉藤寛、『鉄の棺』に詳しく書かれていますね。
みかわさまはご存知でしょうが、他のメンバーへの説明の必要があると思いますから、少しくどく書いておきます。
>また、少なくとも伊56や伊58では、軍医長の唯一の部下である衛生兵曹は、通称「看護長」と呼ばれていた。
艦ごとによび方が違うことはありません。
看護長で統一されています。
海上自衛隊の場合、正式には衛生員長(一人しかいませんけどね)ですが、看護長と通称されています。
>なお伊58では、潜航するときに最後にハッチを締めるのは、「信号長」の役割だった、とのことです。それから暗号長、聴音長、電機長、連管長。みなさん潜水艦内では下士官兵だったので、これらも通称でしょう。
長という言い方は、士官の場合科長で、下士官の場合は、特技員長、という意味で使います。
水雷長→水雷科の長
連管長→魚雷員の長 魚雷長と言わず、潜水艦では連管長と言う。水雷科の所属であり、水雷長の部下の下士官。普通上等兵曹
航海長→航海科の長
信号長→航海員の長。航法、見張り、信号担当の下士官。航海長の部下。
機関長→機関科の長
電機長→電気員の長。電池、発電機、電動機、艦内の電機関係機器の担当。機関長の部下の下士官。
通信長→通信科はないが、通信担当士官(中少尉)
暗号長→通信長の下で、電報の暗号、翻訳をする暗号員の長。
といった関係です。
>また、少なくとも伊56や伊58では、軍医長の唯一の部下である衛生兵曹は、通称「看護長」と呼ばれていた。
艦ごとによび方が違うことはありません。
看護長で統一されています。
海上自衛隊の場合、正式には衛生員長(一人しかいませんけどね)ですが、看護長と通称されています。
>なお伊58では、潜航するときに最後にハッチを締めるのは、「信号長」の役割だった、とのことです。それから暗号長、聴音長、電機長、連管長。みなさん潜水艦内では下士官兵だったので、これらも通称でしょう。
長という言い方は、士官の場合科長で、下士官の場合は、特技員長、という意味で使います。
水雷長→水雷科の長
連管長→魚雷員の長 魚雷長と言わず、潜水艦では連管長と言う。水雷科の所属であり、水雷長の部下の下士官。普通上等兵曹
航海長→航海科の長
信号長→航海員の長。航法、見張り、信号担当の下士官。航海長の部下。
機関長→機関科の長
電機長→電気員の長。電池、発電機、電動機、艦内の電機関係機器の担当。機関長の部下の下士官。
通信長→通信科はないが、通信担当士官(中少尉)
暗号長→通信長の下で、電報の暗号、翻訳をする暗号員の長。
といった関係です。
大日本帝国海軍潜水艦乗務記録 インド洋 #1〜7
あの有名な映画「轟沈」です。
http://www.youtube.com/watch?v=C0LsAMLkT7M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qpMw_jhFfcM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Xp5YiQGWNOM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZQqVhgBS0ag&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P39lg8ERBpY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ww3zgeIT6Wo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kA07thaVAmk&feature=related
「オリオン」と比較すると、一発で事実がわかるでしょう。
あの有名な映画「轟沈」です。
http://www.youtube.com/watch?v=C0LsAMLkT7M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qpMw_jhFfcM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Xp5YiQGWNOM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZQqVhgBS0ag&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P39lg8ERBpY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ww3zgeIT6Wo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kA07thaVAmk&feature=related
「オリオン」と比較すると、一発で事実がわかるでしょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
本当の潜水艦のコミュ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
本当の潜水艦のコミュのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75479人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6433人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208284人