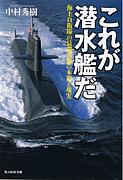テレビ(ディスカバリーチャンネル)で212型の取材番組やってました。
感動したのは、
1 乗員の少なさ
2 艦長が大尉
3 艦型
です。
1
水中排水量1830トンなのに、乗員27名です。海上自衛隊が多すぎるのですが、哨戒直は8名程度ということです。詳細は不明ですが、私の想像では。
哨戒長 潜航管制1 ソーナー1〜2 操舵1 航海1 発射管1 機関当直1〜2でしょうか。
このほか調理員や通信、指揮装置の配置が必要でしょうが、十分な人数が捻出できません。
哨戒直が2直なのでしょうか。それなら、1直13名まで配置できるので、無理なく想像できますが。
う〜ん、わからん。だれか知りませんか・
2 映像では艦長の階級章は2本半でした。一見少佐に見えますが、ドイツは中尉が太線二本、少佐は太線三本です。大尉はその間で二本半、日米なら少佐の階級章なので、知らないと混乱します。ロシアも独流で中尉以上は他国よりひとつ上の階級に見えます。
ともかく、1800トンの潜水艦艦長が大尉です。日本なら中佐ですから、能力の高さがしのばれます。
日本は潜水艦に限らず、自衛隊のポストと階級が不釣合いで、私は階級インフレと呼んでいます。外国や旧軍に比較すれば、1〜3階級インフレです。
3 材料に非磁性物質を使用しているとの説明でした。しかし、耐圧殻は鋼材以外考えられないので、非耐圧の部分に非磁性の材料を使っているのでしょうか。
なによりも、艦橋セイル基部が幅一杯でかなり傾斜していることや、船体もステルス性(対アクティブ)に優れた設計だと見えます。
日本の「おやしお」型みたいな中途半端なものではなく、曲線と傾斜面ばかりです。セイルがはみ出していて前後部全通の甲板は無いので、おそらくセイルの中を通るのでしょう。
無論、X舵です。運動性能がよく、水深20mの海域で行動できるとの解説でした。特殊部隊は魚雷発射管から、発進するそうです。水深20mというのは、海図を見ればわかりますが、陸岸のすぐそこです。発進した特殊部隊が何キロも泳ぐ必要はありません。
東京湾や瀬戸内海に軽く進入できるということです。
排水量から言えば、日本のL型(おおしお以降)と同じですが太めなので、水上ではずいぶん小さく見えました。
発射管は6門(533mmは日本と同じ)ですが、3門づつ二段なので、発射管室がコンパクトです。縦3段より横2段の方が、レイアウトが楽なのかもしれません。
燃料電池の潜水艦として有名ですが、それ以上に先進性を感じさせる艦です。
発令所も洗練されていたし、潜望鏡も日本のよりはスマートな印象です。
写真はここにあります。
http://
「そうりゅう」より感動しました。
感動したのは、
1 乗員の少なさ
2 艦長が大尉
3 艦型
です。
1
水中排水量1830トンなのに、乗員27名です。海上自衛隊が多すぎるのですが、哨戒直は8名程度ということです。詳細は不明ですが、私の想像では。
哨戒長 潜航管制1 ソーナー1〜2 操舵1 航海1 発射管1 機関当直1〜2でしょうか。
このほか調理員や通信、指揮装置の配置が必要でしょうが、十分な人数が捻出できません。
哨戒直が2直なのでしょうか。それなら、1直13名まで配置できるので、無理なく想像できますが。
う〜ん、わからん。だれか知りませんか・
2 映像では艦長の階級章は2本半でした。一見少佐に見えますが、ドイツは中尉が太線二本、少佐は太線三本です。大尉はその間で二本半、日米なら少佐の階級章なので、知らないと混乱します。ロシアも独流で中尉以上は他国よりひとつ上の階級に見えます。
ともかく、1800トンの潜水艦艦長が大尉です。日本なら中佐ですから、能力の高さがしのばれます。
日本は潜水艦に限らず、自衛隊のポストと階級が不釣合いで、私は階級インフレと呼んでいます。外国や旧軍に比較すれば、1〜3階級インフレです。
3 材料に非磁性物質を使用しているとの説明でした。しかし、耐圧殻は鋼材以外考えられないので、非耐圧の部分に非磁性の材料を使っているのでしょうか。
なによりも、艦橋セイル基部が幅一杯でかなり傾斜していることや、船体もステルス性(対アクティブ)に優れた設計だと見えます。
日本の「おやしお」型みたいな中途半端なものではなく、曲線と傾斜面ばかりです。セイルがはみ出していて前後部全通の甲板は無いので、おそらくセイルの中を通るのでしょう。
無論、X舵です。運動性能がよく、水深20mの海域で行動できるとの解説でした。特殊部隊は魚雷発射管から、発進するそうです。水深20mというのは、海図を見ればわかりますが、陸岸のすぐそこです。発進した特殊部隊が何キロも泳ぐ必要はありません。
東京湾や瀬戸内海に軽く進入できるということです。
排水量から言えば、日本のL型(おおしお以降)と同じですが太めなので、水上ではずいぶん小さく見えました。
発射管は6門(533mmは日本と同じ)ですが、3門づつ二段なので、発射管室がコンパクトです。縦3段より横2段の方が、レイアウトが楽なのかもしれません。
燃料電池の潜水艦として有名ですが、それ以上に先進性を感じさせる艦です。
発令所も洗練されていたし、潜望鏡も日本のよりはスマートな印象です。
写真はここにあります。
http://
「そうりゅう」より感動しました。
|
|
|
|
コメント(26)
>風林火山さん。
私も何でX舵が十字舵より運動性がいいのか、最初ピンと来ませんでした。が、ちょっと考えるとこういうことだと思います。
従来の十字舵ならば、左右の運動は縦の2枚、上下は横の2枚と潜舵。が、X舵ならば2枚の舵(組み合わせはいろいろあるとしても)だけを使うとどうしても運動がねじれてしまう(回転する)。ですからX舵は行きたい方向へ全部の舵が同じように動くんだと思います。4枚すべてが同じ向きになるのですからより機敏な動きになるのでしょう。
(違っていたらどなたかツッコミをお願いします)
独212型、良く見たら茂木大輔のHP(「日豪潜水艦博物館比較」の2に書き込みしました)にも画像がありますね。日付を見ると2004年撮影になってますから結構以前から見らるようになっていたようです。乗組員の少なさですが、憶測で言うと、調理員などは3直の中に含まなくてもいい(もともと少ししかいないのならまとめて作ってチンしてもらう)し、通信も兼務できるのかもしれません。昔の旅客機なんか機長・コパイ・FE(航空機関士)・通信士・航法士と5名も載ってたのに今や2名です。
艦長が大尉とのこと。が、戦争中日本までやってきたUボートのシュネーベント艦長(ウロ覚え)なんか中尉で26歳ですから、ドイツにはそういう伝統もあるのかもしれません。
非磁性物質…アルファ級みたいにチタンだったりして??
私も何でX舵が十字舵より運動性がいいのか、最初ピンと来ませんでした。が、ちょっと考えるとこういうことだと思います。
従来の十字舵ならば、左右の運動は縦の2枚、上下は横の2枚と潜舵。が、X舵ならば2枚の舵(組み合わせはいろいろあるとしても)だけを使うとどうしても運動がねじれてしまう(回転する)。ですからX舵は行きたい方向へ全部の舵が同じように動くんだと思います。4枚すべてが同じ向きになるのですからより機敏な動きになるのでしょう。
(違っていたらどなたかツッコミをお願いします)
独212型、良く見たら茂木大輔のHP(「日豪潜水艦博物館比較」の2に書き込みしました)にも画像がありますね。日付を見ると2004年撮影になってますから結構以前から見らるようになっていたようです。乗組員の少なさですが、憶測で言うと、調理員などは3直の中に含まなくてもいい(もともと少ししかいないのならまとめて作ってチンしてもらう)し、通信も兼務できるのかもしれません。昔の旅客機なんか機長・コパイ・FE(航空機関士)・通信士・航法士と5名も載ってたのに今や2名です。
艦長が大尉とのこと。が、戦争中日本までやってきたUボートのシュネーベント艦長(ウロ覚え)なんか中尉で26歳ですから、ドイツにはそういう伝統もあるのかもしれません。
非磁性物質…アルファ級みたいにチタンだったりして??
gejim さん
通信は兼務できるとは思えません。
ドイツの通信システムが、海上自衛隊とは全く別物なら話は違うのでしょうが。それにしても、暗号は、兼務できるような仕事ではないのです。通信とは8割以上が暗号と言うことです。
X舵は、4枚が同じ方向を向くのではなく、4枚ともで姿勢管制と方向管制が出来るので、効率的なのだと思います。
これは、コンピュータ制御が出来ないと、難しいためこれまで日本では実現しませんでした。
伝統だけで1800トンの艦長を大尉にやらせることが出来るとしたら、ドイツは大海軍国ですね。
潜水艦の艦長は、戦術単位の指揮官です。日本なら護衛隊群で、海将補が部下の幕僚を使ってやっと勤まる仕事です。それが、大尉の艦長が独りで出来るということの意味は軽くはありません。
戦争中は、Uボートを陸上の司令部(デーニッツ)が一元指揮しており、戦術や作戦は艦長の心配事ではありませんでした。
通信は兼務できるとは思えません。
ドイツの通信システムが、海上自衛隊とは全く別物なら話は違うのでしょうが。それにしても、暗号は、兼務できるような仕事ではないのです。通信とは8割以上が暗号と言うことです。
X舵は、4枚が同じ方向を向くのではなく、4枚ともで姿勢管制と方向管制が出来るので、効率的なのだと思います。
これは、コンピュータ制御が出来ないと、難しいためこれまで日本では実現しませんでした。
伝統だけで1800トンの艦長を大尉にやらせることが出来るとしたら、ドイツは大海軍国ですね。
潜水艦の艦長は、戦術単位の指揮官です。日本なら護衛隊群で、海将補が部下の幕僚を使ってやっと勤まる仕事です。それが、大尉の艦長が独りで出来るということの意味は軽くはありません。
戦争中は、Uボートを陸上の司令部(デーニッツ)が一元指揮しており、戦術や作戦は艦長の心配事ではありませんでした。
こんばんは、大変久しぶりに書き込みます。
いつも拝見させていただいていますが、次世代潜ネタ等は職業柄書き込めず、ROMのみです><
1.当直が3直制なのは我が国と米国だけと聞きました。ドイツ及び212の輸出先は2直制なのではないかと思います。
2.は、よく知りません。
3.ドイツの潜水艦の耐圧殻は、現在ステンレス製です。
外殻板に関しては、1990年代よりGFRPの適用が始まり、現在はCFRPの適用範囲も増えているようです。(我が国は構造部材としてはGFRPのみ。音響窓の一部にCFRPを適用。)
艦橋に関しては、係留状態では艦橋の前部と後部の外板が開くようになっていて、艦橋の中を通行するようにするようです。(写真を見たことあり)
X舵のメリットについてですが、抗たん性の向上の他、舵面積が十字舵より(幾何学的に)大きく取れるため、舵性能が向上します。
以上、簡単ですが、失礼いたします
いつも拝見させていただいていますが、次世代潜ネタ等は職業柄書き込めず、ROMのみです><
1.当直が3直制なのは我が国と米国だけと聞きました。ドイツ及び212の輸出先は2直制なのではないかと思います。
2.は、よく知りません。
3.ドイツの潜水艦の耐圧殻は、現在ステンレス製です。
外殻板に関しては、1990年代よりGFRPの適用が始まり、現在はCFRPの適用範囲も増えているようです。(我が国は構造部材としてはGFRPのみ。音響窓の一部にCFRPを適用。)
艦橋に関しては、係留状態では艦橋の前部と後部の外板が開くようになっていて、艦橋の中を通行するようにするようです。(写真を見たことあり)
X舵のメリットについてですが、抗たん性の向上の他、舵面積が十字舵より(幾何学的に)大きく取れるため、舵性能が向上します。
以上、簡単ですが、失礼いたします
Suzさん 貴重な情報提供感謝します。
こういう堅実な情報を基にすることが、本コミュの身上なので、今後ともよろしく。
他のメンバーも、積極的に参加をお願いします。
自分の強いジャンルで、貢献してください。
若い女性の好奇心も、貴重なものですから、すべてのメンバーが知識のみならず、自分の興味や感想を述べていただくのも、有益です。
ところで
X舵が操縦性を高めているため、浅い海域での行動を可能にしたものと推察します。
また、独潜水艦は北海が行動圏なので、安全潜航深度が浅く、船体強度が日本など深海で行動する潜水艦より楽なつくりになっているようです。
それで、グラスファイバーやカーボンが使用できるのでしょうか?
ただ、一部を非磁性にしても、全部を非磁性にするのは、掃海艇の例にみるように、相当努力が必要でしょうね。
2直だとすると。
艦長のほか乗員は26名、一直13名ですね。適当な推定をしますが、ご存知の方は、修正をお願いします。
哨戒長 1名(士官 指揮)
哨戒長付 1名(士官または准士官 指揮装置または潜航管制)
指揮装置または潜航管制 1名
ソーナー 2名
操舵 1名
発射管 1名
航海 1名
ESM 1名
通信 1名
機関 2名
調理 1名
これでも、海上自衛隊のほぼ半分の当直体制です。むかしから、小型で少人数がドイツ潜水艦の特徴でした。乗員が少なければ、居住用の装備も少なくて済み、性能上も有利です。
まして、ホットベットならば、乗員の半数のベッドで済むわけですから、海上自衛隊の2割以下の居住装備ということです。
行動期間、行動海域を限定できる強みもあるのでしょう。
当然、任務も具体的に限定できるから、武器やセンサーも拡散することはありません。
潜水艦の設計以前の問題として、学ぶべきことが多いと思います。
こういう堅実な情報を基にすることが、本コミュの身上なので、今後ともよろしく。
他のメンバーも、積極的に参加をお願いします。
自分の強いジャンルで、貢献してください。
若い女性の好奇心も、貴重なものですから、すべてのメンバーが知識のみならず、自分の興味や感想を述べていただくのも、有益です。
ところで
X舵が操縦性を高めているため、浅い海域での行動を可能にしたものと推察します。
また、独潜水艦は北海が行動圏なので、安全潜航深度が浅く、船体強度が日本など深海で行動する潜水艦より楽なつくりになっているようです。
それで、グラスファイバーやカーボンが使用できるのでしょうか?
ただ、一部を非磁性にしても、全部を非磁性にするのは、掃海艇の例にみるように、相当努力が必要でしょうね。
2直だとすると。
艦長のほか乗員は26名、一直13名ですね。適当な推定をしますが、ご存知の方は、修正をお願いします。
哨戒長 1名(士官 指揮)
哨戒長付 1名(士官または准士官 指揮装置または潜航管制)
指揮装置または潜航管制 1名
ソーナー 2名
操舵 1名
発射管 1名
航海 1名
ESM 1名
通信 1名
機関 2名
調理 1名
これでも、海上自衛隊のほぼ半分の当直体制です。むかしから、小型で少人数がドイツ潜水艦の特徴でした。乗員が少なければ、居住用の装備も少なくて済み、性能上も有利です。
まして、ホットベットならば、乗員の半数のベッドで済むわけですから、海上自衛隊の2割以下の居住装備ということです。
行動期間、行動海域を限定できる強みもあるのでしょう。
当然、任務も具体的に限定できるから、武器やセンサーも拡散することはありません。
潜水艦の設計以前の問題として、学ぶべきことが多いと思います。
燃料電池は、興味がありますね。どなたかが、他のトピで燃料電池が問題だと書かれていましたね。
実際のところを知りたいところですが。
ところで、番組では、危険な水素の貯蔵タンクが耐圧殻の外にあり、爆発した場合、外側に爆発のエネルギーが逃げるような構造だと言ってました。単純で有効な対策だと思いました。
どーどーさん提供の写真で、艦首の三つの孔は、ボルトでふたをするようですが、その後ろの孔は開閉式の蓋に見えます。
整備や上構チェックのため、日常的に出入りするのでしょうか。
また、最前部水線付近に横に広がっている黒い部分は、ソーナーの音響窓だと思いますが、材質はゴムでしょうか?
セイルトップまで、喫水マークがついているのは、試験か何かの都合でしょうか?
いろいろ疑問がわく、興味深い写真です。
実際のところを知りたいところですが。
ところで、番組では、危険な水素の貯蔵タンクが耐圧殻の外にあり、爆発した場合、外側に爆発のエネルギーが逃げるような構造だと言ってました。単純で有効な対策だと思いました。
どーどーさん提供の写真で、艦首の三つの孔は、ボルトでふたをするようですが、その後ろの孔は開閉式の蓋に見えます。
整備や上構チェックのため、日常的に出入りするのでしょうか。
また、最前部水線付近に横に広がっている黒い部分は、ソーナーの音響窓だと思いますが、材質はゴムでしょうか?
セイルトップまで、喫水マークがついているのは、試験か何かの都合でしょうか?
いろいろ疑問がわく、興味深い写真です。
こんばんは 横須賀出張帰りです^^
> また、独潜水艦は北海が行動圏なので、安全潜航深度が浅く、船体強度が日本など深海で行動する潜水艦より楽なつくりになっているようです。
> それで、グラスファイバーやカーボンが使用できるのでしょうか?
GFRPやCFRPの適用箇所は非水防部なので、潜航深度とは直接関係ないと思われます
GFRPを構造用材料として見た場合、材料減衰性能が鋼板より良いため、外殻板に適用することにより、航走雑音の低減に寄与することが可能です。
また、モノコック構造として製造するなら、鋼製構造より軽量化することも可能です。
CFRPは強度が強く、板厚を薄くできるため、音響窓としての使用に向いています。(但し、非常に高価であることと、導通性があるため、船体構造材料としての使用には向いていない。)
そうそう、212のX舵の舵板もGFRP製ですよ!
>また、最前部水線付近に横に広がっている黒い部分は、ソーナーの音響窓だと思いますが、材質はゴムでしょうか?
212の艦首ソーナードームはFRP製です。
(製造中の212ソーナードームの写真を見たことあり)
但し、表面はゴムでコーティングされていると考えられます。
(流木等の衝突の際に簡単にFRPを損傷しないようにするため)
セイルトップまで喫水マークが付いているのは、公試中で沈降試験用でしょうかね−?
> また、独潜水艦は北海が行動圏なので、安全潜航深度が浅く、船体強度が日本など深海で行動する潜水艦より楽なつくりになっているようです。
> それで、グラスファイバーやカーボンが使用できるのでしょうか?
GFRPやCFRPの適用箇所は非水防部なので、潜航深度とは直接関係ないと思われます
GFRPを構造用材料として見た場合、材料減衰性能が鋼板より良いため、外殻板に適用することにより、航走雑音の低減に寄与することが可能です。
また、モノコック構造として製造するなら、鋼製構造より軽量化することも可能です。
CFRPは強度が強く、板厚を薄くできるため、音響窓としての使用に向いています。(但し、非常に高価であることと、導通性があるため、船体構造材料としての使用には向いていない。)
そうそう、212のX舵の舵板もGFRP製ですよ!
>また、最前部水線付近に横に広がっている黒い部分は、ソーナーの音響窓だと思いますが、材質はゴムでしょうか?
212の艦首ソーナードームはFRP製です。
(製造中の212ソーナードームの写真を見たことあり)
但し、表面はゴムでコーティングされていると考えられます。
(流木等の衝突の際に簡単にFRPを損傷しないようにするため)
セイルトップまで喫水マークが付いているのは、公試中で沈降試験用でしょうかね−?
こんばんは
上構スリット、我が国のも無くすべきだと思うのですけどね...我が国ではいろんな障壁があるのです><
艦橋フィレット(艦橋と上構をなめらかにつなぐ部分)にしても...です。(16SSではやっと前部に装備されましたが)
私が212で驚くのは、艦橋前後を通行する手段として、艦橋内を通れるようにしているところです。
212は排水量の小さい艦なので、艦橋内装備も高密度化がなされているように思うのですが、艦橋内はマストの昇降装置が詰まっているはずです。通行するだけで乗員や造船所の人間はグリスまみれ? 機能重視とはいえ、相当、割り切った設計です。(我が国では「鶴の一声」が無い限り、不可能?)
あと、212は先進的な設計がなされているようなのに、潜舵が艦橋に装備されているところも私は注目しました。
(最近の攻撃型原潜では潜舵を艦首装備にしている艦が多い)
これは、スノーケル航走時や浅海域行動では、(潜水艦先進国のドイツでさえ)艦橋装備の方が操艦しやすいと考えているということなのかもしれません。
上構スリット、我が国のも無くすべきだと思うのですけどね...我が国ではいろんな障壁があるのです><
艦橋フィレット(艦橋と上構をなめらかにつなぐ部分)にしても...です。(16SSではやっと前部に装備されましたが)
私が212で驚くのは、艦橋前後を通行する手段として、艦橋内を通れるようにしているところです。
212は排水量の小さい艦なので、艦橋内装備も高密度化がなされているように思うのですが、艦橋内はマストの昇降装置が詰まっているはずです。通行するだけで乗員や造船所の人間はグリスまみれ? 機能重視とはいえ、相当、割り切った設計です。(我が国では「鶴の一声」が無い限り、不可能?)
あと、212は先進的な設計がなされているようなのに、潜舵が艦橋に装備されているところも私は注目しました。
(最近の攻撃型原潜では潜舵を艦首装備にしている艦が多い)
これは、スノーケル航走時や浅海域行動では、(潜水艦先進国のドイツでさえ)艦橋装備の方が操艦しやすいと考えているということなのかもしれません。
潜舵について。
潜舵のセイル装備は、操舵装置の雑音低減が不十分だからではないでしょうか。
潜舵は、重心より遠い艦首の方が効率がいいので舵を小さく出来るし、舵効もいいと認識しています。
それが、艦橋セイルに移動したのは、操舵時の騒音(油がシリンダを流れる音?)がソーナーに悪影響を与えるためだと。
(その結果、バウプレーンBPをセイルプレーンSPと言うようになった)
日本のL型(おおしお)では、時々潜舵を使用禁止にしてソーナー捜索をした記憶があります。ソーナーにシューシューと大きな音がしていました。
米原潜688級の後期型がセイルからバウに移ったのは、雑音対策が確立したからだと思ってます。
いかがでしょう?
セイル内の通行については、
グリースのついている昇降マストを個々あるいは全体に覆いをして、人間がすり抜けても付かないような対策と想像しています。
潜舵のセイル装備は、操舵装置の雑音低減が不十分だからではないでしょうか。
潜舵は、重心より遠い艦首の方が効率がいいので舵を小さく出来るし、舵効もいいと認識しています。
それが、艦橋セイルに移動したのは、操舵時の騒音(油がシリンダを流れる音?)がソーナーに悪影響を与えるためだと。
(その結果、バウプレーンBPをセイルプレーンSPと言うようになった)
日本のL型(おおしお)では、時々潜舵を使用禁止にしてソーナー捜索をした記憶があります。ソーナーにシューシューと大きな音がしていました。
米原潜688級の後期型がセイルからバウに移ったのは、雑音対策が確立したからだと思ってます。
いかがでしょう?
セイル内の通行については、
グリースのついている昇降マストを個々あるいは全体に覆いをして、人間がすり抜けても付かないような対策と想像しています。
ふくろうさん、早速のレスありがとうございます
ふくろうさんは、SSLにも乗られてたのですね!
42SS(SSS)で潜舵が艦橋に移動したのは、「潜舵が艦首装備だと艦首ソーナーに潜舵関連雑音が入るため」と、私も先輩から学びました^^
潜舵のフローノイズが艦首アレイに入るのかと思ってたのですが、油圧音だったのですね!勉強になりました! また、BP、SPなんて略語もあったのですね!
で、212ですが...ドイツは潜水艦先進国なので、潜舵の雑音対策はできているのではないか?なんて私は勝手に思っているのですが...
(ちなみにロシアのキロ級は通常動力潜だが潜舵は艦首装備)
ずいぶん前、潜水艦設計技術の海外文献調査を行った際、アメリカだったかイギリスだったかの1980年頃の文献に「SSBN、SSKはPD程度での操艦しやすさも軽視してはならず(SSBNはICBMを発射するため、SSKはスノーケル航走するため)、そのためこれら艦種にはバウプレーンよりセイルプレーンの方が向いている」てなことが書いてあったのを見かけました。
(バウプレーンだと、深度微調整で潜舵を操舵することによりトリムが変化しやすいため、浅深度だとセイルプレーンの方が都合よい)
一方、電子制御技術が格段の進歩を遂げた現在、SSBNもバウプレーン化している艦はあるので(英海軍・ヴァンガード)、上記の文献の記述も過去の話かな?なんて思っていました。
で、212のセイルプレーンの写真を見て、先の書き込みのようなことを思った次第です^^
私の書き込みに誤解等、ありましたら、ご指摘いただけるとありがたいです。
艦橋内通行の件、そうかもしれませんね^^
あ、そういえば212のマスト類はユニット化されているとの話も聞くので、マスト類は筐体に入っていて、外にグリスなんか付かないのかもしれませんねー
今でも定年検時のノイズサーベイではるしお型の艦橋に入ることがありますが、中はギッチリ詰まっていて、毎回ひと苦労です><
ふくろうさんは、SSLにも乗られてたのですね!
42SS(SSS)で潜舵が艦橋に移動したのは、「潜舵が艦首装備だと艦首ソーナーに潜舵関連雑音が入るため」と、私も先輩から学びました^^
潜舵のフローノイズが艦首アレイに入るのかと思ってたのですが、油圧音だったのですね!勉強になりました! また、BP、SPなんて略語もあったのですね!
で、212ですが...ドイツは潜水艦先進国なので、潜舵の雑音対策はできているのではないか?なんて私は勝手に思っているのですが...
(ちなみにロシアのキロ級は通常動力潜だが潜舵は艦首装備)
ずいぶん前、潜水艦設計技術の海外文献調査を行った際、アメリカだったかイギリスだったかの1980年頃の文献に「SSBN、SSKはPD程度での操艦しやすさも軽視してはならず(SSBNはICBMを発射するため、SSKはスノーケル航走するため)、そのためこれら艦種にはバウプレーンよりセイルプレーンの方が向いている」てなことが書いてあったのを見かけました。
(バウプレーンだと、深度微調整で潜舵を操舵することによりトリムが変化しやすいため、浅深度だとセイルプレーンの方が都合よい)
一方、電子制御技術が格段の進歩を遂げた現在、SSBNもバウプレーン化している艦はあるので(英海軍・ヴァンガード)、上記の文献の記述も過去の話かな?なんて思っていました。
で、212のセイルプレーンの写真を見て、先の書き込みのようなことを思った次第です^^
私の書き込みに誤解等、ありましたら、ご指摘いただけるとありがたいです。
艦橋内通行の件、そうかもしれませんね^^
あ、そういえば212のマスト類はユニット化されているとの話も聞くので、マスト類は筐体に入っていて、外にグリスなんか付かないのかもしれませんねー
今でも定年検時のノイズサーベイではるしお型の艦橋に入ることがありますが、中はギッチリ詰まっていて、毎回ひと苦労です><
艦橋内の狭さは、セイルを無理に細くしているからでしょうか。212みたいに基部が広ければ、下のほうは広くなっているでしょう。写真を見ると、マスト類は中央に縦に並んでいるようですから、人がかがめばゆっくり通れる余地があるように見えます。
潜舵の件。
キロ級は、雑音対策が完全にできていると言うより、操舵効率を追求したのではないか、と愚考します。
米SSNよりわが電池潜水艦のほうが、PDでの深度管制は厳しいので(SNKのため)潜舵の位置が下に装備され、舵面積も大きいと造船所の技術屋さんに聞いたことがあります。
確かに、SSNは艦橋からすぐ下ですが、わが潜水艦はだいぶ離れています。
バウプレーンの場合、操舵でツリムが変化する、と言う話は初耳です。
SSL時代の記憶(潜航指揮官で苦労しました)では、潜舵をとってもツリムが敏感に変化した覚えはありません。あいまいですが。
艦型が長大なL型から太くなったことで、より安定したと思いますから、BPの方が得なのでは、と思います。
おやしお型のセイル傾斜が中途半端なのは、艦側の通行スペースを優先したための中途半端な設計だと思います。
海上自衛隊は、だれも決断しないため、中途半端になりがちですね。
潜舵の件。
キロ級は、雑音対策が完全にできていると言うより、操舵効率を追求したのではないか、と愚考します。
米SSNよりわが電池潜水艦のほうが、PDでの深度管制は厳しいので(SNKのため)潜舵の位置が下に装備され、舵面積も大きいと造船所の技術屋さんに聞いたことがあります。
確かに、SSNは艦橋からすぐ下ですが、わが潜水艦はだいぶ離れています。
バウプレーンの場合、操舵でツリムが変化する、と言う話は初耳です。
SSL時代の記憶(潜航指揮官で苦労しました)では、潜舵をとってもツリムが敏感に変化した覚えはありません。あいまいですが。
艦型が長大なL型から太くなったことで、より安定したと思いますから、BPの方が得なのでは、と思います。
おやしお型のセイル傾斜が中途半端なのは、艦側の通行スペースを優先したための中途半端な設計だと思います。
海上自衛隊は、だれも決断しないため、中途半端になりがちですね。
おはようございます
ふくろうさん、遅い時間なのに早速のレス、ありがとうございました。
212艦橋通行性の件>
そうですね、05SSおやしお型が末広がり形状してて、中に空洞スペースがあること考えると、天蓋平面の面積がマスト類に必要な面積ですから、ふくろうさんがおっしゃられてる通りなのかもしれません。
>おやしお型のセイル傾斜が中途半端なのは、艦側の通行スペースを優先したための中途半端な設計だと思います。
おやしお型の艦橋傾斜角度に関しては...あまり詳しい話は書けないですが、まあTS性能と艦橋側面通行性とのトレードオフもあるでしょうね...
キロ級バウプレーンの件>
割り切って設計してそうですものね^^
>米SSNよりわが電池潜水艦のほうが、PDでの深度管制は厳しいので(SNKのため)潜舵の位置が下に装備され、舵面積も大きいと造船所の技術屋さんに聞いたことがあります。
この話は初めて聞きました! ちょっと調べてみます...
>バウプレーンの場合、操舵でツリムが変化する、と言う話は初耳です。
そうですか!
舵を操舵すると、船体は重心位置(Midship・G)を中心に回頭しますので、バウプレーンの場合は舵面積を小さくできる反面、トリムを維持しようとすれば、横舵を当て舵に取ってその回頭モーメントを打ち消さなければなりません。これがセイルプレーンだと、舵力作用点はMidsip・Gに近く、この回頭モーメントが小さ目で、横舵の当て舵量は少なくて済む(深度微調整のための潜舵操舵なら、横舵を当てなくてもよい)と考えられます。
ですが...
>SSL時代の記憶(潜航指揮官で苦労しました)では、潜舵をとってもツリムが敏感に変化した覚えはありません。
とのことなので、これは文献に書かれているほど大きな影響は無いのかもしれません...
こちらも、ちょっと調べてみます。
ふくろうさん、遅い時間なのに早速のレス、ありがとうございました。
212艦橋通行性の件>
そうですね、05SSおやしお型が末広がり形状してて、中に空洞スペースがあること考えると、天蓋平面の面積がマスト類に必要な面積ですから、ふくろうさんがおっしゃられてる通りなのかもしれません。
>おやしお型のセイル傾斜が中途半端なのは、艦側の通行スペースを優先したための中途半端な設計だと思います。
おやしお型の艦橋傾斜角度に関しては...あまり詳しい話は書けないですが、まあTS性能と艦橋側面通行性とのトレードオフもあるでしょうね...
キロ級バウプレーンの件>
割り切って設計してそうですものね^^
>米SSNよりわが電池潜水艦のほうが、PDでの深度管制は厳しいので(SNKのため)潜舵の位置が下に装備され、舵面積も大きいと造船所の技術屋さんに聞いたことがあります。
この話は初めて聞きました! ちょっと調べてみます...
>バウプレーンの場合、操舵でツリムが変化する、と言う話は初耳です。
そうですか!
舵を操舵すると、船体は重心位置(Midship・G)を中心に回頭しますので、バウプレーンの場合は舵面積を小さくできる反面、トリムを維持しようとすれば、横舵を当て舵に取ってその回頭モーメントを打ち消さなければなりません。これがセイルプレーンだと、舵力作用点はMidsip・Gに近く、この回頭モーメントが小さ目で、横舵の当て舵量は少なくて済む(深度微調整のための潜舵操舵なら、横舵を当てなくてもよい)と考えられます。
ですが...
>SSL時代の記憶(潜航指揮官で苦労しました)では、潜舵をとってもツリムが敏感に変化した覚えはありません。
とのことなので、これは文献に書かれているほど大きな影響は無いのかもしれません...
こちらも、ちょっと調べてみます。
Suz さん
だんだん議論も深まってきました。
せっかくの情報交換が、二人だけのものにならないよう、この辺で読者への考慮をしたいと思います。
あなたは当然ご存知だと思いますが、他のメンバーの理解のため、多少冗長な表現や解説を加えることがあるので、ご了解ください。
潜舵とモーメントの関係
理論的にはおっしゃるとおりだと思います。それが現実に影響がない、というよりBP(艦首)の方がいいと思われる理由は次の通りです。
1 モーメントが出るような大きな潜舵の使用は、深度変換(深度を変える)の時です。この場合、同時に姿勢角も変えるので、モーメントの大小にかかわらず横舵で姿勢制御をするため、モーメントを横舵で抑えることの不利は影響がない。
2 露頂深度でセンチ単位の深度維持(深度を保つ)での潜舵は、小さく頻繁に使用します。そのため、モーメントの影響が出にくいのではないでしょうか。
TS(ターゲットストレングス、対アクティブソーナー音響反射の強さ)
他のメンバーのために、解説します。
潜水艦の形状から、丸い艦体はアクティブソーナーの音波を拡散する。唯一艦橋セイルは直立しているため、反響が強いと考えられる。
電波ステルス同様、敵のアクティブセンサーの信号反射を小さくするため、傾斜させることが得策である。
という理由で、おやしお型の艦橋セイルは傾斜しています。
そこで、セイルの傾斜の程度や形状です。
私は、遠距離で探知されることのない潜水艦は、近距離でのステルスを優先すべきと考えています。そうすると傾斜させることの適否自体が問い直されるのではないでしょうか。
至近距離で上にいる水上艦や上から落とされる魚雷への考慮をすれば、上向きの傾斜はむしろTSを高める気がします。
それより直立ないし下向き傾斜のほうがステルス性があるように思えます。
それと平行して、前後方向の形状の直線性をなくして、上から見たらまさに涙滴型のずんぐりむっくりにする努力が有効だと考えます。
どうでしょう。
だんだん議論も深まってきました。
せっかくの情報交換が、二人だけのものにならないよう、この辺で読者への考慮をしたいと思います。
あなたは当然ご存知だと思いますが、他のメンバーの理解のため、多少冗長な表現や解説を加えることがあるので、ご了解ください。
潜舵とモーメントの関係
理論的にはおっしゃるとおりだと思います。それが現実に影響がない、というよりBP(艦首)の方がいいと思われる理由は次の通りです。
1 モーメントが出るような大きな潜舵の使用は、深度変換(深度を変える)の時です。この場合、同時に姿勢角も変えるので、モーメントの大小にかかわらず横舵で姿勢制御をするため、モーメントを横舵で抑えることの不利は影響がない。
2 露頂深度でセンチ単位の深度維持(深度を保つ)での潜舵は、小さく頻繁に使用します。そのため、モーメントの影響が出にくいのではないでしょうか。
TS(ターゲットストレングス、対アクティブソーナー音響反射の強さ)
他のメンバーのために、解説します。
潜水艦の形状から、丸い艦体はアクティブソーナーの音波を拡散する。唯一艦橋セイルは直立しているため、反響が強いと考えられる。
電波ステルス同様、敵のアクティブセンサーの信号反射を小さくするため、傾斜させることが得策である。
という理由で、おやしお型の艦橋セイルは傾斜しています。
そこで、セイルの傾斜の程度や形状です。
私は、遠距離で探知されることのない潜水艦は、近距離でのステルスを優先すべきと考えています。そうすると傾斜させることの適否自体が問い直されるのではないでしょうか。
至近距離で上にいる水上艦や上から落とされる魚雷への考慮をすれば、上向きの傾斜はむしろTSを高める気がします。
それより直立ないし下向き傾斜のほうがステルス性があるように思えます。
それと平行して、前後方向の形状の直線性をなくして、上から見たらまさに涙滴型のずんぐりむっくりにする努力が有効だと考えます。
どうでしょう。
USNロサンゼルス級(688)の潜舵位置の件についてウンチクを・・・。
このロサンゼルス級の初期設計段階においては、試作中であったトマホークVLS(垂直発射筒)の搭載(艦首装備)を考慮しており、この影響もあって艦橋潜舵方式としたものと認識しています。
ロサンゼルス級のVLS未搭載初期艦は浮上するとアップトリム姿勢が顕著になります。(重量バランスもVLS搭載を前提に計画されたため)
この艦橋潜舵方式は後期艦では艦首潜舵方式に改められるのですが、これは、北極海での行動が重要視された結果とも言われています。
艦橋潜舵方式であると北極海での浮上時に砕氷による損傷を避けるため、潜舵を垂直に向ける必要があり、この浮上用の潜舵回転機構を別途持つ必要があります。
後期艦ではVLS装置も確定し、艦首部に潜舵を引き込むスペースが確認されたことにより艦首潜舵に変更したのでしょう。但し、艦首潜舵も皆さんが言われるように操舵系の雑音や、接岸時用の引き込み機構が必要となるため、どちらの方式とも優劣付け難いと考えます。
マスト類について。
USNの潜水艦のマスト換装は、「あっ」という間です。完全にマストシステムがユニット化されており、スポスポ入れ替えできるそうです。
オーストラリア海軍のX舵艦を見たことがありますが、これも艦橋内通行方式でした。でもこの艦で一番驚いたのは・・・女性乗員がいたことでした!!!
このロサンゼルス級の初期設計段階においては、試作中であったトマホークVLS(垂直発射筒)の搭載(艦首装備)を考慮しており、この影響もあって艦橋潜舵方式としたものと認識しています。
ロサンゼルス級のVLS未搭載初期艦は浮上するとアップトリム姿勢が顕著になります。(重量バランスもVLS搭載を前提に計画されたため)
この艦橋潜舵方式は後期艦では艦首潜舵方式に改められるのですが、これは、北極海での行動が重要視された結果とも言われています。
艦橋潜舵方式であると北極海での浮上時に砕氷による損傷を避けるため、潜舵を垂直に向ける必要があり、この浮上用の潜舵回転機構を別途持つ必要があります。
後期艦ではVLS装置も確定し、艦首部に潜舵を引き込むスペースが確認されたことにより艦首潜舵に変更したのでしょう。但し、艦首潜舵も皆さんが言われるように操舵系の雑音や、接岸時用の引き込み機構が必要となるため、どちらの方式とも優劣付け難いと考えます。
マスト類について。
USNの潜水艦のマスト換装は、「あっ」という間です。完全にマストシステムがユニット化されており、スポスポ入れ替えできるそうです。
オーストラリア海軍のX舵艦を見たことがありますが、これも艦橋内通行方式でした。でもこの艦で一番驚いたのは・・・女性乗員がいたことでした!!!
こんばんは、外出してましたので、携帯から見ていたものの、少々遅レスになってしまい、ごめんなさい
ふくろうさん>
潜舵の件、
1.に関しては、もちろん、そうだと思います。
2.に関しては...舵力によるモーメントが発生して、どの程度のレスポンスで船体にトリム変化が発生するかによりますね。バウプレーンだったSSLにお乗りだったふくろうさんが、潜舵を操舵しても敏感にトリム変化を感じなかったのであれば、問題になるようなレベルではなさそうなので、文献に書いてあった内容は「定性論」ということになりますね。
ということで、「艦首ソーナーへ入る自艦雑音」と「船体主要構造の合理性」のトレードオフにより、バウプレーンかセイルプレーンかに別れるってことになりますね。
びんどんさん>
>このロサンゼルス級の初期設計段階においては、試作中であったトマホークVLS(垂直発射筒)の搭載(艦首装備)を考慮しており、この影響もあって艦橋潜舵方式としたものと認識しています。
この話は初耳です!
豪海軍・コリンズ乗員の女性の件は...ディスカバリーチャンネルで見ましたが、結構キレイな女性で驚きましたw
コリンズ寄港時の見学の話を某艦乗員の方から聞きましたが、コリンズには女性が乗っているにも関わらず、艦内には女性のヌード写真が貼ってあったりするようで、「日本の船だったらセクハラだ!」てな話も聞きましたw
どーどーさん>
貴重な写真情報、ありがとうございます。
艦橋内の雰囲気は少し判りました。狭そうですね!
マストのシリンダー類は露出しているので、そのまま通行すると、やはり作業服がグリスで汚れそうですね^^
(TSの件、おやしお型に関しては、私はこれ以上は書けません)
艦橋形状に関して、アメリカ海軍の潜水艦を見ると、最新のヴァージニアでさえ直立型なので、TSの考え方や想定条件が違うのかな?なんて思ったりします。
ふくろうさん>
潜舵の件、
1.に関しては、もちろん、そうだと思います。
2.に関しては...舵力によるモーメントが発生して、どの程度のレスポンスで船体にトリム変化が発生するかによりますね。バウプレーンだったSSLにお乗りだったふくろうさんが、潜舵を操舵しても敏感にトリム変化を感じなかったのであれば、問題になるようなレベルではなさそうなので、文献に書いてあった内容は「定性論」ということになりますね。
ということで、「艦首ソーナーへ入る自艦雑音」と「船体主要構造の合理性」のトレードオフにより、バウプレーンかセイルプレーンかに別れるってことになりますね。
びんどんさん>
>このロサンゼルス級の初期設計段階においては、試作中であったトマホークVLS(垂直発射筒)の搭載(艦首装備)を考慮しており、この影響もあって艦橋潜舵方式としたものと認識しています。
この話は初耳です!
豪海軍・コリンズ乗員の女性の件は...ディスカバリーチャンネルで見ましたが、結構キレイな女性で驚きましたw
コリンズ寄港時の見学の話を某艦乗員の方から聞きましたが、コリンズには女性が乗っているにも関わらず、艦内には女性のヌード写真が貼ってあったりするようで、「日本の船だったらセクハラだ!」てな話も聞きましたw
どーどーさん>
貴重な写真情報、ありがとうございます。
艦橋内の雰囲気は少し判りました。狭そうですね!
マストのシリンダー類は露出しているので、そのまま通行すると、やはり作業服がグリスで汚れそうですね^^
(TSの件、おやしお型に関しては、私はこれ以上は書けません)
艦橋形状に関して、アメリカ海軍の潜水艦を見ると、最新のヴァージニアでさえ直立型なので、TSの考え方や想定条件が違うのかな?なんて思ったりします。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
本当の潜水艦のコミュ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
本当の潜水艦のコミュのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75479人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6452人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208290人