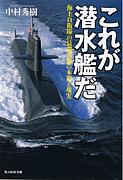本日12月5日、三菱神戸造船所において16SS「そうりゅう」が着水しました。
艦名が「〜しお」からついに、というかなんというか脱塩しました。
17SSは、やっぱり「ひりゅう」かな?
ニュース検索かけましたが、ひっかからなかったのでWikiから・・・
http://
艦名が「〜しお」からついに、というかなんというか脱塩しました。
17SSは、やっぱり「ひりゅう」かな?
ニュース検索かけましたが、ひっかからなかったのでWikiから・・・
http://
|
|
|
|
コメント(20)
AIPを導入するのに、ずいぶんかかったものです。
平成2年頃、導入が決まったと思いますが、スターリングエンジンは当時すでに実用化されてました。なんで、実用化された機関を、海上自衛隊の潜水艦に積むのに、長々と研究が必要だったのか、理解できません。
計画がどんどん遅れている間に、燃料電池が出てきたのですが、日本の官僚主義は、既存の計画を絶対に修正しません。
「おやしお」型も「そうりゅう」型も、「うずしお」や「はるしお」ほどの革新性を感じないのです。
潜望鏡も一本だけ非貫通にしても、しょうがないとおもうのですが。
とりあえずは、AIPとX舵が目玉ということでしょうか。世界的には目新しい技術ではないのですが。
なにか、ほかに取り柄を知っている人があれば、書き込みお願いします。
平成2年頃、導入が決まったと思いますが、スターリングエンジンは当時すでに実用化されてました。なんで、実用化された機関を、海上自衛隊の潜水艦に積むのに、長々と研究が必要だったのか、理解できません。
計画がどんどん遅れている間に、燃料電池が出てきたのですが、日本の官僚主義は、既存の計画を絶対に修正しません。
「おやしお」型も「そうりゅう」型も、「うずしお」や「はるしお」ほどの革新性を感じないのです。
潜望鏡も一本だけ非貫通にしても、しょうがないとおもうのですが。
とりあえずは、AIPとX舵が目玉ということでしょうか。世界的には目新しい技術ではないのですが。
なにか、ほかに取り柄を知っている人があれば、書き込みお願いします。
ううむ。
とにかく保守的な技術のブラッシュアップという事なのでしょうか。
まだ先行量産型というか実験艦の段階ですので
新旧が共存するという状況はいたしかたないと思います。
燃料電池搭載艦といえばドイツの212型ですが
量産型でカタログどうりの性能が出せずに
ギリシャが受け取りだか支払いだかを拒んでいるという話も
聞きますし、
ドイツと言えば毎度おなじみの新技術の初期不良を解決出来てないようです。
スターリングエンジンはまだまだ発展途上とも言える技術であり
ゴトランド級は1995年就役と言う事でまだまだ新しいと言えるのでは。
軍用艦、特に潜水艦への応用は
保守的で枯れた技術とは言えない、「比較的」新しい技術を
導入しようという姿勢で、
私はこのチョイスは悪くは無いと思います。
とにかく保守的な技術のブラッシュアップという事なのでしょうか。
まだ先行量産型というか実験艦の段階ですので
新旧が共存するという状況はいたしかたないと思います。
燃料電池搭載艦といえばドイツの212型ですが
量産型でカタログどうりの性能が出せずに
ギリシャが受け取りだか支払いだかを拒んでいるという話も
聞きますし、
ドイツと言えば毎度おなじみの新技術の初期不良を解決出来てないようです。
スターリングエンジンはまだまだ発展途上とも言える技術であり
ゴトランド級は1995年就役と言う事でまだまだ新しいと言えるのでは。
軍用艦、特に潜水艦への応用は
保守的で枯れた技術とは言えない、「比較的」新しい技術を
導入しようという姿勢で、
私はこのチョイスは悪くは無いと思います。
海上自衛隊の艦名命名基準があって、潜水艦には海象と水中動物しかつけられません。
だから、水中動物の竜を使用しています。
「伊○潜」は規定外ですね。
私としては、伝統のない「しお」を反復するより、「りゅう」に変わったのは進歩だと思っています。
「しお」シリーズで意味のあるのは、くろしお、おやしおだけですから、これらは欠番か、革新的な型のネームシップにとどめるべきでした。
あとの方法は、未使用の「しお」(学者の意見では結構あると聞いている)か、海象の「なみ」を水上艦から取り返す、また、鯨シリーズもあります。大鯨、迅鯨、など。
まだ、海中動物でいい名前があれば、使えばいいのです。米潜水艦は戦争中そうでしたね。英語だと印象が違うから、日本は別の配慮が要りますが。
はつがつお、じゃまずい(いやおいしい)し。
切り札として、命名基準を変えるという手もありますね。
米潜水艦が魚名から、都市名、州名に変えたように、海上自衛隊潜水艦も、旧都市名や旧国名を使ってもいいでしょう。
自衛艦はひらがな、なのでその印象も考慮する必要があります。
このテーマは、皆さんの感性が反映されて、おもしろいですね。
他の方のご意見も拝見したいものです。
だから、水中動物の竜を使用しています。
「伊○潜」は規定外ですね。
私としては、伝統のない「しお」を反復するより、「りゅう」に変わったのは進歩だと思っています。
「しお」シリーズで意味のあるのは、くろしお、おやしおだけですから、これらは欠番か、革新的な型のネームシップにとどめるべきでした。
あとの方法は、未使用の「しお」(学者の意見では結構あると聞いている)か、海象の「なみ」を水上艦から取り返す、また、鯨シリーズもあります。大鯨、迅鯨、など。
まだ、海中動物でいい名前があれば、使えばいいのです。米潜水艦は戦争中そうでしたね。英語だと印象が違うから、日本は別の配慮が要りますが。
はつがつお、じゃまずい(いやおいしい)し。
切り札として、命名基準を変えるという手もありますね。
米潜水艦が魚名から、都市名、州名に変えたように、海上自衛隊潜水艦も、旧都市名や旧国名を使ってもいいでしょう。
自衛艦はひらがな、なのでその印象も考慮する必要があります。
このテーマは、皆さんの感性が反映されて、おもしろいですね。
他の方のご意見も拝見したいものです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
本当の潜水艦のコミュ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-