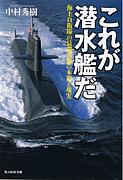パースへの機内で「硫黄島からの手紙」観ました。
最近の戦争映画は考証がひどいので、感動できませんでした。
特に変なところは
1 栗林中将が指揮官なのに参謀懸章を吊っている。
2 幕僚が副官ひとりで参謀が居ない
3 将校が兵隊を殴っている(画面が小さかったので階級章は見えませんでしたが、軍刀吊ってたらか士官でしょうね)
4 西中佐が馬に乗っている(戦車連隊の指揮官が戦場に馬を持ってきているのは不自然)
5 元気な兵隊が、戦況不利のため手りゅう弾で自決する。
絶対ありえません。負傷兵にはその例がありますが、五体満足な兵隊がそんなことするわけがない。出撃します。
その他の戦闘状況の描写はキリがありません。戦争や軍隊について知識が欠如しているため、イメージが変でした。ブラックホークダウンやプライベートライアンなどと比較すると、明らかです。
軍事アドバイザーを使っていなんでしょうか?
戦闘の推移も実際と違うし、欲求不満になってしまった。
最近の戦争映画は考証がひどいので、感動できませんでした。
特に変なところは
1 栗林中将が指揮官なのに参謀懸章を吊っている。
2 幕僚が副官ひとりで参謀が居ない
3 将校が兵隊を殴っている(画面が小さかったので階級章は見えませんでしたが、軍刀吊ってたらか士官でしょうね)
4 西中佐が馬に乗っている(戦車連隊の指揮官が戦場に馬を持ってきているのは不自然)
5 元気な兵隊が、戦況不利のため手りゅう弾で自決する。
絶対ありえません。負傷兵にはその例がありますが、五体満足な兵隊がそんなことするわけがない。出撃します。
その他の戦闘状況の描写はキリがありません。戦争や軍隊について知識が欠如しているため、イメージが変でした。ブラックホークダウンやプライベートライアンなどと比較すると、明らかです。
軍事アドバイザーを使っていなんでしょうか?
戦闘の推移も実際と違うし、欲求不満になってしまった。
|
|
|
|
コメント(10)
将校は兵隊を殴らないのが不文律です。
兵隊は兵長(上等兵)が締めるというのが陸軍のやり方です。
海軍は海兵団で班長の下士官が新兵を殴る(けつを)ことはありましたが、艦隊では先任の水兵長の仕事だったようです。
大叔父さんは将校だったんじゃ?
兵隊を殴る将校は異常者です。
捕虜になるより死を選べ、ということの先入観が強すぎるのですね。不自然なのは戦力十分なのに簡単に手りゅう弾自決です。映画の状況は、戦史を見る限りありません。
出撃するのが普通です。
ストーリーは不自然で、歴史的事実と反していて、問題になりません。
戦争が悲惨であるということを強調したい、底の浅さは戦後映画の共通点ですな。
兵隊は兵長(上等兵)が締めるというのが陸軍のやり方です。
海軍は海兵団で班長の下士官が新兵を殴る(けつを)ことはありましたが、艦隊では先任の水兵長の仕事だったようです。
大叔父さんは将校だったんじゃ?
兵隊を殴る将校は異常者です。
捕虜になるより死を選べ、ということの先入観が強すぎるのですね。不自然なのは戦力十分なのに簡単に手りゅう弾自決です。映画の状況は、戦史を見る限りありません。
出撃するのが普通です。
ストーリーは不自然で、歴史的事実と反していて、問題になりません。
戦争が悲惨であるということを強調したい、底の浅さは戦後映画の共通点ですな。
初心者ですのでお教えいただけるとありがたいのですが、
1.参謀懸章について
堀 栄三『大本営参謀の情報戦記―情報なき国家の悲劇 』(文春文庫)だったか、当時は「参謀懸章」とはいわず「参謀飾緒」という、と書いていましたが、どちらの言い方でも正しかったのでしょうか?
東条英機が陸相と参謀総長を兼務していたとき、場所を移動するたびに飾緒をつけたりはずしているのを見て、将校さんは苦笑していた、というエピソードがあったようですが、ここからは飾緒をつけるべきTPOがよく伺えました。
4.西中佐について
堀江芳孝『闘魂 硫黄島―小笠原兵団参謀の回想 』(光人社NF文庫) によれば、西中佐は硫黄島に移動してくるときに、貴重な資材もろとも一度沈められ、再度、硫黄島へ移動してきた、とか。そのとき馬を運べたかどうかは書いてなかったように思いますが、沈められたばかりの人が再度の決死行にかわいい馬を乗せてこれるかどうか疑問です。
映画では、西中佐が、連合艦隊が壊滅状態であることを栗林中将に伝えるシーンがあったかと思いますが、この本では、堀江芳孝本人が伝えたことになっています。
5.自決について
児島 襄『将軍突撃せり―硫黄島戦記』では、栗林中将が ―― 対する米軍もまた――、戦況を非常に数理的に解析し、次の作戦に生かそうとする様子が書かれていて、非常に興味深く思いました。陸大ではこういう技術を修得するのだな、と。その上で、部隊を鼓舞する意図を込めて、「一人十殺」はては「一人百殺」と訴え、そのためには、自決を許さない、と。
この本は、こうした将軍の命令を、各部隊が理解し、戦闘に臨む様子を淡々と書いていて、悲劇であったとはいえ、一読者として、日本軍を誇りに思えます。
硫黄島は、米軍が占領宣言したあとも、長々と戦闘が続きました。
戦力十分なのに自決というのは、私には理解できませんね。
私には、史実はわかりませんが。以上3冊、私の記憶違いならお許しを。
1.参謀懸章について
堀 栄三『大本営参謀の情報戦記―情報なき国家の悲劇 』(文春文庫)だったか、当時は「参謀懸章」とはいわず「参謀飾緒」という、と書いていましたが、どちらの言い方でも正しかったのでしょうか?
東条英機が陸相と参謀総長を兼務していたとき、場所を移動するたびに飾緒をつけたりはずしているのを見て、将校さんは苦笑していた、というエピソードがあったようですが、ここからは飾緒をつけるべきTPOがよく伺えました。
4.西中佐について
堀江芳孝『闘魂 硫黄島―小笠原兵団参謀の回想 』(光人社NF文庫) によれば、西中佐は硫黄島に移動してくるときに、貴重な資材もろとも一度沈められ、再度、硫黄島へ移動してきた、とか。そのとき馬を運べたかどうかは書いてなかったように思いますが、沈められたばかりの人が再度の決死行にかわいい馬を乗せてこれるかどうか疑問です。
映画では、西中佐が、連合艦隊が壊滅状態であることを栗林中将に伝えるシーンがあったかと思いますが、この本では、堀江芳孝本人が伝えたことになっています。
5.自決について
児島 襄『将軍突撃せり―硫黄島戦記』では、栗林中将が ―― 対する米軍もまた――、戦況を非常に数理的に解析し、次の作戦に生かそうとする様子が書かれていて、非常に興味深く思いました。陸大ではこういう技術を修得するのだな、と。その上で、部隊を鼓舞する意図を込めて、「一人十殺」はては「一人百殺」と訴え、そのためには、自決を許さない、と。
この本は、こうした将軍の命令を、各部隊が理解し、戦闘に臨む様子を淡々と書いていて、悲劇であったとはいえ、一読者として、日本軍を誇りに思えます。
硫黄島は、米軍が占領宣言したあとも、長々と戦闘が続きました。
戦力十分なのに自決というのは、私には理解できませんね。
私には、史実はわかりませんが。以上3冊、私の記憶違いならお許しを。
>7
>これも事実と違うぞ、という点があれば、そのときはお教えください
映画を見て、「これはあまりにひどいだろう!」と思った点を以下に。
・硫黄島の飛行場はすべて海軍のものだったと認識しているのですが、冒頭で渡辺謙扮する栗林陸軍中将が飛行場に着任しますね?あれ変じゃない?と思いました。
そもそも、栗林中将が飛行機で硫黄島に着任したかどうかもあやしい。船でやってきたという話は本で読んだが。
・あと、映画で出てくる飛行場には海軍と陸軍の飛行機が混在しているようにみえます。これも変だろう。
・さらに言えば、栗林中将が乗ってきた飛行機。尾翼が2つあってアメリカの飛行機だろうと思いましたが、一応、当時の日本陸軍にも似たような輸送機がありました。
「一式貨物輸送機」
http://military.sakura.ne.jp/ac/ki56.htm
ただ、これが本当に使われたかどうかはあやしい。
・あと、若手の主役級の兵士(加瀬亮?二宮和也?)も輸送機で降り立つ。
当時、日本陸軍の増援兵士が輸送機で降り立つことなどあったのだろうか。ベトナム戦争じゃあるまいし。当然、輸送船だったでしょうな。
・また、栗林中将のいる陸軍司令部に、陸軍の日の丸の旗と海軍の軍艦旗が並んで置かれているのも気になった。それとも軍艦旗に見えるのは、陸軍の旭日旗なのだろうか?
まだまだありますw
・一番おかしいのは、栗林中将を最高司令官として、陸軍部隊も海軍部隊もその指揮下にあるような描かれ方をしていること。確かに表向きはそうなっていたかもしれないが、実際の関係は協力関係にすぎない。戦闘前はもちろん、戦闘中も陸軍部隊と海軍部隊は基本的に独立して行動している。
したがって、陸軍将兵と海軍将兵が一緒に何かやるというシーンは、実際にはほとんどなかったのではないか?
たとえば、渡辺謙の栗林中将や伊原剛志の西中佐が、海軍部隊の壕に行って中村獅童扮する海軍士官の乱暴を防ぐシーンがあるが、果たしてあのようなことが出来ただろうか。陸軍の指揮官クラスが海軍の担当部署に勝手に出むいて、まして、命令を下すことなど不自然である。
冒頭の方では、栗林中将がいきなり海軍司令官を罷免するように見られるシーンもあるが、本当なら中央を巻き込んでの大騒動となるのでは。
・映画で出てくる地下壕は天然の鍾乳洞のように広いですが、実際は手掘りで1人がやっと通れる洞窟がほとんどだったので、閉所恐怖症や暗所恐怖症の人は、そこにいるだけで発狂しそうな環境だったと思われる。
また、日本軍の地下壕は何層にも及んでおり、最下層にいた兵士などは、戦闘中は一度も太陽など見られなかったらしい。熱さで服など着ておれず、ほぼ真っ裸で戦ったという。
ですから、過酷な戦場の再現という意味では、がっかりしました。
・・長文失礼しました。
>これも事実と違うぞ、という点があれば、そのときはお教えください
映画を見て、「これはあまりにひどいだろう!」と思った点を以下に。
・硫黄島の飛行場はすべて海軍のものだったと認識しているのですが、冒頭で渡辺謙扮する栗林陸軍中将が飛行場に着任しますね?あれ変じゃない?と思いました。
そもそも、栗林中将が飛行機で硫黄島に着任したかどうかもあやしい。船でやってきたという話は本で読んだが。
・あと、映画で出てくる飛行場には海軍と陸軍の飛行機が混在しているようにみえます。これも変だろう。
・さらに言えば、栗林中将が乗ってきた飛行機。尾翼が2つあってアメリカの飛行機だろうと思いましたが、一応、当時の日本陸軍にも似たような輸送機がありました。
「一式貨物輸送機」
http://military.sakura.ne.jp/ac/ki56.htm
ただ、これが本当に使われたかどうかはあやしい。
・あと、若手の主役級の兵士(加瀬亮?二宮和也?)も輸送機で降り立つ。
当時、日本陸軍の増援兵士が輸送機で降り立つことなどあったのだろうか。ベトナム戦争じゃあるまいし。当然、輸送船だったでしょうな。
・また、栗林中将のいる陸軍司令部に、陸軍の日の丸の旗と海軍の軍艦旗が並んで置かれているのも気になった。それとも軍艦旗に見えるのは、陸軍の旭日旗なのだろうか?
まだまだありますw
・一番おかしいのは、栗林中将を最高司令官として、陸軍部隊も海軍部隊もその指揮下にあるような描かれ方をしていること。確かに表向きはそうなっていたかもしれないが、実際の関係は協力関係にすぎない。戦闘前はもちろん、戦闘中も陸軍部隊と海軍部隊は基本的に独立して行動している。
したがって、陸軍将兵と海軍将兵が一緒に何かやるというシーンは、実際にはほとんどなかったのではないか?
たとえば、渡辺謙の栗林中将や伊原剛志の西中佐が、海軍部隊の壕に行って中村獅童扮する海軍士官の乱暴を防ぐシーンがあるが、果たしてあのようなことが出来ただろうか。陸軍の指揮官クラスが海軍の担当部署に勝手に出むいて、まして、命令を下すことなど不自然である。
冒頭の方では、栗林中将がいきなり海軍司令官を罷免するように見られるシーンもあるが、本当なら中央を巻き込んでの大騒動となるのでは。
・映画で出てくる地下壕は天然の鍾乳洞のように広いですが、実際は手掘りで1人がやっと通れる洞窟がほとんどだったので、閉所恐怖症や暗所恐怖症の人は、そこにいるだけで発狂しそうな環境だったと思われる。
また、日本軍の地下壕は何層にも及んでおり、最下層にいた兵士などは、戦闘中は一度も太陽など見られなかったらしい。熱さで服など着ておれず、ほぼ真っ裸で戦ったという。
ですから、過酷な戦場の再現という意味では、がっかりしました。
・・長文失礼しました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
本当の潜水艦のコミュ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
本当の潜水艦のコミュのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75482人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6444人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208287人