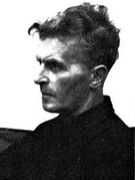|
|
|
|
コメント(19)
この本、もっと読まれていい本だと、感じてます。
「ここに記した、Schroeginger方程式の導き出しかたは、ひとつの推量で、もちろん論理的の帰結ではない。一般に、自然科学の法則は、どれもまったく論理的にでて来るものではない。と言って、実験結果だけから、全く帰納的に導かれるものでもない。実験から暗示される推測、仮定に基づいて理論を作る。その結果が多くの実験と一致するものを与えれば、仮説は法則原理として容認されるようになる。Schroedinger方程式の場合も、この方程式のただしいことは、これから求めたエネルギーその他の物理量の価が、実験から求めたものと一致することによって保障される。」
ある教科書で、物理の基礎的な問題に触れた部分ですが、「考察」の確実性の問題に、重なるでしょう。(独断ですが、、) 必ずしも、自明でない話で、かなり無器用に表現されてる訳ですが。この物理屋さんが、L。W。を意識してたら、もっとスマートに表現したと、思うんです。
「ここに記した、Schroeginger方程式の導き出しかたは、ひとつの推量で、もちろん論理的の帰結ではない。一般に、自然科学の法則は、どれもまったく論理的にでて来るものではない。と言って、実験結果だけから、全く帰納的に導かれるものでもない。実験から暗示される推測、仮定に基づいて理論を作る。その結果が多くの実験と一致するものを与えれば、仮説は法則原理として容認されるようになる。Schroedinger方程式の場合も、この方程式のただしいことは、これから求めたエネルギーその他の物理量の価が、実験から求めたものと一致することによって保障される。」
ある教科書で、物理の基礎的な問題に触れた部分ですが、「考察」の確実性の問題に、重なるでしょう。(独断ですが、、) 必ずしも、自明でない話で、かなり無器用に表現されてる訳ですが。この物理屋さんが、L。W。を意識してたら、もっとスマートに表現したと、思うんです。
ぼくはこの本を読んでもいまいちしっくりきませんでした。。
もともと哲学屋ではなく、「語りえないもの」を示すために「語りえるもの」を規定したところが凄い!と思っている一人なので、ところどころで理解できてなかったり、荒い読み方をしていることもあるのですが。
まず、P.78からのところで、「安易な神秘主義」と安易に言ってしまっている部分なんか、かなり不満。それは後世の人間だから言えることであって、ヴィトゲンシュタインがやろうとしていたことはむちゃくちゃ難しいことだったのに。。と思いました。その後の、論理的思考と神秘主義が組み合わさって「論理的神秘主義と呼ぼう。」とか言ってるのも安易だよなあと思ってしまいます。
あと、P.169の「世界が私の世界であることは、唯一の言語(私が理解する唯一の言語)の限界が私の世界の限界を意味することに示されている。」という『論考』からの引用に対して、「最後の部分は意味不明であるが、それは必然的に意味不明なのであると考えねばならない。…」というのもかなり無理なこじつけのように思えます。だったらなぜこの部分にだけそんな無意味な文章を書こうとヴィトゲンシュタインは思ったのでしょうか?ぜんぜん「意味不明」ではないように思えますが。。
その他にもいくつかうーん。。と思ってしまう点がいくつかありました。
ぼくが考えるヴィトゲンシュタインが思っていた「神」と、この著者のそれとはかなり違うんだろうなあということを感じた一冊でした。
哲学の解説本だから、「語りえないもの」についての記述に期待するのもおかしな話ですが。(笑)
もともと哲学屋ではなく、「語りえないもの」を示すために「語りえるもの」を規定したところが凄い!と思っている一人なので、ところどころで理解できてなかったり、荒い読み方をしていることもあるのですが。
まず、P.78からのところで、「安易な神秘主義」と安易に言ってしまっている部分なんか、かなり不満。それは後世の人間だから言えることであって、ヴィトゲンシュタインがやろうとしていたことはむちゃくちゃ難しいことだったのに。。と思いました。その後の、論理的思考と神秘主義が組み合わさって「論理的神秘主義と呼ぼう。」とか言ってるのも安易だよなあと思ってしまいます。
あと、P.169の「世界が私の世界であることは、唯一の言語(私が理解する唯一の言語)の限界が私の世界の限界を意味することに示されている。」という『論考』からの引用に対して、「最後の部分は意味不明であるが、それは必然的に意味不明なのであると考えねばならない。…」というのもかなり無理なこじつけのように思えます。だったらなぜこの部分にだけそんな無意味な文章を書こうとヴィトゲンシュタインは思ったのでしょうか?ぜんぜん「意味不明」ではないように思えますが。。
その他にもいくつかうーん。。と思ってしまう点がいくつかありました。
ぼくが考えるヴィトゲンシュタインが思っていた「神」と、この著者のそれとはかなり違うんだろうなあということを感じた一冊でした。
哲学の解説本だから、「語りえないもの」についての記述に期待するのもおかしな話ですが。(笑)
そうですかね?
ぼくは『ウィトゲンシュタインは〜』はかなり初心者向けに感じましたが。。
わかりやすくしようと書いてるために、かえって安直な解釈のようになってしまってるなあ
と思うところがけっこうありますよ〜。
永井さんのは永井哲学として読むとおもしろいですね。
ウィトゲンシュタインの本としては、ちと独我論を誇張しすぎな気がします。
『言語の限界』はちらっと読んだけど、あまり食指が動かなかったので、
なんとも言えません。
ウィトゲンシュタインの哲学の中でいつまでもくるくると回ってるだけの解釈本って、
結局ウィトゲンシュタインが彼の哲学の中でもっとも言いたかったことをまるでわかってないような感じがするので、『梯子を捨てる』ところに向けて、個々の解釈をしていくような本の
ほうがおもしろいですよ。
ウィトゲンシュタインは、哲学をやってきた結果「語りえぬもの」を見つけたんじゃなくて、
まず第一に「語りえぬもの」を示したくて彼の哲学が生まれたんですから。
そういう意味では、トルストイの本から入ったほうが良いのかも。
ぼくは『ウィトゲンシュタインは〜』はかなり初心者向けに感じましたが。。
わかりやすくしようと書いてるために、かえって安直な解釈のようになってしまってるなあ
と思うところがけっこうありますよ〜。
永井さんのは永井哲学として読むとおもしろいですね。
ウィトゲンシュタインの本としては、ちと独我論を誇張しすぎな気がします。
『言語の限界』はちらっと読んだけど、あまり食指が動かなかったので、
なんとも言えません。
ウィトゲンシュタインの哲学の中でいつまでもくるくると回ってるだけの解釈本って、
結局ウィトゲンシュタインが彼の哲学の中でもっとも言いたかったことをまるでわかってないような感じがするので、『梯子を捨てる』ところに向けて、個々の解釈をしていくような本の
ほうがおもしろいですよ。
ウィトゲンシュタインは、哲学をやってきた結果「語りえぬもの」を見つけたんじゃなくて、
まず第一に「語りえぬもの」を示したくて彼の哲学が生まれたんですから。
そういう意味では、トルストイの本から入ったほうが良いのかも。
>>[9]
>P169の「世界が私の世界であることは、唯一の言語(私が理解する唯一の言語)の限界が私の世界の限界を意味することに示されている。」という『論考』からの引用に対して、「最後の部分は意味不明であるが、それは必然的に意味不明なのであると考えねばならない」というのもかなり無理なこじつけのように思えます。だったらなぜこの部分にだけそんな無意味な文章を書こうとヴィトゲンシュタインは思ったのでしょうか?ぜんぜん「意味不明」ではないように思えますが。
僕もそこの所はちょっと頭をかしげました。鬼界さんがどんな主旨を語っているのか、もう少し考えて疑問と向き合ってみたいと思います。
>P169の「世界が私の世界であることは、唯一の言語(私が理解する唯一の言語)の限界が私の世界の限界を意味することに示されている。」という『論考』からの引用に対して、「最後の部分は意味不明であるが、それは必然的に意味不明なのであると考えねばならない」というのもかなり無理なこじつけのように思えます。だったらなぜこの部分にだけそんな無意味な文章を書こうとヴィトゲンシュタインは思ったのでしょうか?ぜんぜん「意味不明」ではないように思えますが。
僕もそこの所はちょっと頭をかしげました。鬼界さんがどんな主旨を語っているのか、もう少し考えて疑問と向き合ってみたいと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ヴィトゲンシュタイン 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ヴィトゲンシュタインのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75492人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208295人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196025人