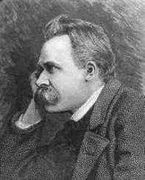ここでいう懐疑とは、懐疑主義ではなく、あくまでも「懐疑的な見方」のことですが、これを論駁する方法ってあると思いますか?
例えば、デカルトのいう「われ思う、故にわれあり」って有名な言葉ですけど、これは方法的懐疑であって、全ての疑えるものは徹底的に疑ったが、「疑っている自分」は疑えない、もしくは、「疑っている自分は確かに存在する」ということだと解釈していますが、「疑われるもの」「疑っている者」「それを疑っている者」は確かに永遠に連続し、「最終的には疑っている自分を疑う自分は疑えない」という結論になるところですが、ここでひとつ、「疑われるもの、疑っている者、それを疑う者とうこの「最後のもの」をあくまでも方法であって、絶対化しないとどうなるでしょうか?」つまり、「永遠の連鎖ではなく、傍観する感じ」です。
皆さんはどうお考えでしょうか?是非、ご意見をお聞かせ下さい。
例えば、デカルトのいう「われ思う、故にわれあり」って有名な言葉ですけど、これは方法的懐疑であって、全ての疑えるものは徹底的に疑ったが、「疑っている自分」は疑えない、もしくは、「疑っている自分は確かに存在する」ということだと解釈していますが、「疑われるもの」「疑っている者」「それを疑っている者」は確かに永遠に連続し、「最終的には疑っている自分を疑う自分は疑えない」という結論になるところですが、ここでひとつ、「疑われるもの、疑っている者、それを疑う者とうこの「最後のもの」をあくまでも方法であって、絶対化しないとどうなるでしょうか?」つまり、「永遠の連鎖ではなく、傍観する感じ」です。
皆さんはどうお考えでしょうか?是非、ご意見をお聞かせ下さい。
|
|
|
|
コメント(15)
>「疑われるもの」「疑っている者」「それを疑っている者」は確かに永遠に連続し・・・
一切の疑いうるものを疑う者の存在もまた疑って、その疑っている者の存在も疑えば、永遠に疑いうるという意味でしょうか。
>「最終的には疑っている自分を疑う自分は疑えない」という結論になるところですが・・・
デカルトはそういう疑いの無限連鎖のようなことは考えていないでしょう。
>ここでひとつ、「疑われるもの、疑っている者、それを疑う者」というこの「最後のもの」をあくまでも方法であって、絶対化しないとどうなるでしょうか? つまり、永遠の連鎖ではなく傍観する感じです。皆さんはどうお考えでしょうか? 是非、ご意見をお聞かせ下さい。
デカルトにおいては、いろいろなものを疑うということはあっても、疑っているということを疑うとか、疑っている者が存在するということを疑って、この疑っている者が存在すると認めそうになるのをさらに疑うというようなことはありませんでしたね。
なぜか。
今ここで疑っている、思っているということは確実で、そのこと自体を永遠に疑うなどということは言葉の上での遊びに過ぎないからでしょう。
一切の疑いうるものを疑う者の存在もまた疑って、その疑っている者の存在も疑えば、永遠に疑いうるという意味でしょうか。
>「最終的には疑っている自分を疑う自分は疑えない」という結論になるところですが・・・
デカルトはそういう疑いの無限連鎖のようなことは考えていないでしょう。
>ここでひとつ、「疑われるもの、疑っている者、それを疑う者」というこの「最後のもの」をあくまでも方法であって、絶対化しないとどうなるでしょうか? つまり、永遠の連鎖ではなく傍観する感じです。皆さんはどうお考えでしょうか? 是非、ご意見をお聞かせ下さい。
デカルトにおいては、いろいろなものを疑うということはあっても、疑っているということを疑うとか、疑っている者が存在するということを疑って、この疑っている者が存在すると認めそうになるのをさらに疑うというようなことはありませんでしたね。
なぜか。
今ここで疑っている、思っているということは確実で、そのこと自体を永遠に疑うなどということは言葉の上での遊びに過ぎないからでしょう。
歩いている、ということはそれが実は夢だったということによって否定される。
しかし、たとえ夢の中でも歩いていると「思っている」こと自体は疑い。
―――そう言えるか。
永井均さんは悪霊にあざむかれて、あたかもそう自分が思っているかのような心理状態が生じている、実は何も思っていないということが考えられるし、そう考えるのがそもそものデカルトの姿勢のはずだったのにデカルトはこの姿勢から後退し、「思っている」はもう疑いえないと考えてしまった、
と言う。
う〜ん。悪霊にあざむかれて「思っている」のも「思っている」のうちだとは言えないだろうか。
石のように何も考えもしない物の上に、悪霊がもし石が「自分は歩いている」という心理状態を付与することができるとしたら、その場合はその心理状態は石なんかにはありえない偽物だと言えるかもしれないが・・・
しかし、たとえ夢の中でも歩いていると「思っている」こと自体は疑い。
―――そう言えるか。
永井均さんは悪霊にあざむかれて、あたかもそう自分が思っているかのような心理状態が生じている、実は何も思っていないということが考えられるし、そう考えるのがそもそものデカルトの姿勢のはずだったのにデカルトはこの姿勢から後退し、「思っている」はもう疑いえないと考えてしまった、
と言う。
う〜ん。悪霊にあざむかれて「思っている」のも「思っている」のうちだとは言えないだろうか。
石のように何も考えもしない物の上に、悪霊がもし石が「自分は歩いている」という心理状態を付与することができるとしたら、その場合はその心理状態は石なんかにはありえない偽物だと言えるかもしれないが・・・
大辞林 第三版の解説
ろんばく【論駁】
( 名 ) スル
相手の意見や説の誤りを非難し、論じ返すこと。 「第十六条に就て−する所あるべし/天賦人権論 辰猪」
………………………………………………………………………………………………
論駁って、基本的には自説の正当性を証明することだから、
仮に「懐疑的な疑問」を提示されたときには、
「その疑問が誤りであることを論理的に提示する」ことなわけ。
1、自説に関する論理的問題、証明の不手際を示される
→「論理的正当性の追加証明」
2、自説に関して「前提条件の疑義」、前提そのもののデタラメさを示される
→「前提条件設定に関しての正当性の論理的証明」
懐疑がどうとか一切関係なく、
どんな説や論を提示しようがそれが出来が悪いのであれば、
当然いくらでも「デタラメさ」を指摘される。
それを懐疑とは呼ばない。
「信じる」方がただバカなだけ。
ろんばく【論駁】
( 名 ) スル
相手の意見や説の誤りを非難し、論じ返すこと。 「第十六条に就て−する所あるべし/天賦人権論 辰猪」
………………………………………………………………………………………………
論駁って、基本的には自説の正当性を証明することだから、
仮に「懐疑的な疑問」を提示されたときには、
「その疑問が誤りであることを論理的に提示する」ことなわけ。
1、自説に関する論理的問題、証明の不手際を示される
→「論理的正当性の追加証明」
2、自説に関して「前提条件の疑義」、前提そのもののデタラメさを示される
→「前提条件設定に関しての正当性の論理的証明」
懐疑がどうとか一切関係なく、
どんな説や論を提示しようがそれが出来が悪いのであれば、
当然いくらでも「デタラメさ」を指摘される。
それを懐疑とは呼ばない。
「信じる」方がただバカなだけ。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|