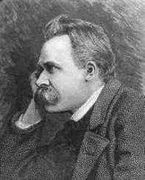はじめまして
自分では結論がでないのでおうかがいします
デカルトの
コギト=エルゴ=スム(cogito ergo sum)
「我思うゆえに我あり」
この表現に疑問を感じました
デカルトは
理性の力を以ってして、あらゆるものを、それが真の存在であるかを疑いました
いわゆる「方法的懐疑」ですね
そして、様々なものを疑って疑って疑い尽くした後に
疑っている自分自身は疑えない
つまり疑っている自分はその存在を確信できる
これがデカルトの真理「コギト=エルゴ=スム」です
しかし、私はそのことを考えていたら
私が私である事を疑っている私は私であるのかそうでないのか?
つまり、私が私であることを疑っている私は本当に真理であるのか
という疑問に出くわしました
どうなのでしょうね?
これを考えるにあたって
私は命題を2通りに分けました
1、私が私であることを疑っている私が私でないとき
この時は、私が私であることを疑っている私が私でないのだから
疑っている「私」は私以外の第三者ですね?
でも、私の事を内省できるのは二人称や三人称ではなく
一人称であることは明白です
2、私が私であることを疑っている私が私であるとき
私が私であることを疑っている私が私であるのならば、疑われている「私」は私ではないのでしょうか?
疑われている「私」が私ならば、疑っている私は誰なのでしょうか?
友人の中にはどちらも「私」であるとの見解を示す人がいましたが
「私」とは複数の精神的な存在の複合体なのでしょうか?
また、もしそうならばその存在根拠はあるのでしょうか?
私はまだまだ未熟者なので自分一人では答えに至ることができません
よろしければ皆さん考えてみて下さい
※このトピは以前にあった「私について」とは主旨を異すものです
|
|
|
|
コメント(39)
>> Erlko"nigさん
>1、私が私であることを疑っている私が、私でないとき。この時は、私が私であることを疑っている私が私でないのだから、疑っている「私」は私以外の第三者ですね?
「私が私であることを疑う」というのは、まずまったくの言葉の上での矛盾を露呈していることが知られますね。
それでもこの言葉を成り立たせるとしたら、最初の私と次の私は別のものだと想定しなければなりません。さらにこの「疑っている私が、私でないとき」という思考も、明らかに言葉の上での矛盾を露呈しており、同じように私という一つの言葉でいくつかの私を表しているのだと想定して初めて成り立つ文章だと思います。
結局、問題は疑う私と、疑われる対象としての私と、その両者をながめている私などをどのように心の構造の中に位置づけるか、ということだと思います。
>1、私が私であることを疑っている私が、私でないとき。この時は、私が私であることを疑っている私が私でないのだから、疑っている「私」は私以外の第三者ですね?
「私が私であることを疑う」というのは、まずまったくの言葉の上での矛盾を露呈していることが知られますね。
それでもこの言葉を成り立たせるとしたら、最初の私と次の私は別のものだと想定しなければなりません。さらにこの「疑っている私が、私でないとき」という思考も、明らかに言葉の上での矛盾を露呈しており、同じように私という一つの言葉でいくつかの私を表しているのだと想定して初めて成り立つ文章だと思います。
結局、問題は疑う私と、疑われる対象としての私と、その両者をながめている私などをどのように心の構造の中に位置づけるか、ということだと思います。
>2、私が私であることを疑っている私が私であるとき、私が私であることを疑っている私が私であるのならば、疑われている「私」は私ではないのでしょうか? 疑われている「私」が私ならば、疑っている私は誰なのでしょうか?
これはトピ主のみの疑問ではなく、古くはプラトンによって探究のアポリアとしてつかみ出されたものであり、
またカントが指摘した「不断の循環」(『純粋理性批判』)でもあり、
フィヒテが「私たちは循環の内に封じ込まれてしまう」(「知識学の概念について」)と見たものであり、
フッサールが『デカルト的省察』において指摘した反省に前提されている「自我分裂」の問題に他なりませんね。
これはトピ主のみの疑問ではなく、古くはプラトンによって探究のアポリアとしてつかみ出されたものであり、
またカントが指摘した「不断の循環」(『純粋理性批判』)でもあり、
フィヒテが「私たちは循環の内に封じ込まれてしまう」(「知識学の概念について」)と見たものであり、
フッサールが『デカルト的省察』において指摘した反省に前提されている「自我分裂」の問題に他なりませんね。
>「諸カテゴリーの根底にある意識の統一を、そこでは誤って客体である主体の直観だとみなしてしまっているのだ。そしてこれに実体のカテゴリーがあてがわれることになってしまった。」
(イマヌエル・カント)
諸カテゴリーの根底には意識の統一作用が働いている。
これによって私たちは諸カテゴリーがただ一つの操り手の手綱に結び付けられている感覚を持つことができる。
ところがデカルトはこの、諸カテゴリーの根底にある意識の統一というものを、あたかも私そのもの、主体そのものを直観しているのだと誤解してしまった。
その上でデカルトは、この意識の統一に実体のカテゴリーをあてがってしまい、ここに私が存在しているのは明らかだ、
と勇み足を踏んでしまったのである、
ということでしょうか?
(イマヌエル・カント)
諸カテゴリーの根底には意識の統一作用が働いている。
これによって私たちは諸カテゴリーがただ一つの操り手の手綱に結び付けられている感覚を持つことができる。
ところがデカルトはこの、諸カテゴリーの根底にある意識の統一というものを、あたかも私そのもの、主体そのものを直観しているのだと誤解してしまった。
その上でデカルトは、この意識の統一に実体のカテゴリーをあてがってしまい、ここに私が存在しているのは明らかだ、
と勇み足を踏んでしまったのである、
ということでしょうか?
トップの文章は、私が私を見つめるという時に常に浮かび上がってくる「見つめている私と見つめられている私は違うのか同じなのか」という問題だと思います。
主観が単に自足している状態から出て、何ものかを見つめようとする志向性として立ち上がる時、
もしその志向性が自分自身を見つめようとする観念に従うものである場合、
見つめる志向性と見つめられること、客体であることを想定される自分とは、内省というドラマの中の二人の役者である。
前者(見つめる志向性)も後者(見つめられること、客体であることを想定される自分)もともに、
主体を根底で範囲決定している統覚の、強調点の移動あるいは分節化の変更に根拠を持っている。
しかし志向性として私自身を見つめようとしている主観は、常に客体として想定される見つめられる側の自己よりも、分節化されているものはより小さいものだと言える。
主観が単に自足している状態から出て、何ものかを見つめようとする志向性として立ち上がる時、
もしその志向性が自分自身を見つめようとする観念に従うものである場合、
見つめる志向性と見つめられること、客体であることを想定される自分とは、内省というドラマの中の二人の役者である。
前者(見つめる志向性)も後者(見つめられること、客体であることを想定される自分)もともに、
主体を根底で範囲決定している統覚の、強調点の移動あるいは分節化の変更に根拠を持っている。
しかし志向性として私自身を見つめようとしている主観は、常に客体として想定される見つめられる側の自己よりも、分節化されているものはより小さいものだと言える。
「我思う故に我あり」というデカルトの言葉は大変有名です。
懐疑論の根拠となる「我=存在」をも疑ってしまうと、哲学の「自己否定」となってしまうからということがその言葉の動機なのでしょうか?
「存在論」というものは「哲学的主観」としての価値論であり、「唯物論」や「唯心論」という考え方もあります。
そのため、「存在」という言葉の意味も明確に定めることは困難でしょう。
どちらにしても、「存在論」というものは「哲学的な問いかけ」であり、「存在論」というものを「客観的」に議論するということは実益がないといわざるを得ません。
なぜなら、「哲学的な問いかけ」というものは、本来的には意味論としての問いかけだからです。
より詳しく言えば、自然科学の役割は自然界における事象を「客観的に記述する」ことであり、「存在論」というテーマは形而上学という範疇で議論されているものだということです。
存在論について「客観的に議論する」ということであれば、そのような試みは「現象学」や「科学哲学」という哲学のカテゴリーにおいて考察されるということになるでしょう。
デカルトの「我思う故に我あり」という言葉は、哲学的な問いかけをするための「立ち位置(=原点)」として重要な“ものさし”ですが、モノをはかる(存在論の「拠り所」となる)ための「ものさし=我」を正しく使えるようにするために同じ「ものさし=我」で測定して「我思う故に我あり」という合格検定証を与えたという印象を受けます。
「同義反復」という言葉がありますが、哲学的な問いかけというものは前述のように「主観的な価値論」がその本旨である以上、自然科学の立場から「人間原理」という言葉をあえて持ち出されるまでもなく、「我が道を行く」ということが哲学の使命ということなのでしょう。
極論ですが、人間の主体的な精神活動が「生活の糧」として魅力ある輝きを失わない限り、「哲学の使命」は時代の息吹を得て再生の時を迎えることでしょう。
懐疑論の根拠となる「我=存在」をも疑ってしまうと、哲学の「自己否定」となってしまうからということがその言葉の動機なのでしょうか?
「存在論」というものは「哲学的主観」としての価値論であり、「唯物論」や「唯心論」という考え方もあります。
そのため、「存在」という言葉の意味も明確に定めることは困難でしょう。
どちらにしても、「存在論」というものは「哲学的な問いかけ」であり、「存在論」というものを「客観的」に議論するということは実益がないといわざるを得ません。
なぜなら、「哲学的な問いかけ」というものは、本来的には意味論としての問いかけだからです。
より詳しく言えば、自然科学の役割は自然界における事象を「客観的に記述する」ことであり、「存在論」というテーマは形而上学という範疇で議論されているものだということです。
存在論について「客観的に議論する」ということであれば、そのような試みは「現象学」や「科学哲学」という哲学のカテゴリーにおいて考察されるということになるでしょう。
デカルトの「我思う故に我あり」という言葉は、哲学的な問いかけをするための「立ち位置(=原点)」として重要な“ものさし”ですが、モノをはかる(存在論の「拠り所」となる)ための「ものさし=我」を正しく使えるようにするために同じ「ものさし=我」で測定して「我思う故に我あり」という合格検定証を与えたという印象を受けます。
「同義反復」という言葉がありますが、哲学的な問いかけというものは前述のように「主観的な価値論」がその本旨である以上、自然科学の立場から「人間原理」という言葉をあえて持ち出されるまでもなく、「我が道を行く」ということが哲学の使命ということなのでしょう。
極論ですが、人間の主体的な精神活動が「生活の糧」として魅力ある輝きを失わない限り、「哲学の使命」は時代の息吹を得て再生の時を迎えることでしょう。
「もう一体、何が本当の動かざる真実で、何がたまたまそうなっているだけの不確かなもの、相対的なものなのか、一度徹底的に考えてやる!」と始められたデカルトの探究は、疑いうるものをどんどん弾いていって最後にどうしても疑いえないものが残るなら、それをしっかりとつかまえようという構想のもとに始められた。
すると、な〜に、後から後からあらゆるものは疑いうるようなものばかりだった。
そしてふと気づいた。
あらゆるものを疑う作業をしているこの作業の中心点たる自己意識は確かに有るじゃないか!
意識としての自己は有るじゃないか。これは、これだけはどうしたって疑いようがない、とデカルトは思った。
このデカルトの輝くような、喜びあふれる洞察は、果たして正しかったか。
そしてその喜びに満ちた洞察を表現した言葉は、真にその洞察を正しく反映させることができているか。ズレやほころびは無いか。
すると、な〜に、後から後からあらゆるものは疑いうるようなものばかりだった。
そしてふと気づいた。
あらゆるものを疑う作業をしているこの作業の中心点たる自己意識は確かに有るじゃないか!
意識としての自己は有るじゃないか。これは、これだけはどうしたって疑いようがない、とデカルトは思った。
このデカルトの輝くような、喜びあふれる洞察は、果たして正しかったか。
そしてその喜びに満ちた洞察を表現した言葉は、真にその洞察を正しく反映させることができているか。ズレやほころびは無いか。
>「私が私であることを疑っている私」が私であるのならば、疑われている私は私ではないのでしょうか?疑われている私が私ならば、疑っている私は誰なのでしょうか? 友人の中にはどちらも私であるとの見解を示す人がいましたが、私とは複数の精神的な存在の複合体なのでしょうか? また、もしそうならばその存在根拠はあるのでしょうか?
私は私自身を対象化して、その対象化された私と対象化した側の私を分岐させて考えうるものですね。
対象化された側の私は主体の座から客体の座へと降ろされることになる。
そしてこれらのことすべてが私の内部で行われ、私の内部で疑われる私と疑う私が分節化されている。
この両者を浮かべた基盤としての私もまた潜在している。
私は私自身を対象化して、その対象化された私と対象化した側の私を分岐させて考えうるものですね。
対象化された側の私は主体の座から客体の座へと降ろされることになる。
そしてこれらのことすべてが私の内部で行われ、私の内部で疑われる私と疑う私が分節化されている。
この両者を浮かべた基盤としての私もまた潜在している。
>>[28]
>「我思うゆえに我あり」。「我」と「思う」は同じものなのだから、ことさら「我」と言わなくてよいのではないか。「思うゆえに我あり」
私たちが普通にあると信じてしまっているさまざまなものをすべて実は疑いうるんだと考えて、いったんすべて括弧に入れるなら、
思いが巡らされている、表象されている、という直接経験だけがあって、U さんがおっしゃるように「我と思いは同じだ」というのは必ずしも自明ではないのではないでしょうか。
「思っている主体、表象している主体は誰か」という反省的思考が生起してきて初めて「これを我、私と呼ぶのだ」という命名がなされるのではないでしょうか。
我と思いはそもそも同じではなく、展開しているさまざまな思いの帰属先として見定められる主語として我、私が立ち上がってくるのではないでしょうか。
>「我思うゆえに我あり」。「我」と「思う」は同じものなのだから、ことさら「我」と言わなくてよいのではないか。「思うゆえに我あり」
私たちが普通にあると信じてしまっているさまざまなものをすべて実は疑いうるんだと考えて、いったんすべて括弧に入れるなら、
思いが巡らされている、表象されている、という直接経験だけがあって、U さんがおっしゃるように「我と思いは同じだ」というのは必ずしも自明ではないのではないでしょうか。
「思っている主体、表象している主体は誰か」という反省的思考が生起してきて初めて「これを我、私と呼ぶのだ」という命名がなされるのではないでしょうか。
我と思いはそもそも同じではなく、展開しているさまざまな思いの帰属先として見定められる主語として我、私が立ち上がってくるのではないでしょうか。
思いが展開されているその様を一歩引いて眺めている眼。この眼をたくましく育て、分化することができないでいる時、人は思いそのものとまったく同一化してしまっていて、展開されている思いこそ自分だと思い込む。
しかし、思いというものは確かに主語と区別されるべき述語だという文法上の反省が生じると、思いの帰属先として超越論的に主語が措定されるに至る。
とはいえ、これはまだ文法的操作がもたらす文法的認識でしかなく、その主語自体を十分に味わい体認するには至っていない。
思い自体とは分化されて、思いを眺め観察(サティ、ヴィパッサナー)する眼の側にこそ私の実質を求めようとする進歩がさらに進捗すると、この観察する眼の背後に回り込んで、この観察の眼を今度は観察できないかという微妙な実践に取り組むことになる。
しかし、思いというものは確かに主語と区別されるべき述語だという文法上の反省が生じると、思いの帰属先として超越論的に主語が措定されるに至る。
とはいえ、これはまだ文法的操作がもたらす文法的認識でしかなく、その主語自体を十分に味わい体認するには至っていない。
思い自体とは分化されて、思いを眺め観察(サティ、ヴィパッサナー)する眼の側にこそ私の実質を求めようとする進歩がさらに進捗すると、この観察する眼の背後に回り込んで、この観察の眼を今度は観察できないかという微妙な実践に取り組むことになる。
バートランド・ラッセルは『哲学入門』において言う。
デカルトの議論を援用する際には注意が必要だと。
厳密な確実性をもとめてデカルトの議論を振り返るなら、「われ思う、ゆえにわれ有り」においてデカルトは余分なことまで言ってしまっていると。
例えば、テーブルが茶色いのを見ている時、「茶色を見ている私がいる」が確実なのではなく、「茶色が見られている」が確実なことなのであって、もちろんこれは茶色を見ている者を含むだろうが、決して〈われ〉と呼ばれ存在し続ける人物まで含むものではないのだ、と。
茶色が見られているというこの直接的な経験の確実性は、この茶色を見ている者がもしかしたら極めて刹那的な存在で次の瞬間には別の経験をする人物とあくまでも区別される可能性を排除するものではない、と。
デカルトの議論を援用する際には注意が必要だと。
厳密な確実性をもとめてデカルトの議論を振り返るなら、「われ思う、ゆえにわれ有り」においてデカルトは余分なことまで言ってしまっていると。
例えば、テーブルが茶色いのを見ている時、「茶色を見ている私がいる」が確実なのではなく、「茶色が見られている」が確実なことなのであって、もちろんこれは茶色を見ている者を含むだろうが、決して〈われ〉と呼ばれ存在し続ける人物まで含むものではないのだ、と。
茶色が見られているというこの直接的な経験の確実性は、この茶色を見ている者がもしかしたら極めて刹那的な存在で次の瞬間には別の経験をする人物とあくまでも区別される可能性を排除するものではない、と。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|