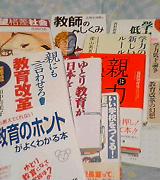全国一斉テスト「中下位想定の問題」 学力低下把握 効果は…
4月25日8時0分配信 産経新聞
24日、全国一斉に行われた43年ぶりの学力テスト。文部科学省は「学力の土台・基盤となる力に絞って出題した」とし、生活に即した問題で考える力を重視したが、子供の弱点の計算問題などがやさしく、学力低下を知るのは難しい、との指摘も出ている。子供たちの学習実態など背景調査を深めたり、指導法改善の検証に効果的に使うべきだと専門家はアドバイスしている。
今回の試験は小学6年で、基礎問題「A」が国語20分、算数20分、応用力をみる「B」が国語、算数が各40分。中学3年はいずれも45分だった。
文科省が「生活の中で使える問題を選んだ」というようにチラシを読み解いたり、ケーキの割り引きを計算させるなど工夫された問題が多い一方、専門家からは「中下位を想定した問題レベルだ」との意見がある。
桜美林大の芳沢光雄教授(数学教育)は、6年生の問題について「2つの数字の計算が多い。子供が弱いのは3つの数字による四則混合計算なので、これではあまり意味をもたないのではないか」と指摘する。大量採点のため「中3の証明問題も穴埋めだし、センター試験のような5択問題が多いのはいかがなものか」と疑問を呈する。
埼玉県内の数学教師は「算数・数学Aはやさしい問題。これでは学力低下は計れないし、得点の二極分化は表れないだろう」と話す。
文科省でも「Aは平均が高くなるだろう」とみており、一部に43年前の問題はあるが、データの比較は難しいと漏らす。
むしろ、これからこの結果をどう生かすかが大事なようだ。
東大の市川伸一教授(教育心理学)は、行政がデータを取るだけなら抽出調査で十分だとして、全員を対象としたテストには否定的な姿勢を示してきた。
だが、今回の結果をフィードバックさせ子供の学習改善に役立てようという目的については評価する。
市川教授は、学力テストのデータを利用しての学力改善策として、(1)要因分析(2)新しい指導法の検証−を提案する。
(1)は学校や教育委員会で、独自に子供の生活や学習実態をより細かく調査して、成績が良かったり、学力向上の理由を具体的に知る(2)は自校などで新たな指導法を試み、効果があったかを検証する−べきだという。
「効果的な使い方ができれば進んでテストを受けるようになるのではないか」と市川教授。
芳沢教授は「Bでは理科と数学を融合させた問題や、よく読んで状況把握しないと答えられない文章題など、算数や数学の垣根を越えた良い問題がある。こういう問題が解けるように、学校で指導していけば学力向上に役立つ」としている。
4月25日8時0分配信 産経新聞
24日、全国一斉に行われた43年ぶりの学力テスト。文部科学省は「学力の土台・基盤となる力に絞って出題した」とし、生活に即した問題で考える力を重視したが、子供の弱点の計算問題などがやさしく、学力低下を知るのは難しい、との指摘も出ている。子供たちの学習実態など背景調査を深めたり、指導法改善の検証に効果的に使うべきだと専門家はアドバイスしている。
今回の試験は小学6年で、基礎問題「A」が国語20分、算数20分、応用力をみる「B」が国語、算数が各40分。中学3年はいずれも45分だった。
文科省が「生活の中で使える問題を選んだ」というようにチラシを読み解いたり、ケーキの割り引きを計算させるなど工夫された問題が多い一方、専門家からは「中下位を想定した問題レベルだ」との意見がある。
桜美林大の芳沢光雄教授(数学教育)は、6年生の問題について「2つの数字の計算が多い。子供が弱いのは3つの数字による四則混合計算なので、これではあまり意味をもたないのではないか」と指摘する。大量採点のため「中3の証明問題も穴埋めだし、センター試験のような5択問題が多いのはいかがなものか」と疑問を呈する。
埼玉県内の数学教師は「算数・数学Aはやさしい問題。これでは学力低下は計れないし、得点の二極分化は表れないだろう」と話す。
文科省でも「Aは平均が高くなるだろう」とみており、一部に43年前の問題はあるが、データの比較は難しいと漏らす。
むしろ、これからこの結果をどう生かすかが大事なようだ。
東大の市川伸一教授(教育心理学)は、行政がデータを取るだけなら抽出調査で十分だとして、全員を対象としたテストには否定的な姿勢を示してきた。
だが、今回の結果をフィードバックさせ子供の学習改善に役立てようという目的については評価する。
市川教授は、学力テストのデータを利用しての学力改善策として、(1)要因分析(2)新しい指導法の検証−を提案する。
(1)は学校や教育委員会で、独自に子供の生活や学習実態をより細かく調査して、成績が良かったり、学力向上の理由を具体的に知る(2)は自校などで新たな指導法を試み、効果があったかを検証する−べきだという。
「効果的な使い方ができれば進んでテストを受けるようになるのではないか」と市川教授。
芳沢教授は「Bでは理科と数学を融合させた問題や、よく読んで状況把握しないと答えられない文章題など、算数や数学の垣根を越えた良い問題がある。こういう問題が解けるように、学校で指導していけば学力向上に役立つ」としている。
|
|
|
|
コメント(15)
>事前対策をやってましたよ
中止されるまでは、
カンニングを容認する教師
成績の悪い子を欠席させテストを受けさえない教師
反対活動が行き過ぎて逮捕された教師
等々、がいたそうです。
競争を煽るという懸念がありますが、事前対策など、
そういうインチキをやるのは現場の教師なんですよね。
普段、子どもに学力がつかないような指導をしておいて、
テストの直前だけそういうことをして誤魔化そう
というやましい精神がいただけません。
この学力テスト、「実施する意義」は大いにあります。
例えば、これまでの教育行政が子どもの学力状況など
しっかりとデータや実態に基づいて改善されてこなかった
という実態です。
とはいえ、結果の公表は各都道府県レベルにとどめる
としながらも、開示の裁量は学校ごとに任せる
というダブルスタンダードが問題です。
文科省は都道府県レベルにとどめるとしてますが、
各学校が独自の判断で結果を公表して、
それが結果として競争を煽るような結果になっても
文科省は「各学校の判断なので」ということで
黙りを決め込むこと必至です。
あとは、設問の問題点ですが、
冊子Bの問題は、知識を活用する問題で
比較的良問が多いとされています。
問題は冊子Aの問題です。
簡単すぎるという指摘があります。
芳沢光雄教授も指摘しているように
「2つの数字の計算が多い。
子供が弱いのは3つの数字による四則混合計算なので、
これではあまり意味をもたないのではないか」
と述べています。
1.8+2.5(出題されていると予想されるレベル)
1.8×0.5+2.5(実際にはこれくらいのレベルが欲しい)
おそらく上の問題の正答率は、8割程度でしょう。
しかし下の問題の正答率は5割か下手をしたら4割程度でしょう。
下の問題は、ゆとり教育以前の教科書では
当たり前に教えられていた問題です。
現行では、教えるかどうかは各学校に委ねられていますが、
考える力を重視しているのならば
下の問題も解けるようになっているはずです。
文科省がそういうことをしないのは、
下の問題の正答率がボロボロなのを知っているからでしょう。
簡単な問題を出題しておいて。結果が出た時に
「ゆとり世代の学力は良好」
と、されたらたまりません。
文科省自身はゆとり教育を失政とは思っていないので。
中止されるまでは、
カンニングを容認する教師
成績の悪い子を欠席させテストを受けさえない教師
反対活動が行き過ぎて逮捕された教師
等々、がいたそうです。
競争を煽るという懸念がありますが、事前対策など、
そういうインチキをやるのは現場の教師なんですよね。
普段、子どもに学力がつかないような指導をしておいて、
テストの直前だけそういうことをして誤魔化そう
というやましい精神がいただけません。
この学力テスト、「実施する意義」は大いにあります。
例えば、これまでの教育行政が子どもの学力状況など
しっかりとデータや実態に基づいて改善されてこなかった
という実態です。
とはいえ、結果の公表は各都道府県レベルにとどめる
としながらも、開示の裁量は学校ごとに任せる
というダブルスタンダードが問題です。
文科省は都道府県レベルにとどめるとしてますが、
各学校が独自の判断で結果を公表して、
それが結果として競争を煽るような結果になっても
文科省は「各学校の判断なので」ということで
黙りを決め込むこと必至です。
あとは、設問の問題点ですが、
冊子Bの問題は、知識を活用する問題で
比較的良問が多いとされています。
問題は冊子Aの問題です。
簡単すぎるという指摘があります。
芳沢光雄教授も指摘しているように
「2つの数字の計算が多い。
子供が弱いのは3つの数字による四則混合計算なので、
これではあまり意味をもたないのではないか」
と述べています。
1.8+2.5(出題されていると予想されるレベル)
1.8×0.5+2.5(実際にはこれくらいのレベルが欲しい)
おそらく上の問題の正答率は、8割程度でしょう。
しかし下の問題の正答率は5割か下手をしたら4割程度でしょう。
下の問題は、ゆとり教育以前の教科書では
当たり前に教えられていた問題です。
現行では、教えるかどうかは各学校に委ねられていますが、
考える力を重視しているのならば
下の問題も解けるようになっているはずです。
文科省がそういうことをしないのは、
下の問題の正答率がボロボロなのを知っているからでしょう。
簡単な問題を出題しておいて。結果が出た時に
「ゆとり世代の学力は良好」
と、されたらたまりません。
文科省自身はゆとり教育を失政とは思っていないので。
ヤバイです。
問題用紙見ましたが、とてもじゃないけど簡単すぎます。ほぼ全員ができていてもおかしくない問題がかなりみられます。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/index.htm
算数A問題
1
(1)28+72
(2)27×3.4
(3)9.3×0.8
(4)12÷0.6
(5)1−5/8
(6)3/7+4/7
(7)6+0.5×2
→ひき算なら105−27とか3桁のひき算、
あと小数第2位までのたし算ひき算、
分数と小数が混じったたし算ひき算、
かっこを使った計算、などを入れないと。
分数のたし算ひき算なんて、
バカにしているのかと思いましたよ。
(通分が必要な加減は習っていないのである意味当然ですが)
3
(1)1を10等分した目もりの中から、7/10を選ぶ
→やはり小数第2位くらいの数を出題しないと、理解できているかどうかはわからない。
4
210×0.6の式で求められる問題を選ぶ
→比べる量を求める問題ではなく、もとにする量を求める問題の方が良い。
5次の図形の面積を求める式と答え(図あり)
(1)底辺4?、高さ6?の平行四辺形
(2)底辺6?、高さ4?の三角形
(3)半径が10?の円(円周率は3.14)
→図が描いてあること自体、すでに易しい。平行四辺形と三角形の
底辺と高さの数値が同じ(逆にはなっているが)なのが解せない。円周率が3.14なのは当然だが、学校では計算機を使って計算しているはず。解けるのだろうか?
数学A問題
1
(1)2/3÷5/7
→小学生の問題かと思いました。のっけから簡単すぎます。せめて約分が必要な数字にするとか、小数と分数と混ぜるとか、やりようがあっただろうに。
(3)2×(−3)^2
(4)8−5×(−6)
→簡単すぎる。底辺校の私立でもこんな簡単な問題を入試で出すような学校はない。なぜ小数や分数を入れない?
5
(3)見取図で示された立体(円錐)の展開図を選ぶ
→展開図は描かせないと。
6
(1)直線l、mは平行で、角x(70度の同位角)の大きさ(ダミーの数字あり)
→ダミー数字があるのは良いが、答えの数値が図の中に描いてある角度を問うのはどうかと。
(2)同一の弧に対する円周角が60度の時の中心角。
→せめて円周角を鈍角にするとか、円周角の頂点が弧側にある時とかにすべき。そうでないと8、9割方の子が、パッと問題を見ただけで2倍するだけでいいということがわかってしまう。
(3)「AB//DC、AB=DC」が表しているもの(文章)を選ぶ
→そのまんますぎます。
7
(1)平行四辺形の2組の向かい合う辺はそれぞれ等しいことを証明しました(証明文、略)。ある学級で、この証明について下のア〜エのような意見が出されました。正しいものを1つ選ぶ
ア.上のように証明しても、平行四辺形の2組の向かい合う辺がそれぞれ等しいかどうかは測って確認しなければならない。
イ.上のように証明しても、ほかの平行四辺形については、2組の向かい合う辺がそれぞれ等しいことを、もう一度証明する必要がある。
ウ.上の証明から、すべての平行四辺形で、2組の向かい合う辺はそれぞれ等しいことがわかる。
エ.上の証明から、台形の2組の向かい合う辺はそれぞれ等しいこともわかる。
→選択肢が不自然すぎる。
9
(1)yがxに比例するときのxとyの関係について選ぶ
→教科書的な定義そのまんま、9割方の子ができて当たり前の問題だろう。せめて反比例で問うべき。
(2)下の図の直線は、比例のグラフを表しています。このグラフについて、yをxの式で表しなさい(答えy=2x)。
→これも9割方の子ができて当たり前の問題。比例定数を4/3といった分数にするか、負の数にするなど工夫のしようがあったはず。
10
(1)下の表はyがxに反比例する関係を表したものです。
x −2 −1 0 1 2 3
y −6 −12 × 12 6 □
(1)□にあてはまる数を求める
→旧課程では小6でもできる問題(負の数の部分は除きますが)。中3で問うようなレベルの問題ではない。
(2)上の表のxとyの関係を表すグラフを選ぶ
→双曲線が2つ、比例のグラフが1つ、一次関数のグラフが1つ、反比例っぽいカクカクのグラフが1つ。比例定数が正の数の反比例のグラフ(ただ反比例のデフォルトのグラフ)を選ぶだけ。
11
(1)yがxの一次関数であるものがあります。正しいものを選ぶ
ア.面積が60平方?の長方形で、たての長さがx?のときの横の長さy?
イ.水が5リットル入っている水そうに、毎分3リットルの割合でいっぱいになるまで水を入れる時、水を入れ始めてからx分後の水の量yリットル
ウ.身長x?の人の体重y?
エ.6mのリボンをx人で同じ長さに分ける時の1人分の長さym
オ.午後x時の気温y度
→選択肢が易しすぎる上に、ウとオは選択肢として明らかに不適切。
12
学さんが家から公園まで進んだ時のグラフ
(1)グラフから、家を出発して2分後までは100mを一定の速さで進んだことがわかります。家を出発してから2分間進んだ速さは毎分何mですか。
→数字が簡単すぎる。小学生でも解ける。
13
直線1は方程式x+y=5のグラフ、直線2は方程式x−y=1のグラフです。
グラフの点AからEの間に連立方程式の解を座標に持つ点を選べ(ここでは便宜上グラフを文章で表現)
ア.点A(直線1とy軸との交点)
イ.点B(直線1と2の交点)
ウ.点C(直線1とx軸との交点)
エ.点D(直線2とx軸との交点)
オ.点E(直線2とy軸との交点)
→やはり簡単すぎる。
14
(1)1の目が出る確率が1/6であるさいころがあります。このさいころを投げるとき、どのようなことが言えるか選ぶ
ア.5回投げて、1の目が1回も出なかったとすれば、次に投げると必ず1の目が出る。
イ.6回投げるとき、そのうち1回は必ず1の目が出る。
ウ.6回投げるとき、1から6までの目が必ず1回ずつ出る。
エ.30回投げるとき、そのうち1の目は必ず5回出る。
オ.3000回投げるとき、1の目はおよそ500回出る。
→ア〜エまで「必ず」という言葉が使ってあって、オだけ「およそ」が使ってある。選択肢を見ただけで答えがわかるという典型的な愚問。
問題用紙見ましたが、とてもじゃないけど簡単すぎます。ほぼ全員ができていてもおかしくない問題がかなりみられます。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/index.htm
算数A問題
1
(1)28+72
(2)27×3.4
(3)9.3×0.8
(4)12÷0.6
(5)1−5/8
(6)3/7+4/7
(7)6+0.5×2
→ひき算なら105−27とか3桁のひき算、
あと小数第2位までのたし算ひき算、
分数と小数が混じったたし算ひき算、
かっこを使った計算、などを入れないと。
分数のたし算ひき算なんて、
バカにしているのかと思いましたよ。
(通分が必要な加減は習っていないのである意味当然ですが)
3
(1)1を10等分した目もりの中から、7/10を選ぶ
→やはり小数第2位くらいの数を出題しないと、理解できているかどうかはわからない。
4
210×0.6の式で求められる問題を選ぶ
→比べる量を求める問題ではなく、もとにする量を求める問題の方が良い。
5次の図形の面積を求める式と答え(図あり)
(1)底辺4?、高さ6?の平行四辺形
(2)底辺6?、高さ4?の三角形
(3)半径が10?の円(円周率は3.14)
→図が描いてあること自体、すでに易しい。平行四辺形と三角形の
底辺と高さの数値が同じ(逆にはなっているが)なのが解せない。円周率が3.14なのは当然だが、学校では計算機を使って計算しているはず。解けるのだろうか?
数学A問題
1
(1)2/3÷5/7
→小学生の問題かと思いました。のっけから簡単すぎます。せめて約分が必要な数字にするとか、小数と分数と混ぜるとか、やりようがあっただろうに。
(3)2×(−3)^2
(4)8−5×(−6)
→簡単すぎる。底辺校の私立でもこんな簡単な問題を入試で出すような学校はない。なぜ小数や分数を入れない?
5
(3)見取図で示された立体(円錐)の展開図を選ぶ
→展開図は描かせないと。
6
(1)直線l、mは平行で、角x(70度の同位角)の大きさ(ダミーの数字あり)
→ダミー数字があるのは良いが、答えの数値が図の中に描いてある角度を問うのはどうかと。
(2)同一の弧に対する円周角が60度の時の中心角。
→せめて円周角を鈍角にするとか、円周角の頂点が弧側にある時とかにすべき。そうでないと8、9割方の子が、パッと問題を見ただけで2倍するだけでいいということがわかってしまう。
(3)「AB//DC、AB=DC」が表しているもの(文章)を選ぶ
→そのまんますぎます。
7
(1)平行四辺形の2組の向かい合う辺はそれぞれ等しいことを証明しました(証明文、略)。ある学級で、この証明について下のア〜エのような意見が出されました。正しいものを1つ選ぶ
ア.上のように証明しても、平行四辺形の2組の向かい合う辺がそれぞれ等しいかどうかは測って確認しなければならない。
イ.上のように証明しても、ほかの平行四辺形については、2組の向かい合う辺がそれぞれ等しいことを、もう一度証明する必要がある。
ウ.上の証明から、すべての平行四辺形で、2組の向かい合う辺はそれぞれ等しいことがわかる。
エ.上の証明から、台形の2組の向かい合う辺はそれぞれ等しいこともわかる。
→選択肢が不自然すぎる。
9
(1)yがxに比例するときのxとyの関係について選ぶ
→教科書的な定義そのまんま、9割方の子ができて当たり前の問題だろう。せめて反比例で問うべき。
(2)下の図の直線は、比例のグラフを表しています。このグラフについて、yをxの式で表しなさい(答えy=2x)。
→これも9割方の子ができて当たり前の問題。比例定数を4/3といった分数にするか、負の数にするなど工夫のしようがあったはず。
10
(1)下の表はyがxに反比例する関係を表したものです。
x −2 −1 0 1 2 3
y −6 −12 × 12 6 □
(1)□にあてはまる数を求める
→旧課程では小6でもできる問題(負の数の部分は除きますが)。中3で問うようなレベルの問題ではない。
(2)上の表のxとyの関係を表すグラフを選ぶ
→双曲線が2つ、比例のグラフが1つ、一次関数のグラフが1つ、反比例っぽいカクカクのグラフが1つ。比例定数が正の数の反比例のグラフ(ただ反比例のデフォルトのグラフ)を選ぶだけ。
11
(1)yがxの一次関数であるものがあります。正しいものを選ぶ
ア.面積が60平方?の長方形で、たての長さがx?のときの横の長さy?
イ.水が5リットル入っている水そうに、毎分3リットルの割合でいっぱいになるまで水を入れる時、水を入れ始めてからx分後の水の量yリットル
ウ.身長x?の人の体重y?
エ.6mのリボンをx人で同じ長さに分ける時の1人分の長さym
オ.午後x時の気温y度
→選択肢が易しすぎる上に、ウとオは選択肢として明らかに不適切。
12
学さんが家から公園まで進んだ時のグラフ
(1)グラフから、家を出発して2分後までは100mを一定の速さで進んだことがわかります。家を出発してから2分間進んだ速さは毎分何mですか。
→数字が簡単すぎる。小学生でも解ける。
13
直線1は方程式x+y=5のグラフ、直線2は方程式x−y=1のグラフです。
グラフの点AからEの間に連立方程式の解を座標に持つ点を選べ(ここでは便宜上グラフを文章で表現)
ア.点A(直線1とy軸との交点)
イ.点B(直線1と2の交点)
ウ.点C(直線1とx軸との交点)
エ.点D(直線2とx軸との交点)
オ.点E(直線2とy軸との交点)
→やはり簡単すぎる。
14
(1)1の目が出る確率が1/6であるさいころがあります。このさいころを投げるとき、どのようなことが言えるか選ぶ
ア.5回投げて、1の目が1回も出なかったとすれば、次に投げると必ず1の目が出る。
イ.6回投げるとき、そのうち1回は必ず1の目が出る。
ウ.6回投げるとき、1から6までの目が必ず1回ずつ出る。
エ.30回投げるとき、そのうち1の目は必ず5回出る。
オ.3000回投げるとき、1の目はおよそ500回出る。
→ア〜エまで「必ず」という言葉が使ってあって、オだけ「およそ」が使ってある。選択肢を見ただけで答えがわかるという典型的な愚問。
B問題(活用)の中には良問がちらほらみられるものの、
A問題(知識)はどれもこれも簡単すぎる。
ゆとり教育でのけた数制限があるとはいえ数値が整数ばかり、
中学生の問題に至っては、小学生の問題かと見間違えるほど。
あまりにもバカにしすぎている。
進学塾の生徒に解かせたら、ほぼ全員が満点、
塾に通っていない子でも8割はとれないとまずいでしょう。
簡単な問題を出しておいて、
「ゆとり教育で学習指導要領の内容が十分定着している」
というみえみえの見解を文科省が出すのは目に見えている。
77億円もかけてやるような内容の調査ではない。
はっきり言ってがっかり。
A問題(知識)は簡単すぎてお話にならず、
B問題(活用)は良問があるものの
例えば「連続する5つの自然数(数学B)」といった、
進学塾の問題集でも出てこないような問題があったり、
やたら図表を読み取らせる問題が多かったりと、
難しい問題が混在。
総じて、
A問題(知識)は良好な結果でB問題(活用)は難あり、
といった感じで、
「学習内容を削減しても知識の部分は問題なし」
「むしろ、知識を活用する力が弱い」
「よって、教科の学習でも、総合的な学習の時間でも、
日常生活と関連づけた体験を重視した教育に
よりいっそう力を注ぐべき」
つまり、
「ゆとり教育の方向性が正しい」
という結論を誘導するような作りになっていると言わざるを得ない。
A問題(知識)はどれもこれも簡単すぎる。
ゆとり教育でのけた数制限があるとはいえ数値が整数ばかり、
中学生の問題に至っては、小学生の問題かと見間違えるほど。
あまりにもバカにしすぎている。
進学塾の生徒に解かせたら、ほぼ全員が満点、
塾に通っていない子でも8割はとれないとまずいでしょう。
簡単な問題を出しておいて、
「ゆとり教育で学習指導要領の内容が十分定着している」
というみえみえの見解を文科省が出すのは目に見えている。
77億円もかけてやるような内容の調査ではない。
はっきり言ってがっかり。
A問題(知識)は簡単すぎてお話にならず、
B問題(活用)は良問があるものの
例えば「連続する5つの自然数(数学B)」といった、
進学塾の問題集でも出てこないような問題があったり、
やたら図表を読み取らせる問題が多かったりと、
難しい問題が混在。
総じて、
A問題(知識)は良好な結果でB問題(活用)は難あり、
といった感じで、
「学習内容を削減しても知識の部分は問題なし」
「むしろ、知識を活用する力が弱い」
「よって、教科の学習でも、総合的な学習の時間でも、
日常生活と関連づけた体験を重視した教育に
よりいっそう力を注ぐべき」
つまり、
「ゆとり教育の方向性が正しい」
という結論を誘導するような作りになっていると言わざるを得ない。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ゆとり教育にもの申す! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-