ども。
もしもお待ちいただいていた方がいたらごめんなさい。
先月30日に広尾のthe Jewish Community of Japanで行われた『過ぎ越しの祭り』Passoverに参加した(というより間近で目撃、といった方が正しいかもしれませんが)のご報告をいたします。
不肖せんまつ先週末から連夜の夜桜見物でちとかぜをひきました。
なので、ぽちぽち書き込みしますので、お許しください。。。
『過ぎ越し』につきましては先のトピックの方にもいろいろリンク貼りましたのでいまさら、なんですが、とりあえず「前回までのあらすじ」的に”過ぎ越しって何?”は以下をご参照ください。
http://
…しかし、ここを読んだからといって一応体験(いえ目撃)してきた拙者でも
なんだかよくわかりません(このはがゆさみたいなのは芥川賞を受賞した米谷ふみ子さんの『過ぎ越しの祭り』という小説によくあらわれてます)。
それが『ユダヤ教』なのかもしれません。
ので、ここから書くことでよくわからない、と思われたら、
ゴメンナサイ、よくわからないのが正解です。
でも、一生懸命書くから許してね(のっけからEXCUSE ME)。

ユダヤ教…本当に名前はよく知っているのにでは何、といわれたらわかりません。私は内に向かう厳しい宗教というイメージでした。でも、今回この言葉を別のいい方するとしたら「とても家族的な宗教、集団」という印象を受けました。
それはGoogle創設者のセルゲイ・ブリン(彼はソビエト出身のユダヤ人です)のお父さんが"Jewishnessは genetic(遺伝)だ”と言ってるんですが、本当にそう思いました。外部のものにはそこはかとなく不思議というかミラクルワールドなのです。
でも、それがある意味ユダヤ教さんの本質のような気もします。
かく言うわたくしめ、Niki’s根性(?!)が出てしまい、ちょっとしたセキュリティチェック(刃物等の持ち込みは禁止です)のあと、シナゴークに入ったとき、受付の方が親切でこちらの名前を覚えていてくださったことに気をよくし「食べ物写真とってもいいですか?」と無知丸出しの質問をし
”No! This is holy festival!!"
と当たり前ながら厳しいお言葉を頂戴し、以降とんだおっちょこちょいが来ちゃった、と思われたのか、プチ無視されながら、でも逆に静かに観察させていただきました(そんなわけで写真はありません)。
考えたら「シナゴーク」ですから。
勢い(ただただどんな食事=セダーを食べるのか知りたかった )で出かけてしまいましたが、儀式に参加させて下すった寛容に感謝するばかりです。
)で出かけてしまいましたが、儀式に参加させて下すった寛容に感謝するばかりです。
おそらく一生に一度の体験です。今になってちょっと蛮勇だったと反省しております。
でも、
もしチャンスがあったらいずこかで体験するのはいいことかもしれません。
ちなみに日本ヘブライ協会というお茶の水などにヘブライ語やアラム語を教えているカルチャーセンターがあるようで、そちらでは4月6日に非教徒に過ぎ越しを体験させてくれる企画があったようで、もしぜひとも、というのでしたらそちらへ行った方が解説もあってわかりやすい、かもしれませんね。来年のご参考までに。
さてさて前置きが長くなりましたが、
3月30日、
広尾の東京女学館のお隣に位置するシナゴークに私の好奇心にお付き合いいただいたAさんと道に迷い迷いながら、でもわくわくして伺いました。
建物は昨年新築されたとてもモダンな外観で、星の印がなかったら見逃してしまいそうです。
ちなみに
日本で最初のシナゴークは長崎に明治の初めに出来たようです。
ここはアシュケナディ系(ヨーロッパ出身のユダヤ人)の人たちが作ったようですが、その後は神戸にセファルディ系(中東出身)のシナゴークが出来たそうで、今は東京、横浜、神戸、名古屋にあるようです。
…キリスト教に比べると圧倒的な少なさ、というか、一応そうではない、ということらしいですが、「ユダヤ人」さんでないと行きにくい感はありますよね。
ちなみに伝統の考え方ではお母さんがユダヤ人でないとユダヤ人と見なさなかったそうです(どちらかが、でよいになったのは80年代以降)。
おっとっと
また話がそれましたが、
それたついでにユダヤ教の三大祭りのことを書きます。
(すいません、ここに書いてるっていうのは第一に自分がわかりたい、というのがあるので、いろいろ脱線してごめんなさい)。
それは
ぺサハ(passover) 春 最初の穀物(大麦)収穫を祝う
シャブオット(七週祭)初夏 春蒔き小麦と果物の収穫を祝う
スッコート(仮庵祭) 秋 一年を締めくくる収穫の祭り
の三つで、祭りはシナゴークだけでなく家庭でも行われるそうで、Nikiさんたちがいらっしゃったのはそちらに近いスタイルなのでは、と思います。
で、この中で一番有名なのがぺサハで、その祝宴がセデルなんですね。
イスラエルではPassoverの初日に、ディアスポラでは2日目に行われる御馳走の宴、という規定もあるそうです。
で、
この三つの祭りの共通点は「神の前でも喜び」だそうで、歴史的であり宗教であり、さらに農業行事的でもあり、さらに楽しいというものなんですね。
そのせいか
祭りを執り行うラビがワインでどんどん真っ赤になって
「昨日は酔っ払っちゃって忘れたことがあるから今言うね〜」
てな具合に楽しそーにしていたり、ラビの横に座っていた青少年たちもワイン飲んじゃってトローンとしてたり、聖なる祈りの合間に結構家庭内での食卓風景みたいな展開もありました。
…と、、まったく内容に入ることなく今晩はここまででお許しください。
ちょっとかぜ薬が効いてきちゃいましたの模様です。
なお、
次回への予習にお時間あったら
『旧約聖書』の出エジプト記が参考になると思います。
ある意味数千年前の出来ごとにこんなにも則って執り行う儀式ってすごいな、という感じです。
それでは、また。
もしもお待ちいただいていた方がいたらごめんなさい。
先月30日に広尾のthe Jewish Community of Japanで行われた『過ぎ越しの祭り』Passoverに参加した(というより間近で目撃、といった方が正しいかもしれませんが)のご報告をいたします。
不肖せんまつ先週末から連夜の夜桜見物でちとかぜをひきました。
なので、ぽちぽち書き込みしますので、お許しください。。。
『過ぎ越し』につきましては先のトピックの方にもいろいろリンク貼りましたのでいまさら、なんですが、とりあえず「前回までのあらすじ」的に”過ぎ越しって何?”は以下をご参照ください。
http://
…しかし、ここを読んだからといって一応体験(いえ目撃)してきた拙者でも
なんだかよくわかりません(このはがゆさみたいなのは芥川賞を受賞した米谷ふみ子さんの『過ぎ越しの祭り』という小説によくあらわれてます)。
それが『ユダヤ教』なのかもしれません。
ので、ここから書くことでよくわからない、と思われたら、
ゴメンナサイ、よくわからないのが正解です。
でも、一生懸命書くから許してね(のっけからEXCUSE ME)。
ユダヤ教…本当に名前はよく知っているのにでは何、といわれたらわかりません。私は内に向かう厳しい宗教というイメージでした。でも、今回この言葉を別のいい方するとしたら「とても家族的な宗教、集団」という印象を受けました。
それはGoogle創設者のセルゲイ・ブリン(彼はソビエト出身のユダヤ人です)のお父さんが"Jewishnessは genetic(遺伝)だ”と言ってるんですが、本当にそう思いました。外部のものにはそこはかとなく不思議というかミラクルワールドなのです。
でも、それがある意味ユダヤ教さんの本質のような気もします。
かく言うわたくしめ、Niki’s根性(?!)が出てしまい、ちょっとしたセキュリティチェック(刃物等の持ち込みは禁止です)のあと、シナゴークに入ったとき、受付の方が親切でこちらの名前を覚えていてくださったことに気をよくし「食べ物写真とってもいいですか?」と無知丸出しの質問をし
”No! This is holy festival!!"
と当たり前ながら厳しいお言葉を頂戴し、以降とんだおっちょこちょいが来ちゃった、と思われたのか、プチ無視されながら、でも逆に静かに観察させていただきました(そんなわけで写真はありません)。
考えたら「シナゴーク」ですから。
勢い(ただただどんな食事=セダーを食べるのか知りたかった
おそらく一生に一度の体験です。今になってちょっと蛮勇だったと反省しております。
でも、
もしチャンスがあったらいずこかで体験するのはいいことかもしれません。
ちなみに日本ヘブライ協会というお茶の水などにヘブライ語やアラム語を教えているカルチャーセンターがあるようで、そちらでは4月6日に非教徒に過ぎ越しを体験させてくれる企画があったようで、もしぜひとも、というのでしたらそちらへ行った方が解説もあってわかりやすい、かもしれませんね。来年のご参考までに。
さてさて前置きが長くなりましたが、
3月30日、
広尾の東京女学館のお隣に位置するシナゴークに私の好奇心にお付き合いいただいたAさんと道に迷い迷いながら、でもわくわくして伺いました。
建物は昨年新築されたとてもモダンな外観で、星の印がなかったら見逃してしまいそうです。
ちなみに
日本で最初のシナゴークは長崎に明治の初めに出来たようです。
ここはアシュケナディ系(ヨーロッパ出身のユダヤ人)の人たちが作ったようですが、その後は神戸にセファルディ系(中東出身)のシナゴークが出来たそうで、今は東京、横浜、神戸、名古屋にあるようです。
…キリスト教に比べると圧倒的な少なさ、というか、一応そうではない、ということらしいですが、「ユダヤ人」さんでないと行きにくい感はありますよね。
ちなみに伝統の考え方ではお母さんがユダヤ人でないとユダヤ人と見なさなかったそうです(どちらかが、でよいになったのは80年代以降)。
おっとっと
また話がそれましたが、
それたついでにユダヤ教の三大祭りのことを書きます。
(すいません、ここに書いてるっていうのは第一に自分がわかりたい、というのがあるので、いろいろ脱線してごめんなさい)。
それは
ぺサハ(passover) 春 最初の穀物(大麦)収穫を祝う
シャブオット(七週祭)初夏 春蒔き小麦と果物の収穫を祝う
スッコート(仮庵祭) 秋 一年を締めくくる収穫の祭り
の三つで、祭りはシナゴークだけでなく家庭でも行われるそうで、Nikiさんたちがいらっしゃったのはそちらに近いスタイルなのでは、と思います。
で、この中で一番有名なのがぺサハで、その祝宴がセデルなんですね。
イスラエルではPassoverの初日に、ディアスポラでは2日目に行われる御馳走の宴、という規定もあるそうです。
で、
この三つの祭りの共通点は「神の前でも喜び」だそうで、歴史的であり宗教であり、さらに農業行事的でもあり、さらに楽しいというものなんですね。
そのせいか
祭りを執り行うラビがワインでどんどん真っ赤になって
「昨日は酔っ払っちゃって忘れたことがあるから今言うね〜」
てな具合に楽しそーにしていたり、ラビの横に座っていた青少年たちもワイン飲んじゃってトローンとしてたり、聖なる祈りの合間に結構家庭内での食卓風景みたいな展開もありました。
…と、、まったく内容に入ることなく今晩はここまででお許しください。
ちょっとかぜ薬が効いてきちゃいましたの模様です。
なお、
次回への予習にお時間あったら
『旧約聖書』の出エジプト記が参考になると思います。
ある意味数千年前の出来ごとにこんなにも則って執り行う儀式ってすごいな、という感じです。
それでは、また。
|
|
|
|
コメント(12)
いやはや
まことにすみません。
せんまつは借金取りに追われたり、スパイ容疑で拉致られたり、
そういう大事件には巻きこまれているわけではありませんが、
プチ行方不明でした?
京都に花見に行ってました。
花→団子→花→団子…でした。
(本当にみよしやの団子食べながら祇園で夜桜…、とかね)。
と、お詫びの言葉もないくらいのご乱行?&今さら、ですが、
PASSOVERです
もういいよ、とお思いの方々もおありでしょうが(ほんとにゴメンナサイ)、いろんな本に「ユダヤ教を理解すればキリスト教=西欧文明の全体像があきらかになるでしょう」とあるので…
実際よくわからないんですけど
でも
もう個人的趣味の域ですが
書きまする。
その方がいろんな国の文化歴史そして食を知る時楽しみが倍増だし、
それに
♪フロイトもマルクスも、アインシュタインもマーラーも
みーんな みんな ユダヤ人♪
昔こんな歌がありました。
世界のインテリジェンスはこんなところに起源があるのか、と
ちょっと面白いかな?と私めは思っております。

さてさて
当日の次第を『ハガター』に従ってレポします。
まず『ハガター』ですが、
これた”語る”という意味だそうで、祭り次第が記されています。
日本の和綴じ本と同じ右開き本です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%AC%E3%83%80%E3%83%BC
(http://myrtos.shop-pro.jp/?pid=9065216…こちらはヘブライ語、英語、日本語の三言語表記)
『出エジプト記』13章8節
「あなたはこの日、自分の子供に語らなければならない」
が起源で、過去の記憶を次の世代に伝えるという掟(ミツヴァ)なんですって。
ちなみに出エジプトは紀元前1230年ごろ…
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E8%A8%98
ギリシアはミケーネ文明(ギリシャ文明が生まれ始めた位)、インドはインダス文明、中国では殷の国、日本に至っては縄文時代…
私たちのご先祖さまが貝拾ってた頃の記憶を忘れまいという儀式が今でも続いているという…
すごすぎる、だけに興味津々。
。
まことにすみません。
せんまつは借金取りに追われたり、スパイ容疑で拉致られたり、
そういう大事件には巻きこまれているわけではありませんが、
プチ行方不明でした?
京都に花見に行ってました。
花→団子→花→団子…でした。
(本当にみよしやの団子食べながら祇園で夜桜…、とかね)。
と、お詫びの言葉もないくらいのご乱行?&今さら、ですが、
PASSOVERです
もういいよ、とお思いの方々もおありでしょうが(ほんとにゴメンナサイ)、いろんな本に「ユダヤ教を理解すればキリスト教=西欧文明の全体像があきらかになるでしょう」とあるので…
実際よくわからないんですけど
でも
もう個人的趣味の域ですが
書きまする。
その方がいろんな国の文化歴史そして食を知る時楽しみが倍増だし、
それに
♪フロイトもマルクスも、アインシュタインもマーラーも
みーんな みんな ユダヤ人♪
昔こんな歌がありました。
世界のインテリジェンスはこんなところに起源があるのか、と
ちょっと面白いかな?と私めは思っております。
さてさて
当日の次第を『ハガター』に従ってレポします。
まず『ハガター』ですが、
これた”語る”という意味だそうで、祭り次第が記されています。
日本の和綴じ本と同じ右開き本です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%AC%E3%83%80%E3%83%BC
(http://myrtos.shop-pro.jp/?pid=9065216…こちらはヘブライ語、英語、日本語の三言語表記)
『出エジプト記』13章8節
「あなたはこの日、自分の子供に語らなければならない」
が起源で、過去の記憶を次の世代に伝えるという掟(ミツヴァ)なんですって。
ちなみに出エジプトは紀元前1230年ごろ…
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E8%A8%98
ギリシアはミケーネ文明(ギリシャ文明が生まれ始めた位)、インドはインダス文明、中国では殷の国、日本に至っては縄文時代…
私たちのご先祖さまが貝拾ってた頃の記憶を忘れまいという儀式が今でも続いているという…
すごすぎる、だけに興味津々。
。
さてさて(ほんとに前置き長い )
)
過越祭の始まりは夕方のシナゴーク(会堂)でのお祈りから始まりました。
ユダヤ教の一日は前夜の日没からはじまるんだそうです。
また
”シナゴーク”は私たちの感覚だとキリスト教の礼拝堂やお寺の本堂みたいなものかと思いますが、でも、ちょっと違うのは本来が”教育の場”ということであるせいか、シンプルで、当たり前ですが、偶像崇拝禁止だからいわゆる「●●の像」がないのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%B0
ですから
お祈りが始まり、
ラビの祈り、みんなで唱和、そして沈黙、が繰り返されるんですが、
この「沈黙」の祈りでユダヤ教の人々が身体を揺すって、そう、あのエルサレム嘆きの壁の前で黒帽子にカールもみあげの男性たちの映像と同じように身体を揺すって無言で祈る時、
おっちょこちょいさん(私)はちょっと困りました。
実は会堂の前にはトーラー(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC)が置いてあって、それを持って入るのですが、私たちは持って入るのを忘れちゃったので、どこを見てればよいのか、わからなかったのです。
トーラーというのは『モ―ゼの五書』のことで創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記のこと…
…書いて気がついたんですが、置いてあったのはトーラーではなく、
『シッドゥリーム』(祈祷書)だったかもしれない…
ユダヤ人はとにかく本が好き、本が大切、で
イスラエルの新聞の購読おまけは『タルムード』(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%89)だったりするそうで、洗剤がおまけの日本と大違い
教会やお寺ならとりあえずそこにキリスト像や阿弥陀如来がいるので、
ありがたい感じでそれを見てると儀式に参加している気分になりますが、
会堂はラビの立つスピーチ台みたいな場所を囲んでコの字に席が配置され、そう、ほんとに会議場といった方がぴったりな感じなのです。
しかも、
お祈りの途中でラビが「●●ページ、はい、デビット」みたいに
指名する!
するとおもむろにその人は
たぶんへブライ語で滔々と読む!
次々と指名されてゆく中、
まさか私たちには言わないよね、と思いながらも
米谷ふみ子さんの『過ぎ越しの祭』という本の中では主人公が
本を読むように当てられて(小姑にいぢわるされて)というシーンを思いだし、
ホント、ちょっとドキドキしました。
ちなみに
儀式はそんな風に参加型のものが多く、
よい儀式とは議論が白熱するようなものなんだそうです。



日本人の苦手な感じ
しかし、
その即興性、ディベート感、臨機応変みたいな感じが
欧米式の教育の中のある部分とつながってる感じがして、
こういうところでも脳を養ってるのかなー、と
妙に感心してしまいました。
過越祭の始まりは夕方のシナゴーク(会堂)でのお祈りから始まりました。
ユダヤ教の一日は前夜の日没からはじまるんだそうです。
また
”シナゴーク”は私たちの感覚だとキリスト教の礼拝堂やお寺の本堂みたいなものかと思いますが、でも、ちょっと違うのは本来が”教育の場”ということであるせいか、シンプルで、当たり前ですが、偶像崇拝禁止だからいわゆる「●●の像」がないのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%B0
ですから
お祈りが始まり、
ラビの祈り、みんなで唱和、そして沈黙、が繰り返されるんですが、
この「沈黙」の祈りでユダヤ教の人々が身体を揺すって、そう、あのエルサレム嘆きの壁の前で黒帽子にカールもみあげの男性たちの映像と同じように身体を揺すって無言で祈る時、
おっちょこちょいさん(私)はちょっと困りました。
実は会堂の前にはトーラー(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC)が置いてあって、それを持って入るのですが、私たちは持って入るのを忘れちゃったので、どこを見てればよいのか、わからなかったのです。
トーラーというのは『モ―ゼの五書』のことで創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記のこと…
…書いて気がついたんですが、置いてあったのはトーラーではなく、
『シッドゥリーム』(祈祷書)だったかもしれない…
ユダヤ人はとにかく本が好き、本が大切、で
イスラエルの新聞の購読おまけは『タルムード』(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%89)だったりするそうで、洗剤がおまけの日本と大違い
教会やお寺ならとりあえずそこにキリスト像や阿弥陀如来がいるので、
ありがたい感じでそれを見てると儀式に参加している気分になりますが、
会堂はラビの立つスピーチ台みたいな場所を囲んでコの字に席が配置され、そう、ほんとに会議場といった方がぴったりな感じなのです。
しかも、
お祈りの途中でラビが「●●ページ、はい、デビット」みたいに
指名する!
するとおもむろにその人は
たぶんへブライ語で滔々と読む!
次々と指名されてゆく中、
まさか私たちには言わないよね、と思いながらも
米谷ふみ子さんの『過ぎ越しの祭』という本の中では主人公が
本を読むように当てられて(小姑にいぢわるされて)というシーンを思いだし、
ホント、ちょっとドキドキしました。
ちなみに
儀式はそんな風に参加型のものが多く、
よい儀式とは議論が白熱するようなものなんだそうです。
日本人の苦手な感じ
しかし、
その即興性、ディベート感、臨機応変みたいな感じが
欧米式の教育の中のある部分とつながってる感じがして、
こういうところでも脳を養ってるのかなー、と
妙に感心してしまいました。
(すんません、2000字超えるとアップできないので枝分かれしばしば)
そんな
興味あるけど居心地わるくてごめんなさい、の祈りの時間が終わると、
場所を移し、いよいよ過越祭の食事です。
またここでちょっと説明が必要ですが、
会場のテーブルには以下の6種類の食品が用意されています。
1.マツォット(マッツァー)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC)(http://en.wikipedia.org/wiki/Matzah)(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC)
イーストの入っていないパン(というより形状は巨大クラッカー)を
三枚重ね。一枚ずつが祭司、レビ、イスラエルを象徴する。
上記のページにもありますが、モーセに導かれてエジプトを脱出する時、発酵をさせる時間さえなくあわただしく家を出た、ということが起源で、イーストが入ってないんだそうです。
で、味はどうかというと…
ない。
…
ないんです。
あえて言うなら
「粉い」。
しょっぱくもないし、甘くもなく、
大食漢異教徒としてはサーモンとかクリームとかイチゴジャムでもいい、
載せたい…って思うのはユダヤ教的にはバチあたりなんでしょうね。
と、いうのは
これは本当かどうか確認してませんが、
人々に与えられるパンというのは主のことであり、
主の身体は人々に代わって傷つく、ということだそうで、
実は私、マッツァーの表面に開けられた孔(ふくらまないようにフォーク状のもので開ける)がどうも肌あれみたいで苦手だなー、と思ってたら、”そう”いう話を小耳に挟んでしまい、今ちょっと食べられないです(泣)。
とはいえ、マッツァー粉を使ったお菓子(フレムゼムとか)もあるようなので、
誰かメニューにしてくださらないでしょうか。
そんな
興味あるけど居心地わるくてごめんなさい、の祈りの時間が終わると、
場所を移し、いよいよ過越祭の食事です。
またここでちょっと説明が必要ですが、
会場のテーブルには以下の6種類の食品が用意されています。
1.マツォット(マッツァー)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC)(http://en.wikipedia.org/wiki/Matzah)(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC)
イーストの入っていないパン(というより形状は巨大クラッカー)を
三枚重ね。一枚ずつが祭司、レビ、イスラエルを象徴する。
上記のページにもありますが、モーセに導かれてエジプトを脱出する時、発酵をさせる時間さえなくあわただしく家を出た、ということが起源で、イーストが入ってないんだそうです。
で、味はどうかというと…
ない。
…
ないんです。
あえて言うなら
「粉い」。
しょっぱくもないし、甘くもなく、
大食漢異教徒としてはサーモンとかクリームとかイチゴジャムでもいい、
載せたい…って思うのはユダヤ教的にはバチあたりなんでしょうね。
と、いうのは
これは本当かどうか確認してませんが、
人々に与えられるパンというのは主のことであり、
主の身体は人々に代わって傷つく、ということだそうで、
実は私、マッツァーの表面に開けられた孔(ふくらまないようにフォーク状のもので開ける)がどうも肌あれみたいで苦手だなー、と思ってたら、”そう”いう話を小耳に挟んでしまい、今ちょっと食べられないです(泣)。
とはいえ、マッツァー粉を使ったお菓子(フレムゼムとか)もあるようなので、
誰かメニューにしてくださらないでしょうか。
わあ、「南部せんべい」がですか?!
…(笑)。
こういうお話って「義経=ジンギスカン説」的な感じもしますが、
京都にも広隆寺を建てた秦氏の祖先である弓月氏が渡来ユダヤ人という説があり、京都三大奇祭である牛祭の神はユダヤの神ではないか、みたいなお話があります。この寺の近所にある大酒神社に祀られてるのがユダヤ人の祖先だ、とか木島神社の鳥居かユダヤの星の形だ、とか、世界は案外狭い?(笑)
ちなみに中国にユダヤコミュニティが12世紀ごろからあったらしいという話はかなり信憑性がありそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%8B%E5%B0%81%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E4%BA%BA
…でも、中国人でユダヤ教徒はきつそうだなあ。
豚肉だめなんですものね。
…(笑)。
こういうお話って「義経=ジンギスカン説」的な感じもしますが、
京都にも広隆寺を建てた秦氏の祖先である弓月氏が渡来ユダヤ人という説があり、京都三大奇祭である牛祭の神はユダヤの神ではないか、みたいなお話があります。この寺の近所にある大酒神社に祀られてるのがユダヤ人の祖先だ、とか木島神社の鳥居かユダヤの星の形だ、とか、世界は案外狭い?(笑)
ちなみに中国にユダヤコミュニティが12世紀ごろからあったらしいという話はかなり信憑性がありそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%8B%E5%B0%81%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E4%BA%BA
…でも、中国人でユダヤ教徒はきつそうだなあ。
豚肉だめなんですものね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
世界の料理教室 Niki's Kitchen 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
世界の料理教室 Niki's Kitchenのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8447人
- 2位
- 一行で笑わせろ!
- 82528人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208286人
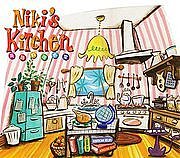


















![[dir]料理・お菓子教室](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/46/75/1224675_159s.gif)




