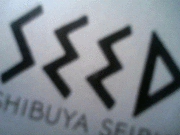映画評論家の梅本洋一氏が亡くなりました。ご冥福をお祈りします。
梅本氏には、ヴィム・ベンダース特集の際、ベンダースとの対談をしていただきました。以下、シードホールでの様子を書いた方の記事を転載します。
「シード・ホールのヴェンダース」
座席はとっくになく、ステージの前のわずかなスペースまで聴衆があぐらをかいて座っている。その会場にヴェンダースは現れた。最初の言葉は「おはよう」。もちろん小津の映画のタイトルだ。映画の可能性を問い続けるヴェンダースは、その登場の仕方まで映画的だった。
梅本洋一氏とヴィム・ヴェンダースの座談会が開かれたのは3月15日、渋谷シード・ホール。11時からもう長い行列ができている。列の後尾では、スタッフが整理券を配布している。道行く人たちは何の行列かと眺めていく。
時間通りに現れたヴェンダースは、実に愛想よく笑顔を見せてくれた。目が合うとニッコリ微笑みかけ、カメラを向けるファンにはおどけてみせる。そのうえ8ミリビデオを回している観客からカメラを受け取って、自らフィルムを回してさえくれたのだ。
ヴェンダースといえば、もっと神経質な芸術家肌の人かと思っていたが、そのにこやかな態度は、何だか気軽に話せる我々映画ファンの兄貴分といった感じで、実に親しみやすい。
どのヴェンダース作品もそうであるように、彼の映画は他者とのコミュニケートの難しさが最大のテーマとなっている。特に『パリ、テキサス』。ここでは去って行った妻との対話の方法を探し出そうとする、H・D・スタントンの真摯な姿に感動の焦点があった。『ベルリン・天使の詩』は、触れ合いのコミュニケーションをまさぐった映画である。『ハメット』と『ことの次第』は、製作者のコッポラ、ひいてはハリウッド・システムとのコミュニケーションの失敗から生まれた映画だった。
ところでそんなヴェンダースも、会場では実に活発にファンとコミュニケートする。質問には真剣に耳を傾け、丁寧に回答する。時間がなくなってきて、あせっている主催者を制するように、「あと2人、あともう1人」と、いつまでも終わることのないファンの挙手に応えてくれる。けれどよく考えてみると、それはコミュニケーションの作家ヴェンダースだからこそ、その大切さを身を以って示した振る舞いだったようにも思うのだ。
「映画学校で学んだことはたいして役に立たなかったが、映画を見てそれについて書くことは大変な勉強になった」と語ったヴェンダースの言葉は、彼が常に映画との対話、つまりコミュニケートにおいて自らを磨いたことの告白と受け止めた。
けれど何より会場を沸かせたのは、やっぱり『ベルリン・天使の詩パート2』を現在製作中だという発表だった。楽しみである。
講演が終わった後、ヴェンダースに握手をしてもらった。そのときの彼の柔らかい笑顔が忘れられない。その大きくて肉厚の手の感触は、人間になった天使との最初のコミュニケーションのようだった。(南波 克行)
本稿は「FLIX」1992年6月号に掲載されたものです。
梅本氏には、ヴィム・ベンダース特集の際、ベンダースとの対談をしていただきました。以下、シードホールでの様子を書いた方の記事を転載します。
「シード・ホールのヴェンダース」
座席はとっくになく、ステージの前のわずかなスペースまで聴衆があぐらをかいて座っている。その会場にヴェンダースは現れた。最初の言葉は「おはよう」。もちろん小津の映画のタイトルだ。映画の可能性を問い続けるヴェンダースは、その登場の仕方まで映画的だった。
梅本洋一氏とヴィム・ヴェンダースの座談会が開かれたのは3月15日、渋谷シード・ホール。11時からもう長い行列ができている。列の後尾では、スタッフが整理券を配布している。道行く人たちは何の行列かと眺めていく。
時間通りに現れたヴェンダースは、実に愛想よく笑顔を見せてくれた。目が合うとニッコリ微笑みかけ、カメラを向けるファンにはおどけてみせる。そのうえ8ミリビデオを回している観客からカメラを受け取って、自らフィルムを回してさえくれたのだ。
ヴェンダースといえば、もっと神経質な芸術家肌の人かと思っていたが、そのにこやかな態度は、何だか気軽に話せる我々映画ファンの兄貴分といった感じで、実に親しみやすい。
どのヴェンダース作品もそうであるように、彼の映画は他者とのコミュニケートの難しさが最大のテーマとなっている。特に『パリ、テキサス』。ここでは去って行った妻との対話の方法を探し出そうとする、H・D・スタントンの真摯な姿に感動の焦点があった。『ベルリン・天使の詩』は、触れ合いのコミュニケーションをまさぐった映画である。『ハメット』と『ことの次第』は、製作者のコッポラ、ひいてはハリウッド・システムとのコミュニケーションの失敗から生まれた映画だった。
ところでそんなヴェンダースも、会場では実に活発にファンとコミュニケートする。質問には真剣に耳を傾け、丁寧に回答する。時間がなくなってきて、あせっている主催者を制するように、「あと2人、あともう1人」と、いつまでも終わることのないファンの挙手に応えてくれる。けれどよく考えてみると、それはコミュニケーションの作家ヴェンダースだからこそ、その大切さを身を以って示した振る舞いだったようにも思うのだ。
「映画学校で学んだことはたいして役に立たなかったが、映画を見てそれについて書くことは大変な勉強になった」と語ったヴェンダースの言葉は、彼が常に映画との対話、つまりコミュニケートにおいて自らを磨いたことの告白と受け止めた。
けれど何より会場を沸かせたのは、やっぱり『ベルリン・天使の詩パート2』を現在製作中だという発表だった。楽しみである。
講演が終わった後、ヴェンダースに握手をしてもらった。そのときの彼の柔らかい笑顔が忘れられない。その大きくて肉厚の手の感触は、人間になった天使との最初のコミュニケーションのようだった。(南波 克行)
本稿は「FLIX」1992年6月号に掲載されたものです。
|
|
|
|
コメント(1)
梅本氏がシードホールに関連して書かれた文章を転載いたします。
October 14, 2009
『無印ニッポン──20世紀消費社会の終焉』堤清二、三浦展 梅本洋一
辻井喬名義の小説は読んでいないけれども、セゾン・グループの総帥を退任してからの堤清二の発言は本当に興味深い。前に上野千鶴子との対談本を採り上げたことがあるが、今回は、『下流社会』の三浦展だ。上野も三浦もパルコ出身といってもいいから、当時は「天上人」(三浦の表現)だったにせよ、セゾン・グループは、確かに多くの人材を輩出している(もちろん居なくなっちゃった人もたくさんいるけど)。
三浦展が書いたこの本の前書きにはこうある。「堤さんはずっと『詩人経営者』と言われてきた。まったく矛盾する二足のわらじを履いて歩くとは一体どういうことだと、多くの人は訝しがり、また多くの人は、堤さんを揶揄した。/だが、矛盾しているからといって何だというのだろう。私も、マーケッターでありながら消費社会を批判するのは何故かと幾度となく聞かれてきた。疲れる質問である。/しかし、私はそのときこう答える。私はマーケッターである以前に市民です、人間です、人の親です。と。/だから思うに、「無印ニッポン」とは、まさに日本人が、その属する国や企業や組織から自由になってものを考え、発言し、行動する国のイメージであるのかも知れない」。
この新書の読後感もそれだ。もちろん現在の消費社会の諸々の矛盾の先鞭を付けたのは堤清二とセゾン・グループだったろう。80年代初頭から仕事を始めたぼく自身も、スタジオ200やシネ・ヴィヴァン、シードホール、スタジオアムス等、セゾンとのつき合いは多かった。東京の西友ストアの中に全部、劇場と映画館を併設するのだという勢いだった。すべて失敗だった。
でも失敗の後の光景が、郊外のショッピングセンターとシネコンという「ファスト風土」であり、六本木ヒルズであり、商店街のシャッターストリート化だ。それについて堤清二はどう考えているのか、というのが本書だ。だからすごく面白い。本書のタイトルが『無印ニッポン』であるのは象徴的だ。おそらく堤清二が仕掛けたことで今でも成功しているのは「無印良品」だけかもしれない。服飾についてはユニクロに劣るかも知れないが、家具や食器などのすべての面での生活の提案である「無印良品」の思想は、海外でこそブランドになっているが、今こそ説得力を持っているように感じられる。Mujiの家具は、確かにIKEAより高価だが、それでもIKEAが船橋や港北といった郊外に巨大な駐車場を持つ無機質な建物で展開しているのに対して、Mujiのフラッグシップ店が有楽町にあり、それも、著名建築家たちの建物の中で「無印」であるような仮設建築であるのは、すてきだと思う。本書を読みながら、Mujiの有楽町店こそが、この本を体現していると思った。
October 14, 2009
『無印ニッポン──20世紀消費社会の終焉』堤清二、三浦展 梅本洋一
辻井喬名義の小説は読んでいないけれども、セゾン・グループの総帥を退任してからの堤清二の発言は本当に興味深い。前に上野千鶴子との対談本を採り上げたことがあるが、今回は、『下流社会』の三浦展だ。上野も三浦もパルコ出身といってもいいから、当時は「天上人」(三浦の表現)だったにせよ、セゾン・グループは、確かに多くの人材を輩出している(もちろん居なくなっちゃった人もたくさんいるけど)。
三浦展が書いたこの本の前書きにはこうある。「堤さんはずっと『詩人経営者』と言われてきた。まったく矛盾する二足のわらじを履いて歩くとは一体どういうことだと、多くの人は訝しがり、また多くの人は、堤さんを揶揄した。/だが、矛盾しているからといって何だというのだろう。私も、マーケッターでありながら消費社会を批判するのは何故かと幾度となく聞かれてきた。疲れる質問である。/しかし、私はそのときこう答える。私はマーケッターである以前に市民です、人間です、人の親です。と。/だから思うに、「無印ニッポン」とは、まさに日本人が、その属する国や企業や組織から自由になってものを考え、発言し、行動する国のイメージであるのかも知れない」。
この新書の読後感もそれだ。もちろん現在の消費社会の諸々の矛盾の先鞭を付けたのは堤清二とセゾン・グループだったろう。80年代初頭から仕事を始めたぼく自身も、スタジオ200やシネ・ヴィヴァン、シードホール、スタジオアムス等、セゾンとのつき合いは多かった。東京の西友ストアの中に全部、劇場と映画館を併設するのだという勢いだった。すべて失敗だった。
でも失敗の後の光景が、郊外のショッピングセンターとシネコンという「ファスト風土」であり、六本木ヒルズであり、商店街のシャッターストリート化だ。それについて堤清二はどう考えているのか、というのが本書だ。だからすごく面白い。本書のタイトルが『無印ニッポン』であるのは象徴的だ。おそらく堤清二が仕掛けたことで今でも成功しているのは「無印良品」だけかもしれない。服飾についてはユニクロに劣るかも知れないが、家具や食器などのすべての面での生活の提案である「無印良品」の思想は、海外でこそブランドになっているが、今こそ説得力を持っているように感じられる。Mujiの家具は、確かにIKEAより高価だが、それでもIKEAが船橋や港北といった郊外に巨大な駐車場を持つ無機質な建物で展開しているのに対して、Mujiのフラッグシップ店が有楽町にあり、それも、著名建築家たちの建物の中で「無印」であるような仮設建築であるのは、すてきだと思う。本書を読みながら、Mujiの有楽町店こそが、この本を体現していると思った。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
シードホール 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
シードホールのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8436人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196006人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89507人