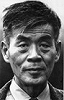|
|
|
|
コメント(37)
毎日新聞夕刊編集部「〈3/11後〉忘却に抗して━━識者53人の言葉」
四六判上製/232頁 定価1700円+税 現代書館
*宣伝文(現代書館のサイトより)
震災直後の余震と原発事故進行の中、考え、未来への提言を諦めな
かった勇気ある言論人たちの必死のメッセージ。これだけの重要人
物がよくぞ集まったというほどの多士済々。言論人、新聞記者の渾
身のメッセージは必読です。
なお、本書収録の吉本隆明氏インタビューは、氏の生前最後の新聞
インタビューになりました。
*53名のリスト
高村薫、梁石日、石原信雄、秋山駿、柳田邦男、金子兜太、梅原猛、
津島祐子、保阪正康、内田樹、緒方貞子、倉本聰、鎌田慧、有馬朗
人、辻井喬、黒井千次、吉本隆明、武村正義、浅野史郎、高橋哲哉、
中谷巌、小柴昌俊、野田正彰、津本陽、赤坂憲雄、池内紀、姜尚中、
小熊英二、辺見庸、半藤一利、橋田壽賀子、石牟礼道子、高橋源一
郎、関川夏央、むのたけじ、柄谷行人、平野啓一郎、佐野眞一、吉
武輝子、森まゆみ、落合恵子、池澤夏樹、東浩紀、丸山健二、藤本
義一、坂本義和、玄侑宗久、佐伯啓思、中島岳志、俵万智、大城立
裕、和合亮一、平田オリザ、総勢の懸命なメッセージ。
削除
四六判上製/232頁 定価1700円+税 現代書館
*宣伝文(現代書館のサイトより)
震災直後の余震と原発事故進行の中、考え、未来への提言を諦めな
かった勇気ある言論人たちの必死のメッセージ。これだけの重要人
物がよくぞ集まったというほどの多士済々。言論人、新聞記者の渾
身のメッセージは必読です。
なお、本書収録の吉本隆明氏インタビューは、氏の生前最後の新聞
インタビューになりました。
*53名のリスト
高村薫、梁石日、石原信雄、秋山駿、柳田邦男、金子兜太、梅原猛、
津島祐子、保阪正康、内田樹、緒方貞子、倉本聰、鎌田慧、有馬朗
人、辻井喬、黒井千次、吉本隆明、武村正義、浅野史郎、高橋哲哉、
中谷巌、小柴昌俊、野田正彰、津本陽、赤坂憲雄、池内紀、姜尚中、
小熊英二、辺見庸、半藤一利、橋田壽賀子、石牟礼道子、高橋源一
郎、関川夏央、むのたけじ、柄谷行人、平野啓一郎、佐野眞一、吉
武輝子、森まゆみ、落合恵子、池澤夏樹、東浩紀、丸山健二、藤本
義一、坂本義和、玄侑宗久、佐伯啓思、中島岳志、俵万智、大城立
裕、和合亮一、平田オリザ、総勢の懸命なメッセージ。
削除
○「吉本隆明が最後に遺した三十万字 上巻『吉本隆明、自著を語る』」
四六判/319頁 定価2500円+税 ロッキング・オン
*帯の文。ご予約者には本日発送します。
『固有時との対話』『芸術的抵抗と挫折』から
『言語にとって美とはなにか』『共同幻想論』
『最後の親鸞』『ハイ・イメージ論』まで
吉本隆明が最後に描いた自画像
−連載「自作を語る」をすべて収録した完全版インタビュー集
*目次
第一章『固有時との対話』『転位のための十篇』
第二章『マチウ書試論』
第三章『高村光太郎』
第四章『芸術的抵抗と挫折』
第五章『擬制の終焉』
第六章『言語にとって美とはなにか』
第七章『共同幻想論』
第八章「花田清輝との論争」
第九章『心的現象論』
第十章『最後の親鸞』
第十一章『悲劇の解読』
第十二章『「反核」異論』
第十三章『マス・イメージ論』
第十四章『源氏物語論』
第十五章『死の位相学』
第十六章『超西欧的まで』
第十七章『ハイ・イメージ論』
あとがき「十四歳の思想」高橋源一郎
※初出は「SIGHT」21号(2004年10月号)から41号(2009年11月号)まで
連載(休載あり)。第九章までは「吉本隆明 自著を語る」として、
2007年6月に同社から刊行されました。
○「吉本隆明が最後に遺した三十万字 下巻『吉本隆明、時代と向き合う』」
四六判/407頁 定価2500円+税 ロッキング・オン
*帯の文
9・11アメリカ同時多発テロ、少年犯罪、引きこもり、
グローバル資本主義、自衛隊法、
「新しい歴史教科書をつくる会」etc.
吉本隆明は2000年以降、時代をどう読んだのか?
*目次
第一章「頻発する無根拠な殺人事件をめぐって」
第二章「少年法改正をめぐって」
第三章「日本の現在の政治状況について」
第四章「小泉改革による真の構造改革がもたらすものは何か」
第五章「『新しい歴史教科書をつくる会』について」
第六章「アメリカで起こった同時多発テロについて」
第七章「同時多発テロをめぐる自衛隊法改正について」
第八章「天皇による『韓国とのゆかり』発言について」
第九章「同時多発テロにまつわる有事立法について」
第十章「小泉内閣による自民党政権について」
第十一章「世界を席巻するグローバル資本主義について」
第十二章「9・11以後のイラクの問題について」
第十三章「アメリカの中東戦争について」
第十四章「著書『引きこもれ』と少年犯罪について」
第十五章「小林秀雄賞受賞について」
第十六章『一言芳談』『歎異抄』
第十七章『花伝書(風姿花伝)』
第十八章『十七条憲法』
第十九章『トーテムと命名』
あとがき「非政治的大衆の政治性について」内田樹
※第一章から第十五章までは“時代と向き合う”で、初出は第5号
(2000年10月号)から第18号(2004年1月号)と2001年11月増刊号に連載。
第十六章以降は“古典を読む”で、初出は第1号(1999年10月号)から
第4号(2000年7月号)まで連載。
四六判/319頁 定価2500円+税 ロッキング・オン
*帯の文。ご予約者には本日発送します。
『固有時との対話』『芸術的抵抗と挫折』から
『言語にとって美とはなにか』『共同幻想論』
『最後の親鸞』『ハイ・イメージ論』まで
吉本隆明が最後に描いた自画像
−連載「自作を語る」をすべて収録した完全版インタビュー集
*目次
第一章『固有時との対話』『転位のための十篇』
第二章『マチウ書試論』
第三章『高村光太郎』
第四章『芸術的抵抗と挫折』
第五章『擬制の終焉』
第六章『言語にとって美とはなにか』
第七章『共同幻想論』
第八章「花田清輝との論争」
第九章『心的現象論』
第十章『最後の親鸞』
第十一章『悲劇の解読』
第十二章『「反核」異論』
第十三章『マス・イメージ論』
第十四章『源氏物語論』
第十五章『死の位相学』
第十六章『超西欧的まで』
第十七章『ハイ・イメージ論』
あとがき「十四歳の思想」高橋源一郎
※初出は「SIGHT」21号(2004年10月号)から41号(2009年11月号)まで
連載(休載あり)。第九章までは「吉本隆明 自著を語る」として、
2007年6月に同社から刊行されました。
○「吉本隆明が最後に遺した三十万字 下巻『吉本隆明、時代と向き合う』」
四六判/407頁 定価2500円+税 ロッキング・オン
*帯の文
9・11アメリカ同時多発テロ、少年犯罪、引きこもり、
グローバル資本主義、自衛隊法、
「新しい歴史教科書をつくる会」etc.
吉本隆明は2000年以降、時代をどう読んだのか?
*目次
第一章「頻発する無根拠な殺人事件をめぐって」
第二章「少年法改正をめぐって」
第三章「日本の現在の政治状況について」
第四章「小泉改革による真の構造改革がもたらすものは何か」
第五章「『新しい歴史教科書をつくる会』について」
第六章「アメリカで起こった同時多発テロについて」
第七章「同時多発テロをめぐる自衛隊法改正について」
第八章「天皇による『韓国とのゆかり』発言について」
第九章「同時多発テロにまつわる有事立法について」
第十章「小泉内閣による自民党政権について」
第十一章「世界を席巻するグローバル資本主義について」
第十二章「9・11以後のイラクの問題について」
第十三章「アメリカの中東戦争について」
第十四章「著書『引きこもれ』と少年犯罪について」
第十五章「小林秀雄賞受賞について」
第十六章『一言芳談』『歎異抄』
第十七章『花伝書(風姿花伝)』
第十八章『十七条憲法』
第十九章『トーテムと命名』
あとがき「非政治的大衆の政治性について」内田樹
※第一章から第十五章までは“時代と向き合う”で、初出は第5号
(2000年10月号)から第18号(2004年1月号)と2001年11月増刊号に連載。
第十六章以降は“古典を読む”で、初出は第1号(1999年10月号)から
第4号(2000年7月号)まで連載。
猫々堂「吉本隆明資料集122:イメージ論1993〜1994」
全163頁 頒価1700円+税(送料80円)
・目次
イメージ論1993〜1994(7〜13)………………… 2(イ)
ドストエフスキーのアジア……………………… 116(ロ)
「未来元型」を求めて(対談)…………………… 139(ハ)
編集ノート……………………………………… 161
※(イ)『新潮』に1993年8月からほぼ隔月で全13回掲載されたうちの
後半分で、前半分は「資料集113」に収録済み。この連載は1994
年12月に新潮社から「現在はどこにあるか」として刊行されま
した。現在絶版。
(ロ)1981年2月、澁谷・山手教会にての講演。1981年12月刊行の
「現代のドストエフスキー」所収。後に「超西欧的まで」にも
収録されました。
(ハ)樋口和彦との対談。1989年発行の「プシケー 8号」(日本ユング
クラブ会報)収録。
全163頁 頒価1700円+税(送料80円)
・目次
イメージ論1993〜1994(7〜13)………………… 2(イ)
ドストエフスキーのアジア……………………… 116(ロ)
「未来元型」を求めて(対談)…………………… 139(ハ)
編集ノート……………………………………… 161
※(イ)『新潮』に1993年8月からほぼ隔月で全13回掲載されたうちの
後半分で、前半分は「資料集113」に収録済み。この連載は1994
年12月に新潮社から「現在はどこにあるか」として刊行されま
した。現在絶版。
(ロ)1981年2月、澁谷・山手教会にての講演。1981年12月刊行の
「現代のドストエフスキー」所収。後に「超西欧的まで」にも
収録されました。
(ハ)樋口和彦との対談。1989年発行の「プシケー 8号」(日本ユング
クラブ会報)収録。
*吉本さんが逝去されたのち、保留されていた本がではじめました。
これはその最初のものでした。
(注)これらも順次整理して、掲載してゆきますね。●
●吉本隆明+石川九楊「書 文字 アジア」
四六判上製/270頁 定価2300円+税 筑摩書房
*帯の文
良寛、副島種臣、高村光太郎、宮沢賢治、岡本かの子、井上有一――
などの書字の構造を読み解き、
文字や言葉が孕む本源的問題に迫るとともに
日本的なるものの深層を浮彫りにする。
書の美はどこからくるのか。
戦後最大の思想家と現代書の鬼才による幻の白熱討議、全十二時間!
二十年の歳月を経ていま世に問う。
*目次
第1章 書の美はどこからくるのか
第2章 アジア的段階以前をどうとらえるのか
第3章 日本的なるものをどこで見るのか
付録 関連資料
石川九楊論 吉本隆明
石川九楊著『日本書史』を読む 吉本隆明
『言語にとって美とは何か』−二十一世紀へ残す本残る本 石川九楊
吉本さんからの宿題 石川九楊
編集後記 編集部
引用図版・参照文献一覧
※この本ための対談は1992年に行われた。
※関連資料はいずれも旧稿の再録です。
これはその最初のものでした。
(注)これらも順次整理して、掲載してゆきますね。●
●吉本隆明+石川九楊「書 文字 アジア」
四六判上製/270頁 定価2300円+税 筑摩書房
*帯の文
良寛、副島種臣、高村光太郎、宮沢賢治、岡本かの子、井上有一――
などの書字の構造を読み解き、
文字や言葉が孕む本源的問題に迫るとともに
日本的なるものの深層を浮彫りにする。
書の美はどこからくるのか。
戦後最大の思想家と現代書の鬼才による幻の白熱討議、全十二時間!
二十年の歳月を経ていま世に問う。
*目次
第1章 書の美はどこからくるのか
第2章 アジア的段階以前をどうとらえるのか
第3章 日本的なるものをどこで見るのか
付録 関連資料
石川九楊論 吉本隆明
石川九楊著『日本書史』を読む 吉本隆明
『言語にとって美とは何か』−二十一世紀へ残す本残る本 石川九楊
吉本さんからの宿題 石川九楊
編集後記 編集部
引用図版・参照文献一覧
※この本ための対談は1992年に行われた。
※関連資料はいずれも旧稿の再録です。
「吉本隆明資料集123:物語の中のメタファー/心の病の時代」
猫々堂 2013.3.10
・目次
出口裕弘『夜の扉』…………………………………… 2(イ)
よしもとばななをめぐって…………………………… 7(ロ)
諸悪の根源は民主・平等の思想(対談)………………25(ハ)
『鳩よ!』に寄せる言葉があれば……………………62(ニ)
茂吉の短歌を読む………………………………………64(ホ)
物語の中のメタファー…………………………………78(ヘ)
心の病の時代(対談)………………………………… 100(ト)
ブッダの実在性から究極の宗教的倫理まで(対談) 110(チ)
笠原さんのいちばん重要な思想…………………… 145(リ)
私の京都観…………………………………………… 146(ヌ)
こころの世紀………………………………………… 154(ル)
編集ノート………………………………………… 158
※(イ)1993年4月刊『夜の扉』跋文。
(ロ)『海燕』1993年5月号。
(ハ)安原顕との対談。1993年5月刊行『ふざけんな!』所収。
(ニ)『鳩よ!』1993年6月号
(ホ)『波』1993年7月号
(ヘ)『情況』1993年8/9月号
(ト)古井由吉との対談。『中央公論文藝特集』1993年9月号
(チ)笠原芳光『宗教の森』1993年9月刊所収
(リ)同上、帯文
(ヌ)『京都新聞』1993年10月29日
(ル)『京都新聞』1993年12月16-17日
※(ヘ)は後に深夜叢書社「寺山修司が生前構想した同人誌『雷帝』」
創刊終刊号(1993.12)に転載。
(ロ)と(ホ)以外は、吉本氏の単行本には未収録。
私的おぼえがき
1993年4月10日 「物語の中のメタファー」の講演に大澤と行く。そのあと吉本さんと懇親会に会費をだしてもらってでたが、(イベントなどで話ができず雰囲気ではなく)「あっ、これは・・・くさいですね。出ましょうか・・・」と言ってすぐ自宅に戻りしばらく気さくに話をさせてもらったことがある。
あれから20年たった。大澤が車を運転できた頃の話だ。(へ)物語の中のメタファー/心の病の時代」にまつわる思い出、深夜叢書の斉藤さんもきていて、主催者に近かったのか、主催者か・・・はじめてその時会った。
『フランシス子へ』 講談社2013.3.8
*宣伝文
吉本隆明が最晩年(亡くなる3ヵ月前)に、
自らの老いに重ね合わせながら語った、
最愛の猫・フランシス子の死。
猫好きで知られる吉本隆明氏は、人生のなかで数十匹の猫を飼ったが、
猫との長い生活をふりかえると、
なかでも「フランシス子」という猫が
いちばん心に残っているという。
そのフランシス子といえば、「とりたてて何もない猫」だった。
最愛の猫に死なれたとき、吉本氏は何を感じ、
その悲しみをどう乗り越えたのか。
「戦後思想界の巨人」が、生、老、病、死を考察する一冊を、
一周忌に寄せて刊行。
*帯の文
とりたてて何もない猫、
しかし相思相愛の仲だった――。
自らの死の三ヶ月前、吉本隆明が語った、
忘れがたき最愛の猫フランシス子の死。
*主な内容(目次はありません)
一匹の猫が死ぬこと
特別なところは何もない
いったいおまえは何なんだよ
(以下略)
吉本さんへ あとがきにかえて 瀧晴巳
鍵のない玄関 ハルノ宵子
『開店休業』
四六判並製/…頁 本体予価1500円+税 プレジデント社
*最後の作品。父と娘、感動のコラボ。
*40編すべてに長女のハルノ宵子さんによる「解説」つき!
*糸井重里氏“ほぼ日”で大絶賛!
「一周忌も近い吉本隆明さんの本が、4月になったらまた出版されるとの
ことです。雑誌『dancyu』に連載されていた食べものにまつわるエッセイ
集です。晩年は、目が不自由になっていたこともあって、口述筆記の原
稿ばかりになっていましたが、 この連載だけはなんとか手書きで書いて
いたものです。
(中略)ひとつひとつのエッセイの解説に、ハルノ宵子さんこと長女の
「さわちゃん」が、 本文を上回るような情報量と思いのある文を添えて
いる。食べものの軽いエッセイを読みはじめたつもりが、吉本家、いや、
日本のある家庭の歴史を読みこんでいるような気がしてくるものでした。」
※4月中旬刊となっていましたが、少し遅れるようです。
猫々堂「吉本隆明資料集124:二葉亭の文學/三木成夫さんについて」
全180頁 頒価1800円+税(送料80円)
・目次
二葉亭の文學…………………………………………… 2(イ)
「外側の文学」としてのビジネス書(対談)………… 9(ロ)
三木成夫さんについて…………………………………62(ハ)
社会党あるいは社会党的なるものの行方……………87(ニ)
『共同幻想論』を語る(鼎談)……………………… 120(ホ)
青年について………………………………………… 168(ヘ)
編集ノート………………………………………… 158
※(イ)「二葉亭四迷全集 別巻」月報。1993年9月
(ロ)芹沢俊介との対談。芹沢俊介「『ビジネス書』時代の欲望」。
1993年10月、時事通信社刊所収。
(ハ)1993年10月の講演。1994年11月刊「モルフォロギア 第16号
“特集・三木成夫の思想”」所収。この雑誌はゲーテ自然科学
の集いの発行で定価1262円+税。在庫あります。送料95円。
この講演はその後改題されて「新・死の位相学」に収録。
(ニ)1993年11月の講演。1994年1月刊「社会新報ブックレット16」所収。
その後、「全講演ライブ集」に収録。
(ホ)1993年12月収録、1996年7月刊のCD-ROM「吉本隆明『共同幻想論』
を語る」所収。その後「ミシェレル・フーコーと『共同幻想論』」
に収録。
(ヘ)千葉県立天羽高校にて、1965年10月の講演。「天高新聞 第50号」
1966年1月発行に掲載。
全180頁 頒価1800円+税(送料80円)
・目次
二葉亭の文學…………………………………………… 2(イ)
「外側の文学」としてのビジネス書(対談)………… 9(ロ)
三木成夫さんについて…………………………………62(ハ)
社会党あるいは社会党的なるものの行方……………87(ニ)
『共同幻想論』を語る(鼎談)……………………… 120(ホ)
青年について………………………………………… 168(ヘ)
編集ノート………………………………………… 158
※(イ)「二葉亭四迷全集 別巻」月報。1993年9月
(ロ)芹沢俊介との対談。芹沢俊介「『ビジネス書』時代の欲望」。
1993年10月、時事通信社刊所収。
(ハ)1993年10月の講演。1994年11月刊「モルフォロギア 第16号
“特集・三木成夫の思想”」所収。この雑誌はゲーテ自然科学
の集いの発行で定価1262円+税。在庫あります。送料95円。
この講演はその後改題されて「新・死の位相学」に収録。
(ニ)1993年11月の講演。1994年1月刊「社会新報ブックレット16」所収。
その後、「全講演ライブ集」に収録。
(ホ)1993年12月収録、1996年7月刊のCD-ROM「吉本隆明『共同幻想論』
を語る」所収。その後「ミシェレル・フーコーと『共同幻想論』」
に収録。
(ヘ)千葉県立天羽高校にて、1965年10月の講演。「天高新聞 第50号」
1966年1月発行に掲載。
猫々堂「吉本隆明資料集124:二葉亭の文學/三木成夫さんについて」
3奈良朝以前の言葉
じぶんの言語論の体系を拡張しようとかんがえていったとき、真っ先に問題にしたのは、大昔の日本語です。
現在、日本語といわれているものは、最大限さかのぼっても奈良朝以降の言葉です。
ところが日本人はもっとはるか昔にも日本語を使っていました。ところがその頃、どういう言葉を使っていたかというのはわからないんです。
でも、それを知る方法はふたつあります。
ひとつは日本語と類似した事だけれども、まだ未発達な社会、ぼくの事でいうと、「アフリカ的段階」にある地域で話されている言語で、日本語の祖先と似ていると思われるような言語を探っていくやり方です。
もうひとつは、個人のばあいで、母親のお腹にある時期の後半から一歳未満までの人間の言葉というのをつきつめていくやり方です。
このふたつのやり方は、三木さんの言葉でいえば、種族の発展と個体の発展ということになりますが、このふたつのやり方で接近するほかありません。
三木成夫さんについて…………………………………62(ハ)
『モルフォロギア・特集ゲーテと自然科学・第16号』1994.11.3所収
改題「三木成夫の方法と前古代言語」『新・死の位相学』春秋社1997.8
3奈良朝以前の言葉
じぶんの言語論の体系を拡張しようとかんがえていったとき、真っ先に問題にしたのは、大昔の日本語です。
現在、日本語といわれているものは、最大限さかのぼっても奈良朝以降の言葉です。
ところが日本人はもっとはるか昔にも日本語を使っていました。ところがその頃、どういう言葉を使っていたかというのはわからないんです。
でも、それを知る方法はふたつあります。
ひとつは日本語と類似した事だけれども、まだ未発達な社会、ぼくの事でいうと、「アフリカ的段階」にある地域で話されている言語で、日本語の祖先と似ていると思われるような言語を探っていくやり方です。
もうひとつは、個人のばあいで、母親のお腹にある時期の後半から一歳未満までの人間の言葉というのをつきつめていくやり方です。
このふたつのやり方は、三木さんの言葉でいえば、種族の発展と個体の発展ということになりますが、このふたつのやり方で接近するほかありません。
三木成夫さんについて…………………………………62(ハ)
『モルフォロギア・特集ゲーテと自然科学・第16号』1994.11.3所収
改題「三木成夫の方法と前古代言語」『新・死の位相学』春秋社1997.8
『心的現象論本論』文化科学高等研究院出版局(E.H.E.S.C.)2008.7.1
植物のからだは、動物の腸管をひきぬいて裏返しにしたもので、根毛は腸内の繊毛が露出したとおなじで、それによって大地と大気にからだを開放しているから、たんに自然の一部だというだけでなく、自然の「生物学的な部分」をなしている。
動物のからだは、肝臓と腎臓という入口と出口で、きびしく外界の自然から遮断されている。さらに体壁系で、それを体内に封じこめて、体腔と腸腔を入江にしている。体壁系は感覚−運動をつかさどる大脳皮質とともに、接触する外界の自然に反応する。内臓系は遠方の外界と共振する「植物器官」であるといえる。「101原了解論以前(7)」p436p437
植物のからだは、動物の腸管をひきぬいて裏返しにしたもので、根毛は腸内の繊毛が露出したとおなじで、それによって大地と大気にからだを開放しているから、たんに自然の一部だというだけでなく、自然の「生物学的な部分」をなしている。
動物のからだは、肝臓と腎臓という入口と出口で、きびしく外界の自然から遮断されている。さらに体壁系で、それを体内に封じこめて、体腔と腸腔を入江にしている。体壁系は感覚−運動をつかさどる大脳皮質とともに、接触する外界の自然に反応する。内臓系は遠方の外界と共振する「植物器官」であるといえる。「101原了解論以前(7)」p436p437
吉本隆明『改訂新版心的現象論序説』角川学芸文庫2013.2.25
わたしたちがなにものかとして振舞おうとするとき、すでに常識からの踏みはずしを意味しており、現在スターリン的唯物論は、ひとによっては〈マルクス主義〉と呼んだりしているが、説話になった常識以外の意味を、どんな領域でももっていないのである。わたしのかんがえではマルクスの知見のうちもっともすぐれており、もっとも貴重なのはかれがその体系のうちに観念の運動についての弁償を保存しているところにある。それなくしてはかれの体系は自然科学、抽象論理学の発展によってとうに古びてしまっていたであろう。げんにそれは悪しき唯物論の現在における命運によって検証される。
「心的現象論」初出『試行第十五号』1965.10.25発行
わたしたちがなにものかとして振舞おうとするとき、すでに常識からの踏みはずしを意味しており、現在スターリン的唯物論は、ひとによっては〈マルクス主義〉と呼んだりしているが、説話になった常識以外の意味を、どんな領域でももっていないのである。わたしのかんがえではマルクスの知見のうちもっともすぐれており、もっとも貴重なのはかれがその体系のうちに観念の運動についての弁償を保存しているところにある。それなくしてはかれの体系は自然科学、抽象論理学の発展によってとうに古びてしまっていたであろう。げんにそれは悪しき唯物論の現在における命運によって検証される。
「心的現象論」初出『試行第十五号』1965.10.25発行
吉本隆明『定本言語にとって美とはなにか』角川文庫2001.9.25
おわりにいや味になるので小さな声でいわなくてはならないが、そのときは夢中でわからなかったが、こんど読みかえしてみて、無意識だったがじぶんはじぶんがそのときおもっていたよりも、ずっと重要なことをやったなと感じて、すこし興奮しながら旧稿を読みおえた。いまおなじことをやれと言われれば、ちがうやり方をするだろうし、すこしは成熟しているだろうが、旧稿のこころがおどるような発見の手ごたえは、なかなか獲得できないとおもう。読者に知識といっしょにそのこころおどりが提供できたら、なによりだとおもっている。「選書のための覚書」1990.2.24
おわりにいや味になるので小さな声でいわなくてはならないが、そのときは夢中でわからなかったが、こんど読みかえしてみて、無意識だったがじぶんはじぶんがそのときおもっていたよりも、ずっと重要なことをやったなと感じて、すこし興奮しながら旧稿を読みおえた。いまおなじことをやれと言われれば、ちがうやり方をするだろうし、すこしは成熟しているだろうが、旧稿のこころがおどるような発見の手ごたえは、なかなか獲得できないとおもう。読者に知識といっしょにそのこころおどりが提供できたら、なによりだとおもっている。「選書のための覚書」1990.2.24
『iichiko吉本隆明の文学論SPRING 2013 NO.118』文化科学高等研究院出版局 2013.4.30(新刊)
文学は、言語物質性を基盤にしながら、想像的表出が多様になされていく。それを解釈したり批評したりする多様性は、さらに拡散していく。そこを不可能さとみなすのではなく、可能条件の考究として道筋をつけていくには、吉本文学論をひとつの基準にしていく事が要される。ポリティカルな規制性へ還元するのではない、文学からしかせまれない閾が、たとえば「非自己」界などは、そこにある。「Director’s Note編集・研究ディレクター 山本哲士」
(メモ)この人の文章のいいまわしには馴れないのだが、ここで提出している「非自己」界は西欧社会にはない日本人の独自な意識領域であることは『心的現象論』などでいわれている。主体的自我+非自己が日本人の〈わたし〉であるそうな。これは世界レヴェルでの発見で翻訳されれば世界が驚愕するだろうと山本はいう。
文学は、言語物質性を基盤にしながら、想像的表出が多様になされていく。それを解釈したり批評したりする多様性は、さらに拡散していく。そこを不可能さとみなすのではなく、可能条件の考究として道筋をつけていくには、吉本文学論をひとつの基準にしていく事が要される。ポリティカルな規制性へ還元するのではない、文学からしかせまれない閾が、たとえば「非自己」界などは、そこにある。「Director’s Note編集・研究ディレクター 山本哲士」
(メモ)この人の文章のいいまわしには馴れないのだが、ここで提出している「非自己」界は西欧社会にはない日本人の独自な意識領域であることは『心的現象論』などでいわれている。主体的自我+非自己が日本人の〈わたし〉であるそうな。これは世界レヴェルでの発見で翻訳されれば世界が驚愕するだろうと山本はいう。
吉本隆明・ハルノ宵子(追想・画)『開店休業』プレジデント社2013.4.30≪新刊≫
何歳くらいから、老いの自覚がやってくるのか。それは人によってさまざまだろう。(中略)そのとき、何が自分の中で変わったのかを、思いつくままに挙げてみると、ひとつは、自分よりも年寄だったとわかれば、性別や世間的な因縁に関係なく、敬意を表すようになったということ。いきおい、近所で出くわすおばあさんやおじいさんに対して、ということになる。もうひとつ挙げれば、歯が浮くようになったこと。固いものが食べにくくなったということである。「老いてますます」
メモ:吉本さんの日常の何気ない立居振舞から、食べ物の好き嫌いまで世話役を〈
関係の絶対性として〉(笑)引き受けた長女の父への思いが切々とあるいは淡々と語られている。ともかく彼女も生きてある限りのぎりぎりの瀬戸際でこの状況を引き受け生きた、のだと思う。ひとつまちがえば、彼女のほうがさきに逝ってしまったかもしれない・・・
何歳くらいから、老いの自覚がやってくるのか。それは人によってさまざまだろう。(中略)そのとき、何が自分の中で変わったのかを、思いつくままに挙げてみると、ひとつは、自分よりも年寄だったとわかれば、性別や世間的な因縁に関係なく、敬意を表すようになったということ。いきおい、近所で出くわすおばあさんやおじいさんに対して、ということになる。もうひとつ挙げれば、歯が浮くようになったこと。固いものが食べにくくなったということである。「老いてますます」
メモ:吉本さんの日常の何気ない立居振舞から、食べ物の好き嫌いまで世話役を〈
関係の絶対性として〉(笑)引き受けた長女の父への思いが切々とあるいは淡々と語られている。ともかく彼女も生きてある限りのぎりぎりの瀬戸際でこの状況を引き受け生きた、のだと思う。ひとつまちがえば、彼女のほうがさきに逝ってしまったかもしれない・・・
吉本隆明『マスイメージ論』講談社学芸文庫(新刊)2013.3.16
大ざっぱな言葉でくくってしまうと、『マス・イメージ論』において吉本が引用した個々の作品の断片は、そのことごとくが「全体的な暗喩」として、『現在』という共同幻想のありようを示唆しているということになるのである。いいかえると、「現代」という共同幻想は、そうした「全体的な暗喩」を「介して」、それを「迂回路」として用いることで、「現代」にアクセスを試みることである。p330鹿島茂「解説」
メモ)
『マスイメージ論』が鹿島の解説がついて再刊された。鹿島は吉本がまったく評価することのなかったヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』と相似していると述べる。「個人にとって外的であるようなかなり多くのものが、集団にとっては内的なものである」と。
しかし、依然としてこの論を読み解くことはむづかしい。
大ざっぱな言葉でくくってしまうと、『マス・イメージ論』において吉本が引用した個々の作品の断片は、そのことごとくが「全体的な暗喩」として、『現在』という共同幻想のありようを示唆しているということになるのである。いいかえると、「現代」という共同幻想は、そうした「全体的な暗喩」を「介して」、それを「迂回路」として用いることで、「現代」にアクセスを試みることである。p330鹿島茂「解説」
メモ)
『マスイメージ論』が鹿島の解説がついて再刊された。鹿島は吉本がまったく評価することのなかったヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』と相似していると述べる。「個人にとって外的であるようなかなり多くのものが、集団にとっては内的なものである」と。
しかし、依然としてこの論を読み解くことはむづかしい。
吉本隆明『マスイメージ論』講談社学芸文庫(新刊)2013.3.16
しかしそれにしても、いや、それにしても、一九八〇年代初頭に、この必敗の戦いに、それまでのすべてを捨てて踏み切ろうとした吉本隆明はやはり偉大なる思想的ファイターであったというほかはないのである。
なぜならば、二十一世紀もすでに十三年を経過し、いよいよ、世紀をまたぐ三十年という決定的な過渡期が終わろうとしている今日においてさえ、「現代」という共同幻想の実態は依然として見えてきてはいないからである。p331p332鹿島茂「解説」
メモ
『パサージュ論』で述べているように、世紀をまたぐ三十年という過渡期がおわろうとしている、それはいまこそが「目覚め」の瞬間であり、現代を捉えるときであろうと鹿島はいう。刊行からほぼ三十年を経た今日、若い世代によって「現代」からの目覚めの契機として読まれることを切に願ってやまない、と。
しかしそれにしても、いや、それにしても、一九八〇年代初頭に、この必敗の戦いに、それまでのすべてを捨てて踏み切ろうとした吉本隆明はやはり偉大なる思想的ファイターであったというほかはないのである。
なぜならば、二十一世紀もすでに十三年を経過し、いよいよ、世紀をまたぐ三十年という決定的な過渡期が終わろうとしている今日においてさえ、「現代」という共同幻想の実態は依然として見えてきてはいないからである。p331p332鹿島茂「解説」
メモ
『パサージュ論』で述べているように、世紀をまたぐ三十年という過渡期がおわろうとしている、それはいまこそが「目覚め」の瞬間であり、現代を捉えるときであろうと鹿島はいう。刊行からほぼ三十年を経た今日、若い世代によって「現代」からの目覚めの契機として読まれることを切に願ってやまない、と。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
<吉本隆明・戦後最大の思想家> 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
<吉本隆明・戦後最大の思想家>のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 38350人
- 2位
- 暮らしを楽しむ
- 77055人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19835人