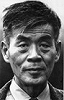|
|
|
|
コメント(42)
「地に足を着ける」と言うのは「自分自身の根拠と向き合う」と言う事かと思います。
例えば「天皇」にたいする自分の考え方についてです。私は吉本さんの「山本七平らが、天皇は立憲君主だから戦争責任はない、というのは納得ゆかない。神聖皇帝的な要素があったんだ、それをどうするんだ」と言う発言(だいたいこういう主旨だったと思います。)に深く共感しました。
特に「神聖皇帝」と言う部分です。山本氏の意見は一理以上のものがあるし「現人神の創作者たち」を興味深く読みました。しかし、そこに掬い上げれないもの、そして非常に深く暗いものがあります。それば三島由紀夫の「英霊の声」に通じるものかもしれません。
私は保守派の微温的な「親皇室」にも、コミンテルンテーゼの「反天皇」にも、古典右翼の「天皇崇拝」にも違和感を覚えます。私は戦後世代ですが祖母の世代の「皇室崇敬」に心情的影響を受けておりました。そんな私が吉本さんの受け売りで「体制の補完物に過ぎないのさ、終わってるのさ!」と言っても「嘘」になりますし、又魅力的なイデオロギーが出てきた時に変説するのがオチでしょう。
自分自身の根拠と向き合いながら、紆余曲折して現在では「政治権力と結び付かない神聖な皇室」を希求したいと思っております。実現可能かどうか別として。
地に足を着けるとは自身の経験からするとこのような事かな、と理解しております。吉本さんの主旨とはずれてるかもしれませんし、私は大衆なので「思想」なんて高尚なものではありませんが。
例えば「天皇」にたいする自分の考え方についてです。私は吉本さんの「山本七平らが、天皇は立憲君主だから戦争責任はない、というのは納得ゆかない。神聖皇帝的な要素があったんだ、それをどうするんだ」と言う発言(だいたいこういう主旨だったと思います。)に深く共感しました。
特に「神聖皇帝」と言う部分です。山本氏の意見は一理以上のものがあるし「現人神の創作者たち」を興味深く読みました。しかし、そこに掬い上げれないもの、そして非常に深く暗いものがあります。それば三島由紀夫の「英霊の声」に通じるものかもしれません。
私は保守派の微温的な「親皇室」にも、コミンテルンテーゼの「反天皇」にも、古典右翼の「天皇崇拝」にも違和感を覚えます。私は戦後世代ですが祖母の世代の「皇室崇敬」に心情的影響を受けておりました。そんな私が吉本さんの受け売りで「体制の補完物に過ぎないのさ、終わってるのさ!」と言っても「嘘」になりますし、又魅力的なイデオロギーが出てきた時に変説するのがオチでしょう。
自分自身の根拠と向き合いながら、紆余曲折して現在では「政治権力と結び付かない神聖な皇室」を希求したいと思っております。実現可能かどうか別として。
地に足を着けるとは自身の経験からするとこのような事かな、と理解しております。吉本さんの主旨とはずれてるかもしれませんし、私は大衆なので「思想」なんて高尚なものではありませんが。
吉本さんは敗戦によってそれまで信じていた思想が崩壊した時、ならば戦前や戦中に何か優れた思想的いとなみが築かれていたのか探索し、そうしたものがあったならそれを糧として戦後を出発しようと思ったところ、
右から左まで何ら本質的な思想の営みなど日本人はして来なかったことを発見して愕然とし、ならば自分で徹底的に読み考えてゆくしかない、と思われたそうですね。
マルクス主義に向き合うのも、自分でマルクスその人のテキストを読み込むしかないと思ってそうした時、吉本さんは衝撃を受ける。
あんなに自分たちがすべてを捨てて国家のためにと思い、賭けて来たのに、
「何とマルクスは国家とは幻想だ、と言っている!」
『カールマルクス』光文社文庫2006.3.20
「ランボー若くはカール・マルクスの方法に就いての諸註」『詩文化第13号8月号』1949.8.20初出.『擬制の終焉』現代思潮社1962.6.30 『吉本隆明全著作集5』勁草書房1970.6.25
詩的思想とは正に意識の実在を、あたかも樹木があり建築があると同じ意味で確信する処にのみ成立するのである。斯かる確信は何ら理論的根拠を有しないかも知れぬ。だが、斯かる確信は最上の詩人たちが生涯を通じて失わなかった例外なき真実の措定である。意識は意識的存在以外の何ものでもないといふマルクスの措定は
存在は意識がなければ意識的存在であり得ないといふ逆措定を含む。
「ランボー若くはカール・マルクスの方法に就いての諸註」『詩文化第13号8月号』1949.8.20初出.『擬制の終焉』現代思潮社1962.6.30 『吉本隆明全著作集5』勁草書房1970.6.25
詩的思想とは正に意識の実在を、あたかも樹木があり建築があると同じ意味で確信する処にのみ成立するのである。斯かる確信は何ら理論的根拠を有しないかも知れぬ。だが、斯かる確信は最上の詩人たちが生涯を通じて失わなかった例外なき真実の措定である。意識は意識的存在以外の何ものでもないといふマルクスの措定は
存在は意識がなければ意識的存在であり得ないといふ逆措定を含む。
>>[14] 78910さん
すみません、いま操作をミスしたので13を消去してしまったので、15に再掲載しました。
遅いのは、わたしも遅くってこまってはいますが、そういうことです。
ところで、この「マルクス論」は、はじめての本格的英訳のようですね。
マニュエル・ヤンはこれが博士論文だったようです。つまり翻訳できれば博士号はとれる・・・。
いやぁ吉本のものは、英訳も仏訳もないので世界市場では未だ無名のようです。『共同幻想論』が昔出たこともありましたが・・・本格的仏訳も未だ・・・というその筋の認識のようですね。
いま吉本全集40巻が晶文社のほうで準備されていますが、そこでは仏訳の話がでているようでは・・・あるようです。はっきりはしていませんが・・・。
いずれにしても、文化的土壌の全く違う西洋と東洋での翻訳は「高度なもの」ほど微妙にむずかしいでしょうね。
特に吉本の文体は、自己表出の多くはいった日本語で思考されている文体なので訳してみたら、おもしろくもなんでもない(たとえば俳句の仏訳のようなものなど)ということもありうるのかなぁ・・・。いやぁ、むずかしいものです。
>>[016]
吉本さんの作品はどれも、戦中や戦後の日本人の各層の心の機微を丁寧にすくってくれる所に独特の魅力があるように僕は思うのですが、
そういう吉本さんが第一に想定していた読者すなわち日本人ではない人々、アメリカ人やらフランス人やらに対して吉本さんの魅力が果たしてちゃんと届くかというのは、ほんと難しいですね。
ただ、一語一語を訳せばいいというのではなく、その言葉を誰にどう届かせようとしているか、という解説が伴わなければ、
日本人が吉本隆明を受けとめた真実はなかなか外国人には伝わらないのではないかなあとも思います。
とはいえ、吉本さんが極力、普遍的グローバルな文脈で語っている著書があるとするならば、
そのような作品を厳選してまずは翻訳する、ということはぜひ試みられるべきだと思います。
吉本さんの作品はどれも、戦中や戦後の日本人の各層の心の機微を丁寧にすくってくれる所に独特の魅力があるように僕は思うのですが、
そういう吉本さんが第一に想定していた読者すなわち日本人ではない人々、アメリカ人やらフランス人やらに対して吉本さんの魅力が果たしてちゃんと届くかというのは、ほんと難しいですね。
ただ、一語一語を訳せばいいというのではなく、その言葉を誰にどう届かせようとしているか、という解説が伴わなければ、
日本人が吉本隆明を受けとめた真実はなかなか外国人には伝わらないのではないかなあとも思います。
とはいえ、吉本さんが極力、普遍的グローバルな文脈で語っている著書があるとするならば、
そのような作品を厳選してまずは翻訳する、ということはぜひ試みられるべきだと思います。
>>[17]
>吉本さんが第一に想定していた読者すなわち日本人ではない人々、アメリカ人やらフランス人
>普遍的グローバルな文脈で語っている著書があるとするならば、
そのような作品
ここはわかりません。こういう発想はたぶんないでしょう。普遍的であることを日本語では追及しておりましたが・・・。
>日本人が吉本隆明を受けとめた真実はなかなか外国人には伝わらないのではないかなあ
そうでしょうね。日本人にだってわからない人にはわからない。特に若い世代には読めないようですね。書き言葉としての吉本は・・・。
晩年目が見えなくなってからは若い人向きの口述筆記はおおくなりましたが・・・。特に糸井さん経由の読者はいましたけれどね・・・。
本質的な文章はおもしろい人にはおもしろいでしょうけれど、機能主義的な人にはまったくわからないようですね・・・。
>吉本さんが第一に想定していた読者すなわち日本人ではない人々、アメリカ人やらフランス人
>普遍的グローバルな文脈で語っている著書があるとするならば、
そのような作品
ここはわかりません。こういう発想はたぶんないでしょう。普遍的であることを日本語では追及しておりましたが・・・。
>日本人が吉本隆明を受けとめた真実はなかなか外国人には伝わらないのではないかなあ
そうでしょうね。日本人にだってわからない人にはわからない。特に若い世代には読めないようですね。書き言葉としての吉本は・・・。
晩年目が見えなくなってからは若い人向きの口述筆記はおおくなりましたが・・・。特に糸井さん経由の読者はいましたけれどね・・・。
本質的な文章はおもしろい人にはおもしろいでしょうけれど、機能主義的な人にはまったくわからないようですね・・・。
>>[018]
言葉足らずでした。(^o^ゞ
戦中、戦後の日本人のジリジリと焼けつくような実際の心に向き合いながら、
しかもまさにその時その時の日本と日本人がたどっていた沸騰する時代状況に鋭くメスを入れる中で、
普遍的な理念を紡ぎ出そうと格闘されていた吉本さんの一つ一つの言説が、
そういう1940年代、50年代、60年代の日本人の心にも特別な関心もなく、またそこで彼ら彼女らが実際に直面しもがいていた情況そのものにも特別な関心や知識のない人々に、
一体どれほど読んでみたいという需要を喚び起こすか、ということです。
おっしゃるように吉本さんは、日本という地域的な特殊事情やら時代的特殊事情と積極的に切り結びながら、あくまでも普遍的な何かを常につかみ出そうとされていたと思います。
言葉足らずでした。(^o^ゞ
戦中、戦後の日本人のジリジリと焼けつくような実際の心に向き合いながら、
しかもまさにその時その時の日本と日本人がたどっていた沸騰する時代状況に鋭くメスを入れる中で、
普遍的な理念を紡ぎ出そうと格闘されていた吉本さんの一つ一つの言説が、
そういう1940年代、50年代、60年代の日本人の心にも特別な関心もなく、またそこで彼ら彼女らが実際に直面しもがいていた情況そのものにも特別な関心や知識のない人々に、
一体どれほど読んでみたいという需要を喚び起こすか、ということです。
おっしゃるように吉本さんは、日本という地域的な特殊事情やら時代的特殊事情と積極的に切り結びながら、あくまでも普遍的な何かを常につかみ出そうとされていたと思います。
吉本隆明『カールマルクス』光文社文庫p52p53
マルクスが、ヘーゲルの法哲学と国法論の主要な箇条を批判的にとりあげることによってあきらかにしようとしたのは、政治的国家の実体構造であり、これに対応する市民社会の政治的要素とはなにか、であったということができる。
まず、政治的国家というものは、〈家族〉という人間の自然的な基礎と、〈市民社会〉という人工的な基礎が、自己自身を〈国家〉にまで疎外するものであるにもかかわらず、ヘーゲルは、逆に、現実的理念によって国家がつくられたようにかんがえているというのが、マルクスの根本的なヘーゲル批判であった。
たとえば、古代国家では、政治的な国家がすべてであり、人間の現実的社会は、すみずみまで政治的な国家の手足のように存在している。
しかし、近代資本制国家では、政治的な国家と非政治的な国家とが〈法〉によって調節されて二重に存在している。政治的国家は非政治的国家の具体性である市民社会を内容としながら、それから疎外された形式上の共同性として存在する。だから国家と家族や市民社会とはヘーゲルのいうような矛盾のない存在ではありえない。
国家は、家族や市民社会自体の生活過程が表象されたものではなく、家族や市民社会が、自己から区別し分離する(〈疎外〉する)理念の生活過程である。
だから、この理念の生活過程を政治的に集中した〈法〉(憲法=政治的国家制度)は、国民の現実的な生活の地上性に対立する普遍性の宗教的な天国である。
政治的国家を実体的に(いいかえれば形式と内容との幻想の合一として)ささえているのは官僚制であり、この官僚制の内部では、実在の国家とならんだ想像力の国家が成立している。
マルクスが、ヘーゲルの法哲学と国法論の主要な箇条を批判的にとりあげることによってあきらかにしようとしたのは、政治的国家の実体構造であり、これに対応する市民社会の政治的要素とはなにか、であったということができる。
まず、政治的国家というものは、〈家族〉という人間の自然的な基礎と、〈市民社会〉という人工的な基礎が、自己自身を〈国家〉にまで疎外するものであるにもかかわらず、ヘーゲルは、逆に、現実的理念によって国家がつくられたようにかんがえているというのが、マルクスの根本的なヘーゲル批判であった。
たとえば、古代国家では、政治的な国家がすべてであり、人間の現実的社会は、すみずみまで政治的な国家の手足のように存在している。
しかし、近代資本制国家では、政治的な国家と非政治的な国家とが〈法〉によって調節されて二重に存在している。政治的国家は非政治的国家の具体性である市民社会を内容としながら、それから疎外された形式上の共同性として存在する。だから国家と家族や市民社会とはヘーゲルのいうような矛盾のない存在ではありえない。
国家は、家族や市民社会自体の生活過程が表象されたものではなく、家族や市民社会が、自己から区別し分離する(〈疎外〉する)理念の生活過程である。
だから、この理念の生活過程を政治的に集中した〈法〉(憲法=政治的国家制度)は、国民の現実的な生活の地上性に対立する普遍性の宗教的な天国である。
政治的国家を実体的に(いいかえれば形式と内容との幻想の合一として)ささえているのは官僚制であり、この官僚制の内部では、実在の国家とならんだ想像力の国家が成立している。
吉本隆明著『カール・マルクス』光文社文庫2006.3.20から「マルクス紀行」
マルクスの自然哲学―疎外論が『言語にとって美とは何か』『共同幻想論』『心的現象論』の礎。
引用
〈疎外〉という概念は、マルクスによって(略)それがどのようにつかわれていても、累層と連環によって他の概念におおわれているという点にあった。そこにマルクス思想の総体性が存在している。
かれの思想が、宗教・法・国家・市民社会・自然をつなぐ総体性として完結したとき、まだ、ほんとうの意味で社会の歴史的現存性のおそろしさをしらぬ青年であった。(略)
(なぜ、一見すると脆弱そうにみえるこの不合理な社会はこれほど強固なのか?マルクスが、こういう自問自答をほんとうの意味で強いられたのは、西欧のデモクラートの蜂起が挫折し、そのあおりをくらって解体した〈共産主義同盟〉が内紛のうちにかれをしめだし、かれが貧困のさ中に公然と孤立したときである。ここで、マルクスの現実的な体験が、転向としてその思想に関与する。その意味は、マルクス自身がかんがえたよりも、おそらく重要であった。)
世のいわゆる〈マルクス〉の思想的棺は、現存する社会を歴史的な累積として検討するために、かれがのめりこんでいったそれ以後の経済的カテゴリーを第一義とする思想にかぎられている。わたしは、ただ、かれらのような棺のかつぎかたをしないということだけをいってこの稿と訣れなければならぬ。もはや、読者はそれぞれの道をゆくべきときだ。
◆「マルクス紀行」『図書新聞』(1964年7月18日号〜8月29日号)に「マルクス紀行―幻想性の考察から『詩的』と『非詩的』の逆立へ」の題で七回連載。
以後『カール・マルクス』(1966年、試行出版部刊)その後様々な著作集に収録されている。一番身近なものでは、光文社文庫『カール・マルクス』2006.3.20に収録されている。
メモ
・すでに1964年に吉本はいわゆるマルクス主義左翼(新左翼)とは深く決別していた。
・そのことを確認するために、わたしは半世紀におよぶ生存経験を必要とした・・・。いや、まだほんとうはわかっていないかもしれない・・・。
参考:初期マルクス
★1841
学位論文『デモクリトスの自然哲学とエピクロスの自然哲学の差異』
□『マルクス=エンゲルス全集』第四〇巻、岩崎允胤訳、大月書店
★1843
◆ヘーゲル法哲学の批判から
□『マルクス=エンゲルス全集』第一巻、真下信一訳、大月書店
□Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegelschen Staatsrechts
★1844
◆ユダヤ人問題によせて
□『マルクス=エンゲルス全集』第一巻、花田圭介訳、大月書店
□『ユダヤ人問題によせて ヘーゲル法哲学批判序説』城塚登訳、岩波文庫
□On The Jewish Question
◆ヘーゲル法哲学批判 序説
□『マルクス=エンゲルス全集』第一巻、花田圭介訳、大月書店
□『ユダヤ人問題によせて ヘーゲル法哲学批判序説』城塚登訳、岩波文庫
□『ヘーゲル法哲学批判序論』真下信一訳、国民文庫、大月書店、1970
□Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law. Introduction.
◆経済学・哲学手稿
□『マルクス=エンゲルス全集』第四〇巻、真下信一訳、大月書店
□『経済学・哲学草稿』城塚・田中訳、岩波文庫、1964
□『経済学・哲学草稿』藤野渉訳、国民文庫、大月書店、1963
□Economic and Philosophic Manuscripts
マルクス著作目録(作成:中山元)
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/marxismco/marxism_genriron_gensyo_tyosakumokuroku.htm
吉本隆明著『カール・マルクス』中沢新一解説・光文社文庫2006年から
こんなにも平易な文章によって、空恐ろしいほどに深い真実をあきらかにしてみせる吉本隆明の力量に、なによりも圧倒された。あとにもさきにも、日本にもヨーロッパにも、これほどに深いマルクス論に、私は出会ったことがない。
マルクスの自然哲学―疎外論が『言語にとって美とは何か』『共同幻想論』『心的現象論』の礎。
引用
〈疎外〉という概念は、マルクスによって(略)それがどのようにつかわれていても、累層と連環によって他の概念におおわれているという点にあった。そこにマルクス思想の総体性が存在している。
かれの思想が、宗教・法・国家・市民社会・自然をつなぐ総体性として完結したとき、まだ、ほんとうの意味で社会の歴史的現存性のおそろしさをしらぬ青年であった。(略)
(なぜ、一見すると脆弱そうにみえるこの不合理な社会はこれほど強固なのか?マルクスが、こういう自問自答をほんとうの意味で強いられたのは、西欧のデモクラートの蜂起が挫折し、そのあおりをくらって解体した〈共産主義同盟〉が内紛のうちにかれをしめだし、かれが貧困のさ中に公然と孤立したときである。ここで、マルクスの現実的な体験が、転向としてその思想に関与する。その意味は、マルクス自身がかんがえたよりも、おそらく重要であった。)
世のいわゆる〈マルクス〉の思想的棺は、現存する社会を歴史的な累積として検討するために、かれがのめりこんでいったそれ以後の経済的カテゴリーを第一義とする思想にかぎられている。わたしは、ただ、かれらのような棺のかつぎかたをしないということだけをいってこの稿と訣れなければならぬ。もはや、読者はそれぞれの道をゆくべきときだ。
◆「マルクス紀行」『図書新聞』(1964年7月18日号〜8月29日号)に「マルクス紀行―幻想性の考察から『詩的』と『非詩的』の逆立へ」の題で七回連載。
以後『カール・マルクス』(1966年、試行出版部刊)その後様々な著作集に収録されている。一番身近なものでは、光文社文庫『カール・マルクス』2006.3.20に収録されている。
メモ
・すでに1964年に吉本はいわゆるマルクス主義左翼(新左翼)とは深く決別していた。
・そのことを確認するために、わたしは半世紀におよぶ生存経験を必要とした・・・。いや、まだほんとうはわかっていないかもしれない・・・。
参考:初期マルクス
★1841
学位論文『デモクリトスの自然哲学とエピクロスの自然哲学の差異』
□『マルクス=エンゲルス全集』第四〇巻、岩崎允胤訳、大月書店
★1843
◆ヘーゲル法哲学の批判から
□『マルクス=エンゲルス全集』第一巻、真下信一訳、大月書店
□Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegelschen Staatsrechts
★1844
◆ユダヤ人問題によせて
□『マルクス=エンゲルス全集』第一巻、花田圭介訳、大月書店
□『ユダヤ人問題によせて ヘーゲル法哲学批判序説』城塚登訳、岩波文庫
□On The Jewish Question
◆ヘーゲル法哲学批判 序説
□『マルクス=エンゲルス全集』第一巻、花田圭介訳、大月書店
□『ユダヤ人問題によせて ヘーゲル法哲学批判序説』城塚登訳、岩波文庫
□『ヘーゲル法哲学批判序論』真下信一訳、国民文庫、大月書店、1970
□Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law. Introduction.
◆経済学・哲学手稿
□『マルクス=エンゲルス全集』第四〇巻、真下信一訳、大月書店
□『経済学・哲学草稿』城塚・田中訳、岩波文庫、1964
□『経済学・哲学草稿』藤野渉訳、国民文庫、大月書店、1963
□Economic and Philosophic Manuscripts
マルクス著作目録(作成:中山元)
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/marxismco/marxism_genriron_gensyo_tyosakumokuroku.htm
吉本隆明著『カール・マルクス』中沢新一解説・光文社文庫2006年から
こんなにも平易な文章によって、空恐ろしいほどに深い真実をあきらかにしてみせる吉本隆明の力量に、なによりも圧倒された。あとにもさきにも、日本にもヨーロッパにも、これほどに深いマルクス論に、私は出会ったことがない。
>>[27]
あ、いま気がつきました。この、
『ヘーゲル法哲学批判序論』真下信一訳、国民文庫、大月書店、1970
に「ヘーゲル国法論批判Kritik des Hegelschen Staatsrechts 」が収録されてたんです。
「ユダヤ人問題」もこれに入ってた。
「序論」は短いもので、それほどのこと言ってません。
分量的にも「国法論批判」が圧倒的です。
「国法論批判」はヘーゲルのテキストを、ほとんど逐行的に批判していきます。
相手をここまで徹底して読まなくては「批判」なんてできない。
それを知るだけでも、読む価値があります。
吉本さんは、これ読んでるかどうか。
この国民文庫はたぶん、大月版『全集』からの抜粋です(未確認)。
吉本さんがマルクス論書くのと、この翻訳の刊行とどちらが先か。
またこれ以外に、翻訳があったか。
その辺は調べれば分りますよね。
どうなのかなあ。
あ、いま気がつきました。この、
『ヘーゲル法哲学批判序論』真下信一訳、国民文庫、大月書店、1970
に「ヘーゲル国法論批判Kritik des Hegelschen Staatsrechts 」が収録されてたんです。
「ユダヤ人問題」もこれに入ってた。
「序論」は短いもので、それほどのこと言ってません。
分量的にも「国法論批判」が圧倒的です。
「国法論批判」はヘーゲルのテキストを、ほとんど逐行的に批判していきます。
相手をここまで徹底して読まなくては「批判」なんてできない。
それを知るだけでも、読む価値があります。
吉本さんは、これ読んでるかどうか。
この国民文庫はたぶん、大月版『全集』からの抜粋です(未確認)。
吉本さんがマルクス論書くのと、この翻訳の刊行とどちらが先か。
またこれ以外に、翻訳があったか。
その辺は調べれば分りますよね。
どうなのかなあ。
>[28] papapapapaさん
このことについて、手元にある資料で調べましたところ
★1843
◆ヘーゲル法哲学の批判から
□『マルクス=エンゲルス全集』第一巻、真下信一訳、大月書店
「ヘーゲル法哲学の批判から」の副題がヘーゲル国法論(第261節―第313節)の批判ですね。
いま、てもとにある『マルクス=エンゲルス全集』第一巻は1959年10月20日発行とありますので、吉本は当然、これを読んでいると思われます。
また、中山元さんのマルクス著作目録では翻訳はこれしかないようですが・・・・どうでしょうか。
>「国法論批判」はヘーゲルのテキストを、ほとんど逐行的に批判していきます。
相手をここまで徹底して読まなくては「批判」なんてできない。
それを知るだけでも、読む価値があります。
おっしゃるとおりですね。刺激になります。ありがとうございます。
このことについて、手元にある資料で調べましたところ
★1843
◆ヘーゲル法哲学の批判から
□『マルクス=エンゲルス全集』第一巻、真下信一訳、大月書店
「ヘーゲル法哲学の批判から」の副題がヘーゲル国法論(第261節―第313節)の批判ですね。
いま、てもとにある『マルクス=エンゲルス全集』第一巻は1959年10月20日発行とありますので、吉本は当然、これを読んでいると思われます。
また、中山元さんのマルクス著作目録では翻訳はこれしかないようですが・・・・どうでしょうか。
>「国法論批判」はヘーゲルのテキストを、ほとんど逐行的に批判していきます。
相手をここまで徹底して読まなくては「批判」なんてできない。
それを知るだけでも、読む価値があります。
おっしゃるとおりですね。刺激になります。ありがとうございます。
>>[29]
ありがとうございます。
ケンちゃんさんに調べ物を押し付けちゃったみたいで恐縮してます。
おなじヘーゲル批判でも、『経済学哲学草稿』はよく言及されますよね。
でも、この「国法論批判」はあまり注目されない。
不思議な気がします。
レーニンの『国家と革命』が言ってるのは、
「国家とは階級支配の道具である。
ある階級が、ある階級を支配するための暴力装置だ」
ということに尽きる気がします。
だけどそのくらいのことは、誰だってすぐ気づくことです。
国家の問題は、そんなとこにはないと思うのです。
レーニンが言う「支配の道具」に、多くの人が唯々諾々としたがいます。
それどころか、自発的にその犠牲になろうとする。
国家はその意味で、至高のものです。
個々の大衆や家族、市民社会の全体を超越した絶対者です。
日本でも「英霊」だなんて気味の悪いコトバが、まだプラスの意味で使われますよね。
こうした「幻想の至高物」が、国家の本質です。
これがあるからこそ、国家は階級支配の道具にもなりうる。
この幻想によって、初めて国家の振るう暴力が「正義」の衣装をまというるわけです。
この「正義」の成立を弁証法的に通覧し、肯定しようとしたのがヘーゲルでしょう。
その虚構性を衝こうとしたのが、マルクスの批判だと思います。
「現実的な理念によって国家がつくられる」というヘーゲルの弁証法。
その虚構性と論理的なトリックを、暴こうというマルクス。
マルクスのこの方法を『古事記』と、それから連綿する「日本」に対して適用する。
吉本さんが『共同幻想論』でやろうとしたのは、そういうことっだったと思います。
マルクスにとっての、市民社会とプロイセン絶対国家、そしてそれを擁護するヘーゲル哲学。
それにあたるのが、吉本さんにとっての「遠野物語」の常民の世界と「日本」国家、そしてそれを弁証する『古事記』であったろうと思うのです。
ありがとうございます。
ケンちゃんさんに調べ物を押し付けちゃったみたいで恐縮してます。
おなじヘーゲル批判でも、『経済学哲学草稿』はよく言及されますよね。
でも、この「国法論批判」はあまり注目されない。
不思議な気がします。
レーニンの『国家と革命』が言ってるのは、
「国家とは階級支配の道具である。
ある階級が、ある階級を支配するための暴力装置だ」
ということに尽きる気がします。
だけどそのくらいのことは、誰だってすぐ気づくことです。
国家の問題は、そんなとこにはないと思うのです。
レーニンが言う「支配の道具」に、多くの人が唯々諾々としたがいます。
それどころか、自発的にその犠牲になろうとする。
国家はその意味で、至高のものです。
個々の大衆や家族、市民社会の全体を超越した絶対者です。
日本でも「英霊」だなんて気味の悪いコトバが、まだプラスの意味で使われますよね。
こうした「幻想の至高物」が、国家の本質です。
これがあるからこそ、国家は階級支配の道具にもなりうる。
この幻想によって、初めて国家の振るう暴力が「正義」の衣装をまというるわけです。
この「正義」の成立を弁証法的に通覧し、肯定しようとしたのがヘーゲルでしょう。
その虚構性を衝こうとしたのが、マルクスの批判だと思います。
「現実的な理念によって国家がつくられる」というヘーゲルの弁証法。
その虚構性と論理的なトリックを、暴こうというマルクス。
マルクスのこの方法を『古事記』と、それから連綿する「日本」に対して適用する。
吉本さんが『共同幻想論』でやろうとしたのは、そういうことっだったと思います。
マルクスにとっての、市民社会とプロイセン絶対国家、そしてそれを擁護するヘーゲル哲学。
それにあたるのが、吉本さんにとっての「遠野物語」の常民の世界と「日本」国家、そしてそれを弁証する『古事記』であったろうと思うのです。
わたしたちがかんがえているよりもずっと怖ろしいこと.
メモ
・もしかしたら、この言葉はわたしの青春のなかでもっとも衝撃的だったかもしれない。
・>これは、わたしたちがかんがえているよりもずっと怖ろしいことである・・・。
いや、まてよ、ほんとうの意味をわたしはまだわかっていないのでは・・・。
引用
ここでとりあげる人物は、きっと、千年に一度しかこの世にあらわれないといった巨匠なのだが、その生涯を再現する難しさは、市井の片隅に生き死にした人物の生涯と別にかわりない。市井の片隅に生まれ、そだち、子を生み、生活し、老いて死ぬといった生涯をくりかえした無数の人物は、千年に一度しかこの世にあらわれない人物の価値とまったくおなじである。
人間が知識―それはここでとりあげる人物の云い方をかりれば人間の意識の唯一の行為である―を獲得するにつれて、その知識が歴史のなかで累積され、実現して、また記述の歴史にかえるといったことは必然の経路である。そしてこれをみとめれば、知識について関与せず生き死にした市井の無数の人物よりも、知識に関与し、記述の歴史に登場したものは価値があり、またなみはずれて関与したものは、なみはずれて価値あるものであると幻想することも、人間にとって必然であるといえる。
しかし、この種の認識はあくまでも幻想の領域に属している。幻想の領域から、現実の領域へとはせくだるとき、じつはこういった判断がなりたたないことがすぐにわかる。市井の片隅に生き死にした人物のほうが、判断の蓄積や、生涯にであったことの累積について、けっして単純でもなければ劣っているわけでもない。これは、わたしたちがかんがえているよりもずっと怖ろしいことである。
千年に一度しかあらわれない巨匠と、市井の片隅で生き死にする無数の大衆とのこの〈等しさ〉を、歴史はひとつの〈時代〉性として抽出する。
吉本隆明「マルクス伝」、『カールマルクス』光文社文庫2006.3.20
メモ
・もしかしたら、この言葉はわたしの青春のなかでもっとも衝撃的だったかもしれない。
・>これは、わたしたちがかんがえているよりもずっと怖ろしいことである・・・。
いや、まてよ、ほんとうの意味をわたしはまだわかっていないのでは・・・。
引用
ここでとりあげる人物は、きっと、千年に一度しかこの世にあらわれないといった巨匠なのだが、その生涯を再現する難しさは、市井の片隅に生き死にした人物の生涯と別にかわりない。市井の片隅に生まれ、そだち、子を生み、生活し、老いて死ぬといった生涯をくりかえした無数の人物は、千年に一度しかこの世にあらわれない人物の価値とまったくおなじである。
人間が知識―それはここでとりあげる人物の云い方をかりれば人間の意識の唯一の行為である―を獲得するにつれて、その知識が歴史のなかで累積され、実現して、また記述の歴史にかえるといったことは必然の経路である。そしてこれをみとめれば、知識について関与せず生き死にした市井の無数の人物よりも、知識に関与し、記述の歴史に登場したものは価値があり、またなみはずれて関与したものは、なみはずれて価値あるものであると幻想することも、人間にとって必然であるといえる。
しかし、この種の認識はあくまでも幻想の領域に属している。幻想の領域から、現実の領域へとはせくだるとき、じつはこういった判断がなりたたないことがすぐにわかる。市井の片隅に生き死にした人物のほうが、判断の蓄積や、生涯にであったことの累積について、けっして単純でもなければ劣っているわけでもない。これは、わたしたちがかんがえているよりもずっと怖ろしいことである。
千年に一度しかあらわれない巨匠と、市井の片隅で生き死にする無数の大衆とのこの〈等しさ〉を、歴史はひとつの〈時代〉性として抽出する。
吉本隆明「マルクス伝」、『カールマルクス』光文社文庫2006.3.20
三浦つとむ氏の仕事が吉本さんに量り知れない恩恵をもたらしたことは、吉本さん自身、繰り返し認めている。
神山派に属していた三浦氏は上部構造の自立性という考えに立って、言語論や芸術論や国家論が下部構造から相対的に切り離して論じうることを実践していた。
哲学者三浦つとむ氏が属していた神山派の神山茂夫氏は、講座派も労農派もともに経済決定論(生産力理論)であると批判して、
国家などの上部構造は下部構造から相対的に自立しているのだと主張した。
吉本さんの『言語にとって美とはなにか』や『共同幻想論』や『心的現象論』は、
吉本さんが理論的に神山氏の圏内に入ることによって初めて可能になったものである。
(参考文献 挂秀実著『吉本隆明の時代』)
神山派に属していた三浦氏は上部構造の自立性という考えに立って、言語論や芸術論や国家論が下部構造から相対的に切り離して論じうることを実践していた。
哲学者三浦つとむ氏が属していた神山派の神山茂夫氏は、講座派も労農派もともに経済決定論(生産力理論)であると批判して、
国家などの上部構造は下部構造から相対的に自立しているのだと主張した。
吉本さんの『言語にとって美とはなにか』や『共同幻想論』や『心的現象論』は、
吉本さんが理論的に神山氏の圏内に入ることによって初めて可能になったものである。
(参考文献 挂秀実著『吉本隆明の時代』)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
<吉本隆明・戦後最大の思想家> 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
<吉本隆明・戦後最大の思想家>のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 38350人
- 2位
- 暮らしを楽しむ
- 77055人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19835人