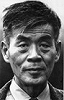NHKのテレビ番組『100de名著』の7月のテーマは吉本隆明の『共同幻想論』です。私がこの本を初めて読んだのは、多分高校生ぐらいの頃だったと思います。非常に難しい本ではありますが、著者の吉本隆明の文章の語り口に独特な魅力があり、一応最後まで読みました。
しかし、テキストを買ってパラパラと読んでみると、高校生のころには気がつかなかった視点がたくさんちりばめられているという印象です。「ああ、こういうふうに読むのか…」と気づかされることしきりで、逆に言えば、高校生のころはこの本をほとんど理解していなかったということでもあると思います。テレビの講義でどんな解説がなされるのか、とても楽しみです。
なお、今回のテレビ講義に使われる『共同幻想論』の底本テキストは、角川ソフィア文庫の「改訂新版」という版のようです。私が読んだ版は『全著作集』の中の巻です。角川ソフィア文庫版は、序文が充実しており、番組の講師の人も、この序文を大変重視しているようです。「序文の中にこの本を読み解くカギがある」とのことです。角川ソフィア文庫版も買いなおして読んでみてもいいかもしれません。
【関連項目】
NHKHP
https:/
「人間にとって国家とは何か?」「国家の起源とは?」「国家はどのようなプロセスで成立したのか?」……私たちにとって根源的ともいえる、国家を巡る問いに独力で答えを導き出そうとした著作があります。「共同幻想論」。執筆したのは、数々の評論活動を通して戦後思想に巨大な影響を与え続けてきた、日本を代表する思想家・吉本隆明(1924-2012)です。学生運動が激化していた1968年に出版されたこの著作は当時の青年たちに熱心に読まれ、「共同幻想」という言葉は国家や権力の本質を言い当てた言葉として広く流通しました。出版から50年以上を経て、再び数多くの論考によって再評価の機運が高まる今、この名著を通して「国家と個人の関係」をあらためて見つめなおします。
吉本がこの著作を書く原点となったのは、皇国少年として過ごした戦時中から終戦直後にかけての体験。戦中は「絶対的に『善なるもの』として戦争を鼓舞してきた文化人たち」が敗戦後にあっけなく意見を変えたことを若年で体験しました。それは吉本に「権威に対する不信感」を生みました。何が正しいのかという基準が崩壊し、何を信じてよいのかわからない混沌状態の中、前提を根本から考え直し、自らの思考によって価値観や国家観を組み立て直そう。そういった切実な問いが吉本にはあったといいます。「共同幻想論」はその問いに対して一つの答えを導き出そうとした著作なのです。
「国家とは何か」という問いに対して、多くの批判者は、政治的支配者が自分たちの利害を社会全体の利害と見せかける装置とみなすことで、国家を否定できると考えてきました。しかし、吉本はそれでは不十分であり、本質的・根源的でないといいます。人間は容易には国家から自由にはなれない。それは、国家が「私たちはあたかも家族が血で繋がっているように遠い先祖と血で繋がっている。だから私たちは本来一つもののだ」という共有された根深い「幻想」から成り立っているからなのです。
そこで、吉本は「遠野物語」や「古事記」を徹底的に分析することで、「共同幻想」としての国家の成立機序を解明し、私たちが国家にきちんと対峙し、自立的に生きていく方法を模索したのだと、日本思想史研究者・先崎彰容さんはいいます。「ポピュリズム」によって誕生する権力が時代を左右する現在、安易な国家批判だけでは、問題の根本的解決を導きだすことはできない。今こそ、吉本が主張したような、より本質的な国家論が必要なのであり、だからこそ「共同幻想論」を再読するべきだというのです。
番組では先崎彰容さん(日本大学教授)を指南役として招き、戦後思想の中で最も難解な著作として知られる「共同幻想論」を分り易く解説。この著作に現代の視点から光を当てなおし、そこにこめられた「国家論」や「自立して考えるとはどういうことか」といった問いなど、現代の私達にも通じるメッセージを読み解いていきます。
第1回 焼け跡から生まれた思想
【放送時間】
2020年7月6日(月)午後10時25分〜10時50分/Eテレ
【再放送】
2020年7月8日(水)午前5時30分〜5時55分/Eテレ
2020年7月8日(水)午後0時00分〜0時25分/Eテレ
※放送時間は変更される場合があります
【指南役】
先崎彰容(日本大学教授)…倫理学者・日本思想史研究者。「維新と敗戦」「バッシング論」等、著書多数。
【朗読】
柄本明(俳優)
【語り】
小口貴子
吉本を決定的に変えた戦争体験。それは「あらゆる価値観は信じるに足るものではありえない」という根源的な体験だった。昨日まで信じていたものがすべてひっくり返る混沌の中で、吉本が生みだした概念が「関係の絶対性」だ。一人でどれだけつきつめて考えぬき辿り着いた「正しさ」も間違う可能性がある。他者との関係性の中からしか「正しさ」は導き出せないのに人はそのことを忘却している……それが「関係の絶対性」だ。この概念によって、国家や宗教など何かを容易に信じ込んでしまう人間の性を吉本は浮き彫りにしていく。それが限度を超えていったとき、全体主義や国家の暴走が生じるというのだ。第一回は、吉本が著作を書く大きなきっかけとなった戦争体験の意味を紐解き、「共同幻想論」を今、なぜ読むべきかを深く考察する。
第2回 「対幻想」とはなにか
【放送時間】
2020年7月13日(月)午後10時25分〜10時50分/Eテレ
【再放送】
2020年7月15日(水)午前5時30分〜5時55分/Eテレ
2020年7月15日(水)午後0時00分〜0時25分/Eテレ
※放送時間は変更される場合があります
【指南役】
先崎彰容(日本大学教授)…倫理学者・日本思想史研究者。「維新と敗戦」「バッシング論」等、著書多数。
【朗読】
柄本明(俳優)
【語り】
小口貴子
吉本は国家の起源を考える上でまず「対幻想」という概念を生み出した。人間には、他者と関係する場合に必ず「性」として関係する根源的な在り方がある。好いたり好かれたり、嫉妬したりされたり。それは男女の関係に限らない。あの上司が嫌いだ、この研究者とはそりが合わない等々、人間の関係性には、論理以前に必ず好悪の感情がまとわりつく。吉本はこれをエロス的な関係と呼び、そこから生まれる「対幻想」が、国家のような「共同幻想」が形成されるベースに存在するという。国家が単な装置ではなく、愛する対象になったり容易に相対化できないのは、こうした機序に由来するのだ。第二回は、「対幻想」という概念はどんなものかを読み解き、国家が成立する基盤となる人間の在り様に迫っていく。
第3回 国家形成の物語
【放送時間】
2020年7月20日(月)午後10時25分〜10時50分/Eテレ
【再放送】
2020年7月22日(水)午前5時30分〜5時55分/Eテレ
2020年7月22日(水)午後0時00分〜0時25分/Eテレ
※放送時間は変更される場合があります
【指南役】
先崎彰容(日本大学教授)…倫理学者・日本思想史研究者。「維新と敗戦」「バッシング論」等、著書多数。
【朗読】
柄本明(俳優)
【語り】
小口貴子
吉本は、家族や氏族集団から国家へと形成されていく機序が「古事記」の中に子細に書き込まれているという。それを分析していくと、国家形成は「罪の自覚」「倫理の発生」「法の形成」といったプロセスを経ることがわかる。例えばスサノオの神話には、「対幻想」と「共同幻想」に引き裂かれる人間の在り様が象徴的に表現され、人間社会が「血」や「性」でつながる氏族集団から「法」を基盤とする国家へと変貌するプロセスが辿れる。そこでは「対幻想」と「共同幻想」は不可分に共存している。第三回は、国家の起源や成立プロセスを解き明かし、人間がなぜ国家という桎梏から容易に自由になれないかを明らかにする。
第4回 「個人幻想」とはなにか
【放送時間】
2020年7月27日(月)午後10時25分〜10時50分/Eテレ
【再放送】
2020年7月29日(水)午前5時30分〜5時55分/Eテレ
2020年7月29日(水)午後0時00分〜0時25分/Eテレ
※放送時間は変更される場合があります
【指南役】
先崎彰容(日本大学教授)…倫理学者・日本思想史研究者。「維新と敗戦」「バッシング論」等、著書多数。
【朗読】
柄本明(俳優)
【語り】
小口貴子
吉本は、国家の成立機序を解明した上でその国家をどう相対化し個人がどう自立できるかを問う。その際の鍵概念が「沈黙の有意味性」だ。吉本にとって「沈黙」とは国家を沈黙をもって凝視するということが含意される。声高に国家を批判することでは何も変わらない。庶民たちが日常に根をはりながら沈黙をもって問い始める「違和感」や「亀裂」。そうした日々の生活感に寄り添いながら思考を紡いでいくことにこそ人が自立して思考する拠点があるという。第四回は、私たちが国家を相対化し対峙する視座を持ちうるかや、真に自立して思考するとはどういうことかを、問い直していく。
しかし、テキストを買ってパラパラと読んでみると、高校生のころには気がつかなかった視点がたくさんちりばめられているという印象です。「ああ、こういうふうに読むのか…」と気づかされることしきりで、逆に言えば、高校生のころはこの本をほとんど理解していなかったということでもあると思います。テレビの講義でどんな解説がなされるのか、とても楽しみです。
なお、今回のテレビ講義に使われる『共同幻想論』の底本テキストは、角川ソフィア文庫の「改訂新版」という版のようです。私が読んだ版は『全著作集』の中の巻です。角川ソフィア文庫版は、序文が充実しており、番組の講師の人も、この序文を大変重視しているようです。「序文の中にこの本を読み解くカギがある」とのことです。角川ソフィア文庫版も買いなおして読んでみてもいいかもしれません。
【関連項目】
NHKHP
https:/
「人間にとって国家とは何か?」「国家の起源とは?」「国家はどのようなプロセスで成立したのか?」……私たちにとって根源的ともいえる、国家を巡る問いに独力で答えを導き出そうとした著作があります。「共同幻想論」。執筆したのは、数々の評論活動を通して戦後思想に巨大な影響を与え続けてきた、日本を代表する思想家・吉本隆明(1924-2012)です。学生運動が激化していた1968年に出版されたこの著作は当時の青年たちに熱心に読まれ、「共同幻想」という言葉は国家や権力の本質を言い当てた言葉として広く流通しました。出版から50年以上を経て、再び数多くの論考によって再評価の機運が高まる今、この名著を通して「国家と個人の関係」をあらためて見つめなおします。
吉本がこの著作を書く原点となったのは、皇国少年として過ごした戦時中から終戦直後にかけての体験。戦中は「絶対的に『善なるもの』として戦争を鼓舞してきた文化人たち」が敗戦後にあっけなく意見を変えたことを若年で体験しました。それは吉本に「権威に対する不信感」を生みました。何が正しいのかという基準が崩壊し、何を信じてよいのかわからない混沌状態の中、前提を根本から考え直し、自らの思考によって価値観や国家観を組み立て直そう。そういった切実な問いが吉本にはあったといいます。「共同幻想論」はその問いに対して一つの答えを導き出そうとした著作なのです。
「国家とは何か」という問いに対して、多くの批判者は、政治的支配者が自分たちの利害を社会全体の利害と見せかける装置とみなすことで、国家を否定できると考えてきました。しかし、吉本はそれでは不十分であり、本質的・根源的でないといいます。人間は容易には国家から自由にはなれない。それは、国家が「私たちはあたかも家族が血で繋がっているように遠い先祖と血で繋がっている。だから私たちは本来一つもののだ」という共有された根深い「幻想」から成り立っているからなのです。
そこで、吉本は「遠野物語」や「古事記」を徹底的に分析することで、「共同幻想」としての国家の成立機序を解明し、私たちが国家にきちんと対峙し、自立的に生きていく方法を模索したのだと、日本思想史研究者・先崎彰容さんはいいます。「ポピュリズム」によって誕生する権力が時代を左右する現在、安易な国家批判だけでは、問題の根本的解決を導きだすことはできない。今こそ、吉本が主張したような、より本質的な国家論が必要なのであり、だからこそ「共同幻想論」を再読するべきだというのです。
番組では先崎彰容さん(日本大学教授)を指南役として招き、戦後思想の中で最も難解な著作として知られる「共同幻想論」を分り易く解説。この著作に現代の視点から光を当てなおし、そこにこめられた「国家論」や「自立して考えるとはどういうことか」といった問いなど、現代の私達にも通じるメッセージを読み解いていきます。
第1回 焼け跡から生まれた思想
【放送時間】
2020年7月6日(月)午後10時25分〜10時50分/Eテレ
【再放送】
2020年7月8日(水)午前5時30分〜5時55分/Eテレ
2020年7月8日(水)午後0時00分〜0時25分/Eテレ
※放送時間は変更される場合があります
【指南役】
先崎彰容(日本大学教授)…倫理学者・日本思想史研究者。「維新と敗戦」「バッシング論」等、著書多数。
【朗読】
柄本明(俳優)
【語り】
小口貴子
吉本を決定的に変えた戦争体験。それは「あらゆる価値観は信じるに足るものではありえない」という根源的な体験だった。昨日まで信じていたものがすべてひっくり返る混沌の中で、吉本が生みだした概念が「関係の絶対性」だ。一人でどれだけつきつめて考えぬき辿り着いた「正しさ」も間違う可能性がある。他者との関係性の中からしか「正しさ」は導き出せないのに人はそのことを忘却している……それが「関係の絶対性」だ。この概念によって、国家や宗教など何かを容易に信じ込んでしまう人間の性を吉本は浮き彫りにしていく。それが限度を超えていったとき、全体主義や国家の暴走が生じるというのだ。第一回は、吉本が著作を書く大きなきっかけとなった戦争体験の意味を紐解き、「共同幻想論」を今、なぜ読むべきかを深く考察する。
第2回 「対幻想」とはなにか
【放送時間】
2020年7月13日(月)午後10時25分〜10時50分/Eテレ
【再放送】
2020年7月15日(水)午前5時30分〜5時55分/Eテレ
2020年7月15日(水)午後0時00分〜0時25分/Eテレ
※放送時間は変更される場合があります
【指南役】
先崎彰容(日本大学教授)…倫理学者・日本思想史研究者。「維新と敗戦」「バッシング論」等、著書多数。
【朗読】
柄本明(俳優)
【語り】
小口貴子
吉本は国家の起源を考える上でまず「対幻想」という概念を生み出した。人間には、他者と関係する場合に必ず「性」として関係する根源的な在り方がある。好いたり好かれたり、嫉妬したりされたり。それは男女の関係に限らない。あの上司が嫌いだ、この研究者とはそりが合わない等々、人間の関係性には、論理以前に必ず好悪の感情がまとわりつく。吉本はこれをエロス的な関係と呼び、そこから生まれる「対幻想」が、国家のような「共同幻想」が形成されるベースに存在するという。国家が単な装置ではなく、愛する対象になったり容易に相対化できないのは、こうした機序に由来するのだ。第二回は、「対幻想」という概念はどんなものかを読み解き、国家が成立する基盤となる人間の在り様に迫っていく。
第3回 国家形成の物語
【放送時間】
2020年7月20日(月)午後10時25分〜10時50分/Eテレ
【再放送】
2020年7月22日(水)午前5時30分〜5時55分/Eテレ
2020年7月22日(水)午後0時00分〜0時25分/Eテレ
※放送時間は変更される場合があります
【指南役】
先崎彰容(日本大学教授)…倫理学者・日本思想史研究者。「維新と敗戦」「バッシング論」等、著書多数。
【朗読】
柄本明(俳優)
【語り】
小口貴子
吉本は、家族や氏族集団から国家へと形成されていく機序が「古事記」の中に子細に書き込まれているという。それを分析していくと、国家形成は「罪の自覚」「倫理の発生」「法の形成」といったプロセスを経ることがわかる。例えばスサノオの神話には、「対幻想」と「共同幻想」に引き裂かれる人間の在り様が象徴的に表現され、人間社会が「血」や「性」でつながる氏族集団から「法」を基盤とする国家へと変貌するプロセスが辿れる。そこでは「対幻想」と「共同幻想」は不可分に共存している。第三回は、国家の起源や成立プロセスを解き明かし、人間がなぜ国家という桎梏から容易に自由になれないかを明らかにする。
第4回 「個人幻想」とはなにか
【放送時間】
2020年7月27日(月)午後10時25分〜10時50分/Eテレ
【再放送】
2020年7月29日(水)午前5時30分〜5時55分/Eテレ
2020年7月29日(水)午後0時00分〜0時25分/Eテレ
※放送時間は変更される場合があります
【指南役】
先崎彰容(日本大学教授)…倫理学者・日本思想史研究者。「維新と敗戦」「バッシング論」等、著書多数。
【朗読】
柄本明(俳優)
【語り】
小口貴子
吉本は、国家の成立機序を解明した上でその国家をどう相対化し個人がどう自立できるかを問う。その際の鍵概念が「沈黙の有意味性」だ。吉本にとって「沈黙」とは国家を沈黙をもって凝視するということが含意される。声高に国家を批判することでは何も変わらない。庶民たちが日常に根をはりながら沈黙をもって問い始める「違和感」や「亀裂」。そうした日々の生活感に寄り添いながら思考を紡いでいくことにこそ人が自立して思考する拠点があるという。第四回は、私たちが国家を相対化し対峙する視座を持ちうるかや、真に自立して思考するとはどういうことかを、問い直していく。
|
|
|
|
|
|
|
|
<吉本隆明・戦後最大の思想家> 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
<吉本隆明・戦後最大の思想家>のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90013人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208278人
- 3位
- 暮らしを楽しむ
- 75464人