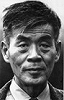明確に『吉本隆明論』という書名はないけれど、そのなかに吉本論が入っている書籍などご存じの方はぜひ教えてください。
いつもすみません、よろしくお願いいたします。
(例)
*直接吉本論と書名がないが、実質的に吉本論であるもの
竹田青嗣『世界という背理ー小林秀雄と吉本隆明』河出書房新社1988.1.20
*吉本論が目次のなかしかに入っていないもの
三浦雅士『批評という鬱』〜「批評という鬱−吉本隆明ノート」岩波書店2001.9
井口時男『批評の誕生/批評の死』〜「吉本隆明-失語者の思想」 講談社2001.5.
笠井潔 『外部の思考・思考の外部』〜「エロスそして超越ー吉本隆明」作品社1988.6
*アンソロジー系
疋田雅昭『戦後史のポエティクス1935-1959』「吉本隆明―思索と詩作の間で」
和田博文編世界思想社2009.4
いつもすみません、よろしくお願いいたします。
(例)
*直接吉本論と書名がないが、実質的に吉本論であるもの
竹田青嗣『世界という背理ー小林秀雄と吉本隆明』河出書房新社1988.1.20
*吉本論が目次のなかしかに入っていないもの
三浦雅士『批評という鬱』〜「批評という鬱−吉本隆明ノート」岩波書店2001.9
井口時男『批評の誕生/批評の死』〜「吉本隆明-失語者の思想」 講談社2001.5.
笠井潔 『外部の思考・思考の外部』〜「エロスそして超越ー吉本隆明」作品社1988.6
*アンソロジー系
疋田雅昭『戦後史のポエティクス1935-1959』「吉本隆明―思索と詩作の間で」
和田博文編世界思想社2009.4
|
|
|
|
コメント(83)
加藤典洋「誤り」「遅れ」から戦後思想築く・吉本さんの死に際して」『毎日新聞(夕刊))2012.3.19
吉本隆明。この人がいなければ、戦後思想がいまある明瞭な姿を取ることはなかったはずだ。その一つの特徴は「誤り」を、「正しさ」よりも深い経験だと見たことである。戦後、誰もが戦前の誤りを反省し、「正しく」軍部に抵抗した人を手本にしようとしたとき、二十代の吉本さんは、戦時中に愛読した高村光太郎という「誤った人」から眼を離さず、この深い経験をもった知識人がそれでもなぜ「誤った」のかについて考えた。誰もが沈む船から去る鼠たちのように「誤った人」を離れ、「正しかった人」に移ったとき、沈む船を動かず、そこを出発点にした。
(メモ)倖か不幸か深入りせずに引返したが、ぼくの敗戦体験はマルクス主義(吉本はロシアマルクス主義とかソフトスターリン主義といっていたが)党派体験だ、そして、その裏返しとしてのこちらは人生の大半を使ったが公務員体験といってもよい、その誤りから考えるということだ。それは、気づいたときからやればいい。
吉本隆明。この人がいなければ、戦後思想がいまある明瞭な姿を取ることはなかったはずだ。その一つの特徴は「誤り」を、「正しさ」よりも深い経験だと見たことである。戦後、誰もが戦前の誤りを反省し、「正しく」軍部に抵抗した人を手本にしようとしたとき、二十代の吉本さんは、戦時中に愛読した高村光太郎という「誤った人」から眼を離さず、この深い経験をもった知識人がそれでもなぜ「誤った」のかについて考えた。誰もが沈む船から去る鼠たちのように「誤った人」を離れ、「正しかった人」に移ったとき、沈む船を動かず、そこを出発点にした。
(メモ)倖か不幸か深入りせずに引返したが、ぼくの敗戦体験はマルクス主義(吉本はロシアマルクス主義とかソフトスターリン主義といっていたが)党派体験だ、そして、その裏返しとしてのこちらは人生の大半を使ったが公務員体験といってもよい、その誤りから考えるということだ。それは、気づいたときからやればいい。
吉本隆明『マスイメージ論』講談社学芸文庫(新刊)2013.3.16
大ざっぱな言葉でくくってしまうと、『マス・イメージ論』において吉本が引用した個々の作品の断片は、そのことごとくが「全体的な暗喩」として、『現在』という共同幻想のありようを示唆しているということになるのである。いいかえると、「現代」という共同幻想は、そうした「全体的な暗喩」を「介して」、それを「迂回路」として用いることで、「現代」にアクセスを試みることである。p330鹿島茂「解説」
メモ)
『マスイメージ論』が鹿島の解説がついて再刊された。鹿島は吉本がまったく評価することのなかったヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』と相似していると述べる。「個人にとって外的であるようなかなり多くのものが、集団にとっては内的なものである」と。
しかし、依然としてこの論を読み解くことはむづかしい。
大ざっぱな言葉でくくってしまうと、『マス・イメージ論』において吉本が引用した個々の作品の断片は、そのことごとくが「全体的な暗喩」として、『現在』という共同幻想のありようを示唆しているということになるのである。いいかえると、「現代」という共同幻想は、そうした「全体的な暗喩」を「介して」、それを「迂回路」として用いることで、「現代」にアクセスを試みることである。p330鹿島茂「解説」
メモ)
『マスイメージ論』が鹿島の解説がついて再刊された。鹿島は吉本がまったく評価することのなかったヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』と相似していると述べる。「個人にとって外的であるようなかなり多くのものが、集団にとっては内的なものである」と。
しかし、依然としてこの論を読み解くことはむづかしい。
吉本隆明『マスイメージ論』講談社学芸文庫(新刊)2013.3.16
しかしそれにしても、いや、それにしても、一九八〇年代初頭に、この必敗の戦いに、それまでのすべてを捨てて踏み切ろうとした吉本隆明はやはり偉大なる思想的ファイターであったというほかはないのである。
なぜならば、二十一世紀もすでに十三年を経過し、いよいよ、世紀をまたぐ三十年という決定的な過渡期が終わろうとしている今日においてさえ、「現代」という共同幻想の実態は依然として見えてきてはいないからである。p331p332鹿島茂「解説」
メモ
『パサージュ論』で述べているように、世紀をまたぐ三十年という過渡期がおわろうとしている、それはいまこそが「目覚め」の瞬間であり、現代を捉えるときであろうと鹿島はいう。刊行からほぼ三十年を経た今日、若い世代によって「現代」からの目覚めの契機として読まれることを切に願ってやまない、と。
しかしそれにしても、いや、それにしても、一九八〇年代初頭に、この必敗の戦いに、それまでのすべてを捨てて踏み切ろうとした吉本隆明はやはり偉大なる思想的ファイターであったというほかはないのである。
なぜならば、二十一世紀もすでに十三年を経過し、いよいよ、世紀をまたぐ三十年という決定的な過渡期が終わろうとしている今日においてさえ、「現代」という共同幻想の実態は依然として見えてきてはいないからである。p331p332鹿島茂「解説」
メモ
『パサージュ論』で述べているように、世紀をまたぐ三十年という過渡期がおわろうとしている、それはいまこそが「目覚め」の瞬間であり、現代を捉えるときであろうと鹿島はいう。刊行からほぼ三十年を経た今日、若い世代によって「現代」からの目覚めの契機として読まれることを切に願ってやまない、と。
『群像2012年5月号』講談社2012.5.1
「正しさ」の絶対喪失に直面する場面で、どこかに「正しい」思想があるはずだという強迫観念から、日本の知識人はまだ脱却できていないのだ。吉本は、そういう場面で、この喪失体験自体を思想化する以外には、決して普遍的な思想を作り出すことができないことを示した稀有の思想家だった。(略)しかし、その本質的な継承は、まだどこにも現れていないかも知れない。竹田青嗣「正しさから見放される体験」
(メモ)
竹田は加藤のいう、吉本の方法の特質は、思想は必ず「誤りうる」(可謬性)と言う場所から出発して普遍的なものへ届きうる可能性の条件を見いだした。ということについて、これが西洋近代哲学が普遍的認識の問題について長く格闘してきたプロセスのエッセンスなのだ、哲学からみてもこれは極めて妥当という。
「正しさ」の絶対喪失に直面する場面で、どこかに「正しい」思想があるはずだという強迫観念から、日本の知識人はまだ脱却できていないのだ。吉本は、そういう場面で、この喪失体験自体を思想化する以外には、決して普遍的な思想を作り出すことができないことを示した稀有の思想家だった。(略)しかし、その本質的な継承は、まだどこにも現れていないかも知れない。竹田青嗣「正しさから見放される体験」
(メモ)
竹田は加藤のいう、吉本の方法の特質は、思想は必ず「誤りうる」(可謬性)と言う場所から出発して普遍的なものへ届きうる可能性の条件を見いだした。ということについて、これが西洋近代哲学が普遍的認識の問題について長く格闘してきたプロセスのエッセンスなのだ、哲学からみてもこれは極めて妥当という。
三浦雅士「鮎川信夫のレンズ」『吉本隆明代表詩選』あとがき思潮社2004.4.25
だが、『日時計編』は乗り越えられない。『固有時との対話』も『転位のための十編』も乗り越えられるだろう。だが、『日時計編』は乗り越えられない。なぜならばそれは決意でも宣言でもないからである。ひとつの時代の、痛む様に染み入る感性の記録、すなわち詩そのものだからである。三浦雅士「鮎川信夫のレンズ」p237『吉本隆明代表詩選』思潮社2004.4.25
メモ:
三浦は、ここで「吉本さんは一九五〇年にまさに言葉の肉体に触ったということだと思います」「きわめて強烈な恋愛体験と、その結果の婚約をまるでキルケゴールのように破棄してしまったという重要な事件があった。」「一九五〇年の段階でそれがぜんぶ一緒に来てしまったというのが「日時計編」からは滲み出てきている。」と述べている。
だが、『日時計編』は乗り越えられない。『固有時との対話』も『転位のための十編』も乗り越えられるだろう。だが、『日時計編』は乗り越えられない。なぜならばそれは決意でも宣言でもないからである。ひとつの時代の、痛む様に染み入る感性の記録、すなわち詩そのものだからである。三浦雅士「鮎川信夫のレンズ」p237『吉本隆明代表詩選』思潮社2004.4.25
メモ:
三浦は、ここで「吉本さんは一九五〇年にまさに言葉の肉体に触ったということだと思います」「きわめて強烈な恋愛体験と、その結果の婚約をまるでキルケゴールのように破棄してしまったという重要な事件があった。」「一九五〇年の段階でそれがぜんぶ一緒に来てしまったというのが「日時計編」からは滲み出てきている。」と述べている。
見田宗助VS加藤典洋「吉本隆明を未来へつなぐ」2012.4.26対談『中央公論特別編集吉本隆明の世界』中央公論新社2012.6.25
見田:僕にとって吉本さんの魅力の核は、あの人の文体なのです。吉本さんの文章はとてもゴツゴツと節くれだっていて、深みや澱みを作りながら決して流暢に流れていかない。その文章が、僕には何より信頼できるものなんです。そうなるのは吉本さんの内部に矛盾があるためだと思います。「矛盾」というのは僕にとって褒め言葉で、シェイクスピアでも、ゲーテでもマックス・ウェーバーでも巨大な思想家の仕事には必ず矛盾がはらまれています。
メモ:自分の中にある処理に窮する大きな情念を、明哲で強靭な論理で押さえつけるような文体がどこから来るのか。この問題を解かなければ自分は生きていられないのだというような、切実な問題に真正面から取り組んでいる葛藤や拮抗から、それは立ち現れている。内容以上に、その文体が僕には信頼の理由だった。と見田はいう。
見田:僕にとって吉本さんの魅力の核は、あの人の文体なのです。吉本さんの文章はとてもゴツゴツと節くれだっていて、深みや澱みを作りながら決して流暢に流れていかない。その文章が、僕には何より信頼できるものなんです。そうなるのは吉本さんの内部に矛盾があるためだと思います。「矛盾」というのは僕にとって褒め言葉で、シェイクスピアでも、ゲーテでもマックス・ウェーバーでも巨大な思想家の仕事には必ず矛盾がはらまれています。
メモ:自分の中にある処理に窮する大きな情念を、明哲で強靭な論理で押さえつけるような文体がどこから来るのか。この問題を解かなければ自分は生きていられないのだというような、切実な問題に真正面から取り組んでいる葛藤や拮抗から、それは立ち現れている。内容以上に、その文体が僕には信頼の理由だった。と見田はいう。
磯田光一「吉本隆明論」『戦後批評家論』河出書房新社1969.9.10
「告白」は「告白」なるがゆえに真であると信じている者は、そう信じている度合いだけ、かえって真実から遠ざかる。そして逆に、「告白」がついに「体験」を覆うにたりないことを知っている者だけが、「告白」聖化のナルシシズムに足をすくわれることから免れるのである。戦中派」と呼ばれる人々のなかで、吉本隆明の存在がひときわ目立っているとすれば、それはおそらく、彼が「告白」につきまとう陥穽について、他のだれよりも凝視を怠らなかったという一点にかかっている。磯田光一「吉本隆明論」『戦後批評家論』河出書房新社1969.9.10
「告白」は「告白」なるがゆえに真であると信じている者は、そう信じている度合いだけ、かえって真実から遠ざかる。そして逆に、「告白」がついに「体験」を覆うにたりないことを知っている者だけが、「告白」聖化のナルシシズムに足をすくわれることから免れるのである。戦中派」と呼ばれる人々のなかで、吉本隆明の存在がひときわ目立っているとすれば、それはおそらく、彼が「告白」につきまとう陥穽について、他のだれよりも凝視を怠らなかったという一点にかかっている。磯田光一「吉本隆明論」『戦後批評家論』河出書房新社1969.9.10
◆北川透連載評論第一回 「吉本隆明の詩と思想」
北川透編集・制作 ひとり雑誌『「KYO(峡)」創刊号』
序章 最後の根本的問題 吉本隆明の死とその後
あとがき
「KYO(峡)」創刊にあたり、必要なことを書きます。まず、これは北川透が執筆
し、みずから編集・発行する季刊の詩と批評の雑誌です。
発行月は9月、12月、3月、6月。
直接購読を基本とします。
一冊の売価は送料含んで400円。予約購読される方は、5冊分2000円ご送金
下さい。もし、終刊することがあれば、その号より先の予約金は、必ず、返金します。
二〇一三年九月一日発行 編集・発行者 北川透
〒七五二―〇九九七
下関市前田町一―一五―三三
前田コーポラス四〇四
DTP 加藤邦彦
印 刷 東京カラー印刷
価 格 四〇〇円(送料込)
◆お願い:畏友、菅谷規矩雄、松下昇からの書信やそれに類するものを、連載で掲載したいので直接購読を願いたい。
引用
直接購読者が100名に近づけば、かつて思想的にも交流の深かった、畏友、菅谷
規矩雄、松下昇からの書信やそれに類するものを、連載で掲載できます。そのために
は、発行費の基盤が安定することが不可欠です。資料の整理と、著作権などの困難の
解決のために、少し時間もかかります。これはわたしの以前からの宿題ですし、少し
でも余力がある内に実現したい、と考えています。
北川透編集・制作 ひとり雑誌『「KYO(峡)」創刊号』
序章 最後の根本的問題 吉本隆明の死とその後
あとがき
「KYO(峡)」創刊にあたり、必要なことを書きます。まず、これは北川透が執筆
し、みずから編集・発行する季刊の詩と批評の雑誌です。
発行月は9月、12月、3月、6月。
直接購読を基本とします。
一冊の売価は送料含んで400円。予約購読される方は、5冊分2000円ご送金
下さい。もし、終刊することがあれば、その号より先の予約金は、必ず、返金します。
二〇一三年九月一日発行 編集・発行者 北川透
〒七五二―〇九九七
下関市前田町一―一五―三三
前田コーポラス四〇四
DTP 加藤邦彦
印 刷 東京カラー印刷
価 格 四〇〇円(送料込)
◆お願い:畏友、菅谷規矩雄、松下昇からの書信やそれに類するものを、連載で掲載したいので直接購読を願いたい。
引用
直接購読者が100名に近づけば、かつて思想的にも交流の深かった、畏友、菅谷
規矩雄、松下昇からの書信やそれに類するものを、連載で掲載できます。そのために
は、発行費の基盤が安定することが不可欠です。資料の整理と、著作権などの困難の
解決のために、少し時間もかかります。これはわたしの以前からの宿題ですし、少し
でも余力がある内に実現したい、と考えています。
加藤典洋『人類が永遠に続くのではないとしたら』新潮社
無機物が生命をもつ。すると、なんだか変だな、と生命体は感じる。この生きていることへの違和感が、人間のタナトス欲動―「死への欲動」―の根源だとフロイトはいうのだが、ここで吉本〔隆明〕は、フロイトのようには考え進めない。…フロイトは、人間から発想し、人間に帰る。そこから人の名づけようのない無意識の動きが「死への欲動」として取り出されもするのだが、吉本は、その考えは「古い」のではないかと、と考えている。そして、いわばアメーバの場所にとどまり、そこで、この名づけられない動き、力を、「生きていることへの違和感」として生命種に普遍の心的現象の根源と考えようとする。それが、吉本のいう、生あるものが生きているゆえにもつ、「原生的疎外」という概念である。
無機物が生命をもつ。すると、なんだか変だな、と生命体は感じる。この生きていることへの違和感が、人間のタナトス欲動―「死への欲動」―の根源だとフロイトはいうのだが、ここで吉本〔隆明〕は、フロイトのようには考え進めない。…フロイトは、人間から発想し、人間に帰る。そこから人の名づけようのない無意識の動きが「死への欲動」として取り出されもするのだが、吉本は、その考えは「古い」のではないかと、と考えている。そして、いわばアメーバの場所にとどまり、そこで、この名づけられない動き、力を、「生きていることへの違和感」として生命種に普遍の心的現象の根源と考えようとする。それが、吉本のいう、生あるものが生きているゆえにもつ、「原生的疎外」という概念である。
内田樹『街場の文体論』ミシマ社 2012年
翻訳されるものと、されないものの違いはどこにあるのか。どう考えてみても、作物のクオリティとは関係がない。なんでこんなに優れたものが訳されていないのかと思うものがいくつもあります。たとえば、吉本隆明。
吉本隆明の思想は世界性を獲得できなかった。本質的には世界的な思想だったのだけれど、世界各国の地域性がそれを受け入れるだけの成熟に達していなかった。そういうかたちで「翻訳されない」ということもあるんです。丸山眞男は翻訳されるが、吉本隆明は訳されないのは、吉本のほうが「ローカル」だからではなく、吉本が「あらゆる国の人々が目を背けようとしている事象」を扱っているからなのだと僕は思います。
翻訳されるものと、されないものの違いはどこにあるのか。どう考えてみても、作物のクオリティとは関係がない。なんでこんなに優れたものが訳されていないのかと思うものがいくつもあります。たとえば、吉本隆明。
吉本隆明の思想は世界性を獲得できなかった。本質的には世界的な思想だったのだけれど、世界各国の地域性がそれを受け入れるだけの成熟に達していなかった。そういうかたちで「翻訳されない」ということもあるんです。丸山眞男は翻訳されるが、吉本隆明は訳されないのは、吉本のほうが「ローカル」だからではなく、吉本が「あらゆる国の人々が目を背けようとしている事象」を扱っているからなのだと僕は思います。
「日本語・言語を考える本質軸」末尾「☆山本自註ノート」:吉本隆明×山本哲士『思想を読む 世界を読む』 所収
吉本さんの思想的裁定は、実に肝心なところをおさえきっている、そこを「意味された」答えとしてみていくとこちらが見誤るにすぎない。何を「意味するもの」において吉本さんは考えているのかは、いかなる学者・研究者たちからも学びえないものとして正鵠な指標をだしている。「意味されたこと」だけを追っている大学人の言説からは、絶対的に語られえないことが開削されているのである。
主語制言語の概念空間と述語制言語の概念空間の差異は、近代社会国家言語の歴史編制のなかで前者優位になされていくのだが、述語制言語に言語の原初を観ていく視座を見落とすと、言語論が浮き足立つ。自然言語・内臓語と後に吉本さんが言う意味するものは、述語表出にかかってこよう。
吉本さんの思想的裁定は、実に肝心なところをおさえきっている、そこを「意味された」答えとしてみていくとこちらが見誤るにすぎない。何を「意味するもの」において吉本さんは考えているのかは、いかなる学者・研究者たちからも学びえないものとして正鵠な指標をだしている。「意味されたこと」だけを追っている大学人の言説からは、絶対的に語られえないことが開削されているのである。
主語制言語の概念空間と述語制言語の概念空間の差異は、近代社会国家言語の歴史編制のなかで前者優位になされていくのだが、述語制言語に言語の原初を観ていく視座を見落とすと、言語論が浮き足立つ。自然言語・内臓語と後に吉本さんが言う意味するものは、述語表出にかかってこよう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
<吉本隆明・戦後最大の思想家> 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
<吉本隆明・戦後最大の思想家>のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90012人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208278人
- 3位
- 暮らしを楽しむ
- 75464人