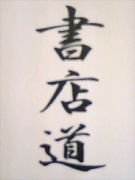総論)
先日、後輩社員くん何人かに近況を尋ねてみたところ
「売上が悪くって・・・。」などと言う。
「じゃあ、どうしたら売上が上がると思う?」
って聞いたら答えられない・・・
実際の所、彼らは
単に日々の業務をこなしているだけで、
どうしたら売上をあげられるのか、
真剣に考えて取り組んでいないで
結果だけ見て落ち込んでいる、
それだけの事なのです。
まるで昔の自分を見ているようです。
では、どうしたら売上をあげられるのか?
むろん、
こうしたら間違いなく売上がUPする、なんて答えはありませんが、
これをしてたら売上落ちてもしかたないよ〜、くらいの事は
いくつかありますよね。
私SUNは、今の店舗を任されたのが昨年の4/11〜なので
もうじき丸1年が経とうとしています。
幸い、売上の方は8月あたりから持ち直し
この数ヶ月は前年実績をクリアしていますが
単に前年が悪すぎただけのコトと思っており、
この4月以降は、1年前の自分との戦いになるので
なんとか継続して売上UPを達成するために
今一度、作戦を練っている次第です・・・
ここでは、相方社員のKくんに話をした
売上UPについてのあれこれを
まずは書いてみます。
本当は各部門ごとに
具体的な手段・方法を伴ったお店の現場でのお話をしたいのですが、
それはまた後日・・・。
?「売上」とは?
書店で言う所の「売上」とは
当たり前ですが
お客様にお買い上げ頂いた商品の
「単価×数量」の合計
ですよね。
一日あたりの店舗の売上、月間・年間の店舗の売上、
各部門毎の売上等々・・・
どれも切り口が違うだけで
「単価×数量」の集合体ですね。
?「売上が上がる」とは?
一口に「売上が上がる」「売上を上げたい」
と言ってしまいがちですが、
実際、どうなったら売上が上がるのか?
まずはこれを知っていなければ・・。
A)お買い上げ単価のUP
来店客数もお買い上げ点数も同じだが、単価の高い商品が
売れる結果として売上が上がる場合。
B)お買い上げ点数のUP
来店客数も売単価も同じだが、1人あたりのお買い上げ点数が
増えることにより売上が上がる場合。
C)来店客数増に伴う販売数量UP
1人あたりのお買い上げ点数も単価も同じだが、
来店客数増に伴う販売数量UPの結果として売上が上がる場合。
D)上記3つの複合パターン
簡単に言うと以上の4パターンあると思います。
売上を上げるために、
客単価を上げたいのか、販売数を増やしたいのか、
来店客数を増やしたいのか・・・・。
売上UPに取り組むには
まずは現状を数値で正しく認識した上で
問題点を発見し
具体的な改善方法を立てる必要があるのではっ・・?
?改善に取り組む前に・・・
あれこれ考える前に、まず確認したいのが商品の状態。
たとえ話題の本や人気のある本であっても、
すばらしい内容の良書でも、
担当者個人がお気に入りのお薦め本であっても、
肝心の商品が、やけていたりカバーが破れていては
とても売り物にはなりません。
新刊書店である以上、
古本チェーンより汚い商品を並べているようでは・・・。
まずは、きれいな本が「ある」ということ!
次に、商品の中身。
お客様が興味・関心を持って手にとって下さるモノ
=売れそうなモノ
が、並んでいるか?
いくら状態の良い商品でも、売れ残りみたいな本ばかり
売り場に飾っていては、意味がありません。
常備品の入れ替えをしていていつも思うのですが
例えば100冊あるうちで何回も回転している商品はホント数点で、
ほとんどの商品は1年間、売れることなく棚に飾られていた、
単に「常備品だから」という理由で・・。
また、自店の客層・ニーズに合った商品構成・アイテム選別も重要です。
喩えは悪いですが、魚のいない釣り堀で、
どんなに頑張って良いエサ付けて釣り糸たらしていても、
釣れっこないですよね。
売れそうな本が「ある」ということ!
言い換えれば、売れない商品を売り場から取り除く、ということ!
次に、定番商品などの欠本。
いくらこまめに補充発注をしていても、実際に入荷するかどうかは
取次や版元の在庫状況次第ですから、
往々にして、売り場の商品は売れ残りみたいなモノが
場所を占めているなんて事がよく見受けられます。
また、巻数物の欠本も要注意です。
見えないチャンスロスを生み出しているかも・・。
必要な本が常に「ある」ということ!
続く・・・・。
*各書店員の皆様の
「売上を上げるために、こんなコトをしている。」
「こんなコトを考えている。」などのお声や、
「○○の売上を上げたいんだけど・・」
「この商品をもっと売りたいんだけど・・」みたいなお悩みを
募集致しております。
ぜひぜひ、みんなで考えませんか!
先日、後輩社員くん何人かに近況を尋ねてみたところ
「売上が悪くって・・・。」などと言う。
「じゃあ、どうしたら売上が上がると思う?」
って聞いたら答えられない・・・
実際の所、彼らは
単に日々の業務をこなしているだけで、
どうしたら売上をあげられるのか、
真剣に考えて取り組んでいないで
結果だけ見て落ち込んでいる、
それだけの事なのです。
まるで昔の自分を見ているようです。
では、どうしたら売上をあげられるのか?
むろん、
こうしたら間違いなく売上がUPする、なんて答えはありませんが、
これをしてたら売上落ちてもしかたないよ〜、くらいの事は
いくつかありますよね。
私SUNは、今の店舗を任されたのが昨年の4/11〜なので
もうじき丸1年が経とうとしています。
幸い、売上の方は8月あたりから持ち直し
この数ヶ月は前年実績をクリアしていますが
単に前年が悪すぎただけのコトと思っており、
この4月以降は、1年前の自分との戦いになるので
なんとか継続して売上UPを達成するために
今一度、作戦を練っている次第です・・・
ここでは、相方社員のKくんに話をした
売上UPについてのあれこれを
まずは書いてみます。
本当は各部門ごとに
具体的な手段・方法を伴ったお店の現場でのお話をしたいのですが、
それはまた後日・・・。
?「売上」とは?
書店で言う所の「売上」とは
当たり前ですが
お客様にお買い上げ頂いた商品の
「単価×数量」の合計
ですよね。
一日あたりの店舗の売上、月間・年間の店舗の売上、
各部門毎の売上等々・・・
どれも切り口が違うだけで
「単価×数量」の集合体ですね。
?「売上が上がる」とは?
一口に「売上が上がる」「売上を上げたい」
と言ってしまいがちですが、
実際、どうなったら売上が上がるのか?
まずはこれを知っていなければ・・。
A)お買い上げ単価のUP
来店客数もお買い上げ点数も同じだが、単価の高い商品が
売れる結果として売上が上がる場合。
B)お買い上げ点数のUP
来店客数も売単価も同じだが、1人あたりのお買い上げ点数が
増えることにより売上が上がる場合。
C)来店客数増に伴う販売数量UP
1人あたりのお買い上げ点数も単価も同じだが、
来店客数増に伴う販売数量UPの結果として売上が上がる場合。
D)上記3つの複合パターン
簡単に言うと以上の4パターンあると思います。
売上を上げるために、
客単価を上げたいのか、販売数を増やしたいのか、
来店客数を増やしたいのか・・・・。
売上UPに取り組むには
まずは現状を数値で正しく認識した上で
問題点を発見し
具体的な改善方法を立てる必要があるのではっ・・?
?改善に取り組む前に・・・
あれこれ考える前に、まず確認したいのが商品の状態。
たとえ話題の本や人気のある本であっても、
すばらしい内容の良書でも、
担当者個人がお気に入りのお薦め本であっても、
肝心の商品が、やけていたりカバーが破れていては
とても売り物にはなりません。
新刊書店である以上、
古本チェーンより汚い商品を並べているようでは・・・。
まずは、きれいな本が「ある」ということ!
次に、商品の中身。
お客様が興味・関心を持って手にとって下さるモノ
=売れそうなモノ
が、並んでいるか?
いくら状態の良い商品でも、売れ残りみたいな本ばかり
売り場に飾っていては、意味がありません。
常備品の入れ替えをしていていつも思うのですが
例えば100冊あるうちで何回も回転している商品はホント数点で、
ほとんどの商品は1年間、売れることなく棚に飾られていた、
単に「常備品だから」という理由で・・。
また、自店の客層・ニーズに合った商品構成・アイテム選別も重要です。
喩えは悪いですが、魚のいない釣り堀で、
どんなに頑張って良いエサ付けて釣り糸たらしていても、
釣れっこないですよね。
売れそうな本が「ある」ということ!
言い換えれば、売れない商品を売り場から取り除く、ということ!
次に、定番商品などの欠本。
いくらこまめに補充発注をしていても、実際に入荷するかどうかは
取次や版元の在庫状況次第ですから、
往々にして、売り場の商品は売れ残りみたいなモノが
場所を占めているなんて事がよく見受けられます。
また、巻数物の欠本も要注意です。
見えないチャンスロスを生み出しているかも・・。
必要な本が常に「ある」ということ!
続く・・・・。
*各書店員の皆様の
「売上を上げるために、こんなコトをしている。」
「こんなコトを考えている。」などのお声や、
「○○の売上を上げたいんだけど・・」
「この商品をもっと売りたいんだけど・・」みたいなお悩みを
募集致しております。
ぜひぜひ、みんなで考えませんか!
|
|
|
|
コメント(26)
現在、私SUNが任されているお店は100坪位の
ロードサイド型書店なのですが
今はもう、100坪規模の書店なんて中小書店ですし
数年前にもよりの駅前に競合店ができたり
近くに大型商業施設ができて、全国規模の大書店が入ったりで
この2年間ほどは、売上激減でボロボロだったのです(号泣)
ただ、いつまでも外的要因を売上ダウンの言い訳にしてても
しょうがないので、
つたない知識と経験を駆使し
売上ダウンの内的要因と思われるものを、ひとつづつ
つぶしていっているところです・・・
どの店に行っても同じ品揃えの金太郎飴書店のようにはしたくない
まったく同感です!
新刊、売れ行き良好書の品揃えでは大書店には到底かないませんし
売上の構成比が一番高い雑誌にしても
今はコンビニなどで、24時間買うことができますし・・
何をもってお客様を自店に引き込むか?
この観点が重要ですよね。
物量やアイテム数等、品揃えなのか?
陳列や演出の創意工夫なのか?
接客・サービスなのか?
個々の商品の内容なのか?
価格に関しては、大書店もうちのような中小書店も
全く同じ土俵の上にいる訳ですから・・・。
虎吉さんが頑張って作っておられるPOP,
一度拝見してみたいですねっ☆
ぜひぜひ画像、アップして下さいませ!!
ロードサイド型書店なのですが
今はもう、100坪規模の書店なんて中小書店ですし
数年前にもよりの駅前に競合店ができたり
近くに大型商業施設ができて、全国規模の大書店が入ったりで
この2年間ほどは、売上激減でボロボロだったのです(号泣)
ただ、いつまでも外的要因を売上ダウンの言い訳にしてても
しょうがないので、
つたない知識と経験を駆使し
売上ダウンの内的要因と思われるものを、ひとつづつ
つぶしていっているところです・・・
どの店に行っても同じ品揃えの金太郎飴書店のようにはしたくない
まったく同感です!
新刊、売れ行き良好書の品揃えでは大書店には到底かないませんし
売上の構成比が一番高い雑誌にしても
今はコンビニなどで、24時間買うことができますし・・
何をもってお客様を自店に引き込むか?
この観点が重要ですよね。
物量やアイテム数等、品揃えなのか?
陳列や演出の創意工夫なのか?
接客・サービスなのか?
個々の商品の内容なのか?
価格に関しては、大書店もうちのような中小書店も
全く同じ土俵の上にいる訳ですから・・・。
虎吉さんが頑張って作っておられるPOP,
一度拝見してみたいですねっ☆
ぜひぜひ画像、アップして下さいませ!!
陳列に力をいれている…とは言いがたいのですが
こちらの店は面陳を多めで
棚ざしの本をとっぱらって本の表紙を見せるようにしています
確かにファーストインパクトはあると思うのですが
その手法ではそこに並べる本を厳選できる目がないと
意味がないのではないかと最近思います
私も勉強不足を常に感じているので
棚を殺している気がしてなりません
売れ筋を並べるだけでなく
「おや」とお客様に手に取っていただける棚を作りたいですね
しかし、みっしり棚に本が詰まっている本屋が好きなんですよ
本当は><;
にしても、お客様にやる気をアピールできないと
金太郎飴的書店になってしまうんでしょうね…
私も虎吉さんを見習ってPOP制作頑張ります><
こちらの店は面陳を多めで
棚ざしの本をとっぱらって本の表紙を見せるようにしています
確かにファーストインパクトはあると思うのですが
その手法ではそこに並べる本を厳選できる目がないと
意味がないのではないかと最近思います
私も勉強不足を常に感じているので
棚を殺している気がしてなりません
売れ筋を並べるだけでなく
「おや」とお客様に手に取っていただける棚を作りたいですね
しかし、みっしり棚に本が詰まっている本屋が好きなんですよ
本当は><;
にしても、お客様にやる気をアピールできないと
金太郎飴的書店になってしまうんでしょうね…
私も虎吉さんを見習ってPOP制作頑張ります><
確かにOPENから3年〜4年位は、とどさんのお店も
みっしり棚に本が詰まっていましたよね。
社員のSさん、とどさんのお力で
毎年確実に売上が上がっていってたのですが・・・
そこからさらに上げていくために
Sさんと交代で私SUNが配属されたときに店長が
面陳を増やしたり、平積みスペースを増やしたりされたのです。
むろん、売上と在庫のバランスを取る目的もあったのですが・・・。
あの時は、女性客や子供さんをもっと増やすため
高校学参を撤去して小中学参を増やし、
アダルト雑誌も一切やめ、
ファンシー文具やおしゃれな文具、玩具なども増やし
お店全体の雰囲気を明るく、軽くするために
面陳を大幅に増やしたのでした。
あの当時、店長は
あと、200〜300万ほど売上が上がれば
堅めの本・専門的な本など、細かい品揃えも必要になってくるが
今はまだいらない
などと、仰っておられました。
そんなとどさんのお店は先月も、昨対107%以上の実績でした!!
未だに右肩上がりの実績を続けています!
もしかしたら、そろそろ
また、みっしり棚に本が詰まっている本屋に戻すかもしれませんよ☆
みっしり棚に本が詰まっていましたよね。
社員のSさん、とどさんのお力で
毎年確実に売上が上がっていってたのですが・・・
そこからさらに上げていくために
Sさんと交代で私SUNが配属されたときに店長が
面陳を増やしたり、平積みスペースを増やしたりされたのです。
むろん、売上と在庫のバランスを取る目的もあったのですが・・・。
あの時は、女性客や子供さんをもっと増やすため
高校学参を撤去して小中学参を増やし、
アダルト雑誌も一切やめ、
ファンシー文具やおしゃれな文具、玩具なども増やし
お店全体の雰囲気を明るく、軽くするために
面陳を大幅に増やしたのでした。
あの当時、店長は
あと、200〜300万ほど売上が上がれば
堅めの本・専門的な本など、細かい品揃えも必要になってくるが
今はまだいらない
などと、仰っておられました。
そんなとどさんのお店は先月も、昨対107%以上の実績でした!!
未だに右肩上がりの実績を続けています!
もしかしたら、そろそろ
また、みっしり棚に本が詰まっている本屋に戻すかもしれませんよ☆
>SUNさん
女性客、お子さん向けというコンセプトは私も店長から伺ってました
それにあわせた仕入れをするようにも心がけているつもりはしているのですが…
それが結果に繋がっているのか否かというのが
今ひとつ見えないんですよね
データは取次ぎからのデータを検証したらよいのでしょうけれど
今ひとつ活用法がわからなかったり^^;
結果がわからない(分析しない)まま方法だけを模索するのも
妙かなと思うのですよ…
ちょっと結果が良かったからといって
その結果の上にあぐらをかいているようではダメですが…
さて右肩上がりと仰って下さってはいますが
系列店に比べたらまだまだと思えるところがたくさんあります
(逆に良いところもあるんでしょうけど)
問題点は改善し、良いところはもっと伸ばす!
そういう風にもって行きたいですよね^^
女性客、お子さん向けというコンセプトは私も店長から伺ってました
それにあわせた仕入れをするようにも心がけているつもりはしているのですが…
それが結果に繋がっているのか否かというのが
今ひとつ見えないんですよね
データは取次ぎからのデータを検証したらよいのでしょうけれど
今ひとつ活用法がわからなかったり^^;
結果がわからない(分析しない)まま方法だけを模索するのも
妙かなと思うのですよ…
ちょっと結果が良かったからといって
その結果の上にあぐらをかいているようではダメですが…
さて右肩上がりと仰って下さってはいますが
系列店に比べたらまだまだと思えるところがたくさんあります
(逆に良いところもあるんでしょうけど)
問題点は改善し、良いところはもっと伸ばす!
そういう風にもって行きたいですよね^^
掛け持ちでやってるシャトレーゼなんかも同じなのですが・・
何かの仕入れとか企画を立てる時には、誰もがいろいろ真剣に考えるのですが、
終わった後の結果の検証って、以外にしないんですよね〜!
まあ、次のコトに取りかかるので忙しいんでしょうが・・。
私SUNは変わり者なので・・・
例えば、
クリスマスが終わった=来年のクリスマスの準備が始まった!
みたいに考えているので、
販売データまとめたり、結果の検証したりなんかをけっこうします。
さすがに一年も前からアタマの中で考えてたら、
実際に商品選定したり、発注したり、売り場の陳列考えたりする時に
う〜ん、って悩んで時間を費やすコトは、ほとんどありませんよ!
だから、こうやってmixiして遊ぶ時間もできちゃうのです〜☆
何かの仕入れとか企画を立てる時には、誰もがいろいろ真剣に考えるのですが、
終わった後の結果の検証って、以外にしないんですよね〜!
まあ、次のコトに取りかかるので忙しいんでしょうが・・。
私SUNは変わり者なので・・・
例えば、
クリスマスが終わった=来年のクリスマスの準備が始まった!
みたいに考えているので、
販売データまとめたり、結果の検証したりなんかをけっこうします。
さすがに一年も前からアタマの中で考えてたら、
実際に商品選定したり、発注したり、売り場の陳列考えたりする時に
う〜ん、って悩んで時間を費やすコトは、ほとんどありませんよ!
だから、こうやってmixiして遊ぶ時間もできちゃうのです〜☆
ふくさん、有難うございます!
>ベストセラーリストも「金額ベース」で作り直すと、意外な
ものが上位に来ますよ。
正に、仰るとおりですねっ!!
例えば、私SUNのお店の3月度を例にしてみると・・・
(メイン帳合がOさかやなのでweb-opasなるPOSレジのデータ参照)
3月度の書籍のデータを単品売上ベスト照会指定で見ると
売上冊数順の上位20位は
1 HUNTER×HUNTER NO.23
2 NANA 15
3 BLEACH 21
4 鋼の錬金術師 13 初回限定特装版
5 新世紀エヴァンゲリオン Volume10
6 ナニワトモアレ 23
7 20世紀少年 21
8 エンジェル・ハート 18
9 バガボンド 22
10 バキ 31
11 バキ外伝疵面−スカーフェイス 2
12 はじめの一歩 75
13 FINAL FANTASY 12 First Flight
14 ベルセルク 30
15 海皇紀 27
16 ダヴィンチ・コード 上
17 アイシールド21 18
18 ダヴィンチ・コード 下
19 スティール・ボール・ラン 7
20 TOUGH 10
となります。
一方、売上金額順で見てみると
1(4) 鋼の錬金術師 13 初回限定特装版
2(1) HUNTER×HUNTER NO.23
3(66) 関西道路地図 3版
4(2) NANA 15
5(13) FINAL FANTASY 12 First Flight
6(3) BLEACH 21
7(5) 新世紀エヴァンゲリオン Volume10
8(6) ナニワトモアレ 23
9(7) 20世紀少年 21
10(9) バガボンド 22
11(8) エンジェル・ハート 18
12(11) バキ外伝疵面−スカーフェイス 2
13(44) 自分を磨く方法
14(38) おいでよどうぶつの森ザ・コンプリートガイド
15(14) ベルセルク 30
16(16) ダヴィンチ・コード 上
17(10) バキ 31
18(18) ダヴィンチ・コード 下
19(84) モンスターハンターポータブル公式ガイドブック
20(12) はじめの一歩 75
このようになります。
ちなみに( )内の数字は、売上冊数順の時の順位です。
確かに違いがありますね!
こんなふうに、様々な視点で検討することにより
今まで気づかなかった事が見えてきたりしますよ!
いずれにせよ、
単なる「感覚」だけではなく
数値を伴った認識を持つ事が大事ですよねっ☆
>ベストセラーリストも「金額ベース」で作り直すと、意外な
ものが上位に来ますよ。
正に、仰るとおりですねっ!!
例えば、私SUNのお店の3月度を例にしてみると・・・
(メイン帳合がOさかやなのでweb-opasなるPOSレジのデータ参照)
3月度の書籍のデータを単品売上ベスト照会指定で見ると
売上冊数順の上位20位は
1 HUNTER×HUNTER NO.23
2 NANA 15
3 BLEACH 21
4 鋼の錬金術師 13 初回限定特装版
5 新世紀エヴァンゲリオン Volume10
6 ナニワトモアレ 23
7 20世紀少年 21
8 エンジェル・ハート 18
9 バガボンド 22
10 バキ 31
11 バキ外伝疵面−スカーフェイス 2
12 はじめの一歩 75
13 FINAL FANTASY 12 First Flight
14 ベルセルク 30
15 海皇紀 27
16 ダヴィンチ・コード 上
17 アイシールド21 18
18 ダヴィンチ・コード 下
19 スティール・ボール・ラン 7
20 TOUGH 10
となります。
一方、売上金額順で見てみると
1(4) 鋼の錬金術師 13 初回限定特装版
2(1) HUNTER×HUNTER NO.23
3(66) 関西道路地図 3版
4(2) NANA 15
5(13) FINAL FANTASY 12 First Flight
6(3) BLEACH 21
7(5) 新世紀エヴァンゲリオン Volume10
8(6) ナニワトモアレ 23
9(7) 20世紀少年 21
10(9) バガボンド 22
11(8) エンジェル・ハート 18
12(11) バキ外伝疵面−スカーフェイス 2
13(44) 自分を磨く方法
14(38) おいでよどうぶつの森ザ・コンプリートガイド
15(14) ベルセルク 30
16(16) ダヴィンチ・コード 上
17(10) バキ 31
18(18) ダヴィンチ・コード 下
19(84) モンスターハンターポータブル公式ガイドブック
20(12) はじめの一歩 75
このようになります。
ちなみに( )内の数字は、売上冊数順の時の順位です。
確かに違いがありますね!
こんなふうに、様々な視点で検討することにより
今まで気づかなかった事が見えてきたりしますよ!
いずれにせよ、
単なる「感覚」だけではなく
数値を伴った認識を持つ事が大事ですよねっ☆
本日、自店M店の
8〜10月の売上獲得の短期的施策について
K店長と話をしました。
昨年10月から現在まで前年実績をクリアし続けているM店ですが
そろそろ伸び率が低くなってきており
現状のままではおそらく前年実績を割るであろう、
という危機感の元での検証です。
私SUNの考えでは
まずは「客数UPによる売上UP」なのですが・・・
ふだん我々が口にする「客数」というのは大概、
実際に何かお買い上げ下さったお客様の数=「レジ登録件数」であり
ここでの「客数UP」というのは
新規顧客の取り込みという「来店客数UP」を意味しません。
あくまでも現在ご来店下さっているお客様に対する
アプローチが先、という考えです。
書店の売上UPに関して
まずはこの私SUNの考えを
皆様どのように思われますでしょうか?
求む、ご意見・ご反論!!
8〜10月の売上獲得の短期的施策について
K店長と話をしました。
昨年10月から現在まで前年実績をクリアし続けているM店ですが
そろそろ伸び率が低くなってきており
現状のままではおそらく前年実績を割るであろう、
という危機感の元での検証です。
私SUNの考えでは
まずは「客数UPによる売上UP」なのですが・・・
ふだん我々が口にする「客数」というのは大概、
実際に何かお買い上げ下さったお客様の数=「レジ登録件数」であり
ここでの「客数UP」というのは
新規顧客の取り込みという「来店客数UP」を意味しません。
あくまでも現在ご来店下さっているお客様に対する
アプローチが先、という考えです。
書店の売上UPに関して
まずはこの私SUNの考えを
皆様どのように思われますでしょうか?
求む、ご意見・ご反論!!
初めてこちらにカキコさせて頂きます。はりはりと申します。
よろしくお願いします。
SUNさんのお考えは、「現状来店客数中の、お買上げ率UP」と言うことですよね。私もそれに大賛成です。ただ、私が普段やっている書籍売上UP法は、客数や客単価の変化は見ずに、売上=在庫×回転率を基本にしています。
SUNさんの言われる通り、通常「客数」=レジ登録件数であり、これは結果に過ぎません。お客様に対するアプローチの究極の形とはつまり、来店されたお客様が「何も買わずには帰れない」店にする事です。理想的にはすべての本がお客様の目に止まり、お気に入りの本を確実に見つけて頂けるようにする事ですが、これはもちろん完全に不可能です。だとすれば、限られた売場を最大限に効率よく活用するしかありません。
具体的には、売筋を追いかける事よりも、売場効率を優先させる事の方が大事だと思うのです。売場効率とは、単位面積あたりの売上金額です。つまり、店内で本を陳列する事が可能な面積、(棚差しであれば背表紙の面積、面陳・平積みであれば表紙の面積)の店内すべての総合計面積を仮に ”T” とし、希望する売上目標金額を ”Y” とすると、 「Y÷T」が理想売場効率であると言えます。
そして次にこの売場効率を、現在の実際の面積と売上実績金額で、店全体の平均数字と、各ジャンルごとに分けて調べた数字を計算してみて、現実と理想の売場効率を見比べてみると、店内のどこが効率を下げているか、または上げているかが見えてきます。
狭い面積で多額の売上を上げているジャンル、広い割にあまり数字を上げていないジャンル、またはジャンルでなく棚単位でもいいですが、それが分かれば対策もおのずと分かって来ます。
たとえば、平均年2回転する文庫の棚があるとします。この棚の一部を棚差しでなく、面陳にする場合、6〜7冊分の面積を必要とします。仮に6冊分を要するとした場合、理論的には棚差しならば年間に12冊の売上が見込まれます。これを1点の面陳にする場合は、少なくとも年間に12冊、つまり月1冊以上は確実に売れる商品しか選んではいけないと言う事が出来ます。
同じ論理で、ジャンルごとの棚構成比も見直ししなければなりません。攻略本が縦5段、3列のスペースで月50万売れ、学参が10列で30万の売上である場合、どうすべきでしょうか?
実は、私はこの論理を実際に使って売上UPに成功しているのですが、ウチの会社では猛反発を食らっているのです。
「そんなことをしたらまともな本屋ではなくなってしまう!」
「効率優先でそんな事をすれば、低回転商品が店頭から消えてしまい、客離れを起こす!」
などなど厳しい意見を浴びせられています。
過去3年で3店舗で実施し、すべて成功しているのですが、未だに認められていません。
もちろん、私も低回転商品の排除をしようというのではなく、低回転商品群はそれに見合った売場面積に縮小すべき、と言っているだけなのです。また、雑誌やコミックなど他の商品と比べて、明らかに回転率の差が激しいジャンルはあえて含めず、それ以外の商品を対象に計算しています。
それでもなお、根強い抵抗感がみんなにはあるようです。
皆さんはどう思われますか?
初めての書き込みで長々となってしまい申し訳ありません。
ぜひご意見、ご感想をお聞かせください。
よろしくお願いします。
SUNさんのお考えは、「現状来店客数中の、お買上げ率UP」と言うことですよね。私もそれに大賛成です。ただ、私が普段やっている書籍売上UP法は、客数や客単価の変化は見ずに、売上=在庫×回転率を基本にしています。
SUNさんの言われる通り、通常「客数」=レジ登録件数であり、これは結果に過ぎません。お客様に対するアプローチの究極の形とはつまり、来店されたお客様が「何も買わずには帰れない」店にする事です。理想的にはすべての本がお客様の目に止まり、お気に入りの本を確実に見つけて頂けるようにする事ですが、これはもちろん完全に不可能です。だとすれば、限られた売場を最大限に効率よく活用するしかありません。
具体的には、売筋を追いかける事よりも、売場効率を優先させる事の方が大事だと思うのです。売場効率とは、単位面積あたりの売上金額です。つまり、店内で本を陳列する事が可能な面積、(棚差しであれば背表紙の面積、面陳・平積みであれば表紙の面積)の店内すべての総合計面積を仮に ”T” とし、希望する売上目標金額を ”Y” とすると、 「Y÷T」が理想売場効率であると言えます。
そして次にこの売場効率を、現在の実際の面積と売上実績金額で、店全体の平均数字と、各ジャンルごとに分けて調べた数字を計算してみて、現実と理想の売場効率を見比べてみると、店内のどこが効率を下げているか、または上げているかが見えてきます。
狭い面積で多額の売上を上げているジャンル、広い割にあまり数字を上げていないジャンル、またはジャンルでなく棚単位でもいいですが、それが分かれば対策もおのずと分かって来ます。
たとえば、平均年2回転する文庫の棚があるとします。この棚の一部を棚差しでなく、面陳にする場合、6〜7冊分の面積を必要とします。仮に6冊分を要するとした場合、理論的には棚差しならば年間に12冊の売上が見込まれます。これを1点の面陳にする場合は、少なくとも年間に12冊、つまり月1冊以上は確実に売れる商品しか選んではいけないと言う事が出来ます。
同じ論理で、ジャンルごとの棚構成比も見直ししなければなりません。攻略本が縦5段、3列のスペースで月50万売れ、学参が10列で30万の売上である場合、どうすべきでしょうか?
実は、私はこの論理を実際に使って売上UPに成功しているのですが、ウチの会社では猛反発を食らっているのです。
「そんなことをしたらまともな本屋ではなくなってしまう!」
「効率優先でそんな事をすれば、低回転商品が店頭から消えてしまい、客離れを起こす!」
などなど厳しい意見を浴びせられています。
過去3年で3店舗で実施し、すべて成功しているのですが、未だに認められていません。
もちろん、私も低回転商品の排除をしようというのではなく、低回転商品群はそれに見合った売場面積に縮小すべき、と言っているだけなのです。また、雑誌やコミックなど他の商品と比べて、明らかに回転率の差が激しいジャンルはあえて含めず、それ以外の商品を対象に計算しています。
それでもなお、根強い抵抗感がみんなにはあるようです。
皆さんはどう思われますか?
初めての書き込みで長々となってしまい申し訳ありません。
ぜひご意見、ご感想をお聞かせください。
なるほどなるほど!
数値を元によく考えて取り組んでいらっしゃるのが伝わってきます。
素晴らしいですねっ。
なので、はりはりさんが仰ることはよく分かります。
実際、私SUNのこの一年の取り組みを振り返ると・・・
ジャンルごとの棚構成比の見直し
各部門毎の商品構成見直し
陳列方法の見直し(棚差し商品を絞り込んで面陳商品増)
などなども
過去数年の各部門の実績や推移を踏まえながらやってきましたから。
ちなみに私SUNの場合、
乳幼児〜小学生位のお子様と、そういう子供さんを持つ親御さんという
ファミリー層をメイン・ターゲットとし、
そういうお客様の増加と固定客化を意識した上での取り組みでした。
けっして短期的な視点ではなく、中・長期的な展望での戦略です。
そういう意味では
現状の売り場の構成が最大限に効率が良い、
とは言えません。
そう考えたら、はりはりさんと私SUNは
一見、同じ様な事をしているようですが
過去〜現在の売上実績金額を元にした売場面積の拡大・縮小と、
将来期待する売上実績金額を元にした売場面積の拡大・縮小・・・
多少、意味合いが違いますね。
むろん、
お店の規模や立地などなどの条件により違いがありますから
どちらが良い・悪いとか、正しい・間違いなんてのはありません。
また「商売」としたら「最大限の効率化」がBESTであるのも
これまた、言うまでもありません。
「まともな本屋」っていう幻想にしがみつき
売れもしない本ばっかりいつまでも棚に飾っておいて
自己満足だけの売り場を作ってうっとり、
なーんてのがまかり通る時代じゃないですからねー。
皆様、どう思われますかっ?
>はりはりさん
個人的に、
他の書店員の方と、こういったお話が出来るのは
大変勉強になりますし
おおいに刺激になります。
今後とも、よろしくお願い致します。
数値を元によく考えて取り組んでいらっしゃるのが伝わってきます。
素晴らしいですねっ。
なので、はりはりさんが仰ることはよく分かります。
実際、私SUNのこの一年の取り組みを振り返ると・・・
ジャンルごとの棚構成比の見直し
各部門毎の商品構成見直し
陳列方法の見直し(棚差し商品を絞り込んで面陳商品増)
などなども
過去数年の各部門の実績や推移を踏まえながらやってきましたから。
ちなみに私SUNの場合、
乳幼児〜小学生位のお子様と、そういう子供さんを持つ親御さんという
ファミリー層をメイン・ターゲットとし、
そういうお客様の増加と固定客化を意識した上での取り組みでした。
けっして短期的な視点ではなく、中・長期的な展望での戦略です。
そういう意味では
現状の売り場の構成が最大限に効率が良い、
とは言えません。
そう考えたら、はりはりさんと私SUNは
一見、同じ様な事をしているようですが
過去〜現在の売上実績金額を元にした売場面積の拡大・縮小と、
将来期待する売上実績金額を元にした売場面積の拡大・縮小・・・
多少、意味合いが違いますね。
むろん、
お店の規模や立地などなどの条件により違いがありますから
どちらが良い・悪いとか、正しい・間違いなんてのはありません。
また「商売」としたら「最大限の効率化」がBESTであるのも
これまた、言うまでもありません。
「まともな本屋」っていう幻想にしがみつき
売れもしない本ばっかりいつまでも棚に飾っておいて
自己満足だけの売り場を作ってうっとり、
なーんてのがまかり通る時代じゃないですからねー。
皆様、どう思われますかっ?
>はりはりさん
個人的に、
他の書店員の方と、こういったお話が出来るのは
大変勉強になりますし
おおいに刺激になります。
今後とも、よろしくお願い致します。
SUNさん、こちらこそ大変勉強になりますっ!
今後ともよろしくお願い致します。
確かに、メインターゲットとする客層を意識した店作りはとても重要ですねー。店のコンセプトをはっきり意識しての品揃えをしないと、よく言う「金太郎飴書店」になってしまいますね。特に1000坪複合店などが珍しくなくなりかけている現状では、既存店は将来の客層をどう見るか、それによって対策を立てていかなければ、生き残れないかもしれません。
特に来年は、例の「2007年問題」という、重要な年です。団塊世代の一斉退職によって、従来の客層が大きく変化するかもしれません。将来を見据えた店作り、よく考えていきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
確かに、メインターゲットとする客層を意識した店作りはとても重要ですねー。店のコンセプトをはっきり意識しての品揃えをしないと、よく言う「金太郎飴書店」になってしまいますね。特に1000坪複合店などが珍しくなくなりかけている現状では、既存店は将来の客層をどう見るか、それによって対策を立てていかなければ、生き残れないかもしれません。
特に来年は、例の「2007年問題」という、重要な年です。団塊世代の一斉退職によって、従来の客層が大きく変化するかもしれません。将来を見据えた店作り、よく考えていきたいと思います。
はりはりさん、みなさん、こんにちは。
なかなか面白い展開になってきました。
「効率優先でそんな事をすれば、低回転商品が店頭から消えてしまい、客離れを起こす!」
というのは、いかにもワタクシがいいそうなことです。(笑)
ただ、これはお店の規模にもよりますね。棚が維持できないとこ
ろは、お客さんがいないのだからしょうがないです。そのぶん
大規模店に流れてきていることを実感しています。
大規模専門店では、恐竜の尻尾を意識せざるをえず、低回転の
排除とはいえなくなってきました。
それで、低回転率でも残すべきものと、返品するものを見分け
る「眼力」が必要になっていて、それだけの商品知識をもつ社
員を育てるのが難しいということになります。
もうひとつ、高回転だが安いものをどうするか。棚1本あたり
の売上を見ているのですが、500円のパソコン書を減らすと
その棚の売上は上がります。版元営業担当氏からはクレームが
きますが。
いずれにせよ、難しい問題です。
なかなか面白い展開になってきました。
「効率優先でそんな事をすれば、低回転商品が店頭から消えてしまい、客離れを起こす!」
というのは、いかにもワタクシがいいそうなことです。(笑)
ただ、これはお店の規模にもよりますね。棚が維持できないとこ
ろは、お客さんがいないのだからしょうがないです。そのぶん
大規模店に流れてきていることを実感しています。
大規模専門店では、恐竜の尻尾を意識せざるをえず、低回転の
排除とはいえなくなってきました。
それで、低回転率でも残すべきものと、返品するものを見分け
る「眼力」が必要になっていて、それだけの商品知識をもつ社
員を育てるのが難しいということになります。
もうひとつ、高回転だが安いものをどうするか。棚1本あたり
の売上を見ているのですが、500円のパソコン書を減らすと
その棚の売上は上がります。版元営業担当氏からはクレームが
きますが。
いずれにせよ、難しい問題です。
>ふくさん
いつも、いい所に現れて下さり、
かつ的確なご提言頂きありがとうございます。
本当に勉強になります。
「恐竜の尻尾」・・・
アマゾンなどの事例で知られる「ロングテール」ですねっ。
大規模専門店の現場でも「ロングテール現象」がみられるとは
知りませんでした。
ふくさんの仰る通り、
私SUNの勤める会社の様な100坪クラスの中小書店の現状として
低回転商品を抱え続けるだけの体力がないのです。
10年ほど前とは違い・・。
回転率や棚効率を考慮しながら
お店全体の商品バランスをどうとるべきか?
うーん、ホント難しいですねー!
「回転率」に関してご存知ない方、興味をお持ちの方は
↓ も、ご参照下さいませ。
http://www.ikimono.org/inkyo/book/book_industry_03.html
http://www.sanyodo.co.jp/contents/05syanaiho/430.html
http://www.haccp99.com/HTM/c_tanaka_04.html
http://homepage3.nifty.com/toyoda-kaz/keisuukouza.htm
いつも、いい所に現れて下さり、
かつ的確なご提言頂きありがとうございます。
本当に勉強になります。
「恐竜の尻尾」・・・
アマゾンなどの事例で知られる「ロングテール」ですねっ。
大規模専門店の現場でも「ロングテール現象」がみられるとは
知りませんでした。
ふくさんの仰る通り、
私SUNの勤める会社の様な100坪クラスの中小書店の現状として
低回転商品を抱え続けるだけの体力がないのです。
10年ほど前とは違い・・。
回転率や棚効率を考慮しながら
お店全体の商品バランスをどうとるべきか?
うーん、ホント難しいですねー!
「回転率」に関してご存知ない方、興味をお持ちの方は
↓ も、ご参照下さいませ。
http://www.ikimono.org/inkyo/book/book_industry_03.html
http://www.sanyodo.co.jp/contents/05syanaiho/430.html
http://www.haccp99.com/HTM/c_tanaka_04.html
http://homepage3.nifty.com/toyoda-kaz/keisuukouza.htm
みなさん、こんにちは。
>10年ほど前とは違い・・。
そうですね。この20年くらいの間に、街の本屋さんから
「ちゃんとした本を買う客」というのがいなくなってしまっ
たのだろうと思います。いない客は、探してもしかたがあり
ません。
私のところはまだ大学の先生もきますし、古典的な教養人が
来ますのでそのあたりは(他店にない分)しっかし押さえて
います。
教養主義がいかなるものだったかは、最近出た下記の本など
で完膚なきまでに暴露されてしまいました。(やれやれ)
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9980759690
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9977167214
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9979584475
>10年ほど前とは違い・・。
そうですね。この20年くらいの間に、街の本屋さんから
「ちゃんとした本を買う客」というのがいなくなってしまっ
たのだろうと思います。いない客は、探してもしかたがあり
ません。
私のところはまだ大学の先生もきますし、古典的な教養人が
来ますのでそのあたりは(他店にない分)しっかし押さえて
います。
教養主義がいかなるものだったかは、最近出た下記の本など
で完膚なきまでに暴露されてしまいました。(やれやれ)
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9980759690
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9977167214
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9979584475
はりはりさんの手法の検証に戻ります。
はりはりさんが考える、お客様に対するアプローチの究極の形
来店されたお客様が「何も買わずには帰れない」店=売場効率の優先
これって本当に実行しようとしたら、各数値の検証だけでも
とっても大変ですよね。
それを実際にした上での売り場の改善をされ、
過去3年で3店舗で実施し、
すべて成功しておられるのにもかかわらず
社内では厳しい意見を浴びせられておられるという。
「そんなことをしたらまともな本屋ではなくなってしまう!」
「効率優先でそんな事をすれば、低回転商品が店頭から消えてしまい、客離れを起こす!」
などの根強い抵抗感!?
これは
「一通り全てのジャンルの商品をまんべんなく取り揃える」
「本当に本のお好きなお客様のために
あまり回転はしなくても
良質の本、硬めの本などを品揃えする事が必要である」
みたいな会社の方針が元々あって
単にその方針にそぐわなかったというだけのことでしょうか?
それとも、会社の方々を納得させるための「何か」が
不足していたのでしょうか?
効率優先の是非については
お店の規模や立地、競合状況など様々な条件によるのは
正にふくさんのご指摘の通りだと思います。
また、お店の成長段階に合わせることも必要ではないか
と、私SUNは考えます。
例えば私SUNの会社のH店。
現在開店から7年目くらいの
幹線道路沿いに位置する100坪クラスの総合書店で、
OPENから3年ほどは
一通りのジャンルの商品が並ぶ、ごく普通の商品構成で
売上・客数ともに地道に上がっていたのですが
4年目に入るに当たり、商品構成の見直しを行いました。
さらなる売上・客数のUPをはかるため
一般のお客様をもっと増やす、
中でもお子様や女性客をそれまで以上に取り込もうとの意図の元に
確実に売上を稼いでいた成人雑誌の類を一切排除し
高校学参も全部はずし、小中学参をひろげ
学童文具やファンシー文具・玩具などを大幅に増やし
トレーディングカードの取り扱いも始め
児童書売り場の平台スペースも拡張し
コミックの在庫を増やし
専門的な本を減らす代わりに教育関係の書籍などを充実させ
店内全体、棚差しを減らして面陳を増やし・・・・
などなどいろんな事を思い切って行いました。
結果、いまだに右肩上がりの成長を続けております。
そんな中、昨年
再び高校学参の棚も復活させ、
成人雑誌の一部も再び置き始めました。
確かに本当に本のお好きな「教養人」のお客様は
定期的に単価の高い商品をたくさんお買い上げ下さるので
上顧客には違いないのですが
お店全体の売上に占める、そういう上顧客のお客様の売上って
ホントごく数パーセントにしか満たないのが実情で
売上の9割以上が、
いわゆる「一般のお客様」からのものである事を踏まえると
まずはその「一般のお客様」をしっかり掴むことが先決なのでは。
そういう、中・長期的な戦略の過程での売場効率の見直し。
そのあたりが
はりはりさんの会社の方々にうまく伝わらなかったのでは?
「置いてないとお客様が来ない」こともありますが
「置いていてもお客様が来ない」場合もありますし
「お客様が来てから置く」も、ありだと思います。
ここまでの私SUNの考えについて
はりはりさん始め皆様方は
どのように思われますか???
はりはりさんが考える、お客様に対するアプローチの究極の形
来店されたお客様が「何も買わずには帰れない」店=売場効率の優先
これって本当に実行しようとしたら、各数値の検証だけでも
とっても大変ですよね。
それを実際にした上での売り場の改善をされ、
過去3年で3店舗で実施し、
すべて成功しておられるのにもかかわらず
社内では厳しい意見を浴びせられておられるという。
「そんなことをしたらまともな本屋ではなくなってしまう!」
「効率優先でそんな事をすれば、低回転商品が店頭から消えてしまい、客離れを起こす!」
などの根強い抵抗感!?
これは
「一通り全てのジャンルの商品をまんべんなく取り揃える」
「本当に本のお好きなお客様のために
あまり回転はしなくても
良質の本、硬めの本などを品揃えする事が必要である」
みたいな会社の方針が元々あって
単にその方針にそぐわなかったというだけのことでしょうか?
それとも、会社の方々を納得させるための「何か」が
不足していたのでしょうか?
効率優先の是非については
お店の規模や立地、競合状況など様々な条件によるのは
正にふくさんのご指摘の通りだと思います。
また、お店の成長段階に合わせることも必要ではないか
と、私SUNは考えます。
例えば私SUNの会社のH店。
現在開店から7年目くらいの
幹線道路沿いに位置する100坪クラスの総合書店で、
OPENから3年ほどは
一通りのジャンルの商品が並ぶ、ごく普通の商品構成で
売上・客数ともに地道に上がっていたのですが
4年目に入るに当たり、商品構成の見直しを行いました。
さらなる売上・客数のUPをはかるため
一般のお客様をもっと増やす、
中でもお子様や女性客をそれまで以上に取り込もうとの意図の元に
確実に売上を稼いでいた成人雑誌の類を一切排除し
高校学参も全部はずし、小中学参をひろげ
学童文具やファンシー文具・玩具などを大幅に増やし
トレーディングカードの取り扱いも始め
児童書売り場の平台スペースも拡張し
コミックの在庫を増やし
専門的な本を減らす代わりに教育関係の書籍などを充実させ
店内全体、棚差しを減らして面陳を増やし・・・・
などなどいろんな事を思い切って行いました。
結果、いまだに右肩上がりの成長を続けております。
そんな中、昨年
再び高校学参の棚も復活させ、
成人雑誌の一部も再び置き始めました。
確かに本当に本のお好きな「教養人」のお客様は
定期的に単価の高い商品をたくさんお買い上げ下さるので
上顧客には違いないのですが
お店全体の売上に占める、そういう上顧客のお客様の売上って
ホントごく数パーセントにしか満たないのが実情で
売上の9割以上が、
いわゆる「一般のお客様」からのものである事を踏まえると
まずはその「一般のお客様」をしっかり掴むことが先決なのでは。
そういう、中・長期的な戦略の過程での売場効率の見直し。
そのあたりが
はりはりさんの会社の方々にうまく伝わらなかったのでは?
「置いてないとお客様が来ない」こともありますが
「置いていてもお客様が来ない」場合もありますし
「お客様が来てから置く」も、ありだと思います。
ここまでの私SUNの考えについて
はりはりさん始め皆様方は
どのように思われますか???
SUNさんのお考え、私と手法は違うのかもしれませんが、考え方は大賛成です! そもそも意図、戦略の元に品揃えを考えていく、それこそ絶対に必要な事だと思うのです。私の会社が私の手法に反対している理由のひとつは、ずばり、「一担当者、もしくは一店長の意図、戦略だけで売上を上げる事などできるものか! 失敗したら誰が責任を取るのか?」と言う事なのです。
以前私がいた店では、私がその店に赴任した時、周りの客層を全く無視した品揃えになっていました。幹線道路沿いの中型店で、地域2番店、書籍280坪(近くの1番店は500坪)周辺は工場が多く、20〜30代独身男性がメイン客層の店でした。しかし前任者は「本屋らしい本屋」を理想としており、文芸書中心、それも文学賞作品コーナーなどの品揃えはものすごく、アフリカ文学コーナー、ブッカー賞コーナーなどまで充実していました。
地域一番店ならともかく、客層から言っても当然回転率は悪いのですが、(その時点で在庫のほとんどが過去一年0回転でした)そういう品揃えをしてこそ、一番店を蹴落とす事が出来るのだ、という考え方が社内の上層部及び、社内の主流の考えだったようです。
しかし私は、赴任後、そこの実際に売れている単品データを調査し、やはり独身男性向けの、車・写真集・アイドル・コミック・ミリタリー・ホビー系の書籍・雑誌が売上の主流を占めていることを確認しました。
そこでそういった商品を充実させ、先の文学作品等を一斉排除し、それでも空いたスペースには、出版社扱いのアイドルDVD等の面陳陳列(平均単価3800円くらいで結構稼ぐのです♪)を大幅に増やし、大きく前年比をアップさせました。
売上はそれで上がったのですが、確かに売場の見た目は、私から見ても、本屋らしい本屋ではないなあ、と思えるものであったことは事実です。私も本好きでこの業界に入ったわけですから、きちんとした文芸書で正々堂々とした本屋にしたいと言う欲求はありますが、私の考えとしては、それは書店員としての欲望であって、お客様のことを考えた施策ではないと思うのです。
書店の売上とは、単なる店側の利益追求のみならず、その店に対する周辺のお客様からの投票のようなものだと思うのです。これならお金を払ってもいいと思えるものを、お客様は購入されるのであって、たとえどんなにいい本を並べたとしても、そのお客様自身にとって価値を見いだせない本しかない書店には、お客様はお金を落としては頂けません。売上が上がると言う事は、それだけたくさんのお客様がその店を支持し、賛成投票をした様なものだと思うのです。
その考えに立てば、やはり売れるものを置くということと、立派な品揃えで店の、そして会社の品格を保つ事(うちの会社は老舗なのでその辺にこだわる年配の方が多いのです。)のどちらを選択すべきか、という問題に行き着くわけです。その結果、私はどちらかと言うと「異端者」扱いになってしまったわけです。
私も「売れるものなら何でも置く」というわけではなく、SUNさんがされたように、客層からして本来なら売れるであろう、成人雑誌等はなるべく排除し、女性客も取り込むため、女性エッセイ書などの大幅な充実も図っていました。直扱いですがディスカバー21の本などは売上が3倍近くになり、東京からわざわざ営業の人が来てくれるようになりましたし。
しかしまあ、今までと違う事をしようとすると、なんにせよ、保守的な方々(上司にせよ、部下にせよ)からは、抵抗感があるのでしょうね。もはや社内でこういった事を相談・議論できる人はほとんどいなくなってしまいました。老舗会社の一番悪い所ですかね。
でも最近、ミクシィに入れる機会があり、このコミュニティがあることを知って、こういうお話を皆さんと議論できて、本当に嬉しく思っております。これこそ私の望んでいた事なのです。こちらの場をお借りして、私自身ももっと勉強し、今の会社では得られないノウハウを身に付けたり、研鑚できればなあ、と思っております。今後ともよろしくお願い致します。
毎度長々と書いてしまい申し訳ありません。
ちなみに、こういう件で会社に不満がたまっていた頃書いたブログかあります。(最近は書いておりませんが・・) 書店員版ゴーマニズム宣言みたいでえらそうな事ばかり書いておりますが、よろしかったらご笑読下さいませ。
↓
http://blog.livedoor.jp/hariharidax/
以前私がいた店では、私がその店に赴任した時、周りの客層を全く無視した品揃えになっていました。幹線道路沿いの中型店で、地域2番店、書籍280坪(近くの1番店は500坪)周辺は工場が多く、20〜30代独身男性がメイン客層の店でした。しかし前任者は「本屋らしい本屋」を理想としており、文芸書中心、それも文学賞作品コーナーなどの品揃えはものすごく、アフリカ文学コーナー、ブッカー賞コーナーなどまで充実していました。
地域一番店ならともかく、客層から言っても当然回転率は悪いのですが、(その時点で在庫のほとんどが過去一年0回転でした)そういう品揃えをしてこそ、一番店を蹴落とす事が出来るのだ、という考え方が社内の上層部及び、社内の主流の考えだったようです。
しかし私は、赴任後、そこの実際に売れている単品データを調査し、やはり独身男性向けの、車・写真集・アイドル・コミック・ミリタリー・ホビー系の書籍・雑誌が売上の主流を占めていることを確認しました。
そこでそういった商品を充実させ、先の文学作品等を一斉排除し、それでも空いたスペースには、出版社扱いのアイドルDVD等の面陳陳列(平均単価3800円くらいで結構稼ぐのです♪)を大幅に増やし、大きく前年比をアップさせました。
売上はそれで上がったのですが、確かに売場の見た目は、私から見ても、本屋らしい本屋ではないなあ、と思えるものであったことは事実です。私も本好きでこの業界に入ったわけですから、きちんとした文芸書で正々堂々とした本屋にしたいと言う欲求はありますが、私の考えとしては、それは書店員としての欲望であって、お客様のことを考えた施策ではないと思うのです。
書店の売上とは、単なる店側の利益追求のみならず、その店に対する周辺のお客様からの投票のようなものだと思うのです。これならお金を払ってもいいと思えるものを、お客様は購入されるのであって、たとえどんなにいい本を並べたとしても、そのお客様自身にとって価値を見いだせない本しかない書店には、お客様はお金を落としては頂けません。売上が上がると言う事は、それだけたくさんのお客様がその店を支持し、賛成投票をした様なものだと思うのです。
その考えに立てば、やはり売れるものを置くということと、立派な品揃えで店の、そして会社の品格を保つ事(うちの会社は老舗なのでその辺にこだわる年配の方が多いのです。)のどちらを選択すべきか、という問題に行き着くわけです。その結果、私はどちらかと言うと「異端者」扱いになってしまったわけです。
私も「売れるものなら何でも置く」というわけではなく、SUNさんがされたように、客層からして本来なら売れるであろう、成人雑誌等はなるべく排除し、女性客も取り込むため、女性エッセイ書などの大幅な充実も図っていました。直扱いですがディスカバー21の本などは売上が3倍近くになり、東京からわざわざ営業の人が来てくれるようになりましたし。
しかしまあ、今までと違う事をしようとすると、なんにせよ、保守的な方々(上司にせよ、部下にせよ)からは、抵抗感があるのでしょうね。もはや社内でこういった事を相談・議論できる人はほとんどいなくなってしまいました。老舗会社の一番悪い所ですかね。
でも最近、ミクシィに入れる機会があり、このコミュニティがあることを知って、こういうお話を皆さんと議論できて、本当に嬉しく思っております。これこそ私の望んでいた事なのです。こちらの場をお借りして、私自身ももっと勉強し、今の会社では得られないノウハウを身に付けたり、研鑚できればなあ、と思っております。今後ともよろしくお願い致します。
毎度長々と書いてしまい申し訳ありません。
ちなみに、こういう件で会社に不満がたまっていた頃書いたブログかあります。(最近は書いておりませんが・・) 書店員版ゴーマニズム宣言みたいでえらそうな事ばかり書いておりますが、よろしかったらご笑読下さいませ。
↓
http://blog.livedoor.jp/hariharidax/
はりはりさんの「書店員版ゴーマニズム宣言」拝読致しました!(笑)
「本」を売る書店員の専門知識が「口伝え」でしか伝えられていないというのは、なんという皮肉であろうか。いや、口伝えですら伝えられず、一人の書店員が辞めると同時に、その大量の知識も失われていく事が少なくない。
それもこれも、こうしたノウハウが目に見える形で文章化されていないせいである
これは私SUNも全く同感です。
もちろん、大書店チェーンなんかでは
しっかりした社員教育が行われているのでしょうが
私SUNの勤める中小書店の現状は正に
はりはりさんのご指摘の通りです。
残念ながら「プロの書店員を育てる」という風土は
わが社にもありません。
「自ら、育つ」しかないのです。
なので中堅社員以下が、
年々、現場の「作業」しか出来ない者ばかりになっているのです。
そんな訳で、私SUNが当コミュを作った目的のひとつに、
書店業務に関する様々なノウハウの明文化があったのです。
私SUNのつたない知識と経験だけでは到底出来ませんが、
この「書店道」コミュが
私SUNのように、専門知識の「口伝え」の機会を得られぬ書店員の方の
スキルアップの参考に多少なりともなれば良いのですが・・。
ふくさん・はりはりさんを始め、皆様方、
今後とも、よろしくご指導・ご助言、お願い致しますーーーっ!!!
「本」を売る書店員の専門知識が「口伝え」でしか伝えられていないというのは、なんという皮肉であろうか。いや、口伝えですら伝えられず、一人の書店員が辞めると同時に、その大量の知識も失われていく事が少なくない。
それもこれも、こうしたノウハウが目に見える形で文章化されていないせいである
これは私SUNも全く同感です。
もちろん、大書店チェーンなんかでは
しっかりした社員教育が行われているのでしょうが
私SUNの勤める中小書店の現状は正に
はりはりさんのご指摘の通りです。
残念ながら「プロの書店員を育てる」という風土は
わが社にもありません。
「自ら、育つ」しかないのです。
なので中堅社員以下が、
年々、現場の「作業」しか出来ない者ばかりになっているのです。
そんな訳で、私SUNが当コミュを作った目的のひとつに、
書店業務に関する様々なノウハウの明文化があったのです。
私SUNのつたない知識と経験だけでは到底出来ませんが、
この「書店道」コミュが
私SUNのように、専門知識の「口伝え」の機会を得られぬ書店員の方の
スキルアップの参考に多少なりともなれば良いのですが・・。
ふくさん・はりはりさんを始め、皆様方、
今後とも、よろしくご指導・ご助言、お願い致しますーーーっ!!!
いやーっ、悪かった!
実に悪かったなー、8月の売上。
うちの書店はどの店舗も思わしくない結果で、
昨年10月以来、前年実績をクリアし続けてたM店までも
ついに昨対割っちゃったしー・・・。
取次の担当者の話によると8月は
全体的に厳しい結果のお店が多かったそうで
平均で昨対94%くらい、とのこと。
特に雑誌の落ち込みが顕著であったようです。
さて、どうするか?
ここが、思案のしどころ・腕の見せ所です!
他の書店員の皆様のお店は、8月はいかがでしたか?
また、「売上UP」達成のために
どんなことを考え
どんなことを取り組んでいらっしゃいますか??
むろん経営戦略的な部分では
「社外秘」なこともおありでしょうから
差し支えない程度で結構です。(笑)
ぜひぜひご助言・ご提言、お待ちしておりますー!
実に悪かったなー、8月の売上。
うちの書店はどの店舗も思わしくない結果で、
昨年10月以来、前年実績をクリアし続けてたM店までも
ついに昨対割っちゃったしー・・・。
取次の担当者の話によると8月は
全体的に厳しい結果のお店が多かったそうで
平均で昨対94%くらい、とのこと。
特に雑誌の落ち込みが顕著であったようです。
さて、どうするか?
ここが、思案のしどころ・腕の見せ所です!
他の書店員の皆様のお店は、8月はいかがでしたか?
また、「売上UP」達成のために
どんなことを考え
どんなことを取り組んでいらっしゃいますか??
むろん経営戦略的な部分では
「社外秘」なこともおありでしょうから
差し支えない程度で結構です。(笑)
ぜひぜひご助言・ご提言、お待ちしておりますー!
やっぱりそうですかー!
うちも8月めちゃ悪かったです。
7月まで前年106%前後で絶好調だったのですが
8月は前年96%・・・ やっぱり同じように雑誌
の落ち込みが激しいです。
うちのチェーンの他の店も同様です。
さて原因はなんでしょう?
私の考えたのは、
? 景気回復による夏休み旅行増加で、出費がそちらに回った。
? 取次の配本減による売り逃し。
? NINTENDO DSLite の増産で出費がそちらに回った。
? 単に前年が良すぎただけ。
このぐらいしか思いつかないのですが、あまり釈然としません。
とにかく原因がつかめないと、対策の立てようがないですね。
ちなみにうちは文芸・文庫・新書は好調のままです。
悪いのはやはり雑誌・ムックですね。
ちょうど先日、取次担当者が来て、
「返品率が高いので、さらに配本を減らします」
と言いに来たので、ちょっとケンカしましたが、
巨大書店増加で、中小書店への配本減がやはり一番の
原因ではないかと思うのですが・・・
(版元の刷り部数減もあるかもしれませんが。)
版元への事前注文や、こまめな定期改正が必要かなあと
色々考えているところです。
ちなみに9月に入ってからも、調子が戻りません。
正直、頭を抱えています・・・
皆さんのところはどうですか?
うちも8月めちゃ悪かったです。
7月まで前年106%前後で絶好調だったのですが
8月は前年96%・・・ やっぱり同じように雑誌
の落ち込みが激しいです。
うちのチェーンの他の店も同様です。
さて原因はなんでしょう?
私の考えたのは、
? 景気回復による夏休み旅行増加で、出費がそちらに回った。
? 取次の配本減による売り逃し。
? NINTENDO DSLite の増産で出費がそちらに回った。
? 単に前年が良すぎただけ。
このぐらいしか思いつかないのですが、あまり釈然としません。
とにかく原因がつかめないと、対策の立てようがないですね。
ちなみにうちは文芸・文庫・新書は好調のままです。
悪いのはやはり雑誌・ムックですね。
ちょうど先日、取次担当者が来て、
「返品率が高いので、さらに配本を減らします」
と言いに来たので、ちょっとケンカしましたが、
巨大書店増加で、中小書店への配本減がやはり一番の
原因ではないかと思うのですが・・・
(版元の刷り部数減もあるかもしれませんが。)
版元への事前注文や、こまめな定期改正が必要かなあと
色々考えているところです。
ちなみに9月に入ってからも、調子が戻りません。
正直、頭を抱えています・・・
皆さんのところはどうですか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
書店道 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
書店道のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6478人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19254人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人