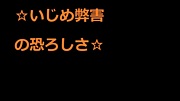http://
いじめってどんなものだと思っていますか?
殴られたり、けられたり、悪口を言われたり、嫌がらせをされたり。そんな、いじめる子も、いじめられる子も、見ている子も「いじめてる。」「いじめられている」とはっきり分かるような派手なものばかりではありません.
周りの子にとっては、たいしたいじめとは思っていないものもあります。「あの子なら、しょうがないや」とか、「いつものこと」と、自分たちの生活の一部の風景のように受け取ってしまうこともあります。
でも、いじめられる子にとっては、非常に苦痛に満ちた学校生活を、何年も強いられる残酷なものもあるのです。それを【長期のいじめ】といいます。最も深刻ないじめです。
長期のいじめは、小学校中学年に発生することが多いようです。そして、中学校に引き継がれ、時には高校まで持ち越す子もいるようです。ゆうに、10年近くにもなることがあります。
その苦しみは大変なものです。毎日が、ストレスフルな生活。その壮絶な時間を想像できるでしょうか。
その生活から、どのように成人していくのでしょうか。一生を左右する深い心のキズを背負って生活しな ければならない。その子の長い人生の困難さを、周りの誰が想像していることでしょう。
1 例を紹介しましょう
これは、長期のいじめの事例をいくつか組み合わせたものですが、こうしたいじめはどこの学校にもあると思っています。
? バイ菌遊びでいじめの対象となったA
3年生の時、クラスにバイ菌遊びが蔓延した。最初は、いろいろな子が対象になり、遊び感覚であったが、やがてAに集中するようになった。ドンとわざとAにぶつかってきて、キャアキャアとみんなに付けに行く。やがて、体にぶつけられることはなくなったが、Aの所持品全てが、バイ菌遊びの対象となった。机、カバン、靴等、手当たり次第に、その場からAへのバイ菌遊びが始められた。Aが、そこにいようといまいと、おかまいなしにバイ菌遊びは続けられた。
朝、Aが、「おはよう」と声をかけても、みんな聞こえない振り。「ねえ」と肩をたたこうとすると、さっと体をかわされる。そんな日が何日も続く内にさすがのAも、みんなに声をかけることも、近づくこともできなくなった。
やがてその遊びも下火になったが、Aに声をかける子は勿論だれもいなくなり、完全にAは孤立した。放課は何もすることがなく、自分の席に座っていることしかできなくなった。すると、通りすがりに「きもい」「うざい」「死ね」[消えろ]と、小さな声でののしる子が、出るようになった。それは、周りの子にはほとんど聞き取れない程度に、密かに行われた。毎日ではないが、週に数回、こうした状況は生まれた。
保護者は、度々担任に「うちの子がいじめられている。何とかして欲しい。」と訴えたが、何をされているのか、具体的に説明できなかった。担任の目からは、何の異常も観察できなかった。(友達のいない子。外遊びの嫌いな子。自分からは決して友達に近づかない子)としか、映らなかった。
子供の世界で起こっているこうしたいじめ現象を、担任は、捉えることはできなかった。「本人があんな性格ではどうしようもない。何と被害妄想の強い親か。」担任は度重なる保護者の訴えにうんざりしていた。
3年、4年と散々バイ菌遊びの対象とされたAは、5年生になって4クラスが混ざるクラス編成が行われても、孤立状態は改善しなかった。すでにAのことは、クラスを越え、学年全体に広まっていたからである。
Aにとって自分のつらい立場をいやが上にも認識させられるのは、グループ作りの時であった。社会見学、自然教室、各教科で発生する学習のためのグループ作り等、その編成のたびに、だれもチームに誘ってくれる子は、いなかった。担任の声かけでAを誘う子もいたが、Aは(先生に言われたから無理矢理誘ってくれている。ほんとは、とっても嫌なんだ。)という考えが頭を駆けめぐり、動くことができなかった。
5年生になった年から、生活アンケートが実施され、「Aが、いじめられている」と数人の友達からも指摘があり、Aも「いじめられている」と毎回記入した。そのため、5,6年の担任は、熱心に「Aと遊ぶように。」とクラスに呼びかけた。その都度、一時的に遊びに誘う動きが見られたが、すぐに孤立してしまった。こうしたことが、担任の働きかけの度に何度も繰り返された。しかし、Aに対して、男子を中心に密かに「バイ菌遊び」が小学校を卒業するまで続いていた。それを、45名近い職員の誰も目撃することはできなかった。女子は、全く毛嫌いをする子と「分からなければ、いいよね」と6年生の春休みまで、密かに家では遊ぶ子もいた。
中学に入り、1か月くらいはよかったが、同じ学校の生徒が、小学校時代のAの実態を、おもしろおかしく吹聴したため、またたく間に他小学校出身の同学年に知れ渡り、再び孤立し、不潔なものの対象として扱われた。時に、廊下で通りすがりに大げさな態度で嫌悪感を現す子どもも出てきて、嫌がらせはエスカレートしていった。机へのいたずら書き、物隠し、給食の時のグループ作りで机を離される、集会ではAの周りはみんな間隔をとって離れて並んでいた等、細やかな嫌がらせは、Aの神経を痛め続けた。時の、クラスのリーダーの発言(「体育の時のAの態度は何だ!」というような単なる感想であったのだが)に呼応するように、数人の子による暴力行為が発生することもあった。
小学校からの連絡もあり、中学の生徒指導担当の教師が、何度も指導を重ねたが、事態は一向に改善されなかった。小学校の時、密かに遊んでいた子も、危険を感じて、中学では全く遊ばなくなった。
一時的に、Aに友達ができたが、それは全て他小学校の出身者であった。2年生になり、Aは教室に入ろうとすると、胸がどきどきして、苦しくなり、どうしても教室に入れなくなり、教室と保健室を行き来する生活となった。2年の3学期から不登校となり、そのままま2度と学校には姿を見せなくなった。
? グループ内のいじめ
上の事例は、学校集団そのものが、Aに対していじめの構図になっていったものですが、グループの中でいじめ構造になるものもあります。このタイプは悪口や嫌がらせをされていても、仲良し仲間のじゃれ合いのような形(いじめている子は本気でそう思っていることが多い)を取るため、周りの子からもほとんどいじめと認識されません。使役行為やいたずらが、どんどんエスカレートし、嫌がらせも、グループの最下位の子に集中します。やがてそのいたずらや使役行為が犯罪の域に達し、事件として発覚する事があります。名古屋の5000万円強奪事件も、このタイプです。上位の者は際限なく権力を拡大し、京都までタクシーで豪遊するまでに発展した経緯は、皆様も記憶にあるのではないかと思います。
2 これらの事例からどんなことがわかりますか?
? どんなことからでもいじめは発生する
「バイ菌遊び」という何の根拠もない遊びから、こんなにまでエスカレートしてしまういじめ。他にも、あだ名、からかい、ちょっとした失敗がきっかけ等、取るに足りないことからスタートすることが多いようです。
? いじめは集団現象化する→一部の子から→クラス全体へ→学年全体へ →学校集団全体へ
一部の子から始まった遊び混じりのいじめが、次第に集団化し、本人は身動きできなくなる。また、クラス替えで、Aの現状を知らない子もいるはずなのに、5年生でも3,4年生と同じ孤立状態で最下位に位置してしまう。中学ではもっと知らない子がたくさん居るはずなのに、すぐに孤立してしまう。周りの子は、意味もなくみんなと同じ行動をしてしまいます。いじめが持つ、集団現象の恐ろしさです。
? 小学校で全員が体験済み?
自分が、Aに対して嫌悪感を体験したわけでもないのに、5年生の時も、中学入学後も、子供達はみんな周りの子と同じように行動しています。なぜ、みんな同じ行動をするのでしょうか。それは、こうした子に対して、どう対応するのか、子供達全員がすでに小学校で経験ているからではないでしょうか。つまり、Aのような事件は、どこの学校でも発生し、子供達にとっては身近な問題なのだと考えられます。
小学校で学んだ経験から、こうした子に近づかないことが懸命な手段であると判断し、行動します。自分がこうした立場になったと感じられたときには、非常な恐怖心からすぐに不登校になる子も居ます。いじめ、からかいはだれかれとなくその子に集中します。それがどんどんエスカレートします。「あの子にはそうしていいんだ」と経験上思う子が多いからです。悲惨な状態がちょっとしたきっかけから生まれてしまいます。
学校には、30人に1,2名、少なくとも60人に1名は、Aのような立場の子が発生しているように感じます。この数は、実は大変な数で深刻な問題なのです。
? いじめは教師や大人には見えない
小学校3,4年生の担任は、全くいじめを認識できませんでした。放課になって一人教室に残っている子を見て、担任はそこから何が見えるたしょうか。何も、見えなかったのです。
また、5,6年生の担任も、生活アンケートでようやくいじめられていることを知りました。しかし、いじめの真の姿が見えていなかったため、子供の世界でできあがった子供にとっては無視できない構造を壊すことが出来ず、孤立状態はすぐに戻ってしまい、Aを救い出すことはできませんでした。
45名いる学校職員も、卒業まで続いたバイ菌遊びを一度も目撃することは出来ませんでした。子供達がキャアキャア大騒ぎして追いかけっこをしているのは見たかもしれませんが、バイ菌遊びとは想像だにできなかったのでしょう。でも、子供達は追いかけっこの意味を知っているのす。そこで、アンケートの具体的な質問に、数人の子が「Aは、ばい菌遊びをされている。きもいと言われている」と、答えることができたのです。
集団を観察できない保護者は、自分の子供の今までと違った様子から「いじめられているようだ」とは感じながら、どのようにいじめられているか、具体的にはとらえることができなかったのは当然です。訴えは具体性を欠き、担任には被害妄想としか受け取ってもらえなかったのです。
? 担任の働きかけ→子供集団の構造が揺らぐとき
5,6年の担任が「Aとも遊ぶように」と働きかけることで、子供集団の動きが何度も一部崩れています。いつもは、子供達は、自分たちが作り上げた構造の中で、自分たちが常識と考える行動(無視や仲間外れ等)を、何の疑念も持たずに行動しているのでしょう。
しかし、教師の働きかけで、すぐにAに働きかける子、遊ぶ子が存在する事実。また、学校集団の中では動けない子供も、家に帰ってから「(みんなに)分からなければいいよね。」と遊ぶ子どもがいる事実から、子供達全員がAに嫌悪感を持っているわけではないことが分かります。
しかし、せっかくのこうした子供の動きも、嫌悪感を抱いている他の子からの働きかけで、再び元に戻ってしまうのでしょう。「あんな子と遊ばないほうがいいよ」と耳打ちされれば、子供は恐怖心を感じるのではないでしょうか。しかし、根本的な解決にはなりませんが、教師の働きかけは、結構、子供達に大きな力を発揮することが分かります。
? 深く傷つくいじめられっ子
子供は、よくぞこんなに長く耐えるものだと驚嘆します。しかし、その子の心のキズの深さは、測り知れないものがあります。Aの将来を考えると暗澹たる気持ちになりますが、これについては、【弊害】の項で詳しく扱っておりますのでご覧ください。
? 子供はいじめが自覚できない
子供はなぜ、訴えないのでしょうか。本人も、いじめられていることは当然感じていると思いますが、それ程強くは訴えないようです。
「ウザイ、と言われた。」と訴えられた担任は、どうするでしょう。たぶん、「人が傷つくことを言ったりしたりしてはいけません。あやまっておいで。」ではないでしょうか。
「ウザイ」と言った子は無意識ないじめの構図の中で行動しているので、根本的な解決にならず、「あの子へのいたずらは、先生に叱られるからやめるけど」と、また違うターゲットを見つけ繰り返されることがあります。いじめの構図の中で行動していることの非を担任は学ばせることができないからです。「人にされていやなことは自分もするな」と言うような、まとまった抽象的な言葉だけでは子供はよく分からないのです。「あの子を、こうしたことをしてもいい子だとバカにしていない?」等、いじめとしての認識から発生していることを指摘しなくては、いじめの構造は壊れません。
また、違う子がその子をいじめます。何度もそれが繰り返される内に、いじめられる子は(訴えても無駄)とあきらめてしまうのではないでしょうか。
では、周りにいる子はなぜ担任に知らせないのでしょう。これは、いじめの構造が長い時間かかって作られるため、「いつの間にかこうなっている」という状態で、その子にやられていることを異常とも、いじめとも認識できず、普通のことと、受け入れてしまうからではないでしょうか。
生活アンケートに、具体的に質問され「ああ、そういえば、この質問はあの子に当てはまるな」ということで回答しているように感じます。しかし、それも全員ではなく、一部の子しか答えていません。
いじめられる子にとっては、こうした現状はとても苦しいものなのですが、周りの子にとっては「たいした問題ではない」と感じているふしがあります。子供達は言われなければ、自分たちの作り出した世界の異常性、病的な部分に気づかず、それを分析する力はない、と感じられます。
そこで、こうした無意識に対して、教師が「あなた達の考えていること、おかしくない?やっていること、変じゃない?」と子供に問いかけ、子供が持っている無意識のいじめの構造を意識化し壊す必要があるのです。
ただし、自覚していじめていることもあるのですが、それが長期化すると、自覚できないいじめに移行してしまうこともあります。「こんなのいつものことじゃん。」となってエスカレートします。それが、無知なる未熟な子供の世界の怖さです。
? いじめはなぜ解決しない?
また、せっかく遊びだしたのに、なぜ、すぐに孤立状態になってしまうのでしょうか。 そ れは、先生という、子供にとっては非常に偉大な力を持った人の働きかけよりも、なお、子ども達が長い間かけて作り出したいじめの構図の世界の方が勝っているからではないでしょうか。
Aを集団の最下位と見なす意識は、Aに対する嫌悪感を生みます。嫌悪感は全員が持っているわけでは無いのに、嫌悪感を持たない子をも飲み込んでしまうほど、強大だと言えます。小学校の高学年や中学で、いじめの解決が難しいと感じる先生は多いようです。それは、何年もかかって作られた強固ないじめの構造を壊すこと、つまり子供の認識を変えることが、いかに難しいかを示しているのではないでしょうか。 【いじめの発生と諸問題】参照
★ママリンコメント★
虐める子は勿論悪いですが
虐める子が怖くて同調する子がいるのが大きく問題な気がします。
虐められてる子を感じたら、虐められている対象が自分でなくとも
先生、親に相談して貰いたいです。
親の間で話題になるのも必要かと思います。
いじめってどんなものだと思っていますか?
殴られたり、けられたり、悪口を言われたり、嫌がらせをされたり。そんな、いじめる子も、いじめられる子も、見ている子も「いじめてる。」「いじめられている」とはっきり分かるような派手なものばかりではありません.
周りの子にとっては、たいしたいじめとは思っていないものもあります。「あの子なら、しょうがないや」とか、「いつものこと」と、自分たちの生活の一部の風景のように受け取ってしまうこともあります。
でも、いじめられる子にとっては、非常に苦痛に満ちた学校生活を、何年も強いられる残酷なものもあるのです。それを【長期のいじめ】といいます。最も深刻ないじめです。
長期のいじめは、小学校中学年に発生することが多いようです。そして、中学校に引き継がれ、時には高校まで持ち越す子もいるようです。ゆうに、10年近くにもなることがあります。
その苦しみは大変なものです。毎日が、ストレスフルな生活。その壮絶な時間を想像できるでしょうか。
その生活から、どのように成人していくのでしょうか。一生を左右する深い心のキズを背負って生活しな ければならない。その子の長い人生の困難さを、周りの誰が想像していることでしょう。
1 例を紹介しましょう
これは、長期のいじめの事例をいくつか組み合わせたものですが、こうしたいじめはどこの学校にもあると思っています。
? バイ菌遊びでいじめの対象となったA
3年生の時、クラスにバイ菌遊びが蔓延した。最初は、いろいろな子が対象になり、遊び感覚であったが、やがてAに集中するようになった。ドンとわざとAにぶつかってきて、キャアキャアとみんなに付けに行く。やがて、体にぶつけられることはなくなったが、Aの所持品全てが、バイ菌遊びの対象となった。机、カバン、靴等、手当たり次第に、その場からAへのバイ菌遊びが始められた。Aが、そこにいようといまいと、おかまいなしにバイ菌遊びは続けられた。
朝、Aが、「おはよう」と声をかけても、みんな聞こえない振り。「ねえ」と肩をたたこうとすると、さっと体をかわされる。そんな日が何日も続く内にさすがのAも、みんなに声をかけることも、近づくこともできなくなった。
やがてその遊びも下火になったが、Aに声をかける子は勿論だれもいなくなり、完全にAは孤立した。放課は何もすることがなく、自分の席に座っていることしかできなくなった。すると、通りすがりに「きもい」「うざい」「死ね」[消えろ]と、小さな声でののしる子が、出るようになった。それは、周りの子にはほとんど聞き取れない程度に、密かに行われた。毎日ではないが、週に数回、こうした状況は生まれた。
保護者は、度々担任に「うちの子がいじめられている。何とかして欲しい。」と訴えたが、何をされているのか、具体的に説明できなかった。担任の目からは、何の異常も観察できなかった。(友達のいない子。外遊びの嫌いな子。自分からは決して友達に近づかない子)としか、映らなかった。
子供の世界で起こっているこうしたいじめ現象を、担任は、捉えることはできなかった。「本人があんな性格ではどうしようもない。何と被害妄想の強い親か。」担任は度重なる保護者の訴えにうんざりしていた。
3年、4年と散々バイ菌遊びの対象とされたAは、5年生になって4クラスが混ざるクラス編成が行われても、孤立状態は改善しなかった。すでにAのことは、クラスを越え、学年全体に広まっていたからである。
Aにとって自分のつらい立場をいやが上にも認識させられるのは、グループ作りの時であった。社会見学、自然教室、各教科で発生する学習のためのグループ作り等、その編成のたびに、だれもチームに誘ってくれる子は、いなかった。担任の声かけでAを誘う子もいたが、Aは(先生に言われたから無理矢理誘ってくれている。ほんとは、とっても嫌なんだ。)という考えが頭を駆けめぐり、動くことができなかった。
5年生になった年から、生活アンケートが実施され、「Aが、いじめられている」と数人の友達からも指摘があり、Aも「いじめられている」と毎回記入した。そのため、5,6年の担任は、熱心に「Aと遊ぶように。」とクラスに呼びかけた。その都度、一時的に遊びに誘う動きが見られたが、すぐに孤立してしまった。こうしたことが、担任の働きかけの度に何度も繰り返された。しかし、Aに対して、男子を中心に密かに「バイ菌遊び」が小学校を卒業するまで続いていた。それを、45名近い職員の誰も目撃することはできなかった。女子は、全く毛嫌いをする子と「分からなければ、いいよね」と6年生の春休みまで、密かに家では遊ぶ子もいた。
中学に入り、1か月くらいはよかったが、同じ学校の生徒が、小学校時代のAの実態を、おもしろおかしく吹聴したため、またたく間に他小学校出身の同学年に知れ渡り、再び孤立し、不潔なものの対象として扱われた。時に、廊下で通りすがりに大げさな態度で嫌悪感を現す子どもも出てきて、嫌がらせはエスカレートしていった。机へのいたずら書き、物隠し、給食の時のグループ作りで机を離される、集会ではAの周りはみんな間隔をとって離れて並んでいた等、細やかな嫌がらせは、Aの神経を痛め続けた。時の、クラスのリーダーの発言(「体育の時のAの態度は何だ!」というような単なる感想であったのだが)に呼応するように、数人の子による暴力行為が発生することもあった。
小学校からの連絡もあり、中学の生徒指導担当の教師が、何度も指導を重ねたが、事態は一向に改善されなかった。小学校の時、密かに遊んでいた子も、危険を感じて、中学では全く遊ばなくなった。
一時的に、Aに友達ができたが、それは全て他小学校の出身者であった。2年生になり、Aは教室に入ろうとすると、胸がどきどきして、苦しくなり、どうしても教室に入れなくなり、教室と保健室を行き来する生活となった。2年の3学期から不登校となり、そのままま2度と学校には姿を見せなくなった。
? グループ内のいじめ
上の事例は、学校集団そのものが、Aに対していじめの構図になっていったものですが、グループの中でいじめ構造になるものもあります。このタイプは悪口や嫌がらせをされていても、仲良し仲間のじゃれ合いのような形(いじめている子は本気でそう思っていることが多い)を取るため、周りの子からもほとんどいじめと認識されません。使役行為やいたずらが、どんどんエスカレートし、嫌がらせも、グループの最下位の子に集中します。やがてそのいたずらや使役行為が犯罪の域に達し、事件として発覚する事があります。名古屋の5000万円強奪事件も、このタイプです。上位の者は際限なく権力を拡大し、京都までタクシーで豪遊するまでに発展した経緯は、皆様も記憶にあるのではないかと思います。
2 これらの事例からどんなことがわかりますか?
? どんなことからでもいじめは発生する
「バイ菌遊び」という何の根拠もない遊びから、こんなにまでエスカレートしてしまういじめ。他にも、あだ名、からかい、ちょっとした失敗がきっかけ等、取るに足りないことからスタートすることが多いようです。
? いじめは集団現象化する→一部の子から→クラス全体へ→学年全体へ →学校集団全体へ
一部の子から始まった遊び混じりのいじめが、次第に集団化し、本人は身動きできなくなる。また、クラス替えで、Aの現状を知らない子もいるはずなのに、5年生でも3,4年生と同じ孤立状態で最下位に位置してしまう。中学ではもっと知らない子がたくさん居るはずなのに、すぐに孤立してしまう。周りの子は、意味もなくみんなと同じ行動をしてしまいます。いじめが持つ、集団現象の恐ろしさです。
? 小学校で全員が体験済み?
自分が、Aに対して嫌悪感を体験したわけでもないのに、5年生の時も、中学入学後も、子供達はみんな周りの子と同じように行動しています。なぜ、みんな同じ行動をするのでしょうか。それは、こうした子に対して、どう対応するのか、子供達全員がすでに小学校で経験ているからではないでしょうか。つまり、Aのような事件は、どこの学校でも発生し、子供達にとっては身近な問題なのだと考えられます。
小学校で学んだ経験から、こうした子に近づかないことが懸命な手段であると判断し、行動します。自分がこうした立場になったと感じられたときには、非常な恐怖心からすぐに不登校になる子も居ます。いじめ、からかいはだれかれとなくその子に集中します。それがどんどんエスカレートします。「あの子にはそうしていいんだ」と経験上思う子が多いからです。悲惨な状態がちょっとしたきっかけから生まれてしまいます。
学校には、30人に1,2名、少なくとも60人に1名は、Aのような立場の子が発生しているように感じます。この数は、実は大変な数で深刻な問題なのです。
? いじめは教師や大人には見えない
小学校3,4年生の担任は、全くいじめを認識できませんでした。放課になって一人教室に残っている子を見て、担任はそこから何が見えるたしょうか。何も、見えなかったのです。
また、5,6年生の担任も、生活アンケートでようやくいじめられていることを知りました。しかし、いじめの真の姿が見えていなかったため、子供の世界でできあがった子供にとっては無視できない構造を壊すことが出来ず、孤立状態はすぐに戻ってしまい、Aを救い出すことはできませんでした。
45名いる学校職員も、卒業まで続いたバイ菌遊びを一度も目撃することは出来ませんでした。子供達がキャアキャア大騒ぎして追いかけっこをしているのは見たかもしれませんが、バイ菌遊びとは想像だにできなかったのでしょう。でも、子供達は追いかけっこの意味を知っているのす。そこで、アンケートの具体的な質問に、数人の子が「Aは、ばい菌遊びをされている。きもいと言われている」と、答えることができたのです。
集団を観察できない保護者は、自分の子供の今までと違った様子から「いじめられているようだ」とは感じながら、どのようにいじめられているか、具体的にはとらえることができなかったのは当然です。訴えは具体性を欠き、担任には被害妄想としか受け取ってもらえなかったのです。
? 担任の働きかけ→子供集団の構造が揺らぐとき
5,6年の担任が「Aとも遊ぶように」と働きかけることで、子供集団の動きが何度も一部崩れています。いつもは、子供達は、自分たちが作り上げた構造の中で、自分たちが常識と考える行動(無視や仲間外れ等)を、何の疑念も持たずに行動しているのでしょう。
しかし、教師の働きかけで、すぐにAに働きかける子、遊ぶ子が存在する事実。また、学校集団の中では動けない子供も、家に帰ってから「(みんなに)分からなければいいよね。」と遊ぶ子どもがいる事実から、子供達全員がAに嫌悪感を持っているわけではないことが分かります。
しかし、せっかくのこうした子供の動きも、嫌悪感を抱いている他の子からの働きかけで、再び元に戻ってしまうのでしょう。「あんな子と遊ばないほうがいいよ」と耳打ちされれば、子供は恐怖心を感じるのではないでしょうか。しかし、根本的な解決にはなりませんが、教師の働きかけは、結構、子供達に大きな力を発揮することが分かります。
? 深く傷つくいじめられっ子
子供は、よくぞこんなに長く耐えるものだと驚嘆します。しかし、その子の心のキズの深さは、測り知れないものがあります。Aの将来を考えると暗澹たる気持ちになりますが、これについては、【弊害】の項で詳しく扱っておりますのでご覧ください。
? 子供はいじめが自覚できない
子供はなぜ、訴えないのでしょうか。本人も、いじめられていることは当然感じていると思いますが、それ程強くは訴えないようです。
「ウザイ、と言われた。」と訴えられた担任は、どうするでしょう。たぶん、「人が傷つくことを言ったりしたりしてはいけません。あやまっておいで。」ではないでしょうか。
「ウザイ」と言った子は無意識ないじめの構図の中で行動しているので、根本的な解決にならず、「あの子へのいたずらは、先生に叱られるからやめるけど」と、また違うターゲットを見つけ繰り返されることがあります。いじめの構図の中で行動していることの非を担任は学ばせることができないからです。「人にされていやなことは自分もするな」と言うような、まとまった抽象的な言葉だけでは子供はよく分からないのです。「あの子を、こうしたことをしてもいい子だとバカにしていない?」等、いじめとしての認識から発生していることを指摘しなくては、いじめの構造は壊れません。
また、違う子がその子をいじめます。何度もそれが繰り返される内に、いじめられる子は(訴えても無駄)とあきらめてしまうのではないでしょうか。
では、周りにいる子はなぜ担任に知らせないのでしょう。これは、いじめの構造が長い時間かかって作られるため、「いつの間にかこうなっている」という状態で、その子にやられていることを異常とも、いじめとも認識できず、普通のことと、受け入れてしまうからではないでしょうか。
生活アンケートに、具体的に質問され「ああ、そういえば、この質問はあの子に当てはまるな」ということで回答しているように感じます。しかし、それも全員ではなく、一部の子しか答えていません。
いじめられる子にとっては、こうした現状はとても苦しいものなのですが、周りの子にとっては「たいした問題ではない」と感じているふしがあります。子供達は言われなければ、自分たちの作り出した世界の異常性、病的な部分に気づかず、それを分析する力はない、と感じられます。
そこで、こうした無意識に対して、教師が「あなた達の考えていること、おかしくない?やっていること、変じゃない?」と子供に問いかけ、子供が持っている無意識のいじめの構造を意識化し壊す必要があるのです。
ただし、自覚していじめていることもあるのですが、それが長期化すると、自覚できないいじめに移行してしまうこともあります。「こんなのいつものことじゃん。」となってエスカレートします。それが、無知なる未熟な子供の世界の怖さです。
? いじめはなぜ解決しない?
また、せっかく遊びだしたのに、なぜ、すぐに孤立状態になってしまうのでしょうか。 そ れは、先生という、子供にとっては非常に偉大な力を持った人の働きかけよりも、なお、子ども達が長い間かけて作り出したいじめの構図の世界の方が勝っているからではないでしょうか。
Aを集団の最下位と見なす意識は、Aに対する嫌悪感を生みます。嫌悪感は全員が持っているわけでは無いのに、嫌悪感を持たない子をも飲み込んでしまうほど、強大だと言えます。小学校の高学年や中学で、いじめの解決が難しいと感じる先生は多いようです。それは、何年もかかって作られた強固ないじめの構造を壊すこと、つまり子供の認識を変えることが、いかに難しいかを示しているのではないでしょうか。 【いじめの発生と諸問題】参照
★ママリンコメント★
虐める子は勿論悪いですが
虐める子が怖くて同調する子がいるのが大きく問題な気がします。
虐められてる子を感じたら、虐められている対象が自分でなくとも
先生、親に相談して貰いたいです。
親の間で話題になるのも必要かと思います。
|
|
|
|
コメント(12)
http://www.ijime110.com/001/post-1.html
陰湿な現代の「いじめ」
最近の「いじめ」は、
なかなか手のこんだものが多いんです。
昔は、それこそすぐに手を出してきていましたから、
生徒の身体に痣があったり、服が傷んでいたりして
気づくケースがよくありました。
ですが、今は違います。
もちろん、暴力による「いじめ」、
そして言葉による「いじめ」もまだまだ存在しますが、
今はより手がこんでいます。
まず陰湿なのは、インターネットを使ったもの。
今はネット社会。
子供も小さな頃から携帯を持つ子が増えました。
携帯を持つということは、
簡単にネットに繋ぐことのできる環境にいるということです。
ネットを使って「いじめ」の代表的なものは、
いわゆる学校裏サイトなどで特定の生徒の悪口を
ひたすら書き綴ったりするものです。
酷いものだと、
「あの子は男にだらしないから、すぐに誰にでもOKだよ。
電話かけてあげて。電話番号はこちら...」
とか、こんな卑劣なものまであるのです。
こんな噂を流されると、一人で帰るのが大変危険になります。
その噂を真に受けた男性が、
悪口を書かれた女子生徒に暴行してしまうかもしれません。
冗談ではなくて、本当にあり得るのが現状なんです。
またこういった「いじめ」は表面に出難いですので、
なかなか暴露されません。
より陰湿で、より危険な「いじめ」が、
今ははびこっているのです。
陰湿な現代の「いじめ」
最近の「いじめ」は、
なかなか手のこんだものが多いんです。
昔は、それこそすぐに手を出してきていましたから、
生徒の身体に痣があったり、服が傷んでいたりして
気づくケースがよくありました。
ですが、今は違います。
もちろん、暴力による「いじめ」、
そして言葉による「いじめ」もまだまだ存在しますが、
今はより手がこんでいます。
まず陰湿なのは、インターネットを使ったもの。
今はネット社会。
子供も小さな頃から携帯を持つ子が増えました。
携帯を持つということは、
簡単にネットに繋ぐことのできる環境にいるということです。
ネットを使って「いじめ」の代表的なものは、
いわゆる学校裏サイトなどで特定の生徒の悪口を
ひたすら書き綴ったりするものです。
酷いものだと、
「あの子は男にだらしないから、すぐに誰にでもOKだよ。
電話かけてあげて。電話番号はこちら...」
とか、こんな卑劣なものまであるのです。
こんな噂を流されると、一人で帰るのが大変危険になります。
その噂を真に受けた男性が、
悪口を書かれた女子生徒に暴行してしまうかもしれません。
冗談ではなくて、本当にあり得るのが現状なんです。
またこういった「いじめ」は表面に出難いですので、
なかなか暴露されません。
より陰湿で、より危険な「いじめ」が、
今ははびこっているのです。
いじりが暴走する時
http://www.nhk.or.jp/tokkatsu/ijimezero/teacher/2013_003_02_shidou.html
NHK いじめをノックアウトより
番組を見ていて思い出しました。数年前のこと。大学生に「『いじり』っていじめでしょう?僕の少年、青年時代にはその言葉は友だち関係にはなかったよ」と聞くと、O君は「先生、それ、ちょっと違いますよ。いじりは、ほんの楽しみなんです」と答えました。するとY君は「そんなことはない、あれはやっぱりいじめです。こいつはすぐに俺をいじるんだから」と反論。「お前だって結構楽しそうだよ」「お前にはそう見えてるだけだよ。俺は合わせて笑っているけど、しょっちゅう言われると頭にくるんだから」。それを聞いていたF君が「まあまあ、仲良くやりましょう。ちょっとふざけて笑い合うくらい、いいやないですかあ」と言った調子でなだめ終わりました。この場合、いじられるY君は、いじるO君にはっきり「嫌だ」「頭にくる」と言えていますが、周りにいるF君が結局、事態を曖昧にしていじる側を支え、いじる・いじられる関係性を継続させています。10人以内のゼミにおける男子学生の会話です。60歳を超えた私には、学問を学ぶ学生にして何とも「軽すぎる」受け止めに不満でしたが、この言葉と人間関係の「軽さ」こそが大きな問題だと思います。
さて番組を観た後の話し合いや日常の指導のポイントを書きます。
絵本の中のようすけ君、自殺した真矢君に共通している「いじられ」は、友だちという対等な関係ではなく、勉強ができたり、運動能力が高かったり、腕力が強いという強者から、それらの要素の弱い弱者が苦役や一定の役を演じ(果たし)「続けさせられている」こと。それは、たまたまあった子ども特有のふざけ合いっこではないということです。弱者であるが故に集団内で一定の位置を得るために、外見上は「積極的に楽しんで」演じているのではないか?! との見方を番組終了後に、さらに自らの体験を掘り起こして話し合い、明らかにすることです。
高橋さんは「いじられるということは、人に笑われるということ、どこか自分を殺さなければいけないこと」と的確にまとめていますが、話し合いでは、それぞれの子どもが「言われるとなんで僕ばっかりと暗い気持ちになる」「心がちくちく痛くなる」など、「自分なりの言葉」で多様に表現することが大切になります。話し合いの冒頭か途中に、教師自身が自分史を見つめ直して、ある日ある時の「いじり・いじられ」体験を、リアルに感情豊かに込めて語ることを忘れてはならないでしょう。
軽い気持ちで始めたいじめ、いじり、からかい、ふざけ合いなどの多くは、する側が次第に慣れっこになり、エスカレートしていく(ひどくなっていく)ことを番組の中で紹介された「パンツを下ろす」「振り向きざまに頬をたたく」「馬乗りになり、床に顔を押しつける」などを確認し、「なぜ、このように次第にひどくエスカレートするのか」を自分の体験を掘り起こしながら話し合いをすることです。
番組では「暴走」という言葉を使っていますが、三、四年生ということで私は「エスカレート」と表現しました。
軽い気持ちがそのまま続く理由の一つは、最初「いじられキャラ」として級友の笑いを得たことが、人気者になったと喜ぶ、錯覚するといういじられ側の矛盾、問題点もあるでしょう。
(つづく)
http://www.nhk.or.jp/tokkatsu/ijimezero/teacher/2013_003_02_shidou.html
NHK いじめをノックアウトより
番組を見ていて思い出しました。数年前のこと。大学生に「『いじり』っていじめでしょう?僕の少年、青年時代にはその言葉は友だち関係にはなかったよ」と聞くと、O君は「先生、それ、ちょっと違いますよ。いじりは、ほんの楽しみなんです」と答えました。するとY君は「そんなことはない、あれはやっぱりいじめです。こいつはすぐに俺をいじるんだから」と反論。「お前だって結構楽しそうだよ」「お前にはそう見えてるだけだよ。俺は合わせて笑っているけど、しょっちゅう言われると頭にくるんだから」。それを聞いていたF君が「まあまあ、仲良くやりましょう。ちょっとふざけて笑い合うくらい、いいやないですかあ」と言った調子でなだめ終わりました。この場合、いじられるY君は、いじるO君にはっきり「嫌だ」「頭にくる」と言えていますが、周りにいるF君が結局、事態を曖昧にしていじる側を支え、いじる・いじられる関係性を継続させています。10人以内のゼミにおける男子学生の会話です。60歳を超えた私には、学問を学ぶ学生にして何とも「軽すぎる」受け止めに不満でしたが、この言葉と人間関係の「軽さ」こそが大きな問題だと思います。
さて番組を観た後の話し合いや日常の指導のポイントを書きます。
絵本の中のようすけ君、自殺した真矢君に共通している「いじられ」は、友だちという対等な関係ではなく、勉強ができたり、運動能力が高かったり、腕力が強いという強者から、それらの要素の弱い弱者が苦役や一定の役を演じ(果たし)「続けさせられている」こと。それは、たまたまあった子ども特有のふざけ合いっこではないということです。弱者であるが故に集団内で一定の位置を得るために、外見上は「積極的に楽しんで」演じているのではないか?! との見方を番組終了後に、さらに自らの体験を掘り起こして話し合い、明らかにすることです。
高橋さんは「いじられるということは、人に笑われるということ、どこか自分を殺さなければいけないこと」と的確にまとめていますが、話し合いでは、それぞれの子どもが「言われるとなんで僕ばっかりと暗い気持ちになる」「心がちくちく痛くなる」など、「自分なりの言葉」で多様に表現することが大切になります。話し合いの冒頭か途中に、教師自身が自分史を見つめ直して、ある日ある時の「いじり・いじられ」体験を、リアルに感情豊かに込めて語ることを忘れてはならないでしょう。
軽い気持ちで始めたいじめ、いじり、からかい、ふざけ合いなどの多くは、する側が次第に慣れっこになり、エスカレートしていく(ひどくなっていく)ことを番組の中で紹介された「パンツを下ろす」「振り向きざまに頬をたたく」「馬乗りになり、床に顔を押しつける」などを確認し、「なぜ、このように次第にひどくエスカレートするのか」を自分の体験を掘り起こしながら話し合いをすることです。
番組では「暴走」という言葉を使っていますが、三、四年生ということで私は「エスカレート」と表現しました。
軽い気持ちがそのまま続く理由の一つは、最初「いじられキャラ」として級友の笑いを得たことが、人気者になったと喜ぶ、錯覚するといういじられ側の矛盾、問題点もあるでしょう。
(つづく)
(つづき) 高橋さんのいじられる側への「やっぱり言わなくては。言葉にしないと周りは分からない」「自分ができないことはやらない」、いじる側への「興を取るなら自分でやれ!」というやや強いメッセージをどう受けとめるか、です。当然のメッセージですが、むしろ「言葉にしないでも、周りで気づいている人がいるはずだ。教師はその言葉無き、身体や生き様で表していることばを受け止めろ!」「本人も周りも言葉にできるような学級にしろ!」ではないでしょうか。
事実、後の調査によって「『いじりが激しくて心配』とクラスの女子生徒が担任に訴えたこともあった」と判明しています。また、「一方で、仲の良かった友人には『まじ痛い』と愚痴をこぼし、『いつかちゃんと注意しなきゃ』と話していた」というのです。さらに、命を絶つ一カ月前、いじる者の教科書をカッターナイフで切り裂くという事件を起こしていたが、担任は電話で親に弁償要求をして、彼のSOS、怒りの強さを見過ごしていたのです。(詳細は『大津中2いじめ自殺』共同通信大阪社会部、PHP新書の第三章を参照)
このコメントは教師向けだからこそ、私は、教師なら今日のいじめ問題について学習を深め、何らかのかたちで必ず発しているSOSを読み取れるようにして欲しいと訴えたいのです。
番組後の話し合いでは、「やっぱり言わなくては!そうだよねえ。言ってほしいよね。どうしたらボク、私は言えるようになるのだろう!」をぜひテーマにして頂きたいものです。
今回、真矢さんの自殺(自死)が取り上げられています。私は当然だと考えています。たとえば、国語の教科書に掲載されている文学作品「スイミー」(二年)「ちーちゃんのかげおくり」(三年)「ごんぎつね」(四年)には、非常に重要な意味で「死」が描かれています。学んでいるのです。子どもの日常には当然「死」との出会いがあります。教師だけが「死」を特別視しているように私には思えます。
「真矢君が生きていたら、そして私たちがこれから生きていけば、今現在とこれからどんな楽しいこと、素敵なことがあるだろうか?私たち、父母、祖父母たち、全部をよ〜く見て考えてごらん」と投げかけ、考え、ノートに書き、発表し、黒板いっぱいびっしりになるまでとことんやります。
生きるということは、それらを求めて、夢見て、多くの人の世話、支え、援助を受け、与えながら、自らと他者を輝かせて命を全うさせることなんだと深く理解することです。真矢君は、それらを捨て、死を選んだのではないのです。追い詰められ、それらを実現する希望を絶たれ、死へと追い詰められていったのです。教師の生きること、追い詰められた死(例えば、過労自殺死)への認識が問われます。そうしないと高橋さんの涙を流しながらの「悔しい、すごい辛い」という言葉、思いが受け止められないでしょう。
いじり(いじめ)、いじられて(いじめられて)楽しむというレベルの楽しみやストレス解消を、もっともっと高める必要があります。「学力向上」「規範意識(道徳)向上」が強調されてから、休み(自由遊び)時間や遠足・運動会・お楽しみ会等の【要求、自主自治、集団、相談、フェスティバル、感動】の要素を強く持った教科外活動が減少しました。「楽しさ」だけでなく、それぞれの個性を生かした活躍の場とそれぞれの新しい人間観がきらりと光って仲間に見えてくる機会が減ったのです。それぞれが様々な場で「興を取る」なら「いじられキャラ」は必要ではなくなります。高橋さんの「興を、笑いを取るなら、自分でやれ!」は、「それぞれ一人ひとりが、どこかでやろうぜ!」ではないでしょうか。まず、教師がそうした場を、活動を、評価を積極的に作ること、生み出すことが問われているのです。
事実、後の調査によって「『いじりが激しくて心配』とクラスの女子生徒が担任に訴えたこともあった」と判明しています。また、「一方で、仲の良かった友人には『まじ痛い』と愚痴をこぼし、『いつかちゃんと注意しなきゃ』と話していた」というのです。さらに、命を絶つ一カ月前、いじる者の教科書をカッターナイフで切り裂くという事件を起こしていたが、担任は電話で親に弁償要求をして、彼のSOS、怒りの強さを見過ごしていたのです。(詳細は『大津中2いじめ自殺』共同通信大阪社会部、PHP新書の第三章を参照)
このコメントは教師向けだからこそ、私は、教師なら今日のいじめ問題について学習を深め、何らかのかたちで必ず発しているSOSを読み取れるようにして欲しいと訴えたいのです。
番組後の話し合いでは、「やっぱり言わなくては!そうだよねえ。言ってほしいよね。どうしたらボク、私は言えるようになるのだろう!」をぜひテーマにして頂きたいものです。
今回、真矢さんの自殺(自死)が取り上げられています。私は当然だと考えています。たとえば、国語の教科書に掲載されている文学作品「スイミー」(二年)「ちーちゃんのかげおくり」(三年)「ごんぎつね」(四年)には、非常に重要な意味で「死」が描かれています。学んでいるのです。子どもの日常には当然「死」との出会いがあります。教師だけが「死」を特別視しているように私には思えます。
「真矢君が生きていたら、そして私たちがこれから生きていけば、今現在とこれからどんな楽しいこと、素敵なことがあるだろうか?私たち、父母、祖父母たち、全部をよ〜く見て考えてごらん」と投げかけ、考え、ノートに書き、発表し、黒板いっぱいびっしりになるまでとことんやります。
生きるということは、それらを求めて、夢見て、多くの人の世話、支え、援助を受け、与えながら、自らと他者を輝かせて命を全うさせることなんだと深く理解することです。真矢君は、それらを捨て、死を選んだのではないのです。追い詰められ、それらを実現する希望を絶たれ、死へと追い詰められていったのです。教師の生きること、追い詰められた死(例えば、過労自殺死)への認識が問われます。そうしないと高橋さんの涙を流しながらの「悔しい、すごい辛い」という言葉、思いが受け止められないでしょう。
いじり(いじめ)、いじられて(いじめられて)楽しむというレベルの楽しみやストレス解消を、もっともっと高める必要があります。「学力向上」「規範意識(道徳)向上」が強調されてから、休み(自由遊び)時間や遠足・運動会・お楽しみ会等の【要求、自主自治、集団、相談、フェスティバル、感動】の要素を強く持った教科外活動が減少しました。「楽しさ」だけでなく、それぞれの個性を生かした活躍の場とそれぞれの新しい人間観がきらりと光って仲間に見えてくる機会が減ったのです。それぞれが様々な場で「興を取る」なら「いじられキャラ」は必要ではなくなります。高橋さんの「興を、笑いを取るなら、自分でやれ!」は、「それぞれ一人ひとりが、どこかでやろうぜ!」ではないでしょうか。まず、教師がそうした場を、活動を、評価を積極的に作ること、生み出すことが問われているのです。
2学期が始まりますね。
いじめの勉強をしてると
休み明けは怖い時期であると思います。
一学期新しい友人が出来みんな様子見でそんなに暴れませんが
休み中とはラインやネット掲示板、メールなどで人の悪口を
回しあい 二学期は虐めが本格化する季節です。
最初の我慢があり、10月、11月頃に事件発覚が多くなります。
いじめの勉強をしてると気になる季節です。
集団であいつを無視しようぜとかやってる人達。
自分がいかに最低か自分を見直す事ができないのか?
第三者からみれば、恥ずかしいと思われる事を
集団で堂々とする真理
異常である。
異常者が多いと正常者が異常に立場が逆転される
集団心理とは恐ろしい。
いじめの勉強をしてると
休み明けは怖い時期であると思います。
一学期新しい友人が出来みんな様子見でそんなに暴れませんが
休み中とはラインやネット掲示板、メールなどで人の悪口を
回しあい 二学期は虐めが本格化する季節です。
最初の我慢があり、10月、11月頃に事件発覚が多くなります。
いじめの勉強をしてると気になる季節です。
集団であいつを無視しようぜとかやってる人達。
自分がいかに最低か自分を見直す事ができないのか?
第三者からみれば、恥ずかしいと思われる事を
集団で堂々とする真理
異常である。
異常者が多いと正常者が異常に立場が逆転される
集団心理とは恐ろしい。
http://www.izime.info/izime1/mysite1/sub2.html
昔と今のいじめの違い
昔と今のいじめの違いの一つに、「クラスのルールを決める権力」が「地域社会や先生から、一部の学生に移ったこと」があります。
昔は地域社会や先生が差別を認めない限り、いじめっ子はどんな手段をつかっても、クラスメイトの中で「いじめる側=悪者(問題児)」になっていました。
一部、地域社会自体が差別的にいじめを認めるところもありましたが、地域社会や先生が、学生の善悪の基準を決めていた時代だといえます。
今はクラスのルールや善悪観をクラスの中で決めることができます。
だから「いじめられている人が悪い」「いじめは遊び」などの考えも、本気で信じている人もいます。
「最近の若者は・・・」などと思うかもしれませんが、別に年齢は関係ありません。
歴史の中では、このようなことは多数存在します。
戦時中は、戦争を反対する人を非国民だと迫害やいじめをしていました。
「戦争を反対する人が悪い」「粛清(しゅくせい)は正義」などの考えを、本気で信じている人もいたのです。
これは国という大きな社会で起きたことですが、今はクラスという小さな社会で同じようなことが起きています。
これから「最近のいじめと昔のいじめ」を架空の世界で再現していき、それらの「違い」と「問題」を見ていきましょう。
昔と今のいじめの違い
昔と今のいじめの違いの一つに、「クラスのルールを決める権力」が「地域社会や先生から、一部の学生に移ったこと」があります。
昔は地域社会や先生が差別を認めない限り、いじめっ子はどんな手段をつかっても、クラスメイトの中で「いじめる側=悪者(問題児)」になっていました。
一部、地域社会自体が差別的にいじめを認めるところもありましたが、地域社会や先生が、学生の善悪の基準を決めていた時代だといえます。
今はクラスのルールや善悪観をクラスの中で決めることができます。
だから「いじめられている人が悪い」「いじめは遊び」などの考えも、本気で信じている人もいます。
「最近の若者は・・・」などと思うかもしれませんが、別に年齢は関係ありません。
歴史の中では、このようなことは多数存在します。
戦時中は、戦争を反対する人を非国民だと迫害やいじめをしていました。
「戦争を反対する人が悪い」「粛清(しゅくせい)は正義」などの考えを、本気で信じている人もいたのです。
これは国という大きな社会で起きたことですが、今はクラスという小さな社会で同じようなことが起きています。
これから「最近のいじめと昔のいじめ」を架空の世界で再現していき、それらの「違い」と「問題」を見ていきましょう。
<問題行動>「中学と同じことが起きる」小学校教員の悲鳴
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=voice&id=3099327
文科省の13年度問題行動調査で、荒れる小学生の増加が明らかになった。「中学校と同じことが起きている」。小学校教員からは悲鳴が上がり、専門家は「荒れの背景には貧困など社会のひずみが子供のストレスとなって表面化している」と指摘。学校や行政は対応に追われている。
「精神的に不安定で感情を抑えられない児童が目立つ」。大阪市立小のベテラン男性教諭(60)は現状をそう明かす。反抗的な態度を見せ、ささいなことで教室を飛び出したり、突然壁を殴ったり。広島県の市立小校長は「調査統計には含まれないが『言葉の暴力』も目立つ」と嘆く。教員とすれ違いざまに「うざい」「死ね」と暴言を吐く児童が珍しくない。東京都の区立小校長も「注意すると、かみついたり、いすを投げたりする。過度な指導は『体罰』になりかねず先生も遠慮がち。それが暴力行為を助長させている面もある」と対応に悩む。
自治体は対応に乗り出してはいる。熊本県教委は08年度に小中学校での暴力行為が前年度52件増の171件となったことを受け「子どもの居場所作り」を重視した対策を促進。異学年交流の活発化や教員が連携して生徒指導に当たる学校が増加した。13年度は135件に減り、県教委は「取り組みが浸透した結果」と説明する。福岡県教委は02年度から「非行要因」として不登校への対策を強化。担任とは別の教員によるマンツーマンの相談体制などに取り組む。
小中高校の暴力行為件数が13年度1万187件と、4年連続で全国1位だった大阪府。大阪市教委は来春から、在籍校とは別の施設に特別教室「個別指導教室(仮称)」を設置し、問題行動を起こした生徒を厳格に指導する方針だ。
重い傷害や薬物所持、強盗などを起こしたケースが対象。出席停止にした上で、専門スタッフが警察などと連携して指導する。市教委は「あくまで出席停止措置の受け皿。排除ではない」と説明するが、教員からは「邪魔者扱いと受け取られ、逆に傷つける」「規範意識は集団生活の中で身につく」と疑問の声も上がる。
荒れる児童について、元小学校教員の増田修治・白梅学園大教授(臨床教育学)は「ストレスを抱える子が確実に増えている」と指摘。一因として家庭要因を挙げる。経済的困窮で子を構えなかったり、思い通りの進路を歩ませようとしたりする親も目立つという。学校も受け止める余裕がない。小学校は障害を抱え特別支援が必要な児童も増え、新たな指導方法も求められる。全国学力テストで学校間競争にもさらされる。
増田教授は「問題行動を起こす子どもは親からも先生からも認めてもらえず自己肯定感が低い子が少なくない。社会全体の問題としてとらえ対策を取る必要がある」と話している。【寺岡俊、松田栄二郎、関東晋慈、三木陽介】
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
★いじめの弊害の恐ろしさ ★ 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-