|
|
|
|
コメント(11)
日本の左派はいつから「リベラル」になったのか?(佐々木俊尚)2016/08/17
以下はわたしの近著『21世紀の自由論〜優しいリアリズムの時代へ』(NHK出版)からの抜粋です。同書は日本の「リベラル」と呼ばれている勢力の問題点と、そこからどう脱却して日本人であるわたしたちが新たな政治哲学を構築していくことが可能かを論じているのですが、「リベラル」ということばの誤用がどこから始まったのかを以下の抜粋では指摘しています。
補足しておくと、日本ではもともとリベラルには二つの意味がありました。まず第一に、「オールドリベラリスト」と呼ばれた人たち。これは戦前、欧米滞在経験があり、欧米リベラリズムの洗礼を受け、親米的・親英的な立ち位置に基づいていた人たちのことを指します。よりわかりやすく言えば、大正デモクラシーの体現者。
第二に、アメリカのリベラル。端的に言えば、民主党のことです。日本の新聞では一九八〇年代まで、「リベラル」とはおもに米民主党のことを指し、日本国内の政治勢力に対してはこの言葉は使われていませんでした。
というところで、以下は『21世紀の自由論』からの引用です。
---------------
最大の問題は、彼らが知的な人たちに見えて、実は根本の部分に政治哲学を持っていないことだ。端的にいえば、日本の「リベラル」はリベラリズムのような欧米の政治哲学とはほとんど何の関係もない。彼らの拠って立つのは、ただ「反権力」という立ち位置のみである。
思想ではなく、立ち位置。
そもそも彼らは、もともとは「リベラル」とは呼ばれていなかったし、みずからも名乗っていなかった。戦後メディア史の流れの中で言えば、一九五五年から九〇年代初頭までの昭和の時代、この勢力が名乗っていたのは「革新」だった。「進歩派」という呼び方もあった。保守と革新、保守系文化人と進歩派文化人。
冷戦の時代に資本主義陣営と共産主義陣営があり、日本では前者を自民党と官僚、財界が体現し、後者を社会党や共産党などの革新政党が担っていると考えられていた。つまりは資本主義的な体制に対するアンチテーゼとしての革新、進歩派だったのだ。
このころはリベラルという単語はおもに米国の民主党勢力を指すものとして使われていただけで、日本国内の政治勢力にリベラルという冠をつけた事例は、当時の新聞記事を調べても非常に少ない。一九九一年の朝日新聞には、「リベラル(進歩的)」とカギカッコで説明が加えられている。例外として、保守自民党の中でも比較的自由で進歩的な意見を持つ政治家が、「保守リベラル」と呼ばれていたケースがあるだけだ。たとえば河野洋平氏がそうだ。ロッキード事件のときに自民党を離れて新自由クラブを結成した河野氏や田川誠一氏、西岡武夫氏などが保守リベラルのポジションだった。
それがなぜかリベラルに変わったのか。答は明快だ。一九九〇年代になって冷戦が終わり、共産主義の失敗が明らかになり、共産主義陣営を指す革新や進歩派ということばが使いにくくなったからである。それで代替用語として、進歩的なイメージがある「リベラル」が転用されるようになったのだ。
リベラルが日本の政治で最初に公然と使われたのは、社会党の故山花貞雄氏が一九九五年、離党して新しい政治勢力を結成しようと「民主リベラル新党準備会」という名前の組織をつくったところからである。しかし山花氏の「リベラル新党」は結成予定のその日に阪神・淡路大震災が起きて頓挫して終わった。
以降、革新や進歩派は「リベラル」と名称替えして、いまにいたる。しかしその勢力は、かつての反自民党・反資本主義の立ち位置だったころとほとんど変化しておらず、政治哲学ではない「反権力」という立ち位置にのみ依拠している。
なぜこのような勢力が、日本の政治やマスメディアの中で大きな影響力を持つようになったのだろうか。
[続く]
以下はわたしの近著『21世紀の自由論〜優しいリアリズムの時代へ』(NHK出版)からの抜粋です。同書は日本の「リベラル」と呼ばれている勢力の問題点と、そこからどう脱却して日本人であるわたしたちが新たな政治哲学を構築していくことが可能かを論じているのですが、「リベラル」ということばの誤用がどこから始まったのかを以下の抜粋では指摘しています。
補足しておくと、日本ではもともとリベラルには二つの意味がありました。まず第一に、「オールドリベラリスト」と呼ばれた人たち。これは戦前、欧米滞在経験があり、欧米リベラリズムの洗礼を受け、親米的・親英的な立ち位置に基づいていた人たちのことを指します。よりわかりやすく言えば、大正デモクラシーの体現者。
第二に、アメリカのリベラル。端的に言えば、民主党のことです。日本の新聞では一九八〇年代まで、「リベラル」とはおもに米民主党のことを指し、日本国内の政治勢力に対してはこの言葉は使われていませんでした。
というところで、以下は『21世紀の自由論』からの引用です。
---------------
最大の問題は、彼らが知的な人たちに見えて、実は根本の部分に政治哲学を持っていないことだ。端的にいえば、日本の「リベラル」はリベラリズムのような欧米の政治哲学とはほとんど何の関係もない。彼らの拠って立つのは、ただ「反権力」という立ち位置のみである。
思想ではなく、立ち位置。
そもそも彼らは、もともとは「リベラル」とは呼ばれていなかったし、みずからも名乗っていなかった。戦後メディア史の流れの中で言えば、一九五五年から九〇年代初頭までの昭和の時代、この勢力が名乗っていたのは「革新」だった。「進歩派」という呼び方もあった。保守と革新、保守系文化人と進歩派文化人。
冷戦の時代に資本主義陣営と共産主義陣営があり、日本では前者を自民党と官僚、財界が体現し、後者を社会党や共産党などの革新政党が担っていると考えられていた。つまりは資本主義的な体制に対するアンチテーゼとしての革新、進歩派だったのだ。
このころはリベラルという単語はおもに米国の民主党勢力を指すものとして使われていただけで、日本国内の政治勢力にリベラルという冠をつけた事例は、当時の新聞記事を調べても非常に少ない。一九九一年の朝日新聞には、「リベラル(進歩的)」とカギカッコで説明が加えられている。例外として、保守自民党の中でも比較的自由で進歩的な意見を持つ政治家が、「保守リベラル」と呼ばれていたケースがあるだけだ。たとえば河野洋平氏がそうだ。ロッキード事件のときに自民党を離れて新自由クラブを結成した河野氏や田川誠一氏、西岡武夫氏などが保守リベラルのポジションだった。
それがなぜかリベラルに変わったのか。答は明快だ。一九九〇年代になって冷戦が終わり、共産主義の失敗が明らかになり、共産主義陣営を指す革新や進歩派ということばが使いにくくなったからである。それで代替用語として、進歩的なイメージがある「リベラル」が転用されるようになったのだ。
リベラルが日本の政治で最初に公然と使われたのは、社会党の故山花貞雄氏が一九九五年、離党して新しい政治勢力を結成しようと「民主リベラル新党準備会」という名前の組織をつくったところからである。しかし山花氏の「リベラル新党」は結成予定のその日に阪神・淡路大震災が起きて頓挫して終わった。
以降、革新や進歩派は「リベラル」と名称替えして、いまにいたる。しかしその勢力は、かつての反自民党・反資本主義の立ち位置だったころとほとんど変化しておらず、政治哲学ではない「反権力」という立ち位置にのみ依拠している。
なぜこのような勢力が、日本の政治やマスメディアの中で大きな影響力を持つようになったのだろうか。
[続く]
>>[2] の続き
後ほどくわしく説明するけれども、最初にわかりやすく見渡しておこう。これは日本の戦後メディア史に原因がある。一九五五年に保守合同があって自民党が成立し、「自民党の一党支配と万年野党の社会党」という体制がスタートした。このころから高度経済成長で日本は豊かになり、一九七〇年代には日本人の九割が「自分は中流」と認識する総中流社会が完成した。冷戦の時代、日本は米国の核の傘で安全保障は安定し、経済成長でだんだんと豊かになることを実感できた。
総中流の構造に、メディア空間も引きずられた。安定している社会を支えているのは、自民党であり、財界であり、官僚である。つまり官僚と企業と政府自民党という三位一体が日本の総中流社会を支えるという堅固な基盤があり、そこでメディアの側が何ができるかというと、「反権力」という監視役としての役割でしかなかった。
権力に対抗するメディアと、メディアが代弁する「市民」は自由と平等の擁護者であり、政府と財界のつくる安定的な基盤を批判するアウトサイダーの視点を持った人たちであるという「反権力」である。強者対弱者というような、非常にわかりやすい水戸黄門的な勧善懲悪の構図が色濃く抽出されていた。
しかし政治的・思想的な対立軸がこのような安易な勧善懲悪では、有効な議論はできない。なぜなら勧善懲悪では、市民やメディアが一方的な善になってしまい、しかしその善であるという思想的な背景は何もないからだ。単に反権力であるということでしか担保されていないのである。では反権力の側が政権を握り、責任を負ったらどうなるのか?ということは誰も考えなかった。誰も考えなかったうちに時代が過ぎて自民党がいったん瓦解してしまい、うっかり反権力が政権をとってしまって何もないことが露呈してしまったのが、二〇〇九年の民主党政権だったといえるだろう。
政治思想の対立軸としては、ヨーロッパやアメリカでは完全自由主義(リバタニアリズム)、積極的自由主義(ニューリベラリズム)、コミュニタリアニズム(共同体主義)、コンサバティズム(保守主義)がある。さらにそこから派生し、民主主義を世界に広めていこうと考える新保守主義(ネオコバサティブ、略称ネオコン)がある。リバタニアリズムは最近は新自由主義(ネオリベラリズム、通称ネオリベ)とも呼ばれている。
しかしこうした政治思想のマトリックスは、日本の政治やメディアの現場にはついに導入されることはなかった。さまざまな要素がからんでいるが、ひとつの理由として言われているのは、自民党と官僚がリベラリズム的な分配政策も、リバタニアリズム的な自由な経済活動の推進も、両面でうまく進めていたということだ。この結果、自民党に対抗する社会党や新聞、テレビは有効な対立軸をつくることができず、ただ反対するだけの「反権力」に墜してしまったのだ。そしてメディア空間は、ますます水戸黄門的な勧善懲悪の構図に流れ込んでいった。
それでも経済成長がつづいているあいだは、この構図の問題点が浮上してくることはそれほどなかった。昭和のころ、「経済一流、政治二流」という言葉があった。私はここに「メディア二流」も加えて良いのではないかと思うが、経済成長のエンジンがきちんと駆動していれば、さまざまな問題が起きても不満はさほど起きない。メディアがエンターテインメント的に水戸黄門をやっていても、特に障害にはならなかったのではないかと考えている。
しかし反権力は思想ではなく、単なる立ち位置である。反権力ではない、独自の政治哲学を生み出せなかったところに、日本の「リベラル」の不幸があったといえるだろう。そして二十一世紀になってグローバル化と格差化の波に翻弄される日本社会では、「反権力」でしかない立ち位置は、完全に有効性を失っている。
(以上、引用終わり。なお『21世紀の自由論』はKindle Unlimitedの読み放題サービスでも読めますので、ぜひご一読ください)
http://www.pressa.jp/blog/i/2016/08/post-24.html
佐々木 俊尚(ささき としなお、1961年12月5日 - )は、日本のジャーナリスト・評論家。
妻はイラストレーターの松尾たいこ。
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E4%BF%8A%E5%B0%9A
後ほどくわしく説明するけれども、最初にわかりやすく見渡しておこう。これは日本の戦後メディア史に原因がある。一九五五年に保守合同があって自民党が成立し、「自民党の一党支配と万年野党の社会党」という体制がスタートした。このころから高度経済成長で日本は豊かになり、一九七〇年代には日本人の九割が「自分は中流」と認識する総中流社会が完成した。冷戦の時代、日本は米国の核の傘で安全保障は安定し、経済成長でだんだんと豊かになることを実感できた。
総中流の構造に、メディア空間も引きずられた。安定している社会を支えているのは、自民党であり、財界であり、官僚である。つまり官僚と企業と政府自民党という三位一体が日本の総中流社会を支えるという堅固な基盤があり、そこでメディアの側が何ができるかというと、「反権力」という監視役としての役割でしかなかった。
権力に対抗するメディアと、メディアが代弁する「市民」は自由と平等の擁護者であり、政府と財界のつくる安定的な基盤を批判するアウトサイダーの視点を持った人たちであるという「反権力」である。強者対弱者というような、非常にわかりやすい水戸黄門的な勧善懲悪の構図が色濃く抽出されていた。
しかし政治的・思想的な対立軸がこのような安易な勧善懲悪では、有効な議論はできない。なぜなら勧善懲悪では、市民やメディアが一方的な善になってしまい、しかしその善であるという思想的な背景は何もないからだ。単に反権力であるということでしか担保されていないのである。では反権力の側が政権を握り、責任を負ったらどうなるのか?ということは誰も考えなかった。誰も考えなかったうちに時代が過ぎて自民党がいったん瓦解してしまい、うっかり反権力が政権をとってしまって何もないことが露呈してしまったのが、二〇〇九年の民主党政権だったといえるだろう。
政治思想の対立軸としては、ヨーロッパやアメリカでは完全自由主義(リバタニアリズム)、積極的自由主義(ニューリベラリズム)、コミュニタリアニズム(共同体主義)、コンサバティズム(保守主義)がある。さらにそこから派生し、民主主義を世界に広めていこうと考える新保守主義(ネオコバサティブ、略称ネオコン)がある。リバタニアリズムは最近は新自由主義(ネオリベラリズム、通称ネオリベ)とも呼ばれている。
しかしこうした政治思想のマトリックスは、日本の政治やメディアの現場にはついに導入されることはなかった。さまざまな要素がからんでいるが、ひとつの理由として言われているのは、自民党と官僚がリベラリズム的な分配政策も、リバタニアリズム的な自由な経済活動の推進も、両面でうまく進めていたということだ。この結果、自民党に対抗する社会党や新聞、テレビは有効な対立軸をつくることができず、ただ反対するだけの「反権力」に墜してしまったのだ。そしてメディア空間は、ますます水戸黄門的な勧善懲悪の構図に流れ込んでいった。
それでも経済成長がつづいているあいだは、この構図の問題点が浮上してくることはそれほどなかった。昭和のころ、「経済一流、政治二流」という言葉があった。私はここに「メディア二流」も加えて良いのではないかと思うが、経済成長のエンジンがきちんと駆動していれば、さまざまな問題が起きても不満はさほど起きない。メディアがエンターテインメント的に水戸黄門をやっていても、特に障害にはならなかったのではないかと考えている。
しかし反権力は思想ではなく、単なる立ち位置である。反権力ではない、独自の政治哲学を生み出せなかったところに、日本の「リベラル」の不幸があったといえるだろう。そして二十一世紀になってグローバル化と格差化の波に翻弄される日本社会では、「反権力」でしかない立ち位置は、完全に有効性を失っている。
(以上、引用終わり。なお『21世紀の自由論』はKindle Unlimitedの読み放題サービスでも読めますので、ぜひご一読ください)
http://www.pressa.jp/blog/i/2016/08/post-24.html
佐々木 俊尚(ささき としなお、1961年12月5日 - )は、日本のジャーナリスト・評論家。
妻はイラストレーターの松尾たいこ。
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E4%BF%8A%E5%B0%9A
「リベラル」の逆は「保守」ではない?(中島岳志)
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20171020-00077161/
>「リベラル」は、個人の内面の問題について国家が踏み込まないのが基本。その反対語は「保守」ではなく、「パターナル」です。権威主義ですね。個人の内面に直結する価値観の問題を「日本人ならば、こうあるべきだ」「この問題はこう考えなければならない」といったように、上から決めていく。(中島岳志)
リベラル ⇔ パターナル
革新 ⇔ 保守
中島 岳志(なかじま たけし、1975年2月16日 - )は、日本の政治学者、歴史学者。専門は南アジア地域研究、日本思想史。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E5%B2%B3%E5%BF%97
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20171020-00077161/
>「リベラル」は、個人の内面の問題について国家が踏み込まないのが基本。その反対語は「保守」ではなく、「パターナル」です。権威主義ですね。個人の内面に直結する価値観の問題を「日本人ならば、こうあるべきだ」「この問題はこう考えなければならない」といったように、上から決めていく。(中島岳志)
リベラル ⇔ パターナル
革新 ⇔ 保守
中島 岳志(なかじま たけし、1975年2月16日 - )は、日本の政治学者、歴史学者。専門は南アジア地域研究、日本思想史。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E5%B2%B3%E5%BF%97
宮台真司 × 小林よしのり × 萱野稔人「右翼も左翼も束になってかかってこい」2007/06/29
http://www.videonews.com/marugeki-talk/326/
#マル激 #ビデオニュース・ドットコム
「ワシの本をどう読んだら、『嫌韓流』に向かうのか。ワシは誤解されとるのよ」と勘違い右傾化を嘆く小林氏。
小林氏と同席しただけで「友人の何人かは口を聞いてくれなくなる」と悲壮な決意で参加した萱野氏。
2人のくせ者論客をどのように仕切るか、宮台真司の司会ぶりも要注目。
「今日は、右も左も切り刻むことになる」と宮台真司が不敵に笑ってスタートした鼎談は、小林氏の沖縄へのこだわりから始まり、右派左派の欺瞞から、ナショナリズムと格差社会へと、縦横無尽に広がっていった。
前半 https://youtu.be/CSChgiTudfA
後半 https://youtu.be/t-f2QChfYMY
http://www.videonews.com/marugeki-talk/326/
#マル激 #ビデオニュース・ドットコム
「ワシの本をどう読んだら、『嫌韓流』に向かうのか。ワシは誤解されとるのよ」と勘違い右傾化を嘆く小林氏。
小林氏と同席しただけで「友人の何人かは口を聞いてくれなくなる」と悲壮な決意で参加した萱野氏。
2人のくせ者論客をどのように仕切るか、宮台真司の司会ぶりも要注目。
「今日は、右も左も切り刻むことになる」と宮台真司が不敵に笑ってスタートした鼎談は、小林氏の沖縄へのこだわりから始まり、右派左派の欺瞞から、ナショナリズムと格差社会へと、縦横無尽に広がっていった。
前半 https://youtu.be/CSChgiTudfA
後半 https://youtu.be/t-f2QChfYMY
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
藤原肇 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
藤原肇のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90040人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6420人
- 3位
- 独り言
- 9045人
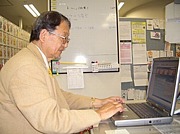
![[dir]右翼コミュ左翼コミュ統合](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/41/79/104179_147s.jpg)






















