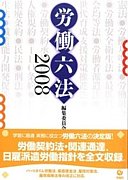はじめまして。
今回、トッピクを作成させてもらいます。
長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
「高年齢者等の雇用の安定などに関する法律」のことで非常に腑に落ちない出来事が今日あった。自分の仕事のプライドにかかわる問題なので、今、非常に悶々としている状況。
65歳未満の定年を定めている場合は、65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講じなければならない。
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
とある。大体は、継続雇用制度を導入する企業が多いはずだ。
うちの会社も(2)を導入することにしていた。
継続雇用制度を導入する場合、原則、希望者全員を対象とする制度を導入することが求められますよね?ただし、「事業主は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を設けることによって、対象者を限定することができる」と、記載されています(高年齢者雇用安定法9条2項)。労使協定を結ぶための協議をし、成立したら、労使協定書を交わすとともに、就業規則を改定し、労働基準監督署へ届け出なければならないですよね?
だが、しかし、これには経過措置がある(厚労省のパンフにも載っている。以下に表記↓)。
『継続雇用制度の書面協定については、事業主が労使協定を締結するために努力したにもかかわらず調わないときは、大企業の事業主は、平成21年3月31日まで、中小企業の事業主は平成23年3月31日までの間は、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できる』と(高年齢者雇用安定法附則5条、同法施行令附則4項〜7項)。
さて、ここから皆さんにお尋ねしたいことがあります。社労士の諸先輩方、同期の仲間、そして出来れば社労士受験生の仲間にもご協力お願いいたします。
私は条文の記載のされ方を見て、このように解釈していた。
(その2につづく)
『継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を設け、労使協定を結ぶ為の協議をしたら、協議は不成立に終わったとのこと。その事実を聞いた私は、高年齢者等の雇用の安定などに関する法律のセミナーや労務管理セミナー等に出席し、更に厚労省のパンフ及び労務管理を専門とされている弁護士の先生が書かれている本を読んで知識の再確認をした上で上司に提案した。労使協定を締結するために努力したにもかかわらず調わなかった場合は、時限措置で就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できるということを。パンフなどを証拠に上司に説明し、その証拠を提出した。上司は私の発言等を信用し、この時限措置を行使し、就業規則に基準を盛り込んだ。このこと事態はだいぶ前の話なのだが、晴天の霹靂となるべきとある出来事が今日発覚した。
昨日、上司がその就業規則を持って、顧問社労士を訪ねたらしい。
で、そこの顧問社労士はこのように言ったらしい。
『労使協定の協議が成立しなかったら、再雇用制度をするという選択肢を選んだのだから今年度定年退職をする人たち(当社は定年を引き上げず、60歳のままに固定しておいた)を再雇用しなければならないね』と。
それを上司から聞かされたとき、オイラ『 うそ〜〜〜???そんなはずないやろ〜???原則はそうだけど、時限措置があるやん。その顧問社労士、時限措置があることを知ってるのかなぁ?』 と、思った。そして半分、自分の考えに自信がなくなった。相手は、ずっと開業している社労士。オイラは、昨年度社労士試験に合格した身。上司は、完全に顧問社労士の発言を信じてしまっている。
オイラ、本格的に何かを読み違えてしまってるのかなぁ?慎重を期して、プロ意識を持って上司に発言しただけに、ものすごく顧問社労士の発言が解せない。
同時に、自信喪失。
みなさま、意見をお願いいたします。
今回、トッピクを作成させてもらいます。
長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
「高年齢者等の雇用の安定などに関する法律」のことで非常に腑に落ちない出来事が今日あった。自分の仕事のプライドにかかわる問題なので、今、非常に悶々としている状況。
65歳未満の定年を定めている場合は、65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講じなければならない。
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
とある。大体は、継続雇用制度を導入する企業が多いはずだ。
うちの会社も(2)を導入することにしていた。
継続雇用制度を導入する場合、原則、希望者全員を対象とする制度を導入することが求められますよね?ただし、「事業主は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を設けることによって、対象者を限定することができる」と、記載されています(高年齢者雇用安定法9条2項)。労使協定を結ぶための協議をし、成立したら、労使協定書を交わすとともに、就業規則を改定し、労働基準監督署へ届け出なければならないですよね?
だが、しかし、これには経過措置がある(厚労省のパンフにも載っている。以下に表記↓)。
『継続雇用制度の書面協定については、事業主が労使協定を締結するために努力したにもかかわらず調わないときは、大企業の事業主は、平成21年3月31日まで、中小企業の事業主は平成23年3月31日までの間は、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できる』と(高年齢者雇用安定法附則5条、同法施行令附則4項〜7項)。
さて、ここから皆さんにお尋ねしたいことがあります。社労士の諸先輩方、同期の仲間、そして出来れば社労士受験生の仲間にもご協力お願いいたします。
私は条文の記載のされ方を見て、このように解釈していた。
(その2につづく)
『継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を設け、労使協定を結ぶ為の協議をしたら、協議は不成立に終わったとのこと。その事実を聞いた私は、高年齢者等の雇用の安定などに関する法律のセミナーや労務管理セミナー等に出席し、更に厚労省のパンフ及び労務管理を専門とされている弁護士の先生が書かれている本を読んで知識の再確認をした上で上司に提案した。労使協定を締結するために努力したにもかかわらず調わなかった場合は、時限措置で就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できるということを。パンフなどを証拠に上司に説明し、その証拠を提出した。上司は私の発言等を信用し、この時限措置を行使し、就業規則に基準を盛り込んだ。このこと事態はだいぶ前の話なのだが、晴天の霹靂となるべきとある出来事が今日発覚した。
昨日、上司がその就業規則を持って、顧問社労士を訪ねたらしい。
で、そこの顧問社労士はこのように言ったらしい。
『労使協定の協議が成立しなかったら、再雇用制度をするという選択肢を選んだのだから今年度定年退職をする人たち(当社は定年を引き上げず、60歳のままに固定しておいた)を再雇用しなければならないね』と。
それを上司から聞かされたとき、オイラ『 うそ〜〜〜???そんなはずないやろ〜???原則はそうだけど、時限措置があるやん。その顧問社労士、時限措置があることを知ってるのかなぁ?』 と、思った。そして半分、自分の考えに自信がなくなった。相手は、ずっと開業している社労士。オイラは、昨年度社労士試験に合格した身。上司は、完全に顧問社労士の発言を信じてしまっている。
オイラ、本格的に何かを読み違えてしまってるのかなぁ?慎重を期して、プロ意識を持って上司に発言しただけに、ものすごく顧問社労士の発言が解せない。
同時に、自信喪失。
みなさま、意見をお願いいたします。
|
|
|
|
|
|
|
|
労働法研究会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
労働法研究会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人