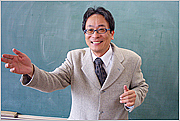「算数のある生活」で、いつの間にか算数ができるようになる。
算数ほど、できるできないがはっきりする教科はありません。
例えば、2年生の授業で、まだ九九を学んでいない子供たちに次のような問題が出されたとします。
「キャラメルを1人当たり3個ずつ配ります。5人の子供に配るとしたら、全部でキャラメルは何個になりますか? 」
すると、子供たちはいろいろな方法でこれを解こうとします。
未知の問題に出会ったとき、子供たちは既知の方法を駆使していろいろに考えるものです。
ある子は、積み木をキャラメルに見立てて、実際に数えてみます。
ある子は、一生懸命にキャラメルの絵を描いて数えます。
ある子は、3+3+3+3+3という式を考えだします。
中には、もう塾や家庭で教わったのか、3×5という式を書いて周りに教えてる子もいます。
ここで大切なのは、何とかして自分で答えを出そうとする意欲です。
ところが、この時、問題に対する子供たちの意欲には、かなりの差があります。
何とかして、答えを出そうとあれこれ試行錯誤して考える子もいます。
中には、どうしていいのか分からないで、何一つしない子もいます。
そういう子供たちは、まず、問題の場面のイメージが湧いてこないのです。
つまり、一体何が問題なのかが分からないのです。
では、なぜ分からないのでしょうか?
その理由は複合的なもので、それだけでも科学的研究の一分野になり得るものだと私は考えています。
ですが、一つの大きな原因として、次のことが考えられます。
それは、実際の生活の中で、このようなことを考えたことがないからです。
つまり、このような「数字を伴った思考を要する状況」に置かれたことがないのです。
言い換えれば、「算数のある生活」を送っていないのです。
もし、この授業を受ける前に、その子の生活の中で似たような場面があったとしたらどうでしょうか?
例えば、もし、これ以前に、親が「お隣でミニトマトをくれるって言うんだけど、1人3個食べるとして4人家族の我が家では、何個もらってくればいいのかな?」と子供に聞いたり一緒に考えたりする場面があったとしたら、この授業に臨む子供の意欲はかなり違ってきたはずです。
子供は親と一緒にこの興味深い問題に、じっくり取り組むことができます。
そして、実際にミニトマトを数えながら、この問題の解き方を理解していきます。
ついでに、親がかけ算について少し手ほどきをするといいと思います。
絶好の機会なのですから、何も学校でやるまで待つ必要などありません。
このような状況を、意図的に親が作り出すことが大切です。
これくらいのことは、ほんの少し心がけるだけで、ほんの少し「教育的配慮」をするだけでできるのです。
このような場面を実際に何回か経験している子は、学校の算数の時間に上記のような問題が出されたとき、とても意欲的に取り組みます。
「何だかやったことがあるな。できそうな気がする。」
こういう気持ちになれるのです。
ところが、それ以前に、このような場面に置かれたことがない子には、何をどうしていいのかさえ分からないのです。
こんな問題は大人には何でもないので、ちょっと考えれば誰でも解けそうに思えます。
ところが、生まれてから7,8年しか経っていない2年生の子供には、結構難しいのです。
ぜひ、「数字を伴った思考を要する状況」を意図的に作ってやってください。
「算数のある生活」を演出してやってください。
「教育的配慮」のある生活を作り出してやってください。
それは、学校で種を蒔く前の土作りなのです。
良い土ができていれば、蒔いた種は大きく育ちます。
良い土作り、それができるのは、親しかありません
算数ほど、できるできないがはっきりする教科はありません。
例えば、2年生の授業で、まだ九九を学んでいない子供たちに次のような問題が出されたとします。
「キャラメルを1人当たり3個ずつ配ります。5人の子供に配るとしたら、全部でキャラメルは何個になりますか? 」
すると、子供たちはいろいろな方法でこれを解こうとします。
未知の問題に出会ったとき、子供たちは既知の方法を駆使していろいろに考えるものです。
ある子は、積み木をキャラメルに見立てて、実際に数えてみます。
ある子は、一生懸命にキャラメルの絵を描いて数えます。
ある子は、3+3+3+3+3という式を考えだします。
中には、もう塾や家庭で教わったのか、3×5という式を書いて周りに教えてる子もいます。
ここで大切なのは、何とかして自分で答えを出そうとする意欲です。
ところが、この時、問題に対する子供たちの意欲には、かなりの差があります。
何とかして、答えを出そうとあれこれ試行錯誤して考える子もいます。
中には、どうしていいのか分からないで、何一つしない子もいます。
そういう子供たちは、まず、問題の場面のイメージが湧いてこないのです。
つまり、一体何が問題なのかが分からないのです。
では、なぜ分からないのでしょうか?
その理由は複合的なもので、それだけでも科学的研究の一分野になり得るものだと私は考えています。
ですが、一つの大きな原因として、次のことが考えられます。
それは、実際の生活の中で、このようなことを考えたことがないからです。
つまり、このような「数字を伴った思考を要する状況」に置かれたことがないのです。
言い換えれば、「算数のある生活」を送っていないのです。
もし、この授業を受ける前に、その子の生活の中で似たような場面があったとしたらどうでしょうか?
例えば、もし、これ以前に、親が「お隣でミニトマトをくれるって言うんだけど、1人3個食べるとして4人家族の我が家では、何個もらってくればいいのかな?」と子供に聞いたり一緒に考えたりする場面があったとしたら、この授業に臨む子供の意欲はかなり違ってきたはずです。
子供は親と一緒にこの興味深い問題に、じっくり取り組むことができます。
そして、実際にミニトマトを数えながら、この問題の解き方を理解していきます。
ついでに、親がかけ算について少し手ほどきをするといいと思います。
絶好の機会なのですから、何も学校でやるまで待つ必要などありません。
このような状況を、意図的に親が作り出すことが大切です。
これくらいのことは、ほんの少し心がけるだけで、ほんの少し「教育的配慮」をするだけでできるのです。
このような場面を実際に何回か経験している子は、学校の算数の時間に上記のような問題が出されたとき、とても意欲的に取り組みます。
「何だかやったことがあるな。できそうな気がする。」
こういう気持ちになれるのです。
ところが、それ以前に、このような場面に置かれたことがない子には、何をどうしていいのかさえ分からないのです。
こんな問題は大人には何でもないので、ちょっと考えれば誰でも解けそうに思えます。
ところが、生まれてから7,8年しか経っていない2年生の子供には、結構難しいのです。
ぜひ、「数字を伴った思考を要する状況」を意図的に作ってやってください。
「算数のある生活」を演出してやってください。
「教育的配慮」のある生活を作り出してやってください。
それは、学校で種を蒔く前の土作りなのです。
良い土ができていれば、蒔いた種は大きく育ちます。
良い土作り、それができるのは、親しかありません
|
|
|
|
|
|
|
|
ありがとう♪親野 智可等さん 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-