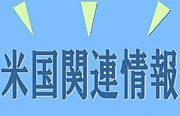日本は今、東日本大震災に伴って起きた原子力発電所の事故によって、深刻な電力不足に陥っている。そのため、地球温暖化問題などで注目され始めていた太陽光や風力などの再生可能な代替エネルギーに対する関心が一段と高まり、原発に代わって安全な再生可能エネルギーによる発電を求める声も強まっていると聞く。
ここアメリカでは日本よりも先に再生可能エネルギーが注目された。シリコンバレーでは2006年ごろから、いわゆるクリーンテックのベンチャー企業への投資が増え始め、2008年のピーク時の投資総額は20億ドル弱(約1700億円)に上った。石油で潤うテキサス州の出身でオイル業界に甘いと言われたブッシュからオバマに政権が代わって以降、再生可能エネルギー産業は全体的に勢いを増している。
クリーンテック:天然資源の消費や大気への温暖化ガス排出、廃棄物を減らすことができる、風力や太陽光といった再生可能な資源を生かした発電技術。さらにそれによって発電した電力を流すスマートグリッド(次世代電力網)や、住宅、ビル、新交通システム、さらには水や廃棄物処理までも含む一連の環境ビジネスを指す。
しかし、技術的にもコスト的にも、太陽光などの再生可能エネルギーによる発電が従来の発電方式に取って代わるものなら、すでにそうなっているはず。なのに、いまだにちょっと石油や天然ガスの価格が下がると、勢いがすぐにしぼんでしまう。代替エネルギーとして「どれが良い・悪い」というイデオロギー的な是非論ではなく、「商売」の観点から見て、どう考えるべきなのだろうか。
そこで、今回はシリコンバレーを中心とするアメリカの「電力問題への挑戦」について、シリコンバレーのクリーンテックベンチャーのコンサルタント会社、Cando Advisorsの安藤千春さんと阪口幸雄さん(ブログはこちら)のお2人にお話をうかがった。その模様を「代替発電技術編」と「節電・送電技術編」の2回に分けてリポートする。
アメリカの主役は風と太陽
アメリカの現在の発電状況をエネルギーの種類別に見ると、石炭と天然ガスが7割を占め、原子力も2割に上る。「再生可能エネルギー」は少々増えているものの、まだ4%にすぎない。石油はもっぱら自動車のガソリンに回すためか、発電にはほとんど使われていない。
「自動車や飛行機を動かすための液体燃料としては、エタノールをはじめとするバイオ燃料などもありますが、実際には現在でも石油がほとんど唯一の有効な動力源です。それに対して、電気はその土地の特性に応じて、さまざまな材料から作ることができます」と安藤さんは語る。
アメリカでは、再生可能エネルギーの大部分を「風力」と「太陽」が占めている。バイオマスや海洋波、地熱などもあるが、そのウェートは小さい。「太陽」はさらに「太陽熱発電」と「太陽光発電」に分けられる。
「現在商業化している発電技術のうち、技術革新のポテンシャルが最も高いのが太陽光発電でしょう。火力、水力、原子力、風力、太陽熱など、ほかのすべての発電技術が『タービンを回して電気を発生させる』というメカニカルな仕組みを持つのに対して、太陽光だけは、光起電力効果を使った可動部分のない仕組みです。そのため、半導体のように急速な技術革新でコストを下げることが期待できます」と安藤さんは続ける。
http://
筆者は、カリフォルニア州南部のロサンゼルスから東内陸部に入ったパームスプリングスの近くで、風力発電用風車が大量に設置されている地域を車で通ったことがある。シリコンバレーからほど近い、リバモア近辺にも風車群があるが、パームスプリングスのものははるかに設置面積が広く設置の密度が高くて、まるで巨人の国に迷い込んでしまったような、異様な感覚に陥った。この辺りは、赤い砂漠に常時強風が吹きすさぶ、風力発電に適した土地だ。
「現在、アメリカで商業化されている再生可能エネルギーの中では風力が最大です。発電コストも、場所にもよりますが、ほぼグリッド・パリティーを達成していると言われています」(阪口さん)
グリッド・パリティー:再生可能エネルギーによる発電コストが 少なくとも既存の商用電力の価格(電力料金)と同等かそれ以下になる分岐点、もしくは 境界となるコストや価格を指す。
リバモアやパームスプリングスの風車群は、いずれも1970年代の石油危機をきっかけに、政府の補助金を受けて作られたものだ。古くて止まっているものも多いが、その分、風力は長く使われている技術である。
補助金と化石エネルギーの価格に左右される風力発電
時代により、天然ガスの値段(石油とほぼ連動)が下がったり、政府補助金が減ったり、需要が落ち込んだりすれば放置される、といった経緯を経ながら、それでも2010年現在、全米で35.6ギガワットの発電能力を持ち、電力全体の約2%を占めている。
AWE(American Wind Energy Association)発表(出所:阪口幸雄ブログ)によれば、全米一の「風力州」は、9.7ギガワットを持つテキサス州。カリフォルニア州は全米3位で2.7ギガワット、原発一基(原子炉一つ)の発電能力が大雑把にいって1ギガワットなので、あの見渡すかぎりの「巨人の国」をいくつか合わせて、ようやく原発3基分弱といったスケールだ。
風力発電は、「とにかくブレード(羽根)を安く作ることが製品競争力のポイントとなるので、メーカーは技術開発というよりひたすら安値のたたき合いで、商売としてはあまりうまみがないのが実情」(阪口さん)という。もちろん、技術の向上で発電効率は高まっているが、メカニカルな改良にとどまるため、劇的にコスト構造を変えるには至っていない。
風力発電は、騒音が大きい、鳥が巻き込まれる、落雷の危険、自然災害で倒れたりブレードが落ちたりする懸念、といった種々の要因から、普通は住宅地の近くに設置できない。風光明媚な場所に作れば景観を破壊する。このため、グリッド(電力会社が供給する電力)向けとしては、風の強い、人里離れた広大な場所に大量に安価な風車を並べ、大容量送電線で消費地に送り込むという、力技スタイルが中心となる。
こうした力技に、シリコンバレーのベンチャーの出番はあまりない。一方、住宅の屋根に設置するような小型風力発電のベンチャーもあるが、「見栄えに配慮して低くすれば風があまり当たらず、さらに騒音の問題もあるため、都市部には向かない。電気の通っていない農場の真ん中の井戸ポンプ用などといったニッチ向けにとどまっています」(阪口さん)。
風力発電は、経済的には化石エネルギー価格と政府の補助金という「風向き」次第なため、不安定で、利益は薄いという苦しい状況が続いている。
http://
太陽を原料とする発電のうち、太陽熱発電は、反射板などで太陽の熱を集め、オイルなどの高温になる液体をまず熱し、その熱で水から水蒸気を発生させてタービンを回す方式が主流だ。太陽が沈んでも、熱くなった液体はすぐには冷めないため、数時間は動かすことができる。Green Tech Mediaの発表(出所:阪口幸雄ブログ)によればアメリカは太陽熱発電では世界最大で、11ギガワットの発電能力を持っている。
一方、アメリカの太陽光発電能力は2009年で435メガワット(出所:SEIA、GTM Research)。「太陽光先進国」であるドイツと比べ、日射量の多いアメリカでは、パネル面積辺りの発電量は倍と言われるが、それでも全米をかき集めてもまだ原発一基分にもならない。
アリゾナ、カリフォルニア、ネバダの3州にまたがるモハベ砂漠はそのメッカだ。太陽熱のように発電能力をためておくことはできず、天気により発電量は不安定になる。しかし「日本では電力消費のピークは午後5時以降と言われているが、アメリカでは午後の勤務時間帯がピーク。太陽光が強い時間帯とほぼ一致しているので、ためておかなくても何とか使える」(阪口さん)そうだ。
太陽光発電は、「現時点ではグリッド・パリティーに達していないが、太陽電池素子や材料の技術革新によってコスト構造が大きく変わる可能性があるため、今後グリッド(電力会社の供給する電力)の主力になり得るものとしては太陽光に期待したい」(安藤さん)という将来のホープだ。
太陽光発電もアメリカでは「力技勝負」
シャープ、三洋、京セラなどの日本企業各社も効率向上の技術開発競争を繰り広げているのだが、「アメリカでは残念ながら、太陽のがんがん当たる土地が余っているので、効率を上げる努力よりも、コモディティー(汎用品)である安価なパネルをとにかくたくさん並べる方が勝ち」(安藤さん)という。ここでも「力技」の勝負になっている。
個人宅や事業所の屋根に設置するものも増えているが、今後のグリッド向け主力は、風力同様、パネルを大量に並べた砂漠の「巨人国」だ。
また、最終的には「発電ワット時当たり単価」が勝負となるので、効率が高くても製品自体の値段が高い日本メーカーは、スケールに勝るアメリカメーカーやコスト勝負の中国メーカーに対して苦戦している。GTM Research発表(出所:阪口幸雄ブログ)によれば、世界の太陽光パネルメーカーの競争力ランキング(出荷量に信頼性などのいくつかの要素を組み合わせたもの)では、アメリカのファースト・ソーラー社がトップで、それ以外の上位はほとんど中国メーカーが並び、日本からはシャープが辛うじて8位に食い込んでいる。
http://
シリコン素子技術を応用できる太陽光発電は、シリコンバレーとの親和性も高く、再生可能エネルギー分野のうち、シリコンバレーで人気があるのは太陽光だ。ただ、上記のような理由から、技術自体よりも「最近では、運用コストやプロジェクト・ファイナンスも含めた、TCO(Total Cost of Ownership)を下げるための情報・ITサービスが注目されている」(安藤さん)そうだ。
なお、太陽光についても、景観の問題があり、また補助金に依存する状態は風力と同じだ。
では、日本では何が有望なのか?
このほかにも、例えば海藻を使ったバイオマスなど、研究が緒についたばかりの技術もある。あるいはアメリカではマイナーだが、欧州では進んでいるやり方もあるだろう。しかし、どのやり方も、今すぐに日本で原発の代わりになる規模やコスト構造はない。風力や太陽などのある程度確立された方法以外では、時間軸としては10年、20年のスパンの話となる。
アメリカほどの土地の余裕も砂漠の太陽もない日本で、せいぜい数年程度の時間軸で考えるとしたら、何が有望なのだろうか?
「アメリカで使われているもののうち、消去法で言うなら、太陽光ではないかと思います」というのが阪口さんの意見だ。「日本のパネルはアメリカの倍の効率があるので、設置面積は半分で済む。どこかにパネルを集中設置し、これと電力需要ピークを太陽のある昼間に持っていくライフスタイル変更との合わせ技で、発電絶対量では足りなくても、ピーク需要をしのぐ助けぐらいにはなるのでは」と考えているそうだ。
お2人のお話をうかがって、この分野については素人である筆者は、考え込んでしまった。原発は、今回の事故の賠償金や、今後のさらなる安全対策などのコストが上乗せされるので、従来と比べて再生可能エネルギーとの差は縮まるだろう。
しかし一方で、一番進んでいる風力で世界最大の規模を持つアメリカでさえ、70年代から今に至るも、補助金漬け状態が続いている。化石燃料に対抗するためには、代替手段のスケールや技術が自立できるレベルに達するまで、補助金がある程度必要なのは仕方ないとしよう。
しかし、それを実施するためには、かなり長期にわたって税金や電気料金などの形で国民の負担を増やし、もしかしたら永遠にモノにならないかもしれないリスクも覚悟して、それでも多数の国民の理解を得て法案を成立させ、長期にわたって補助金政策を維持する必要がある。
今の日本の不安定な政治状況下で、それができるかは大いに疑問だ。むしろ、東京電力が「原発事故ごめんなさい基金」でも作り、長期にわたって再生可能エネルギーに資金を出すなどといった、民間ベースの仕組みの方がいいのかもしれない。
今のままでは、結局、手っ取り早い「現状維持+原発の改良」にずるずると戻るような気が、筆者はしている。
次回は、電力問題のもう1つの側面である「節電・送電」の動向についてお伝えする。
http://
ここアメリカでは日本よりも先に再生可能エネルギーが注目された。シリコンバレーでは2006年ごろから、いわゆるクリーンテックのベンチャー企業への投資が増え始め、2008年のピーク時の投資総額は20億ドル弱(約1700億円)に上った。石油で潤うテキサス州の出身でオイル業界に甘いと言われたブッシュからオバマに政権が代わって以降、再生可能エネルギー産業は全体的に勢いを増している。
クリーンテック:天然資源の消費や大気への温暖化ガス排出、廃棄物を減らすことができる、風力や太陽光といった再生可能な資源を生かした発電技術。さらにそれによって発電した電力を流すスマートグリッド(次世代電力網)や、住宅、ビル、新交通システム、さらには水や廃棄物処理までも含む一連の環境ビジネスを指す。
しかし、技術的にもコスト的にも、太陽光などの再生可能エネルギーによる発電が従来の発電方式に取って代わるものなら、すでにそうなっているはず。なのに、いまだにちょっと石油や天然ガスの価格が下がると、勢いがすぐにしぼんでしまう。代替エネルギーとして「どれが良い・悪い」というイデオロギー的な是非論ではなく、「商売」の観点から見て、どう考えるべきなのだろうか。
そこで、今回はシリコンバレーを中心とするアメリカの「電力問題への挑戦」について、シリコンバレーのクリーンテックベンチャーのコンサルタント会社、Cando Advisorsの安藤千春さんと阪口幸雄さん(ブログはこちら)のお2人にお話をうかがった。その模様を「代替発電技術編」と「節電・送電技術編」の2回に分けてリポートする。
アメリカの主役は風と太陽
アメリカの現在の発電状況をエネルギーの種類別に見ると、石炭と天然ガスが7割を占め、原子力も2割に上る。「再生可能エネルギー」は少々増えているものの、まだ4%にすぎない。石油はもっぱら自動車のガソリンに回すためか、発電にはほとんど使われていない。
「自動車や飛行機を動かすための液体燃料としては、エタノールをはじめとするバイオ燃料などもありますが、実際には現在でも石油がほとんど唯一の有効な動力源です。それに対して、電気はその土地の特性に応じて、さまざまな材料から作ることができます」と安藤さんは語る。
アメリカでは、再生可能エネルギーの大部分を「風力」と「太陽」が占めている。バイオマスや海洋波、地熱などもあるが、そのウェートは小さい。「太陽」はさらに「太陽熱発電」と「太陽光発電」に分けられる。
「現在商業化している発電技術のうち、技術革新のポテンシャルが最も高いのが太陽光発電でしょう。火力、水力、原子力、風力、太陽熱など、ほかのすべての発電技術が『タービンを回して電気を発生させる』というメカニカルな仕組みを持つのに対して、太陽光だけは、光起電力効果を使った可動部分のない仕組みです。そのため、半導体のように急速な技術革新でコストを下げることが期待できます」と安藤さんは続ける。
http://
筆者は、カリフォルニア州南部のロサンゼルスから東内陸部に入ったパームスプリングスの近くで、風力発電用風車が大量に設置されている地域を車で通ったことがある。シリコンバレーからほど近い、リバモア近辺にも風車群があるが、パームスプリングスのものははるかに設置面積が広く設置の密度が高くて、まるで巨人の国に迷い込んでしまったような、異様な感覚に陥った。この辺りは、赤い砂漠に常時強風が吹きすさぶ、風力発電に適した土地だ。
「現在、アメリカで商業化されている再生可能エネルギーの中では風力が最大です。発電コストも、場所にもよりますが、ほぼグリッド・パリティーを達成していると言われています」(阪口さん)
グリッド・パリティー:再生可能エネルギーによる発電コストが 少なくとも既存の商用電力の価格(電力料金)と同等かそれ以下になる分岐点、もしくは 境界となるコストや価格を指す。
リバモアやパームスプリングスの風車群は、いずれも1970年代の石油危機をきっかけに、政府の補助金を受けて作られたものだ。古くて止まっているものも多いが、その分、風力は長く使われている技術である。
補助金と化石エネルギーの価格に左右される風力発電
時代により、天然ガスの値段(石油とほぼ連動)が下がったり、政府補助金が減ったり、需要が落ち込んだりすれば放置される、といった経緯を経ながら、それでも2010年現在、全米で35.6ギガワットの発電能力を持ち、電力全体の約2%を占めている。
AWE(American Wind Energy Association)発表(出所:阪口幸雄ブログ)によれば、全米一の「風力州」は、9.7ギガワットを持つテキサス州。カリフォルニア州は全米3位で2.7ギガワット、原発一基(原子炉一つ)の発電能力が大雑把にいって1ギガワットなので、あの見渡すかぎりの「巨人の国」をいくつか合わせて、ようやく原発3基分弱といったスケールだ。
風力発電は、「とにかくブレード(羽根)を安く作ることが製品競争力のポイントとなるので、メーカーは技術開発というよりひたすら安値のたたき合いで、商売としてはあまりうまみがないのが実情」(阪口さん)という。もちろん、技術の向上で発電効率は高まっているが、メカニカルな改良にとどまるため、劇的にコスト構造を変えるには至っていない。
風力発電は、騒音が大きい、鳥が巻き込まれる、落雷の危険、自然災害で倒れたりブレードが落ちたりする懸念、といった種々の要因から、普通は住宅地の近くに設置できない。風光明媚な場所に作れば景観を破壊する。このため、グリッド(電力会社が供給する電力)向けとしては、風の強い、人里離れた広大な場所に大量に安価な風車を並べ、大容量送電線で消費地に送り込むという、力技スタイルが中心となる。
こうした力技に、シリコンバレーのベンチャーの出番はあまりない。一方、住宅の屋根に設置するような小型風力発電のベンチャーもあるが、「見栄えに配慮して低くすれば風があまり当たらず、さらに騒音の問題もあるため、都市部には向かない。電気の通っていない農場の真ん中の井戸ポンプ用などといったニッチ向けにとどまっています」(阪口さん)。
風力発電は、経済的には化石エネルギー価格と政府の補助金という「風向き」次第なため、不安定で、利益は薄いという苦しい状況が続いている。
http://
太陽を原料とする発電のうち、太陽熱発電は、反射板などで太陽の熱を集め、オイルなどの高温になる液体をまず熱し、その熱で水から水蒸気を発生させてタービンを回す方式が主流だ。太陽が沈んでも、熱くなった液体はすぐには冷めないため、数時間は動かすことができる。Green Tech Mediaの発表(出所:阪口幸雄ブログ)によればアメリカは太陽熱発電では世界最大で、11ギガワットの発電能力を持っている。
一方、アメリカの太陽光発電能力は2009年で435メガワット(出所:SEIA、GTM Research)。「太陽光先進国」であるドイツと比べ、日射量の多いアメリカでは、パネル面積辺りの発電量は倍と言われるが、それでも全米をかき集めてもまだ原発一基分にもならない。
アリゾナ、カリフォルニア、ネバダの3州にまたがるモハベ砂漠はそのメッカだ。太陽熱のように発電能力をためておくことはできず、天気により発電量は不安定になる。しかし「日本では電力消費のピークは午後5時以降と言われているが、アメリカでは午後の勤務時間帯がピーク。太陽光が強い時間帯とほぼ一致しているので、ためておかなくても何とか使える」(阪口さん)そうだ。
太陽光発電は、「現時点ではグリッド・パリティーに達していないが、太陽電池素子や材料の技術革新によってコスト構造が大きく変わる可能性があるため、今後グリッド(電力会社の供給する電力)の主力になり得るものとしては太陽光に期待したい」(安藤さん)という将来のホープだ。
太陽光発電もアメリカでは「力技勝負」
シャープ、三洋、京セラなどの日本企業各社も効率向上の技術開発競争を繰り広げているのだが、「アメリカでは残念ながら、太陽のがんがん当たる土地が余っているので、効率を上げる努力よりも、コモディティー(汎用品)である安価なパネルをとにかくたくさん並べる方が勝ち」(安藤さん)という。ここでも「力技」の勝負になっている。
個人宅や事業所の屋根に設置するものも増えているが、今後のグリッド向け主力は、風力同様、パネルを大量に並べた砂漠の「巨人国」だ。
また、最終的には「発電ワット時当たり単価」が勝負となるので、効率が高くても製品自体の値段が高い日本メーカーは、スケールに勝るアメリカメーカーやコスト勝負の中国メーカーに対して苦戦している。GTM Research発表(出所:阪口幸雄ブログ)によれば、世界の太陽光パネルメーカーの競争力ランキング(出荷量に信頼性などのいくつかの要素を組み合わせたもの)では、アメリカのファースト・ソーラー社がトップで、それ以外の上位はほとんど中国メーカーが並び、日本からはシャープが辛うじて8位に食い込んでいる。
http://
シリコン素子技術を応用できる太陽光発電は、シリコンバレーとの親和性も高く、再生可能エネルギー分野のうち、シリコンバレーで人気があるのは太陽光だ。ただ、上記のような理由から、技術自体よりも「最近では、運用コストやプロジェクト・ファイナンスも含めた、TCO(Total Cost of Ownership)を下げるための情報・ITサービスが注目されている」(安藤さん)そうだ。
なお、太陽光についても、景観の問題があり、また補助金に依存する状態は風力と同じだ。
では、日本では何が有望なのか?
このほかにも、例えば海藻を使ったバイオマスなど、研究が緒についたばかりの技術もある。あるいはアメリカではマイナーだが、欧州では進んでいるやり方もあるだろう。しかし、どのやり方も、今すぐに日本で原発の代わりになる規模やコスト構造はない。風力や太陽などのある程度確立された方法以外では、時間軸としては10年、20年のスパンの話となる。
アメリカほどの土地の余裕も砂漠の太陽もない日本で、せいぜい数年程度の時間軸で考えるとしたら、何が有望なのだろうか?
「アメリカで使われているもののうち、消去法で言うなら、太陽光ではないかと思います」というのが阪口さんの意見だ。「日本のパネルはアメリカの倍の効率があるので、設置面積は半分で済む。どこかにパネルを集中設置し、これと電力需要ピークを太陽のある昼間に持っていくライフスタイル変更との合わせ技で、発電絶対量では足りなくても、ピーク需要をしのぐ助けぐらいにはなるのでは」と考えているそうだ。
お2人のお話をうかがって、この分野については素人である筆者は、考え込んでしまった。原発は、今回の事故の賠償金や、今後のさらなる安全対策などのコストが上乗せされるので、従来と比べて再生可能エネルギーとの差は縮まるだろう。
しかし一方で、一番進んでいる風力で世界最大の規模を持つアメリカでさえ、70年代から今に至るも、補助金漬け状態が続いている。化石燃料に対抗するためには、代替手段のスケールや技術が自立できるレベルに達するまで、補助金がある程度必要なのは仕方ないとしよう。
しかし、それを実施するためには、かなり長期にわたって税金や電気料金などの形で国民の負担を増やし、もしかしたら永遠にモノにならないかもしれないリスクも覚悟して、それでも多数の国民の理解を得て法案を成立させ、長期にわたって補助金政策を維持する必要がある。
今の日本の不安定な政治状況下で、それができるかは大いに疑問だ。むしろ、東京電力が「原発事故ごめんなさい基金」でも作り、長期にわたって再生可能エネルギーに資金を出すなどといった、民間ベースの仕組みの方がいいのかもしれない。
今のままでは、結局、手っ取り早い「現状維持+原発の改良」にずるずると戻るような気が、筆者はしている。
次回は、電力問題のもう1つの側面である「節電・送電」の動向についてお伝えする。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
米国関連情報 (2) 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
米国関連情報 (2)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90002人
- 3位
- 酒好き
- 170653人