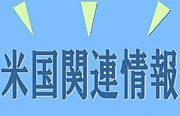「率直に言って、私たちは騙(だま)されたのだ」。メディアや自動車専門家が米ゼネラルモーターズ(GM)への批判を強めている。11月に発売される自称“長距離電気自動車”の「シボレーボルト」が、当初の触れ込みとは異なり高速走行時などでガソリンエンジンからも直接駆動力を得ることが判明したためだ。同社関係者は、より良い製品に仕上げるための変更だったと主張するが、消費者に失望が広がれば、ボルトは、病み上がりのGMにとって、救世主どころか、足を引っ張る疫病神ともなりかねない。
(文/ジャーナリスト、ポール・アイゼンスタイン)
米ゼネラルモーターズ(GM)が11月、再生の象徴(と目されていた)「シボレーボルト」をついに発売する。このいわゆる「長距離電気自動車」(Extended Range Electric Vehicle、E-REV)は、GMが持てる技術の粋を結集して開発したものとされ、GM復活の狼煙になると期待されてきたものだ(同社自身が「自動車による移動を再創造する」と宣言し、そう世間に信じ込ませてきた)。しかし、発売を前に、GMはかつての「ウォーターゲート事件」のような情報隠蔽をやったのではないかとの批判にさらされている。
当初の構想では、この「ボルト」は純粋にバッテリー駆動だけで走行するよう設計されていた(少なくともGM関係者はそう公言していた)。1時間あたり16キロワットの出力を誇るリチウムイオン電池により、電動モードだけで約40マイル(64.4キロ)の航続距離と時速90マイル(144.9キロ)以上のスピードを実現するとされていた。
しかし、驚いたことに、知らぬ間にこの「ボルト」にはいくつかの重大な変更が施されていた。一つは、航続距離だ。GMは突然、「ボルト」のバッテリー駆動のみによる航続距離は正確には25〜50マイル(40.25〜80.5キロ)のあいだであり、路面・天候や個々の運転パターンによって変わってくる、と主張しはじめた。
もうひとつは(こちらのほうが深刻な変更点だ!)、「長距離電気自動車」という名称の正当性に関わる基本的な駆動システムに対するものだ。
当初の「ボルト」の売りはこうだった。従来のバッテリー駆動電気自動車(BEV)と異なり、「ボルト」はバッテリーが消耗しても走り続ける能力を持っている。その秘密は、小型の直列4気筒ガソリンエンジンで、バッテリーが消耗するとこれが自動的に点火される。構想では、このいわゆる「シリアル(逐次)・ハイブリッド」設計は、「ボルト」のモーターを駆動する電力を発生させるためだけにガソリンエンジンを用いるものだった。
ところが、9月21日付けでGMが取得した特許を注意深く調べてみると、これは正確ではないことが判明した。運転効率(つまり最大航続距離と性能)を改善するため、GMの言う「ボルテック推進システム」の核心である電気駆動ユニット「4ET50」には、いくつかの変更が加えられたのである。
http://
「ボルト」のコンセプトが最初に明らかになった時点から3年近くにわたり、筆者が個人的につけてきた記録、また筆者が書いた記事や他のニュースソースから集めた記事を注意深く読めば、「ボルト」に搭載されたガソリンエンジンが、どんなときであれ車輪に直接駆動力を与える予定はなかったことは明らかである。
だが実際にはそうした状況が生じることを、「ボルト」開発計画のチーフであるトニー・ポザワッツは認めている。
長時間のインタビューのなかでポザワッツは、圧倒的に多数の状況において「ボルト」は「電動モーターの駆動力だけで走ることができる」と主張したが、その一方でいくつかの状況ではこの戦略が変更されたことを認めた。そうした状況とは、つまりバッテリーが消耗し、いわゆる「長距離モード」で走行している場合に生じるという。「時速約70マイルで走行し、追い越しをかけようとする」とき、あるいは定員いっぱいの「ボルト」が長い急坂で加速しようとするときなどだ。
こうした状況では、4ET50に内蔵された複雑なギアとクラッチの働きにより、ポザワッツの言葉を借りれば「わずかな」パワーが、直4エンジンから直接引き出される。つまり、ガソリンエンジンによるトルクの一部が電気モーターの出力に追加され、負荷を処理することになる。ポザワッツは、「ボルテック推進システム」の全般的な効率を改善するためだと強調する。
これでは、「プリウス」など標準的なハイブリッド車で起きていることとあまり違わない。もっともポザワッツは、こうした状況が起きる頻度は圧倒的に低く、何より大切なのは、あらゆる状況において、電動モーターが常に作動しており、トルクの大半を供給しているという点だと主張している。
http://
だがそれでも、自動車情報サイトEdmunds.comは、その怒りをこめた宣言のなかで、「率直に言って、私たちは騙されたのだ」と断じている。
これは公平な評価だろうか。
ある関係者は「情報を完全に開示していたわけではない」と認めつつも、「一つには特許の承認を待つあいだの戦略であった。故意に騙していたわけではない」と嘆く。(「ボルト」のように)壮大で革新的なプログラムでありながら、これほどオープンで透明性が高いものはこれまでになかった」。
恐らく故意ではないだろう。しかし、今回の騒ぎで生じた最大の疑問は「ではそもそも、2011年型『シボレーボルト』とは何であるのか」というものだ。
今となっては、「ボルト」は単に従来よりも手の込んだハイブリッド車であって本当の電気自動車ではない、と主張することも可能だろう。
もちろん「長距離電気自動車」とは何かという皆が認める共通定義などまだ存在しないが、「ボルト」に対して政府の提供する電気自動車を対象とした7500ドルの免税措置(日産「リーフ」など純粋なバッテリー電気自動車にも与えられる)を適用すべきだという意見に反発する人にとって、これは一つの論点になる可能性がある。
さらに重要な問題は、この議論を消費者がどう受け止めるかだ。ポザワッツとGMの支持者は、こうした駆動系の見直しは、実際には消費者に奉仕するものだと言うだろう。「ボルト」ができるだけ幅広い走行条件のもとで期待通りの性能を発揮できるようになるからだ。
だが、この騒ぎで、消費者のあいだに失望が広がるようならば、病み上がりのGMにとって大打撃となりかねない。長らく待ち望まれた株式の再公開の準備を進めている今、これ以上ない悪いタイミングで「ボルト」騒動に火が付いた。
(翻訳/エァクレーレン 沢崎冬日)
http://
(文/ジャーナリスト、ポール・アイゼンスタイン)
米ゼネラルモーターズ(GM)が11月、再生の象徴(と目されていた)「シボレーボルト」をついに発売する。このいわゆる「長距離電気自動車」(Extended Range Electric Vehicle、E-REV)は、GMが持てる技術の粋を結集して開発したものとされ、GM復活の狼煙になると期待されてきたものだ(同社自身が「自動車による移動を再創造する」と宣言し、そう世間に信じ込ませてきた)。しかし、発売を前に、GMはかつての「ウォーターゲート事件」のような情報隠蔽をやったのではないかとの批判にさらされている。
当初の構想では、この「ボルト」は純粋にバッテリー駆動だけで走行するよう設計されていた(少なくともGM関係者はそう公言していた)。1時間あたり16キロワットの出力を誇るリチウムイオン電池により、電動モードだけで約40マイル(64.4キロ)の航続距離と時速90マイル(144.9キロ)以上のスピードを実現するとされていた。
しかし、驚いたことに、知らぬ間にこの「ボルト」にはいくつかの重大な変更が施されていた。一つは、航続距離だ。GMは突然、「ボルト」のバッテリー駆動のみによる航続距離は正確には25〜50マイル(40.25〜80.5キロ)のあいだであり、路面・天候や個々の運転パターンによって変わってくる、と主張しはじめた。
もうひとつは(こちらのほうが深刻な変更点だ!)、「長距離電気自動車」という名称の正当性に関わる基本的な駆動システムに対するものだ。
当初の「ボルト」の売りはこうだった。従来のバッテリー駆動電気自動車(BEV)と異なり、「ボルト」はバッテリーが消耗しても走り続ける能力を持っている。その秘密は、小型の直列4気筒ガソリンエンジンで、バッテリーが消耗するとこれが自動的に点火される。構想では、このいわゆる「シリアル(逐次)・ハイブリッド」設計は、「ボルト」のモーターを駆動する電力を発生させるためだけにガソリンエンジンを用いるものだった。
ところが、9月21日付けでGMが取得した特許を注意深く調べてみると、これは正確ではないことが判明した。運転効率(つまり最大航続距離と性能)を改善するため、GMの言う「ボルテック推進システム」の核心である電気駆動ユニット「4ET50」には、いくつかの変更が加えられたのである。
http://
「ボルト」のコンセプトが最初に明らかになった時点から3年近くにわたり、筆者が個人的につけてきた記録、また筆者が書いた記事や他のニュースソースから集めた記事を注意深く読めば、「ボルト」に搭載されたガソリンエンジンが、どんなときであれ車輪に直接駆動力を与える予定はなかったことは明らかである。
だが実際にはそうした状況が生じることを、「ボルト」開発計画のチーフであるトニー・ポザワッツは認めている。
長時間のインタビューのなかでポザワッツは、圧倒的に多数の状況において「ボルト」は「電動モーターの駆動力だけで走ることができる」と主張したが、その一方でいくつかの状況ではこの戦略が変更されたことを認めた。そうした状況とは、つまりバッテリーが消耗し、いわゆる「長距離モード」で走行している場合に生じるという。「時速約70マイルで走行し、追い越しをかけようとする」とき、あるいは定員いっぱいの「ボルト」が長い急坂で加速しようとするときなどだ。
こうした状況では、4ET50に内蔵された複雑なギアとクラッチの働きにより、ポザワッツの言葉を借りれば「わずかな」パワーが、直4エンジンから直接引き出される。つまり、ガソリンエンジンによるトルクの一部が電気モーターの出力に追加され、負荷を処理することになる。ポザワッツは、「ボルテック推進システム」の全般的な効率を改善するためだと強調する。
これでは、「プリウス」など標準的なハイブリッド車で起きていることとあまり違わない。もっともポザワッツは、こうした状況が起きる頻度は圧倒的に低く、何より大切なのは、あらゆる状況において、電動モーターが常に作動しており、トルクの大半を供給しているという点だと主張している。
http://
だがそれでも、自動車情報サイトEdmunds.comは、その怒りをこめた宣言のなかで、「率直に言って、私たちは騙されたのだ」と断じている。
これは公平な評価だろうか。
ある関係者は「情報を完全に開示していたわけではない」と認めつつも、「一つには特許の承認を待つあいだの戦略であった。故意に騙していたわけではない」と嘆く。(「ボルト」のように)壮大で革新的なプログラムでありながら、これほどオープンで透明性が高いものはこれまでになかった」。
恐らく故意ではないだろう。しかし、今回の騒ぎで生じた最大の疑問は「ではそもそも、2011年型『シボレーボルト』とは何であるのか」というものだ。
今となっては、「ボルト」は単に従来よりも手の込んだハイブリッド車であって本当の電気自動車ではない、と主張することも可能だろう。
もちろん「長距離電気自動車」とは何かという皆が認める共通定義などまだ存在しないが、「ボルト」に対して政府の提供する電気自動車を対象とした7500ドルの免税措置(日産「リーフ」など純粋なバッテリー電気自動車にも与えられる)を適用すべきだという意見に反発する人にとって、これは一つの論点になる可能性がある。
さらに重要な問題は、この議論を消費者がどう受け止めるかだ。ポザワッツとGMの支持者は、こうした駆動系の見直しは、実際には消費者に奉仕するものだと言うだろう。「ボルト」ができるだけ幅広い走行条件のもとで期待通りの性能を発揮できるようになるからだ。
だが、この騒ぎで、消費者のあいだに失望が広がるようならば、病み上がりのGMにとって大打撃となりかねない。長らく待ち望まれた株式の再公開の準備を進めている今、これ以上ない悪いタイミングで「ボルト」騒動に火が付いた。
(翻訳/エァクレーレン 沢崎冬日)
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
米国関連情報 (2) 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
米国関連情報 (2)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82541人
- 2位
- 酒好き
- 170695人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人