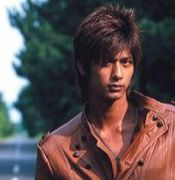|
|
|
|
コメント(72)
国鉄時代は、相場が決まっていて、特急列車はグリーン車はフルリクライニングシートでフットレスト付、普通車は回転クロスシート(比較的新しい車は簡易リクライニングシート)。
急行列車はグリーン車はフルリクライニングシートでフットレスト付、普通車は当然だけどボックスシート
寝台列車はA寝台はプルマン式開放寝台、B寝台は三段式寝台(一部の特急列車は二段式寝台)でした。
相場破壊が始まったのは、JRの時からだったと、いえます。
バブルの時は、JRはグリーン車は2&1、普通車はフリーストップ式リクライニングだったのと、寝台列車は個室化が進行したことに加えて、割安な値段で豪華な設備が楽しめる、快速列車などが誕生しました。
ようは進歩がないと、社会はいらないという典型の時代だったことが解ります。
急行列車はグリーン車はフルリクライニングシートでフットレスト付、普通車は当然だけどボックスシート
寝台列車はA寝台はプルマン式開放寝台、B寝台は三段式寝台(一部の特急列車は二段式寝台)でした。
相場破壊が始まったのは、JRの時からだったと、いえます。
バブルの時は、JRはグリーン車は2&1、普通車はフリーストップ式リクライニングだったのと、寝台列車は個室化が進行したことに加えて、割安な値段で豪華な設備が楽しめる、快速列車などが誕生しました。
ようは進歩がないと、社会はいらないという典型の時代だったことが解ります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
悪いか?鉄道マニアで… 更新情報
-
最新のアンケート