日本語における曜日呼称は月火水木金土日ですが、これは5惑星と太陽と月の名称に由来しています。7つになるのは太陽と月も5惑星と同様に星座の間を移動する天体として惑星の仲間と考えられるからでしょう。このように日々に惑星たちを割り当てていくことを行ったのは、紀元前2世紀頃のバビロニア人またはギリシア人らしい、ということになっています。まず、日々への割り当てに先行して時間時間への割り当てが在ったようです。そして、24の時間への割り当てから現在の曜日のような順番での惑星割り当てが決まったようです。(この順番が出来た経緯に関しては、ものの本にもありますし私のHP(http://
地上から肉眼で見える惑星とは地域風土に関係なく同じものであり、共通して持てる言葉(概念)です。曜日配当の設定根拠には大した必然性があるとは本当のところ思えませんが、紀元前から連綿と続いているこの曜日を、民族的地域色を盛り込まずに、その連続性を尊ぶならば日本、朝鮮、インドのような古代からの伝統を受け継いだ曜日呼称が最も良いように思われます。どうして、もともと日々への惑星配当だった曜日を、惑星とはほとんど関係など無いと思われる神話の神々の名前にしてしまうのでしょうね。
では、日本語の曜日呼称が惑星名だということは解かりましたが、どうしてそれが、火(fire)、水(water)、木(tree)、金(metal)、土(earth)なのでしょうか?
中国には物事の循環、森羅万象の法則を陰と陽の2極(二元)を持つ5要素(五行)で説明する「陰陽五行説」という考え方があります。陰陽の思想(易の八卦)は人面牛身とも言われている神話伝説上の古帝王“伏犧または伏羲または包羲(ふくぎ、ふっき、フーイー、バオイー)”が作ったと言われ、五行の思想は世襲王朝“夏(か、ヒア)”の開祖“禹(う)”が定めたと言われています。陽と陰のシンボルとして、昼夜、夏冬、高低、熱い冷たい、火水、などを挙げるとイメージが広がります。五行のシンボルとしては、[上昇‐極大‐基準‐下降‐極小]∽[春・夏・土用・秋・冬]∽[成長‐炎上‐生成‐凝結‐浸透(めばえ)]∽[木・火・土・金・水]、を挙げることができます。そして、陰陽説と五行説を統一した“斉(せい)”の思想家“鄒衍(すうえん)”が、五行に対して肉眼観測できる5惑星を当てはめました。歳星には木、けい惑には火、填星には土、太白には金、辰星には水と。歳星、けい惑、填星、太白、辰星というのは5惑星の中国名です。中国ではこのように5惑星を水・金・火・木・土星ではない別の呼び方をしていますが、この惑星たちに鄒衍(すうえん)が配当した五行を元にして日本語における5惑星の呼称が決まったようです。
歳星はだいたい12年で星々の間を一周する明るい星です。12という数が地球上の生物の営みのサイクル12ヶ月と一致することから成長のシンボルとして“木”の性格に属する惑星ということでしょうか。けい惑は夜中にも現れる惑星としては最も動きも変化も速い明るい赤い星です。運動や変化の活発さと輝きの色から“火”の性格に属する星ということでしょうか。填星は5惑星中で輝きは最も鈍く、動きも最も遅い惑星です。その落ち着いた性格から“土”ということでしょうか。太白は“宵の明星”“明けの明星”として知られ、夕方または朝にしか見られない非常に明るい星です。昼の終わり、または夜の終わりを象徴するこの明るい星に、秋の実りのイメージに重なる“金”はふさわしいかもしれません。辰星は日の入り後の夕空または日の出前の朝空の比較的低い高度でしか見られない惑星です。輝きじたいは弱くありませんが高度も低く、見られる時間も短いというはかなさから陰のシンボルである“水”ということでしょうか。
こうして、斉の鄒衍による5惑星への五行配当の思考を追いかけて見てみると、水星を“水(water)”星、金星を“金(metal)”星、火星を“火(fire)”星、木星を“木(tree)”星、土星を“土(earth)”星、と日本人の私達が現在呼び習わしていることの辻褄が五行説から理解することができます。
西洋での惑星の名称が、神話に出てくる神々の名称だということと比較すると、惑星の名称の由来までも日本語での名称の方が理知的な付け方に従っているような気がしてなりません。やはり、東洋が天空や自然を支配者として敬うのに対して、西洋は得体の知れない地球外存在を絶対神として敬っているということに起因しているのでしょうか。
地上から肉眼で見える惑星とは地域風土に関係なく同じものであり、共通して持てる言葉(概念)です。曜日配当の設定根拠には大した必然性があるとは本当のところ思えませんが、紀元前から連綿と続いているこの曜日を、民族的地域色を盛り込まずに、その連続性を尊ぶならば日本、朝鮮、インドのような古代からの伝統を受け継いだ曜日呼称が最も良いように思われます。どうして、もともと日々への惑星配当だった曜日を、惑星とはほとんど関係など無いと思われる神話の神々の名前にしてしまうのでしょうね。
では、日本語の曜日呼称が惑星名だということは解かりましたが、どうしてそれが、火(fire)、水(water)、木(tree)、金(metal)、土(earth)なのでしょうか?
中国には物事の循環、森羅万象の法則を陰と陽の2極(二元)を持つ5要素(五行)で説明する「陰陽五行説」という考え方があります。陰陽の思想(易の八卦)は人面牛身とも言われている神話伝説上の古帝王“伏犧または伏羲または包羲(ふくぎ、ふっき、フーイー、バオイー)”が作ったと言われ、五行の思想は世襲王朝“夏(か、ヒア)”の開祖“禹(う)”が定めたと言われています。陽と陰のシンボルとして、昼夜、夏冬、高低、熱い冷たい、火水、などを挙げるとイメージが広がります。五行のシンボルとしては、[上昇‐極大‐基準‐下降‐極小]∽[春・夏・土用・秋・冬]∽[成長‐炎上‐生成‐凝結‐浸透(めばえ)]∽[木・火・土・金・水]、を挙げることができます。そして、陰陽説と五行説を統一した“斉(せい)”の思想家“鄒衍(すうえん)”が、五行に対して肉眼観測できる5惑星を当てはめました。歳星には木、けい惑には火、填星には土、太白には金、辰星には水と。歳星、けい惑、填星、太白、辰星というのは5惑星の中国名です。中国ではこのように5惑星を水・金・火・木・土星ではない別の呼び方をしていますが、この惑星たちに鄒衍(すうえん)が配当した五行を元にして日本語における5惑星の呼称が決まったようです。
歳星はだいたい12年で星々の間を一周する明るい星です。12という数が地球上の生物の営みのサイクル12ヶ月と一致することから成長のシンボルとして“木”の性格に属する惑星ということでしょうか。けい惑は夜中にも現れる惑星としては最も動きも変化も速い明るい赤い星です。運動や変化の活発さと輝きの色から“火”の性格に属する星ということでしょうか。填星は5惑星中で輝きは最も鈍く、動きも最も遅い惑星です。その落ち着いた性格から“土”ということでしょうか。太白は“宵の明星”“明けの明星”として知られ、夕方または朝にしか見られない非常に明るい星です。昼の終わり、または夜の終わりを象徴するこの明るい星に、秋の実りのイメージに重なる“金”はふさわしいかもしれません。辰星は日の入り後の夕空または日の出前の朝空の比較的低い高度でしか見られない惑星です。輝きじたいは弱くありませんが高度も低く、見られる時間も短いというはかなさから陰のシンボルである“水”ということでしょうか。
こうして、斉の鄒衍による5惑星への五行配当の思考を追いかけて見てみると、水星を“水(water)”星、金星を“金(metal)”星、火星を“火(fire)”星、木星を“木(tree)”星、土星を“土(earth)”星、と日本人の私達が現在呼び習わしていることの辻褄が五行説から理解することができます。
西洋での惑星の名称が、神話に出てくる神々の名称だということと比較すると、惑星の名称の由来までも日本語での名称の方が理知的な付け方に従っているような気がしてなりません。やはり、東洋が天空や自然を支配者として敬うのに対して、西洋は得体の知れない地球外存在を絶対神として敬っているということに起因しているのでしょうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
暦 こよみ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
暦 こよみのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90005人
- 3位
- 酒好き
- 170655人
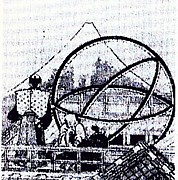


![月夜見 [ツクヨミ]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/3/72/1110372_2s.gif)



















