旧暦ファンの人が、新暦だと節供日が季節外れになるので旧暦の季節の方が正しい、という趣旨のことを言うのをよく聞きます。
それに対して旧暦に批判的な人は、旧暦の月日は30日くらいの幅の中で厳密な季節の上を毎年変動しているから、太陽暦であるグレゴリオ暦(新暦)の方が季節が正確で便利、という趣旨のことを言うのもよく聞きます。
一見すると、この二つの意見は互いに矛盾しているように見えますがどちらも正論です。
・「日本が旧暦と共に季節感を育んできた旧暦行事の日取りは新暦ではなく旧暦でするのが正しい。」
・「異年同月日の季節位置は陰暦よりも太陽暦であるグレゴリオ暦が正確」
こうして二つの意見の要点をまとめてみると、この二つの意見は「年中行事の日取りの仕方」問題と「季節位置の厳密さ」問題という異なる次元の問題であることが分かります。だから、「新暦vs旧暦」のような形でこの二つの意見による衝突議論はたまに湧き起りますがほとんど噛み合いません。旧暦ファンは旧暦復権を願い季節の正しさを唱えますが、旧暦批判派は季節の正確さで旧暦復権論を跳ね返すという構図。
では、月日についての季節上の厳格な位置の正確さとはどのような時にどのくらいの精度で必要なのでしょうか?
まず節供について考えてみましょう。日本において明治改暦以前まで節供は、古来からずっと旧暦月日で行われてきました。30日くらいの幅に関しては、昔詠まれた俳句を見れば、むしろ年による違いが風流として楽しまれてきているのが分かります。つまり、問題ではないわけです。むしろ外れた季節の上に恒常的に節供がくくり付けられている現状の方が節供の意味を破壊しかねないので、問題ではないでしょうか。例えば、初春に必要な栄養を摂る七草粥をするための野草を摘みに野に行くとか、雛形を流しに大潮の浜辺に行くとか、七夕飾りで梅雨明けを喜ぶとか、そういうことは昔は当たり前だったはずです。ところが現在は、この不可能性が恒久的になってしまっていることが問題なのです。だから、季節位置の正確さも不動性も問題でない節供の日取りは旧暦でやればよいのではないかと思います。節供を旧暦でやったからといってローマ法王から処罰も批判もされることはありません。中国だって新暦新年よりも旧正月(春節)を盛大にやっているわけだし、ロシア正教会だってユリウス暦でクリスマスを祝っているわけだし。
次に、作物の種蒔きの時期を考えてみましょう。種蒔きに適する日というのは作物の種類によっても相当違いはありますが、概して言えることは種蒔きに適する日というのは一年に一日しかないものではなくて、季節的にある程度の幅を持っているということです。そして、その幅(期間)の中でも最も適している日ということになると、もうそれは暦の上で“○月○日”という日付よりも実際のその年の季節の廻り方や前後の天気情況によって相当左右されるということです。もはや太陽暦上の月日よりも現場で読み取る“自然暦”の方が当てになるということです。この場合は、自然暦が制定暦に優先するから、農業にとっては陰暦よりも季節の正確な太陽暦が良いという判断にはならないということです。(※ 地方の伝承には、種蒔きや苗の植付けや収穫の日などを特定の月齢の時が適日と教えるものがありますが、それを加味した場合、季節内の厳密な時期の同一性よりも時期変化の速い月齢を教える陰暦の方がむしろ有益とも考えられますが…)
次に太陽暦的な年中行事を考えてみます。例えばお彼岸ですが、この日取りは春分や秋分をもとに決めるわけだからいわば太陽暦的行事であると言えます。そこで、せっかく太陽暦であるグレゴリオ暦を採用しているのだしグレゴリオ暦の月日で固定しても良さそうなものです。ところが、グレゴリオ暦という太陽暦を採用してもなお、春分と秋分(つまり、お彼岸の中日)はグレゴリオ暦月日で決めずに、グレゴリオ暦よりも厳密に二十四節気で日が決められます。ということは、お彼岸や節分(立春前日)のような太陽を元にした季節行事さえもグレゴリオ暦に無関係に“旧暦の二十四節気”で決められるているというわけです。
西洋にも太陽を元にした季節行事として冬至祭(クリスマス)があります。この冬至祭はグレゴリオ暦の月日によって実際の冬至よりも数日遅れたDec.25に固定して行っていますが、正確さを誇るグレゴリオ暦の西洋においてさえその程度でなのです。季節の不正確さが問題になるのは紀元前1世紀頃のように季節が数ヶ月(具体的にはほぼ3ヶ月)までのずれに膨らむ時です。グレゴリオ暦というのは、カトリックのいろいろな季節行事を暦の“月日”に頼る西洋において、この失敗を繰り返さずに済むように、ローマ法王グレゴリオ13世が制定しただけの暦ではないでしょうか。
こうして考えてくると、日付の季節上の厳格な位置の正確さというものは、正確さを要求される時には旧暦時代であろうと新暦時代であろうと日本においては二十四節気を用いて決められます。一方、“年による差がある季節現象”にちなんだ行事に関しては、古来の日本では初めから月日の季節位置の正確さは当てにしないで、年ごとの違いを観察して対応したり、むしろ風流として楽しんだりしてきた、ということです。だから30日程度の幅も全く問題ないわけです。要するに、旧暦月日の季節上の変動というものもとやかく言うほどの問題はないし、季節の正確さは必要に応じ二十四節気で対応すればいいということです。
結論として、暦月日の季節位置同一性はあんまり厳密さは必要とされないし(←都市生活ならなおさら?)、季節の厳密さが本当に必要とされる場合にはグレゴリオ暦よりも正確な二十四節気の方が用いられるから、約2620年で1日ずつ季節がずれていくグレゴリオ暦にどれほどの価値があろうか?と思います。千年万年単位で考えた場合には、月日の季節位置のズレが蓄積されていくグレゴリオ暦よりも、月日が必ず約30日の季節幅の中につながれている旧暦の方がむしろ永久使用に耐えうる暦のような気がしてなりません。
それに対して旧暦に批判的な人は、旧暦の月日は30日くらいの幅の中で厳密な季節の上を毎年変動しているから、太陽暦であるグレゴリオ暦(新暦)の方が季節が正確で便利、という趣旨のことを言うのもよく聞きます。
一見すると、この二つの意見は互いに矛盾しているように見えますがどちらも正論です。
・「日本が旧暦と共に季節感を育んできた旧暦行事の日取りは新暦ではなく旧暦でするのが正しい。」
・「異年同月日の季節位置は陰暦よりも太陽暦であるグレゴリオ暦が正確」
こうして二つの意見の要点をまとめてみると、この二つの意見は「年中行事の日取りの仕方」問題と「季節位置の厳密さ」問題という異なる次元の問題であることが分かります。だから、「新暦vs旧暦」のような形でこの二つの意見による衝突議論はたまに湧き起りますがほとんど噛み合いません。旧暦ファンは旧暦復権を願い季節の正しさを唱えますが、旧暦批判派は季節の正確さで旧暦復権論を跳ね返すという構図。
では、月日についての季節上の厳格な位置の正確さとはどのような時にどのくらいの精度で必要なのでしょうか?
まず節供について考えてみましょう。日本において明治改暦以前まで節供は、古来からずっと旧暦月日で行われてきました。30日くらいの幅に関しては、昔詠まれた俳句を見れば、むしろ年による違いが風流として楽しまれてきているのが分かります。つまり、問題ではないわけです。むしろ外れた季節の上に恒常的に節供がくくり付けられている現状の方が節供の意味を破壊しかねないので、問題ではないでしょうか。例えば、初春に必要な栄養を摂る七草粥をするための野草を摘みに野に行くとか、雛形を流しに大潮の浜辺に行くとか、七夕飾りで梅雨明けを喜ぶとか、そういうことは昔は当たり前だったはずです。ところが現在は、この不可能性が恒久的になってしまっていることが問題なのです。だから、季節位置の正確さも不動性も問題でない節供の日取りは旧暦でやればよいのではないかと思います。節供を旧暦でやったからといってローマ法王から処罰も批判もされることはありません。中国だって新暦新年よりも旧正月(春節)を盛大にやっているわけだし、ロシア正教会だってユリウス暦でクリスマスを祝っているわけだし。
次に、作物の種蒔きの時期を考えてみましょう。種蒔きに適する日というのは作物の種類によっても相当違いはありますが、概して言えることは種蒔きに適する日というのは一年に一日しかないものではなくて、季節的にある程度の幅を持っているということです。そして、その幅(期間)の中でも最も適している日ということになると、もうそれは暦の上で“○月○日”という日付よりも実際のその年の季節の廻り方や前後の天気情況によって相当左右されるということです。もはや太陽暦上の月日よりも現場で読み取る“自然暦”の方が当てになるということです。この場合は、自然暦が制定暦に優先するから、農業にとっては陰暦よりも季節の正確な太陽暦が良いという判断にはならないということです。(※ 地方の伝承には、種蒔きや苗の植付けや収穫の日などを特定の月齢の時が適日と教えるものがありますが、それを加味した場合、季節内の厳密な時期の同一性よりも時期変化の速い月齢を教える陰暦の方がむしろ有益とも考えられますが…)
次に太陽暦的な年中行事を考えてみます。例えばお彼岸ですが、この日取りは春分や秋分をもとに決めるわけだからいわば太陽暦的行事であると言えます。そこで、せっかく太陽暦であるグレゴリオ暦を採用しているのだしグレゴリオ暦の月日で固定しても良さそうなものです。ところが、グレゴリオ暦という太陽暦を採用してもなお、春分と秋分(つまり、お彼岸の中日)はグレゴリオ暦月日で決めずに、グレゴリオ暦よりも厳密に二十四節気で日が決められます。ということは、お彼岸や節分(立春前日)のような太陽を元にした季節行事さえもグレゴリオ暦に無関係に“旧暦の二十四節気”で決められるているというわけです。
西洋にも太陽を元にした季節行事として冬至祭(クリスマス)があります。この冬至祭はグレゴリオ暦の月日によって実際の冬至よりも数日遅れたDec.25に固定して行っていますが、正確さを誇るグレゴリオ暦の西洋においてさえその程度でなのです。季節の不正確さが問題になるのは紀元前1世紀頃のように季節が数ヶ月(具体的にはほぼ3ヶ月)までのずれに膨らむ時です。グレゴリオ暦というのは、カトリックのいろいろな季節行事を暦の“月日”に頼る西洋において、この失敗を繰り返さずに済むように、ローマ法王グレゴリオ13世が制定しただけの暦ではないでしょうか。
こうして考えてくると、日付の季節上の厳格な位置の正確さというものは、正確さを要求される時には旧暦時代であろうと新暦時代であろうと日本においては二十四節気を用いて決められます。一方、“年による差がある季節現象”にちなんだ行事に関しては、古来の日本では初めから月日の季節位置の正確さは当てにしないで、年ごとの違いを観察して対応したり、むしろ風流として楽しんだりしてきた、ということです。だから30日程度の幅も全く問題ないわけです。要するに、旧暦月日の季節上の変動というものもとやかく言うほどの問題はないし、季節の正確さは必要に応じ二十四節気で対応すればいいということです。
結論として、暦月日の季節位置同一性はあんまり厳密さは必要とされないし(←都市生活ならなおさら?)、季節の厳密さが本当に必要とされる場合にはグレゴリオ暦よりも正確な二十四節気の方が用いられるから、約2620年で1日ずつ季節がずれていくグレゴリオ暦にどれほどの価値があろうか?と思います。千年万年単位で考えた場合には、月日の季節位置のズレが蓄積されていくグレゴリオ暦よりも、月日が必ず約30日の季節幅の中につながれている旧暦の方がむしろ永久使用に耐えうる暦のような気がしてなりません。
|
|
|
|
コメント(2)
明治政府以来日本政府は旧暦は存在してはいけないもの、存在を認めるわけにはいかないもの、としているように、本来の七夕や中秋の名月の日取りに関して国立天文台は二十四節気や新月からの日数などを駆使した面倒な説明を行っています。そしてそのややこしい方法で算出する日を「伝統的七夕」、「中秋の名月」と呼んでいます。そうまでして旧暦の存在を認めまいとする姿はむしろ“こっけい”です。
日本の年中行事の矛盾は旧暦の存在を一切認めまいという政府主導の風潮によると思います。最初の理由としては、旧暦が新暦の定着を阻害するからとか、新旧暦の混在によって混乱を招くからという理由も考えられます。しかし、改暦当時は福沢諭吉が旧暦を無闇矢鱈に非難をし、さらに旧暦を口汚く罵る議員がいたとかいう情況を想像するに、自分たちのルーツに関係している伝統を徹底的に破壊し隠滅しようという悪意(あるいは悪魔)が明治期を制覇したと思わずにはいれません。そうでなければ、新暦を公式の暦とたとしても外国のように宗教上の暦だとか民族的な暦として年中行事の日取りを確定する基準として温存させても良かったはず、と思います。
国際関係の多い現代の日本が新暦を取り下げ旧暦に戻るべきだとまでは思いませんが、日本が真に他の国々と対等に関わっていくためには自分たちのルーツ・根拠・伝統をきちんと踏まえなければならないはずです。そうしなければ、自分のルーツを相対化させ相手を理解するという視点さえもその立脚点が危ういものでしかないと思います。日本政府は、日本が本当の国際国になるためにも、日本のルーツ・伝統に関わる旧暦を事務公文書用暦とは別な位置付けできちんと定めるべきではないかと私は思います。そうすると、節句などの季節行事の日取りなども合理的に設定することができるようになり、旧暦時代から育まれてきた風情ある様々な年中行事もみんないきいきと蘇ってくることでしょう。
日本の年中行事の矛盾は旧暦の存在を一切認めまいという政府主導の風潮によると思います。最初の理由としては、旧暦が新暦の定着を阻害するからとか、新旧暦の混在によって混乱を招くからという理由も考えられます。しかし、改暦当時は福沢諭吉が旧暦を無闇矢鱈に非難をし、さらに旧暦を口汚く罵る議員がいたとかいう情況を想像するに、自分たちのルーツに関係している伝統を徹底的に破壊し隠滅しようという悪意(あるいは悪魔)が明治期を制覇したと思わずにはいれません。そうでなければ、新暦を公式の暦とたとしても外国のように宗教上の暦だとか民族的な暦として年中行事の日取りを確定する基準として温存させても良かったはず、と思います。
国際関係の多い現代の日本が新暦を取り下げ旧暦に戻るべきだとまでは思いませんが、日本が真に他の国々と対等に関わっていくためには自分たちのルーツ・根拠・伝統をきちんと踏まえなければならないはずです。そうしなければ、自分のルーツを相対化させ相手を理解するという視点さえもその立脚点が危ういものでしかないと思います。日本政府は、日本が本当の国際国になるためにも、日本のルーツ・伝統に関わる旧暦を事務公文書用暦とは別な位置付けできちんと定めるべきではないかと私は思います。そうすると、節句などの季節行事の日取りなども合理的に設定することができるようになり、旧暦時代から育まれてきた風情ある様々な年中行事もみんないきいきと蘇ってくることでしょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
暦 こよみ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
暦 こよみのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
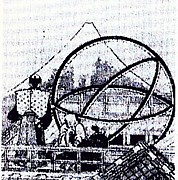


![月夜見 [ツクヨミ]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/3/72/1110372_2s.gif)



















